第五節 入滅以後の身延山
一、六老僧の守塔
聖人入滅の報に各地の僧俗は池上に集まり、14日の夜12時葬送荼昆(だび)の式を行ない、次いで遺品を分配し、21日遺骨を奉じて池上を立ち、25日身延山着、11月29日、尽7日忌葬送の式を虔(けん)修して、草庵北方の小丘に葬った。すなわち現在の御廟所である。かくして六老僧以下の人々が御廟所を守護申し上げている間に、年は明けて弘安6年正月23日、一百日忌にあたって盛大に追慕の法筵(えん)を修し、席上六老僧以下直房は順番に登山し1ヵ月ずつ交代に、御廟所を守護する制度を定めた。これを輪番守塔という。月番順は下記の通りである。
正月 弁阿闍梨 (玉沢日昭上人)
二月 大国阿闍梨 (池上日朗上人)
三月 越前公 淡路公
四月 伊予公 (真間日頂上人)
五月 蓮華阿闍梨 (貞松日持上人)
六月 越後公 下野公
七月 伊賀公 筑前公
八月 和泉公 治部公
九月 白蓮阿闍梨 (富士日興上人)
十月 但馬公 卿公
十一月 佐渡公 (身延日向上人)
十二月 丹波公 寂日房
右守番帳次第無懈怠可令勤仕之状如件
弘安六年正月 日
聖人の直弟には六老僧の外に、中老僧といわれる人々がある。12人とも18人とも諸説があるが、輪番帳に載せられた12人とするのが妥当のようである。六尊中老合して18聖、月番制が定まると、六老僧は各々山内に草庵を構えて奉仕した。すなわち二月 大国阿闍梨 (池上日朗上人)
三月 越前公 淡路公
四月 伊予公 (真間日頂上人)
五月 蓮華阿闍梨 (貞松日持上人)
六月 越後公 下野公
七月 伊賀公 筑前公
八月 和泉公 治部公
九月 白蓮阿闍梨 (富士日興上人)
十月 但馬公 卿公
十一月 佐渡公 (身延日向上人)
十二月 丹波公 寂日房
右守番帳次第無懈怠可令勤仕之状如件
弘安六年正月 日
日昭——南之坊不軽院——西谷
日朗——竹之坊正法院——中谷
日興——林蔵坊常在院——西谷
日向——樋沢坊安立院——西谷
日頂——山本坊本国院——中谷
日持——窪之坊本応院——東谷
番帳のように六老僧は1人ずつ、また中老若輩は2人ずつとして六老僧は6ヵ月、中老僧6ヵ月、以上18人で順番に守塔した。六老僧の庵室は上記の通りであったが、中老僧諸師がどこに住まったかは、房跡録ならびに古記にも明らかでない。おもうに六老僧の草庵にしても、そこに常住したものでなく、各地の布教に従い、輪番の月に登山して務を果たし、終ればまた布教に出たものであろう。前記六老僧の坊以外に、この当時建立されたものと考えられる山内坊舎には、下之房・志摩坊(あるいは嶋房)・端場坊等がある。日朗——竹之坊正法院——中谷
日興——林蔵坊常在院——西谷
日向——樋沢坊安立院——西谷
日頂——山本坊本国院——中谷
日持——窪之坊本応院——東谷
このように聖人滅後の身延山の経営、並びに宗門の発展は六老僧の協力治宗であったが、日昭・日朗は鎌倉に、日向は上総藻原に、日頂は下総若宮の常忍(富木氏)を助けて真間に、日持は駿州松野に、それぞれ檀越信者の外護を受けて教田の開拓に、門弟の教養に、信者の訓化に、寺門の経営につとめていたので、宗祖墓守の月番を定めたが、遠隔の地にあって交通不便な当時、実行困難となったためか、自然と甲駿の間に縁故の深い日興が、その門弟とともに身延山に在住し、墓守が委ねられる結果となった。
二、守塔廃止
正応元年(1288)宗祖7回忌の時、地頭の波木井氏が藻原の日向を挙(あ)げて身延の別当と定めたので、日興は身延を去って富士山の南麓に一門家を建てた。こうして一味の法水は遂にその流れを分けて、これから日興一門の側を富士方、その他を鎌倉方と呼ぶようになった。これについて「之を要するに、興師の身延離山は、輪番制の廃止に依るものではなく、対五上足(日昭・日朗・日向・日頂・日持)の学的異解、葛藤(かっとう)に由るものでもなく、只興師と波木井氏及日向師との間の得意(理解)修行の異解より、遂に離山に至ったと見るべきである」と早川達道は述べている。
三、身延山の進展
「守塔輪番制」は廃止され、日向が別当(住職)となり、久遠寺住職制度が決定し、宗祖を開山すなわち初祖と仰ぎ、日向は第二祖となった。民部阿闍梨日向師は、房州男金の小林実信公の一子、13歳の文永2年宗祖門下に投じ、正応元年(1288)より26年間の在位で、病気をもって退山後は房州法華谷に隠棲、正和3年(1314)9月3日(寿63)化寂された。
その後、宗祖の直弟より3世日進、4世日善法灯をつぎ、5世日台より、6世日院、7世日叡、8世日億、9世日学の諸師は、波木井家より出た方であって、ともに身延山草創時代を形成された。この創業時代は御廟所を中心として、山内に坊舎が点在していたが、次第に諸国より参詣者も多くなり、堂宇が狭く感じたので、寛正2年(1461)行学院日朝上人(第11世)法灯をつぐと、鋭意計画を練り、文明7年(1475)現在の久遠寺の地に堂塔を営み、久遠寺伽藍整備の源をつくられた。
宗祖滅後200年は身延山草創時代、内面的準備の時代であったが、日朝上人に至り、単に伽藍の移転増築だけでなく、学問の奨励、諸制度並びに法式等を制定し、すべての方面を組織立てられて、身延山史上ばかりでなく、宗門史の上からも、その顕著な法功は忘れてはならぬ方である。第12世日意上人、第13世日伝上人はともに日朝上人の門下で、3上人心を合わせて山勢の発展に尽力されたので、「身延中興三師」と尊称されている。三上人の在職年数は合計85年であった。
第14世日鏡上人より第17世日新上人まで4代48年間は、身延山の外においては対外的な法難や法論など幾多の災厄に見舞われたが、幸いにも身延山は山勢逐次進展し、特に武田氏、徳川氏の外護を受けて堂宇の再建新築などが行なわれ、中でも日鏡上人は弘治2年(1556)西谷に善学院を創立し、所化を集めて学を講じ、西谷檀林の基礎を開かれた。甲斐国主武田氏は、当時の一般武門と同様代々禅宗に帰依していたが、信玄の父武田信虎の時、その重臣遠藤掃部介なる人、深く法華経を信じてしばしば信虎に改宗を勧めたが聴かれず遂に自殺した。このことを縁として信虎は後に一寺を創し、延山13世日伝上人を開山と仰いだのが今日の甲府市若松町信立寺である。時に大永2年(1522)、日伝上人41歳、信虎29歳であった。
身延山には信玄関係の下記が記録または保存されている。
「身延山諸堂宇建立記」宝蔵の部(これは後に御真骨堂と称されたもの)に、
一、磬台
右は甲斐信玄公寄附、机同時に寄進、今は御蔵に在也(この机、磬台共に文政十二年九月六日焼失す)青貝の机、唐物(寸法記載あるも略す)
一、妙経(一部七巻) この法華経は、明本で、明の七世景帝の景泰二年(一四五一)の刊本にして、我国の後花園天皇の宝徳三年に当たる。
毎巻の終りに下の如く自署してある。寄進甲斐身延山久遠寺
従四位下武田大膳大夫兼信濃守源晴信判
天文十九庚戌年十一月念(廿)四日
従四位下武田大膳大夫兼信濃守源晴信判
天文十九庚戌年十一月念(廿)四日
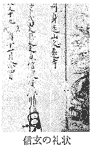 |
本状は古記録に名を留め、中途身延より紛失したが、去る昭和六年十二月大阪の筧半兵衛より身延へ寄進された。本書は前文を欠くが、前記の日付で大僧正法性院信玄の花押があり、あて名は身延山貫主近侍閣下とある。
時の貫主は15世日敍上人である。文によれば
一山の僧侶法華経1万部を読誦して武運長久の祈誓を凝らし、且つ日鏡上人御自筆贈与の法華経を子の勝頼が帯して戦場に出たが、この法華経の功力によって、去る4月川中島に大捷を博したことについての感謝状である。
このほか信玄関係のものが10通記録されているが数度の火災で焼失したもののようである。
なお、天文年間は日蓮宗と浄土宗との宗論が各地で盛んに行なわれていた時代であるが、信玄は同16年に、両者の争論を禁じた。
更に武田24将の1人穴山伊豆守梅雪(母は信玄の姉)は、身延山麓の下山に居城を有していた関係から(今の本国寺はその邸跡)信玄と身延山との間の斡旋に当たったものと伝えられ、息女の延寿院妙正日厳大姉(天正3年12月1日逝去)追福のために一坊舎を建立し、日敍上人を開基に仰いだ。今の延寿坊がこれである。別に梅雪は、永禄元年(1558)12月15日定書を身延山に下し、また子息勝千代は延寿院追善のため、天正11年(1583)12月その領地の塩沢一円の土地を久遠寺に寄せた。
また17代日新上人の代、甲斐を領した家康は、天正16年(1588)甲斐巡視の途中身延山に参詣し、他日天下統一の砌りには、幕府所在の地に身延山のため一宇を建立して寄進することを誓約され、御朱印を下付した。この時の約束によって天正19年(1591)谷中瑞輪寺を創建寄進したという。
家康は身延山に対しては比較的好意をもっていたようで、たびたびの御朱印下付等の事例で推知し得るのである。
徳川時代に入って、幕府は諸宗本山に命じて山規寺法等を制定せしめ、各宗の独立と本山本寺の権威を認め、仏教界の確立を望んだので、本宗でも身延山を総本山と呼ぶことになった。
この間21世日乾上人、22世日遠上人が晋(しん)山されたが、両師は師匠日重上人を20世の法灯に推戴し、内外の制度を改革するとともに、紀州、水戸両家をはじめ、前田、松山、京極、三浦等諸大名の外護を受けて、学塔は輪奐(かん)の美を極めた。日重・日乾・日遠の三師は学識深く高徳、育英に、伝道にと活躍され、徳川開幕期に当たって宗風宣揚につとめ、身延山を総本山としての威容を備え、法功は大きく、第2期の中興三師と敬称されている。
日遠上人は慶長9年(1604)春33歳をもって第22世の法灯をついだ。同年7月身延山掟を定めて山内を取締まると同時に、同年冬に町中掟を定め、町内人をして厳守させてその平和を計った。門前町研究の上からも興味深い布達である。
町中掟
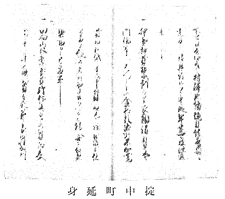 |
| 一、 | ふかく信力を励まし、節々堂参すべき事。 |
| 一、 | 刃傷かたく停止せしむべき事。 若此旨そむくにおいては永代追放たるべし。 |
| 一、 | 打擲禁制 若此旨背むくにおいては一年追放あるべし、退出の間は其組として家役相つとむべし。 |
| 一、 | 口論かたく停止、若この旨そむくにおいては人足三拾人過代あるべし。 右三ヶ条縦令すいきやうたりとも宥免あるべからず。 |
| 一、 | 往復にても内にても松火(たいまつ)停止並にかまど能く火の用心すべき事。 |
| 一、 | 火の用心のためなる間屋敷一間に他人住宅せしむべからざる事。 |
| 一、 | 番の者にして毎夜火並に盗人の用心能くよばふべき事。 |
| 一、 | 公儀をえずして他所の者抱へおくべからず。 |
| 一、 | 大坊へ申上ずして屋敷の売買をすべからざる事 |
| 一、 | うりとめをなすべからざる事。 |
| 一、 | 米穀等の売買他所を聞きあはせずして私権を立つべからざる事。 |
| 一、 | 参詣の衆にたとひ不如意の仁なりとも一宿も致すべからざる事、 |
| 一、 | 山中松の木のある山に於いて下払をも致すべからざる事。 |
| 一、 | 五日に一度づつ未明に出て家のまへ一同に掃除すべき事。 |
| 一、 | 女房とも日出まへ、いりあひの後寺内へ往復すべからざる事。 |
| 一、 | 衆非衆老若をえらばず僧衆に対して慮外致すべからざる事。 |
| 一、 | 僧中のうはさ実不実によらず町中において惣じてとり沙汰いたすべからず、若申上べき者あらば、急度大坊江申上糺明あるべし。ただし無実に於ては追放あるべし。 |
| 一、 | 大小事によらず惣じて宿太郎の下知に随ふべき事。 |
慶長第九甲霜月七日
辰 身延山
とある。辰 身延山
以上の掟から見て、身延町民が大坊(本院)の支配下にあったことが明らかで、その制文からして、当時の住民の日常生活の半面を推知することができる。
これより先、文禄、慶長年間に豊臣秀吉の姉、瑞竜院殿(妙慧日秀大姉)並びに浅野忠吉公によって本堂、大方丈、唐門が寄進された。更に日乾、日遠二師より十数代にわたっては祖山発展の時代ともいうことができ、数多くの名門の夫人が身延山に丹誠を尽した。
加賀候前田利家の側室寿福院日栄夫人(寛永8年(1631)3月6日卒62)が元和5年に3間(5.45メートル)四方、高さ20間半(37.27メートル)の五重塔を寄進したのを始め、同5年思親閣祖師堂、拝殿が造立された。洪鐘(大鐘)は養珠院殿、時鐘は伊予松平定頼室養仙院よりそれぞれ寄進を受け、その他菩提梯、三門、丈六堂、一切経蔵、千体仏、浴場、総門等の主要建造物がつぎつぎと完成した。
身延山史に、「慶安元年(一六四八)第廿七世通心院日境上人入山してより、第三十代寂遠院日通上人の延宝七年(一六七九)に至る四代三二年間は、前時代の努力と、篤信家の外護によって、祖山の堂塔伽藍は一層整備し、その配置等も秩序整然たるに至れり」とある。
万治2年(1659)8月、深草元政上人が、79歳の老母を伴って身延山に詣で、その旅行記「身延道の記」に、
諸堂拝まんとて、西谷より橋わたりてのぼる。山水の奇秀はさらにもいはず、伽藍の荘厳綺麗、又いはんかたなし。(中略)
祖師堂の開帳す、御影拝み、一たび延山に上て、心愈悲し、倶に末法に生れて師に逢はず、手香頂礼す影堂の下、涙「尼檀」(注・にだん 僧拝礼の時用ふる小さな敷物)を湿して起たんと欲すること遅し。
それよりこなたかなたをめぐりて、御骨堂にまゐりて拝み奉る。玉の宝塔の中にいとあざやかなり。
なにゆゑにくだきし骨の名残ぞと思へば袖に玉ぞ散りける
とある。祖師堂の開帳す、御影拝み、一たび延山に上て、心愈悲し、倶に末法に生れて師に逢はず、手香頂礼す影堂の下、涙「尼檀」(注・にだん 僧拝礼の時用ふる小さな敷物)を湿して起たんと欲すること遅し。
それよりこなたかなたをめぐりて、御骨堂にまゐりて拝み奉る。玉の宝塔の中にいとあざやかなり。
なにゆゑにくだきし骨の名残ぞと思へば袖に玉ぞ散りける
延宝7年(1679)31世日脱上人入山され、次いで日省、日亨上人と続いた。脱・省・亨の三師は、重・乾・遠三師につぐ身延山中興の師として、身延山の全盛期を現出し、中でも日脱上人は元禄6年(1693)上洛参内して、東山天皇から紫衣の輪(りん)旨を拝受し、また立正安国を祈念するため、三六ヵ坊の祈祷坊を創立して、不断に祈祷経を読誦する制度を定められ、明治維新に至るまで読経の声は、昼夜の別なく唱えられたと伝えている。
山内の坊は、文永12年9月8日妙了日仏の造立が初めで、この坊を下之坊といった。また、小室山妙法寺の開基となった日伝上人が、建治元年2月8日草庵を結んだのが基となった。志摩坊および弘安3年四条金吾の開創の端場坊、その他弘安6年六老僧が山内に結んだ諸坊などに次いで、宝徳、長禄年間の、岸之坊・花の坊・慶林坊の建立があった。日朝上人御在山の文明年間には36坊を数えた。下って貞享4年(1687)には、祈祷坊36坊の建立があった。なお「身延山諸堂軒数覚」という貞享3年(1686)の古書を見ると、当時の坊数を下記の通り掲げている。
寺中
一、東谷 一六坊
一、西谷 二二坊
一、中谷 四坊
一、醍醐谷 五坊
一、河原谷 五坊
一、南谷 一〇坊
一、逢島 一坊
一、土島 一坊
一、梅平 一坊
一、下山 一坊 (現在の本国寺なり 山史一八三)
一、塩沢(金剛谷と云う)六坊
一、祈祷坊 三六坊
合計 一〇八坊
正徳2年(1712)には133坊に増加しているがおそらく空前の繁栄であったであろう。一、東谷 一六坊
一、西谷 二二坊
一、中谷 四坊
一、醍醐谷 五坊
一、河原谷 五坊
一、南谷 一〇坊
一、逢島 一坊
一、土島 一坊
一、梅平 一坊
一、下山 一坊 (現在の本国寺なり 山史一八三)
一、塩沢(金剛谷と云う)六坊
一、祈祷坊 三六坊
合計 一〇八坊
下って徳川末期万延時代(1860)には93坊となって、40坊を減少している。これは火災などの被災坊が復興しないで合併したり、住職に人がなくて廃坊となったりしたためであろう。また「宿坊の定」がきめられて、山中の坊について、何国の寺院信徒は何坊へ、何門流は何坊へと、宿院を割当てたことから見ても、当時身延が、宗門全体の信仰の中心であると同時に、各門流の中において、その外形内容ともに断然頭角をあらわし、全宗門の総本山であったことが知られる。
この宿坊割の記録には、第17世日新上人筆天正20年(1592)の古書が残っている。
明治維新期の廃仏毀釈の波や経済変動は坊の廃合を促し、明治7年(1874)11月の身延山内支院総会で合併が決議され、当時寺中総計82ヵ坊の内35ヵ坊を建置とし、47ヵ坊を合摂した。現在は支院32坊となり、別に「清兮寺」1寺がある。
身延山住職の就任は種々の関係によって決定されたが、徳川幕府中期以後は主として、飯高檀林(千葉県香取郡)の能化(学長)が順次に就任する制度となった。
山内の諸制度も既に確立し、伽藍も整備し、明治に至ったが、この間に身延山の進展を阻害したものに火災、水害の厄があった。
火災の第1回は寛保4年(1744)7月7日下之坊より出火、山内11坊を焼失した。第2回は安永5年(1776)10月12日夜、七面山堂宇を全焼した。第3回は文政4年(1821)8月9日夜の出火により、西谷御廟の八角堂、拝殿焼失、第4回は文政7年(1824)8月27日、祖師堂より出火し、大雨中にもかかわらず、13棟を焼失した。
第5回は文政12年(1829)9月6日の大火で、五重塔より出火して、28棟の伽藍堂宇を灰燼(じん)に帰し、なお山内寺中町方の大半もこの厄にかかり全山悉く焦土と化した。「蓋し祖山における回禄中其の受けた損害前代に比なく、歴代諸聖の苦辛造営は空しく一片の煙と化し終れり」とあり、第6回は慶応元年(1865)12月14日昼、中谷の仙台坊より出火、支院17坊、小堂8ヵ所を焼き、延焼して、上町・中町・上新町・横町・片隅町・下町の106軒を焼失した。
明治に入って以後の大火は8年(1875)1月10日夕西谷、本種坊からの出火で、本堂、祖師堂を始め本院75棟、寺中12ヵ坊、町家10軒を焼失し、総計144棟の堂宇と幾多の財宝什器を烏有に帰した。これが祖山火災中の最大のものである。
この火災で、日蓮聖人の重要な御書・開目鈔・報恩鈔等が焼失したことは、まことに残念なことであった。また明治20年(1887)3月4日午後2時、中町より出火し、町方138軒を焼失し、寺中に延焼、仮二王門・竹之坊・山本坊・松井坊等を焼失した。大正・昭和になって支院町方に数回の火災があったが、本院は昭和27年2月9日夜、信徒休憩所および時鐘を焼失した。
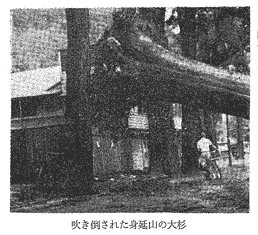 |
洪水については古く11世日朝上人時代にも記録を見るが、文政11年(1828)6月30日に、大風雨に伴って河水汎(はん)濫し、上新町および下新町の人家多数流失した。
さて明治維新前後にわたり前述のように度々の災厄にもかかわらず、仏天の加護の下、日薩・日鑑上人をはじめ、一山大衆の努力並びに10万信者の丹精によって、逐次諸堂宇も再建され、昔日の結構には到らなかったが、次第に整備された。
近時最大の被害をうけたのは昭和34年8月の台風7号、同年9月の伊勢湾台風であった。

