第六節 明治以後の身延山
一、概説
明治初年内外多端の間、73世日薩上人、74世日鑑上人、75世日修上人相続いて入山され山務に尽粋された。しかも明治初年の政治改革に伴って仏教界に加えられた圧制に対して、管長として日薩上人は、山外にあって、日蓮宗ばかりでなく、全仏教界興隆の大志をいだいて各宗派と協調、日夜努力された。なお日鑑上人は日薩上人の院代を勤め、護法愛宗の真心を吐露して山勢発展に努力された。こうして宗門内外多事多端の間にもかかわらず、山色日々に進展した。国運の進展に伴って、身延山もまた新時代に対応すべく、山規改正、教学の充実、経営基盤の確立、また諸堂宇の営繕等に努め、年とともに発展して大正時代に至った。
身延山にも次第に近代的施設がなされた。大正元年(1912)富士身延鉄道が企画され、大正9年5月富士身延間に汽車が、昭和3年(1928)3月には身延、甲府間に電車が開通し、参詣は非常に便利となった。また大正2年には電灯が点じ、同14年には特設電話の開通をみ、同年従来の馬車や人力車に代って身延駅−三門間にバスが運転されるなど通信運輸に大なる変革が行なわれた。去る昭和38年8月にはロープウェイが開通した。
明治末より大正にかけて、異体同心、皆帰妙法の祖訓を実践しようとする意図から、日蓮門下各派教団の統合ということが論ぜられるに至ったが、たまたま大正11年10月13日、宗祖に対し「立正大師」号が宣下されるにいたり、統合気運は一層促進された。
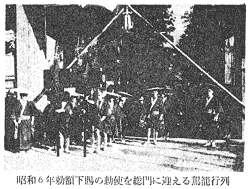 |
御遠忌法会は4月より前後4回、39日間奉行され、並びに各種記念行事が盛大感銘裡に虔(けん)修されたが、なかんずく10月13日御入滅正当日を期して、今上陛下より「立正」の勅額が祖廟に下賜され、82世日帰上人が参内これを拝受した。
昭和7年(1932)3月、望月日謙上人83世に晋山されるとともに、祖廟備整会、祖廟奉仕会が結成され、祖廟聖域は大いに整備された。昭和14年4月には西谷に信行道場が完成し、昭和16年3月には、日謙上人、顕本法華宗井村日成上人、本門宗由比日光上人が中心となって、三派合同が実現し、今日の日蓮宗が生まれた。
昭和18年9月、日謙上人御遷化、同年10月深見日円上人84世に就任された。上人は終戦直後、よく困難を克服し、老躯を省みず、布教、興学に尽粋された。
昭和24年には、永年の懸案であった、宗祖御得度の霊場清澄山が改宗本宗に転じ、同27年には立教開宗700年の慶祝行事が全宗門を挙げて奉行された。身延山においては、三期の大法要、諸堂宇の整備、教育施設の拡充などに努めたが、中でも日蓮聖人御遺文の集大成として「昭和定本遺文」4巻の刊行は特筆すべき記念事業であった。
昭和32年2月、第84世深見上人は89歳にて遷化、2月増田日遠上人85世を継承、大いに祖廟整備に努め、翌33年10月に壮大な常経殿が竣工した。けれども翌34年夏、再度の台風により祖廟域はもちろん全山にわたり大被害を受け、日遠上人日夜の労苦に不幸病を得て同年7月退山され、藤井日静上人が7月24日第86世の法灯を継いで入山した。上人は第83世日謙上人のお弟子であり、師匠の遺志をを体して山内を督し身延山の興隆、発展に精進されている。42年10月には永年の宿願たる、身延山大学の大講堂および校舎の大建築が完成した。
以前は全国および海外にわたり約600の末寺と多数の教会や布教所が、久遠寺門末として所属していたが、前述の三派合同が行なわれて、宗門規則改正の結果本末関係は解かれた。しかし宗祖栖神の地身延は全門下の信仰の中心地として衆心帰一の霊地であり、宗門規則の上からは「祖山」と呼ばれている。
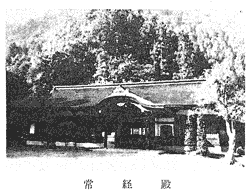 |
久遠寺には、総務・教学・庶務・布教・法要・経理・参拝等の各部その他が設けられそれぞれ事務を分担処理している。
また遠く400年の昔に、第14世日鏡上人が創立、第22世日遠上人により発展した西谷檀林という教育道場は、現在の身延山短期大学、身延山高等学校として、次代の宗門を担当する僧徒の育成に努めている。
久遠寺の諸堂宇、各参道の諸堂、境内の案内等に関しては既に詳細な案内書、手引が多数刊行されているので本項には省略する。
久遠寺歴代出身関係
| 世寿 | 在職年数 | |||||||
| 開山 | 宗祖大聖人 | |||||||
| 62 | 2世 | 日向 | 26 | 宗祖直弟 | ||||
| 76 | 3世 | 日進 | 17 | 宗祖直弟 | ||||
| 未詳 | 4世 | 日善 | 3 | |||||
| 46 | 5世 | 日台 | 35 | 波木井実長の孫長氏の2男4世の弟子 | ||||
| 62 | 6世 | 日院 | 8 | 波木井実長の孫長氏の3男3世の弟子 | ||||
| 83 | 7世 | 日叡 | 28 | 院上の俗弟か3世の弟子 | ||||
| 未詳 | 8世 | 日億 | 23 | 7世の弟子 | ||||
| 未詳 | 9世 | 日学 | 38 | 億師の俗弟7世の弟子 | ||||
| 68 | 10世 | 日延 | 3 | 8世の弟子 | ||||
| 79 | 11世 | 日朝 | 40 | 三島日出の弟子、日出は学師の弟子9世の孫弟子 | ||||
| 未詳 | 12世 | 日意 | 20 | 11世の弟子 | ||||
| 67 | 13世 | 日伝 | 25 | 10世の弟子 | ||||
| 53 | 14世 | 日鏡 | 13 | 12世の弟子 | ||||
| 55 | 15世 | 日叙 | 21 | 13世の弟子 | ||||
| 76 | 16世 | 日整 | 2 | 13世の弟子 | ||||
| 58 | 17世 | 日新 | 15 | 初め13世の弟子後14世の弟子 | ||||
| 41 | 18世 | 日賢 | 8 | 17世の弟子 | ||||
| 40 | 19世 | 日道 | 3 | 18世の弟子 | ||||
| 75 | 廿世 | 日重 | 加歴 | 光山南泉房の弟子 | ||||
| 76 | 廿一世 | 日乾 | 初2後6 初め若州小浜長源寺日欽の弟子後ち重師の弟子 | |||||
| 71 | 廿二世 | 日遠 | 初5後2 20世の弟子 | |||||
| 49 | 廿三世 | 日祝 | 2 | 22世の弟子 | ||||
| 48 | 廿四世 | 日要 | 8 | 22世の弟子 | ||||
| 54 | 廿五世 | 日深 | 5 | 初め日明の弟子後ち21世の弟子 | ||||
| 63 | 廿六世 | 日暹 | 22 | 22世の学門の徒 | ||||
| 58 | 廿七世 | 日境 | 12 | 玉沢日達の弟子 | ||||
| 67 | 廿八世 | 日奠 | 8 | 初め22世の弟子後中正日護の弟子 | ||||
| 73 | 廿九世 | 日莚 | 6 | 中正日日護の弟子 | ||||
| 66 | 卅世 | 日通 | 8 | 京の本隆寺の弟子飯高松和田谷の祖 | ||||
| 73 | 卅一世 | 日脱 | 20 | 飯高中台谷出身祖山晋山の初め、弟子日湛をして院代とす初めてなり | ||||
| 85 | 卅二世 | 日省 | 7 | 水戸庠より祖山へ | ||||
| 76 | 卅三世 | 日亨 | 10 | 飯高第25代講主 | ||||
| 75 | 卅四世 | 日裕 | 20 | 飯高能化33世の弟子 | ||||
| 58 | 卅五世 | 日竟 | 3 | 飯高講師後33世の弟子 | ||||
| 75 | 卅六世 | 日潮 | 9 | 草山日灯の弟子飯高 | ||||
| 67 | 卅七世 | 日寛 | 5 | 36世の弟子飯高 | ||||
| 73 | 卅八世 | 日答 | 60日 | 31世の弟子飯高61世 | ||||
| 83 | 卅九世 | 日総 | 80日 | 飯高54世 | ||||
| 64 | 40世 | 日輪 | 4 | 飯高86世 | ||||
| 77 | 41世 | 日妙 | 4 | 飯高66世 | ||||
| 80 | 42世 | 日辰 | 5 | 中台松和田順次交替晋山となる | ||||
| 77 | 43世 | 日見 | 5 | 飯高松和田98世 | ||||
| 59 | 44世 | 日宝 | 2 | 飯高115世 | ||||
| 79 | 45世 | 日応 | 5 | 上同108世 | ||||
| 74 | 46世 | 日 |
1 | 同113世 | ||||
| 74 | 47世 | 日豊 | 7 | 同126世 | ||||
| 81 | 46世 | 日源 | 8 | 同124世 | ||||
| 90 | 49世 | 日地 | 5 | 同136世 | ||||
| 81 | 50世 | 日沽 | 1 | 同153世 | ||||
| 83 | 51世 | 日全 | 5 | 同166世 | ||||
| 75 | 52世 | 日盛 | 3 | 同192世 | ||||
| 84 | 53世 | 日奏 | 9 | 同187世 | ||||
| 81 | 54世 | 日審 | 3 | 同203世 | ||||
| 91 | 55世 | 日逞 | 9 | 同222世 | ||||
| 72 | 56世 | 日晴 | 2 | 同234世 | ||||
| 74 | 57世 | 日舜 | 1 | 同232世 | ||||
| 83 | 58世 | 日環 | 5 | 同238世 | ||||
| 71 | 59世 | 日 |
3 | 同240世 | ||||
| 80 | 60世 | 日潤 | 4 | 同255世 | ||||
| 75 | 61世 | 日心 | 5 | 同256世 | ||||
| 72 | 62世 | 日扇 | 3 | 同278世 | ||||
| 77 | 63世 | 日闡 | 3 | 同262世 | ||||
| 73 | 64世 | 日仲 | 2 | 同282世 | ||||
| 77 | 65世 | 日桂 | 1 | 同277世 | ||||
| 77 | 66世 | 日薪 | 8 | 同289世 | ||||
| 79 | 67世 | 日楹 | 5 | 同298世 | ||||
| 83 | 68世 | 日実 | 3 | 同292世 | ||||
| 80 | 69世 | 日琢 | 5 | 同302世 | ||||
| 86 | 70世 | 日祥 | 7 | 明治 飯高講師 | ||||
| 81 | 71世 | 日祷 | 2 | 飯高327世 | ||||
| 82 | 72世 | 日健 | 4 | 飯高320世 | ||||
| 59 | 73世 | 日薩 | 3 | 飯高充洽園 | ||||
| 60 | 74世 | 日鑑 | 11 | (御代理3年)飯高充洽園 | ||||
| 69 | 75世 | 日修 | 6 | 充洽園 | ||||
| 58 | 76世 | 日阜 | 1 | 充洽園 | ||||
| 51 | 77世 | 日厳 | 5 | 玉沢 | ||||
| 64 | 78世 | 日良 | 12 | 飯高 大教院 | ||||
| 83 | 79世 | 日慈 | 15 | 中村 日薩 大学林長 宗務総監 | ||||
| 87 | 80世 | 日調 | 2 | 宗務総監 | ||||
| 76 | 81世 | 日布 | 7 | 大教院 大学長 宗務総監 | ||||
| 68 | 82世 | 日帰 | 1 | 宗務総監 | ||||
| 79 | 83世 | 日謙 | 12 | 大学長 宗務総監 | ||||
| 89 | 84世 | 日円 | 14 | 身延山常置会議長 日蓮宗財務部長 | ||||
| 85世 | 日遠 | 2 | 昭和34年7月23日退山 | |||||
| 86世 | 日静 | 昭和34年7月24日入山 | ||||||

