第二章 生活
第一節 衣食住
一、衣
(一)衣類のうつりかわり
ア、絹、綿以前の衣について当地域で絹や綿を衣料として用いる以前には、樹皮の繊維をよって織った布地が用いられた。科(シナ)・楮(コウゾ)・藤(フジ)・麻(アサ)等がそれで、これらの樹皮を水に晒し甘皮を除き残りの繊維を使用したという。
イ、絹、綿の伝来について
絹は古くから用いられていたが、其の生産は少なく上層階級のみで一般人は樹皮をまとう者が多く、広く庶民に使用されるようになったのは江戸時代からで、山梨県でも甲斐絹としての記録が1668年すなわち江戸中期ごろはじめてみえている。(925年風土記より)
綿は東印度原産のものが支那を経てわが国に伝来したのは、称徳天皇の神護景雲3年(769)で続日本記に
しらぬひの筑紫の綿は身につけて、いまだ着ねどもあたたけく見ゆ
と詠まれているが、得難い綿花のほどがうかがわれる。
しかし、一時奈良期末期にはその綿の種が絶えていたと言われ、新撰六帖衣笠の大臣家良の歌に、
敷島のやまとにあらぬ唐人の植えてし綿の種は絶えにし
と載せられている。その後足利時代の永禄年間に、ヨーロッパ人によって新たにもたらされたのが、現在の綿である。
このように暖かく耐久力のある綿の衣料は多くの人々のあこがれているものであったが、身延地域に最初綿の入ってきたのはいつ頃であるかはっきりしていない。とにかく維新前よりこの地域でも綿を栽培し、糸に紡いで、それを染め、自家製の布を織って家人に着せたり、その布で足袋を作ってはかせたりするのが主婦の仕事であった。現在でも畑に木綿地という地名が残っている。
ウ、明治から大正にかけて
明治維新になって、綿が安く多量に輸入され、紡績工業の発達とともに身延にも静岡や鰍沢方面から綿糸が安く入るようになると、衣類も綿を主として着るようになった。一方明治から大正にかけて、この地は養蚕が盛んであったため、玉繭や屑繭から糸をとり「つむぎ」と称する自家用の織物をつくって着た。なお中繭から紡いだ上等な糸で織った布は「ななこ」といって、貴重な外出着として上流家庭の人達が用いた。
エ、染色、機織り
染色・糸操り・機織りは明治から大正へかけてこの地方でも盛んに行なわれ、今でも当時使用した糸車や、織機(はたや)などが所々に残っている。
明治生れの人に当時の様子を聞くと「あの頃は、夜通し機を織って家の者達にお正月の晴着を着せたものだ」と話してくれた。糸繰りや機織りについては一般に知られておりその記録も多くあるので、ここでは当地域の特色ある染色について述べることとする。
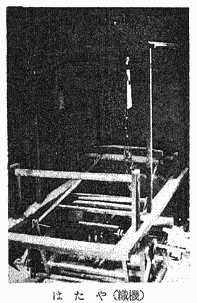 |
次にむずかしかったのが浅黄だったとか。紺と浅黄以外は家庭で染めたという。染料としてこの地特有のものに、ねず色(桐の小枝を炭にし、その炭を湯の中へ入れたもので染める)がある。
赤(ぐみの木をせんじた汁で染めると、黒味を帯びた赤に染まったという)黄色(口なしの実をせんじた汁で染めた)
このように糸を自分の好みの色に染色し、自家製の織り物を作って着ることが女性の楽しみであったようだ。この地の唄に、「稼げば着せる大目縞、稼がにゃ着せぬ木綿縞でも」というのがあるが、絹糸とガス糸とを織りまぜた大きい縞めのにぶい光を放つ大目縞は、女性のあこがれの衣類であったらしい。
オ、大正から昭和にかけて
衣類の最もうつり変りの激しかったのはこの時代である。明治に入って綿の輸入に前後し、羊毛も輸入され毛織物(メリンス)が当地域に入ってきたのが大正初期であり、また毛、絹、綿に加えて、人工樹脂で織物をつくるようになったのがこの時代である。ファイバーだとかナイロンだとかいって光沢のある火に弱い布ではあるが、割合安く出回ったため利用者の数も多くなっていった。
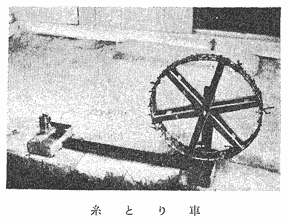 |
かぶり物についても明治から大正にかけて男子にみられたカンカン帽子や山高帽子は、第二次世界大戦に入るとともに姿を消し、男子はほとんど外出時には戦闘帽をかぶり、女子は防空ずきんをかぶった。しかし、これも終戦になると、しぜんにかぶらなくなり、現在では男女ともに無帽のものが多くなり、男子はほとんどのものが髪の毛をのばし、女子も髪型をいろいろ工夫するようになった。
履物について
古くは木の繊維や、草で編んだものをはいていたが、その後藁草履や、竹の皮で編んだ草履など日常の履物とする時期が長く続いた。この地方で使用した履物について次のものがあげられる。わらじ、こま下駄・あしだ・ひより下駄(女)・ぽっくり下駄(女)・ふじくら・せった・フエルト草履・ゴム草履・ズック靴・ゴム靴・皮靴・サンダル等で作業時には地下足袋が長い期間を通じて使用されており、あしなか(富士川を上り下りする船頭がはいたもので藁草履の半分位のもの)は過去のものとなって、民俗資料として陳列されている。
(二)衣類の種類
ア、平常着 |
イ、作業着
明治から大正にかけては和服にももひきを着用し、女子は前掛をした。はげしい労働の時には、「はばき」をつけ、たびをはき、藁草履か、わらじを履くことが多かった。頭にはほほかぶり、ねえさんかぶりなどをして、すげ笠やまんじゅう笠をかぶった。雨の時や暑い時は、「けでえ」と言って藁でつくったみののようなものを着たり、「着ござ」といって、「い」のむしろを二つ折にしたものに紐をつけて着たりした。富士川を上り下りする船頭は「足なか」をはいて爪先立ちして舟を引いた。
時代が進むにつれて、男女とも上着にズボンまたはモンペを着用していたが、現在では作業する場所によって、種々異った型の作業着を使用している。
ウ、外出着、式服
明治から大正にかけて特色ある外出着として被布(ひふ)がある。上流家庭の婦女子がコートとして着たり、男でも老人・医師・隠居さんなどが着た。また、男女とも外出の場合の衣類は大方絹物で和服の場合は必ず羽織を着た。
結婚式の服装として明治から大正の頃の女性は、小袖のネズミ色・赤色・黒色の三枚重ねを着用し男子は、うち織りの黒の長着に紋付羽織を着て、縞の袴をつけた。袴は冠婚葬祭には必ずつけ、また教員は日常これをつけた。時代が進んできて、男子が結婚式にモーニングを着るようになってから、女子も江戸褄模様の小袖(留袖)からふり袖となり、また、最近はほとんど裲襠(うちかけ)を着るようになった。中にはウエディングドレスを着る者もある。現在ではお金のかかる結婚式の服は、ほとんど貸衣裳屋から借用して間に合わせている。
(三)衣料の統制
第二次世界大戦のころになると、綿花や羊毛の輸入が制限され、昭和17年(1942)2月には衣料統制令が出された。国民は政府から配給された衣料切符で衣料を買ったのであるが、統制品だけでは間にあわず統制外品を得るのに苦労したものである。二、食
(一)3回食習慣の確立
長い封建時代、各地とも日常とられた食事内容はほとんど変わりなく、現在のように3回食習慣の確立したのは鎌倉時代の末期から室町時代にかけてである。公家のごとき非労働者は日に2回食であったが、労働に従事する農民階級は長い1日の仕事に堪えるため、日に5、6回食べていたという。5、6回食の内容
① 早朝
② 朝食 あさみし あさめし
③ 午前中間食 こびり(小昼)
④ 昼 ひり、なかこよい、おちゃづ
⑤ 午後三時 おやつ、おこぢゅ、こぢゅはん
⑥ 晩食、ようめし、ようはん
⑦ 夜食 おやしょく
「朝は茶のこ、昼はばく、夜はおほうとう」と、甲斐路富士山麓粉食記にも記されているように、朝は「おやき」か、「おねり」の、まるめただんご状のもの、昼は「麦飯」、夜は「おほうとう」が常食であったが、当地域にあっては昼と夜の間に「ようじゃ」といって麦飯または、大根めし、芋飯などを食し、1日4回食を大正末期から昭和の初期まで続けていたが、現在では食料がでまわり副食物が自由に手に入るようになったので、食事は朝昼晩と3回とり、午前と午後に1度ずつお茶を飲み、茶菓子をたべている。また、明治の頃からわが国でも外国の影響を受けて、肉を食べるようになったが、この地方でも明治の末期から大正にかけて肉を食べる人がぼつぼつでてきた。日蓮聖人の食事
日蓮聖人の毎日定った食事は、日に二回であったという。朝と昼の中間時に第一回を食した。その内容は、白米(しらよね、しらけごめ)焼米・干米・麦飯・粟飯等で日によって異っていた。第二回は夜で、芋粥、蒸餅(もちい)といって糯米をついたものをぞう煮のようにして食した。(身延山史話)
(二)敗戦前後の雑食時代
第二次世界大戦が始まるや次第に食糧難となり、配給制となって3度の食事も満足に得られなかった。この地域にあっても芋粥や雑炊が常食となり、甘藷・馬鈴しょ・大豆なども主食として食べた。副食にはいままで食べたことのない甘藷の葉柄や、山にはえている「ぎぼうしゅ」の葉柄も食べ、なお野草でたべられるものはほとんど食べて、野草を試食する会などがもうけられたりした。路傍の「よもぎ」などは伸びることができないほどに摘まれたりした。空腹しのぎにフスマの焼き餅を食べる者さえでてきて、栄養失調のため顔色が黄色くなり、労働ができなくなった人もあった。敗戦後はアメリカの放出食糧として、大豆粕、あんずの砂糖煮、バナナの砂糖煮、その他罐詰類なども配給された。(三)現在の食事内容
敗戦後しばらくして食糧も豊富になり、最近では、白米を主食にして副食も好みものもが得られるようになった。が、まだまだ米主食偏重の習慣がぬけきらず、栄養の片寄る心配もある。身延町では、昔から、山野に生える山菜や町内を流れている富士川に住んでいる豊富な魚類の恩恵により、副食物には事欠かなかった。しかし、人々の栄養に対する知識が低かったため、材料はありながらもカロリー不足、ビタミン不足の食事内容であったことは見のがせない。そこで、これからの食生活においては、米食偏重をさけ、良質のたんぱく質やビタミン各種を補給すべく、1日必ず1回は粉食をとることが理想とされており、また出来るだけの有色の生野菜や果物を多くとることと、肉や卵などつとめて食べ、牛乳も飲むようにすることが望ましい。しかし、肉、卵、牛乳など高価で得られない場合は、良質の蛋白質と脂肪を含んでいる大豆を使った食物を多くとることが良いとされている。(四)学校給食
 |
(五)主食
昔から主食としてこの地で取りあげられているものにつぎのものがある。・麦飯(麦をよくにて食べる)・半飯またはばくめし(麦と米を半々かまたは、7・3に使ったもの)・だいこめし、または、いとこめし(米と麦と大根をせん切りにしてたいたもの)・おほうとう、この地域ではのし入れとも言う。小麦粉で麺類をつくり、野菜とともにみそ汁で煮込んだもので、「うまいもんだよ、南瓜(かぼちゃ)のほうとう」という言葉があるようにこれは甲州名物とされている食べ物である。それに類似したものに
おすいとん、うどん、そばなどあり、おやき(小麦粉、とうもろこし粉、赤もろこし粉をねって焼いたもの)米飯、まぜ飯(米に粟や芋や野菜をまぜる)などもある。
(六)副食物、調味料、嗜好品
教報みのぶ御用私考にはこの地の副食品としてつぎのものがあげてある。・芋類(自然薯、里芋)みょうが、くくだち(茎立)、山菜野菜のとう、ふき、すずななど、
このほか、現在副食物としてあげられるものに
・汁物(みそ汁、すまし汁その他)、漬物、煮〆、果物類、魚貝類、肉類、卵、牛乳、海草類があり、また加工品として、ハム、ソーセージ、罐詰類等がある。なお、戦後特に目立って食べられるようになったものに、西洋野菜があり、セロリー、アスパラガス、レタス、パセリ、カリフラワーなどが各家庭で食膳にのぼるようになった。
昔調味料としての塩が、この地方では非常に得難かったことが、身延山御書類聚につぎのように書いてあることからもわかる。
海遠き甲斐の山中に在っては、調味料の王者たる塩は悉く海辺にたよらなけれてならぬ。その塩は駿河上野の南条殿から常に一俵一駄と送られた。併し時に塩飢饉に見舞われ、就中長雨期に路を流し船渡らず、馬は通わずために塩一升に銭百、塩五合を麦一斗に替え候しが今は全態塩無し何を以てか替うべき味噌も絶えぬ小児の乳をしのぶが如し。
船の外には佐野峠を越えて駿河との交通路があり、米や塩がこれを通って駿河から大河内に入って来たが、ごくわずかで雨でも降るとこれもと絶えたということである。(甲州夏草道中記)塩の外に、酢、ひしお(今の醤油のようなもの)、味噌、鼓(くき)(ひしおに類似したもの)、煎汁(いろり)、鰹などを煮つめてつくった汁、などが用いられ甘味料として、飴、蜂蜜、甘戦後、この地方でも自家製の味噌、醤油を使っていたが、現在ではほとんどの家庭で醤油は作らなくなり市販のものを使用している。しかし味噌だけは自家製のものを使用している家庭がまだ多い。
甘味料として明治から大正にかけてずっと砂糖を使用していたが第二次世界大戦当時輸入ができなかったため、人工甘味料としてサッカリン、ズルチン等が盛んに使用されたが、戦後砂糖が自由に入るようになって料理も味が良くなってきた。なお、料理の味を良くするために戦前までは煮干しや肉類、こんぶ類のだし汁を使用していたが戦後人工調味料として、味の素、いの一番、ハイミーなどをどの家庭でも使用するようになってきた。
嗜好品としては酒は日蓮聖人もお召しになったとみえ、「御命講やあぶらのような酒五升」、「人の血を絞れる如くなる古酒持参」などと身延山史話の中に記されている。茶褐色のとろりとしたのが昔の酒で、現在のような透明な酒はなかった。一般の人は芋酒、どぶろくなどをも飲んでいた。(教報みのぶ)しかし、現在では日本酒、ビール、洋酒、果実酒など酒類の数は多い。
茶
駿河に近いこの地にあっては、お茶の木がよく育ち各家庭で昔から自家製のお茶をつくって飲んだ。一年中使用するお茶を家で製造するため、茶製造用の茶部屋を設け船型の「ろ」をつくり、炭火をおこしその上に写真のようなほいろをのせ茶の若葉を蒸したものをほいろの上で手でもみながらお茶にするのである。針状の上等なお茶を造るには高い技術を要し、部落の中でも「お茶師」といってお茶造りを専門にする者もでてきた。茶師には他の労働者の倍額の賃金を払ったという。でも「お茶師よりふかし手」という言葉があって、上等なお茶は何といっても「ふかし手」が上手でなければだめであったらしい。今でも自家用のお茶をつくる家もあるが、大方は南部方面や静岡方面から購入している家が多い。
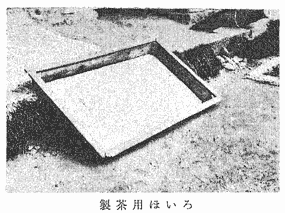 |
(七)食器、燃料、飲料水
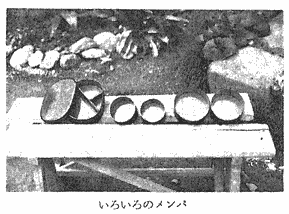 |
燃料は薪炭から石油、石炭、プロパンガス、電熱と進歩を見せ、現在では、プロパンガスが最も多く使用されている。
飲料水は長い間自然の流れや湧き水を利用していたものが井戸水を使うようになり、現在では動力で井戸水を汲み上げ、または、各部落で共同で簡易水道を設置して、豊富に水を使用して便利な生活が営めるようになった。
三、住
(一)河内地方の住居について
この地方の住宅は他の地方と趣を異にしている。甲府盆地を離れて河内地方に入るにしたがって、家の南側に切妻、他の側面は入母屋づくりの変った家が目立ち、身延付近から万沢にいたる間は笹板屋根、または杉檜の皮葺屋根等の家が多かった。なお特徴として、家の外部は下塗りの上に下見板の板壁で覆いをして、壁を保護している家が多い。これは夏南風が強いことと、降雨量が多い(明治30年以降35年間の年平均降雨量は2,600ミリメートル)ためにこのような傾向があらわれたものとみえる。内部の構造とか間取り付属建物等については国中地方と大同小異であって、特にこの地方の特色としてあげるものはない。 |
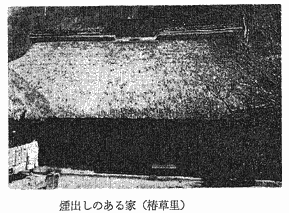 |
(二)間取りと衛生
昔の家は居間、座敷、奥座敷、なんどなどがあり、居間には「ひじろ」が切られていた。ここで薪を燃しては煮炊きをしたため家中が煤煙のために汚れ、古い家ほど家の中は黒く光るようになっている。また一般に北に面した採光の少ない室を納戸(なんど)と称して、押入れ代用としたり、また寝室に当てたりしていたが、この室は来客等の影響が少ないために、多忙の時は夜具を敷き続けたり、またここでお産をしたりなどしてその生活はごく非衛生的であった。なお昔の家はおおかたお勝手を北方の寒いところに取り、裏口をあけて背戸と言った。この背戸より水汲みに遠方の流れや戸外の井戸に出たものである。水も桶などに入れて運んできたもので、食器を洗ったり煮炊きをしたりしていたため、充分に水を利用することができず、非衛生的であった。 |
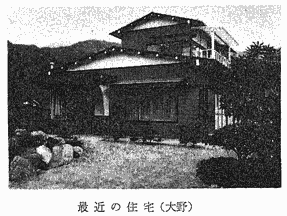 |
(三)その後の改造
明治34年(1901)ころよりトタンが入りはじめ、壁も次第にトタンを使用する家がでてきた。屋根もわら屋根から瓦屋根と変ってきて、現在ではブロック建築から鉄筋コンクリート造りの家などもぼつぼつでてきており、新らしく建築される家は、その間取り等も充分衛生的な配慮がされるようになって、暖かい南に面した部屋に居間やお勝手を取るようになった。台所は床を張ってステンレスの調理台には、ガスコンロや電熱器が備え付けられ冷蔵庫や換気扇なども設置して極めて文化的な生活ができるような様式が取り入れられつつある。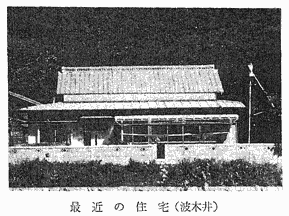 |
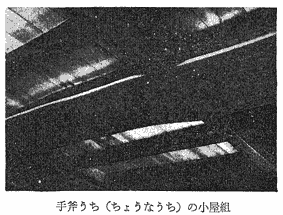 |
(四)照明
昔は灯火用として松の木の根(あかし)をともしていたが、その後菜種の油などを灯芯に浸し、「あんどん」として用いた。明治の中ごろから「ランプ」に変り石油を灯芯に浸し点火してガラスの「ホヤ」をかぶせたため自由に持ち歩きができた。その後電灯になったのは大正の初期である。身延町に最初に電灯がともったのは大正2年(1912)で今では各家庭が自由に電灯の使用可能なメートル制となり、蛍光灯の電球なども出回って金さえあればいくらでも明るい生活ができるようになった。
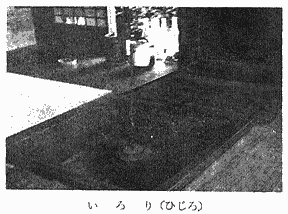 |
(五)現在の生活様式
現在の生活様式は非常に文化的になってきたといえる。大方の家で、テレビを入れ、冷蔵庫を備えつけて、新鮮な食物がいつでも手に入るようになり、ガスや、電熱をつかって手をよごさずに、たやすく食事のしたくもできて、しかも栄養のある、好みのものが自由に食べられ、また、自分の希望する衣類を自由に選んで着るようになった。そして1日の仕事を終えると、夜はテレビを見て時を過し、ねるときは、ふかふかしたマットレスに、やわらかい布団を重ねてねる家庭が多くなってきた。昔、暗い納戸のつめたい布団に一人苦痛をこらえてお産をした女性が、今では、明るい産院に入院して、極めて衛生的なしかも安全なお産をしていることなど、昔の人人にとっては想像もできないことであったろう。このように文化的な生活ができるようになってくると、何といってもお金が必要になってくる。お金さえあれば、より高い文化生活ができるとあって、今では、現金収入を目あてにして、お金にならない百姓などを専業にする家庭が次第に少なくなり、一家の主婦まで、出稼ぎをして現金を取ることを考えるようになった。明治のころから比べると物価の上昇は驚くほどで、自由に品物を得られる時代とはいえ、労働力がなく現金収入の少ないものにとっては、物価高の今の生活は、実に暮しにくく、そういう者にとっては、みじめな時代であるともいえる。参考までに明治のころの物価と、現在の物価を記してみたい。
| ○明治22年(1889)(伊藤商店売上台帳による) 塩1俵…20銭 米1俵…2円10銭 砂糖100匁…6銭 サバ20本…5銭(いわぶち仕入値) 木綿白地1反…50銭 下駄1足…13銭 汽車賃(岩淵←→東京間)…上等…3円90銭中等…2円30銭下等…1円20銭 |
|
| ○明治44年(1911)(伊藤商店売上台帳より)現在 | |
| 塩1叺…1円35銭 米京マス1升…60銭 酒1升…45銭 醤油1升…20銭 |
540円 220円 580円 200円 |
表1 米価の変遷
| 年次 | 一石当り 価格 |
歴史 | 年次 | 一石当り 価格 |
歴史 |
| 明治元年 | 4円23銭 | 大正10年 | 25円50銭 | ||
| 8年 | 5.13 | ロシアと千島樺太との交換 | 昭和元年 | 34円90銭 | |
| 10年 | 3.36 | 西南の役 | 3年 | 27.00 | 世界的不景気時代 |
| 20年 | 3.78 | 7年 | 17.50 | 満州事変 | |
| 27年 | 6.66 | 日清戦争 | 10年 | 26.00 | |
| 30年 | 14.30 | 16年 | 49.00 | 大東亜戦争 (第二次世界大戦) |
|
| 37年 | 11.80 | 日露戦争 | 20年 | 1500.00 | 終戦 |
| 40年 | 14.30 | 25年 | 5420.00 | ||
| 42年 | 10.00 | 米穀検査制度 | 31年 | 9470.00 | |
| 大正元年 | 8.23 | 35年 | 9755.00 | ||
| 7年 | 36.50 | 40年 | 16,375.00 | ||
| 8年 | 50.00 | 米騒動 | 43年 | 20,672.00 |