第二節 年中行事
民間の年中行事は古くから貴族や武士、更に寺、社の年中行事とともに相互に深いつながりをもって遠い昔から受けつぎ伝えられてきたものである。特に民衆は何よりも生産に従事する階級であったから、その年中行事も生産生活に直接関係をもったものが多い。
更に民衆の中心は農民であり、農耕の中心も稲作であったから民間の年中行事には稲作りにちなむ要素が根幹をなしているため、それを無視してはとうてい民間の年中行事の本質をとらえることはできない。
また、民間の年中行事には、その他漁業・商工業・養蚕などや、貴族・武士の行事から採用したと思われる要素もあり、また仏教や中国文化の影響によると思われるものも認められる。
それらのさまざまな影響を内外から受け、長い歳月を経ているうちに変化を重ねて現在に至っている。
特に第二次世界大戦後は、大きな変革をきたした。古来の行事が、多くは神仏を祭ることを中心としたものが、生活の近代化とともに簡素化され、昔ながらのものが少なくなった。そして、同じ年中行事でも、部落ごとに、また家ごとに違ってきているほどである。いまその概略を月を追って記述してみると次のようである。
正月行事
○餅搗(もちつ)き
早い家では暮の28日に搗(つ)く家もあるが、「苦餅」といって29日に搗く事を嫌い、30日に搗く家が多い。
朝、暁方から臼(うす)や杵(きね)を洗い、一握りほどの藁(わら)を十文字に敷いてその上に臼を据(す)えて搗く。お供餅の数は家によって異なるが、各神仏に供える数と家によっては、何軒かの家に配る数を主婦は、考えねばならないので、大へんである。
昔は多く搗く事を自慢したが、食生活の習慣の変わった今日では多く搗く家はなくなった。早朝から威勢よい隣近所の餅搗きの音に正月の近づいた感を深くしたものだが、今では身延の門内のように賃搗きや、買ってすませる家が多くなったので、餅搗きの音も聞こえないところもある。
○鏡餅
鏡餅は特に念を入れて搗きあげる。厚みをもったどっしりと落ち着きのある大小2つの重ねのもので、歳神や三宝などの上に白紙を敷いて置き、それに裏白・ゆずり葉・密柑などを添えて床の間に飾る家が多い。
その他神仏や日常使う農具や俵などに小さなお供餅をあげる風習もある。
○門松
「お松ヘエシ」とか「お松ハヤシ」とかいって、ふつう暮れの28日か30日に松を立てる。「九日松とか一夜松」といって嫌う風があり、立てる日も30日がよいとされていたが今はあまり気にしなくなった。
門松は、5段とか3段といって枝振りのよいものを立てたが、最近では一般に枝松で、それに竹・梅・南天などをそえ、形ばかりの門松が多くなった。門松を立てる杭(くい)に栗(くり)・樫(かし)など実のなる木を使うものだというところもある。
門松に朝夕炊(た)いたものを供える風があり、朝は餅で晩は暖く炊いたものをあげる。
門松を収めるのはふつう7日で、それを小正月のドンド焼きで燃(も)やす。なお門松をとったあとに、4日の初山の時伐って来た木を束ねて立てるところもある。
注連縄(しめなわ)は、自分の家で新しい藁で作る者が多いが、すべてが簡易化された今日では、歳末街頭に出た店から美しいものを買って来てすませる家もだんだん多くなっている。特に農家以外ではそうせざるを得ないような時代になった。
○歳神棚
座敷の中央に年々新しい縄で棚をつり下げるのがふつうだが、その座敷も奥座敷とか、南面している座敷とか、家によって違っている。また神棚の横に棚をつくるとか、神棚に注連縄(しめなわ)と松をつけるというところもあって一定していない。
歳神棚の注連縄には、両端に小松をゆわえつけ、四手(おしんめい)を月数の12枚(閏月の年は13枚)はさみこみ、棚にお供餅や柿・栗・密柑・御神酒を上げ、さかずきに生米を入れ、水を入れて供え、灯明をあげるところがある。
お供餅は月数の12膳というところと、「トシオソナエ」といって家族の人数だけ供える家、家によっては2膳とか3膳とかという家もある。また歳神棚の一部にほうそう神様をお祀りするところもある。
歳神様は「アラタカの神だから早く送るがいい」といって歳神送りは2日の朝早くするところがあるが、4日の朝お吸物をあげて明きの方へ送るというところもある。
歳神送りをすませると、棚板を傾けておくという風習もあったというが、現在はあまり見られなくなった。
○大晦日
「おもっせ」といい、この日は家の内外を清掃し、神棚・仏壇を清め、すべて新しい気持で歳神様を迎える準備をする。この日の夕食は早くするとよいとか、「おもっせ」の食事をしない者は、家の役に立たないといって、つとめて家族揃って食事をする。多くは御飯であるが、年越し蕎麦(そば)を食べる風習もある。
○元旦
108の除夜の鐘で一夜が明けると新しい年の始めである。一般に除夜の鐘の鳴り始めるのを待って、町内の寺々や、氏神様に初詣をする風習がある。
この日は朝早く起き、若水を汲(く)んで心を清め、歳神様に灯明を供え、邪気を払い、長生を祝う意味からトソを頂き家人と「おめでとう」のあいさつを交わす。
また、この朝は雑煮を食べる風習がある。昔は「若水は男子が汲み、三カ日は男子が炊事をする」といわれ、主人や長男が年男としてやったようだが、現在では女子1年の労をねらぎうほどにしか解しておらず、実際にはほとんど見られない。
年始回礼は、以前は氏神様へ詣でたあと、地類、大家とか親分、そして隣近所と回るのが普通であったが、今は年始回りを廃して氏神様や寺または公民館などへ集まって御神酒を汲み交わし、新年を祝う所が多くなった。また明治以来続いていた学校の新年祝賀式は、昭和43年正月から廃止されたので、部落毎に子どもを含めた新年を祝う会を行なうようになった。
○年賀状
近年、お年玉くじつき年賀はがきの発売とともに年賀状を出すことが盛んになり、早朝配達される年賀状に目を通すのも正月の楽しみの一つになった。特にいろいろな趣向をこらした手刷りの美しい年賀状や、昔なつかしい毛筆の年賀状など、年に1度の友人知人からの便りを見ることも新年の感を深くする。
○2日
「送り正月」といって、この日に歳神様を送る家がある。
また、この日は「初仕事」といって一般の家では何らかの仕事をするという風習がある。商店では初売りをする。
○初売り、初荷
2日は初売りといって商家の仕事始めである。この日は、福引きや景品などをつけて大売出しをして客を呼ぶ。また一般の人は初買いといって銭の使い初めをした。
また昔は荷物を馬や車に華やかに飾りつけて積み、「初荷」と書いた札を林立させて運んだが、現在ではトラックなどに「初荷」の旗をなびかせて通る。この光景は時代の差こそあれ、同じ風習である。
○書初め
この日子どもたちは半紙を2、3枚つないで書初めを書き、天神様に納めて上達を祈願した。
大河内地区では毎年公民館主催で小、中学生の書初め展覧会を実施している。それへ出品するため子どもたちは競って練習している。
○3日
元旦よりこの日までを「三カ日」という。3日は不浄日のため何もしないというところもある。
○正月の遊び
昔は外の遊びとして男の子はたこあげやこままわし、それに竹馬に乗って遊んだものである。一方女の子は、晴着に着飾って羽根つきをしたが、今はそういった遊びもほとんど見られず凧上げをする子どもの姿を時々見かける程度である。羽根つきは戦後バドミントンに代わった感じである。
室内遊びでは、かるた・双六・百人一首など昔は盛んに行なわれたものだが、最近はあまりしなくなった。百人一首が町内の一部の愛好家の間でなされているにすぎない。
○初山
4日を「初山」といい、正月の仕事始めとして山に木を伐りに行くことは、山の村や山添いの村では全国的になされていることで、山入りをして一把(わ)でも薪をとって来るものとしている。
今でも山へ行き、アボウ様をハヤシて来て木々の供養としてお吸物をあげているところがある。またこの木を7日の門松を送ったあとへ立てて、お茶や吸物をあげるところもある。
○お棚さがし
正月三カ日の間、歳神様に朝夕炊いた物を供え、下げずにおいて、4日の朝みんなおろし、「お棚さがしのおじや」といって、それでおじやを作って食べる習わしがある。
しかし、衛生思想の普及した現在ではあまり見られなくなった。
○消防出初(ぞめ)式(6日)
出初式には町内4分団20部よりなる身延町消防団員およそ600名と、身延町婦人消防後援隊員も参加し、また近代装備の消防車をはじめとする十数台のポンプが勢揃いする。
式は県や郡、また隣接町村より関係者多数が来賓として招かれ、寒風の中で厳粛に進められる。そして機材の点検やポンプ操法の実演があって出初式が終了すると各部落に帰って放水試験が行なわれ、1年間の無火災を祈念する。役員は各家庭を回って祝儀をもらい、午後より初総会が開かれ、そのあと祝宴が催される。
○七草粥(がゆ)
七草は一般に7日の朝行なう。なずなや大根・人参(にんじん)・牛蒡(ごぼう)など手近に得られる草や野菜をなるべく多く集めて、「七草なずな、唐土の鳥と、いなばの鳥と、日本の橋を渡らぬ先に、あっちへ向いちゃばたばた、こっち向いちゃばたばた」という唱えごとをしながら爼板を叩き、そして細かくきざんで粥をつくって食べる行事だといわれるが、実際には七草といっても春の七草ではなく何でも野菜を使っている所が多い。唱えごとも土地によってまちまちで一定していない。
一部には6日が女の山入りで、その時にとって来た野菜を6日の夜俎板の上で叩いて、7日の朝のお粥の中に入れて煮るというところがある。
七草までを松の内といっており、この日で門松を収め正月もおわるのである。
○田植え節句
11日を田ウネェ節句といっている。波木井では蔵開きの日だともいい、「蔵は籾を入れる所だから田の神様だ」といって鏡餅に挿した松を田に持って行き、田をわずかばかりうなって立て、帰って来て吸物をいただく。家によっては松の小枝に注連飾りと、米を3、4粒紙に包んでしばりつけたものを田に立てる。更に餅や酒、茶などを供えるところもあったが、今はあまりやらなくなった。
○削り花
13日に、みずくさの木で花を掻(か)き、削り花をする家もある。昔は三椏(みつまた)や楮(こうぞ)の一ヵ所を削りかけにして花といい、神棚や歳神様、墓などへあげ20日の風をあてないうちにとるといわれている。
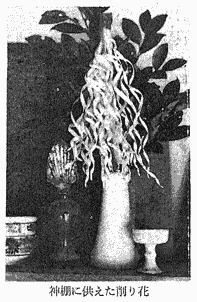 |
13日に米の粉をねって団子をつくる。繭の形をつくるというが、ふつうは丸い団子で、そのほか、大判、小判、きんちゃくとか南瓜とうがらし、にわりと等々をつくり、樫の枝にさして大黒柱や土間等に飾りつける。梅の枝を使うところもある。
なお、団子をゆでた湯を家の周囲にまくと長虫除けになるといって撒くところもある。
この団子は15日におさめて雑煮に入れて食べる。
また大黒様には俵を積んだ形にして供えたり、お荒神様へ鳥の形を作って供えるところもある。
更にほうそう団子というものを作る。大きく丸形(そろばん玉の形のところもある)に3個つくって、樫の木の三ツ又になったものにさして飾る。小形のものを作って初っ子のあった家に配る風習もあった。
○ドンド焼き
各家の門松や注連飾りを集めて、若い人が昔は道祖神の前や川原などに小屋を作り、焼くことがドンド焼き(またはドンドン焼き)と呼ばれ、各地区で広く行なわれている。
ドンド焼きは、14日の朝か夕方で、小屋は建てないが道祖神場の注連飾りや柳飾りを焼いてドンド焼きをする。
この火でほうそう団子を焼くが、それを食べると虫歯にならないとか、ほうそうを病まないといわれている。また書き初めが高く上がればうでが上がるということがどこでもいわれている。
○道祖神
いかなる山間僻地にいたるまで道祖神の姿をみない所はない。村々の道端・辻々・山道の分岐点等に必ず見られる。
このように民衆に親しまれ、民心に喰込(くいこ)んでいる神であるが、道路の悪魔を防いで行人を保護する神道陸神ともいい、自然石に文字をきざむもの、像をきざむものなど、形はいろいろあり、祭神はくなどのかみ、たむけのかみともいわれているが五穀の神、安全の神、男女和合などを祈願する、祭は男女青年が行なったが子供に親しい神である。
道祖神の前に注連縄を張り、幟(のぼり)を立てる。
また、7日か11日に柳飾りを若い人が中心になって立て、14日には獅子舞をする。
14日の朝、道祖神の前で獅子を舞い、それから部落の各戸を回るところや厄年の家を回るところがある。下山の大庭ではこの時万才をする。
昔はその夜、新婚の家にお宮を担ぎこみ、獅子舞をして振舞いを受けまた幣束を持って、新婚の家を回り、座敷に上って花嫁の前へ幣束を載せた三宝を据え、祝言をいい、花嫁が有難く頂くと青年頭が謡をする。このようなことを「オカタウチ」といっているところもある。
(大野の道祖神祭り)
大野では、道祖神祭りを長男の成長を祝う祭りとして昔から行なってきた。
いまから4、5年前までは、上村では正月7日、宿では正月11日にそれぞれ組内の人がその年の当家(長男のお祝いをしてもらい御神体を祭る家)に集まって、屋敷内に柳飾りや道祖神棚のお飾りをして祝った。
この道祖神棚の飾りは、座敷に棚をつくり、棚の上部に巻き藁をゆわえつける。そして、長さ2メートルほどの竹ひごに、色紙でつくった花を、9個か11個つけ、ひごを全部で12本作って巻き藁に通して飾った。更に棚の両はしには紙の幟を立てた。
また、7日に柳を立て11日にそれぞれ倒し、14日には若い者が中心になって、ドンド焼きをする。そのあとお頭が道祖神の祠に御神酒をそなえて、御神体を前年の当家から新しい年の当家へ送り届ける。
現在では、社会生活の変化によって柳飾りや道祖神棚も廃止し、形ばかりの道祖神祭りをするようになった。
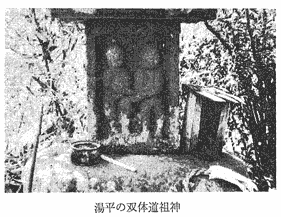 |
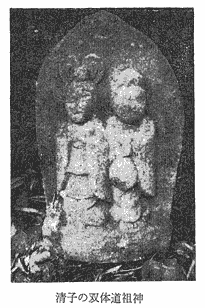 |
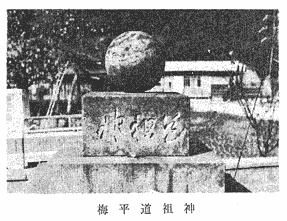 |
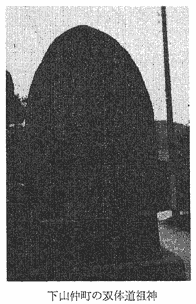 |
7日に建てるところと11日に建てるところがある。この日は朝から若い人が集まって準備をする。長い竹を細く割り、それに色紙をまきつけて束にし、その一端を長い幟竿に結びつけて八方に垂らす。その上に竹と縄で山形の網の目を作ってつける。これを道祖神を祀ってある祠の前に建てるのであるが、その細く割った竹がシナシナ曲って垂れる様が、いかにも柳の枝のように見えるところからヤナギといわれている。
柳の数は12本とか36本とかいい、世帯数だけつくるというところもある。
たおした時は柳は輪にして各戸に配られ、屋根にのせて火除けの呪(まじな)いにするところがあるがドンド焼きで焼いてしまう所もある。
現在ではヤナギを作って建てるところも少なくなった。
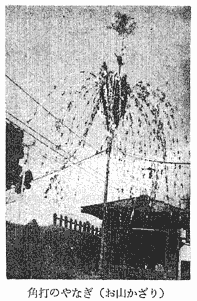 |
15日の朝、ぬるでの木で作った太箸(はし)で小豆を入れた粥(かゆ)を食べる習わしがある。お福粥(ふくかゆ)ともいい、その年万病を避けることができるという。また切り口に十字の割れ目をつくったぬるでの木2本を縄で結び、粥をかきまわしその割れ目に入った粥の数で豊作を占ったという。後にこの粥かき棒(けえかき)を大黒様にあげておき、春、苗代をつくる時に水口に立てて田の神としたり魔除けとして用いるところもある。
この粥を吹いて食べると田植えに風が吹くといって自然にさまして食べるといわれている。
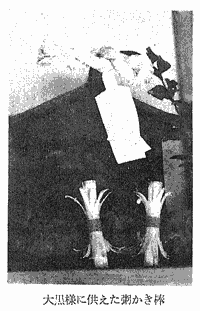 |
満20歳の成人に達した若人が社会の一員として仲間入りするのを祝い、激励する意味で式典といろいろな行事が町の主催で行なわれる。行事はその年によって異なるが、記念講演やフォークダンスなど成人を祝うにふさわしい有意義な催しが行なわれている。
この成人式は町内の地区により異なるが早いところでは昭和24年頃より行なわれている。
 |
 |
山の神はいうまでもなく山を支配する神である。農民の信ずる山の神は、春には山から里に降りて田の神となり、秋には再び山に帰って山の神となるのであるが、山かせぎをする人の信ずる山の神は、田の神とは関係ないようで、入山者の安全を守るといわれている。
一般に、17日の弓張り節供と21日の冠落としの2日を祝う。
17日には竹の弓矢を作り、山の神に納め、21日は、山の神が自分の冠の落ちるのも忘れて山の悪者を弓で射る日なので、山に入ってはいけないといわれている。