○初午
昔は旧暦の年初の午の日であったが、今は2月の初の午の日、稲荷をまつる風習がある。
これは農神としての稲荷信仰が早くから流行したためである。
この日、稲荷に「正一位稲荷大明神」と書いた色紙5枚つなぎの紙旗あるいは布旗などを立てたり、赤飯や油揚げなどを供えて祭る。
なおこの日は朝早く神仏へお茶をあげてはいけないというところがある。
○節分
立春の前日を普通節分という。冬から春になることを祝うのであるが、節分の晩には煎(いり)り豆を「福は内、鬼は外」と撒(ま)く追儺(ついな)の行事が行なわれている。
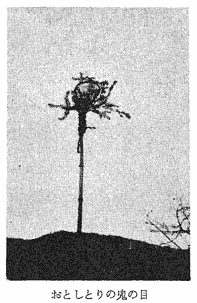 |
なお、庭へ目籠(めかご)や手すくいざるを竿の先に結びつけて立て、これを鬼の目にたとえて、「福は内、鬼は外」と家の内外に豆を撒いたあと、「鬼の眼をぶっつぶせ」といって豆を投げつける。
撒いた豆は掃き出さず、明朝これを拾って始末する。福を掃き出さないという意味であろう。
また、煎り豆を年齢より一つ余計食べると幸いがあるといい、その豆を保存しておき、初雷の日に食べれば1年中風邪をひかぬとか、落雷の災から逃れるといわれている。
この行事も、最近は、次第にひっそりと行なうようになってきた。
一方、身延山の豆撒きは盛大である。
祖師堂で節分会大法要が行なわれ、そのあと、祖師堂前広場の特設された舞台で豆撒きの行事が催される。この豆撒きは、毎年映画スター、力士、野球選手などを年男に招いて行なうので近郷近在の者はもちろん遠く県外からも観光バスを連ねて参拝と見物に集まる人々で賑わう。
3月の行事
○春の彼岸と春分の日
彼岸は、春分の日とその前後3日の7日間にわたる仏教行事である。寺では彼岸の法要が行なわれ、各家々では墓を清掃し、「中日ぼた餅明け団子」とか「入りぼた餅に明け団子」とかいって、ぼた餅を作り、祖先に供えて供養をし、墓参りを行なう。
○弁天様の祭(26日)
高島河原(下山上沢地区)はその昔大きな松林であったという。そこに弁天様をお祀りしてあったが、明治40年(1907)の水害で流されてしまった。その頃の交通は富士川を船で上り下りしていたので船の往来が盛んであった。
たまたま丸滝の今の大河内中学校近くでその弁天様が発見されたので、上沢区の代表者がその破損したところを修繕して、現遊園地にお祀りして今日に至っている。
したがってこの弁天様は弁財天ともいい、貧窮を救い財宝を与える神といわれ、ここでは水難守護の神様として、早川河原の開墾をした早川新田組合の者も上沢地区と一緒に毎年1月26日にお祭りをしていたが、昭和39年から、3月26日に日を改めて、上沢地区が組ごとに当番に当たり、餅を搗(つ)いて供え、これをお仏供(ぶつく)として上沢区全戸に配ってお祭りをしている。
4月の行事
○桃の節句
女の節句として女児のある家では座敷に雛(ひな)段を設け、それに内裏雛(だいりひな)や官女あるいは御殿・高砂等いろいろな雛人形やぼんぼりを飾り、白酒・菱餅・料理の重詰めなどを供えて女児の成長を祝い息災を祈願する。一般に月おくれでするところが多く4月3日にする。
また、出生後初めての節句を迎える女児のある家では「初節句」といって親戚知人よりお祝いの品や雛人形などを贈られる。そして返礼として赤・白・草餅の三色の菱餅を引出物に添えて出すところもある。
○大野山のお会式
 |
4日は開祖日遠上人の命日で、稚児の出仕があり、祭文を読み上げるなどして法要が行なわれる。5日は施餓鬼法要のあと稚児行列を伴い富士川の河原まで川供養に行く。法要に供えた米・果物・菓子等をも蓮台に載せて船頭が担ぎ、川端まで行き読経後供え物を川へ流して、昔から富士川で水難にあった人の霊を供養した。
この日は参道や境内に露店や見世物小屋が立ち並び終日参詣人で賑わった。
以前は4月3日・4日であったが、現在は数年前から4月最初の日曜日に法要と施餓鬼会を1日にまとめて行ない、稚児行列はあるが、川供養も塔婆を流すだけで、露店もまばらで昔に比べて参詣者も少ない。
○灌(かん)仏会
各寺院では釈迦の誕生日として灌仏会を行ない、甘茶を参詣人に振舞った。その甘茶を家の周囲に撒(ま)くと家の中に悪い虫が入らないといわれた。
今は身延山で甘茶をくれるぐらいでほかの寺院ではあまりやっていない。
○御殿山(ごてんさん)の祭
豊岡地区の南部町との境に、御殿山という山がある。その山頂に小さな祠(ほこら)があり、天狗さんとかタカガミさんが祀ってあるといわれる。
昔から土地の人の間にはその辺を通ると足が前へ進まなかったとか、馬に乗っていても馬の足が足止めされたようになってしまって、天狗さんにかどわかされたという言い伝えがある。
この祭りは、昔は旧の3月17日に行なわれたが、今は新の4月17日に横根部落と南部町の中野・本郷・成島の部落の人たちが、店の寄付や賽銭(さいせん)で神酒を買い、赤飯を炊いて持ち上げ、僧侶とともに読経の後(あと)、参詣者にお仏供(ぶつく)として振舞っている。
昔は赤飯の代りに餅を搗いたといわれている。更にお祭がすむと近くへむしろを敷きあちこちにたむろして博打(ばくち)をしたと伝えられていることから、この祭りを別名「バクチマツリ」ともいっていた。たいへんめずらしい祭りであった。
5月の行事
○端午の節句
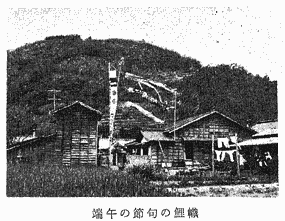 |
「男の節句」といわれ、男児の強く健やかな成長を祈念する行事で、5月にするところと6月にするところがある。
昔の風習にならい、家の軒に菖蒲・よもぎ・すすきを束ねてはさみ、戸外には定紋や武者を染めぬいた幟(のぼり)や吹流し・鯉幟(こいのぼり)などを立てる。家の中には武者人形や金太郎・桃太郎・鐘馗(しょうき)天神などの人形・武具・鎧(よろい)・兜(かぶと)などを並べて飾り、柏(かしわ)餅を作るところが多い。
最初の男子のある家では「初節句」といって親戚知人から祝い品が贈られる。返礼として柏餅を引出物につけて出すところがある。この日に菖蒲湯に入ると疫病を防ぐといわれている。
○八十八夜
立春より数えて88日目ということである。「八十八夜の別れ霜」といってこの日以後は霜もないので何の種子を蒔いても良いとしている。稲の種まきや、茶摘みもはじまる時期である。
6月の行事
○茶堂のお祭り
総門を入った所、左手石段の上に日蓮聖人と波木井公を祀った発珍閣(ほつちんかく)がある。正式にはこの発珍閣のお祭りである。
昔は旧6月17日に御入山会といっしょにお祭りをしたものである。特に戦前は娯楽もなかった時代であったから屋台をかけて演芸をしたり、映画などをしたため、参詣人も多く、露店も並び大いに賑わったものである。
戦後はその祭りもやらなくなり、現在は新の6月18日に豊岡の妙法講の人々が来てお題目をあげる程度である。
○波木井八幡神社祭
1区と2・3区の八幡様が6月15日に祇園祭として同時にお祭りをする。部落では当番を決めて餅を搗いたり、米を集めて団子を作り、それをお供えする。
お祭りには部落の人々が参列し、神主が祝詞をあげる程度の祭りだが、供えた団子をお祭りに集まった子どもたちに配っている。
7月の行事
○祗園
祗園祭は京都の八坂神社の祭りだが、波木井八幡神社外各社の祭りが祗園祭としている程度で、一般の農村の祗園祭はこれら本社のものとは必ずしも趣を一にしていない。祗園はこの辺ではあまりやっていないが、家によっては餅を搗いて神棚に供える程度であったらしい。
農民が祗園を祭るのは主として水神信仰によるものである。
○土用の丑の日
暑さの厳しい時であるので暑気払いによいといって、うなぎや精進揚げを食べる習慣がある。
また、この日に稲の虫送りを6、7年前までは多くの部落でしていたが、いまは次第に少なくなった。
8月の行事
○七夕祭
7月7日およびその日の行事をいうが、この辺では月おくれでする。牽(けん)牛星と織女星の接近を人間の男女になぞらえていろいろ空想の伝説や物語が伝えられている。日本の星祭りは中国の星祭り(乞巧奠)をとり入れたものである。
この日には少女が技芸の上達を願う行事が行なわれ、男の子も字がじょうずになるようにと芋の葉の露で墨をすり、短冊に腕をふるって字を書く風習がある。
色紙を短冊形に切り、それに「天の川」「たなばた」「七夕や」その他星に関する事や、自分の願いごとなど書きつけて笹竹に結びつけて6日の宵(よい)か7日の朝から庭先に飾る。それを7日の夕方には川へ流すが、「夕食の膳」をつくって供えてから川へ流すところもある。
特に「身延の七夕」は有名で門内商店街では競って美しく立派な七夕の飾りを作って観光客を呼び目を楽しませる。一時旅館などでは1週間ぐらい客を断わって七夕飾りの準備をしたともいわれ、その大きさ美しさも見る人を驚かしたものであったが、最近は参詣客の数も増加したため、忙しさのあまり七夕飾りにはあまり手をかけなくなってきた。
○お盆
13日は迎え盆、または宵盆といって家屋敷のまわりを清掃し、墓地を清め、花立てをつくり、門や墓地に立て、それに桔梗(ききょう)・女郎花(おみなへし)などの盆花を供える。「盆花とり」を子どもたちがやっているところもあった。室内には曼陀羅(まんだら)をかけ、きれいな茅萱(ちがや)のござを敷いて祭壇(盆棚)を作り、祖先の位牌を立てる。また、茄子・胡瓜に割り箸を通して馬の形を作り、その背にはめん類(ゆでないもの)をまき、餅や果物、野菜を供える馬の形を作るのは祖先の霊がそれに乗って来るといわれているからである。
また、軒には提灯(ちょうちん)を吊(つる)し、墓地には灯籠(ろう)を掲げ、その日は門や庭で迎え火を焚(た)き、家族揃って墓参りをし、線香をあげ火を焚く。
盆棚に精霊(しょうりょう)が来臨しているとすると墓も空な訳であるが、毎夜墓参りをするところがある。これは墓にまだ残っている精霊があるように考えてのことで、この考えはこの地方だけのことではない。
14日に、新(にい)盆の家には親類縁者が供物を持って訪問し焼香する。新盆の家では月の初めから月の終わりまで高灯を掲げていたといわれている。
16日は俗に「地獄の釜もあく日」または「籔(やぶ)入り」の日といって雇人は父母の許に帰省したり、一般に1日遊ぶ風習がある。
また、この日は「盆送り」とか「精霊送り」といって先祖の霊に供えた食物とか馬をござに包んで川に流し、川や墓で送り火を焚く習慣がある。
なお、盆の13日から16日にかけて寺の境内や部落の広場などで老若男女が集まり、盆踊りが夜半まで続いて賑わったものだが、今はそれもあまり見られない。
○投松明(なげたいまつ)
盆の火焚き行事の一つで、高い柱の頂きに燃料をつけ、下から松明を投げ上げて火をつけ、亡者を供養する行事で一般に投松明といわれている。
この地方でも10年ほど前までは、子どもたちが中心になって川原などでやったものだが今ではあまり見られなくなった。清子では長い歴史を持って現在でも投松明の行事が行なわれている。
開始の年代は不詳だが伝えによると、盆の供養のため、また一説には火伏(ぶ)せ祭りともいわれている。いつの頃か中止したら村内に大火があり、以後引続いて今日に至っているともいわれている。
近村各地で行なわれているが清子の投松明は大規模で他に例を見ないものである。
| 実施月日 | 盆の14・15・16の3日間の夜 | |
| 参加者 | 10歳から20歳までの男子 | |
| 応援 | 消防団員 | |
| 役職 | 大頭(若干名20歳のもの)小頭(若干名) | |
| 係 | かつぎ手若干名刺又 大刺又1組2名、小刺又2名ずつ3組6名 根元2名、綱元東1名 南1名 北1名 引手大勢 はな番、小用たしをするもの(1回ごとに交代する) | |
| 用具 | なる(杉)およそ14メートル 刺又(竹)大小4組笠(麦わら)若干引綱3本現在はマニラ麻製ロープ以前は藁縄松明直径6.7センチ、長さ25.6センチ(各自持参) | |
| 方法 | 松明に火をつけて投げ上げて笠に入れて焼く、焼き終ると倒してまた笠をつけて立てる。一晩に3回から5回ぐらいくり返す。 | |
| 場所 | 部落の中央、俗称投松明場約8アール 所有者青年 | |
| 費用 | (金)区内より若干円を徴収(物)麦わら、藁縄を各戸よりもらう。竹(ま竹・孟宗等)のある家からは竹をもらう 収支について 竹の残品は買却する費用の残金と合して17日に後片付をすませて後菓子などを買って参加者に分配する。 |
存続はすべきだが参加者も年々減少するので、もっと小規模のものにしたらどうか。3日間を1日か2日くらいにしたらどうだろうか、などと考えられている。
 |
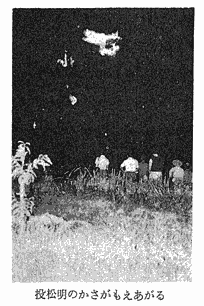 |
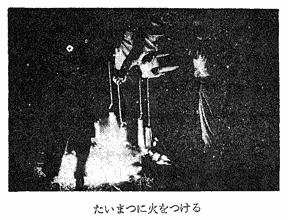 |
○下山愛宕神社祭
この社には火防将軍地蔵尊を祀(まつ)ってある。
昔下山上沢の愛宕山に祀られていたものを、明治初期に新町の現在の地に祀るようになった。
祭りは無火災、五穀豊穣(ほうじょう)を祈るために毎年旧の7月23日に花火をあげてお祭りをしたが、7、8年前からお盆の行事に統一し、16日にお祭りをするようになった。
明治初期は新町の若者が作った横に動く花火をあげたという。その頃は青柳方面から露天商が来て、高田のごまいた・かやあめ・にっき・もろこし・ところてんなどを売っていた。
これを見物に、波高島・飯富・身延方面から大勢集まり盆踊りをして賑わったものである。現在も新町の若者が中心になり、慣例に従って打ち上げる花火は、夏の夜を七色に彩り、その美観は筆舌に尽くせない。
また夜店も新町の通りを一ぱいに埋めつくし身動きもできない程の賑わいである。
○下山穴山八幡祭
穴山梅雪が武将の神、八幡様を祀り、社は下山小学校の井戸の場所にあったが、明治になって小学校建築のため本国寺の境内に移された。
特に武将の神をお祀りするこの神社の祭りは、昔から心身の鍛錬を中心とする相撲が奉納され今日にいたっている。特に明治以前、辻相撲が盛んな頃は各方面から力士が集まり、一週間程練習をしてその祭りに参加したという。
また、文化年間には各部落で神輿(みこし)や屋台を出し、その順位も争ったといわれている。
現在も各部落が毎年順番に当番を引き受け会所を中心にして中老・若者が寄付金を募り会場を整えるなど一切の準備をしてお祭りをしている。
○七面大明神
身延七面山にお詣りできない信者が部落に七面大明神をお祀りして、ここにお詣りして自分の心願を祈念したものであるといわれている。祭典日は部落の都合で定めている。
帯金の七面山は、七面天女を祀り、妙経寺の境内にある。
8月18日に施餓鬼をし、川に流れた人の供養をする。村人はその夜は盆おどりで夜を明かした。昔は露店も多く屋台を連らね、提灯が道の両側にともり、お堂には灯明をあげ、そのまわりに老若男女大勢がすわって太鼓の音とともに読経の声も響き、また一方では相撲も行なわれるなどきわめて盛んなお祭りであった。
しかし、終戦後は人数も減少し、一時は盆踊りも中止したが、最近また復活し盛り上がりつつある。
○波木井山の川供養
正しくは波木井山千部川施餓鬼会という。弘安4年(1281)、当時は水難が多く、富士川での犠牲者の霊を供養するため波木井公の懇請によって日蓮聖人が水難者の施餓鬼供養をしたのが最初であるといわれる。
昔は17日から19日まで3日3晩行なわれたというが、現在は19日1日のみ、先祖の回向と水難、戦災および横死の諸精霊の供養のため、壇家総代と住職とによる本願所が中心となり、波木井区が後援して施餓鬼会を行なっているに過ぎない。
昔は部落の家々の軒には灯籠が立てられ注連縄を張られ、特に水害から部落を守るために部落の若い人が中心になり、力士を頼んで堤防で「土手固めの相撲」が奉納され、盛大な祭りをした。
17日は1区から3区までの若者が出て、辻つきといって相撲の土俵をつくり、18日は寄付集め、19日には相撲をし、20日は片つけをしてこの祭りを終えた。
当日は、トラック数台に優勝旗を何本も靡(なび)かせ、威勢のよいふれ太鼓と若者のかけ声も勇ましく町内の各部落にふれて回った。そして、露店も遠くから来て沿道に並び見物人も村々から集まって賑わった。
なお、波木井山の施餓鬼会が終わり、川供養の行列が川へ行くのを待って、相撲をとっていた若者は一旦(たん)中止し、蓮台を担いで川まで運び読経後川へ流した。戦前は日本軽金属の堰(えん)堤もなかったので舟2艘を出して精霊流しをしたともいわれている。
しかし、最近は若い人も土地に少なくなり、相撲をおこなわず、波木井山の施餓鬼会に打ち上げる花火だけで当時のおもかげは見られない。
なお波木井の人は、川供養が終わらなければ盆は終わらないと考えているという。
○和田の地蔵祭
 |
「宝暦年間、大島の五作という大工と角打の庄屋の娘とは一人息子、一人娘の間でありながら恋仲となった。一緒になれないことを悲しんでいるところへ、白翁という僧が通りかかり、2人が江戸に住むよう努力してやり、彼等の子どもを両家の後継者にした」。
その2人が話し合った場所に2体の地藏さんが祀られたという。
延命と縁結びの地蔵ということで、遠く富士宮の方面まで知られ願をかける者もあるという。
祭りは8月23日夜から24日にかけて行なわれ、以前は踊りや相撲が盛んだったが、7・8年程前から8月17日に御神酒だけを供えてのお祭りということになり、往時をしのび一抹の淋しさを禁じ得ない。
○日朝さんのお祭
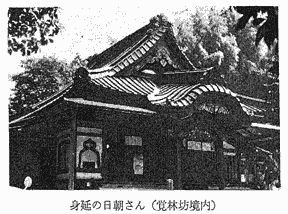 |
その祭りは7月24日のところと8月24日のところとあり部落の人が中心になり、御神酒や餅などを供えてお題目をあげ参詣者にお仏供などをやっているところが多い。
昔は各地のお祭りとも非常に盛大で、各戸で馳走をして近隣や親戚を招いたり、露店も並んで子どもたちにとっても楽しい祭りであった。
24日の夜は相撲や踊り、あるいは演芸会や映画会などいろいろな催しが各地で盛大に行なわれたものだが、今はどこも、そういった催し物もなく、土地の人の素朴(ぼく)な信仰の行事になっている。
なお、東谷の日朝さんは昔から眼病にご利益があるといわれ、多くの参詣者で賑わったといわれるが、これも日朝上人が晩年眼病にかかられご自身で眼病守護の願をたてられ79歳で入寂されたことによる。