○八朔(はっさく)(旧暦8月1日)
八朔には稲作にともなう秋の稔(みの)りの豊穣(ほうじょう)を期待すること、刈穂を直会(なおらい)の料として贈り合ったこと、それから八朔休みと以上三つのいわれがあったようであるが、一般には八朔休みをとって農家の休み日であるとしているところが多い。
各戸では団子を作って祝ったが、この頃より夜長になるので夜業が始まることから俗にこの団子を泣き団子といった。今はあまり聞かれない。
○石割稲荷祭典
日蓮聖人入山の折に、この地の大石を割って出た白髪の老人が聖人をお迎えした。村人は奇異の感にうたれこの地に老人を神として祀ったという。
この石割稲荷さんは、身延山の守護神として大切な神であるといわれている。
祭りは9月1日に元町区で行なう。区では御神酒や、餅を搗(つ)いて供え、赤飯を炊いて参拝者に配っている。
昔は相撲が行なわれ、露店も出て賑やかな祭りだったが、今は福引きをしたり、部落の人が踊りをする程度のお祭りである。
○身延山二王尊祭典
身延山の雄大な三門に祀られている二王尊の祭典である。
昔は旧暦10月8日に行なわれていたが、戦前より七夕祭を盛大にするという意味で8月7日にするようになった。三門前の広場では踊りや若い人の草相撲が行なわれ、露店もでて賑(にぎ)わったものである。
しかし、その後一時祭りも下火になり恵善坊が主体となって、ひっそりとした祭りが行なわれていた時代があったが、昭和42年より町内の有志より成る二王尊奉賛会が作られ、それが主体になって祭礼の日も9月7日に改めて盛大に祭りをするようになった。
祭りは門内の上町・仲町・橘町・元町・清住町の各区で御神酒やお供えをあげ、お経があげられる。
なお、催物として広場に舞台をつくり、東京などから芸人を招いて余興をしたり、花火大会もおこなわれ盛大な祭りである。
○上の山八幡神社祭典
久遠寺の裏にある「上の山」に小社がある。その沿革は必ずしも詳かでないが、古くは梅平の芦沢にあり、甲斐国志によれば「波木井の総鎮守にて日蓮聖人拝謁ありし祠」である。その後宮本坊の傍(かたわら)に移し、更に身延の片隅に、三転して現地に遷座したと伝えられている。
ここには天照皇太神と八幡大菩薩の二神が祀られている。この二神を聖人が我が国の本主としてあがめ、国家守護の見地から崇んでいたといわれている。
祭りは旧暦8月15日だったが、現在では毎年9月15日となり、門内5町(上町・仲町・橘町・元町・清住町)の人が輪番でお祭りをする。当番の所は神酒とお供えを6個あげ、自分の区の寺の僧侶とともに行ってお経をあげる。昔は、草相撲・福引き・俳句の連懸け・席書きなど多彩な行事があって、露店も出て賑わったが、現在では当番の町で金を集め福引きをしたり、各区の青年が万灯を1本ずつ出して題目を唱えながら14日の夜参拝するようになった。
○十五夜
旧暦8月15日、野の芒(すすき)の穂を花瓶にさし、月見団子や枝豆・芋などの野菜・それに果物などを盛り、縁先に出して月に供え月を賞する。一般に生のものを供えるとしており、芒は5本、月見団子は15個作って盛るというところが多いが、団子はつくらないところがある。
また、昔は団子突きという習慣があり、これは全国的なもので、子どもがこっそり供えられた団子などをとったり、家々を回ってもらい歩く風習があちこちに見られる。
とられた家でも笑いながら代りを補充したり、十五夜の団子は盗られるほどよいともいわれ、この晩に限って子供の悪戯(いたずら)が公認された形であった。
○秋の彼岸
春の彼岸と同様である。
10月の行事
○身延山のお会式と万灯行列
12日の夜、門内の通りに沿う家々の軒には提灯が下げられる。
13日は青年が中心になり、門内の各区で1本ずつの万灯を作って総門に勢揃いする。そこから久遠寺まで万灯行列をして練って歩くのであるが、揃いの衣裳で踊る万灯行列は、実に見る人の目を楽しませてくれるものがある。最近は門内各区の婦人会の踊りも万灯のあとに見られるようになった。門内各区あげて盛大な行事である。
○十三夜
後の月見として十五夜と同様月見団子をつくり、果物や野菜などを供えるが、十五夜と異なり煮たものを供える風がある。また団子や芒の数もそれぞれ13個と3本といわれるが最近はあまりやっていないところもある。
○各地区神社の秋祭り
各地の地神の祭りが行なわれる。これは春の社日にお降りなった農業の神様が、収穫も終わったために天に帰られるということで農作に感謝して行なわれるもので、八幡様やその他氏神様の祭りが、各地区で盛大に行なわれている。
部落の家々の前には祭礼の灯籠が立てられ注連縄が張られる。神社には氏子が集まり、神酒を供えたり、お供えをあげて神主が祭典をする。
子どもにはお菓子などが与えられ、子どもたちによる神輿も部落を練って歩くところもある。また、年間の神社の祭典を1度に集めた形で10月に区が主催して秋祭りをする大野区のようなところもある。
時代の流れにそった祭りの形式といえるかもしれない。
○塩之沢の天神様
塩之沢の山頂に天神様がお祀りしてある。ご神体は魔王天神ということである。
元旦は早朝より初詣にお参りするものも多く、またお天神様ということで入学試験などいろいろの試験に合格できるようにとお祈りする者もある。
部落としてのお祭は、毎年2月15日・7月15日・10月25日と3回おこなわれるが最も盛大なお祭りは10月25日である。
この日は、部落各戸より祭典費を集め、お供物を用意したり、茶菓子を準備したりして会場を公会堂に移す。
わが子、わが孫が、より賢くなるようにと老若男女多数集まり、現代的な楽しい集いのお祭りを行なっている。
11月の行事
○蒔上げ
最近麦を田に蒔く家はあまり多くないが、昔は多くの家で田にも麦を蒔いたので秋の農事もたいへん多忙であった。特に麦を蒔き終えると「蒔上げ」といって神棚に御神酒と赤飯、または、ぼたもちを作って供え、家人や手伝いの人々に馳走して祝った。
○十日夜(とうかんや)(旧暦10月10日)
4月10日に山より降りられた田の神様が五穀豊作と見込みが立ったので、最早里にいる必要なしとして山へお帰りになるといい伝えられており、その長い間のお骨折りを感謝するためにお祭りをするのだといわれている。
農家では新穀を用いて鏡餅をつくり、台所に籾俵を2、3俵積んでその上に供えて祀ったといわれ、餅のほかに団子をつくって供えるところもある。
○七五三
子どもが3歳になると髪置、5歳で袴着、7歳になれば帯解の各祝いをし、衣服を整えて産土神に参詣する。そのあと親戚の家などを回礼する行事である。
これは幼児が成長して行く階段ごとに守護を守神に祈り、また社会からも祝福を受ける日であったわけである。
この習慣は一般に都市に多く、農村ではあまり行なわれていない行事であるが、家によってはやっているところもある。着飾った幼児が親に手をひかれて氏神様に詣でる姿も見うけられる。
○恵比寿講
農家の恵比寿講は「百姓えびすは宵えびす」といって19日に行なわれ、神酒や蕎麦(そば)を打って供えたり、果物や野菜等を供えたりする。また20日は赤飯やぼた餅を作って供えたという。今は主として商店の恵比寿講となっている。
商店街では20日に「商いえびす」といって売り出しをする。現在は土地によって異なっている。
昔は各商家では3日間行なって、恵比寿・大黒の2神を祀り、神酒や鯛・鏡餅・大根などを供え、親戚や得意先や近隣の懇意な人を招いて馳走したという。
○文化祭
本町では11月中を総合文化月間とし、町の文化協会が主催して23日の勤労感謝の日を中心に文化祭が催される。
会場は中央公民館や身延地区公民館などを中心に書道・絵画・写真展や生花展、更に音楽・舞踊発表会等多彩な行事が行なわれ、文化の秋にふさわしく、また町民の文化意識を高める上にも資するところ大である。
12月の行事
○水神祭り
我々の日常生活に欠くことのできない水の神としてお祀りされて、飲用水に井戸水や湧水が枯れないように祈念したものであろう。
「お川びたり」ということばも残っている。今はあまり見られないが、昔は川端や井戸端に紙を三角形に折り畳み、竹ではさんでなべ墨で目のように2つの点を書いて立て、おはぎや餅を供えて水神様を祭ることが行なわれていた。
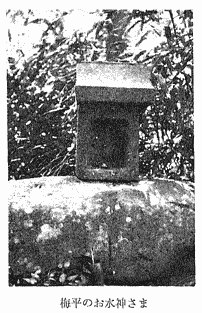 |
昔は婦人が1日針仕事を休み神棚に菓子を供えてお祭した。
また裁縫の師匠の家などでは蒟蒻(こんにゃく)や豆腐に針をさして神棚にあげ1年間の労を感謝した。この日に限り主婦が主人になって客を招いたりしたといわれている。
しかし、現在は一般にはあまり行なわれていない。
○冬至
1年のうちで昼が最も短かい日で、冬至には南瓜を食べる風習が全国的にある。これを食べると魔除けになり、中風や風邪にかからぬとされている。
また柚子湯に入る風習もひろくみられる。
○除夜
除夜は1年の終りの夜であるとともに、新しい1年に続いている。家の内外とも年越し準備をすべて終え、赤々と燃えるいろりを中心にして、一家団欒(だんらん)のうちにこの夜を過すのが昔からの除夜のならわしである。
やがて鳴る108つの煩悩(ぼんのう)を払う除夜の鐘とともに、旧い年は行き去り、新しい年が明けて新年の行事が始まるのである。
以上年中行事として民俗的ないろあいの濃いものを摘記したが、都会ではすでに新しい文化の波におし流されてなくなってしまったものも多いが、農村には、まだ伝統的な行事がかなり残されている。しかし、昔のように信仰と結びつき、部落をあげて盛大に行なわれた神社の祭礼は、すっかり衰微してしまった。