(四)普請(ふしん)
ア 地鎮祭建築を始めるにあたり吉日を選び地鎮祭を行なう。この方法には神式、仏式等がある。一般に、御神酒・塩・洗米・山海の産物(魚や野菜)をお供えし、道具は鍬、スコップ、ドウズキ(タコ)などを中央において建築中事故のないように将来多幸であるようにとお祈りする祭りである。かつてはそれからドウズキが勇ましい掛け声とともに始まった。
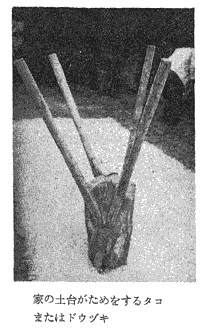 |
棟(むな)木を上げる式である。昔の建物は棟木が大きく、道具もなかったので多勢の人達が力を合わせて木やり音頭を唱えながらロープで上げたものである。
棟梁にとっては、上棟式は自分の腕を参列者に披露する式であって当日までの気の配りようは一通りではない。予め刻まれた柱や、梁(はり)が見事に組み立てられ完成した瞬間、拍手はしばし鳴り止まない。
できあがった屋上には祭壇が設けられ、木綿綱、扇車、破魔(はま)弓(鏑矢(かぶらや)の方向は丑寅(うしとら)にする)、のさき棒(5色の旗を立てる。5本、または7本、あるいは9本を赤を東、白を西に)を整え供物として鏡餅一重、御神酒、干魚、昆布、青海苔、洗米、それに親戚、知人近隣より寄せられた餅俵、御酒などを供えて式は始まる。
餅なげは、最初四方餅を東西南北にまき、また火伏せの意味からお金を色テープにつけて投げる。餅なげが終ると祝宴に移る。
ウ 棟梁、送り
上棟式の祝宴が終ると棟梁のご苦労を謝し、棟梁の宅まで送る。棟梁の宅では送って来たものに振舞う。
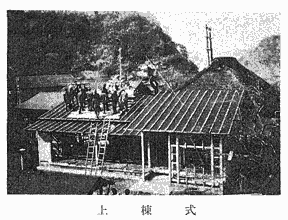 |
(五)親分、子分
ア 親分子分の発生わが国の家族制度は、古代においては、大家族制度であり、一戸の戸主は、絶対的の主権を有し、なお家族全員の生活を保障していた。その大家族制度は、社会、経済のすすむにつれて、次第に崩壊して分家を生ずることになり、その分家は本家に対し従属的関係を結び、主家がその生活保障をするのに対し、分家は労役的仕事をするようになってきた。それは次第に小作人的に変化し、主家の土地をたがやし小作的物品を納入するようになったが、物納をしなくて労役を無償で行なう「なご」の制度が、土地関係や経済関係とは別に社会的にはいってきて主従関係を結び親分子分の関係を生じた。また、このような主従の家族関係は、同族の内部だけでなく、奉公人、分家にもおよんでいたことは論を待たない。またこれら過小農の不安定な生活は、ほんとうの親のほかに、種々の親を必要とした。そのために農村の人々は血縁的に関係がないのにあるいはあってもそれを更に強化するために擬制的な「オヤカタトリ」をしたのである。
イ 親分とは
親分には名付親、取上親、鉄漿付(かねつけ)親、拾い親、ワラジ親などがある。
また、祝言の際には仲人の他に親分をとる。その親分を選ぶには、同族の有力者だから頼む、あるいは近所だから頼む、人物だから頼むなどいろいろあるが、親分となるといろいろ出費がかさむので、相当富裕な家でないと簡単には引き受けられない。
名付親 (一)カ参照
取上親は、子どもが生まれる時産婆の代りに取り上げる女で、親分の妻が普通であったが、最近は産婆さんにとりあげてもらうとか、妊娠すると定期的に産婦人科の医師に診察をうけ、医師の指示に従って病院でお産する者も多くなってきて、今は取上親はほとんどない。
鉄漿(かね)付親は、かつて女子が結婚すると歯を鉄漿(かね)で黒く染めた時代(50年ほど前まで)には、親分の妻がこれをやった。現在はもちろんない。
拾い親というのは、亥(い)年生れの子ども、(よく子どもが育たぬ家の子ども)父母の厄年生れの子どもは捨てないと育たないといわれ、お宮の前や橋のたもとに捨て、それを予めお願いしておいた拾い親に「箕(み)」で拾い上げてもらうことをした。
ワラジ親というのは、他所からこの村へ入った人がこの村に住みつくとき、誰かの厄介になった。屋敷のはなれ座敷を貸してやるとか、あき屋敷を買って入れてやるとか、村持山の入会山やそのほか共同の権利など早く取得できるように努力してやったりしたのでこの名ができた。
ウ 親分の本務
親分は、また子分の広い意味の援助をし、また嫁とりの問題については、一切の相談相手となり、祝言が終れば、親分の家ではお方呼びといって新嫁を招待し、盆正月には「子分呼び」といって親分が子分を招待するのは毎年の仁義となっていた。そしてまた、子分の家に子が生れると名前をつけ、ボコ見(ボコは赤ん坊)と称して産着なりお祝の金を贈るのが普通のならわしであったが、最近では、名付けは行なうが、ボコ見をするのは、長男、長女の2人だけに限り、それ以外はしないことになってきた。
エ 子分の本務
親分の家の吉凶禍福は、お家の大事とばかり馳せ参じて喜憂をともにし、かつ労力奉仕を惜しまない。また無報酬で親分の家の労役に服し、小作人の関係の場合は、地主所有の他の小作地を管理する場合もあった。
そして、多くの場合親分と子分の関係は、1代限りでなく、代々譜代的にむすばれたのであるから簡単に消失しなかった。
オ 社会生活上の意義
以上のように親分子分の関係は、同族の本家分家関係および地主小作関係に支えられながら社会共同生活の上から見て、物質的にも精神的にも大きな相互扶助の機関であったが、明治20年(1887)ころの社会経済の変革と政治的勢力関係の移動によって変化し、更に大正13年(1924)になると小作争議の頻発(ひんぱつ)、農民組合運動の勃興(ぼっこう)等によって子分の分散が起り、一方その後に続く不況とともに、親分子分の従属的な関係は次第におとろえ、第二次世界大戦後の農地開放による地主制度の崩壊と、わが国の工業を中心とする経済成長によって生じてきた農村労働人口の都市への流出、更には民主主義の普及と発展によって台頭してきた新しい社会的な力関係によって親分子分の関係は次第に形が変化してきている。
(六)その他
ア 病気見舞病気になって医者にかかると近隣では1度様子伺いに来て、その様子によっては2度目に見舞を持ってくる。更に病院に入院した場合は病院まで見舞うのが例であったが最近は特に関係ある人、親戚以外は病院まで行くことをしなくなった。
また病気が全快した時は「床上げ」とか「快気祝い」といって赤飯や品物を配って祝ったが、最近は新生活運動の呼びかけで快気祝いの廃止が進められている。
8月は盆の月なので見舞をさける風がある。
イ 長寿の祝い
高齢に達した人のなお長寿であるようにと願う心をこめた祝の儀である。
長寿の祝は40歳を初めとして10年毎に祝うとされている。しかし寿命の延びた現在では40歳の初老の祝はもちろん10年毎の祝はあまり聞かない。一般に61の還暦の祝、77の喜寿、88の米寿などの祝が行なわれているようである。
ウ 男女の厄
一般にいわれている厄年は男子25歳、42歳、61歳。女子19歳、33歳、37歳である。この厄年を厄難のある年として忌み慎しむのは陰陽家の説が民間に広まったと考えられる。特に男子の42歳と女子の33歳は一生中の大厄とされている。
この厄年にあたって昔は年頭に厄ばらいをするならわしがあった。また節分などに氏神に詣でて厄ばらいをするとか、身につけていた櫛や銭などを道に落して厄落しをする習慣もあった。更には正月をその年だけは2度迎えて年を早く進める意味で2月に餅を搗いたり、門松を立ててもう1度祝うことなども行なわれた。
エ 虫送り
夏の農村においては水の不足や風の吹き過ぎなど気にかかることがいろいろある。しかし旱(かん)害や風害にもまして古来恐れられてきたのは虫害である。そのために虫の害の少ないことを祈って虫送りの行事がつい3、4年前までは町内各地で盛大に行なわれていた。
たいてい土用の丑(うし)の日にするところが多いが、実際の害虫の発生を見てから行なうところもあった。
当夜は、部落の上(かみ)から松明(たいまつ)をもって田の畦(あぜ)や道を「イネの虫を送るよ送るよ」と唱えながら歩き部落のはずれまで送って終る。
その様子は夏の夜の風物詩で後々までも忘れられぬ印象深い共同祈願の行事であったが、今日のように科学の力で害虫の駆除をするようになってからは虫送りの行事もほとんど姿を消してしまった。
オ 送り神
12月末、一晩に23戸ずつ火伏題目を唱えてまわり、部落の全戸が完了すると、お寺に集まり、防火と悪神の退散をお祈りする。その後「この功徳(くどく)によって諸悪神退散」と書いた旗と、さんだわらに杉の葉で小さな祠(ほこら)を作ったものを持って各戸にお祈りして歩くと、みんなお賽(さい)銭やお洗米を供えて1年間の悪神を送る。これを子どもが部落のはずれに送るならわしが今も上粟倉で行なわれている。
カ 雨乞(ご)い
稲や畑作物の栽培に対して雨がどれほど大切なものであったかということはひろく昔から雨乞いが行なわれていたことでもわかる。
本町では記録がないので詳(つまび)らかではないが、明治の中頃までは日照りが続くと部落の人々がお寺に籠(こも)って祈祷(とう)題目を唱えたり、身延山の雨乞いの滝、大河内の三ツ石山まで行って題目を唱え、雨乞いをしたと伝えられている。
以上、産育、婚事、葬送、普請、親分子分、その他の習俗をとりあげて見たが、これらも、場所によりかなりの差異がある。特に第二次世界大戦を境に農業形態の変化や生活の進歩の中で次第に廃止されたり、簡略化されてきている。
更に社会一般が昔からの習慣に固執することなく、個人の主張が取り入れられるような形態になった現在では、ひとつの形式にはまることが少なくなりつつある。しかし、反面日本の風土と義理人情に深く結びついた習俗であるがゆえになかなか変えられないものがある。