第六節 方言
一、身延町方言の系統のあらまし
「ハンデメタメタゴッチョデゴイス」は山梨県の方言を端的に表わした言葉として有名である。方言は自然および人為的条件によって発生するといわれるが、自然的条件としては、高山、大河川、森林、海峡といった地理的障害による交通の阻害があげられる。人為的条件としては藩や、県といった行政区画、学区・商圏・通婚圏などの社会的関係があげられる。
わが国は世界でも最も標準語教育の進んだ国であるが、反面、その地域によって方言差が大きい。したがって日本人の多くは、方言と標準語の二重生活をしていることになる。日本語の方言を文法上から区分すると次のようになるが、音韻・アクセント・語などによるとまた違った区分もされる。いずれにしても、わが山梨県方言は東部方言に含まれる。
山梨県は笹子・御坂・大菩薩等の峠によって交通が阻害されていたため、郡内地方・国中地方・河内地方と呼ばれる3ブロックに大別され、それぞれ特色ある方言が使われている。身延町方言はこの中の河内方言の特徴をもっている。(河内方言の中でも北部は中巨摩、国中の西郡(ごおり)方面の影響を受けているし、南部は静岡県の富士宮方面の影響を受けている)
身延町は地理的にも河内地方の中央に位置し、封建色の強い土地だけに河内方言の特色をかなり強くもった方言が残っている。
なお、身延町の面でも町内を流れる富士川によって東・西に分けられ、山をはさんで下山地区は独特の気風をもち、言葉もやや異なったニュアンスをもっている。
この東・西・下山地区の特に目立った違いを挙げると、
○東(大河内地区)
言葉のあとに「ナーヨ」をつける。
「シャー」を使う。
例=ソウダナーヨ(そうだなあ)−同意を求める意
ソウシッシャー(そうしなさい)
○西(身延・豊岡地区)
言葉のあとに「ナーエ」をつける。
「シッセ」を使う。
例=ソウシッセエ(そうしなさい)
ソウダナーエ(そうだなあ)
○下山地区
「チャー」が使われる。
例=ソウシチャー(そうしなさい)
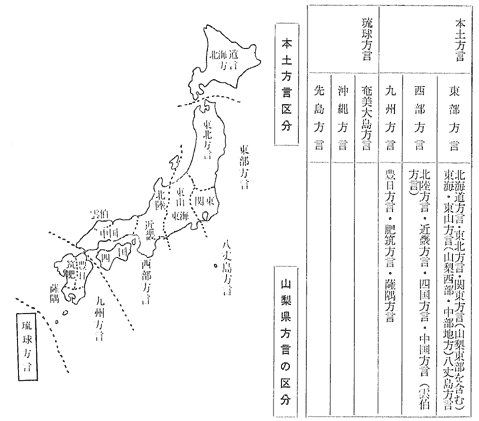 |
軽い驚きの意味で「テ・ホーヤ」を使う。
音韻のうえで特色のある言葉では「ヤッテマッタ」(してしまった)という言い方がみられる。
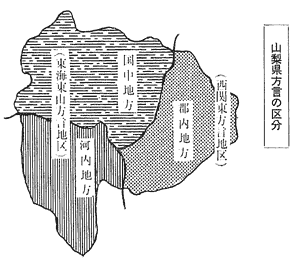 |
二、身延町方言の特色
日蓮宗総本山久遠寺を控えて全国各地からの参詣客に接する機会も多く、首都圏との文化的交流の機会もひんぱんになったので、近年は割り合いに標準語に近い音韻(いん)やアクセントが使われ、訛(なま)りは少なくなっている。1、標準語と比較して、音韻やアクセントの違いは少ない。
2、現在、方言は中年から老年層に多く残っているが、若い層にまで共通して根強く残っている点として、「ザ行」と「ダ行」の混用があげられる。
例=ゴダイマス(ございます)ドーキン(ぞうきん)
デシ(ぜひ=是非)
3、強意の接頭語が非常に多く、その為に言葉が荒々しく感じられる。
例=ウッチンダ(死んだ)ブッコボス(こぼす)4、「出る」と「出来る」の区別が不明瞭である。
例=お月さんが出来た(でた)おだんごが出た(できた)
5、転化した言葉が多い
例=ミシロ(むしろ) イゴク(うごく)6、助動詞の使い方に特殊なものが見られる。
例=行ケサル(行ける) 届ケラカス(届けさせる)三、音韻(いん)
身延町方言の音韻は、標準語の音韻(国語辞典による)に比較して別段特異とする点は認められない。(一)音韻体系
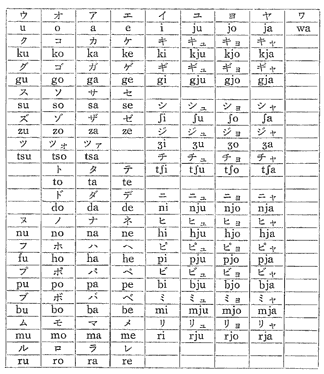 |
(二)音韻の変化
| ○ | ai→e: | |
| 境(サケー)寄り合い(ヨリエー)ひたい口(ヒテーグチ) | ||
| ○ | ae→e: | |
| つかまえる(ツカメール)押える(オセール)かえる(ケール) | ||
| ○ | ie→e: | |
| 煮える(ネール)消える(ケール) | ||
| ○ | ui→e: | |
| 手ねぐい(テネゲー) | ||
| ○ | oi→e: | |
| おととい(オトテー) | ||
| ○ | oe→e: | |
| ひとえもの(ヒテーモン) | ||
| ○ | a→e:・o | |
| 催促(セーソク)たばこ(タボコ)歌う(ウトー) | ||
| ○ | i→e: | |
| 借りる(カレル) | ||
| ○ | u→i・o | |
| ぬのこ(ノノコ)数(カゾ)涼む(ソゾム)する(シル) | ||
| ○ | e→i・o | |
| 前(マイ)杖(ツヨ) | ||
| ○ | o→u | |
| もろい(ムルイ)ふろしき(フルシキ) | ||
| ○ | 母音の長音化 | |
| 毛虫(ケームシ)蛭(ヒール) | ||
| ○ | ju→i | |
| 眉毛(マイゲ) | ||
| ○ | sa→ |
|
| 鮭(シャケ)ざくろ(ジャクロ) | ||
| ○ | ||
| 熟し柿(ズクシガキ) | ||
| ○ | m→b | |
| 冷たい(ツベタイ)ひも(ヒボ) | ||
| ○ | n→g | |
| 死ぬ(シグ) | ||
| ○ | 促音化 | |
| 尻はしょり(シッパショリ) | ||
| ○ | g・jの喪失 | |
| にぎやか(ニーヤカ)麦から(ムイカラ)ゆでる(ウデル) | ||
| ○ | 撥音化 | |
| 手伝う(テンドー) | ||
| ○ | その他 | |
| 飛びおりる(トンビョーリル)いたどり(イタンドリ)雨降り(アメップリ) |
(三)音声的特徴
特に目立った特徴は見られないが、方言の音韻として普通問題になるものをあげると、○母音ウ東京語のウと同じく唇が丸くならない。ス、ズ、ツの場合は中舌化した。
○ガ行の子音は文節の最初に立つ時は鼻に抜けない。
ガッコウ ギンコウ
ガッコウ ギンコウ
○セ、ゼの音がシェ、ジェと発音されることはない(シェンシェイ=先生とはいわない)
○ヲ(WO)の発音はほとんど(O)である。塩(シヲ)臭う(ニヲー)の場合もある。
○クワ、グワの音はなく、すべてカ・ガである。
ツァ・ツォは、ツワ、ツオの音がつまった場合にあらわれる。
あんな奴は(アンナヤツァー)
松をきる(マッツオーキル)
ごちそうさん(ゴッツォーサン)
ツァ・ツォは、ツワ、ツオの音がつまった場合にあらわれる。
あんな奴は(アンナヤツァー)
松をきる(マッツオーキル)
ごちそうさん(ゴッツォーサン)
四、アクセント
身延町方言のアクセントは高低の型や姿が東京アクセントとほとんど同じである。1、アクセントの体系(●▲は高い拍○△は低い拍▼▽は助詞の類)
| 型の名称 | 1拍の語 | 2拍の語 | 3拍の語 | 4拍の語 |
| 平板型 | ○▼ | ○●▼ | ○●●▼ | ○●●●▼ |
| 2高型 | ○●○▽ | ○●○○▽ | ||
| 3高型 | ○●●○▽ | |||
| 尾高型 | ○●▽ | ○●●▽ | ○●●●▽ | |
| 頭高型 | ●△ | ●○▽ | ●○○▽ | ●○○○▽ |
2、この各型の語例(国語学辞典付録の国語アクセント類別語彙表による)
| 1拍平板型 | 柄、蛟、血、帆、実、身、名、葉、藻 | |
| 1拍頭高型 | 絵、尾、酢、荷、根、野、火、矢、粉、田 | |
| 2拍平板型 | 鼻、箱、竹、酒、壁、金、風、売る、置く、散る、巻く | |
| 2拍尾高型 | 歌、音、川、石、旅 | |
| 2拍頭高型 | 粟、糸、稲、笠、肩、鎌、松、雨、井戸、蜘蛛、春、鶴、露、食う、立つ、出る、取る | |
| 3拍平板型 | 着物、額、鼻血、霞、うなぎ、遊ぶ、踊る、登る、曲げる、赤い、厚い、重い、軽い | |
| 3拍二高型 | 朝日、五つ、命、涙、遅い、痛む、頼む、見える、逃げる | |
| 3拍尾高型 | あずき、恨み、宝、はさみ | |
| 3拍頭高型 | きゅうり、姿、錦、烏、高さ、かいこ、かぶと、病(やまい) | |
| 4拍平板型 | にわとり、大麦、夕やけ、雷、絞付、呉服屋 | |
| 4拍二高型 | いろ紙、うぐいす、はまぐり、朝顔、仲良し、紫、そら豆 | |
| 4拍三高型 | からかさ、青空、門松、先生、集まる、大きい、淋しい | |
| 4拍尾高型 | のこぎり、弟、妹、綿入れ、北風、竹やぶ、谷川 | |
| 4拍頭高型 | おおかみ、こうもり、兄(にい)さん、姉(ねえ)さん、たんぽぽ |
なお名詞3拍の語群が東京アクセントの頭高型と異なり、山梨県アクセントは2高型をとっている。
| 東京 | 山梨 | 国中地方 | 河内地方 |
| ア サ ヒ | ア サ ヒ | タ マ ゴ | タ マ ゴ |
| イ ノ チ | イ ノ チ | ハ タ チ | ハ タ チ |
| コ コ ロ | コ コ ロ | ヤ ク バ | ヤ ク バ |
| ナ ミ ダ | ナ ミ ダ | ザ ク ロ | ザ ク ロ |
| ヒ バ チ | ヒ バ チ | ウ ム(産む) | ウ ム |
| マ ナ コ | マ ナ コ | ||
| マ ク ラ | マ ク ラ | ||
| モ ミ ジ | モ ミ ジ |