鎌倉時代、帯金村に帯金刑部亮という豪族がいて、時の人々は帯金どのと称した。頼朝の富士の巻狩りにも参加したということである。
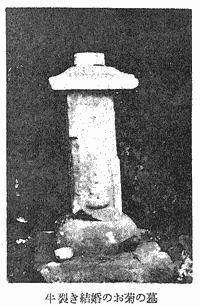 |
これでお菊は双方に義理をたてたのであった。関係者および村人は、厚くその遺体を葬って供養をなし、今にその墓石が、御屋敷という刑部亮の邸址(やしきあと)に存し、墓文はこけむして不明であるが、女人の首をかたむけ、思い悩むさまを刻んであったのが、かすかに見える。村人は御妙貞(おによてん)様と称し、世の貞節の鏡(かがみ)として、悲惨の物語を伝えている。「甲斐から駿河へ」
灰土地蔵 和田
和田原がまだ富士川の河原だった頃、近くの峰に住んでいた和田平馬という者が、この河原を何とかして耕地に拓(ひら)きたいと苦心していた。ある夜、富士の裾野の開拓を夢みた。そこで近所の人々とも話し、和田原の方は後まわしにして、先ず富士の裾野の開墾を始めた。ある日家族のことが心配になって、裾野の灰土を藤袋に入れて担(かつ)ぎ、1晩泊りで村に帰って来た。和田の地蔵様の前まで来ると、そこに一休みし、藤袋の灰土を地蔵様にお供えしてわが家へ帰った。そして家族とも楽しく語り合ってその夜は寝た。すると夜中に、俄(にわ)かに大風が吹き荒れた。翌朝平馬が起きてみると、驚いたことに家の庭先から和田原一帯に灰土が散布され、今まで一面に石ころだった河原は、2尺内外の黒土におおわれ、みごとな耕地と化していた。村人は深く地蔵様の恩を謝し、その祭典は毎年盛大に営まれ、盆踊り、すもうなどが奉納されている。「甲斐伝説集」
和田原の地名
和田原は、戦国時代武田氏が駿河の今川氏に備えて、砦(とりで)を築くため兵を駐屯(とん)させ、工事に当たらせたといわれている。
当時、富士川の水を、いまの和田トンネルに当たる所を切り開いて東に回す工事をしたが、工事なかばで武田氏が滅亡したため完成しなかった。その工事のあとをいまもそのまま道路にして、「切(き)り谷坂(やざか)」と呼んでいる。
そのほか、和田原には、物見櫓を築こうとした「もの見」、弓矢の練習をした「矢先」、信玄がいたところを「殿様(とのさま)」、その家臣のいたところを「大名」とそれぞれ地名となって、いまもなお残っている。
それから、和田原の人たちは、「藤づる」を現在でも、もったいないといって農作業に使うことをさけている。
石割稲荷社 身延総門
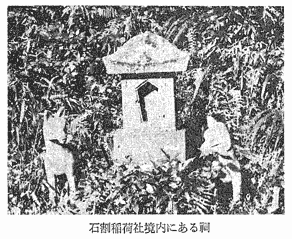 |
また、その節、不思議にも山の中腹の大岩石が自然に割れ、その岩の中から白髪の老人が出てきて聖人を迎えた。
聖人は老人に「お身はいずれより」と言葉優しくお尋ねになった。老人は手を合わせて申すに「私は元来身延の山に住みしもの、今は誰一人として愛してくれる人もないのみならず、追って追われて深い岩屋の中に閉ざされている哀れな野性のものでございます。」と、正体を現わして申すのであった。そしてなお続けて、「今世の生物に憐れみ深き日蓮聖人、甲斐路に入らせ給いて、領主波木井殿と御対面なさる趣を拝し、欣喜躍如、追いこめられた巌を破って出て参りました稲荷大明神の申し子……この世のために一日も早く御開宗なされますよう……」と申し上げるのだった。
村人も奇異な感にうたれて、後にこの地に社を造り老人を神として祀った、これが今の石割稲荷社で、神社の前には、左右に割れた大岩石がそのまま現在も残っている。「身延の伝節」
稲を食う絵馬 身延上の山鬼子母神
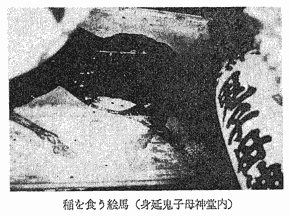 |
初めは、どこの馬か全然見当がつかなかったが、だんだんあとをつけてみると、この絵馬が抜け出したものと判明した。そこで法主にお願いして馬を祈祷して封じこめた。それ以来稲を荒さないようになったという。
しかし現在も絵馬の口や足は泥でよごれている。つまり田を荒した当時の名残りであるという。
「身延の伝説」
犬塔婆 身延山小室の開山日伝上人は、日蓮聖人と法問答をして、負けて弟子となったのであるが、その時、日伝は身延山で粟餅に毒を入れて日蓮聖人に勧めた。日蓮聖人は毒と知って喰(く)わず、その餅を犬に与えた。すると犬はたちまち狂死した。日蓮聖人はその犬のために塔婆をたててやり、今も身延山に犬塔婆というものがある。「甲斐伝説集」
身延攻め
元亀3年(1572)のことであった。突然国守武田信玄は、使者を身延山に遣わして、「身延山に築城するために、よそに大伽藍を建築して寄付するから移転せよ」と申しこんだ。信玄の考えは、京都に出て天下に号令を下すには、駿河から東海道を通って上京するのが最も近道であるから、東海道へ出るために身延山に築城して足だまりをしようというのであった。
身延山の法主第10代日叙上人はかねて信玄も尊信している傑僧であった。上人は、国守の申し出ゆえ、無下に断ることもできず、一山の大衆を集めて、数日間さまざまに相談した。その結果「身延山は宗祖の御霊の留まる永久の浄土であるから、国守の申し出なれども引き渡すことはできない」という決議をなし、このことを使僧を以て府中の信玄まで返答することになった。使者として、岸之坊日代という若僧が発向し、その決議を伝えた。信玄は身延山の意向を聞いて、大変立腹し、早速出陣の用意をして、身延山を攻めとろうとした。元亀3年4月11日、信玄の大軍は、身延山下の飯富村へ来て、早川をへだてて身延山にうち入るばかり。しかし、身延山は元来仏法の山で、兵仗(ひょうじょう)の用意もなく、一山の大衆は祖師堂に集まって宗祖の御前に祈祷をこらしていた、翌朝未明に、信玄の軍隊は早川を押し渡って一気に身延山を乗っとろうとした。しかし、未明の天はにわかに曇り、大雨降り来たり、早川の水は増し、名に負う急流は大木、大石をどんどん流し、渡るすべもなかった。このありさまを見て、武田の長子勝頼は、血気にはやる手兵を引率して急流を乗り切ろうと、川に飛び込んだが、たちまち流され、死する者は数を知らなかった。本陣で見ていた信玄は大いに怒り、全軍に指揮して自ら早川を渡ろうとした。丁度その時、対岸で今まで身延山の杉の林と見えた峰々が、甲胄(こうちゅう)に身を固めたいかめしい大軍にうずめられているありさま。さすがの信玄も、あっと驚くその時、はるか七面山の方角に「法敵信玄」と叫び声が聞こえたかと思うひまもなく、電光ものすごく、白羽の矢が飛んで来て、ザックと信玄の前額に命中した。信玄は前歯一枚を折り、その場に気絶した。(この白羽の矢は現在も飯富に神社をたてて、祀ってあるという。)このありさまに信玄の大軍も早速退陣して、身延山は事なきを得たが、その翌年の4月11日に身延山を攻めたと同月同日、仏罪に依って陣中に、古傷がにわかに悪化して死んだのであると伝えられている。「身延の伝説」
妙見寺裏の金持ち 下山
妙見寺の裏に松の生えているところがある。
ここに昔、たいそうな金持ちが住んでいた。不幸なことに子どもがなかったので、「金ばかりあっても、少しもおもしろくない世の中だ」と、ついには日本国中見物して回ろうと思い立った。金を持てるだけもったが、まだたくさん残ったので、土の中に埋めた。そして、歌一首を詠(よ)み、それを家門のところへ貼(は)って出発した。
朝日さす夕日輝く駒(こま)返し雀子おどる桃の木の下
長者は、再び帰って来なかった。この歌をたよりに、村人は金を掘り探したが、今もって見つからぬという。「下山村誌」
くつわ虫 大城 下山
遠藤伊勢守がある夜学問をしていると、何だか刀のつばのような音がした。急いで外に出てみると、くつわ虫であった。そこで伊勢守がくつわ虫を怒ったところ、それ以来大城にはくつわ虫がいないという。
また下山隧(ずい)道の流れている富沢という沢から北側にもくつわ虫がいないという。穴山八幡に祀ってある神様がくつわ虫をたいへん嫌ったためであるといわれているが、一方、武田の軍勢が、会議をしていたところ、くつわ虫があまりうるさく鳴いたため、それを怒ったところ、それ以来いなくなったともいわれている。
苔提梯(ぼだいてい) 身延山
昔寛永年間に仁蔵という佐渡の船頭が、身延山に登山した。当時まだこの石段はなかったので、仁蔵は本堂前の急坂をを見て、どうかして石段を作りたいと考えた。そして、宗祖の御前へ参籠して、「石段を作るだけの金を授け給え」と祈願した。
それから後、船頭仁蔵は佐渡の近海を航海していた時、佐渡の山の上に何か光るものを見た。不思議に思って登ってみると、一面の金であった。偶然とも、不思議とも例えることばもないような幸運につきあたった仁蔵は、これも日蓮聖人が下されたものであると堅く信じ、巨万の金を持って身延山へ登山した。そして、立札を作り「石一つ運んだものに銭百文を与える。」と村々へ布告した。金の力は偉大なもので、数日の間に必要以上の石材が集まった。こうして、あの天にもとどくかと思われる大菩提梯(ぼだいてい)ができ上ったのであると伝えられている。「身延の伝説」
柿の葉書籍 身延山
いつの頃か檀林に若い学問のできる学問僧があった。夏の盛りの日中に、能化(のうげ)(教授)が寮の廊下を歩きながら、ふと若僧の部屋をみると、驚いたことに大きな狐が寝ていた。後刻、能化に呼ばれた若僧の懺悔(ざんげ)を聞くと若僧は、実は年経た狐であった。法華経を学びたい一心で僧に化けて檀林へ入学した。本体を現わしたのは一期(ご)の不覚で、もう檀林に居ることは出来ない。「ついては、今までお世話になったお礼に、お釈迦様が法華経をお説きになったありさまをそのまま御覧に入れましょう。しかし、畜生のすることだから、決してありがたいと思って合掌して拝(おが)まないように、もし拝まれると私の術が破れて消えます。」…その夜、月の光の中へ檀林の人々を集めて狐の僧は呪文(じゅもん)を唱(とな)えた。すると、目の前へ印度の古代、釈尊当時のありさまが、さもありがたく出現して、釈尊の説いた法華経の説相そのままの儀相が展開してゆく。人々が奇異の思いにかられて居る間に、「序品」「方便品」をすぎて、やがて「見宝塔品」に来た。光明輝くばかりの大宝塔が虚空に浮いて、十方の釈尊の分身諸仏が集まって、やがて宝塔の扉が開く…その壮厳さに、思わず見ていた人々は宝塔を伏し拝んで口口に題目を唱えた。どうであろう。その瞬間、今まで見えていた霊山も、釈尊も、宝塔もなにもかも一瞬に消えて、ただ月の光のみが山々を寂しく照らしているのみ。…その後ついに狐は姿を見せなかった。
その後日談…狐の部屋を整理するとき、部屋一杯につまれた書籍を見ると、驚いたことに、みな柿の葉であった。柿の葉へ何か書いて書物に化けさせ、積んであったのだ。
この葉は、「柿の葉書籍」といって、明治維新まで保存されていたという。「身延の伝説」
塩屋の屋敷 大庭
下山千軒といわれた昔の話である。
山また山に囲まれた甲斐の国では、食塩のほとんどは、駿河の国からの供給ににまつ他はなかった。当時駿河の国より富士川を通じ甲州一円に販売する大量の塩が、一応下山に荷上げされ、そこから国中いたるところ運搬されたという。この塩を荷上げされたところを、だれいうとなく「塩屋の屋敷」というようになり、現に存在する井戸の水は塩辛いというが、それは、たくさんの塩が積み下ろしされた場所であるからだろうといい伝えられている。
帯金のおじいさん 帯金
昔、帯金に1人の老人が住んでいた。毎日ブラブラと遊んで暮らしているというのにその生活は裕福なので若者たちは不思議に思い、ある時そのことを尋ねてみた。すると、老人は、「何月何日の晩何時に、山道を歩けるようなしたくをして俺の所へ来い」といった。
いわれた日に若者達が身じたくをして行ってみると、老人は「俺の後について来い。」と先にたって歩き出した。その歩き方といったら高げたをはいた老人とは思えぬ早さで、わらじばきの若者もかなわぬありさまだった。老人は少しいっては何度も何度も若者たちが追いつくのを待たなければならなかった。
やがて、割石峠から甲府盆地へ出た。甲府のとある立派な塀のある家まで来ると、老人はひらりと塀を乗り越え中に入った。ここでも老人はもたもたしている若者に手を貸さなければならなかった。家の中に入ると、老人は金箱をとり出して来て若者達の前におくと、「これが1両小判だ、これが1分銀だ。」と説明しながら見せた、説明が終わり、それを自分のふところへしまいこむと、もと来た道を再び飛ぶようにして帰って行った。若者達も遅れじと、後を追って帰って行った。
夜どおし歩き、ほうほうの体で村に帰ってみると老人はもうかくしゃくとして、植木の手入れなどしていた。それを見て、若者達はすっかり毒気をぬかれてしまい、ぐうの音も出なかったということである。
へだまの段 大城
昔、大城の奥、古谷城という所に1人の老人が住んでいた。商人から品物を買うのに、すべてつけで買い、商人が代金を請求するときまって、「雨が降ったら来い。」というのであった。そこで、雨が降ったあと商人が行くと必ず砂金でその代金を払うのであった。
実はこれは、雨が降ると川のたまりに砂金が流れて来てたまる場所を、老人が知っているからであった。村人たちは、その秘密の場所を知りたくて、何度も何度も老人に尋ねたのであったが、決してその場所を教えはしなかった。
その老人が、いまわのきわに「へだまの段であと見れば…」ということばを残して死んだ。村人たちはそのことばをたよりに、その近辺を捜してみたが、ついにその場所は発見することはできなかった。
(へだまは、「日だまり」がなまったものではないかと、いわれている。)
八幡社の額 波木井
波木井3区の八幡様の額に、人が2人溺れているところが描かれているのがある。それには、安政4年(1857)7月23日、願主伊藤徳左衛門(41歳)伊藤兵十(27歳)と記されている。これには次のようないい伝えがある。
昔、2人の船頭がある雨上がりの濁流の中を船をこいで、富士川を下って来た。清子の藪が滝という非常に危険な場所がある。そこまで来ると、船はその危険な場所にぶっつかり見る影もなく破船してしまった。2人はなんとか泳いで岸までたどりつこうとしたが、着物は着ているし、身体の自由はきかぬしで、まさに溺れてしまいそうになった。するとどこからともなく1本の太い竹が、彼らの側へと流れて来た。2人がふと空を見上げると、そこには1人の神が現われて、2人を見守っているのであった。無事助かった2人はこの喜びを神に告げようと、この額を寄進したということである。−県立身延中学校昭3卒生編「身延付近の史実と伝説」
醒酷園の本妙さん 波木井
本妙院日臨上人は、波木井の本妙庵に住んでいた。
ある時上人は、鳥の鳴き声を聞いて居られたが、急に涙を流して村人を呼んで「富士川の船が覆没して死人が出たと鳥が知らせている。早く行って助けてくれ」と頼んだ。村人は不思議に思って富士川へいくと果たして、舟が岩のために破船して婦人が1人溺死していた。
また或る年の秋、収穫時、村人の1人が牛蒡(ごぼう)を持参して上人に奉った。上人は早速仏前へ供えて、そのまま持ち帰らせた。村人は怪しんで、その故を問うと、上人はただ「けがれているからお返しする。」といったのみであったが、村人は赤面して持ち帰った。始め村人は家でできた牛蒡を奉納するとき、一番悪い牛蒡を奉納しようとして家人に叱られて、しぶしぶ良い品を奉納したものであるが、上人はそのことをみやぶったものである。
また、丸滝村一帯が数か月雨が降らなくて困っているとき、上人は大崩で祈雨曼荼羅を書いて雨乞いをした。ところがたちまち大雨が降って百姓は大いに助かった。この曼荼羅は現在も大崩に大切に保存されている。
上人は戒律を重んじ、世の中からかくれて生活していたが、その高徳は四方からしたわれて、水戸や土佐から礼を厚くして招かれたが、土佐へは弟子を遣わして水戸檀林へ講主として飛錫して、その地で教化半ばに、文政6年9月17日31歳で示寂された。
上人が土佐の最誠師へ贈った歌
へだたれど心はおなじ大空の雲のうへ路に遊ぶうれしさ
本妙庵は、波木井の小さい山の頂きにあって、現在も昔も遺風をしのぶことができる。「身延の伝説」
日台上人の御夢想
日蓮聖人が九か年間草庵を結んで御生活された所は、現在西谷の御廟所の地で、その後に十世まではその地を身延山久遠寺とよんでいた。それを11世日朝上人が現在の地へ移転して伽藍を営まれたので、日朝上人の移転について次のような事が伝えられている。
日朝上人は移転後、古い経巻の包み紙に5世鏡円院日台上人の書いて置かれた古文書を発見された。この文書によると、日台上人がある夜の夢に、総門外の梅平へおいでになった。そして遙かに身延山の方を望むと、山の中腹に七堂伽藍の姿が美しく聳(そび)えていた。その有様をながめつつ上人は心の中で「身延山も行く末は山の中腹にまで堂塔をたてる程に繁栄するであろう」と思召された。そして夢から覚めて、この有様を書き止めて置かれ、日台上人は夢に正しく未来の有様を見られたので、日朝上人は日台上人の御夢想を見て後に移転したのではないかと。そこに不思議な「力」があるように伝えられている。教報「みのぶ」
身延全山の姿
身延山は、山そのものが宗祖日蓮聖人のお姿であると伝えられている。それであるから山内の諸堂宇はそれぞれの地位に皆意味があるといわれる。それは、奥の院思親閣は宗祖の御頭で御眼の場所は三光堂がたてられ三光天子を祭り眼光にかたどり、両手に笏と経巻を持っている事を示すため一切経蔵と鬼子母神堂とを並べてたて、宗祖が釈尊の御心を奉帯していることを表すために丈六の釈迦牟尼仏を丁度御胸あたりに奉安した。そして祖師堂その他の諸堂のある本山の地は丁度宗祖の御膝の上にあたる平地。山全体に茂っている杉松の常盤木は、宗祖の墨染めの御洗衣になぞられて植林し、三光堂下から本山上まで斜に紅葉樹を植え込んで、これを御袈裟になぞられた。これを「錦ヵ森」と呼んで現在も丈六堂を中心に名残りを止めている。「教報みのぶ」