第八節 民族芸能
一、獅子舞
町内では下山の荒町と本町、身延の波木井1区・清住町・上町・仲町・橘町・豊岡の大城と大久保および大河内の上八木沢・下八木沢・帯金・角打・和田・上大島などの部落に古くから獅子舞が伝わっている。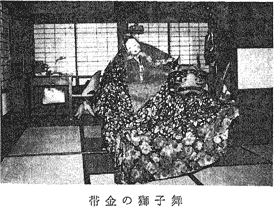 |
 |
獅子舞に関する文献は、荒町の中老箱の中に残されている「定書」と書かれている古文書の中に
一、正月二日初寄会の節は不参無く急度相勤可、若し不参者之有候はば相記申可事
一、同月四日御山荘の節は五ツ時不参なく寄合う可。若し不参の者有し節は相記し申可事
一、十四日祭礼之儀五ツ時中老方へ寄合い随分祭礼等神妙に仕る可事
一、若者酒の儀晩六ツ時会所に寄合い一同不参無く其の座に出、口論無礼がましき儀いたすまじき事
文化十二年丙子正月日
若者
文化十二年丙子正月日
若者
今日伝わっている獅子舞は、それぞれの部落によって舞いもお囃子(はやし)も太鼓も相当異なっている。また伝わってきた経路も違うようであるが、いずれも明確ではない。
以下本町に伝わる2、3のものについて述べてみると次のようである。
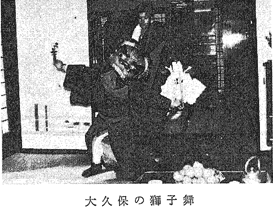 |
 |
 |
(一)荒町・本町の獅子舞
14日朝、道祖神の前を皮きりに、厄歳男女の悪魔っぱらい、初産児の無事息災、新婚の者の和合、新築家屋の安泰、火防などいろいろな願いをこめて各戸を回るのである。 |
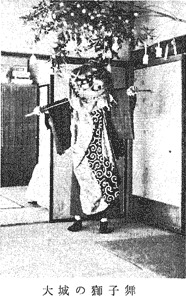 |
(二)大城の獅子舞
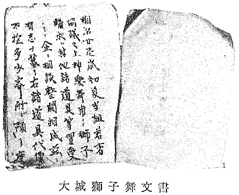 |
その後の記録に、明治21年(1888)の夏、大城の若者が協議して、獅子その他諸道具を購入する計画をたて、有志を募り、多少の寄付を得て、静岡県の安倍より購入したことが明記されている。
それ以後、若者が中心になり、毎年小正月の行事に獅子舞を演じている。ここの獅子は雌獅子だといわれ、舞いも静かである。
戦後数年の間は、若者40名位でこれを管理し、正月14日に演じてきた。人数も多かったので、万歳をも合わせて各家庭をまわっていた。祝儀の多少により、万歳もその数を加減し、厄年の家では特に獅子舞を多く舞ったといわれている。
しかし、現在若者の数も少なくなり、獅子舞のみ舞い、万歳は行なっていない。
正月14日には、早朝寺で獅子その他を準備をし、まず道祖神の前で舞い初めをする。その後、各家々を巡回するのである。
2月1日には、舞いじまいといって部落内の各神社をまわって、その年の獅子舞のすべての行事を終わる。
(三)和田の獅子舞
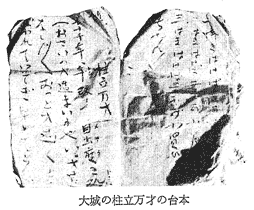 |
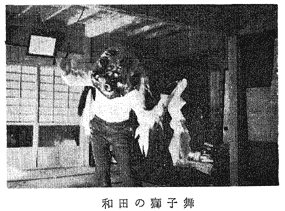 |
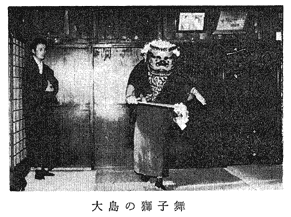 |
また、古老の話によれば、現在の南部町佐野部落から伝わったものといわれている。
獅子舞を始めた動機・演芸の種類・練習の方法などについては、他部落とほぼ同様であるが、ここでも、在村青年がだんだん少なくなったので、区内の有志が集まって「獅子舞保存会」を作り、辛(かろ)うじて例年の行事を継続してきている。
次に、1、2の代表的な演芸について記述してみる。
幕の舞
梵天舞ともいう。麻をつけた白紙を七五三のように切ったのを、棒の先につけた梵天と鈴とを持って舞う。
笛と太鼓師の謡がはいる。
(笛と太鼓)
(謡)
ヤレ、3尺のおのさを持ちて
悪魔を払う めでたいなあ、大平
楽世と
新まる 運勢 しめろ
(笛と太鼓)
アア、ヤレヤレナア
めでた、めでたの この屋の屋敷
でなあ
ホイト
(笛と太笛)(以下同様)
鶴と亀とが ソウダ
舞い遊ぶと なあなあと
(笛と太鼓)(以下同様)
ヤレ、コイナア
今宵来るなら、ぞうりでおいでと
なあなあ
下駄(げた)じゃ二の字の ソウダ
跡がつくとなあ なあと
アア、ヤレコイナア
今度、見て来た 名古屋の城はな
あ
金のしちやちほこ ソウダ
雨ざらしか なあなあと
アア、ヤレコイナア
今夜 ここへ寝て 明日の晩は
どこへかなあ なと
明日は 田の中 ソウダ
あぜ枕か なあ ホイ
ヤレ、ヤレナア
富士の裾野で 曽我兄弟は なあな
18年目で 親のかたきを
打つとなあな
ヤレ、ヤレナア
こよい一夜は浦島太郎となあ
あけてくやしゅう ソウダ
玉手箱なあ な
アア、ヤレヤレナア
これでおしまい お家はご繁盛かなあ
なあと
(笛と太鼓)
ヤレ、舞い遊び 神を
いさめられたるヒートロロ
踊りなあ 踊り竜田川では
紅葉を流す それわいのう ほんがい
東西南北にっこりと
やぶれやかんの底ぬけだ
やぶれたら 綿でも ひっこめしょ
(笛と太鼓)
剣(つるぎ)の舞
剣と鈴とを持って舞う。笛と太鼓
師の謡とがはいる。
(謡)
伊勢の社に注連(しめ)はをり
鈴ふり上げて うずめの命
神歌をうとうたり
いま3尺の剣をぬいて
悪魔を払うめでたいなあ
(笛と太鼓)
いざや 剣を舞い納め
悪魔を払いめでたいなあ
(笛と太鼓)
東西南北にっこりと
やぶれやかんの底ぬけめ
やぶれたら 綿でもひっこめしょ
(謡)
ヤレ、3尺のおのさを持ちて
悪魔を払う めでたいなあ、大平
楽世と
新まる 運勢 しめろ
(笛と太鼓)
アア、ヤレヤレナア
めでた、めでたの この屋の屋敷
でなあ
ホイト
(笛と太笛)(以下同様)
鶴と亀とが ソウダ
舞い遊ぶと なあなあと
(笛と太鼓)(以下同様)
ヤレ、コイナア
今宵来るなら、ぞうりでおいでと
なあなあ
下駄(げた)じゃ二の字の ソウダ
跡がつくとなあ なあと
アア、ヤレコイナア
今度、見て来た 名古屋の城はな
あ
金のしちやちほこ ソウダ
雨ざらしか なあなあと
アア、ヤレコイナア
今夜 ここへ寝て 明日の晩は
どこへかなあ なと
明日は 田の中 ソウダ
あぜ枕か なあ ホイ
ヤレ、ヤレナア
富士の裾野で 曽我兄弟は なあな
18年目で 親のかたきを
打つとなあな
ヤレ、ヤレナア
こよい一夜は浦島太郎となあ
あけてくやしゅう ソウダ
玉手箱なあ な
アア、ヤレヤレナア
これでおしまい お家はご繁盛かなあ
なあと
(笛と太鼓)
ヤレ、舞い遊び 神を
いさめられたるヒートロロ
踊りなあ 踊り竜田川では
紅葉を流す それわいのう ほんがい
東西南北にっこりと
やぶれやかんの底ぬけだ
やぶれたら 綿でも ひっこめしょ
(笛と太鼓)
剣(つるぎ)の舞
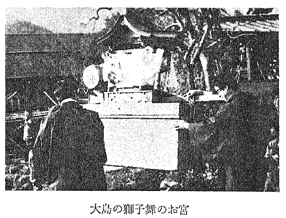 |
師の謡とがはいる。
(謡)
伊勢の社に注連(しめ)はをり
鈴ふり上げて うずめの命
神歌をうとうたり
いま3尺の剣をぬいて
悪魔を払うめでたいなあ
(笛と太鼓)
いざや 剣を舞い納め
悪魔を払いめでたいなあ
(笛と太鼓)
東西南北にっこりと
やぶれやかんの底ぬけめ
やぶれたら 綿でもひっこめしょ