二、辰巳稲荷神社神楽 下山仲町
仲町区の中ほどに、辰巳稲荷神社とよばれる祠がある。通称穴山稲荷といっているが、下山城址から見て辰巳の方角にあるので、辰巳稲荷神社が正しい名称ではないかという。この神社では、毎年正月15日に神楽が奉納される。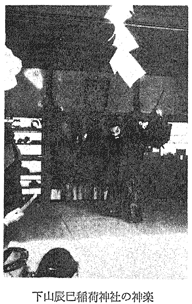 |
以来、神楽は各時代の歌謡や舞・能あるいは外来の音楽などをとり入れて、内容を豊かにするとともに、各地でそれぞれ特徴ある神楽を生ずるに至った。現在各地に分布している神楽は出雲佐陀大社の神事から発した出雲神楽と呼ばれるもので、採物(とりもの)の素面の舞と面をつける能とが、さまざまに組織しなおされて各地にひろがり、それぞれの土地の古風な神事と結びついて独特の様式を生んだものである。
当所で行なわれている神楽は、歴史的にはそれほど古いものではない。大正初年ごろ、大工町にある一宮賀茂神社の先代神官が教えたものである。動機は、神楽をにぎやかに奉納することにより神に感謝し、その神の恵みによって部落に和を生み出そうという考えから始められたものである。
当時、帯金・飯富等この近辺でも盛んに神楽が行なわれており、下山で始められた頃は道具一切そこから借りてやっていた。しかし、年々盛んになるにつれて、道具整備の必要がおこり、現在使われている道具は関東大震災の年(大正12年)(1923)に整えられたものである。面は、当時の金で150円から350円したが、現在残されているそれらの面の中には、相当価値のあるものも含まれている。
従来は、旧正月の20日に奉納される慣わしであったが、現在は新暦の14日夜から15日にかけて行なわれている。「剣の舞」「鈴の舞」「五行の舞」「扇の舞」などの他神話を劇化した神代神楽の一種、「太蛇退治」や「恵比寿大黒」などが、横笛・太鼓・小太鼓などの囃子(はやし)にのせて演じられる、おとなも子どもも舞い納めるが、その囃子が「シャンシャンコココ、シャンコココ」というようように聞こえるところから、部落の人たちは、「シャンココ、シャンココ」といって親しんでいる。
第二次世界大戦後一時とだえたままになっていたが、やはり伝統ある郷土芸能は存続させるべきであると、数年前保存会が生まれ、再びここに神楽も復活し、にぎやかに社に奉納されている。