三、身延の万灯まつり
 |
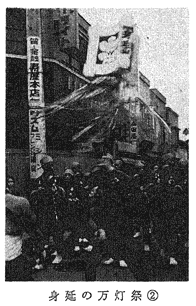 |
万灯はこのお会式と不離のものである。聖人が弘安5年(1282)池上本門寺にて61年の偉大な生涯を終えられたとき、大地は鳴動し、時ならぬ桜の花が一斉に咲き揃ったという。このことから、江戸時代になってから万灯は吉野紙で作った桜花で飾られるようになった。
日蓮門下が聖人の御命日を迎える度に深まる追慕讃仰の念はやがて法悦歓喜となり、お会式の万灯行列も次第に盛大となった。別して入滅の地池上本門寺のお会式は有名であった。古川柳にも
本門寺年に一度の所が疲れ
翌くる日は足のたたぬ本門寺
ぽったりと散るは会式の桜なり
とあり、いわゆる法華かたぎの江戸ッ子は男女老若の別なくそれぞれ万灯を振りかざして大江戸八百八町を練り回った。もちろん身延でもこの行事は早くより伝わったが、江戸池上ほどの盛大さは望むべくもなかった。しかし、総門内の各町内に万灯と纒(まとい)がくり出されて、お会式を飾る伝統的行事として数百年の歴史を今に伝えているのである。万灯を奉納するのにまといを添える習慣は最初旗や幟(のぼり)であったものが、やがて威勢のよいまといにかわったのである。
万灯には大万灯・小万灯・提灯万灯・仮装万灯・奉納手拭万灯その他工夫をこらしたものが桜花に美しく飾られ、紺のもも引、印絆天、黒たびに白鼻緒、豆しぼりの鉢巻にそろばん玉の帯という揃いのいでたちも凛々しい若衆の講中によって笛と鐘、太鼓のお囃子が奏され、見事な体さばき、手さばきでまといが振られ、めまぐるしくも賑やかに繰りひろげられるダイナミックなものである。宗教的行事として、敬けんな中にも華麗、勇壮な風趣をもつ独特なもので、永い伝統に生きている郷土の貴重な文化遺産ともいうべきものである。
万灯講保存会について
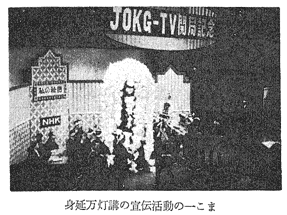 |
主な活動として
昭和37年8月NHKテレビ「私の秘密」に出演
昭和38年NHKテレビ「それは私です」に出演
昭和39年5月「第12回民放大会記念、関東甲信越芸能おくに自慢」に出演
昭和42年11月NHKテレビ「ふるさとの歌まつり」に出演
そのほか、県外街頭宣伝、観光キャラバン、福祉施設慰問等にも活躍しており、今後が期待される。