四、万歳
(一)下山万歳
NHKテレビをはじめ、マスコミにもとりあげられ、近年とみに有名になった下山万歳であるが、その起源、由来等についての文献は、火事で焼かれたり、紛失したりして、今は何も残っていない。ただ人々の記憶に留まっているのみである。長老の語るところによると、これはおよそ115、6年前頃から始まったのではないかという。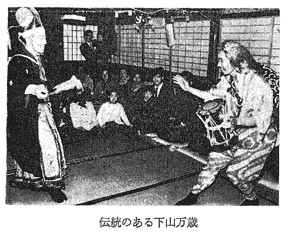 |
大庭の万歳も、形態はこの三河万歳の系統をひくものであるといわれ、祝福芸能の一つである。
現在荒町に獅子舞が伝わっているが、昔はその獅子舞のあとで万歳を演ずるのが習わしであった。そして人々は、その万歳を夜が更けるのも忘れて楽しんだものであったという。ある年の正月、門付芸としての三河万歳が下山に来て、初春の祝言を述べ、舞い、囃した。たまたま荒町で万歳を演じた人が、この三河万歳を見て大変興味をひかれた。そこで、その万歳師からそのしぐさを教わり、文句を速記し、獅子舞のあと演じられる万歳にとり入れていったという。当時若衆の1人で、大庭へ婿入りした人が毎年正月には、大庭の若衆にこれを教え演じた。すなわち獅子舞のあとで演じられた万歳を完全に独立させ、発展させたのが、今の下山万歳だといえる。
現在は、小正月に行われている。烏帽子、大紋(だいもん)に扇をもった太夫(たゆう)が、頭巾(づきん)に裁付(たつつけ)を着て鼓をもった才蔵と一組になり、各戸を巡り、初春の祝言を述べる。そして太夫が才蔵の鼓に合わせて舞ったあとで、2人でこっけいなやりとりを演ずるのである。
ここでも、この芸能を存続させることが困難になってきた。時代が移り、物の見方、考え方が変わった今、一つの大きな壁につきあたっているといえる。とおしで演ずると1時間はゆうにかかるものであるが、全部を完全に演じ切れる人の数は大分少なくなってきている。また年々若衆も減る傾向にあり、一時の活発さがなくなっている。折角の伝統芸能を守り育て、隆盛を極めた昔にもどすべく、保存会が生まれ、いま熱心な活動が続けられている。
万才台本 大庭若者
| 太夫 | あゝら千年吉祥寺、年改まりてか程目出度き折からに後となる才の才三に一寸見参な申そう。 早参れやい才三。 | |
| 才三 | 参りますとも参りますとも太夫さんのおおせなら、食う物も食はず飲む物も飲まず富士山、山をけころばし、駿河の海を一またぎおそかろう、早かろう今参りました太夫さん、はっとくれ。 | |
| 太夫 | 才三年頭に早かった。 | |
| 才三 | 何とおっしゃいまして太夫さん、今日の年頭べらぼうにいたかった。 | |
| 太夫 | 才三を此所に呼び出したるは別儀にあらず | |
| 才三 | 何とおっしゃいまして太夫さん飯つぎや重箱には無いはずだ昨晩のあまり物はこの才三が皆んな食っちゃった。 | |
| 太夫 | 何んだ才三出るから食う事ばかりぬかしやあがる此の方はどうけ万才よ。 | |
| 才三 | 何とおっしゃいまして太夫さん、どうけに万頭こうこで茶をのむ万才どうへ。 | |
| 太夫 | この方はどうけ万才よ。 | |
| 才三 | なる程どうけ万才よ。 | |
| 太夫 | 表6番、裏6番、合せて十二通りの万才よ。 | |
| 才三 | 昨晩6番、今朝6番合せて十二通りの万才よ。 | |
| 太夫 | これこれ才三表6番、裏6番合せて十二通りの万才よ。 | |
| 才三 | なる程十二通りの万才よ。 | |
| 太夫 | この太夫の身に付いてお噺し申せ。 | |
| 才三 | お囃し申しましょう。 | |
| 太夫 | やれ1本の柱が | |
| 才三 | 一の宮神社 | |
| 太夫 | やれ2本の柱が | |
| 才三 | 二の宮神社 | |
| 太夫 | やれ3本の柱が | |
| 才三 | 佐々木明神 | |
| 太夫 | やれ4本の柱が | |
| 才三 | しざいの弁天 | |
| 太夫 | やれ5本の柱が | |
| 才三 | ごふせの明神 | |
| 太夫 | やれ6本の柱が | |
| 才三 | 村八幡宮 | |
| 太夫 | やれ7本の柱が | |
| 才三 | なだほの天神 | |
| 太夫 | やれ8本の柱が | |
| 才三 | 八天宮 | |
| 太夫 | やれ9本の柱が | |
| 才三 | 熊野神社 | |
| 太夫 | やれ10本の柱が | |
| 才三 | 所の氏神 | |
| 太夫 | やれ11本の柱が | |
| 才三 | 秋の権現火防(ぶせ)の神 | |
| 太夫 | やれ12本の柱が | |
| 才三 | 財布を上げておおき | |
| 太夫 | ヤレヤレヤレヤレ大黒天には | |
| 才三 | 恵比寿比シャモン | |
| 2人 | ホーテ 福ロク、マーショージンには弁才天。 | |
| 太夫 | やれ間違ふた間違ふた | |
| 才三 | おじちゃの国でも悪い国 | |
| 太夫 | おじちゃの国でもまた間違うた間違うた | |
| 才三 | 若狭の国では | |
| 太夫 | 八百幾人 | |
| 2人 | 真竹に小枝がお神様 | |
| 太夫 | おやおや才三お囃し申しな | |
| 才三 | ハヤハヤ太夫さんお囃し申してヤレ目出度い所では | |
| 2人 | 尾張の国や三河のおおとり違ってお目出度う万才楽は三腹つい、おしかあかりたら | |
| 才三 | のしかあかり | |
| 2人 | のしかあかりたらお目出度う | |
| 太夫 | アー才三や才三やこんな万才もストトントンととめおいて | |
| 才三 | アーストトントンとうっちゃって | |
| 太夫 | これこれ才三や商売道具をうっちゃっちゃあおまんまの食い上げだ | |
| 才三 | なる程おまんまの食い上げだ | |
| 太夫 | 所で才三謎の1曲でもしようではないか | |
| 才三 | 謎は人参の智恵くらべ、この才三様いたって好きだ。 | |
| 太夫 | これこれ才三に様がいるか才三でたくさんだ これこれ才三や人参があるか、人々の智恵くらべ まず才三役に一挺絞って参れやい | |
| 才三 | まず太夫役に一挺絞って参れやい | |
| 太夫 | まず太夫役に一挺絞って参ろうものならば | |
| 才三 | なる程参ろうものならば | |
| 太夫 | やぶれ障子とかけて何ととく | |
| 才三 | 出たね太夫さん仲々むづかしい | |
| 太夫 | 駄目駄目 | |
| 才三 | この才三には智力が無くてとけないから太夫さんに1本あげてやれ | |
| 太夫 | この謎清くもらって流そうものならば | |
| 才三 | なる程流そうものならば | |
| 太夫 | やぶれ障子と掛けおいてよ | |
| 才三 | なる程掛けおいてよ | |
| 太夫 | うぐいすととく | |
| 才三 | 出たね太夫さんといた心は | |
| 太夫 | といた心は才三、春を待つではないかいな | |
| 才三 | 早々太夫さん良い所お囃し申してお目出度う | |
| 太夫 | まず才三役に一挺絞って参れやい | |
| 才三 | まず才三役に一挺絞って参ろうものならば | |
| 太夫 | なる程参ろうものならば | |
| 才三 | 天保銭と掛けて何ととく | |
| 太夫 | 出たな才三仲々むづかしい | |
| 才三 | 駄目駄目 | |
| 太夫 | この太夫には智力がなくてとけないから才三に1本上げてやれ | |
| 才三 | この謎清くもらってといて流そうものならば | |
| 太夫 | なる程流そうものならば | |
| 才三 | 天保銭と掛けおいてよ | |
| 太夫 | なる程掛けおいてよ | |
| 才三 | おばあちゃんのしわくちゃポポととく | |
| 太夫 | 出たな才三、といた心は | |
| 才三 | といた心は太夫さん、穴があっても通用しないじゃないかいな | |
| 太夫 | やっぱり才三よい所お囃し申してお目出度う | |
| 太夫 | アー才三や才三やこの謎もストトントンととめおいて代々ミカグラにおそくなるこの太夫の身に付いてこうお囃し申せ | |
| 才三 | お囃し申しましょう | |
| 2人 | 昔は白河将軍様のお時熊野様へも御参詣みぎりがやはり年頭の万才楽はかむりたるえぼしのかざおり左り折やなぎのはのこ枝もたまればこれまあみぎりがやはり年頭の | |
| 太夫 | 右が三十三ヶ国 | |
| 才三 | その又左も三十三ヶ国 | |
| 2人 | 合はすれば六十と六ヶ国 | |
| 太夫 | ゆうべも33番な | |
| 才三 | 今夜も33番な、ああ国のなあやれ太夫さん | |
| 二人 | 国の鳴るこの舞も舞もこの舞ひ舞ひすればそなた様の番通り | |
| 太夫 | オヤオヤ才三 | |
| 才三 | やっぱり太夫さん | |
| 2人 | 大平おやおや大平国中安の心に祝をおさむる舞の手天の岩戸をおひらきぞめのためしにも | |
| 太夫 | よよの | |
| 才三 | よよのよよのよよのよよのよよの | |
| 2人 | 世の末が変らんずばで若水が何んでも | |
| 太夫 | チョロリヤ | |
| 才三 | チョロチョロ | |
| 太夫 | チロチロチョロチョロと才三が夜ばいにと出掛ける | |
| 2人 | 変る春の元旦 | |
| 太夫 | アー才三や才三やこの万才もストトントンととめおいて 何か面白い話でもしようではないか何か才三に面白い話があるか | |
| 才三 | あーあーあるあるこの才三江戸村へととびこんだ時の話がある | |
| 太夫 | これこれ江戸に村があるかもったいなくも東御久坊(天子様)のおいで遊ばしまする花の東よ | |
| 才三 | 穴の東よ | |
| 太夫 | これこれ才三穴の東があるか花の東よ | |
| 才三 | なる程花の東よ、まずこんな風では見苦しいから上から下まですっぱりぬいでくそんぼりへとうっちゃった。 | |
| 太夫 | 何うっちゃった | |
| 才三 | 太夫さんが欲が深いからもう拾う気になっている | |
| 太夫 | これこれ才三この大勢の人の前でこの太夫に恥をかかせるものではない | |
| 才三 | それから股引はいいきだ | |
| 太夫 | 何いいきがあるか、あれは甲斐の名産甲斐絹よ | |
| 才三 | でも太夫さん歩けばイイキイイキ言うよ | |
| 太夫 | でも甲斐絹よ | |
| 才三 | なる程甲斐絹よ | |
| 才三 | それから足袋はボロード | |
| 太夫 | 何ボロードがあるかあれはビロードよ | |
| 才三 | でも太夫さんボロボロしていたよ | |
| 太夫 | でもビロードよ | |
| 才三 | なる程ビロードよそれから着物は24丈 | |
| 太夫 | 24丈があるかキ八丈だろう | |
| 才三 | でも太夫さん三、八二十四丈よ | |
| 太夫 | キ八丈よ | |
| 才三 | それから帯は八方だ | |
| 太夫 | 何八方があるか、あれはハカタよ | |
| 才三 | なる程博多よ、これですっかり仕たくもととのったすると太夫さん、むこうから馬が幡屋を引いて来た。 | |
| 太夫 | 何幡屋があるかあれは才三が乗る馬車よ。 | |
| 才三 | なる程馬車よ、才三この馬車に乗ってつつがなく鰍沢へ着いたすると道のこっち側におすみべったり13里と書いてあったよ。 | |
| 太夫 | 何才三あれはやきいもやのかん板で9里よりうまい13里とかいてあったんだろう。 | |
| 才三 | あっそうか、それから甲府のエイシャバへ着いた。 | |
| 太夫 | 何エイシャバがあるか停車場だろう | |
| 才三 | なる程、停車場でイップを買ってトラホームへ出た。 | |
| 太夫 | 何だ才三切符買ってプラットホームに出たんだろう。 | |
| 才三 | あっそうプラットホーム、すると太夫さん向うから長い百足が太い巻たばこをくわえてやって来た。 | |
| 太夫 | 百足があるかあれは中央線の汽車よ。 | |
| 才三 | なる程汽車よ、才三その汽車へ乗った。すると汽車やつドテポッポドテポッポあの坂、この坂土方の掘ったでかいポゝかさかけ、小さいポゝかさかけ、太夫さんのスケマラと言ひながら東京へ着いた。東京仲々にぎやかだね。まず何をおいても才三ドサ草へとお参りに行った。 | |
| 太夫 | でも浅草よ。 | |
| 才三 | なる程浅草雷門へお参りする何んと太夫さん赤面真紅なおっちゃんがあっちいふんばり、こっちいふんばりしてわらじを買っていたよ。 | |
| 太夫 | これこれ才三あれは御門番の仁王さんで、わらじを買っていたんではない多ぜいの参詣の人が御宿願果に上げたよ。 | |
| 才三 | でも太夫さん上から下へぶらさがっていたよ。 | |
| 太夫 | でも上げたのよ。 | |
| 才三 | なる程上げたのよ。それから才三あっちこっち見物して歩くとこっちじゃオヒチノドキあっちじゃチョイチョイ店 | |
| 太夫 | 才三そのまねできるかい。 | |
| 才三 | ああ出来るとも、この才三物おぼえがよくても、どしょうわすれがするからよくおぼえている。 | |
| 太夫 | では一つやって見な。 | |
| 才三 | じゃあチョイチョイ店からやろう、まずこんな具合に中腰になってね。才三じゃあチョイチョイ買いなよどなたも買いなよ、むこ入り道具に、嫁入り道具にキュッキュッと磨けば白いあわたつ舶来シャボン、夜中になるとおとっちゃんおかあやんがむくむくやりだし舟底まくらも1銭と8厘で2銭の銅貨じゃ5銭のおつりだ。 | |
| 太夫 | そんなチョイチョイ店があるかこうなんだろう、チョイチョイどうだね。どなたもどうだね。むこ入り道具に嫁入り道具にキュッキュッと磨けば白い泡立つ舶来シャボン1銭と8厘で2銭の銅貨じゃ2厘のおつりだ、そうなんだろう。 | |
| 才三 | 太夫さんの言う通りだ、それからこっちじゃ八百屋お七のぞき | |
| 太夫 | やって見な。 | |
| 才三 | アーラ、お寺さんは生米ぢゃ煮やくえん | |
| 太夫 | そうではあるまい、こうなんだろう。 アソラお寺さんはよう駒込の吉祥院 | |
| 才三 | それから次が河輪の十郎平 | |
| 太夫 | やって見な | |
| 才三 | アソーラ、おとっちゃんはあわの飯を16ぺえ | |
| 太夫 | ホー、それはずいぶんあわれな所だなあ。 | |
| 才三 | あゝあわれだとも太夫さんの様に涙もろい方ではこんなに大きな涙をポロリポロリこぼしちゃうよ。 | |
| 太夫 | そんなにあわれかい。 | |
| 才三 | あゝそうともそうとももうそこにいる娘は泣いているではないかね。 | |
| 太夫 | ではやってみな。 | |
| 才三 | アソラ、おとっちゃんあわの飯を16ぱい | |
| 太夫 | 何だ才三そんなあわれさがあるか。 | |
| 才三 | なる程太夫さん見なくても何でも知っているんだね。 | |
| 太夫 | あゝあゝそうとも。 | |
| 才三 | これで才三見物もすんだから太夫さんの家へ正月盆れいに行った。 | |
| 太夫 | これこれ才三。正月に盆れいがあるか、正月年頭よ。 | |
| 才三 | なる程正月年頭よ、太夫さんのおかみさん仲々世事物だね。 | |
| 太夫 | あーあー世事者よ。 | |
| 才三 | あーあー才六や才六やよう来てくれた、さあさあ中から外へはい上って上から下へ上って餅でもぬいで下駄でもやいてかじれやい、戸棚に味噌があるから | |
| 太夫 | なんだ才三、いくら太夫のかかあが世事者でもそんな世事は言うまい。こうだったんだろう。 サアサア才三や才三やよう来てくれた外から中へ入って下から上に上って下駄でもぬいで餅でもやいておあがり、戸棚にみつがあるから、 | |
| 才三 | ああそうそう味噌とみつの間違いよ。それから太夫さん御自まんの中庭を拝見に行った。すると何とうどの大木がニューとはえて花ざかりだったよ。 | |
| 太夫 | あれはうどの大木ではない。梅の大木よ。 | |
| 才三 | なるほど梅の大木よ。 それですっかり太夫さんの家で御馳走になって才三又下町見物にでも行こうと思って太夫さんの所を出掛けた。 | |
| 太夫 | これこれ才三や、こんな空ひょうひゃくもストトントンととめおいて代々御かぐらにおそくなるこの太夫の身についてこうお囃し申せ。 | |
| 才三 | おはやし申しましょう。 | |
| 2人 | お伊勢ではおん宮様の御時、都では大りん様の御城下東京入りと下(くん)だりたら天子様の御城下、御本丸や西の丸、ヒヤラ門や虎の門、神田橋やかーじ橋、御福橋の御門燈 | |
| 太夫 | 表の御門が千間町 | |
| 才三 | 裏の御門が万間間口 | |
| 2人 | おつつらつっとつんばらかしたらお目出度う、御門の戸をお開きぞめのその時かいどう裏で音がする。キジンの声だぜ、キリキリカラカラカラカラキリカラといな音がするではないかいな。 | |
| 太夫 | つるは表 | |
| 才三 | かめは裏 | |
| 太夫 | つるは表で舞を舞う。 | |
| 才三 | かめは裏でらく遊び。 | |
| 2人 | つるは千年、かめは万年のお祝。 |