梅平青年のうたいについて
梅平 遠藤亨
梅平では徳川時代より伝わると聞く、うたいぞめが毎年旧正月2日青年(わかいしゅう)によって行なわれて来た。厄(やく)年といって男では42歳女では33歳が人生の命を定める年とされ、なかなか重大な年である。この年を無難に過ごせば相当長生きができるといういい伝えである。この厄年に出合った人を持つ家庭では厄落しといい、梅平の若い衆の頭取に頼んでうたいを正月2日にやってもらう習慣になっていた。出費としては酒1升、豆腐1すり(10丁)を若い衆に寄付するのである。豆腐といっても今の豆腐と異なり1丁が15センチ角、厚さが7センチ位はあった。昔はおさしみなどはとても得られぬので、この豆腐が最上のごちそうであったわけだ。
厄年の人がない年は申込みがないので、宮本坊と称する廃寺を借りてやったものであり、厄年の人が2人もある年は3日は不浄日であるというので、2日と4日にやく年の人のある家に朝から行き、午前中けいこをして午後からやったものである。
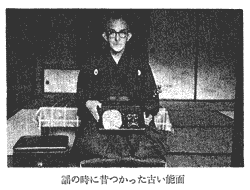 |
今は青年が少なくなったので、うたいぞめはやめてしまったが惜しいことである。大東亜戦争時代まで続いたことを記憶している。うたいは観世流の端謡(はうた)いで私の父正蔵が師匠であったため私も叱られながら、よく父の前へ呼び出され村の若い衆とともに修業したものである。そのうたいの文句を覚えている限り記して後日の参考にしよう。
観世流端謡曲
〇高砂子やこの浦風に帆を上げて 月もろともに出し帆の波の淡路の島影や遠くなる帆の沖過ぎて 早住みの江に着きにけり 早住みの江に着きにけり
〇高砂子と云ふは上代の万葉集の古えの記 神住吉と申すは今此の世に住み給ふ えんぎの御事松とはつきぬ言の葉の栄は古今相同じとは 御代をあがむるたとへなりけり
〇ところは高砂子の 尾の上の松も年ふりておいの波もより来るや 木の下影の落葉かくなるまで 命永らへて なおいつまでかいきの松 それも久しき名所かな それも久しき名所かな
〇四海波静かにて 国も治まる時津風 枝をならさぬ御代なれや げにや仰ぎても 事もおろかやかかる世に 住める民とて 豊かなる君の恵ぞ有り難き 君の恵ぞ有り難き
〇庭の砂子は金銀の 玉をつらねてしきたえの いほべの錦やるりのとぼそ しゃこの雪下駄瑪瑙の箸 池の汀の鶴亀や蓬莱山もよそならず 君の恵ぞ有り難き君の恵ぞ有り難き
〇松根によって腰をそれば1,000年の緑手に満てり 梅花を折って頭にさせば2月の雪衣に落つ ああありがたのようごうや 月住吉の神遊び 御影をおがむあらたさよ げに様々の舞姫の声もすむなり住の江の 松影もうつるなる青海波とは是あらん
〇神と君との道すぐに 都の春に行くべくは これぞけんじょう楽の舞いさて万歳のおみ衣 さすかい波は悪魔を払い 治むる手には寿福をいだき 千秋楽には民をなぜ 万歳楽には命を伸ぶ あいに相生の松風さあさあ津の声で楽しむ さあさあ津の声でたのしむ

