学徒動員の時代
下山 深沢辰雄
私たち県立身延中学校の4年生約150名に、「学徒動員」の命令が下ったのは昭和19年7月半ばのことだった。すでに5年生は愛知県半田の中島飛行機工場へ動員されており、私たちはその直後である。トランクにわずかの着替えと筆記具を詰めこみ、東神奈川の六角橋の寮に入った。寮から東神奈川駅まで市電、東神奈川駅から新子安まで省線、新子安から工場まで徒歩。身中生は自動車のエンジン部品の製作に取り組んだ。(シリンダー・クランク・フライホイル・ブラケットなどの製作研磨・エンジン組立)指導者も少なくなれないため工作機械のドリル・バイト・カッター等の刃を破損したり、おしゃか(失敗品)を出したり容易でなかった。寮に入った2、3日は食事もよかったが、やがてジャガイモがまじり、そのうちに大豆のぼきぼき(固いので私たちはこう呼んだ)入り飯でひどい下痢になやまされる人も多くなってきた。その後乾燥野菜やこうりゃん食も日増しに少量になって、朝食と昼食のべんとうを同時に朝食べても足りない位であった。空べんとうを持って出勤し、箸もたたないような雑炊をすすって働いた。寮に入荷したさつまいもを生でかじったり、帰郷の際持ってきた米をかくれて洗面器で煮て食べたり、そばがきをしたり、こうせん(麦を炒(い)って粉にしたもの)を会社から作ってきたジュラルミンのさじ、或は葉書をさじ代りにして交代ですくって食べたりした。大豆の炒ったもの、小麦粉の油菓子、ふくらし粉を入れたうすやきなどは上等のものであった。帰郷して食べることは唯一の楽しみであった。
作業衣も到着後支給されなかったので油服のまま当分の間通勤した。電車に乗り空席に坐るとお客さんが立ち上がる、そこへまた坐る、つぎつぎに立たせてしまったこともあり、石けんもろくろく支給されず、銭湯なども7・8人が同時に湯舟につかると油が浮き、ずい分きらわれたものだ。布団も糸くずの入ったせんべい布団、不潔な生活にしらみが大発生しても駆除の薬品もない状態であった。
1日300台分の部品確保・突撃(げき)週間というような目標のもとに「日の丸」「神風」「必勝」などの鉢巻、「学徒勤労報国隊」と朱書された腕章姿で祖国の必勝を信じ、産業戦士として職場も戦場とばかりに生産戦に従事した学徒は、遠く東北の青森中学、弘前中学、平商業、近くの日大4中、大妻高女等が日夜交代で働いた。その後寮も六角橋から伊勢崎町近くの末広町の伊勢崎第2寮に入った。
昭和19年秋サイパン島よりの本土空襲が烈しさを加えてきた。工作機械の下に造られた防空ごうに入ったとたん、約1キロばかりはなれた地点に落下した爆弾の物すごい地ひびきと共にポロポロと首筋に土の落ちた時の気持は全く生きた心地はしなかった。また冬夜勤の帰路空襲警報発令となり、とびこんだ防空ごうは水びたし、足袋、くつ下もない素足に下駄の冷たさ、死んでもいいと外に出て手足をこすり合わせて、身ぶるいしながらじっと耐え忍んだ思い出は今でもぞっとする。寮にいてもはじめはキャハン・くつなどをはいて避難したが、そのうち毎夜の警報のため避難する者もなく平気になっていった。遠く東京方面などの空襲の夜景は、花火のようであった。いくすじもの探照灯で敵機はとらえるがただとらえているだけであった。
昭和20年2月、この日の空襲警報は昼間で、艦載機の来襲であった。工場の屋根をつらぬく機銃の音、屋根を貫き事務室は入った銃弾でやられた人、橋上を通っている一学生を旋回しながら射殺したグラマン、そして入りみだれた空中戦のようす、横浜港内の味方の航空母艦が、またたく間に沈められてしまった光景を見て戦争の恐ろしさと、敵がい心を一層深めたが、いかにせん日本の飛行機の少ないこと、高射砲が工場の敷地内にあったが、発砲もせず今思えば木製ではなかったかと思う。
昭和20年3月下旬戦時特別措置法により、4年生で繰り上げ卒業の措置がとられ、3月30日午後第4学年で卒業式が工場の養成工の寮にある講堂で挙行された。写真(注3編5章)を見てもわかるように、戦闘帽あり、学生帽あり、工員帽・学生服・作業服・地下足袋・皮靴・下駄ばき・帯芯のキャハンと服装もまちまちで卒業の晴れやかさどころではなかった。卒業生のうち、進学者は工場に、農家の者は申請により農業用員として食糧増産のため家へ、また教員不足のため代用教員として、それぞれ県内へ別れ別れになっていった。志願兵として一部準卒業生もあった。
空襲も烈しさを増し、工場勤務者も減ったため元町の外人墓地近くフェリス高女(外人)のそばの寮に移った。そして昭和20年5月29日横浜大空襲、防空ずきんを水につけてかぶっても、熱くてどうしようもなかった。火たたきや消火弾を使ってようやく寮は焼かずに幸いひとりの犠牲者もなく助かった。米を井戸にかくしたが空襲後出そうとしても出せず、ようやく求援物資で腹づくりをして、焼け残りのトランクを下げ帰郷の途に着いた。
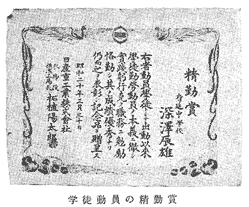 |
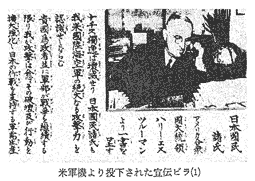 |
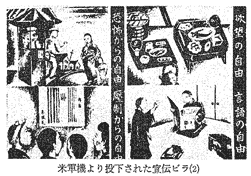 |
|
なお思い出の写真も入って充実したものである。忘れられない動員時代を共に生活したことが、私たちの同級会を今日まで支えてきた原動力といえよう。同級会には毎回必ず恩師を招待している。

