漆かきについて
清子 鈴木富治
漆の木は、漆科植物に属する落葉樹で、葉は4、5月ごろに発芽し、花は5月から6月にかけて咲く。木が新緑の葉をつけるようになると、地中から多量の水分を樹が吸い上げるようになる。それから樹液の採取が可能になる。日本には、古くから漆の木が自生しており、その利用もすでに縄文人の弓の矢をつくるに用いている。奈良朝時代に仏教が伝来し、それにつれて漆を用いた仏具や仏像の製作が盛んになり、また美術工芸も発達した。戦国時代になると武具に漆が使われるようになり、別に蒔絵の創製、さらに日用生活用具の製造等にまでその特性とする防腐性、接着性、堅牢性、装飾性が利用され益々漆の需要が盛んになった。
わが国に産する漆液のうちで、古くから吉野地方に産するものをもって第1とされていた。本県のものについては、甲斐国志巻之123付録5産物製造部耕植類の中に、重要の物産として述べられている。
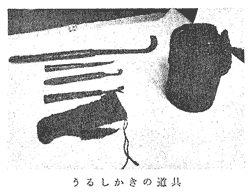 |
漆液をとる人は「漆やさん」と呼ばれて福井県から来た。
刀弥勇太郎の「漆かきとその実態」によると「中部以東、関東、東北は越前の漆かきの稼ぎ場であった。旧藩時代はおくとして、明治13年から14年にかけての調査によると、全国の掻取職工および漆商人の数は1万2,000人で、うち5,000人は福井県人によって占められていた。さらにその内訳をみると、今立郡のもの2,500人、その付近のもの1,500人、丹生郡1,000人となっている。
今立郡とその付近が全体の8割を占めている。さて明治10年の国産漆の産出量は20万貫(推定)であり、推定漆掻人数は10,000人であったから、およそ国内産出量の半分は福井県人が採取したことになる。
今立郡下では、明治初年の統計によると、旧河和田村(現鯖江市)800人、服間村(現今当町)2,000人となっている。
河和田村で漆かきを多く出したのは、上河和田、沢、尾花など山沿いの奥地部落に多いといわれる。この村の片山部落は漆器の産地で、片山椀という粗雑な三つ椀を作っていた。その漆やも終戦後は来なくなってしまった。代って土地の人々がやったが余り続かなかった。
「漆かきは山村の特殊職業の一つ。各地の山を渡り歩いて漆を掻く業であるが、これには技術を要し製品の需要も多かった。夏かく漆は、幹に広く間をおいて筋を切って取るが、樹勢もよく質が佳いので高価である。秋になると、細かく刻み目をつけてとり、質は劣り値も安い。その後は大枝を二尺五、六寸から三尺ほどに切割って水に漬け、寒くなってから家の内で作業する。こうした掠奪産業なので次第に野生樹が乏しくなり、この業は衰えざるを得なかった。今でも北越後や会津地方から漆かきの出稼がある。」(民族学辞典より)
漆の栽培には団地栽培と散り木栽培とがあった。団地栽培は三椏栽培と関係があった。大正末頃まで山畑には三椏を栽培したが、三椏は性として日光の直射をきらったので、三椏の山畑には榛(はん)の木や、漆の木や、高刈りの桑などを立てて直射をふせいだ。これ等の樹木は秋になると落葉して、三椏の肥料にもなったわけである。散り木栽培というのは、山野に点在するものを保護しておく方法であった。
漆の原木の売買については、年期売りと1年売りがあった。年期売りは多くは団地である程度の本数がまとまっているところで、年売りは散在しているもので1本いくらで売ったようであった。
甲斐国志山川部に「漆畠、御立野、吉沢村一町六反二畝二十歩享保九年引渡張に六・七年目に入札を以て漆樹を売る去年払金二両永三十二文」とあり、また「よき漆樹五本うえて持ちたる者は老人夫婦の糧は必ずあるもの也」といわれたほどの収益の多いものであった。
町内の山つき部落へは漆かきが来ていたようだが、豊岡地区の相又・横根・清子へも来ていた。清子へは福井県今立郡炭焼村という僻村から来ていた。5月頃から12月頃までいた。その間は毎日漆をかいていたが、特に土用中は良質の漆が採れたので精を出した。漆かきが終ってからは、鎌や包丁などの刃物の商いや、膳や椀などの漆器類の斡旋をした人もあった。現在でも金物だけの商いをしている人が残っている。なお漆かきの道具としてはカマ・アラカワトリ・ウルシガンナ・トリベラ・ゴウ(盒)・クリベラ・ツルベ(桶)・マワシボーチョウ・サシベラ・ナタ等であったが、特に主役になったものはウルシガンナ・トリベラ・ゴウであった。
漆木売渡約定之証
南巨摩郡豊岡村清子地内
字門原百六十六
一畑壱反壱畝拾五歩
字天神三百四十五
一畑壱反四畝廿九歩
同所三百四十六
一畑五畝五歩
合計反別三反壱畝拾九歩
右山地ニ有之候漆木不残外ニ佐野久之丈ヨリ預リ置候山地ニ立置ク漆木並ニ拙者ノ所有地ニ立置ク漆木不残引当テ
但シ漆木ノ義ハ目通リ六寸廻リヨリ以上ノ木カキトル可クノ約
一金弐拾円也 但利子ノ義ハ前出漆木カキトル上ハ無利子ノ事
右者拙者要用ニ付前書金員正ニ受取リ借用仕リ候処実正也然ル上前但シ書之通リ明治廿四年ヨリ壱ヶ年ヲキカキトリ都合五ヶ年之間前記之通リ木数何程有之候トモ其年々取極リ候相場ニ而元金引去リ御勘定被下候トノ約定ニ而拾ヶ年之間貴殿ヘ前書山地之漆木不残売渡申処実正也右ニ相定メ候得共若万一漆木下落ニ相成候節右年李ニ不拘本金勘定相成候迄ハ御カキ取可被下候若年季内ニ而勘定済相成候トモ他ヘ一切売却不仕相定候通リ年限中無相違貴殿ヘ売却可申候万一本人ニ於テ無拠場合ニ而他ヘ地所売却相成候節ハ前記山地ニ有之候漆木ニ見増タル漆木ヲ以テ保証人方ニ而右元金返済相成候迄ハ弁木仕リ貴殿へ聊御迷惑相掛ケ申間敷為後日保証人連署ノ上漆木売渡約定証差入申処仍而如件
明治廿四年旧十一月廿五日
甲斐国南巨摩郡豊岡村
借用人 鈴木栄兵衛
保証人 三五月久左衛門
越前国南条郡武生町旭廿番地
福田石蔵殿
南巨摩郡豊岡村清子地内
字門原百六十六
一畑壱反壱畝拾五歩
字天神三百四十五
一畑壱反四畝廿九歩
同所三百四十六
一畑五畝五歩
合計反別三反壱畝拾九歩
右山地ニ有之候漆木不残外ニ佐野久之丈ヨリ預リ置候山地ニ立置ク漆木並ニ拙者ノ所有地ニ立置ク漆木不残引当テ
但シ漆木ノ義ハ目通リ六寸廻リヨリ以上ノ木カキトル可クノ約
一金弐拾円也 但利子ノ義ハ前出漆木カキトル上ハ無利子ノ事
右者拙者要用ニ付前書金員正ニ受取リ借用仕リ候処実正也然ル上前但シ書之通リ明治廿四年ヨリ壱ヶ年ヲキカキトリ都合五ヶ年之間前記之通リ木数何程有之候トモ其年々取極リ候相場ニ而元金引去リ御勘定被下候トノ約定ニ而拾ヶ年之間貴殿ヘ前書山地之漆木不残売渡申処実正也右ニ相定メ候得共若万一漆木下落ニ相成候節右年李ニ不拘本金勘定相成候迄ハ御カキ取可被下候若年季内ニ而勘定済相成候トモ他ヘ一切売却不仕相定候通リ年限中無相違貴殿ヘ売却可申候万一本人ニ於テ無拠場合ニ而他ヘ地所売却相成候節ハ前記山地ニ有之候漆木ニ見増タル漆木ヲ以テ保証人方ニ而右元金返済相成候迄ハ弁木仕リ貴殿へ聊御迷惑相掛ケ申間敷為後日保証人連署ノ上漆木売渡約定証差入申処仍而如件
明治廿四年旧十一月廿五日
甲斐国南巨摩郡豊岡村
借用人 鈴木栄兵衛
保証人 三五月久左衛門
越前国南条郡武生町旭廿番地
福田石蔵殿

