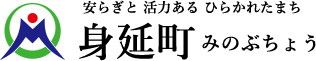印刷【実施中】クラウドファンディング「本栖湖の水産資源の復活に向けて」
【身延町によるガバメントクラウドファンディング第1号】
本栖湖の水産資源の復活に向けて
(背景)
世界遺産富士山の西麓に位置する本栖湖は、周囲12.6㎞、水深が122mの湖で、富士五湖の中でも手付かずの自然が多く残されている湖です。透明度が非常に高くエメラルドグリーンの湖畔から見る富士山は千円札のデザインにも採用されていることで知られています。その本栖湖では、様々なレジャーで訪れる方が多く、ヒメマスやニジマス、コイ、ウナギといった淡水魚を目当てにした釣り客も多く訪れます。特にヒメマス釣りは重要な遊漁、観光資源として大きな役割を担ってきました。
しかし、数年前から本栖湖ではヒメマスの記録的な不漁が続いており、そのような中、令和4年11月に本栖湖におけるレイクトラウトの生息が初めて確認されました。またその後の調査の結果、本栖湖におけるヒメマスの不漁の主な要因がレイクトラウトによる食害であることが確認されました。
本栖湖漁協の地道な駆除活動に加え、山梨県も効果的な駆除に向けた本格的な調査研究を実施している中、身延町としても本栖湖における水産資源の復活に向けた取組みに賛同したいと考えます。これらの本栖湖における水産資源の復活に向け、皆様のご寄付をよろしくお願いします。

(現状と課題)
山梨県水産技術センターでは令和4年12月から底刺網を用いた捕獲調査を実施していますが、1年間で捕獲した魚種ごとの魚の数が漁業権魚種として放流されているニジマスやコイなどよりも多く捕獲されている状況にあります。これは、すでに相当な数のレイクトラウトが本栖湖において繁殖している可能性を示唆しています。そして、この捕獲されたレイクトラウトの胃の中からは丸のみにされた大きなヒメマスや多くのヒメマスの稚魚が確認されており、記録的な不漁の主な要因であることの裏付けがされた形となりました。
山梨県水産技術センターは令和8年度を目標に効果的な手法による駆除(産卵場所を特定して刺網による捕獲駆除)に向けた対応を進めていますが、それまでは遊漁者による釣行で駆除する方法に頼るほかありません。事実、本栖湖漁協では遊漁者がレイクトラウトを釣り上げた際に駆除協力金を支給しています。今後もしばらくは多くの遊漁者による協力は欠かせない状況です。

(レイクトラウトの特徴)
寿命が非常に長い⇒48歳の個体が捕獲されたレイクトラウトの特徴
大型化する⇒ 全長1mを超える個体が捕獲された(Koel et al. 2020)
大型化に伴い魚食性が強くなる⇒ 9歳を超える個体は魚が主食(Ruzycki et al. 2003)
湖だけで生活史が完結する⇒ 繁殖に流入河川を必要としない。湖だけで生活史が完結など
こうしたことから、本栖湖はレイクトラウトの生息に適した環境といえます。
(寄付金の使い道)
皆様よりいただいた寄付金は、レイクトラウト対策に向けた本栖湖漁協の活動及びその他の本栖湖における水産資源保護に使用させていただきます。
 (ヒメマスの様子)
(ヒメマスの様子)
<掲載サイト>
お問い合わせ
担当:産業課
TEL:0556-42-4805(直通)