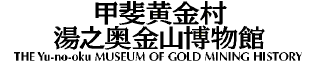印刷シン・ドウノヘヤ
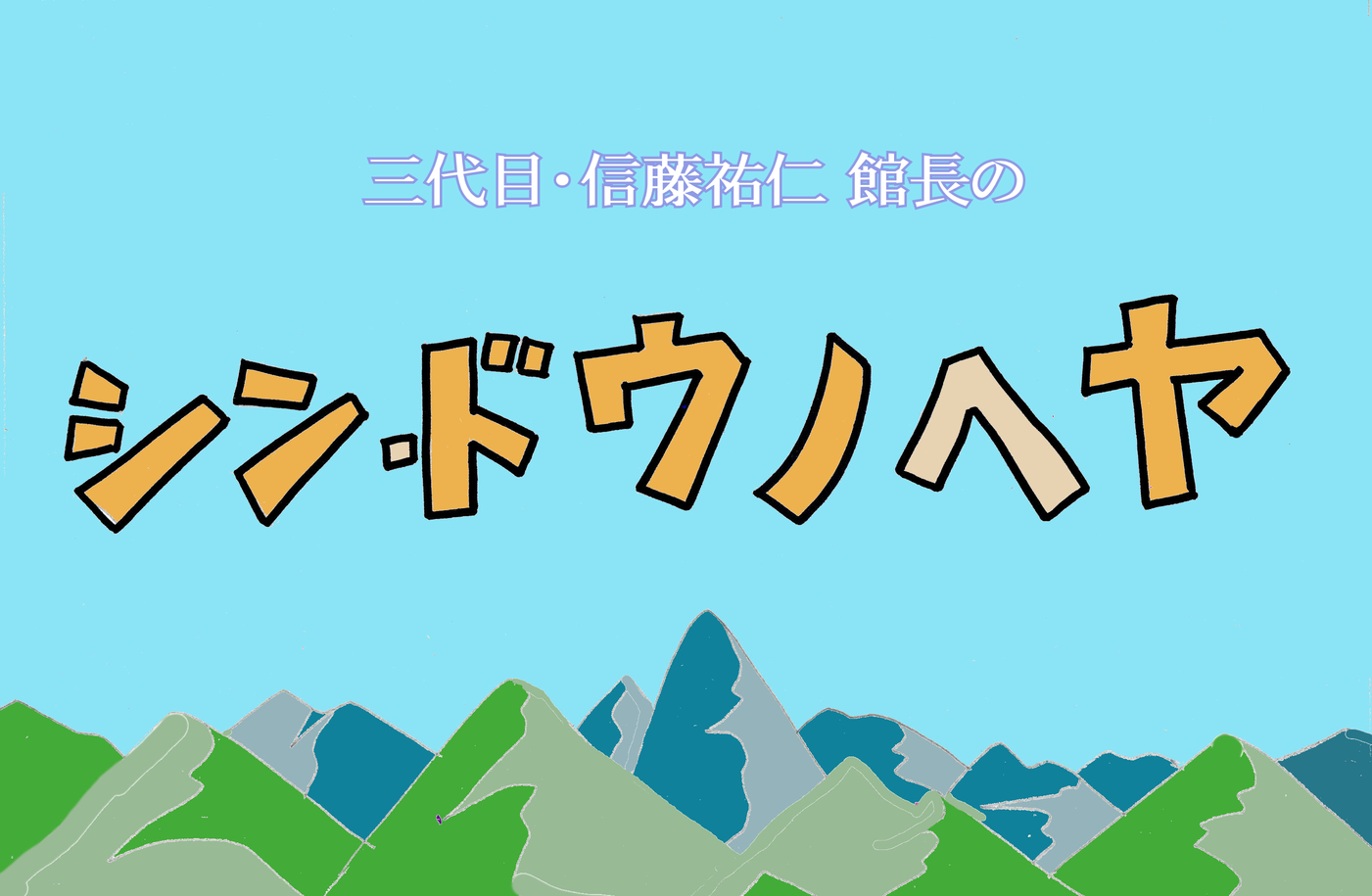
2月21日(土)
テレビやラジオの番組中にあまり聞きなれない言葉を聞いたことを思い出しました。「オノマトぺ」です。小中学校時代の授業では全く聞いたことがなかった言葉であり、使ったこともなかった言葉なのです。国語の教科書では、「擬音語」・「擬態語」と言っていたはずです。「ワンワン」はイヌの鳴き声、「ニャンニャン」は猫の鳴き声の「擬音語」、「キラキラ」光る金や「ポカポカ」の陽気は「擬態語」になります。最近カタカナ言葉に抵抗がなくなってきたのは、英語表現が日常で普通に使われるようになったり、SNSやブログなどインターネットの普及があげられると思います。しかし、堅い頭を持つ私にとっては、若い子供世代の人達の会話には意味不明な言葉が乱舞しているように思われます。
昔を振り返ってみると、ブルースリーの「アチョー」、Dr.スランプアラレちゃんの「ツンツン」、北斗の拳の「あたたたたたた」や不思議な擬音の数々は、テレビやアニメでよく使われていたことがわかります。古典でいうと、狂言の「くっさめ」はくしゃみの擬音で今の「ハクション」なのですが、これは知らないと全く何のことだかわかりません。イヌの鳴き声も英語では「バウバウ」、にわとりの「コケコッコー」は英語で「クックドゥードゥー」擬音語も時代や地域によって全く違った表現がされるのですね。
2月16日(月)
「旧市川家住宅」は、身延町和田平にある山梨県指定文化財になっている大型の民家です。富士川中流域に特徴的なかぶと造りの茅葺屋根を持ち、代々大庄屋や交代名主を務めた家柄です。富士川東岸の背後に山を控えた西面する大きな家で、北側に土蔵を有しています。棟札から享和3年(1803)に建てられたことがわかり、6つの座敷と平面の約4割を占める大きな土間を持ち、2階部分では養蚕をしていました。現在市川家をはじめ周辺地域で昔実際に使われていた道具類が展示されており、地元小学生の地域の歴史や産業の学習教材として活用されています。先日行われた身延町立下山小学生の地域学習の際に、一緒に見学させてもらいました。

市川家のご先祖は、戦国時代には裏山の高台にある烽火台の管理を任されていたと伝わっており、江戸時代には富士川舟運や対岸の身延町大野との渡船に関与していたと思われます。通常の東側の玄関のほかに、代官や賓客を迎え入れる式台が設けられた玄関があり、狆(ちん)くぐり付きの床の間や筬欄間(おさらんま)、棹縁(さおぶち)天井などを用いた格式の高い造りになっています。中でも特徴的なのは、群青色の土壁です。青色系の土壁は非常に珍しく、ほとんど使用された例がありません。古くは青色にはラピスラズリの鉱石が用いられていましたが入手が困難で非常に高価であるため、アズライトなど代替品が利用されていると思われます。ただ、どちらにしても非常に高価なものなので、造られた当時の市川家の経済力には驚かされます。

2月13日(金)
春に先駆けて咲く梅の花。庭木にもよく利用され、我が家の庭でも開花が始まっています。山梨県では甲州小梅が昔から栽培されており、江戸後期の地誌『甲斐国志』には「一梅 数種アリ消梅(コウメ)ニ甲州梅ト呼ブ者極メテ小粒ニシテ味佳ナリ、、、」と名産品として記録されています。実はカリカリの梅に漬けられる場合が多く、子供の頃「梅はその日の難逃れ」だからと毎朝ショッパイ小梅を食べさせられていました。梅はもともと中国原産で、奈良時代に遣唐使によって日本に伝えられたとされています。最初は実が薬用や保存食として利用されるとともに、香り立つその美しい花が愛でられました。花見というと今では桜の花を思い浮かべることが多いのですが、平安時代のある時期までは、花と言えば梅の花のことでした。その人気ぶりを当時の『万葉集』の和歌に詠まれた数で見てみると、「梅」の110首に対して「桜」が43首だそうです。これが平安時代の『古今和歌集』ではその数の比率がまさに逆転して、二倍以上が桜花を歌ったものになっています。

博物館のエントランスにも三ヶ所、梅の花などが花瓶に飾られています。梅は紅梅と白梅がありますが、博物館では蝋梅(ロウバイ)の花が見事です。ロウバイも中国原産で、江戸時代のはじめに日本に伝来しました。中国では新春に香り高い花を咲かせる「梅」、「水仙」、「椿」と合わせて「雪中の四花」として尊ばれているそうです。蝋梅は梅の字が使われて花の形は梅に似ていますが、梅がバラ科なのに対してロウバイはロウバイ科で別種になります。蝋梅(ロウバイ)の名前は鈍いツヤのある花びらがロウソクや蜜蝋が由来であるという説や、陰暦の12月(蝋月)に咲く説などがあり定まっていないものの、その黄金色の輝きはまさに冬に香る黄金の宝石です。写真にはロウバイの実が写っています。実は中に種を包括する集合果で一見虫の冬眠する時の繭のようにも見え、どことなく違和感を感じるのは私だけでしょうか。
2月9日(月)
湯之奥金山博物館応援団AU会主催の「第14回金山遺跡・砂金研究フォーラム」が9日(土)に開催されました。雪が降り交通機関も乱れるあいにくのお天気でしたが、各地から応援団の皆様が駆けつけて発表してくれました。このフォーラムは、金山博物館を拠点にフィールドワークの経験や体験・疑問点などをテーマに、応援団のみなさんが企画・開催する研究発表会です。博物館の応援団のみなさんには、日頃より砂金採り大会のイベントをはじめとして当博物館の運営に大変なご協力をいただいておりますことを深く感謝申し上げます。金山博物館のボランティア活動だけでなく、博物館を通して学習し、互いに研鑽しあい博物館を盛り上げていっていただいております。今回のフォーラムでは、全国各地の砂金採取の調査報告や金・銀山跡や鉱山資料の新たな視点での研究や活用の取り組みなど6名の方々からご披露・発表していただきました。
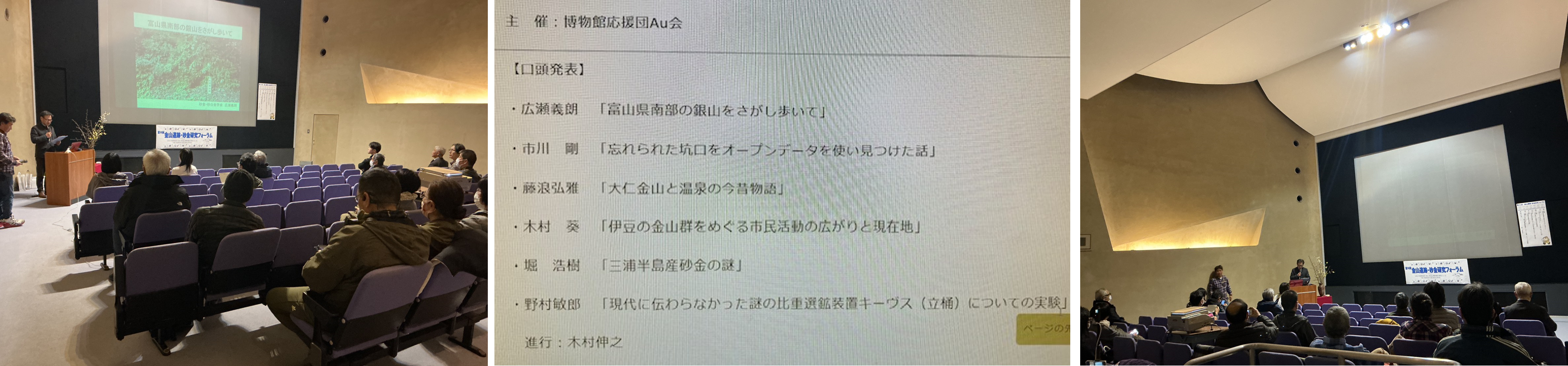 誰でも自由に利用できるオープンデータ(古絵図が掲載された古文献、赤色立体図、0.25mなどの数値標高データ地図など)を有効に活用して、伝承や古文書に残るだけのもしくは誰にも知られていない鉱山跡が新たに発見され、それぞれを現地調査する中で新たな鉱山史、鉱山技術史の解明につながっていくことが期待されます。
誰でも自由に利用できるオープンデータ(古絵図が掲載された古文献、赤色立体図、0.25mなどの数値標高データ地図など)を有効に活用して、伝承や古文書に残るだけのもしくは誰にも知られていない鉱山跡が新たに発見され、それぞれを現地調査する中で新たな鉱山史、鉱山技術史の解明につながっていくことが期待されます。
2月3日(火)
今日は節分です。節分とは読んで字の如し、季節を分ける日なのです。明日の立春の前日、冬から春へ季節が変わる節目の日です。季節には春夏秋冬の四季があるため本来4回の節分がありましたが、江戸時代まで春が1年の始まりとされたため、現在の大晦日のような意味を持って冬から春への節分が特に大切にされてきました。『下部町誌』(1981)には節分について「季節の変わり目にあたって陰と陽の対立により災いが生じるから、この邪気を祓う行事が必要であった。この日は長い竹竿の先の目かごまたは手すくいに、山からとってきたバリバリンの枝やヒイラギの枝にめざしを刺したものを添えて、軒より上に高く立てる。、、、中略、、、バリバリンを燃やしながら豆をホーロクで七回いる。いり豆は部屋ごとに「福は内、鬼は外、鬼の目ぶっつぶせ」と大声で叫びながらまく。節分は、今では家庭だけでなく多くの寺院や神社での催しとなり、年男による豆まきで鬼を追い払う行事として行われている。」と記述されています。バリバリンはモミソともいい、枝を燃すとバリバリと音がする榧(カヤ)や樅(モミ)のことを身延町では言っていたそうです。
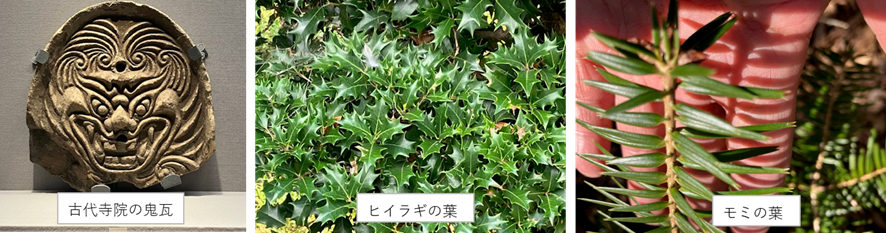
今ではこのような竹竿にかざしたモニュメントやヒイラギイワシはほとんど見ることができませんが、邪気や災厄を鬼に見立ててこの鬼を回避する呪術の一つでした。目籠や手すくいはこの家には物凄く目の数を持った動物が棲んでいるぞとの威嚇の表象であり、葉先の鋭いモミやヒイラギの葉によって鬼の目を刺し、鬼が嫌うめざしを焼いた独特のにおいを発生させることで鬼の侵入を防御する習俗なのです。節分に豆をまくのは、魔物の目をつぶす魔目(マメ)に由来し、鬼を追い払います。炒った豆を年齢の数プラス1個食べると、新しい年が無病息災で送れるとされていました。私もこの年になると、節分の豆だけで腹一杯の満腹になってしまいます。
1月24日(土)
身延町杉山にある珍しい石造物について、町内の知識人であるE氏とY氏に案内していただきその存在を確認してきました。杉山は御坂山地の西麓の栃代川流域に位置し、鎌倉時代には文書に見える地域で、本村(杉山)、和名場、栃代に大別されます。そのうちの本村集落の中ほど、村内の主要道沿いにありました。自然石の上部が平坦になっており、自然の亀裂に添うように4個の穴と2個の穴が2列並行に開けられています。穴はすり鉢(盃)状を呈しており、大きさは大きいもので直径約10センチあります。そのほか、開けかけの小穴も数個が上面にのみ見られます。一般的に六地蔵や道祖神、庚申塔などにつけられているものと同種のものと思われます。この盃状の穴は、誰が、いつ、何のために、どのようにして作ったのかは、確かな伝承に乏しくなぞに包まれています。つけられている石造物が信仰の対象物であるため、なにかの呪いのための呪術や、民間信仰や民間医療などと推測されていますが正確な所は学術的にわかっていません。身延町内でも何か所も確認されています。
 杉山集落の入口の路傍に、双体道祖神があるのも確認してきました。杉山本村の集落は、現在日蓮正宗の有妙寺が存在するのみで、一般の住宅はすべて集落外に出て居住している人はいなくなりました。本来であれば道祖神祭りがこの場所で挙行されていたはずですが、全くその痕跡はありませんでした。下部町誌には「起舟後光握手型双神像」「寛延四年未歳六月十四日」の記銘が報告されています。西暦では1751年にあたり、下部地区では最古の道祖神です。ちなみに前述の盃状の穴のある石造物で最古と言われているものが、山梨市堀内にある石祠型の道祖神とされています。
杉山集落の入口の路傍に、双体道祖神があるのも確認してきました。杉山本村の集落は、現在日蓮正宗の有妙寺が存在するのみで、一般の住宅はすべて集落外に出て居住している人はいなくなりました。本来であれば道祖神祭りがこの場所で挙行されていたはずですが、全くその痕跡はありませんでした。下部町誌には「起舟後光握手型双神像」「寛延四年未歳六月十四日」の記銘が報告されています。西暦では1751年にあたり、下部地区では最古の道祖神です。ちなみに前述の盃状の穴のある石造物で最古と言われているものが、山梨市堀内にある石祠型の道祖神とされています。

1月19日(月)
おととい第6回館長講座を開催しました。これまでは河内地域の歴史を、考古学、山岳信仰、牧と甲斐源氏、中世前半期の武士の時代をテーマとして甲斐国全体から見た視点で講座を開催してきました。今回は中世後半期の「穴山武田氏と信玄・勝頼・家康」と題して、甲斐国河内領を統治した穴山武田氏についてその進出からの興亡を概観してみました。穴山氏は甲斐源氏武田氏の庶流で、韮崎の穴山に所領を与えられてその地名から穴山氏を名乗ります。武田氏中興の祖と言われる武田信武の四男義武が、穴山氏の初代になります。武田信武は甲斐源氏第10代の当主で、室町時代に足利尊氏の近臣として活躍し尊氏の姪を妻としています。南北朝時代には尊氏とともに北朝方に属し、南朝方に与した甲斐源氏南部氏が奥州に移ったのを機に、その空白となったこの地域に進出したと考えられています。最初は南部氏の館に入り、信友時代になって下山に拠点を移します。養子縁組など武田宗家と深い関係を持っていましたが、一時期駿河今川家に帰属していたと考えられます。当時は武田宗家ともども、穴山一族は一時内乱状態にありました。穴山信友は武田信虎の娘南松院を正妻に迎えましたが、武田信玄が父信虎を駿河に追放したクーデターの時に協力した有力家臣の一人でした。息子信君には信玄の次女見性院が正妻となり、武田宗家とは非常に深い血縁関係が結ばれました。武田家臣団の中では親族衆の筆頭となり、肉親以外で武田氏を名乗ることが唯一許された家臣でした。名前も武田氏の通字(とおりじ)である信の字の使用が認められており、信君とその息子ともに信玄の幼名と同じ勝千代を使用しています。穴山氏は東海方面の外交をも担当しており、駿河今川氏・三河徳川氏・尾張織田氏とも緊密な関係を保持していました。

1月17日(土)
穴山梅雪は、一部のネット識者から「アナ雪」と呼ばれているらしいことを耳にしました。「アナヤマ梅雪(ばいせつ)」なので、「穴山」を訓じた「アナ」と「梅雪」の「雪」を合わせ、ディズニー映画の「アナと雪の女王」の略称に合わせた由来らしいのです。梅雪の諱(いみな)は信君(のぶただ)であり、かなり実名としては難読な名前です。

穴山氏は武田家の庶流であり、韮崎市穴山を本拠としていました。南北朝時代から河内谷の南部に拠点を移し、さらに南部町南部から身延町下山へ館を移転して城下町を整えています。穴山梅雪は武田信玄の姉を母に、娘を正妻に持つ血筋的に戦国大名武田家本家に非常に近しい家柄であります。家臣の中では武田家一門であり、対外的に武田姓を名乗ることが許された氏族です。信玄の亡き後勝頼とは意見が合わず、武田家を見限っています。地理的に駿河に接していることから今川家や徳川家とのつながりが強く、陶磁器や漆椀など調度品に高価な物品が残されています。領域内には湯之奥金山など初源期の山の岩石から直接金を採掘した金山が多く存在し、金山村を幾つも形成していました。武田氏を見限って織田・徳川軍に寝返った時、手土産に大判2,000枚を持参したといいます。大判2,000枚では重さが約333㎏となり、最近の高騰した価格に近い数字25,000円/gとして換算すると、おおよそ80億円以上にもなります。穴山氏が統治していた時代の穴山領(河内地域)における金の生産力には驚かされます。
1月12日(月)
博物館では、お正月入口に恒例となっている門松を立てました。松は生命力の強い常緑樹であり、歳神様(としがみさま)が降臨する依り代として平安時代にはすでに中国から伝わった風習とされています。博物館関係者の竹やぶから太い竹数本をいただいてきて、梅や松の枝、実の付いたナンテンの木などをそれぞれさらに調達してきて、職員で正月飾りの門松を作りました。竹は長さの異なる3本を1セットとし上面を斜めに削いでおり、土台は稲わらを下から七五三巻に荒縄で巻いています。松竹梅は古来より「歳寒三友」と呼ばれ、寒い中でも色褪せずめでたいものの象徴でした。松は長寿や不老不死、竹は地面にしっかりと根を張りまっすぐ早く伸びることに加え毎年次々とタケノコを生む子孫繁栄、梅は他の植物に先駆けて香りを放ちながら咲く生命力と気高さをそれぞれ表しています。南天は「難を転ずること」に由来する縁起の良い樹木です。門松はそれぞれ縁起の良いものが集められ、それぞれが持つ良いところの相乗効果が新年にもたらされることを願って立てられるものです。中でも竹が目立つのに門松の名称が用いられるのは、門松の原初形態は松の枝のみであったこと、まつが神様を祀る(まつる)の語源の一つであったからだそうです。ちなみに武田流門松は、竹の先端を削がずに寸胴の形に切った姿のものです。

1月5日(月)
山の仲間たちと今年の干支にちなんで、都留市の馬立山に初登山で登ってきました。富士急行線からのアクセスが良いため、禾生駅➡九鬼山➡馬立山➡田野倉駅のコースをとりました。馬立山(またてやま)の標高は797mと低山ながら、九鬼山からの稜線はかなり険しく、先日の降雪もあって結構滑りながらやや危険をはらむ道のりでした。途中の樹幹の切れた眺望が聞く場所では、雪を頂いた富士山がその雄姿を披露してくれました。天気は快晴で風もなく、心地の良い山行となりました。
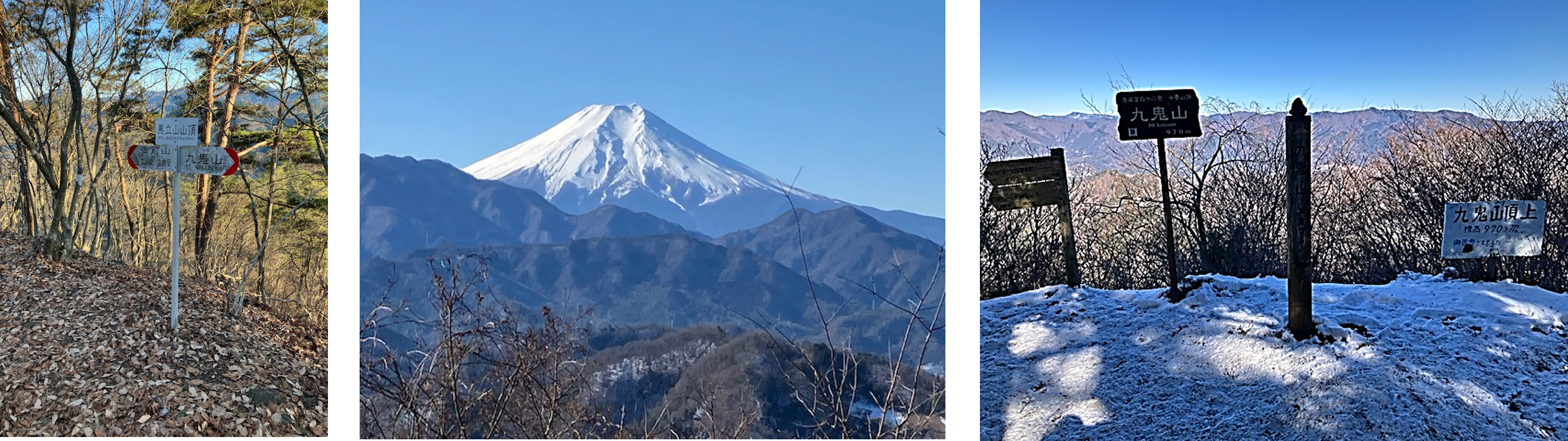
本日も身延町内でクマの目撃情報があり、クマのえさとなるブナの実の不作から、里への出没が相次いでいます。今回登山道沿いでもブナの実は確認できませんでしたが、ミズナラの実はものすごい量が落ちていました。本来はもう冬眠する時期なのですが、冬を越せるだけの十分な食料が確保できていないため、人里へ食料を求めて来ているようです。しかし、ミズナラのドングリの大量散布状況は、山のえさ不足というには疑問を感じます。クマもおいしいものを求めて、収穫されない柿や畑の野菜類の味を学習して覚えてしまったがために、行動範囲を広げているのでしょうか?地球温暖化も一部のクマが冬眠をしない遠因なのでしょう。登山道にはクマと思われる大きなフンが何か所かありましたが、これは調べてみるとタヌキの溜めフンのようで、黒い色をした果実の種子が多く含まれていました。また、緑色をしたヤママユガの天蚕繭が数か所で枯れ葉の中に確認できました。このヤママユガは天蚕ともよばれ、日本原産の野生蚕の一種でその繭糸は独特の淡い緑色をしており、光沢があって珍重されています。飼育が難しいのですが、隣の市川三郷町ではこの天蚕の飼育と製糸の生業が昔から営まれています。

1月3日(土)
陰陽五行説では、万物(宇宙)を構成する五つの構成要素「木火土金水」と「陰陽」の二元構造が干支の十干「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」に充てられています。これに動物がシンボルとなる十二支「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」が加わって60種類の干支を構成し、暦、方位、時間、性格などもそれぞれ割り当てられています。60年で一巡することから、60歳を還暦と言う由縁です。甲子園球場も大正13年(1924)年甲子(きのえね)の年に完成したことにその名は由来します。
丙午(ひのえうま)は火の兄(ひのえ)で、午も火の陽にあたります。太陽が真南に来る正午の時刻は、日差しが最も強まりますよね。丙午は、火の陽が重なる「比和」の年になり、力が増幅されて持っている特徴が顕著となりさらに強まることになるそうです。ひのえうまの年に生まれた人は気性が強い人が多く、特に女性がこの年に生まれると「亭主を食い殺してしまうなど災いをもたらす」という迷信がありました。この迷信は寛文6年(1666)生まれの八百屋お七という女性が、恋人に会いたい一心で放火事件を犯し、火刑になったことがそのもととなったとされています。寛文6年の干支が丙午であり、この事件のことを後の文学作品や歌舞伎で大きくとりあげられてきたことに由来します。
 山梨はかつて馬の名産地であり、甲斐駒として古くから知られていました。聖徳太子の甲斐の黒駒伝説や武田騎馬軍団は有名ですね。日本在来の馬は現代のサラブレットのように大きくはなく、木曽駒やポニー程度の大きさだったようです。甲斐駒ヶ岳は全国に18ある「駒ヶ岳」を冠する山の最高峰であり、ウマオイは博物館周辺のみかけたものです。
山梨はかつて馬の名産地であり、甲斐駒として古くから知られていました。聖徳太子の甲斐の黒駒伝説や武田騎馬軍団は有名ですね。日本在来の馬は現代のサラブレットのように大きくはなく、木曽駒やポニー程度の大きさだったようです。甲斐駒ヶ岳は全国に18ある「駒ヶ岳」を冠する山の最高峰であり、ウマオイは博物館周辺のみかけたものです。
1月2日(金)
新年明けましておめでとうございます。甲斐黄金村湯之奥金山博物館スタッフ一同、昨年同様今年も変わらぬご愛顧の程どうぞよろしくお願いいたします。
さて今年は午年ですね。十干では丙(ひのえ)、十二支では午(うま)の組み合わさった丙午(ひのえうま)の年です。陰陽五行では十干の丙は陽の火、十二支の午も陽の火で同じ運気が重なる「比和」となります。同じ気が重なると、その気は増幅してますます盛んになると信じられています。
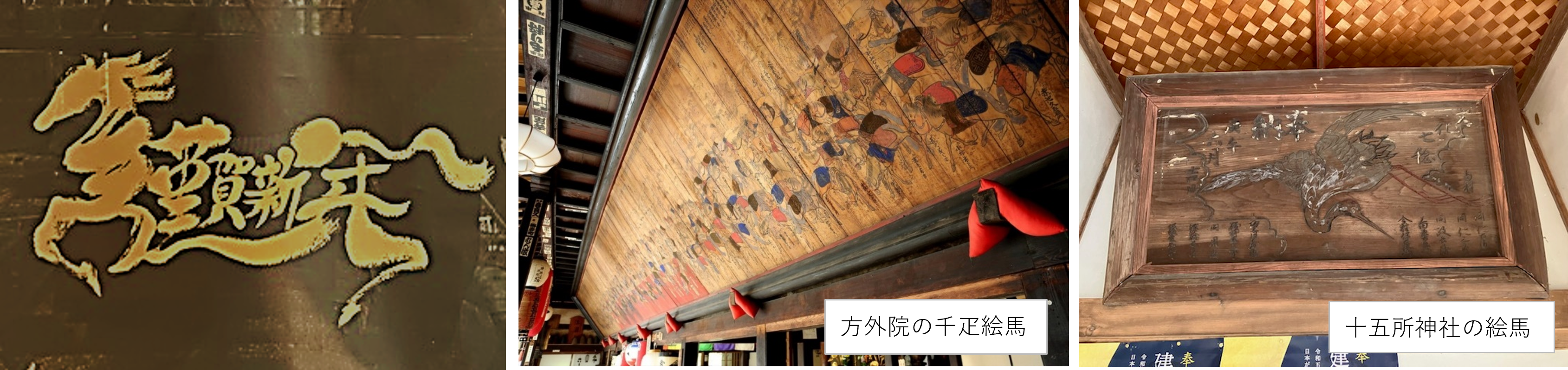 馬といえば身延町指定の方外院の「千疋馬の大額」があります。総桐材で造られた絵馬は、全長19.42m×2.24mあります。全国一と評されるその大きさには驚かされます。また町内久那土の十五所神社にも、鶴を描いた大きな絵馬が奉納されています。
馬といえば身延町指定の方外院の「千疋馬の大額」があります。総桐材で造られた絵馬は、全長19.42m×2.24mあります。全国一と評されるその大きさには驚かされます。また町内久那土の十五所神社にも、鶴を描いた大きな絵馬が奉納されています。
12月23日(火)
今年も黄金色の菊の花たちが博物館来館者を暖かく迎えてくれました。新年を迎えるにあたりこれらの鉢の菊が枯れてきたので、主幹を切り落として整理しました。花が終わった株の根元からは「冬至芽」と呼ばれる新芽がすでに出ており、来年の準備は万端のようです。今年株上げして並べた菊の株は、去年の菊の鉢から生じたこの「冬至芽」を畑に植え替えて養生して育てたもので、数はたくさんできましたが大きくて形の良い株はあまりできませんでした。黄色と赤色2色の菊があり、黄色のものは比較的強いのですが赤色の菊は除草作業で少し触れただけでもすぐに折れてしまい1鉢も鉢上げ迄には至りませんでした。そのため昨年度も株の提供をしていただいた山の仲間Aさんから、今年も菊の鉢を分けていただきました。ありがとうございます。20鉢以上も並べることができ、通路は賑やかで華やかになりました。

12月21日(日)
昨日20日(土)に茅小屋金山の現地調査に行ってきました。そぼ降る雨の中、総勢10人で前回の現地調査において完遂できなかった来年3月に実施する発掘調査の準備調査です。12月も後半だというのに雨が降ったりやんだりの天気ではあるものの気温は比較的暖かく、作業にはさほど影響はありませんでした。暖かいということはクマもまだ冬眠には入っていない可能性があり、爆竹や笛によって人がいることを示しクマの出没による恐怖に怯えながらの調査です。このあたり一帯はかつての金山調査において、クマが何回も目撃されているのでその方面の注意は怠れません。
 茅小屋金山のある入ノ沢は、かつての大雨によって土砂が流失してしまい大きく旧状を変えてしまっています。上流部の宮屋敷地点では、かつてここに存在していた石祠もろとも大きくえぐられて無くなってしまっています。現地の状況を確認する中で発掘調査の3地点を決定し、それぞれ過去に設定した基準杭から仮設の杭を設定しました。また、地形の計測と遺跡内に残っている旧道の位置を測定し、調査予定地で清掃が済んでいない地点の枯葉の除去を行いました。一方金山稼業当時に金が含まれていないとして捨てられた土石はユリカスと呼ばれ、斜面に廃棄されています。含まれている鉄分によって凝固している塊を、ハンマーや乳鉢によって粉状にして、水洗選別による砂金採取を行いました。微細な7粒の砂金粒子の発見があり、ユリカスの堆積物がかつての金鉱山廃棄物であることを確認できました。博物館に戻ってから調査情報を共有し、次回以降の調査までの準備と課題を確認しました。
茅小屋金山のある入ノ沢は、かつての大雨によって土砂が流失してしまい大きく旧状を変えてしまっています。上流部の宮屋敷地点では、かつてここに存在していた石祠もろとも大きくえぐられて無くなってしまっています。現地の状況を確認する中で発掘調査の3地点を決定し、それぞれ過去に設定した基準杭から仮設の杭を設定しました。また、地形の計測と遺跡内に残っている旧道の位置を測定し、調査予定地で清掃が済んでいない地点の枯葉の除去を行いました。一方金山稼業当時に金が含まれていないとして捨てられた土石はユリカスと呼ばれ、斜面に廃棄されています。含まれている鉄分によって凝固している塊を、ハンマーや乳鉢によって粉状にして、水洗選別による砂金採取を行いました。微細な7粒の砂金粒子の発見があり、ユリカスの堆積物がかつての金鉱山廃棄物であることを確認できました。博物館に戻ってから調査情報を共有し、次回以降の調査までの準備と課題を確認しました。
12月14日(日)
第5回シン・サンポを身延町帯金地区で開催しました。地域の歴史を見て歩くアウトドア版の館長講座です。あいにくの雨天でしたが、富士川東岸の東河内領の六組の一つ「帯金組」の史跡と文化財をめぐりました。塩身延線塩之沢駅に集合し、最初に金龍寺を見学しました。勝野上人より金龍寺のご由緒をお聞きし、寺宝の木喰上人作の「日蓮聖人像」をま近で拝観させていただきました。本町丸畑出身の木喰上人の作品中日蓮聖人像は、ただこの一体のみであります。千体仏造立の祈願を立てたのち、84歳の高齢ながら頭巾姿の日蓮聖人を穏やかなお姿に表現しています。木喰上人の作品は「微笑仏」ともいわれ、独特の微笑みを浮かべています。旧帯金小跡地からこの金龍寺がもと存在していた「日朝堂」を見学し、上小路組で管理している木喰仏の「薬師如来像」を拝観しました。木喰上人が83歳の高齢で日本を廻国して故郷の丸畑に帰る時、身延を経て帯金に滞在した寛政12年(1800)の作品で、これも日本千体仏の一つです。その後、帯金氏の菩提寺静仙院に行き、自然石の長い石段を迂回する道を通って十王堂の中の閻魔十王像や古い形式の石造物などの説明を聞きながら拝見しました。帯金地区は富士川に沿って南北に長い地区であるため、途中予定していた何地点かは位置だけお示しして省略させていただきました。旧帯金小跡地以降は、ほとんど小雨で傘もささずに散策することができました。普段は何気なく通り過ぎている集落について、地域の歴史探訪として再認識できたシン・サンポでした。
12月8日(月)
こまくさ山の会のみなさんが、中山金山を経由して毛無山への登山する山行に同行して金山の案内をしてきました。総勢22名の大所帯で、朝8時に湯之奥金山博物館に集合、9時に登山口を出発しました。天気は快晴で雲一つなく、心地良い登山となりました。中山金山では、精錬場跡、大名屋敷、七人塚などそれぞれの場所で、金山の操業時の様子や発掘調査で出土した遺物から見える当時の村の景観を説明しました。また、現地に残されている金山臼や墓石、金を取り出して廃棄されたユリカスが凝固したものを直接お示しすると、参加者のみなさんは戦国時代から江戸時代初期の盛んだった中山金山の村に思いを馳せていました。登山道から一歩足を金山村に踏み入れると、そこには500年前の金山村の生活があったのでした。中山金山から第2地藏峠の尾根に出ると、雪をうっすらとまとった富士山が顔を見せてくれていました。ここからは樹間に富士山を見ながら急登を登り、尾根の途中で昼食。ここからは、体力に自信がある山頂登頂組と帰路選択組に分かれて行動しました。当初計画より時間が押してしまいましたが、明るいうちに全員無事登山口に帰ってくることができました。
 ここの所の朝の寒さもだいぶ厳しくなってきているのにも関わらず、全国各地からクマがいまだに冬眠せず街中に出没し、人に突然襲い掛かり危害を加えたというニュースが流れてきています。真っ白い雪の中を黒いクマが歩き回ったり、雪かき中の人がクマに襲われた後の映像など、冬になってもクマに対して常に十分な警戒心を持っていなくてはいけないと感じさせられてしまいます。今回の山行も出発前や休憩した地点では、随時爆竹を鳴らしてクマに人間の存在をアピールしながら登山してきました。登山道にはクマの糞があったり、登山道わきの樹皮がはがされてクマの爪痕が残されていたり、この付近一帯を縄張りとするクマがいることは間違いありません。今回登山道を数分進んだ地点ではムササビが木のうろから出てきて、木をよじ登っている所を目撃したという幸運な会員もいらしたようです。
ここの所の朝の寒さもだいぶ厳しくなってきているのにも関わらず、全国各地からクマがいまだに冬眠せず街中に出没し、人に突然襲い掛かり危害を加えたというニュースが流れてきています。真っ白い雪の中を黒いクマが歩き回ったり、雪かき中の人がクマに襲われた後の映像など、冬になってもクマに対して常に十分な警戒心を持っていなくてはいけないと感じさせられてしまいます。今回の山行も出発前や休憩した地点では、随時爆竹を鳴らしてクマに人間の存在をアピールしながら登山してきました。登山道にはクマの糞があったり、登山道わきの樹皮がはがされてクマの爪痕が残されていたり、この付近一帯を縄張りとするクマがいることは間違いありません。今回登山道を数分進んだ地点ではムササビが木のうろから出てきて、木をよじ登っている所を目撃したという幸運な会員もいらしたようです。
12月4日(木)
深沢城は静岡県御殿場市深沢にある平城で、静岡県指定の史跡です。今川氏あるいは北条氏が築城したとされ、篭坂峠を越えて甲州へ通じる道の分岐点となる交通の要衝に位置しており、北条氏と武田信玄の攻城戦最前線でした。永禄12年(1569)の信玄駿河侵攻時には北条綱成が守衛しており、翌年の元亀元年12月には大軍を率いて深沢城に迫っています。元亀2年には当町湯之奥中山金山や甲州市黒川金山の金山衆を動員し、外郭を掘り崩して深沢城を攻略しました。この時に発給された古文書には、中山金山の「中山之金山衆十人」に対する褒美として「籾子(もみ)150俵」が与えられており、田辺、中村、古屋などの黒川の金山衆には恩賞として通行税をはじめとする諸税免除の特権が付与されています。当時中山金山には少なくとも十名の金山衆がおり、彼らの持つ土木技術が城攻めに利用されたことが明確にわかります。深沢城のほかにも、金山衆が参加し手柄をたてたという伝承を持つ城がいくつか見られ、「軍役衆」と同じような役割を果たしていたことがわかっています。
 武田方に属した城は駒井政直が入り、対北条氏に対する相模との国境の警護の任にあたっていました。城の普請(造成工事)が重ねられて、三日月堀や丸馬出などの施設を持った武田流の城に大改造されています。天正十年(1582)の武田氏滅亡の時には、その直前に当城の城兵たちは城を捨てて「自落」しています。以後再び北条氏が城とこの付近一帯の支配者となりましたが、織田信長が駿河一国を徳川家康に与えたために家臣の三宅安貞を置いて守らせ、天正十八年北条氏の滅亡により深沢城は廃城となってその役目を終えております。
武田方に属した城は駒井政直が入り、対北条氏に対する相模との国境の警護の任にあたっていました。城の普請(造成工事)が重ねられて、三日月堀や丸馬出などの施設を持った武田流の城に大改造されています。天正十年(1582)の武田氏滅亡の時には、その直前に当城の城兵たちは城を捨てて「自落」しています。以後再び北条氏が城とこの付近一帯の支配者となりましたが、織田信長が駿河一国を徳川家康に与えたために家臣の三宅安貞を置いて守らせ、天正十八年北条氏の滅亡により深沢城は廃城となってその役目を終えております。
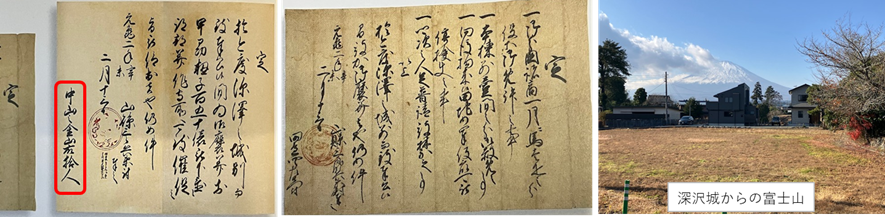
11月30日(土)
11月26・27日の両日茅小屋金山の現地調査を行いました。茅小屋金山遺跡等調査委員、博物館応援団Au会員、博物館職員等の構成で、初日17名、翌日7名で実施ししてきました。今回の調査目的は、過去の測量図と現状テラスとの照合、発掘調査候補地の枯葉除去と遺物の表面採集、鉱石の「ゆりかす」堆積層分布範囲確認、入ノ沢砂金確認調査などです。茅小屋金山は昭和の末年に調査に入り、平成20年代に測量図を作成していますが、平成20年代後半に大雨による川沿いのテラスが流失して大きく地形が変わってしまいました。打ち合わせをしながら、それぞれの班の成果を検討して慎重に確認していきました。

今年はクマが食料を求めて人里に頻繁に出没し、ニュースではこのところ毎日住宅街や街中への出没が取り上げられ、人的被害もでています。ここ身延町でもクマの多数の目撃情報があり、茅小屋金山の過去の調査でも何回か直接目撃されています。クマとばったりと遭遇しないために、ここ最近の金山の調査では登山道中で必ず爆竹を鳴らし、笛やラジオなど音を出して人がいることを動物に先に知らせるようにしています。もちろんクマ撃退スプレーも携帯しましたが、爆竹は金山現地調査の必需品です。
11月23日(日)
「みのぶ黄金の秋探訪会」が昨日開催されました。朝方は少し寒い位の空気感でしたが、歩き始めると風も無い晴天の中なので、後半には汗ばむくらいの快適な陽気の散策会となりました。金山博物館から歩き始め、波高島(はだかじま)トンネルを通り、富山(とみやま)橋で富士川を越えて、下山の集落に入り、上沢寺(じょうたくじ)へ。下山の集落は中世の下山氏、戦国時代の穴山氏の城下町で、下山氏館跡を中心に河内支配の中心地でした。上沢寺ではご住職からオハツキイチョウと日蓮聖人にまつわるお寺の由緒のお話を聞き、本国寺では文化財担当から下山氏の館と城下町や戦没者の忠魂碑について説明を受け、2本目のオハツキイチョウを見ました。イチョウにはギンナンの実がたくさんに実っており、樹の周りには葉っぱとともに銀杏の実が無数に落ちていました。臭いもなかなか強烈です。途中、同行していただいた町文化財審議会会長の石部氏から、石原裕次郎の湯治時代の下部温泉や身延線、富士川舟運や富士川架橋などのお話を聴けたのも、地域の歴史の造詣の深い地元の研究者ならではのお話でした。本国寺での昼食ののち、新しい身延中学校・下山小学校の脇を通って冨士川を渡りました。身延中学校の校章のデザインには身延町の鳥、ブッポウソウが取り入れられており、身延町のシンボルである天然記念物についてより関心を深めることができました。八木沢では学術上非常に珍しい雄株のオハツキイチョウを見学しました。合計13キロ散に及んだ散策のコースは、健康にはちょうどいい運動になったことと思います。参加者のみなさんは博物館に戻った後、館内の見学や砂金採りを体験して、秋の一日を十分に堪能したことと思います。
 3本のイチョウは共に国指定の天然記念物で、見事な黄金色の黄葉を堪能することができました。全国に7本ある国指定天然記念物のオハツキイチョウのうち、3本を見たことになります。オハツキイチョウは葉の上に種子が生ずる珍しいイチョウで、イチョウの変種です。八木沢のオハツキイチョウは雄株なので、さらに珍しく全国で唯一の国指定天然記念物です。イチョウは約2億年前から存在しており、いくつもの氷河期を乗り越えてきて生きた化石とも呼ばれています。雄株と雌株がそれぞれ別に存在しており、上沢寺や本国寺のように雌株には秋になるとたくさんの銀杏(ぎんなん)の実をつけ、八木沢のものは雄株なので葉に葯(花の雄しべの一部)をつけています。イチョウの木は非常に生命力が強く、上沢寺のオハツキイチョウは平成30年の台風で倒伏してしまったのですが、倒れたまま葉が茂っているのには驚かされました。
3本のイチョウは共に国指定の天然記念物で、見事な黄金色の黄葉を堪能することができました。全国に7本ある国指定天然記念物のオハツキイチョウのうち、3本を見たことになります。オハツキイチョウは葉の上に種子が生ずる珍しいイチョウで、イチョウの変種です。八木沢のオハツキイチョウは雄株なので、さらに珍しく全国で唯一の国指定天然記念物です。イチョウは約2億年前から存在しており、いくつもの氷河期を乗り越えてきて生きた化石とも呼ばれています。雄株と雌株がそれぞれ別に存在しており、上沢寺や本国寺のように雌株には秋になるとたくさんの銀杏(ぎんなん)の実をつけ、八木沢のものは雄株なので葉に葯(花の雄しべの一部)をつけています。イチョウの木は非常に生命力が強く、上沢寺のオハツキイチョウは平成30年の台風で倒伏してしまったのですが、倒れたまま葉が茂っているのには驚かされました。
11月15日(土)
金山博物館周辺でもやっと秋らしい季節になってきました。朝の最低気温は5度を下回るようになって霜も降り、肌寒さを感じます。昼の最高気温も10度台の快適な気温に落ち着いてきて、山々の紅葉もやっと錦秋といえるように色づいてきました。博物館からは、西の醍醐山はもとより北の五老峰も山頂に近い部分の茶色から中腹の黄色、麓の黄緑と紅葉のグラデーションがきれいに見ることができます。季節は今が秋本番です。日本の四季の中で、一番華やかな色合いを見せてくれます。

下部リバーサイドパークの駐車場にあるモミジの木も、半月ほどでしっかりした紅葉になってきています。10月30日の本ブログの写真と見比べてください。また、通路に並べた菊の鉢の花もかなり盛りになってきて、見事な黄金色を呈するようになってきました。しかし、シカさんが夜な夜な出没しているようで、菊の花や黄花コスモスの花を食べられた形跡が残されています。土の柔らかいところにはシカさんの足跡が明瞭に付けられており、おみやげにフンが残されていました。

11月11日(火)
東京の身延別院は、東京都中央区小伝馬町にあります。この場所一帯は江戸時代に伝馬町の牢屋敷跡だったところで、明治16年(1883)身延山久遠寺73世日薩上人が当院を創建し、日蓮聖人霊像を安置しました。身延別院のホームページによるとこの牢獄には、吉田松陰、橋本左内などの幕末の志士や、八百屋お七などの放火犯、盗賊など、あらゆる種類の未決囚の罪人が収容され、厳しい拷問や獄内の劣悪な環境などによって多くの人々が獄死し、江戸の人々に恐れられていた場所だったそうです。明治になって取り壊された牢屋の跡地は住む人もなく荒れ果てていたので、ここに法華の道場を建立し多くの獄死亡霊を供養するとともに理想の仏国土を建設しようとして開かれました。安置された日蓮聖人像は、もと身延山久遠寺の奥之院に安置されていた「願満高祖日蓮大菩薩御像」と称されていた御像で、江戸で行われた出開帳に度々請来されました。現在「木造日蓮聖人坐像」として、東京都の文化財に指定されています。私が訪問した11月3日は身延別院のお会式法要の日で、本堂前に回向柱が立てられていました。白い布が巻かれており、この布は日蓮聖人御像と結ばれています。この回向柱に触れることは、日蓮聖人の祖師像に触れることと同じことになります。善光寺の御開帳時の回向柱と同様の信仰形態です。

身延山からの江戸出開帳は、合計10回を数え「日蓮聖人祖師像」が身延山から深川の浄心寺まで運ばれました。江戸の出開帳の四天王の一つに数えられるほど有名なもので(本ブログ9月27日記事)もてはやされ、広い境内の中に仮設の建物が建設され人々が雲集して盛大に挙行されたと伝えられています。『武江年表』には「甲州身延山祖師開帳に付き、江戸到着の日、迎ひの人数品川より日本橋迄つづく。何町何講中と書きたる旗幟あまた立つる」とも書かれているそうです。江戸の出開帳は、境内のみならず周辺にも仮設店舗や見世物小屋などが出来、大変な賑わいを見せていたと言われています。

11月2日(日)
日本はかつて「黄金の国ジパング」として、マルコ・ポーロの『東方見聞録』に紹介されていました。マルコ・ポーロは元(モンゴル帝国)に10数年滞在し、ここで聞いた中尊寺金色堂などの伝聞をもとに、「ジパングは莫大な金を産出し、宮殿や民家は黄金でできている」と記述しています。13世紀のヨーロッパでは、黄金に満ちたユートピアとして我が国が認識されていたのです。この見聞録がやがて訪れる大航海時代のブームの原点となっているのです。
先月北海道において、金山再開発の記事がありました。外資系企業が閉山した金山を試掘し、採算に合うかどうかの検討をするための予備調査が何か所も行われているというのです。その理由として、最近の金相場の急な上昇があり、採掘技術が深化し、金を含む鉱石から金を抽出する技術の進歩など、かつての「黄金の国ジパング」の夢の復活を目指してとのことです。資源の発見や地域経済の活性化が求められる一方、鉱害や自然破壊への危惧が叫ばれています。道南圏の静狩金山跡では調査後に中止が決定されましたが、オホーツク圏の鴻之舞金山跡では1t当たり24.1グラムと高品位の鉱石が発見されています。日本で唯一商業規模の採掘がおこなわれている鹿児島県菱刈金山の平均品位(20g/1t)をも上回っているそうです。
11月1日(土)
甲府市右左口町の敬泉寺で木造十一面観音立像が33年ぶりに御開帳されました。甲府市教育委員会が敬泉寺や地元と協力し、私の地域・歴史探訪「甲府市寺宝特別公開」として、節目の御開帳に合わせて実施されたものです。本堂の東側にある観音堂に安置された秘仏の観音像であり、御開帳されるのは33年に一度以外は大きな自然災害や大凶作の時だけとあって早速行ってきました。地元の住民の方々や歴史愛好家がたくさん遠くからも参拝に訪れていました。御開帳には、寺社内の秘仏が期限を区切って境内で開帳する「居開帳」と江戸や京都など人口の多い地域に運んで公開する「出開帳」の二種があります。社寺が秘蔵する霊験あらたかな神仏を人々に礼拝させ、その神仏と結縁を目的とする宗教的行事を「開帳」というのですが、今回は「居開帳」の典型的なものです。全国でも年一、二度や数年に一度の御開帳はたくさんあるのですが、33年という長い間を経ての御開帳というのは大変珍しくあまり類例がありません。
 敬泉寺(きょうせんじ)の山号は迦葉山(かしょうさん)で、浄土宗の寺です。寺は中道往還沿いにありに迦葉坂、阿難坂や釈迦ガ岳など仏教にちなむ地名が残されています。本堂前には石臼がたくさん集積された石畳があり、鎌倉時代の木造阿弥陀如来立像も公開されていました。こちらの像は一部に截金文様がわずかに残り、胎内の阿弥陀経には正和4年(1315)と記されています。観音堂のある右左口宿は、徳川家康が甲斐入国の際に仮御殿を建てて滞在した所で、観音堂は家康来甲の折に府中を眺めた場所と伝える丘にあります。今回公開された観音像は、平安時代後期の作で桜材と思われる一木造、甲府市の指定文化財になっています。観音様のご尊顔を直接拝顔して、世界中の戦争がなくなり天下泰平になることとそれぞれの地域の平和安寧などを祈願してきました。
敬泉寺(きょうせんじ)の山号は迦葉山(かしょうさん)で、浄土宗の寺です。寺は中道往還沿いにありに迦葉坂、阿難坂や釈迦ガ岳など仏教にちなむ地名が残されています。本堂前には石臼がたくさん集積された石畳があり、鎌倉時代の木造阿弥陀如来立像も公開されていました。こちらの像は一部に截金文様がわずかに残り、胎内の阿弥陀経には正和4年(1315)と記されています。観音堂のある右左口宿は、徳川家康が甲斐入国の際に仮御殿を建てて滞在した所で、観音堂は家康来甲の折に府中を眺めた場所と伝える丘にあります。今回公開された観音像は、平安時代後期の作で桜材と思われる一木造、甲府市の指定文化財になっています。観音様のご尊顔を直接拝顔して、世界中の戦争がなくなり天下泰平になることとそれぞれの地域の平和安寧などを祈願してきました。
10月30日(木)
いよいよ秋の到来、秋本番といったところでしょうか。今朝は特に寒かったです。早朝畑に行くと白く霜が降りていました。車の社外温度は3℃の数値を指しており、日の出前はシーンと静まり返りこの静寂が寒さを一層身に染みて感じました。畑に残っている菊を鉢上げして博物館に飾るためですが、スコップを持つ手もかじかんでしまいます。今年の夏は暑くて猛暑日の記録を更新し、十月に入ってからでも身延町切石で真夏日を記録していますが、10月も下旬になってやっと最低気温が一桁になって秋らしい冷え込みになってきました。この冷え込みのため、博物館駐車場のモミジもやっと色づき始めました。このモミジの木には、たくさんの種が付いています。この種はプロペラ型をした特徴的な形をしています。風に乗ってくるくると回転しながら、遠くに舞い落ちるようになっています。子孫繁栄のための進化した形です。
 モミジはカエデ科カエデ属の植物です。モミジとカエデはどう違うのでしょうか。かつて史跡散策会の時、植物専門の先生からカエデの語源は「カエルの手」であり、「カエルテ」➡「カエルデ」➡「カエデ」と変化したんだと教えていただいておりました。モミジが赤く色づく切れ込みの深い葉に対して、カエデは切れ込みの浅いカナダの国旗にある葉のようなイメージがあります。赤ちゃんの手もモミジのような手とは言いますが、カエデのような手とは言わないですよね。ではモミジの語源はといいますと、紅花(べにばな)から紅や黄の染料を「揉みだす」様子から、動詞の「モミづ」が「モミツ」➡「モミジ」に変化したと考えられています(諸説あり)。でも植物学上からは「モミジ」という植物はないそうです。
モミジはカエデ科カエデ属の植物です。モミジとカエデはどう違うのでしょうか。かつて史跡散策会の時、植物専門の先生からカエデの語源は「カエルの手」であり、「カエルテ」➡「カエルデ」➡「カエデ」と変化したんだと教えていただいておりました。モミジが赤く色づく切れ込みの深い葉に対して、カエデは切れ込みの浅いカナダの国旗にある葉のようなイメージがあります。赤ちゃんの手もモミジのような手とは言いますが、カエデのような手とは言わないですよね。ではモミジの語源はといいますと、紅花(べにばな)から紅や黄の染料を「揉みだす」様子から、動詞の「モミづ」が「モミツ」➡「モミジ」に変化したと考えられています(諸説あり)。でも植物学上からは「モミジ」という植物はないそうです。
10月25日(土)
博物館周辺の植栽にジョロウグモの巣がいくつか作られています。ジョロウグモは比較的大きなクモで、黄色と黒色の縞模様があり腹部の内側は赤色を呈しています。漢字では女郎蜘蛛か上臈蜘蛛と表記されますが、名の由来の説によってこの二種があるそうです。毎年秋口になると、博物館構内の植木や建物に巣が作られます。山に隣接しているので餌となる虫の飛来が比較的多いためか、体長2センチほどのおなかの丸く張った個体もあります。夏から秋にかけて捕食用の網を張り、黄金色の糸が2メートル以上もある大きな巣もありました。オスとメスは体の大きさや色が異なり、大きなメスは鮮やかな黄色と黒の色をしており、体の小さいオスはメスの半分くらいの大きさで褐色の地味な色です。巣のつくりは「円網」と呼ばれる形状をしており、中心から放射状に延びた縦糸と、同心円状に張られた横糸から構成されています。横糸には粘液が付着しており、ここで獲物を捕らえます。ジョロウグモの巣は、主網の前後にバリアーと呼ばれる糸が張られており、三重構造になっていることが多いのだそうです。毒を持っているようですが人間にはほとんど害がないそうで、私は小学生のころジョロウグモのお尻から出された糸を手に巻き付けて遊んでいた記憶があります。糸は比較的頑丈で、黄金色に輝くことから「黄金グモ」とも呼ばれることもあるそうです。

10月20日(月)
鉢上げした博物館入口の菊の花が開花し始めました。友人からいただいたものと去年の鉢から畑に移植しなおしたものと合わせて40鉢以上になります。ほとんど黄金色に近い黄色のものですが、赤いものも数鉢あるようです。黄色の花は少し小さめの複弁の花で、赤のものは単弁の花のようです。まだ開花しているものは3鉢で、9割以上の鉢は蕾のままです。色の識別もできないくらい堅いつぼみのものもかなりあります。移植した土の状況によって、同じ時期にいただいた鉢から苗をとっていますが、80センチ前後のきれいな球形をしているものはわずかで、30センチくらいの小ぶりなものがほとんどです。

日本の国花というと、法律で定められているわけではありませんが、「桜」と「菊」が国民には一般的に認識されていると思います。「桜」は冬から暖かくなる春になると咲く美しい花で、自然の美しさやはかなさを象徴していると言えるでしょう。「桜」の開花は桜前線として、日本人が待ち焦がれていた春の到来を告げる花です。これに対して「菊」は中国が原産の植物であり、薬草として奈良時代に日本に渡来しました。「菊(キク)」の漢字と読み方とともに日本に伝わったので、音読みのみで訓読みはないのだそうです。「菊」というと天皇家の16弁の菊紋や、国会議員の議員バッチやパスポートの表紙でもおなじみの花なのですが、日本の訓読みが無いなんて意外や意外ですね。「菊」の花は生命力が強く、江戸時代には品種改良が盛んに行われて、様々な品種が生まれ現在まで親しまれています。
10月18日(土)
昨日、湯之奥金山遺跡等調査検討委員会を立ち上げ委員の先生方を委嘱させていただきました。この委員会に先立ち、委員の先生方と茅小屋金山の現地確認調査に行ってきました。茅小屋金山は林道から入ノ沢をさかのぼること約40分、湯之奥三金山の中では一番行きやすい金山です。しかし、一昨日の雨で滑りやすく道が崩落している箇所もあって歩行時間は短いものの、危険が伴う行程でした。現地はテラスの平場が連続しており、江戸初期の年号を持つ板碑型の石塔が2基現位置を保ったまま立っています。前回の現地調査同様に龍泉窯の青磁盤の破片が表面採集され、地下には中世にさかのぼる遺構や遺物が包蔵されている可能性が高いものと思われます。このほか選鉱して残ったズリやゆりかすの存在する範囲を特定することでテラスの使用状況の把握ができるという鉱山史の中西先生の指摘も、発掘調査を伴わない調査方法として活用していきたいところです。
 あまり人の入らない茅小屋金山跡には、シカの糞溜まりやスズメバチの巣の抜け殻なども存在していました。行く途中の斜面には鮮やかな紫紺のトリカブトの花が咲いており、枯木にはマスタケも秋を感じさせてくれます。今年はクマが里に下りてきて人間と遭遇する事例が特に多く、被害者や犠牲者迄も出ているというニュースや目撃映像がここのところ毎日報道されています。今頃は冬眠の準備の為食料をたくさん食べる時期ですが、今年はブナなどの木の実の不作が影響しているとのことで、身延町でもクマの目撃情報が度々町内放送されています。前回の茅小屋金山跡の現地調査に行くときにもクマが目撃されているため、爆竹を随所で鳴らしながら十分用心しての調査行きとなりました。林道脇にはクマの捕獲用の檻があり、クマらしき動物の糞もありました。まずは無事に帰還できてよかったです。午後は現地調査をもとに、調査検討委員会で調査の方向性と今後の計画について協議を行いました。
あまり人の入らない茅小屋金山跡には、シカの糞溜まりやスズメバチの巣の抜け殻なども存在していました。行く途中の斜面には鮮やかな紫紺のトリカブトの花が咲いており、枯木にはマスタケも秋を感じさせてくれます。今年はクマが里に下りてきて人間と遭遇する事例が特に多く、被害者や犠牲者迄も出ているというニュースや目撃映像がここのところ毎日報道されています。今頃は冬眠の準備の為食料をたくさん食べる時期ですが、今年はブナなどの木の実の不作が影響しているとのことで、身延町でもクマの目撃情報が度々町内放送されています。前回の茅小屋金山跡の現地調査に行くときにもクマが目撃されているため、爆竹を随所で鳴らしながら十分用心しての調査行きとなりました。林道脇にはクマの捕獲用の檻があり、クマらしき動物の糞もありました。まずは無事に帰還できてよかったです。午後は現地調査をもとに、調査検討委員会で調査の方向性と今後の計画について協議を行いました。

10月13日(月)
三連休の最終日です。一昨日激烈、おやこ金山探険隊と遺跡見学会を開催しました。集合時の天気は曇り。昼前から雨になる予報でしたが、途中で引き返してもいいという心つもりで決行しました。午前8時過ぎに博物館を出発し、30分ほどかけて登山口に到着。雲の中のような細かい霧雨が降る中、中山金山に向けて毛無山の登山道を歩き始めました。中山金山への道は険しい断崖絶壁の部分もある山道で、山に慣れている人でも細心の注意が必要な行程です。山の初心者の方や年配の方もいたので、いつもよりは少しゆっくり目に登りました。山は秋の気配が進み、紅葉も始まっていました。今年の秋は遅いとはいえ、登山道沿いの落ち葉も赤や黄色に色づいたものもあり、いろいろなキノコも生えてきていました。登山道はミミズを探すイノシシの掘った痕や、アナグマなどの小動物の掘った穴があり、夜間に展開された山中の動物行動の痕跡が随所に確認できました。また、漢方薬として有名なセンブリの花や山繭も道端にありました。
 中山金山に到着すると、まず早めの昼食をとって腹ごしらえをしました。雨の心配もあったので昼食の休憩時間を短くし、すぐに中山金山の内部を案内しました。広いテラスの精錬場と大名屋敷について当館職員が説明し埋りかけた坑道跡や新たに発見された鉱山臼などを確認して回り、七人塚の墓石の所では墓前にお線香を手向けました。足早に中山金山村の主要な部分を見学しました。予定より早めに下山を開始。登山道はヒノキやカラマツの植栽した樹林帯の中なので、降ってきている雨も思ったほど濡れませんでしたが、バスが待機している登山入口につく頃には雨脚も強くなっていました。全員無事下山することができました。
中山金山に到着すると、まず早めの昼食をとって腹ごしらえをしました。雨の心配もあったので昼食の休憩時間を短くし、すぐに中山金山の内部を案内しました。広いテラスの精錬場と大名屋敷について当館職員が説明し埋りかけた坑道跡や新たに発見された鉱山臼などを確認して回り、七人塚の墓石の所では墓前にお線香を手向けました。足早に中山金山村の主要な部分を見学しました。予定より早めに下山を開始。登山道はヒノキやカラマツの植栽した樹林帯の中なので、降ってきている雨も思ったほど濡れませんでしたが、バスが待機している登山入口につく頃には雨脚も強くなっていました。全員無事下山することができました。

10月9日(木)
博物館の入口に今年も菊の鉢を並べました。山の仲間から去年に引き続き菊の株をいただいたものと、去年の株から養生して育てた菊の株です。いただいた菊は今年苗の間にシカの食害に会ってしまい、いつもの年のように十分な出来ではなかったようです。私自身も昨年下部リバーサイド公園に植えた菊の苗を、何回もシカに食べられてしまって十分な大きさにならなかった経験がありました。今年はシカの食害を回避すべく、最初から去年の鉢の株から生じた冬至芽を養生して育てたのですが、すべていい形の株にはなりませんでした。自前の畑に植え替えた菊の株については整った良い形状になったものもありましたが、除草の時や鉢上げの時に枝が折れて形が崩れてしまい、半分以上は鉢上げして鑑賞に堪えうる出来栄えにはなりませんでした。博物館の入口に並べることができたものは、シカの食害や畑での枝欠損を回避できた幸運な菊になります。
 菊の節句というのがあります。五節句のうちの最後の節句です。1月7日が人日(じんじつ)の節句、3月3日が上巳(じょうし)の節句、5月5日が端午(たんご)の節句、7月7日が七夕(しちせき)の節句、9月9日が重陽(ちょうよう)の節句です。それぞれ別な呼び方があり、1月7日は七草の節句、3月3日は桃の節句、5月5日は菖蒲の節句、7月7日は笹の節句、9月9日が菊の節句になります。節句というのは季節の節目や変わり目といった意味があり、節目節目に応じて神様に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈り、神様にお供え物をしたり邪気を祓ったりしました。もともとは中国に起源をもつもので、奈良時代には日本に伝わっていました。旧暦の9月9日は、2025年の場合新暦に直すと10月29日にあたります。1か月以上の開きがありますが、この時期は菊の花が最も美しく映えます。菊の生命力にあやかり、不老長寿や繁栄を願うために菊の花を飾り、また食したりしたようです。
菊の節句というのがあります。五節句のうちの最後の節句です。1月7日が人日(じんじつ)の節句、3月3日が上巳(じょうし)の節句、5月5日が端午(たんご)の節句、7月7日が七夕(しちせき)の節句、9月9日が重陽(ちょうよう)の節句です。それぞれ別な呼び方があり、1月7日は七草の節句、3月3日は桃の節句、5月5日は菖蒲の節句、7月7日は笹の節句、9月9日が菊の節句になります。節句というのは季節の節目や変わり目といった意味があり、節目節目に応じて神様に五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄などを祈り、神様にお供え物をしたり邪気を祓ったりしました。もともとは中国に起源をもつもので、奈良時代には日本に伝わっていました。旧暦の9月9日は、2025年の場合新暦に直すと10月29日にあたります。1か月以上の開きがありますが、この時期は菊の花が最も美しく映えます。菊の生命力にあやかり、不老長寿や繁栄を願うために菊の花を飾り、また食したりしたようです。
 今年は猛暑が長引き例年より遅れているようですが、黄金色の玉のような形の菊の花が一斉に開花するのが楽しみです。これから毎日少しずつ菊花の様子を観察していきたいと思います。
今年は猛暑が長引き例年より遅れているようですが、黄金色の玉のような形の菊の花が一斉に開花するのが楽しみです。これから毎日少しずつ菊花の様子を観察していきたいと思います。
9月27日(土)
大聖寺不動明王坐像は、ヒノキ材の一木造で両眼を見開き上歯で下唇を噛む恐ろしい憤怒の表情をしています。右手に剣を左手に羂索を持ち、弁髪を垂らす等身大の像です。丸みを帯びた顔つきやふくよかな体躯は、総体として古様な雰囲気を保っています。いかにも宮中伝来という高貴な由緒にふさわしく、気品に満ちた威厳と風格を備えています。

開帳には普段厨子などに入っていて秘仏とされている扉を開いて拝観できるようにする居開帳と、他の土地に運んで御開帳をする出開帳があります。この不動明王像は霊験あらたかな像として篤く信仰され、都合3回江戸に運ばれて出開帳を行ったという記録が残っています。元禄9年(1696)年王子の金輪寺、宝永8年(1711)両国回向院、安永7年(1778)大塚護国寺です。4回目として天保12年(1841)深川永代寺での出開帳が計画されましたが、何らかの事情で実現はしなかったようです。
出開帳は普段遠方にあって拝観の困難な地方の神仏を、江戸や大坂などをはじめとする人口の多い都市の寺院に運び、多くの信者に結縁を促す機会を創出するのが目的でした。しかしその実態は、寺社の経営のため御堂の再建などの募金活動として行われるのが一般的でした。江戸出開帳の四天王といわれたのは、下総成田山新勝寺の不動明王、京都嵯峨野の清凉寺釈迦如来、信濃善光寺の阿弥陀如来、甲斐身延山久遠寺の祖師(日蓮)像だそうです。宿寺としてその会場にあたったのは、両国の回向院が最多であり、日蓮祖師像は深川の浄心寺でのみ出開帳されていました。
9月22日(月)
平安時代末の承安元年(1171)、宮中において毎夜天空に七重の妖光が現れる怪異が続き、時の高倉天皇は病気になってしまった。誰もこれを退ける者もいなかったが、弓馬の道に秀でていた甲斐源氏の加賀美遠光は、宮中の警護に当たって強弓を打ち鳴らす蟇目鳴弦(ひきめめいげん)の術を用いて妖光を退散させることができた。遠光は病の癒えた天皇から、褒美として京都御所清涼殿に安置されていた不動明王像を賜った。帰国の途に就いた遠光は、富士川をさかのぼっていたところ、一行が身延町八日市場から切石の間を通過中、一天にわかにかき曇り天地暗黒となった。その時闇中に現れた童子が「これより南八町の所に新羅三郎義光の開基の寺あり、これ有縁の聖地なり、ここに安置すべし、我は不動明王の侍童なり」と告げて姿を消した。周辺を調べてみると八日市場に甲斐源氏の祖である新羅三郎義光開基の寺があったので、ここに堂宇を整備して不動明王を安置したのが今の大聖寺なのであります。暗くなった場所は「日下がり」、その一帯を「不動平」と呼ぶようになったとの地名の由来を今に伝えています。
9月16日(火)
三連休の初日13日(土)に、山梨県埋蔵文化財センターと甲府市の主催による令和7年度第1回文化財ウォーキング―目指せ!烽火台・山城マスター―「湯村山城跡」の講師を頼まれ案内をしてきました。今回のコースの湯村山一帯は、山頂の中世の城跡、湯村山古墳群、厄地蔵さんで有名な塩澤寺、湯村温泉など多彩な文化遺産、自然遺産のある変化のあるコースです。湯村山は甲府市の北山野道、山梨県の歴史文化公園、武田の杜など複数のハイキングコース整備が行われており、往復約1時間の手軽なウォーキングや軽登山が可能であり、毎日登られているかたがたが多くいる甲府市民憩いの山です。約30名の参加者と共に、緑が丘スポーツ公園を出発し、湯村山1号墳➡復元烽火台➡湯村山6号墳➡湯村山城跡➡大平1・2号墳➡塩沢寺➡万寿森古墳➡緑が丘スポーツ公園の順に巡ってきました。
湯村山城跡は、永正16年(1519)年躑躅が崎に居館を移した武田信玄の父信虎が、大永三年(1523)に築いた山城です。甲府盆地一帯を見渡すのに適した立地を活かして、監視や情報収集及び伝達といった役割を担い、緊急時に甲府城下への迅速な情報伝達を行うための烽火(のろし)台も設置されていました。城の遺構は、山頂部分に土塁や井戸跡、石積などが見られ、かつての面影が偲ばれます。雨も時折落ちてくるあいにくの空模様ではありましたが、盆地南部の山までも見通せる眺望は確認することはできました。晴れていれば富士山の雄姿が見えたのですが少し残念です。かつての発掘調査によって戦国時代の遺物に混じって平安時代の土師器や陶器が発見され、神奈備形の信仰の山としての祭祀が行われていた側面も併せ持っています。
 塩澤寺は弘法大師が開いたとされ、地元では厄地蔵さんの名で親しまれているお寺です。国指定重要文化財の地蔵堂やご本尊の山梨県指定の石造地蔵菩薩坐像、弥陀種子板碑、無縫塔など貴重な文化財の多い由緒あるお寺です。自然石に頭の部分が乗っている「たんきりまっちゃん」の名で親しまれているお地蔵さまは、痰や咳を治すユニークな顔立ちをしています。湯村温泉も弘法大師の開湯伝説があり、慶長検地帳では湯ノ嶋村とあります。湯村山城も「湯ノ嶋ノ山城」と記録にあり、村は山梨郡北山筋に属していました。現在の湯村地名に変わったのは、後陽成天皇第八皇子の良純法親王が当村に配流されたため、村名から島をとったのだといわれています。そのままでは湯ノ島村に流された島流しとなってしまうので、親王に配慮して村名をあえて変更したとされています。しかし、親王はこの村の寒風を嫌って下積翠寺村(甲府市)の興因寺に移り、さらに上野村(市川三郷町)の薬王寺に移られています。かつての流刑地は、離島に限らず京都や関係場所から遠く離れた地域が充てられていました。鎌倉時代の名僧蘭渓道隆やキリシタン大名の有馬晴信も甲斐国に流されてきており、甲斐も流刑地の一つでした。
塩澤寺は弘法大師が開いたとされ、地元では厄地蔵さんの名で親しまれているお寺です。国指定重要文化財の地蔵堂やご本尊の山梨県指定の石造地蔵菩薩坐像、弥陀種子板碑、無縫塔など貴重な文化財の多い由緒あるお寺です。自然石に頭の部分が乗っている「たんきりまっちゃん」の名で親しまれているお地蔵さまは、痰や咳を治すユニークな顔立ちをしています。湯村温泉も弘法大師の開湯伝説があり、慶長検地帳では湯ノ嶋村とあります。湯村山城も「湯ノ嶋ノ山城」と記録にあり、村は山梨郡北山筋に属していました。現在の湯村地名に変わったのは、後陽成天皇第八皇子の良純法親王が当村に配流されたため、村名から島をとったのだといわれています。そのままでは湯ノ島村に流された島流しとなってしまうので、親王に配慮して村名をあえて変更したとされています。しかし、親王はこの村の寒風を嫌って下積翠寺村(甲府市)の興因寺に移り、さらに上野村(市川三郷町)の薬王寺に移られています。かつての流刑地は、離島に限らず京都や関係場所から遠く離れた地域が充てられていました。鎌倉時代の名僧蘭渓道隆やキリシタン大名の有馬晴信も甲斐国に流されてきており、甲斐も流刑地の一つでした。
9月10日(木)
夏の花として百日紅(サルスベリ)があります。難読漢字として、よくクイズなどに出題される定番です。その木肌はツルツルしていて、サルさえも滑り落ちてしまうということからの命名だといわれています。また、漢字で書く「百日紅」はその字のごとく、百日間も長く赤い花を咲かせることが由来とのことです。実際には一度咲いた枝先から再度花芽が出てきて花をつけるため、花が次から次へと長く咲いているように見えるのです。病害虫に強く長い間花の開花期間を保つことから、庭木としてよく植えられています。
 我が家の庭にもこの百日紅があります。ご近所の庭を観察してみると、何軒もの家の庭木にこの百日紅が植えられていました。この木については、花が散った後に周辺に落下する花の量が多く、掃除が大変だという認識があり、あまりじっくりと花を観賞したことはありませんでした。さらに樹皮も暑い時期に剥がれ落ちて、庭の景観を損ねてくれる厄介者との認識でありました。花言葉は「雄弁」、「愛嬌」、「不用意」です。「雄弁」は花が途切れることなく長く鮮やかに咲き誇っていること、「愛嬌」は炎天下でも明るく華やかな花であること、「不用意」は木登り上手なサルさえも滑ってしまうという木肌の様子から来ているようです。
我が家の庭にもこの百日紅があります。ご近所の庭を観察してみると、何軒もの家の庭木にこの百日紅が植えられていました。この木については、花が散った後に周辺に落下する花の量が多く、掃除が大変だという認識があり、あまりじっくりと花を観賞したことはありませんでした。さらに樹皮も暑い時期に剥がれ落ちて、庭の景観を損ねてくれる厄介者との認識でありました。花言葉は「雄弁」、「愛嬌」、「不用意」です。「雄弁」は花が途切れることなく長く鮮やかに咲き誇っていること、「愛嬌」は炎天下でも明るく華やかな花であること、「不用意」は木登り上手なサルさえも滑ってしまうという木肌の様子から来ているようです。
よく見ると意外ときれいで可憐な花なんですね。頭上の高所に咲いていることからさして気にも留めていませんでした。今年の猛暑の影響で他の庭木が葉枯れをおこしたりして勢いがないのに対して、暑さにもめげず百日紅の樹勢は旺盛なようです。
9月7日(日)
5日に台風15号が襲来し、山梨県をはじめとする東日本でも久々に雨がまとまって降ってくれました。各地の干上がりかけたダムの貯水量も少しは回復するのではないでしょうか。ここ身延町は7月中旬から2ミリ以上の雨が降ることなく、田畑や山々も乾燥しきって農作物や草木に多大な影響が出てきはじめています。夏休み期間中のいつもの年では、昼過ぎに入道雲が湧いてきて限定的な夕立が降る毎日が当たり前だったのですが、これでやっとひと息がつける感じです。我家の家庭菜園においても、秋野菜の苗や種をこの慈雨によって植えることができるようになりました。
今日は二十四節気の白露です。先日の台風以後、朝は比較的涼しくなりました。甲府ではやっと熱帯夜から解放されるようになり、身延ではなんと朝の最低気温が19度台にまでなりました。白露とは露が降り、白く輝く頃の季節を言います。夜の気温がぐっと下がってくるようになり、空気中の水蒸気が冷やされて水滴となり、葉や花につくようになるのです。やっと雨が降って湿度も上昇し、朝露が見られるようになってきました。白露は、俳句の季語としてもよく使われます。

「白露」といえば甲斐の俳人飯田蛇笏の系譜をひく俳句誌『白露』がありました。主宰していた広瀬直人氏は元高校の国語教師で、実直なお人柄と熱心な授業をされていたことを記憶しております。また、関連して「黒露」という甲斐に関係する人物がおりました。山口黒露です。黒露は江戸時代中期の俳人で、山口素堂の門人として甲府に住んで甲州俳諧の指導を行っています。ちなみに素堂は芭蕉の文人仲間であり、一説には甲斐の出身ともいわれ「目には青葉山ほととぎす初鰹」の句で有名です。
9月1日(月)
今日から9月です。あっという間に8か月間が過ぎてしまいました。最近特に感じることは、1年が早い、1か月が早い、1週間が早い、1日が早いということです。それなのに登山での山頂までの登りは、やたらと長く時間がたつのが遅く感じられます。同じ時間であっても楽しいことは時間がたつのが短く感じられ、つらく苦しいことに対しては長く感じられるのはなぜでしょう。年齢を重ねるにつれて時間がより早く感じられるという心理現象(ジャネーの法則)だけでは説明がつきません。
 9月なのに、9月になったのに、まだまだ極端に暑いですね。暦の上ではとっくに秋なのに、今年は猛暑日がまだまだ連日続いています。暑いので高山に行って涼みたいのですが、高山に行くには少し苦しい登りを体験しなくてはなりません。でも山の空気はすがすがしく、下界とはうって変わって気持ちの良いものです。今夏は猛暑のこともあって、乗鞍岳、北岳、唐松岳、天狗岳等々と、できるだけ高い山を目指して涼んできました。やっぱ、山は良いですよね。今年の夏は暑いだけでなく、雨があまり降りません。いつもなら頻繁に来るはずの夕立が、ほとんど見られません。熱風だけは強く吹いてくるので、樹木の葉や実が焼けてしまって変色したり、枝から落ちてしまったりしています。そのため庭の植木や公園の植栽した樹木の葉は、葉枯れを起こしていてみずみずしさがありません。樹木そのものが枯れてしまった木もあります。水田のイネや畑の農作物にも影響が出てきており、米や野菜の高騰が続いています。天候不順による気候変動、農業従事者の減少・高齢化、生産コストの上昇が複合的に作用して価格が上昇しているようです。でも一番の原因はここの所の猛暑と、一部の地域に偏った大雨の影響だと思われます。
9月なのに、9月になったのに、まだまだ極端に暑いですね。暦の上ではとっくに秋なのに、今年は猛暑日がまだまだ連日続いています。暑いので高山に行って涼みたいのですが、高山に行くには少し苦しい登りを体験しなくてはなりません。でも山の空気はすがすがしく、下界とはうって変わって気持ちの良いものです。今夏は猛暑のこともあって、乗鞍岳、北岳、唐松岳、天狗岳等々と、できるだけ高い山を目指して涼んできました。やっぱ、山は良いですよね。今年の夏は暑いだけでなく、雨があまり降りません。いつもなら頻繁に来るはずの夕立が、ほとんど見られません。熱風だけは強く吹いてくるので、樹木の葉や実が焼けてしまって変色したり、枝から落ちてしまったりしています。そのため庭の植木や公園の植栽した樹木の葉は、葉枯れを起こしていてみずみずしさがありません。樹木そのものが枯れてしまった木もあります。水田のイネや畑の農作物にも影響が出てきており、米や野菜の高騰が続いています。天候不順による気候変動、農業従事者の減少・高齢化、生産コストの上昇が複合的に作用して価格が上昇しているようです。でも一番の原因はここの所の猛暑と、一部の地域に偏った大雨の影響だと思われます。
 暑さには植物だけでなく、動物や虫にも影響が出てきています。10センチはあろうという芋虫(セスジスズメ)は岩陰に移動し、消火栓から漏れた水を求めてアサギマダラや小鳥が構内に来ていますし、駐車場のコンクリートの水路には涼を求めてきたシマヘビを見つけました。やっぱり涼しいところがわかるのですね。早くこよみどおりの涼しい秋になって欲しいものです。
暑さには植物だけでなく、動物や虫にも影響が出てきています。10センチはあろうという芋虫(セスジスズメ)は岩陰に移動し、消火栓から漏れた水を求めてアサギマダラや小鳥が構内に来ていますし、駐車場のコンクリートの水路には涼を求めてきたシマヘビを見つけました。やっぱり涼しいところがわかるのですね。早くこよみどおりの涼しい秋になって欲しいものです。
8月25日(月)
午前中の涼しい時間帯を利用して、博物館の建物東北側の砂置き場と通路の除草を少しの間しました。メヒシバ、オオバコ、カタバミ、ドクダミなどの雑草が、いつの間にかあちこちから顔を出し繁茂しています。ほぼ1か月前、砂金掘り大会の前に草を除去してきれいにしたはずなのに、、、、。今年は猛暑日となる暑い日が連日続いており、購入してきた鉢植えのルピナスは早々と枯れてしまい、強いはずのマリーゴールドも勢いがありません。水遣りをしてもすぐに乾いてしまい、今年の強い直射日光は相変わらず弱い花木には容赦がありません。園芸種の花は環境の変化に対して弱いものが多いようです。それに対して自然に生えてくる雑草はやはり強いですね。好ましことではないのですが、厳しい環境下でもたくましく芽を出してきて成長を続けています。
 博物館に隣接している下部リバーサイドパークのヤマボウシの木も、この暑さには勝てないようです。半分ほどの木では、緑色の葉が枯れてきて周囲から変色し始めているだけでなく、実さえも枯れかけているものもあります。暑さと少雨のためか、ヤマボウシの実もまだ大きくなりきっていないのに赤くなり始めているものもあります。また、それぞれの木の幹を観察すると、表面の樹皮がめくれかけているものもあります。
博物館に隣接している下部リバーサイドパークのヤマボウシの木も、この暑さには勝てないようです。半分ほどの木では、緑色の葉が枯れてきて周囲から変色し始めているだけでなく、実さえも枯れかけているものもあります。暑さと少雨のためか、ヤマボウシの実もまだ大きくなりきっていないのに赤くなり始めているものもあります。また、それぞれの木の幹を観察すると、表面の樹皮がめくれかけているものもあります。
 博物館の外回りの状況を見て回った時に、いくつかの虫たちに遭遇しました。ミンミンゼミ、オオシオカラトンボ、ゴマダラカミキリ、アサマイチモンジ、カナブン、アシナガバチ、トノサマバッタ、赤とんぼなどです。さすがに山に接しているせいか、短時間ながら種類は多く確認することができました。セミの声は今年の暑さのせいか、いつもより鳴いている個体数が少ない気がします。いつものお盆さん明けなら朝出勤時には、駐車場にミンミンゼミの死骸がたくさん見られるのに、今年はほとんど落ちていません。まだまだ暑い今年の夏です。
博物館の外回りの状況を見て回った時に、いくつかの虫たちに遭遇しました。ミンミンゼミ、オオシオカラトンボ、ゴマダラカミキリ、アサマイチモンジ、カナブン、アシナガバチ、トノサマバッタ、赤とんぼなどです。さすがに山に接しているせいか、短時間ながら種類は多く確認することができました。セミの声は今年の暑さのせいか、いつもより鳴いている個体数が少ない気がします。いつものお盆さん明けなら朝出勤時には、駐車場にミンミンゼミの死骸がたくさん見られるのに、今年はほとんど落ちていません。まだまだ暑い今年の夏です。
8月18日(月)
松本市の乗鞍岳登山口バスセンター近くに、大樋(おおび)銀山跡がありました。昨日乗鞍岳に登山した折バスの予約時間よりも早く到着したので、地図に大樋銀山跡の文字を見つけ早速現地に行ってみました。道路から鉱山に入る道は下草が繁茂し、わずかに道路の形状をとどめているだけでしたが、数分で坑口の埋もれたところらしき平坦地と窪地にたどり着きました。もとあった説明板と思われる板面は朽ち果ててなくなっており、柱のみが残っている状況です。ただし、周辺の石には新鮮な割れ口のものがあり、銀山跡の調査に来た鉱山愛好家が割ったものと思われます。この大樋鉱山は武田信玄によって発見されたと伝えられており、銀よりも鉛が主の鉱山であったようです。金がとれたとの伝承もあるようです。正保年間の国絵図では「此山先規より銀少々宛出る」とあり、『信府統記』では水野忠清・忠職の時代に繁盛して、諸国から金堀や商人が集まって町屋が形成されていたようです。その後次第に衰えて町屋もだんだん減じてすべてが退転し、江戸中期に再び採掘したが成果が上がらず、明治から昭和にかけても再採掘され、銅、鉛、マンガン、亜鉛などを産したとされています。
 同市鈴蘭の公園には、大樋銀山顕彰碑建立有志の会による大樋銀山についての石碑が2基存在し、かつての同地区の歴史を今に伝えています。木製の看板は十数年もたてば朽ちてしまいますが、石碑はほぼ永久に残ることに驚きました。10年前の写真は、2010.11.23「高原カフェ&バースプリングバンクの日記」から借用させていただきました。
同市鈴蘭の公園には、大樋銀山顕彰碑建立有志の会による大樋銀山についての石碑が2基存在し、かつての同地区の歴史を今に伝えています。木製の看板は十数年もたてば朽ちてしまいますが、石碑はほぼ永久に残ることに驚きました。10年前の写真は、2010.11.23「高原カフェ&バースプリングバンクの日記」から借用させていただきました。
8月14日(木)
お太呂祭(おでいろまつり)という祭りが、かつて身延町内のそれぞれの集落で行われていました。下部町・下部町教育委員会が発行した下部町の民俗調査報告書『わが町の民俗 そのルーツと心を探る』1994では、「お太呂祭……おでえろさま・おでえろ飾り・かざまつり・風神祭などといろいろに称ばれています。風神を祀り、台風の被害の少ないことを祈ってきました。川を挟んで注連縄を張り、両岸の木に縛ります。地区によって固有の場所や、方法がとられ、飾り方や祀りかたにも少しずつ特徴があるようです。」と16地区の概要が記載されています。また、『下部町のくちづたえ』1985にも7地区の記述があり、樋田地区では「●おでいろさま おでいろさまというのはお内裏さまからきており、ヤマトタケルの妻のオトタチバナヒメが相模湾を越すときに海神を慰めるために身を投げた日にあたると思われる。・・・中略・・・梵天という色紙(白・赤・青・黄などの五色の紙を重ねたもの。)を三つ下げてしめを作り、竹をまっすぐにさげる。昔はその竹之下をえぐり、麦で作った甘酒を入れて供えた。二百十日の大風を怖れて行った祭り。」と説明されています。『中富の民話』には大塩地区の「おでえろーばんば」が取り上げられており、7月に行われた風祭が村の入口が番場という地名なので、お出入り番場といわれたものが転訛したと、この不思議な名前の由来説が示されています。
 現在でも身延町岩欠の集落で実際に行われており、張られた縄を見ながら地元のIさんに現地でお話を聞きました。各家から稲藁を持ち寄り、小銭を集めて色紙を買い、村中総出で地区の公民館に集まって縄を綯い、紙垂を切って縄の中心部分につけ、栃代川を挟んで所沢の西から東屋敷まで数十メートルにわたって大注連縄を渡すのです。台風シーズンを前に、大風による民家や農作物への被害を防ぐため、昔からの伝統として行われてきているものだそうです。この「おでいろまつり」の伝統行事は、千葉などで行われている「道切り」とよく似ています。「道切り(辻切)」は、村に悪霊や疾病が入り込まないように、各集落の出入口にあたる村との境や四隅の辻を霊力で守るために縄を張る習俗です。注連縄によって集落を守るため、結界を張る点では同じです。違う点は、「道切り」が主に1月から2月の年頭に行って道に注連縄を渡して村に災厄が入り込まないようにとの習俗に対し、「おでいろまつり」が旧暦7月23日を中心に川に注連縄を渡し風害をよけることが主目的である点です。かつて多くの地区で行われていたこの行事も今ではほとんど行われなくなっており、その意味合いを知る人も少なくなってきていることは残念です。
現在でも身延町岩欠の集落で実際に行われており、張られた縄を見ながら地元のIさんに現地でお話を聞きました。各家から稲藁を持ち寄り、小銭を集めて色紙を買い、村中総出で地区の公民館に集まって縄を綯い、紙垂を切って縄の中心部分につけ、栃代川を挟んで所沢の西から東屋敷まで数十メートルにわたって大注連縄を渡すのです。台風シーズンを前に、大風による民家や農作物への被害を防ぐため、昔からの伝統として行われてきているものだそうです。この「おでいろまつり」の伝統行事は、千葉などで行われている「道切り」とよく似ています。「道切り(辻切)」は、村に悪霊や疾病が入り込まないように、各集落の出入口にあたる村との境や四隅の辻を霊力で守るために縄を張る習俗です。注連縄によって集落を守るため、結界を張る点では同じです。違う点は、「道切り」が主に1月から2月の年頭に行って道に注連縄を渡して村に災厄が入り込まないようにとの習俗に対し、「おでいろまつり」が旧暦7月23日を中心に川に注連縄を渡し風害をよけることが主目的である点です。かつて多くの地区で行われていたこの行事も今ではほとんど行われなくなっており、その意味合いを知る人も少なくなってきていることは残念です。
8月9日(土)
3連休の初日です。大手企業では今日から9連休とか一昨日から11連休とか言う所もあるそうで、夏休み(お盆休み)を長く取れるところはうらやましい限りです。その代わり今朝の通勤の時には、車の渋滞がなくスムーズに走れて快適でした。当金山博物館では毎年この時期に大変賑わうことになるので、14日(木)~17日(日)のお盆を中心とする期間中は開館時間を1時間延長しての営業となります。 みなさん、夕方の涼しくなってからの来館でも大丈夫ですよ。

今日も暑かったのですが昨日までの暑さとは違ってここ身延では、最高気温が29度と真夏日にはならない予報でありました。しかし、少し離れた甲府盆地の底の我家では、ここ連日暑い日が続いたため植栽した花が枯れたり樹木の葉が落ちたり色が変わったりもしています。我家の庭の植栽の木陰に置いた鉢植してあるロウバイ、ナギ、ツルウメモドキは、ほとんど毎日水をやっていましたがついに3鉢とも枯れてしまいました。2日のブログでも書きましたが、クマシデの葉や果穂、モクレンやシラカシの葉は、この夏の強い直射日光を受けて、葉焼けして葉が落ちたものも多くありました。今年の異常な暑さは、植物にとって致命傷になるくらいの猛暑でした。明日からは久々に、まとまった雨が少し続きそうです。お盆期間中は気温も下がって、立秋の暦どおりになるでしょうか。
8月7日(木)
5日に身延町下山の老人クラブ和楽翁会(わらおうかい)伝承部で「下山大工」についての講演会がありました。会場は「下山大工の家 石川庵」で、下山大工のルーツの地に建つ築およそ100年の古民家で行われました。
最初に会伝承部長の遠藤輝昭さんから、下山大工の初見資料の紹介と鎌倉・室町期の動静についてお話がありました。次に、下山大工の棟梁の家系でこの石川庵のオーナーで伝匠舎(株)石川工務所社長の石川重人さんから、-屈指の宮大工集団-「下山大工の技の継承 そして未来へ」と題して発表がありました。石川氏のプロフィールから、本籍はこの下山地で幼稚園までここで育ったということです。下山大工については、戦国期から江戸時代を通じてその活動内容についてのお話と、甲府城の修理、芝の白金御殿、駿府城の普請、甲斐善光寺金堂や山門の再建、金桜神社神楽殿、富士宮の大石寺三門など山梨県内外の多くの建築に携わっていることについてのお話がありました。ご先祖の石川七郎左衛門重甫が著した「匠家雛形増補初心伝」ほかは宮大工必読の書として身延町の文化財に指定されています。近年の文化財修理や再建は社寺建築だけでなく、擬洋風建築から住宅建築にいたるまで手広く扱われています。未来へ向けての取り組みとして、宮大工や全国的に不足している茅葺職人の育成についてその継承のため努力されていることも報告されました。下山甚句に歌われている「下山大工政五郎、御岳神楽殿、運四郎さん」のことについても紹介があり、遠藤さんの補足説明もありました。
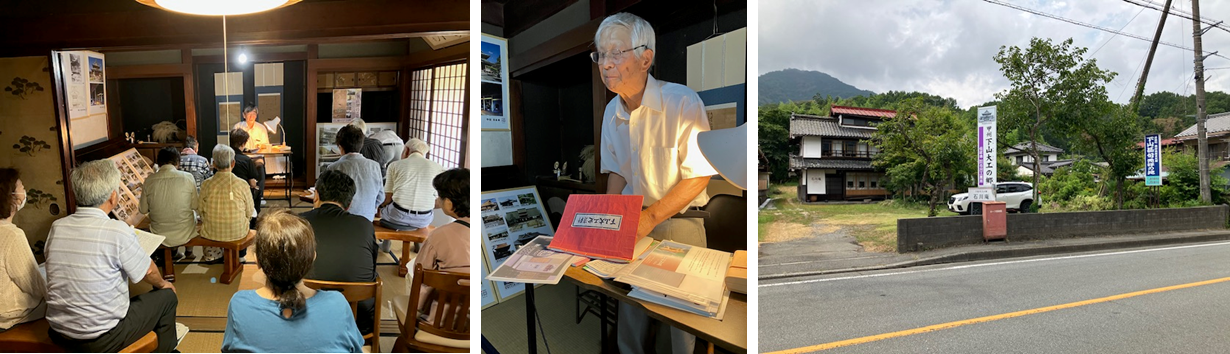 最後に私に感想を求められました。下山大工集団が、下山城下町における番匠小路としての地名に残るほどの職人集団であったこと、甲斐国内はもとより駿河や江戸までその名をはせていたことなどをお話ししました。石川工務所とのご縁は、甲府市の文化財を担当していた時に北口の藤村記念館(旧陸沢学校校舎)の移転修理や高室家住宅の修理などでお世話になりました。石川工務所とそのご先祖から今まで手掛けられたさまざまな仕事の内容と、下山大工の誇りと伝統を今に正しく受け継いでおられることに改めて驚きを感じたところでした。
最後に私に感想を求められました。下山大工集団が、下山城下町における番匠小路としての地名に残るほどの職人集団であったこと、甲斐国内はもとより駿河や江戸までその名をはせていたことなどをお話ししました。石川工務所とのご縁は、甲府市の文化財を担当していた時に北口の藤村記念館(旧陸沢学校校舎)の移転修理や高室家住宅の修理などでお世話になりました。石川工務所とそのご先祖から今まで手掛けられたさまざまな仕事の内容と、下山大工の誇りと伝統を今に正しく受け継いでおられることに改めて驚きを感じたところでした。
8月5日(火)
今朝、サトイモに花が咲いているのを確認しました。サトイモは毎年作るのですが、花を見つけたのは初めてです。サトイモが花をつけることは大変珍しいことらしく、日本各地のニュースや新聞で話題として取り上げられているくらいです。我家の今年の種イモは去年のイモを地中で越冬させたものではなく、園芸店から5月に購入して植えた石川早世と土垂です。このうちの土垂の3株に花がついていました。サトイモは縄文時代から栽培されており、原産地は東南アジア。山に自生している山芋(ヤマイモ)に対して、里で栽培されることから里芋(サトイモ)と呼ばれています。サトイモの花はとても珍しく、これまでサトイモ畑でも見たことがありませんでした。株の中央から明らかに葉とは違う、薄黄色のとがった円錐状の花のつぼみです。水芭蕉やザゼンソウと同じく、サトイモ科特有の形をしています。開花後の様子は、また後日に掲載します。

8月2日(土)
大暑の候、夏のこの時季は暑いに決まっています。今年は特に暑い日が多いんですね。今年の大暑は、7月22日の立夏の翌日から始まり、8月6日の立秋の前日まで続きます。二十四節気の一つで暑さが最も厳しくなる頃。江戸時代の暦の解説書『暦便覧』には「暑気いたりつまりたつゆえんなればなり」と記されています。夏の土用は、大暑の数日前から始まり大暑の期間中続きます。土用の丑の日には「う」の付く食べ物を食べるという習慣があります。「う」の付く食べ物として、瓜、梅干、うどんなどがありますが、夏バテしないように精の付くウナギを食べることが一般的になりました。この風習には、あのエレキテルで有名な平賀源内が関係しています。当時夏場にウナギはあまり売れなかったため、ウナギ屋の主人が源内に相談しました。源内は「本日丑の日」という看板を掲げることを提案し、これが大当たりしたということです。丑の日にウナギを食べると夏バテしないということが、世間一般にも流布するようになったのです。もっともこれには、昭和以降のうなぎ屋やスーパーの広告戦略も大きく寄与していることも事実です。今年の土用の丑の日は、7月19日と31日の2回ありました。みなさんウウナギを食べましたか。
 大暑の候、暑さによってこの金山博物館周辺でも、少し異変があります。猛暑の影響で広葉樹の葉に「葉焼け」が起きているのです。「山の木々が紅葉の季節でもないのに色づいているのが変だな」と、職員がつぶやいたことがこの気づきの発端です。我家の庭を見ても、クマシデ、モチノキなど常緑樹も含めて夏なのに落葉が目立ち掃除を頻繁にしていることを思い出しました。こんなに暑いのだから紅葉が始まったわけもなく、葉が夏の強い直射日光の影響で変色して乾燥し、最終的には枯れて落ちてしまっているのです。博物館構内や駐車場周辺では落葉広葉樹のケヤキ、ヤマボウシなどをはじめアジサイやモミジの類にもこの影響が確認できます。
大暑の候、暑さによってこの金山博物館周辺でも、少し異変があります。猛暑の影響で広葉樹の葉に「葉焼け」が起きているのです。「山の木々が紅葉の季節でもないのに色づいているのが変だな」と、職員がつぶやいたことがこの気づきの発端です。我家の庭を見ても、クマシデ、モチノキなど常緑樹も含めて夏なのに落葉が目立ち掃除を頻繁にしていることを思い出しました。こんなに暑いのだから紅葉が始まったわけもなく、葉が夏の強い直射日光の影響で変色して乾燥し、最終的には枯れて落ちてしまっているのです。博物館構内や駐車場周辺では落葉広葉樹のケヤキ、ヤマボウシなどをはじめアジサイやモミジの類にもこの影響が確認できます。
夏至は一年で日照時間が一番長い日です。しかし、夏の一番暑い時期はそれよりも約1か月以上遅れた大暑のこの時期になります。大地が温まるまでには時間がかかり、その地面を温めた熱が空気に伝わっていき、気温が最高域に達するまでのスピードがこの1か月強の期間なのです。寒いのも一緒です。冬至は日照時間が一年で一番短い日ですが、大寒はそれより約1か月強遅れてきます。大地が冷えきって空気に伝わり、実際の気温に反映されるにはタイムラグがあるのです。一日の気温の変化を見ても太陽が一番高くなるのは12時前後ですが、一番気温が暖かくなるのは13~14時ぐらいになりますよね。それと一緒で、季節の気温変化も一番太陽が高く長く出ている時期よりも少し遅れて最高気温が観測されるわけです。
7月27日(日)
今日は第22回砂金甲子園!東西中高交流砂金掘り大会を開催しました。現在日本各地域では、夏の甲子園野球大会の地区予選会が開催されており、各都道府県の代表校が決まってきています。今回の砂金甲子園では、各地から12校と最多の数の出場校となりました。去年の優勝校灘(兵庫)、準優勝の神戸女学院(兵庫)のほか桐朋学園(東京)、山梨学院(山梨)、大妻(東京)、麻布学園(東京)、市川学園(千葉)、逗子開成(神奈川)、海城学園(東京)、聖心女学院(東京)、城北中高校(東京)がエントリーしてくれました。砂金採りのスピードとテクニックを学校対抗で競う当館の砂金甲子園は、勉学への情熱を上回るものがあります。わが博物館が標榜する「砂金採りはスポーツだ」のとおり、日ごろの訓練や特訓が如実に成果に反映します。初参加の2校をはじめ、各校がその頂点を目指して集まった精鋭たちです。前半の団体戦は通常のパンニング皿による競技。後半の個人戦は先鋒、次鋒、中堅、副将、大将の5人が、試合直前になって決まるいろいろなパンニング皿での砂金選別です。砂の中に含まれている砂金の数は、合計50粒と確定しているのですが、それぞれのバケツの中の数は明かされていません。それぞれ一つも取りこぼすことなくすべて獲得できた場合にはボーナス点が加算され、1粒ロスするごとにペナルティで減点されます。そのほか失格や減点基準が、明確に定められています。団体戦の順位と個人戦の順位の合計点で総合順位が決定する仕組みです。各校とも集中して勢いのある熱戦とともに、甲子園野球大会に劣らぬ応援合戦が繰り広げられました。せっかく砂の中から金をたくさん揺り分けしたのに、最後の小瓶に収納するのに時間がかかってしまい、時間オーバーとなってしまった学生や金を周りに落としてしまった学生もいました。最後の最後まで、気の抜けない戦いです。
 今回は断トツで神戸女学院が優勝しました。準優勝は灘、3位は桐朋学園です。神戸女学院は、2年連続で灘に優勝を阻まれて来たため念願の優勝となりました。リベンジに燃える神戸女学院の日頃の特訓の成果が、ここに実を結んだ形となりました。おめでとうございます。
今回は断トツで神戸女学院が優勝しました。準優勝は灘、3位は桐朋学園です。神戸女学院は、2年連続で灘に優勝を阻まれて来たため念願の優勝となりました。リベンジに燃える神戸女学院の日頃の特訓の成果が、ここに実を結んだ形となりました。おめでとうございます。
7月26日(土)
今日も朝から夏の日差しが強く、とても暑かったですね。全国的な気温だけでなく、当博物館主催の砂金掘り大会についてもとても熱い戦いが繰り広げられました。今年で25回目を数える砂金掘り大会一般の部では、明日の砂金甲子園出場校の学生が今年も数多くエントリーしてくれました。一般部門とジュニア部門の頂上決戦では、逗子開成中学のK君が総合優勝しました。去年も神戸女学院の生徒が優勝し、近年学生の力の伸長が顕著です。学生さんは一般の方々とは違って、普段から短期集中型の訓練を積んできています。世界大会に準拠した時間制限のある当博物館の砂金掘り大会では、若者(中学生)の情熱が一般部門のテクニックに勝利した形になったという所でしょうか。表彰式の後のお楽しみ抽選会では、私が栽培した野菜セットと売店で販売している博物館グッズを抽選で10名の方にプレゼントしました。中央の写真の蝶々は、スルースボックスの水が浸みた土に飛んできたものです。近づくとすぐに逃げてしまいました。
 今日と明日の大会では、博物館応援団AU会、博物館友の会、身延町役場及びボランティアの皆様のご協力があって、数か月前からの準備と今日の運営にあたっていただきました。篤く御礼申し上げます。
今日と明日の大会では、博物館応援団AU会、博物館友の会、身延町役場及びボランティアの皆様のご協力があって、数か月前からの準備と今日の運営にあたっていただきました。篤く御礼申し上げます。
7月24日(木)
昨日は夏の甲子園大会山梨県予選の決勝戦でした。第1シードの山梨学院高校対前回王者日本航空高校、4対3の逆転で山梨学院が勝利し春夏連続出場となりました。高校球児の熱い戦いは、その一生懸命さが人の心を打つんですね。若人の一途なエネルギーは、テレビ中継からでもひしひしと観る人を魅了してくれます。わが金山博物館でも、明後日に砂金掘り大会、明々後日に砂金甲子園大会が開催されます。中高生をはじめ参加者のひたむきでがむしゃらなパンニングを、また間近に見ることができると思うととても楽しみです。今日も博物館応援団AU会、砂金掘り友の会のみなさんが暑い中、大会の準備に来てくれました。この場を借りてお礼申し上げます。
 さて、今朝の出勤途中に竹の花が咲いているのを見つけました。先月6日の神奈山のネマガリタケの笹の花の記事に続いて、中央市玉穂町の道路端でも再び見つけました。竹藪は小規模で小ぶりな竹ではありますが、ほとんどに花が咲いています。竹の花は非常に珍しく、60年から120年に一度しか咲かないので見たくてもなかなか見ることができません。2か月連続とはなんて幸運と思いきや、竹の花が咲くと不吉だと一般には言われています。それまで緑だった竹藪が咲いた後には全体が枯れてしまうので、不吉に見えたのは納得がいく解釈ではないでしょうか。かつては、地震や疫病の前触れなど悪いとが起きる前兆とされてきました。一斉に枯れるのは竹林全体が地下茎でつながっているからです。しかし、花の周期が長いので詳しいことはよくわかっていないようです。竹の花言葉は、「節度」、「節操のある」です。竹には節があることからの由来だそうです。竹は我々にとって身近な植物ですが、意外とよくわかっていないんですね。
さて、今朝の出勤途中に竹の花が咲いているのを見つけました。先月6日の神奈山のネマガリタケの笹の花の記事に続いて、中央市玉穂町の道路端でも再び見つけました。竹藪は小規模で小ぶりな竹ではありますが、ほとんどに花が咲いています。竹の花は非常に珍しく、60年から120年に一度しか咲かないので見たくてもなかなか見ることができません。2か月連続とはなんて幸運と思いきや、竹の花が咲くと不吉だと一般には言われています。それまで緑だった竹藪が咲いた後には全体が枯れてしまうので、不吉に見えたのは納得がいく解釈ではないでしょうか。かつては、地震や疫病の前触れなど悪いとが起きる前兆とされてきました。一斉に枯れるのは竹林全体が地下茎でつながっているからです。しかし、花の周期が長いので詳しいことはよくわかっていないようです。竹の花言葉は、「節度」、「節操のある」です。竹には節があることからの由来だそうです。竹は我々にとって身近な植物ですが、意外とよくわかっていないんですね。
7月21日(月)
今日は3連休の最終日、モーレツな暑い日が続いています。早いところではすでにこの連休から夏休みに入っている学校もあり、家族連れの来館者が多かったのも頷けます。梅雨も18日に明けたのですが、7月15日には大雨が降って当博物館でも雨漏りがありました。一度にたくさんの雨が降ったので、屋根上から処理しきれない排水があふれてしまったのです。東側の山からも雨水に伴って、土砂が裏側の通路部分にも流入してきてしまいました。この土砂の中に、たくさんのクルミの殻が混入していました。去年以前の実です。クルミは5月から6月にかけて開花し、その後に仮果と呼ばれる実をつけます。仮果の中に核果があり、その内側に食用となる仁があります。拾ったものは殻(核果)の堅い部分です。目につくものを拾って、コンクリートの上に並べてみました。ほとんど核果の腹の部分に、両側から穴が開けられています。直径5ミリから1センチ大の、ネズミと思われる動物の食痕です。きれいに半裁されたものもあるので、こちらはリスの可能性もあります。しかし、リスの食痕の特徴である割れ口の上部のかじった痕跡は、はっきりと確認することはできません。自然による割れなのか、堅い殻をもつ鬼クルミと殻の比較的薄い姫グルミがあります。姫クルミには、ネズミの食痕を持つものはありません。中身の詰まったままと思われる重い完形のクルミも4個ありました。これらの一部を割ってみましたが、仁の部分は液状になっていました。7月6日の記事にあるように、核果から芽を出すにはよほど条件が整わないと難しいようです。
 土砂の流入した北側で枯葉の上に、鳥の巣が落ちていました。樹の上から、今回の風雨によって落とされてしまったものかもしれません。直径は約15センチ、下部は苔が主体で乾燥していますがまだ緑色をしています。この苔の中には、ビニールの紐の切れ端なども混入しています。上部の巣の内側は見事に円形になるように、シュロなどの線状の繊維質のもので構成されています。意外にしっかりしたつくりで、鳥がくちばしでこまめに運んでできたものとは驚きの産物です。
土砂の流入した北側で枯葉の上に、鳥の巣が落ちていました。樹の上から、今回の風雨によって落とされてしまったものかもしれません。直径は約15センチ、下部は苔が主体で乾燥していますがまだ緑色をしています。この苔の中には、ビニールの紐の切れ端なども混入しています。上部の巣の内側は見事に円形になるように、シュロなどの線状の繊維質のもので構成されています。意外にしっかりしたつくりで、鳥がくちばしでこまめに運んでできたものとは驚きの産物です。
7月14日(月)
昼休みに常葉川で、アユの集団を見ました。甲斐常葉駅前の橋の北側、流れの緩やかな比較的広くなった場所で、大きさ15~20センチの個体が数十匹、まとまって移動しながら泳いでいました。しばらくの間川岸から観察してみると、体をくねらせながらそれぞれ体当たりをし合っているようにも見えます。成長したアユは、縄張りを持つことで知られています。良いコケ類が生えている川底の石などを中心に、約1平方メートルぐらいを自分のテリトリー(縄張り)として守る行動をして、よそ者のアユが近づくと激しく追い払うという習性があります。このアユの縄張り意識を利用して、世の太公望は友釣りという独特の釣り方でアユを狙います。よそ者は自分のえさ場を荒らす外敵とみなし、体当たりをして追い払おうとします。おとりアユ(よそ者)を侵入させ、縄張りを持つアユを誘い出し、特別な仕掛けの針にかけるという釣り方です。ここ最近の休日ともなると、常葉川や下部川では太公望たちが、ほぼ等間隔で釣りをしている光景が見受けられます。私は友釣りをしないので、その醍醐味はわかりません。ちなみに「太公望」は、釣りをする人をさして言いますが、中国の故事に由来します。中国周時代の政治家呂尚は、釣りをしていた時に周王に見いだされ、まさに周の祖である太公が望んだ人物だということで「太公望」とも呼ばれるようになったことから、釣りをする人をこう言うようになったそうです。
 鮎といえば、南アルプス市に「鮎沢」の地名があります。地名の由来は、『甲斐国志』に「鮎ハ合ノ仮字ニテ又相沢ニ作ル、方言間(アヒダ)二通ズ、大井ノ郷・八田御牧ノ分界コノ辺リニ当ルベシ、故ニ間ト云フ乎」とあり、「あい沢」が「鮎沢」になったと言われています。名字としても「鮎沢」さんがあってこの地が発祥の一つともいわれています。小学校時代の恩師に「鮎沢」先生がおり、前の職場の大先輩にも「鮎沢」、「相沢」さんがおりました。
鮎といえば、南アルプス市に「鮎沢」の地名があります。地名の由来は、『甲斐国志』に「鮎ハ合ノ仮字ニテ又相沢ニ作ル、方言間(アヒダ)二通ズ、大井ノ郷・八田御牧ノ分界コノ辺リニ当ルベシ、故ニ間ト云フ乎」とあり、「あい沢」が「鮎沢」になったと言われています。名字としても「鮎沢」さんがあってこの地が発祥の一つともいわれています。小学校時代の恩師に「鮎沢」先生がおり、前の職場の大先輩にも「鮎沢」、「相沢」さんがおりました。
7月10日(木)
昨日7月9日、帝京大学と身延町は「連携・協力に関する協定」を締結しました。湯之奥金山遺跡の解明に関する連携研究及び連携事業を円滑に行うための体制強化を図ることを目的とした協定です。人的交流、連携研究の実施とその公開、連携事業の相互協力等に関し、身延町の歴史遺産に光を当て、広く社会に公開し、地域活性化が図られることを期待するものです。学校法人帝京大学 冲永佳史理事長と身延町 望月幹也町長が協定書に署名して、無事協定の締結となりました。
 身延町には日本でも山金採掘の先駆けとなった湯之奥金山があり、平成元年から3か年かけて湯之奥3金山の一つ中山金山を中心とした総合学術調査を実施し、帝京大学文化財研究所に大変なご尽力をいただきました。この結果をもとに、平成9年には山金採掘の初源的様相を示す金山として、甲斐金山遺跡/黒川金山・中山金山が国指定史跡に指定され、同じ年に「甲斐黄金村・湯之奥金山博物館」が金山遺跡や金山史のガイダンス館として開館しております。今回湯之奥3金山の茅小屋・内山2金山についても、より学術的な専門的調査・研究を深め正しい歴史価値を付加して湯之奥金山の全体像を明らかにするとともに、将来的には史跡「甲斐金山遺跡」の追加指定までもっていきたいと考えております。
身延町には日本でも山金採掘の先駆けとなった湯之奥金山があり、平成元年から3か年かけて湯之奥3金山の一つ中山金山を中心とした総合学術調査を実施し、帝京大学文化財研究所に大変なご尽力をいただきました。この結果をもとに、平成9年には山金採掘の初源的様相を示す金山として、甲斐金山遺跡/黒川金山・中山金山が国指定史跡に指定され、同じ年に「甲斐黄金村・湯之奥金山博物館」が金山遺跡や金山史のガイダンス館として開館しております。今回湯之奥3金山の茅小屋・内山2金山についても、より学術的な専門的調査・研究を深め正しい歴史価値を付加して湯之奥金山の全体像を明らかにするとともに、将来的には史跡「甲斐金山遺跡」の追加指定までもっていきたいと考えております。
7月7日(月)
先日の休みを利用して、キタダケソウの咲いている姿を見てきました。キタダケソウは、南アルプス北岳の固有種で環境省のレッドデータブックの絶滅危惧種Ⅱ類(VU)に該当します。近い将来絶滅のリスクが高い種で、生息地の範囲が非常に狭く、北岳の山頂付近でしか見られません。長年見たいと思い続けていたのですが、花の咲いている期間が梅雨の時期と重なってごくわずかな間で、天候の不順と相まって行く機会をなかなか作れませんでした。今年の梅雨明けはまだなのですが、晴れの日が続いていたため思い切って行ってきました。森林限界を超えハイマツ帯の間には、シナノキンバイ、ハクサンイチゲなどの群落があり、山頂付近の稜線付近にキタダケソウは咲いていました。世界中でここにしか生息しない花を、はじめて十分に堪能することができました。登っている最中は雨もパラついていましたが、稜線に出ると雲もほとんどなくなって、鳳凰三山、八ヶ岳、甲斐駒、仙丈、間ノ岳から農鳥もはっきり見えました。休憩も入れて往復10時間の登山は、若いころと違ってさすがに疲れました。
 山梨交通のバスは、運転手さんのほかに車掌さんが同乗していました。今朝のラジオでバスガイドさんは、絶滅危惧種だという話題で盛り上がっていました。春や秋の行楽シーズンではバスガイドさんも忙しいのですが、夏冬の閑散期は需要がほとんどないそうです。ましてこのところのバス代の高騰から、ガイドさんを断って金額を下げようとする傾向が多くなってきています。バス会社でもバスガイドさんを新規に雇わなくなってきて、その数は急激に減少しています。運転手さんがワンマンでバスとして運行することが多くなってきているということです。今回の山梨交通バスの車掌さんは、車中から見える山々や滝、旧道やトンネルなどの紹介のほか、この路線の歴史的変遷などもガイドしてくれました。キタダケソウとともに、絶滅危惧種となっているバスガイドさんでした。
山梨交通のバスは、運転手さんのほかに車掌さんが同乗していました。今朝のラジオでバスガイドさんは、絶滅危惧種だという話題で盛り上がっていました。春や秋の行楽シーズンではバスガイドさんも忙しいのですが、夏冬の閑散期は需要がほとんどないそうです。ましてこのところのバス代の高騰から、ガイドさんを断って金額を下げようとする傾向が多くなってきています。バス会社でもバスガイドさんを新規に雇わなくなってきて、その数は急激に減少しています。運転手さんがワンマンでバスとして運行することが多くなってきているということです。今回の山梨交通バスの車掌さんは、車中から見える山々や滝、旧道やトンネルなどの紹介のほか、この路線の歴史的変遷などもガイドしてくれました。キタダケソウとともに、絶滅危惧種となっているバスガイドさんでした。
7月6日(日)
今日も暑かったですね。身延でも35度を超え猛暑日となりました。この暑さの中ではありますが、外の駐車場山際の草取りをしました。雑草は強くすぐに繁茂してしまいます。シカも少しは食べてくれている痕跡はあるのですが、ヤギのようにきれいに食べつくしてはくれません。オダマキやスミレなどの植栽をしたものを除いて、ヒメジョオン、ハルジョオン、ツユクサ、メヒシバ、オオバコ、イノコヅチなどをせっせと除去しました。
 山際の石垣の中に、ヘビの抜け殻がありました。蛇の抜け殻は、開運につながるラッキーアイテムとされています。どちらかというと、ヘビは手足のない形状とその独特の進み方から、気持ち悪いと感じる人が多く、当博物館でもあまりその存在は歓迎されていません。当博物館の周辺には、当博物館の守り神である「アオダイショウ様」が時々姿を現わしてくれます。毎年思いもよらずに出没しては、我々をびっくりさせてくれます。この抜け殻はその「アオダイショウ様」の脱皮したものなのでしょう。環境にもよるのですが、2~3か月に1度脱皮をするそうです。蛇は脱皮して成長すること、大地の中で冬眠をして春に目覚めることから、死と再生、豊穣の象徴であり、幸運をもたらすと考えられています。縄文土器の装飾として、ヘビのモチーフが多用されるのも、古くからヘビの持つ神秘性が認識されていたものと思われます。ヘビは弁財天の使いとされており、ヘビの抜け殻は神が脱いだ洋服として、ご利益にあやかることができると考えられているようです。弁財天は財宝を司る神様です。ちなみに今年の干支は巳年です。金運を招きレアな縁起物とされることから、当金山博物館のますますの繁盛(来館者のアップ)を期待したいと思います。
山際の石垣の中に、ヘビの抜け殻がありました。蛇の抜け殻は、開運につながるラッキーアイテムとされています。どちらかというと、ヘビは手足のない形状とその独特の進み方から、気持ち悪いと感じる人が多く、当博物館でもあまりその存在は歓迎されていません。当博物館の周辺には、当博物館の守り神である「アオダイショウ様」が時々姿を現わしてくれます。毎年思いもよらずに出没しては、我々をびっくりさせてくれます。この抜け殻はその「アオダイショウ様」の脱皮したものなのでしょう。環境にもよるのですが、2~3か月に1度脱皮をするそうです。蛇は脱皮して成長すること、大地の中で冬眠をして春に目覚めることから、死と再生、豊穣の象徴であり、幸運をもたらすと考えられています。縄文土器の装飾として、ヘビのモチーフが多用されるのも、古くからヘビの持つ神秘性が認識されていたものと思われます。ヘビは弁財天の使いとされており、ヘビの抜け殻は神が脱いだ洋服として、ご利益にあやかることができると考えられているようです。弁財天は財宝を司る神様です。ちなみに今年の干支は巳年です。金運を招きレアな縁起物とされることから、当金山博物館のますますの繁盛(来館者のアップ)を期待したいと思います。
 草取りの草の中にクルミの発芽したものを2本発見しました。掘り上げてみると、地下にその種の元となるクルミの実がありました。クルミの堅い殻は、割れて地上部分の本体に数本の枝と葉がついており、下には根が伸びています。クルミは、リスやネズミが食料を確保するために分散貯食したものからの発芽と考えられます。その動物が確保していた場所を忘れてしまったため、芽が出てきたものです。(2025.5.10のブログ参照)
草取りの草の中にクルミの発芽したものを2本発見しました。掘り上げてみると、地下にその種の元となるクルミの実がありました。クルミの堅い殻は、割れて地上部分の本体に数本の枝と葉がついており、下には根が伸びています。クルミは、リスやネズミが食料を確保するために分散貯食したものからの発芽と考えられます。その動物が確保していた場所を忘れてしまったため、芽が出てきたものです。(2025.5.10のブログ参照)
7月3日(木)
「あっ」という間に令和7年も半分が過ぎてしまいました。夏越の大祓い、茅の輪くぐりの神事も、各所の神社で行われていました。関東甲信地方は6月10日に梅雨入りし梅雨明け宣言もまだなのですが、ここ身延町でも15日から連日30度以上の真夏日が続いています。このうち雨が降った3日間のみ夏日だったのですが35度以上の猛暑日もあり、既に本格的な夏の到来を思わせる陽気です。梅雨はどこに行ってしまったのでしょうか。

当金山博物館の夏7月の行事といえば、毎年恒例の砂金掘り大会と砂金甲子園があります。画像右は今年の大会チラシです。浮世絵を思い浮かべさせるようなデザインです。今大会もどんな熱戦が繰り広げられるか楽しみです。
この暑さのためか、重ねてきた年齢のためか、このごろ物事に関心や集中ができなくなってきました。受動的なテレビでさえ、ニュースやバラエティ、ドラマに魅力が感じられません。暑さによって睡眠が浅くなり熟睡できずに頭がぼおっとしているし、食欲もそれほどわいてきません。趣味への情熱もなんとなく薄れてきています。それなのに、時が過ぎる速度は相変わらず加速度がついて早くなってきています。トキメキ(感動)がなくなってきていることが、主な原因であることは確かなようです。(ジャネーの法則)
年を取ると楽しめなくなることもある一方で、年齢や経験を重ねてきたからこそ新しい楽しみを見つけることもできます。若いころとは違った視点で、時間をあまり気にせず人生を楽しむことができるのも、今だからこその特権なのではないでしょうか。それぞれの年代で、人生を楽しく生きましょう。
6月30日(月)
伊豆松崎町の伊那下神社には、大久保長安の奉納した鍍金の釣灯篭があります。伊那上神社にも同じものがありますが、伊那下社のみ公開されています。下社の宮司さんの特別なご配慮により、ガラスケースを開けて直接拝見させていただきました。形状は六角形、唐草模様の透かし彫りに上がり藤の定紋が鋳出されており、下方及び額庇に宝珠が刻まれ、柱は梨地に打ち出されています。柱部分には「奉寄進豆州松崎大明神」、「慶長十四年己酉十一月吉日」、「大久保石見守長安敬白」と記されています。西暦1609年に伊豆の松崎大明神に、伊豆の代官で金山奉行であった大久保長安が奉納したことがわかります。青銅板製の本体に金メッキがされています。当時我が国の金工技術の高かったことを物語り、その精巧さその優秀さが評価されて現在静岡県の指定文化財になっています。
 大久保長安は武田氏の家臣で、その能力を買われ猿楽師から蔵前衆として金山開発や税務を担当していたと言われています。武田氏滅亡後は徳川家康に認められ、有能な役人として武田氏の家臣時代に培ったその知識や技術力を、検地や鉱山開発、土木工事などにいかんなく発揮しました。その権力や諸大名との人脈から「天下の総代官」とも称された人物です。同じような釣灯篭は、武蔵御嶽神社(青梅市)、越後一宮の弥彦神社(弥彦村)にも奉納されています。伊豆の金山は、当時佐渡をもしのぐ産出量だったのがこの時期に衰え始めたので、金山の再興復活を祈願するために寄進したと伝えられています。
大久保長安は武田氏の家臣で、その能力を買われ猿楽師から蔵前衆として金山開発や税務を担当していたと言われています。武田氏滅亡後は徳川家康に認められ、有能な役人として武田氏の家臣時代に培ったその知識や技術力を、検地や鉱山開発、土木工事などにいかんなく発揮しました。その権力や諸大名との人脈から「天下の総代官」とも称された人物です。同じような釣灯篭は、武蔵御嶽神社(青梅市)、越後一宮の弥彦神社(弥彦村)にも奉納されています。伊豆の金山は、当時佐渡をもしのぐ産出量だったのがこの時期に衰え始めたので、金山の再興復活を祈願するために寄進したと伝えられています。
6月26日(木)
16世紀にヨーロッパ人によって、中南米のアメリカ大陸からヨーロッパ、さらにアジアにもたらされた渡来作物として、ジャガイモ、サツマイモ、カボチャ、トウモロコシ、トウガラシなどがあります。玉(唐)蜀黍、唐辛子はその名にあるように、当時外国からはいってくるものはすべて唐(中国)を経由して入ってきたので、唐の文字が入っています。ジャガイモの名前は、諸説ある中でジャガタライモから来ている説が有力です。インドネシアのジャカルタは昔ジャガタラとも呼ばれ、オランダ人によってこの地方から日本にもたらされたようです。カボチャが、カンボジアから来た野菜ということで名付けられたことに似ています。
ジャガイモは、馬鈴薯、二度芋、二作イモ、五升イモ、六月イモ、セイダイモ、清太夫イモ、仙台芋、甲州芋、江州芋、コーシ芋、弘法イモなどいろいろな呼び名があります。山梨県では清太夫イモ、セーダイモ、セーダユー、セーザイモ、セーダなどともよばれ、中井清太夫の功績がその名に残りました。清太夫は甲府代官時代、幕府の許可のもと飢饉対策の救荒食料としてジャガイモを九州から取り寄せて、最初に九一色郷で試作して成功し、後に領内に普及していったとされています。さらに全国へ広まっていった過程で、清太夫イモから仙台芋、甲州芋から江州芋、コウシュー芋からコーシ(孔子)芋やコーボー(弘法)芋、ゴウシュー(江州)芋からゴショー(五升)芋にそれぞれ変化していったという研究がされています。(大西拓一郎「渡来作物の方言と歴史-じゃがいも方言にみる弱い固有名詞の強い力-」)山梨県上野原地方で食べられている「せいだのたまじ」は、ジャガイモの小ぶりなものを味噌味で煮付けた郷土食です。
 中井清太夫は、甲斐の歴代代官の中でも善政を行い、領民から生き神様として祀られています。甲府城下町整備のために横沢町付近に強制移転させられた塩部村民(甲府市塩部)は、家と耕作地が遠くなったため復帰を嘆願していましたがなかなか聞き届けられませんでした。安永8年(1779)中井清太夫が甲府代官の時、帰村を許し無人になった塩部村を再興させています。村民はこの恩義に際し、清太夫をまつる生祠を建立しています。また、天明6年(1786)大塚村(市川三郷町)押出川の悪水路を改修した功によっても、生き神様として生祠が祀られています。岩窪(甲府市)の信玄公墓は、当時魔縁塚と呼ばれ人も寄り付かない祟りのある場所だったそうです。この迷信を打破するためここを掘り返したところ、炭や灰と石碑が発見されたので間違いなく信玄公を火葬した場所であると特定し、新しい墓碑を建立しています。甲斐国(山梨県)において、初めて目的意識を持った発掘調査の最初だと言えるでしょう。
中井清太夫は、甲斐の歴代代官の中でも善政を行い、領民から生き神様として祀られています。甲府城下町整備のために横沢町付近に強制移転させられた塩部村民(甲府市塩部)は、家と耕作地が遠くなったため復帰を嘆願していましたがなかなか聞き届けられませんでした。安永8年(1779)中井清太夫が甲府代官の時、帰村を許し無人になった塩部村を再興させています。村民はこの恩義に際し、清太夫をまつる生祠を建立しています。また、天明6年(1786)大塚村(市川三郷町)押出川の悪水路を改修した功によっても、生き神様として生祠が祀られています。岩窪(甲府市)の信玄公墓は、当時魔縁塚と呼ばれ人も寄り付かない祟りのある場所だったそうです。この迷信を打破するためここを掘り返したところ、炭や灰と石碑が発見されたので間違いなく信玄公を火葬した場所であると特定し、新しい墓碑を建立しています。甲斐国(山梨県)において、初めて目的意識を持った発掘調査の最初だと言えるでしょう。
6月24日(火)
20日に令和7年度第1回甲斐黄金村・湯之奥金山博物館運営委員会を開催しました。当委員会は、湯之奥金山遺跡の発掘調査によって明らかにされた資料をはじめ、日本における産金の歴史に係る資料を保存公開し、学術文化および観光の振興拠点施設として設置した、身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の運営について必要な事項を審議するために設置されたものです。委員会の開催に先立ち、教育長から10名の委員の委嘱をさせていただき、新たに帝京大学の櫛原先生が加わりました。遠方より多くの先生方にご参集いただき、次に用件が控えていた笹本先生のみリモートでのご参加となりました。
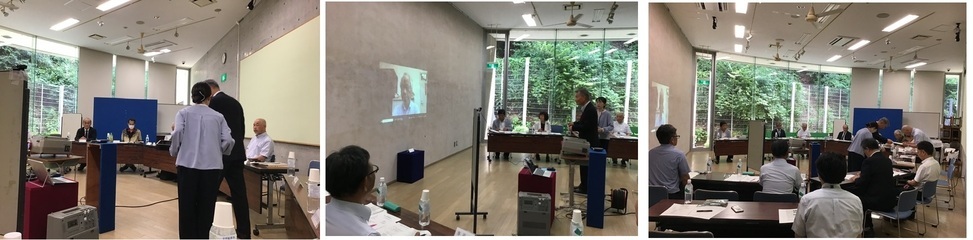
金山博物館は町の組織改編によって文化振興担当となり、文化財保護の職務も兼務になったことを報告しました。昨年度の事業報告では、開館以来歴代最多の有料入館者数となり、通算でも節目の50万人、51万人目を迎えたこと、令和7年1月に料金改定を行ったこと、料金改定後も来館者数の減少や券種選択の変化など変化が見られなかったこと、主催した事業、調査研究活動、教育普及活動、施設改修、黄金の足湯の閉鎖などを報告しました。今年度の年間事業計画では、新たに内山・茅小屋金山遺跡の追加調査計画について説明し、貴重なご意見とご提案をいただきました。すでに4月には文化庁中井調査官を県の担当職員とともに中山金山に案内し、金山遺跡の追加指定に向けて現地説明を実施しました。7月には帝京大学文化財研究所と調査活動に伴う協定を締結し、考古学や鉱山史の諸先生からご指導をいただく調査委員会を立ち上げ、数年かけての継続調査を実施する計画になっています。より詳細な現地測量調査は実施されているので、両金山の史跡指定に至るための詳細な現地での調査プラス既存調査情報の整理を行ってまいります。
6月22日(日)
朝、出勤前に妻の実家の常葉の畑に寄ってきました。収穫前のキャベツが、爆裂していました。まだ生育途中なのですが、10玉の内3玉が破裂してしまいました。キャベツが破裂する原因は、生育が急速に進むことによって引き起こされるようです。内側の生育と外側の生育とのアンバランスによるもので、内側の成長に外形が追い付かなかったためと考えられます。春先にはキャベツの値段が高騰し、スーパーでも1玉800円以上の値段に跳ね上がったこともあって、10連ポットの苗を買って植え付けていました。キャベツが大好物のモンシロチョウが飛び始めると、防虫ネットをかけたのですが隙間から入り込んで卵を産みつけられました。1株に10数匹の青虫がその生育を阻み、畑に行くたびに駆除してやっと大きくなってきたと思ったら、こんな結果が待っていました。梅雨に入って雨が続いていたものが、16日から続いた猛暑日によって急に気温が上がり、急激な成長となったようです。まだ大きくなるところですが、残りのキャベツが食べられるうちにとすべて収穫しました。小さいながらも博物館の職場の皆さんへのささやかなお土産となりました。
 本日第1回目の「みのぶ町民砂金掘り大会」を開催しました。これまで同じ町内に在住していながら、なんとなく湯之奥金山博物館に来館する機会を逃していた町民の皆様が意外と多いことが気がかりでした。当博物館に足を運んでもらう機会の創出と同時に、砂金掘りの楽しさを体験してもらい、家族や親戚ともども気軽に来館していただけるようにと企画したものです。やはり初めての方々もかなりの割合いたのですが、そこは競技ですから皆さん必死になって夢中で水中の砂と格闘していました。常設の茅小屋コースを会場に30分間の砂金掘り体験で、第1位はなんと10粒の砂金をゲットした小学生の女の子でした。結果発表と賞品授与のセレモニーの後、全員で採った砂金を水中に戻し、1分間競技砂金掘り競技を行って、記念撮影をしてイベントを終了しました。多くのみのぶ町民のみなさんに体験していただきました。どうもありがとうございました。
本日第1回目の「みのぶ町民砂金掘り大会」を開催しました。これまで同じ町内に在住していながら、なんとなく湯之奥金山博物館に来館する機会を逃していた町民の皆様が意外と多いことが気がかりでした。当博物館に足を運んでもらう機会の創出と同時に、砂金掘りの楽しさを体験してもらい、家族や親戚ともども気軽に来館していただけるようにと企画したものです。やはり初めての方々もかなりの割合いたのですが、そこは競技ですから皆さん必死になって夢中で水中の砂と格闘していました。常設の茅小屋コースを会場に30分間の砂金掘り体験で、第1位はなんと10粒の砂金をゲットした小学生の女の子でした。結果発表と賞品授与のセレモニーの後、全員で採った砂金を水中に戻し、1分間競技砂金掘り競技を行って、記念撮影をしてイベントを終了しました。多くのみのぶ町民のみなさんに体験していただきました。どうもありがとうございました。

6月20日(金)
3月の初旬に種芋を植え付けた男爵とキタアカリのジャガイモは、地上部の葉が黄色くなり始め、いよいよ収穫の時期になりました。梅雨の合間の晴れている日を見計らって一部、朝の涼しいうちに掘り上げました。今年作った品種は、男爵・キタアカリと○○です。二か所の畑に作付けましたが、種類の違いなのか畑との相性なのか、1株当たりの収量にかなりの違いが出てしまいました。キタアカリは個体も大きめの物が多く順調でしたが、男爵は例年並み、初めて植えてみた○○は植えた時期が少し遅かったためか株も他の品種に比べて大きくならず、植えた個数の割には収穫物の量はあまり多くはない印象です。キタアカリに多く見られたジャガイモの実は、収穫時にもまだ茎についているものもあり、鮮やかな緑色から白っぽい色に変色してきています。この実を半分に切ってみたとこころ、トマトの断面のように種がびっしり詰まっています。トマトのようなみずみずしさはなく、ジャガイモ同様の堅さがあって種の大きさは約2ミリです。近くでじっくり観察して見ると、ジャガイモの実はまるで熟す前のまだ緑色のミニトマトにそっくりです。
 ジャガイモは別名「馬鈴薯(バレイショ)」、「二度芋(ニドイモ)」、「清太芋(セイダイモ)」、「甲州芋」などとも言われます。馬鈴薯は馬の飾りにつける鈴の形に似ていることからの命名で、二度芋は春と夏の二度収穫できることからこの名があります。清太芋・甲州芋は、甲府代官中井清太夫にちなんだ名前です。
ジャガイモは別名「馬鈴薯(バレイショ)」、「二度芋(ニドイモ)」、「清太芋(セイダイモ)」、「甲州芋」などとも言われます。馬鈴薯は馬の飾りにつける鈴の形に似ていることからの命名で、二度芋は春と夏の二度収穫できることからこの名があります。清太芋・甲州芋は、甲府代官中井清太夫にちなんだ名前です。
6月15日(日)
梅雨に入り雨や曇りの日が続き、太陽の日差しが恋しい季節です。この時期にふさわしい花といえば紫陽花(アジサイ)ですね。博物館でも、建物の出口付近にある柏葉アジサイが白い花を咲かせています。アレッ、おかしいな。おととしは見事なアジサイがいろんなところで咲いていたのに、去年も少なかったけれどもそこそこ数株は見事に咲いていました。今年は全く花が咲いているのを見つけることができません。去年も花の数が少なくなってしまったと、剪定の時期や方法について書いた記憶があります。(2024.6.11ブログ参照)とくに今年は冬に博物館周辺の植栽された花木について、かなり大胆に剪定をしてもらい過ぎた感は否めません。柏葉アジサイのある部分は剪定がされなかったので、いつもどおりの花の咲き具合です。博物館に植栽されているアジサイの木を全て調べてみました。50本ほどあるふつうのアジサイやガクアジサイの中で、花のつぼみが確認できたのはたった2枝のみです。1株に数十本の枝がつきますから、その割合は1パーセントにも届きません。
 アジサイの花は2年目の枝に花芽をつけるため、今年に伸びた枝には花はつきません。去年から伸びている枝であっても、9月以降に剪定してから伸びた枝には花芽がつかないそうです。毎年花をつけるためには剪定をしないか、剪定するにしても花が終わってから9月までに枝を切る必要があります。適切な時期に適切な状態になるよう剪定をしなければ、花の咲く良好な状態を維持できません。自宅の庭にもアジサイが数株ありますが、カシワバアジサイは花が咲いており、普通のアジサイはかなり剪定してしまいましたが蕾と花がついていて咲き始めています。毎年花が開花する良い植栽の環境を維持していくためには、その植物の個性に合わせた対応をしなければなりません。
アジサイの花は2年目の枝に花芽をつけるため、今年に伸びた枝には花はつきません。去年から伸びている枝であっても、9月以降に剪定してから伸びた枝には花芽がつかないそうです。毎年花をつけるためには剪定をしないか、剪定するにしても花が終わってから9月までに枝を切る必要があります。適切な時期に適切な状態になるよう剪定をしなければ、花の咲く良好な状態を維持できません。自宅の庭にもアジサイが数株ありますが、カシワバアジサイは花が咲いており、普通のアジサイはかなり剪定してしまいましたが蕾と花がついていて咲き始めています。毎年花が開花する良い植栽の環境を維持していくためには、その植物の個性に合わせた対応をしなければなりません。

6月5日(木)
休日を利用して、新潟の神奈山に行ってきました。雪の多い豪雪地帯で、今年は特に雪が多いとのことです。シラネアオイやツバメオモト、ムラサキヤシロ、ショウジョウバカマなどの高山植物の花がとてもきれいに咲いていました。山頂の標高は1,909メートル、妙高山の外輪山にあたり、関温泉のスキー場からの登山コースを登りました。まだ登山道の日影の窪地部分には雪がかなり残っており、急登であること、雪解けでぬかるんでいることなどから結構ハードな山行になりました。
 樹林帯の下部にはネマガリタケが繁茂しており、「八方睨み」から先の9合目あたりの登山道わきの地点で、ネマガリタケの花のつぼみを発見しました。竹や笹の花は60年~120年に一度しか咲かないと言われ、つぼみでも花の姿が見られたのはラッキーでした。しかし、花が咲くときは大地震や疫病が流行り、不吉なことが起きる前触れだと言い伝えられていることが多いようです。花の咲くことが非常にまれであることや、咲いた後はその一帯の竹や笹が一斉に枯れてしまうことから、このように信じられてきたようです。日本は世界でも有数の地震多発地帯です。竹の花が咲いたときに疫病が流行ったり、大地震が発生したこともあったかもしれませんが、それは偶然の一致で因果関係はまったくありません。竹はイネ科の植物で、同行した山仲間から笹の実を救荒食として食べ、飢饉のときに助かったという話を聞きました。『精選版日本国語大辞典』では、「竹の実」の項で「メダケ、クマザサ、スズタケなどイネ科竹、笹(ささ)類の果実。小麦に似た長楕円形で、胚乳は澱粉質に富み、粉にして救荒食とするが味は悪い。自然秔(じねんご)。竹米(たけまい)。」とあります。救荒食としては、ヒガンバナの球根やトチの実など、毒消しやあく抜きに手間がかかるものが知られています。笹の実は花が咲いて初めて実をつけるので、一生出会わない人の方が多いかもしれません。救荒食としての伝承が伝わっているのは、竹の花の咲くこと自体珍しいのに、飢饉の年とが偶然一致した稀有な事例だから伝わったのでしょうか?
樹林帯の下部にはネマガリタケが繁茂しており、「八方睨み」から先の9合目あたりの登山道わきの地点で、ネマガリタケの花のつぼみを発見しました。竹や笹の花は60年~120年に一度しか咲かないと言われ、つぼみでも花の姿が見られたのはラッキーでした。しかし、花が咲くときは大地震や疫病が流行り、不吉なことが起きる前触れだと言い伝えられていることが多いようです。花の咲くことが非常にまれであることや、咲いた後はその一帯の竹や笹が一斉に枯れてしまうことから、このように信じられてきたようです。日本は世界でも有数の地震多発地帯です。竹の花が咲いたときに疫病が流行ったり、大地震が発生したこともあったかもしれませんが、それは偶然の一致で因果関係はまったくありません。竹はイネ科の植物で、同行した山仲間から笹の実を救荒食として食べ、飢饉のときに助かったという話を聞きました。『精選版日本国語大辞典』では、「竹の実」の項で「メダケ、クマザサ、スズタケなどイネ科竹、笹(ささ)類の果実。小麦に似た長楕円形で、胚乳は澱粉質に富み、粉にして救荒食とするが味は悪い。自然秔(じねんご)。竹米(たけまい)。」とあります。救荒食としては、ヒガンバナの球根やトチの実など、毒消しやあく抜きに手間がかかるものが知られています。笹の実は花が咲いて初めて実をつけるので、一生出会わない人の方が多いかもしれません。救荒食としての伝承が伝わっているのは、竹の花の咲くこと自体珍しいのに、飢饉の年とが偶然一致した稀有な事例だから伝わったのでしょうか?
6月1日(日)
今朝、畑のジャガイモに実がなっているのを確認しました。ジャガイモに実ってあまりピンときませんよね。いつもの年で実がなるのはせいぜい1つか2つくらいなのですが、今年のジャガイモでは2割くらいの割合で実がついていました。毎年ジャガイモを育てていますが、そもそもジャガイモに実がなるのは珍しいことです。5月初旬から中旬にジャガイモに白または薄紫の花が咲くのですが、咲き終わると花は落下しその茎だけが残ります。花をつけたままにすると栄養が花に持っていかれるので摘んだ方がよいという人もいますが、経験則からはそのまま残しておいてもあまり影響はないようです。
 ジャガイモの実は、緑色のプチトマトのような形状をしており、大きいものでも直径3センチくらいです。トマトのように柔らかくはなく、触ってみると固くてしっかりと中身が充実しているのがわかります。しばらくそのままにしておくと落ちてしまうようです。ジャガイモはナス科の野菜ですが、ナスやトマトと違って食べる部分は地下のイモの部分です。一般に園芸品店で市販されて栽培されることの多い男爵、メークインなどは、花の受粉能力が低いため実をつけることはほとんどありません。実がついていたのはキタアカリのみで、男爵にはひとつもありませんでした。キタアカリは他の品種より実がつきやすいとのことです。この実の中に種があり、100個以上も詰まっていて、植えると発芽するとのことです。私たちが普段食べている芋は、茎から伸びた塊茎(かいけい)と呼ばれる部分です。塊茎から子孫を残すことを取得してからは、種子で繁殖する必要性がなくなって受粉能力が低下したとも言われています。ちなみにこの実には天然の毒が含まれており、食べられないということです。ジャガイモの芽の部分や緑化した部分には天然毒のソラニンやチャコニンが含まれていて、食べると食中毒を起こすことは皆さんご存知のとおりです。
ジャガイモの実は、緑色のプチトマトのような形状をしており、大きいものでも直径3センチくらいです。トマトのように柔らかくはなく、触ってみると固くてしっかりと中身が充実しているのがわかります。しばらくそのままにしておくと落ちてしまうようです。ジャガイモはナス科の野菜ですが、ナスやトマトと違って食べる部分は地下のイモの部分です。一般に園芸品店で市販されて栽培されることの多い男爵、メークインなどは、花の受粉能力が低いため実をつけることはほとんどありません。実がついていたのはキタアカリのみで、男爵にはひとつもありませんでした。キタアカリは他の品種より実がつきやすいとのことです。この実の中に種があり、100個以上も詰まっていて、植えると発芽するとのことです。私たちが普段食べている芋は、茎から伸びた塊茎(かいけい)と呼ばれる部分です。塊茎から子孫を残すことを取得してからは、種子で繁殖する必要性がなくなって受粉能力が低下したとも言われています。ちなみにこの実には天然の毒が含まれており、食べられないということです。ジャガイモの芽の部分や緑化した部分には天然毒のソラニンやチャコニンが含まれていて、食べると食中毒を起こすことは皆さんご存知のとおりです。
5月26日(月)
去年山仲間から届けてもらった菊の鉢上げをしたものに、今年もたくさんの脇芽が出てきました。去年は脇芽をそれぞれ1本ずつの苗にして、リバーサイドパークの土手に並べて植えてみました。しかし、少し葉が大きくなると、夜中にシカが山から下りてきて葉の先端の柔らかい部分を食べてしまい、棒だけになったり抜かれてしまったりした苗が散乱していることが続きました。そのたびに苗を植え替えたのですが、結局大きな株にはなることはありませんでした。今年はシカの食害を防ぐために去年の鉢上げした菊株の冬至芽を1本だけ残してシカの来ない場所に鉢を移動させて、成長させて程よい形の菊に仕上げる予定です。鉢の苗を数本から1本にしたところ、小さいバッタが葉の柔らかいところを食しているではないですか。またまた強敵の出現です。バッタを取り除き、シカが来ないことを願って成長を見守りたいと思います。鉢に残した苗以外の苗は、別地点の畑に植え替えたので成長を楽しみたいと思います。去年の状況は12月27日の記事にあります。
5月22日(木)
五月もいよいよ後半です。昨日一昨日と甲府では30度を超える夏日を観測し、ここ身延の博物館周辺の木々の新緑もより深くなって来ました。初夏の到来を感じるこの頃となってきました。この時期の有名な俳句に「目には青葉山ほととぎす初鰹」があります。甲斐の国出身とされる山口素堂の句です。青葉の視覚、ほととぎすの聴覚、初鰹の味覚と三つも季語が連なった季重なりではあるものの、それがかえって一体感となった巧みな表現となっています。さらに、すべてが体言止めになっていて三段切れであり本来は禁じ手なのですが、この句に一定のリズム感を与えています。また、注意していただきたいのは「目には青葉」で字余りなのです。よく間違えられる「目に青葉」ではありません。「は」があることで、後に続く「耳にはほととぎす」、「口には初鰹」と他の体の感覚部分をも続けて連想させる効果があります。「は」がないと平坦な表現になってしまい、新鮮な感覚の印象は出てこないとは思いませんか。約350年もの間、一般の人にも親しまれている俳句の妙がこの辺りにもあると言われています。
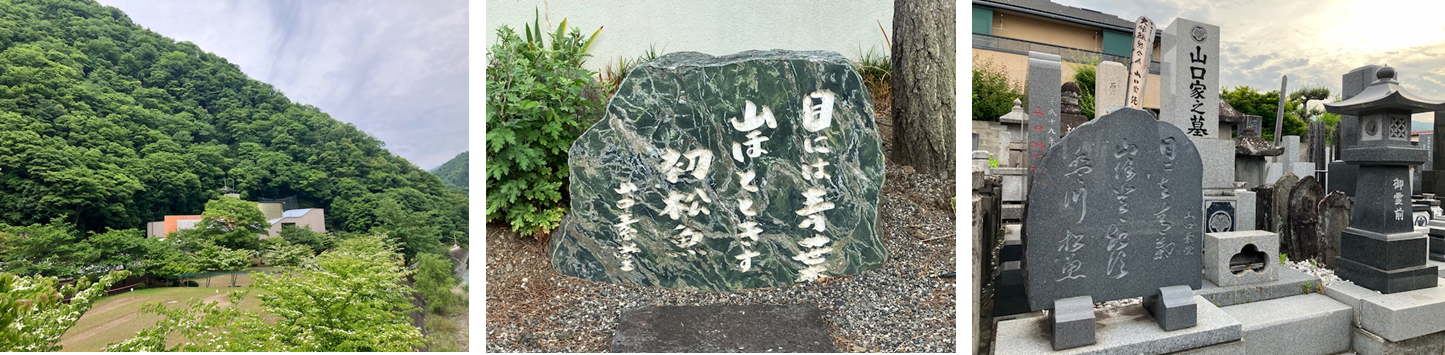 素堂は北杜市白州町山口に生まれ、甲府魚町に移住し裕福な酒造業を営んでいた実家の出身ということになっています。(『甲斐国志』)甲斐と素堂自身とのかかわりは、亡き母のために身延詣でを行った『甲山紀行』に記されています。この中で素堂は、甲府が妻のふる里なので懐かしく感じたこと、妻の実家に宿泊したこと、信玄伝説が残る夢山に登って漢詩を山の主人に贈ったことなどが記されています。甲府が自分の故郷だと示す記述はありません。しかし、甲府の尊躰寺には山口素堂の墓と句碑が残されております。その実態は混沌として伝えられています。
素堂は北杜市白州町山口に生まれ、甲府魚町に移住し裕福な酒造業を営んでいた実家の出身ということになっています。(『甲斐国志』)甲斐と素堂自身とのかかわりは、亡き母のために身延詣でを行った『甲山紀行』に記されています。この中で素堂は、甲府が妻のふる里なので懐かしく感じたこと、妻の実家に宿泊したこと、信玄伝説が残る夢山に登って漢詩を山の主人に贈ったことなどが記されています。甲府が自分の故郷だと示す記述はありません。しかし、甲府の尊躰寺には山口素堂の墓と句碑が残されております。その実態は混沌として伝えられています。
5月19日(月)
博物館の植栽や下部リバーサイド公園の雑草が下刈りされていて、きれいになっています。先日、カラスノエンドウとカスマグサを公園内で見つけたので、しかるべき時期に写真を撮って本欄の記事にしたためようと思っていたところ、きれいに刈り取られ場外へ搬出されてしまっていました。そこで、博物館の対岸の河川敷にあるカラスノエンドウとカスマグサ及び別地点のスズメノエンドウの写真を撮ってきたので、これらの違いと名前の由来について説明したいと思います。
 カラスノエンドウは、漢字で表記すると烏野豌豆になります。カラスのエンドウではなく野豌豆という仲間の一つで、成熟するとカラスのように真っ黒になります。植物の世界では、ヤハズエンドウ(矢筈豌豆)が正式名称でカラスノエンドウは別名ですが、こちらの方がよく知られています。私が子供の頃には、シービービーやシビビーと言っていました。この時季小学生の頃学校帰りに、熟してサヤがまだ緑色の中の豆を取り出して豆殻を筒状にし、笛としてピーピーよく鳴らしたものです。右側の写真2枚はスズメノエンドウです。白っぽい花に、豆は2個しか入っていません。大きさが小さいので、カラスに対してスズメがその名に付けられたようです。カスマグサはカラス野エンドウとスズメ野エンドウの間の大きさなので、カラスの「カ」とスズメの「ス」をとって名付けられたとのことです。真ん中の写真はカラスノエンドウとカスマグサの実です。
カラスノエンドウは、漢字で表記すると烏野豌豆になります。カラスのエンドウではなく野豌豆という仲間の一つで、成熟するとカラスのように真っ黒になります。植物の世界では、ヤハズエンドウ(矢筈豌豆)が正式名称でカラスノエンドウは別名ですが、こちらの方がよく知られています。私が子供の頃には、シービービーやシビビーと言っていました。この時季小学生の頃学校帰りに、熟してサヤがまだ緑色の中の豆を取り出して豆殻を筒状にし、笛としてピーピーよく鳴らしたものです。右側の写真2枚はスズメノエンドウです。白っぽい花に、豆は2個しか入っていません。大きさが小さいので、カラスに対してスズメがその名に付けられたようです。カスマグサはカラス野エンドウとスズメ野エンドウの間の大きさなので、カラスの「カ」とスズメの「ス」をとって名付けられたとのことです。真ん中の写真はカラスノエンドウとカスマグサの実です。
5月17日(土)
 15日の午後から文化庁N調査官、県文化振興・文化財課のI氏と、国指定史跡の中山金山の現地確認に行ってきました。当館からはK学芸員、H文化財担当と私の計5名です。N調査官はスーツの上着を脱いだだけの服装で、足元はナント革靴スタイルです。山に行くのに少し不安を感じたのですが、普段から慣れ親しんでいる服装や靴の方がしっくりくるとの本人の弁。今のスーツは伸縮性が高く、靴も軽くゴム底なのでそれほど問題はありませんでした。登山口からは休憩をはさみつつも、いつもより早いペースで登ることができました。中山金山の大名屋敷から精錬場へと移動し、史跡内にある墓石や炭焼き窯跡、坑道の現状を視察していただきました。史跡の現状をどのように捉えて町としてどうしたいのか、保存を最優先にしながらどう活用していくか現地の状況に合わせて指導していただきました。現状は平成元年から3年まで発掘調査した後30年以上自然に放置された状態で、それぞれの遺構に付けられた説明板や案内板が処々に配置されています。説明板もイラストなど一般にわかりやすい表現を用いて板面のみを取り換えることも可能であることや、歩道を設け現地にある倒木や枯損木をチップなどに加工して敷けば、お金をかけずに一定の整備ができることなど示していただきました。帰りに茅小屋金山、内山金山を遠望できる川の所で二金山の位置と現況を説明し、史跡指定に向けた取り組みへのご指導を再依頼しました。
15日の午後から文化庁N調査官、県文化振興・文化財課のI氏と、国指定史跡の中山金山の現地確認に行ってきました。当館からはK学芸員、H文化財担当と私の計5名です。N調査官はスーツの上着を脱いだだけの服装で、足元はナント革靴スタイルです。山に行くのに少し不安を感じたのですが、普段から慣れ親しんでいる服装や靴の方がしっくりくるとの本人の弁。今のスーツは伸縮性が高く、靴も軽くゴム底なのでそれほど問題はありませんでした。登山口からは休憩をはさみつつも、いつもより早いペースで登ることができました。中山金山の大名屋敷から精錬場へと移動し、史跡内にある墓石や炭焼き窯跡、坑道の現状を視察していただきました。史跡の現状をどのように捉えて町としてどうしたいのか、保存を最優先にしながらどう活用していくか現地の状況に合わせて指導していただきました。現状は平成元年から3年まで発掘調査した後30年以上自然に放置された状態で、それぞれの遺構に付けられた説明板や案内板が処々に配置されています。説明板もイラストなど一般にわかりやすい表現を用いて板面のみを取り換えることも可能であることや、歩道を設け現地にある倒木や枯損木をチップなどに加工して敷けば、お金をかけずに一定の整備ができることなど示していただきました。帰りに茅小屋金山、内山金山を遠望できる川の所で二金山の位置と現況を説明し、史跡指定に向けた取り組みへのご指導を再依頼しました。
 中山金山の登山道の途中で、松ぼっくりを見つけました。その多くが通常の一般的に目にする形ではあったのですが、一部に動物の食痕が残されているものがありました。「森のエビフライ」と言われているリスなど小動物の食痕です。その最終形は、なんとなく「エビフライ」の形に似ていますね。松ぼっくりの鱗片が削られて、その間にある松の実を多分リスかアカネズミが食べた後の食痕です。松ぼっくりが秋口のまだ柔らかい時に、食べられたのでしょう。以前モミの木の松ぼっくりを食べた後の鱗片が散乱している状態を記載しています。(2023.10.19記事参照)
中山金山の登山道の途中で、松ぼっくりを見つけました。その多くが通常の一般的に目にする形ではあったのですが、一部に動物の食痕が残されているものがありました。「森のエビフライ」と言われているリスなど小動物の食痕です。その最終形は、なんとなく「エビフライ」の形に似ていますね。松ぼっくりの鱗片が削られて、その間にある松の実を多分リスかアカネズミが食べた後の食痕です。松ぼっくりが秋口のまだ柔らかい時に、食べられたのでしょう。以前モミの木の松ぼっくりを食べた後の鱗片が散乱している状態を記載しています。(2023.10.19記事参照)
5月12日(月)
今日の博物館の駐車場に「糞虫(フンチュウ・クソムシ)」がいました。コウチュウ目コガネムシ科の虫のうち、動物の糞をエサとする一群の昆虫を「糞虫」というそうですが、実際に糞と一緒にこの類の虫を目にするのははじめてです。この類の虫は、砂漠にいるフンコロガシなど、独特の習性を持っている事でもよく知られています。朝方駐車場から博物館に入る間に、2か所タヌキかハクビシンと思われる動物の糞があるのを見つけました。直径1センチくらいの棒状のもので、長さは最大で5センチくらいです。そのうちの一か所の糞の一部が動いていました。よく見ると、虫が自分の体の数倍もある糞を転がしています。糞は3個に分かれていたのですが、そのうちの一個を頭で前方に転がしていました。よくテレビなどで放映されている、逆立ちをして後ろ足で丸く成形した糞を後退して回転させながら移動させるのとは明らかに違った運搬方法です。少し時間がたった後にもう一度みてみると、糞の大きさが小さく成形されてより球形に近くなっていました。
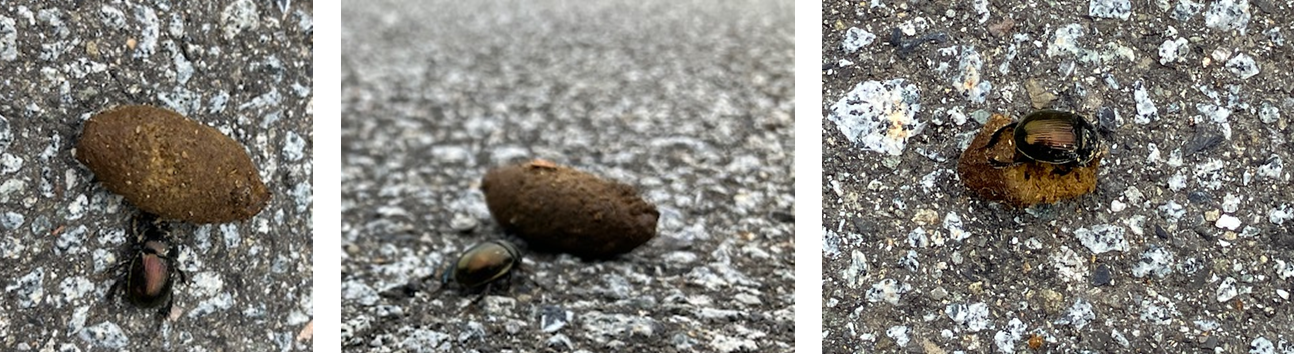 糞は動物が食したもののうち消化器官で消化した後の食べカスや利用できないものを排出したものですが、他の生き物には利用可能な栄養素などを含んでいます。これを食する食糞性コガネムシ類は、新鮮な糞があるとその匂いに引き寄せられ、その場で食べるものもいれば地下に穴を掘って運び込むものもいるそうです。古代エジプトのフンコロガシは、作り上げられた丸い糞の玉を太陽に見立てて、太陽の神の化身「スカラベ」としてこの虫を崇めたのだそうです。
糞は動物が食したもののうち消化器官で消化した後の食べカスや利用できないものを排出したものですが、他の生き物には利用可能な栄養素などを含んでいます。これを食する食糞性コガネムシ類は、新鮮な糞があるとその匂いに引き寄せられ、その場で食べるものもいれば地下に穴を掘って運び込むものもいるそうです。古代エジプトのフンコロガシは、作り上げられた丸い糞の玉を太陽に見立てて、太陽の神の化身「スカラベ」としてこの虫を崇めたのだそうです。
5月10日(土)
ゴールデンウィークも終了し、通常の土曜日に戻りました。早くも学校の校外学習が始まっており、一般客の数も元に戻ってきています。朝方の雨も止んで、昼にはお日様が顔を出してくれました。
 博物館の周辺には、今年になってから芽を出した樹木や、ここ数年で生えてきた樹木に葉や花がついています。ナンテン、クルミ、ヌルデ、センダンなどです。富士川谷地域ではふつうに見られる植物ですが、その拡散には鳥のフンが大きな役割を果たしています。鳥がこれらの実を食べ、果肉は鳥の体内で消化されます。消化されない種はフンと一緒になって排出され、それが土の上に落ちて発芽するシステムです。一方クルミはリスやネズミの大好物です。秋に落下した実は、人間が貯金するのと同じように冬の間の食料として確保しておくため一時的に貯蔵します。これを「貯食」といい、巣穴などにたくさん集めて持ち込む「集中貯食」と、あちこちいろいろなところに貯めておく「分散貯食」があるそうです。分散貯食した実のうち、食べられずに残ったものが発芽したものと思われます。食料なら何でも貯食できるのではなく、栄養価が高くて保存のきくクルミやドングリが冬場の食料として供されるのです。そのクルミに残された食痕から、ネズミの仕業に違いありません。貯食した場所はたくさん分散貯食をすると動物だってすべてを覚えきれません。また、さらにそれを他の動物が狙っているので、自分が最初に見つけ出すのも大変なようです。分散貯食で食されずに残された数少ない個体が、意外なところからも発芽してきます。写真は、今日の駐車場の山際に落ちていたクルミです。まだ実の入っているものもあったのですが、丸く両側に直径1センチぐらいの穴があけられているものはアカネズミの食痕です。半分に割れているものは、リスの食痕の可能性があります。鳥にとってもリスやネズミにとっても、樹木の実は大切な食料なのです。
博物館の周辺には、今年になってから芽を出した樹木や、ここ数年で生えてきた樹木に葉や花がついています。ナンテン、クルミ、ヌルデ、センダンなどです。富士川谷地域ではふつうに見られる植物ですが、その拡散には鳥のフンが大きな役割を果たしています。鳥がこれらの実を食べ、果肉は鳥の体内で消化されます。消化されない種はフンと一緒になって排出され、それが土の上に落ちて発芽するシステムです。一方クルミはリスやネズミの大好物です。秋に落下した実は、人間が貯金するのと同じように冬の間の食料として確保しておくため一時的に貯蔵します。これを「貯食」といい、巣穴などにたくさん集めて持ち込む「集中貯食」と、あちこちいろいろなところに貯めておく「分散貯食」があるそうです。分散貯食した実のうち、食べられずに残ったものが発芽したものと思われます。食料なら何でも貯食できるのではなく、栄養価が高くて保存のきくクルミやドングリが冬場の食料として供されるのです。そのクルミに残された食痕から、ネズミの仕業に違いありません。貯食した場所はたくさん分散貯食をすると動物だってすべてを覚えきれません。また、さらにそれを他の動物が狙っているので、自分が最初に見つけ出すのも大変なようです。分散貯食で食されずに残された数少ない個体が、意外なところからも発芽してきます。写真は、今日の駐車場の山際に落ちていたクルミです。まだ実の入っているものもあったのですが、丸く両側に直径1センチぐらいの穴があけられているものはアカネズミの食痕です。半分に割れているものは、リスの食痕の可能性があります。鳥にとってもリスやネズミにとっても、樹木の実は大切な食料なのです。
5月8日(木)
ゴールデンウィークの後半、4連休の3日目、5月5日のこどもの日のことです。天気も良く大変な数の入館者となりました。その前日4日は500人を超えた入館者数でテンヤワンヤの大忙しでした。5日も400人超えと、スタッフは昼食も取れない恐ろしいほどの混みようです。この日はこどもの日だったので、小学生以下の入館者には、恒例のたまごくじを実施しました。先着80名様限定で、キャラクターのぬいぐるみや博物館グッズが当たる、はずれくじ無しのくじ引きです。思わぬプレゼントに大喜びの子供たちでした。くじに使ったのはガチャでおなじみの卵形容器に数字を書いた札を入れ、同じ番号の札の付いた景品がもらえる仕組みとなっています。

「くじ」は、宝くじやあみだくじ、おみくじなどで、現代の私たちにもなじみのある言葉ですね。紙片や竹片に数字や記号を記しその一つを抜き取って、ことの成否や吉凶を判断したり当落や順番を決めたりもしました。古来より国政や祭事についての重要なことを決める時に、「くじ」を引くことで神仏のお告げを占って進むべき道を決めていました。「籤(くじ)」の由来は、棒状のものを扱うので「串(くし)」から来た説や、箱などに入った中から抉って引き当てる「抉(くじ)る」から来た説などがあります。
 武田信玄は、信長の比叡山焼き討ちののち、比叡山を身延に移すことを計画しました。移転の代償として代わりに別なところに大寺院を普請することを約していました。身延山の各僧は返答に窮し、日蓮聖人の御影の前でくじを引いて判断することにしました。三度、五度、七度とくじを引いても、移転すべきではないとの内容であったと『甲陽軍鑑』は記しています。信玄の時代、身延山久遠寺においても、重要な事項を決する方法として、祖師像の前でくじを引いたのです。日蓮聖人のお告げとして、現在地での存続を暗示されたものであると解釈され、比叡山の身延山移転はかなわなかったのでした。
武田信玄は、信長の比叡山焼き討ちののち、比叡山を身延に移すことを計画しました。移転の代償として代わりに別なところに大寺院を普請することを約していました。身延山の各僧は返答に窮し、日蓮聖人の御影の前でくじを引いて判断することにしました。三度、五度、七度とくじを引いても、移転すべきではないとの内容であったと『甲陽軍鑑』は記しています。信玄の時代、身延山久遠寺においても、重要な事項を決する方法として、祖師像の前でくじを引いたのです。日蓮聖人のお告げとして、現在地での存続を暗示されたものであると解釈され、比叡山の身延山移転はかなわなかったのでした。
5月3日(土)
先日国立科学博物館の特別展「古代DNA―日本人のきた道―」を見てきました。日本人のルーツやその実態が、ゲノム解析の最新の研究によって明らかになってきているのには驚かされました。精緻な人骨の復顔は、ただ頭蓋骨に肉付けされただけではなくて、髪の毛の質や目の色や形、肌の色や皮膚の状態など、DNAの解析によって明らかにされたその人個人の情報が反映されているのです。また、縄文時代人の人骨の分析から、何をどの割合で食べていたのかがわかるそうです。人骨中に含まれる窒素や炭素の同位体を用いた食性分析の結果、海岸部の縄文人と山間部の縄文人では食性の違いが明白です。海岸部では海産物を多く食べ、山間部では主に堅果類や肉を食べていたことが判明しています。このことは遺跡から出土する獣骨や貝類、植物遺体と石器組成から導き出されたこれまでの研究成果を裏付けるものです。
遺跡から発掘された古代人の骨には、ごくわずかなDNAが残っていることがわかっていました。その分析はこれまで母親から受け継がれるミトコンドリアのDNAを対象としましたが、近年両親から受け継がれる核DNAの解析機器の実用化に伴って、人体の設計図ともいうべきはるかに多くの情報を得ることが可能になりました。古代人の髪や目、肌の色のほか、どんな病気にかかりやすかったかまでも明らかにすることができるようになったのです。詳細な遺伝情報を得ることができるようになったことで、これまでの化石の形態研究では分からなかった、我々のホモ・サピエンスの起源や世界への広がりの道筋、人類集団の形成過程の研究なども進んでいます。(特別展パンフレットより)
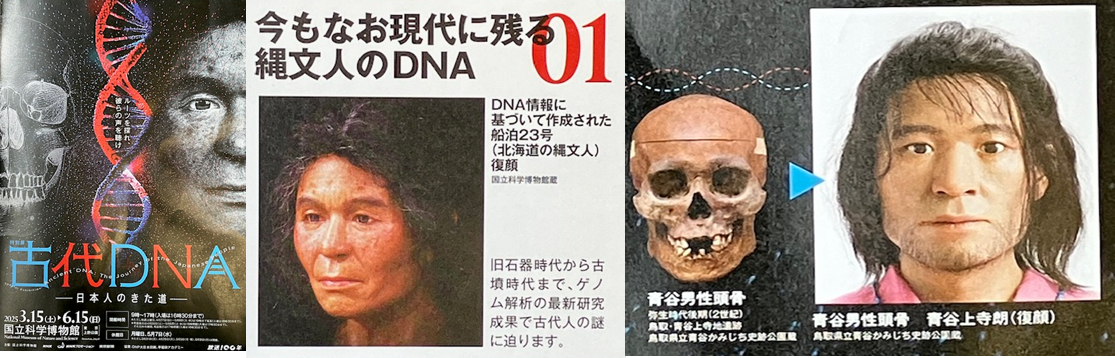 4万年に及ぶ日本列島の人類の足跡をたどる古代DNA研究の最前線が、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代と琉球列島集団の形成史、北の大地の人々の時代別地域別に紹介されています。人骨から個人の情報が得られ、その家族や集団の関係が明確となり、文化の変容の実態解明が進んで来ています。
4万年に及ぶ日本列島の人類の足跡をたどる古代DNA研究の最前線が、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代と琉球列島集団の形成史、北の大地の人々の時代別地域別に紹介されています。人骨から個人の情報が得られ、その家族や集団の関係が明確となり、文化の変容の実態解明が進んで来ています。
5月2日(金)
今日は「ゴールデンウィーク」の間の平日です。「ゴールデンウィーク」とは、4月の下旬から5月上旬の国民の祝日が集中する大型連休のことですね。今年の場合は4月28日(月)が休みになれば26日(土)から29日(昭和の日)までの前半と、3日(憲法記念日)、4日(みどりの日)、5日(こどもの日)、6日(振替休日)の後半の飛び石連休になりますが、28日、30日~2日までの平日を休みにして12連休にしたうらやましい企業もあるそうです。
「ゴールデンウィーク」は、日本語に直訳すれば「黄金週間」になる和製英語ですが、この言葉は映画会社の大映による集客目的の宣伝用語として使用されたことに由来するそうです。そもそも昭和23年(1948)に「国民の祝日に関する法律」によって、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日と、近い数日間に祝日が集中したことがその根底にあります。昭和26年(1951)5月5日、朝日新聞に連載された獅子文六の長編小説を大映と松竹が「自由学校」の同じ題名で映画化し、大映版の方は創業以来の興行成績を記録しました。大映ではこの時期を「ゴールデンウィーク」と名付けて宣伝に利用したのが定着し、一般にも使われるようになったとのことです。その他語源については諸説があり、ラジオ業界の「ゴールデンタイム」由来説、ロッキー山脈の雪解け水が活発化するこの時期に砂金が多く採れたので人々が殺到した由来説、マルコ・ポーロの『東方見聞録』の中で日本を「黄金の国ジパング」として紹介した記述に関係する由来説などがあります。
いずれにしても「ゴールデンウィーク」は、気候も良く春の陽気に心がウキウキする一年の中で最も輝かしい一週間です。後半の連休には、その文字にある通り、黄金のことをより深く知り、実際に黄金(ゴールド)がゲットできる砂金採り体験に当博物館に足を運んでみてはいかがでしょうか。
4月29日(火)
野菜を作っている畑に春になってきれいな花が咲いていました。葉を食する野菜は花が咲く前に収穫してしまうので、その花の姿を見ることはないのがほとんどです。冬の鍋用に栽培していた「春菊」は数回の利用のみで、霜にやられて葉先が枯れて利用できなくなってしまいます。黒マルチに寒冷紗で防寒対策をしていても、いつも冬の寒さで年末年始には傷んでしまいますが、抜かずにそのままほっといたものに淡い黄色の花が咲き始めました。「春菊」は冬が旬の葉を食する野菜ですが、その名のとおり春になって花を咲かせます。花もつぼみも食することができ、葉とは違った風味を堪能できるとのことです。すき焼きの定番食材ですが、小さい頃はその独特の香りや苦みが苦手でした。大人になると不思議とその苦みやえぐみがとりわけおいしく感じられるようになり、フキノトウやウドなどの山菜やセロリも同様に大人になってから好きになった味覚の食べ物です。春菊の原産地は地中海沿岸地域で、花ことばは「とっておき、豊富」になります。 真ん中の写真の黄緑色と赤の葉は、リーフレタスの収穫残りの薹(とう)が立った旬を過ぎたものです。これにも棒状の先に花が付きます。レタスもキク科の野菜です。
 白い花は「韮」(ニラ)の花です。ニラは奈良時代には「みら」と呼ばれていたものが、平安時代には転訛して「にら」に変わったとのことです。ニラは中国原産の多年草で、生命力が強く独特の臭いがあります。この臭いから禅宗などの寺院境内には、「不許禁葷酒入山門」とか「禁葷酒」の結界が張られています。ニラは五葷の一つで、これらの臭気の強い野菜は淫欲、憤怒などが起こりやすく、心を乱し修行の妨げになるので寺の境内に持ち込むことは許されないとされてきました。禅宗寺院の門前には、この文字が刻まれた石柱をしばしば見かけます。
白い花は「韮」(ニラ)の花です。ニラは奈良時代には「みら」と呼ばれていたものが、平安時代には転訛して「にら」に変わったとのことです。ニラは中国原産の多年草で、生命力が強く独特の臭いがあります。この臭いから禅宗などの寺院境内には、「不許禁葷酒入山門」とか「禁葷酒」の結界が張られています。ニラは五葷の一つで、これらの臭気の強い野菜は淫欲、憤怒などが起こりやすく、心を乱し修行の妨げになるので寺の境内に持ち込むことは許されないとされてきました。禅宗寺院の門前には、この文字が刻まれた石柱をしばしば見かけます。
4月24日(木)
本日が正式な湯之奥金山博物館の開館28周年の記念日です。平成9年4月24日、甲斐黄金村・湯之奥金山資料館としてオープンしました。発足時はまだ博物館ではなく、合併前の下部町立の資料館でした。これまで伝承の中にあった湯之奥金山に対して、昭和63年の予備調査、平成元年から3年までの学際的調査の結果を受けて、町ではこれらを貴重な地域資源として位置づけて、金山遺跡や金山史のガイダンス館である観光・文化施設が開館したものです。
 周囲の山々やリバーサイド公園にも、春の新緑が萌木色を呈してきました。河津桜はすでに実をつけ、メロディ橋ではクマンバチが花の蜜を求めてか飛び回ったりホバリングをしたりしています。橋上には1匹の死骸が。クマンバチは正式にはクマバチ(熊蜂)で、体の大きさの割に小さい羽根であることからその飛行構造が航空力学上は解明できていないとされていました。クマンバチは空を飛べないハズの昆虫だといわれていますが、実際にはなぜかスムーズに飛べるのです。飛べる理由は「レイノルズ数」だと言われています。初めて聞く言葉です。最近分かった理論だということですが、「流体の慣性力と粘性力の比を表す無次元数であり、流体解析を実施する前に層流・乱流の見当をつけるために、しばしば利用される」理論だそうです。なんのこっちゃ。私の頭ではよく理解できません。いずれにしても、クマンバチはその体の大きさにも関わらず、小さい羽根を動かすことで航空力学上は不可能であるはずなのに、自由自在な飛行ができるということです。わかりますか?
周囲の山々やリバーサイド公園にも、春の新緑が萌木色を呈してきました。河津桜はすでに実をつけ、メロディ橋ではクマンバチが花の蜜を求めてか飛び回ったりホバリングをしたりしています。橋上には1匹の死骸が。クマンバチは正式にはクマバチ(熊蜂)で、体の大きさの割に小さい羽根であることからその飛行構造が航空力学上は解明できていないとされていました。クマンバチは空を飛べないハズの昆虫だといわれていますが、実際にはなぜかスムーズに飛べるのです。飛べる理由は「レイノルズ数」だと言われています。初めて聞く言葉です。最近分かった理論だということですが、「流体の慣性力と粘性力の比を表す無次元数であり、流体解析を実施する前に層流・乱流の見当をつけるために、しばしば利用される」理論だそうです。なんのこっちゃ。私の頭ではよく理解できません。いずれにしても、クマンバチはその体の大きさにも関わらず、小さい羽根を動かすことで航空力学上は不可能であるはずなのに、自由自在な飛行ができるということです。わかりますか?
4月20日(日)
今日は当博物館開館28周年の記念日です。午前中はシン・サンポ、午後は当館のキャラクター「もーん父さん」のグリーティング会を開催しました。
午前中はアウトドア版館長講座の第4回シン・サンポ「身延町切石編」を実施しました。昨日は甲府で30℃越えの真夏日で切石も28℃を越えて暑かった一日ですが、天気は曇りで程よい散策日和の気候でした。身延町役場に集合し、切石地区の寺社や地名の由来、駿州往還の宿場町、郷蔵や富士川舟運の年貢米の保管や行方について学習しました。参加された皆さんは役場を利用し国道はよく通るのですが、集落内を街道から1歩入って巡るのは今回初めての方ばかりで、切石の宿場の中の様子に新鮮な発見があったようです。善妙寺と正伝寺では本堂にお邪魔させていただき、それぞれのお上人様からお寺の由緒や所蔵されている文化財のお話を直接お伺いすることができました。散策途中の土手などには、ヒトリシズカ、オドリコソウ、イカリソウ、タンポポなどの野生の花が咲いており、ユリやノカンゾウなども見ることができました。ハナミズキやモクレンなどたくさんの花を見ながら、ゆったりと自然も観察しての散策会は、好評でした。
午後はもんちゃんのグリーティング会でした。熱烈なもんちゃんファンのみなさんから、お花やお菓子のプレゼントがあり、飾りつけのされたスタジオでの撮影会や楽しい談笑が絶えませんでした。日頃のもんちゃんのファンサービスの賜物です。
4月19日(土)
埋蔵金、なんと夢のある響きではないですか。埋蔵金伝説は日本各地にたくさん残されています。かつてテレビ局で、徳川埋蔵金伝説を実際に赤城山麓で発掘する特番が放送され、山梨県内でもこの徳川埋蔵金が赤城山麓とは別に旧増穂町(現富士川町)に存在するとの説も一部で信じられていました。また、武田家が滅亡した時、新府城から逃れる時に黄金をどこかに埋蔵したという伝説や、武田氏の金山の廃坑に伴って金を秘匿した伝説や、穴山梅雪の埋蔵金伝説などが県内各地に残されています。
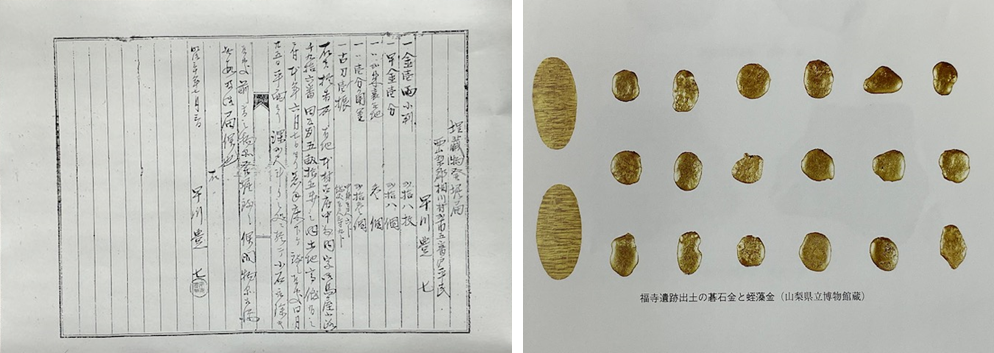 武田氏館の北西、甲府市古府中町に明治時代、甲州金や小判などが発見されたという記録が残されています。小判28枚、甲州金一分判28個、甲州金二朱判3個、一分角金23個の合計41両2朱と刀1振が発見されています。この時に出された埋蔵物発見届では、田圃の高低差をなくすため、深さ弐尺斗(約60センチ)掘り下げ小石を取り除いたところ、これらが発見されたとして役所に届けられました。現在古府中区画整理区域の住宅地になっており、江戸時代のある時期に埋蔵されて明治三十年になって届けられたことがわかります。ここで注目されるのは、丸い甲州金一分判と四角い一般的な一分判が書き分けられていることです。現在これらの埋蔵物はいったいどこに行ってしまったのでしょうか。
武田氏館の北西、甲府市古府中町に明治時代、甲州金や小判などが発見されたという記録が残されています。小判28枚、甲州金一分判28個、甲州金二朱判3個、一分角金23個の合計41両2朱と刀1振が発見されています。この時に出された埋蔵物発見届では、田圃の高低差をなくすため、深さ弐尺斗(約60センチ)掘り下げ小石を取り除いたところ、これらが発見されたとして役所に届けられました。現在古府中区画整理区域の住宅地になっており、江戸時代のある時期に埋蔵されて明治三十年になって届けられたことがわかります。ここで注目されるのは、丸い甲州金一分判と四角い一般的な一分判が書き分けられていることです。現在これらの埋蔵物はいったいどこに行ってしまったのでしょうか。
甲州市勝沼町下岩崎の福寺遺跡から昭和46年に発見された埋蔵金は、碁石金18個、蛭藻金2枚と渡来銭約6,000枚です。ごみ穴を掘っていた時に偶然発見されたものです。現在、山梨県立博物館に買い取られて保管されています。
4月14日(月)
昨日は雨の寒い一日でしたが、今日は気持ちの良いお天気です。朝、中山金山の前衛の五老峰には雲がかかっていました。通称霧雲という層雲です。雲と霧の違いは、どうなんでしょうか。どちらも湿った空気が冷やされて、空気中の水蒸気が凝結して気体から液体に代わることによって細かな水滴になって浮遊している状態を言うのですが、気象庁の資料によれば、空中に浮遊していると雲、地表に接していると霧と言うそうです。朝方の五老峰の中腹に見えていた雲は、水蒸気が地表に接しているので現地では霧ということになります。昼近くになると気温も高くなり雲も上昇してきたので、五老峰がその全容を現わしてくれました。中腹くらいまで芽吹きが進んでいるようすが観て取れます。頂上付近はまだ冬の装いで広葉樹は芽吹きが感じられず樹幹の色の茶色を呈していますが、一雨ごとに暖かさを増してきている陽気からすれば、春めいて木が一気に芽吹いてくるものと思われます。

博物館付近では、河津ザクラがすべて葉桜の黄緑色となり、ソメイヨシノも花びらの花弁が散ってガクや子房の薄いピンク色がわずかに残り、葉桜になるのも時間の問題です。隣接する山々の木々も、淡い緑色に芽吹いてきました。まさに春がやってきたという感じです。
4月12日(土)
今日は武田信玄公の命日です。元亀4年(1573)、今から452年前に信州駒場において、息を引き取りました。京へ攻め上る西上作戦の途中、享年53歳でした。当時の平均寿命は30歳代で、意外と低いのは乳幼児の死亡率が高かったためと言われています。戦国武将全体に関しての平均寿命は60歳前後のようなので、信玄は他の戦国武将に比べてやや短命だと言えます。死因は吐血をしていることから、消化器官上部の食道ガンまたは胃ガン説が有力で、結核説や脳溢血、鉄砲傷の悪化説などもあります。信玄は死に際して、遺言でその死を3年間秘すこととし、弟の逍遥軒信綱を影武者として立てました。対外的には病気のため隠居して勝頼が後を継いだことにし、生前に自分の花押(サイン)だけを書いた白紙を多数用意したことが知られています。自分の死後も信玄が生きているように装い、勝頼の意を受け祐筆がその用紙を使って諸大名等への音信に使ったということが、『甲陽軍鑑』に記されています。信玄の思慮深さがうかがい知れます。
さて、信玄の墓所が当地域にもいくつか存在することを、去年の記事でも書きました。身延町道の慈観寺、根子の満福寺のほかに新たに大磯小磯の八王子神社前の石造物群の中にあるのを見つけました。新発見と思っていたら、既に文化財担当で石造物調査がなされ、西河内地域にはかなりの数が存在することがわかっていました。すべて江戸時代後半に建てられ、自然石に信玄の戒名などが掘られているという共通点があります。
4月10日(木)
 ソメイヨシノの桜の花びらが、風によって舞い散る花吹雪です。桜吹雪とも言いますが、空中で舞っている姿は、写真ではうまく写せませんでした。今日は風が一時的に強く吹いたり雨が降って来たり、落ちた花びらからすればもうほとんど残りはありません。桜の開花情報や満開情報も北上しており、山梨県内でも標高の高い所や富士五湖方面が、今週末以降に見頃を迎えるようです。
ソメイヨシノの桜の花びらが、風によって舞い散る花吹雪です。桜吹雪とも言いますが、空中で舞っている姿は、写真ではうまく写せませんでした。今日は風が一時的に強く吹いたり雨が降って来たり、落ちた花びらからすればもうほとんど残りはありません。桜の開花情報や満開情報も北上しており、山梨県内でも標高の高い所や富士五湖方面が、今週末以降に見頃を迎えるようです。
 南東の山際のヤマブキも花が盛りとなってきました。一重の花の花びらは桜と同じ5枚なのですが、よく見ると6枚の花もかなり見受けられます。きれいな花が咲くことから、古くから庭木に移植されているとのことです。(4月5日のブログ参照)「蛙鳴く甘南備川に影見えて今か咲らむ山振の花」の歌が『万葉集』にあり、『古今集』には「蛙なく井出の山吹散りにけり花の盛りにあはましものを」とあります。奈良時代から平安時代の間に「山振(ヤマブリ)」から「山吹(ヤマブキ)」に変化したことがわかります。
南東の山際のヤマブキも花が盛りとなってきました。一重の花の花びらは桜と同じ5枚なのですが、よく見ると6枚の花もかなり見受けられます。きれいな花が咲くことから、古くから庭木に移植されているとのことです。(4月5日のブログ参照)「蛙鳴く甘南備川に影見えて今か咲らむ山振の花」の歌が『万葉集』にあり、『古今集』には「蛙なく井出の山吹散りにけり花の盛りにあはましものを」とあります。奈良時代から平安時代の間に「山振(ヤマブリ)」から「山吹(ヤマブキ)」に変化したことがわかります。
4月7日(月)
今日は朝方晴れていたのに、昼からは雨がぽつりぽつり。ナント降り初めは霰の氷の粒が降ってきました。20日のシン・サンポの下見に切石に行って来た時の出来事です。傘を持って行かなかったので、善妙寺の山門でしばらく雨宿りをすることになってしまいました。
山門の軒下には鯱瓦(しゃちがわら)があって、たぶんこの門にもと葺かれていたものでしょう。普通は屋根の上にあって遠くからしか見ることができないので、よく見て詳しく観察してみました。鯱は体が魚で顔が虎の姿をした想像上の動物です。鱗(うろこ)や鰭(ひれ)が表現されており、顔は鋭く見開いた目と牙を持った獣になっています。一般的には建物が火事になった時に、口から水をはいて火を消し止めるという伝説があり、防火のまじないのために瓦葺建物の大棟に一対で取り付けられています。
 善妙寺には日蓮聖人が、お手植えされたという伝説のある「年越の松」の大木がかつて存在していました。日蓮聖人は布教の途次、善妙寺に泊まられた時のことです。その日はちょうど立春の前夜、節分の日であったので、聖人手ずから節分会の豆まきをなされ、近隣の参詣の多数の善男善女は良い年を迎えることが出来たといいます。この時聖人は、境内の中央に記念の松をお手植えになったので、この松を年越しの時に植えた松、つまり「年越の松」と呼ぶようになったと伝えています。(『中富町誌』)しかし、大正時代に枯れてしまったので伐採し、その株の跡地に当山日証上人の書になる「宗祖大士越年之霊松」の木碑が立てられています。
善妙寺には日蓮聖人が、お手植えされたという伝説のある「年越の松」の大木がかつて存在していました。日蓮聖人は布教の途次、善妙寺に泊まられた時のことです。その日はちょうど立春の前夜、節分の日であったので、聖人手ずから節分会の豆まきをなされ、近隣の参詣の多数の善男善女は良い年を迎えることが出来たといいます。この時聖人は、境内の中央に記念の松をお手植えになったので、この松を年越しの時に植えた松、つまり「年越の松」と呼ぶようになったと伝えています。(『中富町誌』)しかし、大正時代に枯れてしまったので伐採し、その株の跡地に当山日証上人の書になる「宗祖大士越年之霊松」の木碑が立てられています。
4月5日(土)
春は確実にやってきています。砂金採り体験室のガラス越しに山裾側を見ると、知らない間にヤマブキがもう咲いているではありませんか。周辺のヤマブキを見ても緑の葉とともに、多くのつぼみがかなり膨らんでいます。日当たりの良い株は、すでに花がしっかり開いています。ソメイヨシノの桜は遅いものが今でも満開で、入り口付近のレンギョウもヤマブキとは違った軽やかな黄色を呈しています。博物館はいろいろな花が今まさに楽しむことができます。
 ヤマブキ色は黄金色で、小判の比喩によく使われます。江戸時代の歌舞伎の「河内山」では、「山吹の茶を一服所望いたす」として、「黄色いお茶を一杯ください」ではなく「山吹色の小判(わいろ)が欲しい」の隠語に登場してきます。最近テレビで時代劇が少なくなりましたが、桐箱に入った「山吹色の菓子」を悪代官(権力者)に袖の下として渡し、便宜を図ってもらうなんてシーンが昔の勧善懲悪ものではよくみられました。「山吹」はバラ科ヤマブキ属の落葉低木で、日本・中国・朝鮮半島などに見られます。『万葉集』にも登場し、しなやかな枝が風に揺れるさまから「山振(やまぶり)」が転じて「山吹」になったと言われています。(諸説あり) 山吹の花を見ると、当博物館が所蔵している純度の高い甲州金と同じく、まさにやや赤みがかった鮮やかな黄色の黄金色をしています。
ヤマブキ色は黄金色で、小判の比喩によく使われます。江戸時代の歌舞伎の「河内山」では、「山吹の茶を一服所望いたす」として、「黄色いお茶を一杯ください」ではなく「山吹色の小判(わいろ)が欲しい」の隠語に登場してきます。最近テレビで時代劇が少なくなりましたが、桐箱に入った「山吹色の菓子」を悪代官(権力者)に袖の下として渡し、便宜を図ってもらうなんてシーンが昔の勧善懲悪ものではよくみられました。「山吹」はバラ科ヤマブキ属の落葉低木で、日本・中国・朝鮮半島などに見られます。『万葉集』にも登場し、しなやかな枝が風に揺れるさまから「山振(やまぶり)」が転じて「山吹」になったと言われています。(諸説あり) 山吹の花を見ると、当博物館が所蔵している純度の高い甲州金と同じく、まさにやや赤みがかった鮮やかな黄色の黄金色をしています。
 黄金色の植物としては、ミツマタの花があります。先日の都留アルプスとともに、お隣の南部町ではこの大群落があり、いままさに「黄金街道」として上徳間峠から森山へのルートが花盛りです。「ヤマレコ」に紹介されたり、南部町でも観光客の誘致に取り組んでいます。黄金街道といえば、甲信越静をむすぶ「黄金KAIDO」があります。徳川家康公が開発に力を注いだ佐渡金山(新潟県)と土肥金山(静岡県)を結ぶルートで、途中には湯之奥金山(山梨県)、金鶏金山(長野県)があります。中部横断道の開通により、静岡・山梨・長野・新潟の中央日本4県は交通の利便性が向上し、観光周遊エリアとしての結びつきがより強くなりました。土肥から佐渡までの金山を海路と陸路でつなぎ、広域での観光客誘致を一体的に促進するプロジェクトです。
黄金色の植物としては、ミツマタの花があります。先日の都留アルプスとともに、お隣の南部町ではこの大群落があり、いままさに「黄金街道」として上徳間峠から森山へのルートが花盛りです。「ヤマレコ」に紹介されたり、南部町でも観光客の誘致に取り組んでいます。黄金街道といえば、甲信越静をむすぶ「黄金KAIDO」があります。徳川家康公が開発に力を注いだ佐渡金山(新潟県)と土肥金山(静岡県)を結ぶルートで、途中には湯之奥金山(山梨県)、金鶏金山(長野県)があります。中部横断道の開通により、静岡・山梨・長野・新潟の中央日本4県は交通の利便性が向上し、観光周遊エリアとしての結びつきがより強くなりました。土肥から佐渡までの金山を海路と陸路でつなぎ、広域での観光客誘致を一体的に促進するプロジェクトです。
3月31日(月)
今日は3月31日、令和6年度の最終日です。あっという間に年が明けてから3か月、1年の四分の一が過ぎ去ってしまいました。「光陰矢の如し」、まさに月日のたつのは早いものだと本当に痛感しています。平安時代の歌人凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の歌に「梓弓春たちしより年月の射るがごとくも思ほゆるかな」があります。梓弓につがえて射る矢は見る間に飛び去っていくが、その弓に張るという言葉に違わず、春になったと思うや否やそれから始まった新しい年月が矢を射たように素早く飛んでいってしまうという意味の歌です。凡河内躬恒は、甲斐国の地方官(甲斐介)として赴任し、山を開いて沢の水を流させた治水の功績により民に感謝され、躬恒を祀る祠が今もあるといいます。(『前賢故実』) 篠井山の山名の由来も躬恒の官位(四ノ位)にちなむという説、山霊を鎮めるため山頂へ宝物を埋納した伝説なども当地域とのつながりを今に伝えています。(当ブログ2023.11.5-6参照)紀貫之とともに「古今和歌集」の選者でありながら、どうしても貫之の陰に隠れた二番手はあまり知名度が高くありません。その名前の難しさ読み方の難しさも手伝って、ナンバー2は不遇のもとに置かれています。
さて、暦年と年度はどう違うのでしょうか。暦年では、1月1日の元日に始まり12月31日の大晦日までを1年として取り扱います。学校や会社、あるいは国や地方公共団体では、4月1日に始まり翌年の3月31日までを年度としています。学校年度や会計年度として一般には使われてきています。外国では学校年度が9月1日から8月31日までとしている国が多くあります。日本の会社でも事業年度、会計年度が異なっている場合もあります。
学校教育法により、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」と規定していますが、実際の学年で採用される生年月日は4月2日から翌年の4月1日までを1学年として取り扱っています。4月1日生まれの人は3月31日の午後12時に入学年齢となる満6歳に達するため、誕生日の前日に年齢が加算されるので前の学年になるとのことです。誕生日の前日が終了する時(午後12時)に、歳を一つとることすなわち満年齢になると定められています。(年齢計算に関する法律、民法第143条)小学校時代同級生のF君は4月1日生まれで、生まれた生年月日順に出席番号が付けられていたことから男子の最後の出席番号でした。小学生の時にはなぜ4月1日生まれなのに、前の学年になっているのかよく理解できていませんでした。
3月30日(日)
来月20日は身延町切石地区で、シン・サンポを開催します。「切石」の地名は江戸時代後期に編纂された地誌の『甲斐国志』に「諸職ニ公役アリ、本村石工ヲ置シ処カ」とあり、石工の公役に起因すると考えられています。隣村には夜子沢石工が存在し、武田時代の駿州往還の日下がり岩道開削の御用棟梁をもって夜子沢石工の祖として、新府城、菅沼城、甲府城築城時の活躍が「石大工由来書之事」(夜子沢区有文書)にあるそうです。夜子沢村から産出する石材は当村から搬出されており、駿州往還の難所である八日市場村境の日下がり切通の普請は江戸期を通して村民の大きな負担になっていたそうです。(角川日本地名大辞典)産物としては「切石御座」と呼ぶ敷物があり、周辺地域でも作られていました。
 「切石」は江戸時代初めに甲府と駿河を結ぶ駿州往還の伝馬宿となり、宿場町として隣接する「八日市場宿」と折半して宿継ぎを行い、月の前半を受け持ったといいます。街道に沿って「上宿」、「中宿」、「下宿」の地名があり、高札場、郷蔵も存在したことが江戸時代の古絵図に残されています。地内には正伝寺、善妙寺、御崎神社、赤山神社があり、これらの史跡や路傍の石造物を訪ねる予定です。
「切石」は江戸時代初めに甲府と駿河を結ぶ駿州往還の伝馬宿となり、宿場町として隣接する「八日市場宿」と折半して宿継ぎを行い、月の前半を受け持ったといいます。街道に沿って「上宿」、「中宿」、「下宿」の地名があり、高札場、郷蔵も存在したことが江戸時代の古絵図に残されています。地内には正伝寺、善妙寺、御崎神社、赤山神社があり、これらの史跡や路傍の石造物を訪ねる予定です。
3月27日(木)
博物館に隣接する下部リバーサイドパークのサクラが、ちょうど見ごろを迎えています。構内には河津ザクラ、シダレザクラ、ソメイヨシノ、チョウジザクラを見ることができます。河津ザクラは満開を過ぎて、葉桜になりかけています。先日は写真愛好家の望遠レンズを装着したカメラが、朝から夕方まで数台並んでいました。桜の花に飛来するヒヨドリやメジロなど、サクラの花と野鳥とのシャッターチャンスを狙っての粘りのようでした。ヤナギの木も芽吹いて黄緑色の花が咲いており、河津ザクラの濃いピンク色と好対照を演出しています。リバーサイドパークの駐車場にあるシダレザクラは、ちょうど今満開のようです。シダレザクラといえば、本町の身延山久遠寺が有名です。今朝の観光課情報では、総門が満開、仏殿前が五分咲き、報恩閣前が七分咲きで今週末が見ごろになるのではとのことです。リバーサイドパークでは、ソメイヨシノは三分咲き、チョウジ(丁子)ザクラは満開なのかもしれません。この木は野性種で花の数も少なく、花と葉が一緒に出ていることなどから、満開の時期の特定は難しいようです。名前の由来は、花の萼(ガク)が長く横から見ると丁子形に見えることから名づけられたそうです。開花状況は異なりますが、四種類のサクラの花見が今なら同時にできます。ぜひご覧あれ。

 日本人は桜が好きです。桜の花の咲く季節の春は、寒かった冬を越えて春の訪れを視覚的に私たちに示してくれ、学校に植えられていることが多く卒業式や入学式を象徴する花だからです。しかし、私の小中学校の頃は生活していた標高が高かったために、4月の中旬にならないと桜は咲きませんでした。甲府盆地底部や関東地方とでは季節で約半月以上の差がありました。入学、卒業、入社、退職など人生の節目に当たる季節の花です。一つひとつは薄いピンクの小さい花ではあるけれど、一木が一斉に開花する風情は並木や群落でなく一本のサクラでもまさに壮観そのものであります。また、その花の命が短命で半月も持たずに、あっという間に散ってしまうというそのはかなさにも日本人には心惹かれるものがあるのではないでしょうか。冬から春への季節の移り変わりは、田畑での農作業の始まりを示し、活動が活発化する躍動の季節の到来になります。桜の花はその年の明るい未来への始まりであり、出発点となるメモリアルフラワー的な存在であるのかもしれません。
日本人は桜が好きです。桜の花の咲く季節の春は、寒かった冬を越えて春の訪れを視覚的に私たちに示してくれ、学校に植えられていることが多く卒業式や入学式を象徴する花だからです。しかし、私の小中学校の頃は生活していた標高が高かったために、4月の中旬にならないと桜は咲きませんでした。甲府盆地底部や関東地方とでは季節で約半月以上の差がありました。入学、卒業、入社、退職など人生の節目に当たる季節の花です。一つひとつは薄いピンクの小さい花ではあるけれど、一木が一斉に開花する風情は並木や群落でなく一本のサクラでもまさに壮観そのものであります。また、その花の命が短命で半月も持たずに、あっという間に散ってしまうというそのはかなさにも日本人には心惹かれるものがあるのではないでしょうか。冬から春への季節の移り変わりは、田畑での農作業の始まりを示し、活動が活発化する躍動の季節の到来になります。桜の花はその年の明るい未来への始まりであり、出発点となるメモリアルフラワー的な存在であるのかもしれません。
3月25日(火)
都留アルプスは、都留アルプス会と市が協力して整備した都留市中心部にある里山ハイキングコースです。富士急行線都留市駅から東桂駅にかけて、標高500メートルから650メートルの山々に約8キロのコースや案内標識が整備されています。都留アルプス最大の見どころは、なんといってもミツマタの群生地です。このミツマタを見に出かけてきました。今年はまだ一部の花が開花しているのみで、そのほとんどが白いつぼみのままです。開花しているものは黄色い黄金色が見事で、群生地のすべてが開花したらさぞかし壮観であると思われます。時間配分やその体力度に応じて、間の駅に下れるエスケープルートも幾つも設定されているのも有難い所です。今年の開花はいつもより遅れており、今月末が桜とともに満開になるのではないかと、現地にいた地元関係者が教えてくれました。

三椏(ミツマタ)は、和紙の原料として楮(コウゾ)や雁皮(ガンピ)とともに古代から利用されてきました。ミツマタの名前は、樹の成長にしたがって枝が三又に別れて伸びることに由来します。ミツマタの強い繊維質の樹皮は、上質の和紙や紙幣の原料として利用されています。花言葉は、樹皮からくる「強靭」、三つに分かれた枝を親子にたとえたとする「肉親の絆」です。身延町には「西嶋和紙の里」があり、中世以来和紙の生産地として有名です。西嶋の「和紙製造用具」は山梨県指定文化財になっています。
3月23日(日)
昭和町押越に「曲淵」という小字があり、甲府駅からイオンモール甲府昭和に行く途中にこの名のバス停があります。武田氏の家臣にこの地域出身の、曲淵庄左衛門吉景がいます。のちに武川谷に移住して武川衆の一員として武田信玄・勝頼に仕えて、草履取りから出世して足軽大将になった武勇に優れた人物です。頑固一徹で正論をはいては曲げずに、奇人とも評されています。生涯75度の訴訟を起こして、勝訴はわずか1回、和解が1回で残りはすべて敗訴になったと言われています。(3月13日のブログ参照) また主君の信玄から、自分への褒美として賜った脇差を、気に入らないから投げ返したという逸話も伝わっています。
 吉景及びその子孫は、武田氏滅亡後に徳川家康に従い、天正壬午の乱や関ケ原の戦い、大坂の陣で活躍し、子孫は徳川幕府でも江戸北町奉行など要職についています。吉景から五代目にあたる景衡は、享保10年(1725)に追手甲府勤番支配となり、配下の武将百七十騎を従えて祖先の館跡であり墓のある本妙寺に参拝を果たしています。「八幡宮」の神号旗二旒と願文は、本妙寺とその鎮守である八幡宮に奉納されたもので、昭和町指定文化財となっています。
吉景及びその子孫は、武田氏滅亡後に徳川家康に従い、天正壬午の乱や関ケ原の戦い、大坂の陣で活躍し、子孫は徳川幕府でも江戸北町奉行など要職についています。吉景から五代目にあたる景衡は、享保10年(1725)に追手甲府勤番支配となり、配下の武将百七十騎を従えて祖先の館跡であり墓のある本妙寺に参拝を果たしています。「八幡宮」の神号旗二旒と願文は、本妙寺とその鎮守である八幡宮に奉納されたもので、昭和町指定文化財となっています。
3月17日(月)
甲府城御金蔵破り事件について、再確認してみたいと思います。概要は15日のブログにあるとおりです。犯人についてはわからないまま迷宮入りになるかと思われましたが、事件から8年後に高畑村の百姓次郎兵衛が逮捕されました。次郎兵衛の白状した陳述書によると、片羽町口の門から追手前の腰掛に潜んで暗くなるのを待ち、午後8時過ぎ橋を渡り、石垣を伝って壊れた鉄砲狭間(てっぽうざま)から城内に入った。それから追手渡櫓(おうてわたりやぐら)の戸前の錠を持参の道具でこじ開け、御金箱の錠もねじ切って、御金包みを十包盗み出したという。高畑村の自宅に帰り、盗んだ金を自宅前のわら積みの中に隠し、村内の住吉社に行って世の明けるのを待ってそ知らぬ顔で帰宅したという。
 盗み出した金は、甲金千二十九両三分、小判三百九十三両二分、合計金千四百二十三両一分であった。盗み取った金は、一包だけ当分使い用とし残りを芋畑に埋め、後日また掘り出して壺に甲金を入れ、小判をその上に蓋をするように入れて、居宅のエノキの大木の根元に埋めたという。土中に一旦埋納してほとぼりが冷めたころお金を掘り返し、小判や甲州金は少しずつ両替して使い勝手の良い小額貨幣に交換して使用していたという。次郎兵衛は急に羽振りがよくなり、奉公人を雇い、田畑家財を買い込むなど不相応な暮らしぶりへの変化に、近所の誰もが悪い疑いをかけなかったのは日頃の次郎兵衛の行いの勤勉さが影響したのでしょうか。
盗み出した金は、甲金千二十九両三分、小判三百九十三両二分、合計金千四百二十三両一分であった。盗み取った金は、一包だけ当分使い用とし残りを芋畑に埋め、後日また掘り出して壺に甲金を入れ、小判をその上に蓋をするように入れて、居宅のエノキの大木の根元に埋めたという。土中に一旦埋納してほとぼりが冷めたころお金を掘り返し、小判や甲州金は少しずつ両替して使い勝手の良い小額貨幣に交換して使用していたという。次郎兵衛は急に羽振りがよくなり、奉公人を雇い、田畑家財を買い込むなど不相応な暮らしぶりへの変化に、近所の誰もが悪い疑いをかけなかったのは日頃の次郎兵衛の行いの勤勉さが影響したのでしょうか。
 甲府城には享保12年(1724)に屋形曲輪の中に御金蔵がありましたが、甲府の武家屋敷から出火した大火が城内にも飛び火して焼失したので、いざというとき持ち出しやすいようにと追手渡櫓内に領内から徴収した税金を保管していたといいます。この御金蔵破り事件以来、寛保4年(1744)に城内に御金蔵を新設し追手渡櫓から金を移しました。御金蔵は、鍛冶曲輪門の北西側で「舞鶴通」のあたりになります。明治になってお城が廃城になるとこの付近に甲府中学が置かれ、御金蔵は体育倉庫として使われていました。昭和5年に朝日公園に移築され、御金蔵稲荷社となりましたが甲府空襲によって焼失し、現在の建物は2代目になります。この稲荷社は御金蔵破り事件のこともあって、盗難除けにご利益があるとのことです。
甲府城には享保12年(1724)に屋形曲輪の中に御金蔵がありましたが、甲府の武家屋敷から出火した大火が城内にも飛び火して焼失したので、いざというとき持ち出しやすいようにと追手渡櫓内に領内から徴収した税金を保管していたといいます。この御金蔵破り事件以来、寛保4年(1744)に城内に御金蔵を新設し追手渡櫓から金を移しました。御金蔵は、鍛冶曲輪門の北西側で「舞鶴通」のあたりになります。明治になってお城が廃城になるとこの付近に甲府中学が置かれ、御金蔵は体育倉庫として使われていました。昭和5年に朝日公園に移築され、御金蔵稲荷社となりましたが甲府空襲によって焼失し、現在の建物は2代目になります。この稲荷社は御金蔵破り事件のこともあって、盗難除けにご利益があるとのことです。
3月15日(土)
甲府市相生三丁目に仏国寺というお寺があります。日蓮宗の寺院で、先日甲府勤番士の墓の写真を撮影するために同寺を訪ねたとき、かつて調べたことのある甲府城御金蔵破りに関係する鬼子母神像を再びお参りしてきました。甲府御金蔵破りは、享保19年(1734)12月24日の夜、甲府城内に盗賊が侵入し御金蔵が破られたという事件です。盗賊により小判や甲州金約1,400両が盗まれ、甲府勤番支配の2名が処分され、当直の勤番士など関係者が罰せられました。犯人は寛保2年(1742)に逮捕され、市中引き回しの上磔刑に処せられています。
 仏国寺の鬼子母神は、江戸幕府より甲府勤番を命じられた福島彦四郎が甲府の長禅寺前に居宅を構えたとき、もとから地内に祀られていた尊神を自分の屋敷内に移転安置したことに由来。当夜宿直にあたっていた彦四郎は、その前夜日頃信仰するこの鬼子母神が夢に現れ、「明日の宿直は他に依頼すべし」とお告げがあったので同僚に交代を依頼した。当夜甲府城各御門の警備にあたっていた勤番士(平間、原田、小俣ほか)は、職務怠慢、虚偽報告、賭博などの罪により厳しく処分されています。鬼子母神の霊夢によって危うく大難を免れた彦四郎は、霊験あらたかなこの尊神を個人としてのみ崇拝することは恐れ多いことと思い、代わってもらった同僚一族の菩提の供養と福島一族の繁栄を願って、菩提寺の仏国寺の守護神として安置奉遷したとされています。こんな魔訶不思議な話が伝えられていて、その尊像が現実に存在するとは驚きです。
仏国寺の鬼子母神は、江戸幕府より甲府勤番を命じられた福島彦四郎が甲府の長禅寺前に居宅を構えたとき、もとから地内に祀られていた尊神を自分の屋敷内に移転安置したことに由来。当夜宿直にあたっていた彦四郎は、その前夜日頃信仰するこの鬼子母神が夢に現れ、「明日の宿直は他に依頼すべし」とお告げがあったので同僚に交代を依頼した。当夜甲府城各御門の警備にあたっていた勤番士(平間、原田、小俣ほか)は、職務怠慢、虚偽報告、賭博などの罪により厳しく処分されています。鬼子母神の霊夢によって危うく大難を免れた彦四郎は、霊験あらたかなこの尊神を個人としてのみ崇拝することは恐れ多いことと思い、代わってもらった同僚一族の菩提の供養と福島一族の繁栄を願って、菩提寺の仏国寺の守護神として安置奉遷したとされています。こんな魔訶不思議な話が伝えられていて、その尊像が現実に存在するとは驚きです。
3月13日(木)
通勤途中で「信陽○○株式会社」の会社名の表示を目にしました。「信陽」は信濃の国の美称であるので、同様の名称である甲斐の「甲陽」について少し考えてみました。『甲陽軍鑑』や『甲陽日記』、『甲陽随筆』など戦国時代から江戸時代の資料においては、この「甲陽」を「甲斐」の別称として使用されることが散見します。「信陽」も「甲陽」も、旧国名のはじめの一字の後につけて美称として用いられたものです。例をあげると「武蔵」が「武陽」、「紀伊」が「紀陽」などとして使われており、現在でも地銀の銀行名や高校大学などの学校名や地域に根差す会社名などに、ご当地を意識した名称として使用されています。旧国名の後ろの一字をとっても、「出羽」の「羽陽」、「出雲」の「雲陽」のようにも用いられています。「陽」の漢字は、太陽の当たる場所、明るい場所、陰陽と対比してプラス、暖かい、積極的といった意味があります。
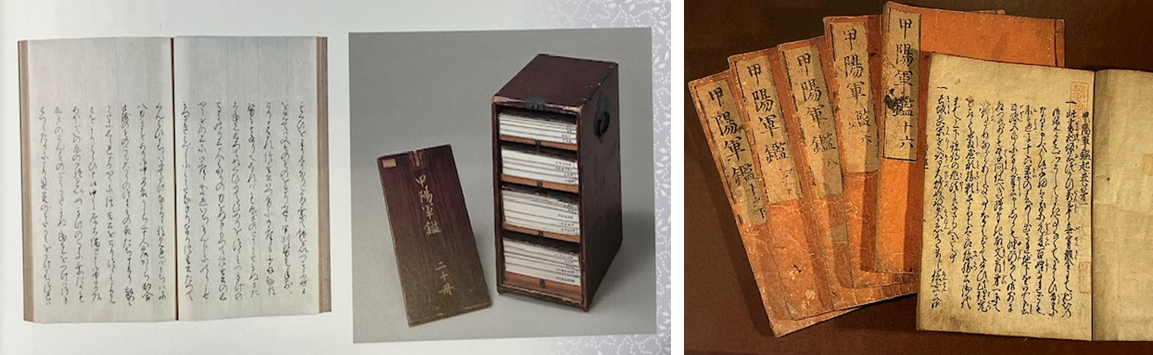 『甲陽軍鑑』は、戦国武将武田信玄・勝頼時代の軍事・戦術を江戸時代初期にまとめられた軍学書です。「金」についての記述も多く、山梨県立博物館の海老沼真治氏が「『甲陽軍鑑』における金の使用事例」としてまとめられています。『甲陽軍鑑』の中には、「碁石金(ごいし金)」、「金子」、「金銀」の使用例が報告されています。河原村伝兵衛に陣中における戦の褒美として信玄自身の手から「ごいし金」を三すくい与えたとした記述、清白寺(山梨市)への供養・祈祷料として「金子廿両もたせ」遣わした記述、「金銀」を褒美としての下賜することや町人が蓄財に用いている記述、曲淵庄左衛門の訴訟で贈答品を送らなかったから負けたのだと言ったことに対し奉行人の桜井が「金銀・米銭」を車に積んできたとしても理が無ければ負けであると言い放った記述などに見られます。
『甲陽軍鑑』は、戦国武将武田信玄・勝頼時代の軍事・戦術を江戸時代初期にまとめられた軍学書です。「金」についての記述も多く、山梨県立博物館の海老沼真治氏が「『甲陽軍鑑』における金の使用事例」としてまとめられています。『甲陽軍鑑』の中には、「碁石金(ごいし金)」、「金子」、「金銀」の使用例が報告されています。河原村伝兵衛に陣中における戦の褒美として信玄自身の手から「ごいし金」を三すくい与えたとした記述、清白寺(山梨市)への供養・祈祷料として「金子廿両もたせ」遣わした記述、「金銀」を褒美としての下賜することや町人が蓄財に用いている記述、曲淵庄左衛門の訴訟で贈答品を送らなかったから負けたのだと言ったことに対し奉行人の桜井が「金銀・米銭」を車に積んできたとしても理が無ければ負けであると言い放った記述などに見られます。
 「甲陽」の名称は、現在の山梨県内でも会社名、学校名に使用されています。江戸時代に柳沢氏が甲府藩の藩主から大和郡山藩に転封以後、甲斐国は江戸幕府の天領(直轄領)になり、ここに勤めることになった甲府勤番士たちは「甲陽勤士」ともいわれ、当時の彼らの墓石にその名が刻まれています。彼らの仕事は甲府城の守備警護や甲府城下の行政や治安を司り、大手・山手の二班の勤番支配のもと体勢総勢200人が新たに江戸から送り込まれてきました。彼らは旗本の次男坊三男坊が主で、ひとたび辞令が下ると一生江戸には帰れないとされ、「山流し」として当時から揶揄され左遷組の代表格として悲嘆にくれたそうです。(2024年4月28日のブログ参照)
「甲陽」の名称は、現在の山梨県内でも会社名、学校名に使用されています。江戸時代に柳沢氏が甲府藩の藩主から大和郡山藩に転封以後、甲斐国は江戸幕府の天領(直轄領)になり、ここに勤めることになった甲府勤番士たちは「甲陽勤士」ともいわれ、当時の彼らの墓石にその名が刻まれています。彼らの仕事は甲府城の守備警護や甲府城下の行政や治安を司り、大手・山手の二班の勤番支配のもと体勢総勢200人が新たに江戸から送り込まれてきました。彼らは旗本の次男坊三男坊が主で、ひとたび辞令が下ると一生江戸には帰れないとされ、「山流し」として当時から揶揄され左遷組の代表格として悲嘆にくれたそうです。(2024年4月28日のブログ参照)
3月9日(日)
絵馬の奉納は、町内のいくつかの神社でも確認することができます。三沢の十五所神社の拝殿には、鶴の絵が描かれた文化7年(1810)の絵馬があります。絵馬は雲間に鶴が飛ぶ姿を彩色で表現しています。輪郭線や文字を掘り窪めて彫刻しているので、この溝部分に残された顔料によって全体像が確認できます。また風景か境内を描いた絵馬は、平面に描かれているので風化のため顔料が変色したり取れてしまって、何が描かれているのか全体像を把握することができません。両者ともに1メート以上ある大型の絵馬です。産土神として、三沢地域の人々の篤い願いが込められています。江戸時代など古い時代の絵馬は大きく製作されており、額装のように縁が作られています。現代の絵馬のように、一枚板で五角形のものとは作りが異なっています。
3月8日(土)

甲府市に「天神町」という町があります。町内に国立甲府病院があり山梨大学甲府キャンパスの南西に隣接する地域です。天神町の名前は、古くから梅屋敷の天神と称される天満宮が存在している事に由来するといいます。現在この地には、梅屋敷公会堂が天満宮の拝殿と兼用で建てられています。この天満宮は、武田信玄時代に越後の上杉謙信の家中を離れ、武田家の家臣となった大熊備前守朝秀の屋敷の鎮守として祀られたものとの伝承があります。ここの小字は「大熊」であり、伝承と符号しています。彼の屋敷の天神様には梅の木がたくさん植栽されていたものと思われ、屋敷自体が「梅屋敷」と呼ばれていたのかもしれません。大熊朝秀は戦国時代の武将で、はじめ上杉謙信、後に武田信玄に仕えました。長尾景虎(上杉謙信)の出家騒動の時、信玄に内通して反旗を翻し、誘いを受けて甲府にきて山県昌景の与力となり、やがて戦場で活躍して信玄の直臣となり侍大将に採りたてられています。信玄・謙信が亡くなった後、武田氏と上杉氏の同盟(甲越同盟)の成立にあたり貢献した人物です。武田家が滅亡する天目山の戦いのとき、離反する家臣が多い中最後まで勝頼とともに行動しています。
 天神様として祀られている菅原道真と梅との関係は、3/2のブログで説明しましたので参照してみてください。天神様は学問の神様として、特にこの時期は合格祈願の受験生でにぎわって絵馬を奉納することが行われています。絵馬といえば本町瀬戸の方外院の千疋絵馬が有名です。日本最大級の絵馬です。絵馬は本来神社や寺院に祈願するとき、または祈願した願いがかなったときにお礼として奉納するための板に描かれた馬の絵です。本来は神様の乗り物として生きた馬を奉納していたと「常陸風土記」や「続日本紀」にあり、時代が下るようになって粘土で造形された土馬や、木や石で彫刻された馬が奉納されるようになり、現在のような個人の祈願のための絵馬に変わってきました。山梨県内では、土馬は金峰山頂で発見され山梨県立博物館に展示されており、木製の馬は南アルプス市鷹尾穂見神社境内、石製の馬は昭和町義清神社境内で見ることができます。本物の馬は冨士山下宮小室浅間神社の神馬舎に奉納されています。
天神様として祀られている菅原道真と梅との関係は、3/2のブログで説明しましたので参照してみてください。天神様は学問の神様として、特にこの時期は合格祈願の受験生でにぎわって絵馬を奉納することが行われています。絵馬といえば本町瀬戸の方外院の千疋絵馬が有名です。日本最大級の絵馬です。絵馬は本来神社や寺院に祈願するとき、または祈願した願いがかなったときにお礼として奉納するための板に描かれた馬の絵です。本来は神様の乗り物として生きた馬を奉納していたと「常陸風土記」や「続日本紀」にあり、時代が下るようになって粘土で造形された土馬や、木や石で彫刻された馬が奉納されるようになり、現在のような個人の祈願のための絵馬に変わってきました。山梨県内では、土馬は金峰山頂で発見され山梨県立博物館に展示されており、木製の馬は南アルプス市鷹尾穂見神社境内、石製の馬は昭和町義清神社境内で見ることができます。本物の馬は冨士山下宮小室浅間神社の神馬舎に奉納されています。
3月3日(月)
「渡唐天神像」の賛を書いた策彦周良(さくげんしゅうりょう)は、大変な人物です。室町幕府の命を受け二度にわたって中国(明)に渡って日明貿易の副使、正使として活躍し、その学徳から今川義元の詩歌会に招かれ、正親町天皇や織田信長とも交流がありました。武田信玄にも弘治元年(1555)招かれて恵林寺の住職になっており、翌年帰京するにあたり身延道を通って下山に宿泊しました。その際に策彦和尚は穴山信友の下山館を訪問し、信友正室の南松院殿(信玄の姉)から法号を頼まれ、「葵庵理誠尼(きあんりせいに)」という法号を授けました。その由来について永禄5年(1562)に策彦和尚が記した字号記があります。「絹本著色穴山信友夫人像一幅付紙本墨書葵庵字号」として、画像とともに山梨県指定文化財になっています。これによりきわめて信仰心の篤い夫人であったことが窺え、またその容貌は唐時代の美人の「馬郎婦」のように美しく、総持尼のような聡明な眼をしていることが、画像の賛に書かれています。

3月2日(日)
身延町下山の南松院に、「紙本著色渡唐天神像」があります。南照院は、穴山梅雪(信君)が母(南松院殿)の菩提寺として、下山に建立した臨済宗のお寺です。山梨県指定の文化財になっている名称には、これが用いられています。「紙本」は書かれた素材が紙であること、「著色」は着色と同じで顔料をもって彩色を施していること、「渡唐天神像」は唐に渡った天神様すなわち菅原道真公の姿が描かれたものです。絵の作者は不明ですが、縦長の料紙の上部に賛と呼ばれる策彦周良の詩文が書かれています。策彦は戦国時代の臨済宗の高僧で、南松院殿が深く帰依していたと伝えられています。おそらく彼女の遺品だったと思われます。
天神様すなわち菅原道真公は平安時代の貴族で、優れた人間性とその頭の回転の良さで学者の家柄から異例の大出世をした政治家です。しかし、その時のライバル藤原時平などの反感を買い、陰謀によって九州の太宰府に左遷されてしまいます。左遷されてから三年後、大宰府で非業の死を遂げます。亡くなられた後、京都では陰謀に加担した貴族たちが落雷で命を落とし、時平や皇太子さらに後には時の醍醐天皇までも突然死を遂げ、疫病や洪水、干ばつといった天変地異が続くようになりました。これは菅原道真が怨霊となって引き起こしたものだと考えられるようになり、「天神」・「雷神」として災いを起こす祟り神であるとされました。このような祟りを鎮めるために、京都に北野天満宮、九州に大宰府天満宮が造営されたのです。道真公は京都の邸宅に梅の木を植えて大切に育てており、左遷が決まった時に詠んだ「東風(こち)吹かば匂いおこせよ梅の花 主(あるじ)なしとて春な忘れそ」(家の主である私が大宰府に行ってしまっても春を忘れないで花を咲かせ、都から西に向かって吹く東風にのせて梅の匂いを大宰府まで届けてくれ)の歌が有名です。また、大宰府に行ってしまった道真公を追って、一夜でこの梅が飛んで行ってしまったという「飛梅」伝説も広く知られています。梅と天神様は切っても切れない関係があります。
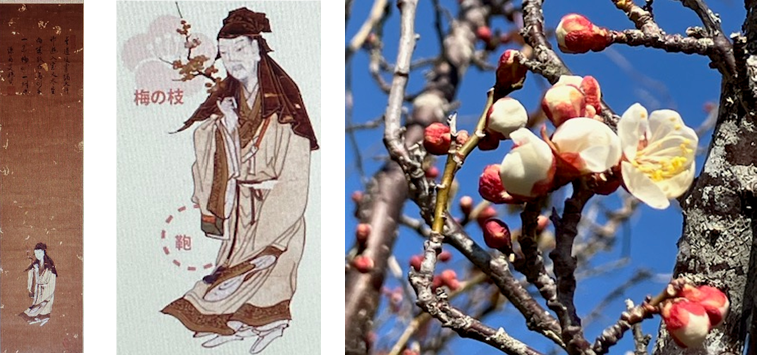
南松院の「紙本著色渡唐天神像」をもう一度見てみましょう。この絵は天神様が一夜で中国にわたり「無準師範(ぶじゅんしばん)」に参禅するという説話を描いたものです。唐服の袖や裾が風になびく立ち姿で、手には梅の枝を持ち授与された袈裟が入っているというかばんを肩に掛けています。渡唐天神像は、このほか恵林寺・一蓮寺・長禅寺等にも同時代のものが伝存し、武田氏との強い関連が伺える作品群の一つです。
2月27日(木)
今日はあったかくなりました。気温は、身延町切石で14度まで上がりました。先週の最強最長の寒波はどこに行ってしまったのでしょうか。春は確実にやってきています。今朝の昭和町の我が家の庭先の紅梅も、妻の実家の身延町常葉の白梅も咲き始めていました。

梅は松竹梅の語順では、上中下の下にランクされてしまいますが、春を告げる花といえばなんといっても梅ですね。紅梅は庭木で花を愛でるだけですが、数が少ないですが実も付けます。熟して小鳥の餌になります。白梅は畑の隅に植えてあり、小梅が生ります。ただ剪定をしていないので、たくさん生るのですが大きくなりません。「桜斬るバカ梅斬らぬバカ」と言うように、切ろうと思っているうちに花が咲いてしまいました。今年も使いようのないミニサイズの梅がたくさん生るのではないかと思います。今年も梅斬らぬバカになってしまいました。
2月24日(月)
今日は昨日の天皇誕生日の振替休日です。三連休の最終日になります。昨日2月23日は「天皇の誕生日」であると同時に、「富士山の日」でもありました。2.23はフジサンの語呂合わせから、記念日として制定されました。
今の天皇陛下は、第126代「今上(きんじょう)天皇」といいます。アレ、令和の元号だから令和天皇じゃないの?と思った方も多いと思います。明治天皇、大正天皇、昭和天皇とは言いますが、125代の明仁上皇陛下も平成天皇とは言いません。なぜ平成天皇や令和天皇と言わないのでしょうか。それは「(元号)天皇」の呼び方が、諡(おくりな)だからです。「諡」とは人が亡くなった後に、生前の功績を讃えて贈る名前だからです。「(元号)天皇」の呼び方は、天皇陛下が崩御されて(亡くなって)からはじめて贈られる名前なので、生前では使用されないものなのです。なので、現在在位中の天皇陛下については、今上天皇という呼称を用いるのです。同様に上皇は退位した天皇のことで、ご存命ですから「平成天皇」のような呼び方はしてはならないのです。明治天皇以降、元号は一世一代限りとされ、諡としてそのまま用いられるようになりました。
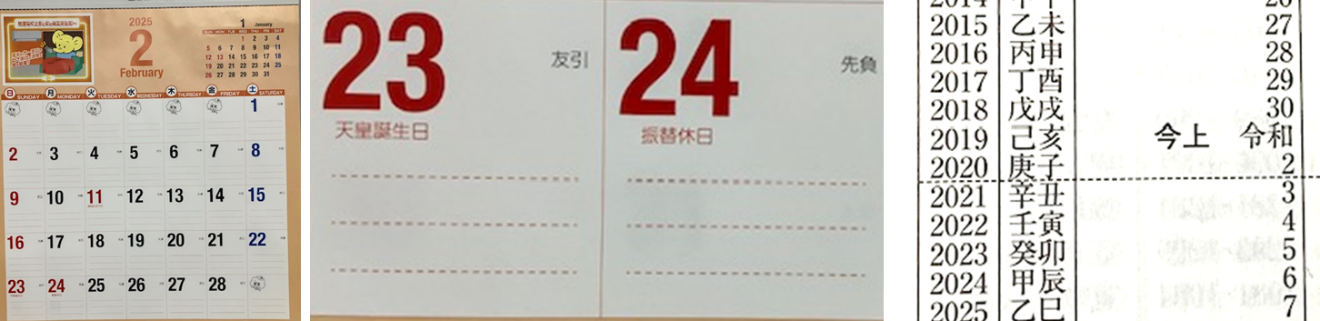 一般の国民には名字と名前がありますが、天皇陛下や皇族の方々には名字は無く名前のみです。天皇陛下の実名であるお名前は、「徳仁(ナルヒト)」です。実名は諱(いみな・忌み名)とも言って、直接呼ぶことは呪術の対象となるためこれを使用することははばかられます。ただし、天皇家には名字がない代わりに「御称号」があります。幼少時の「浩宮(ひろのみや)」様と呼ばれていたこの「〇宮」というのが御称号です。御称号は、皇太子になった時に使われなくなります。現在では「天皇陛下」の呼称が一般には使われます。実名では、男子皇族の場合は「〇仁」、女性皇族の場合は「〇子」という名前が多く使われています。昭和天皇は「裕仁」が実名であって私の名前の「祐仁」と文字が近いこと、「徳仁」天皇とは年齢が近いこと(学年で一個下)などから、浩宮様から皇太子の時代頃までよく雰囲気や外見が似ていると言われていました。ただし、育った環境の違いなどで、現在のこの明確な違いは何なのでしょうか、、、。(名前については、武田信玄を例に去年の8月14日の「シン・ドウノヘヤ」にも書きましたので参考に見てください。)
一般の国民には名字と名前がありますが、天皇陛下や皇族の方々には名字は無く名前のみです。天皇陛下の実名であるお名前は、「徳仁(ナルヒト)」です。実名は諱(いみな・忌み名)とも言って、直接呼ぶことは呪術の対象となるためこれを使用することははばかられます。ただし、天皇家には名字がない代わりに「御称号」があります。幼少時の「浩宮(ひろのみや)」様と呼ばれていたこの「〇宮」というのが御称号です。御称号は、皇太子になった時に使われなくなります。現在では「天皇陛下」の呼称が一般には使われます。実名では、男子皇族の場合は「〇仁」、女性皇族の場合は「〇子」という名前が多く使われています。昭和天皇は「裕仁」が実名であって私の名前の「祐仁」と文字が近いこと、「徳仁」天皇とは年齢が近いこと(学年で一個下)などから、浩宮様から皇太子の時代頃までよく雰囲気や外見が似ていると言われていました。ただし、育った環境の違いなどで、現在のこの明確な違いは何なのでしょうか、、、。(名前については、武田信玄を例に去年の8月14日の「シン・ドウノヘヤ」にも書きましたので参考に見てください。)
2月18日(火)
松はアカマツやクロマツなど、山や公園、庭や海岸などにごく普通に見られるなじみ深い植物です。二次林として山に植栽されたアカマツや、海岸沿いに防潮林として植えられるクロマツがあります。下部リバーサイドパークにも下部川沿いに、何本か主幹の頭を短く剪定されたアカマツが植えられています。松は針のような葉を持ち、松ぼっくりの実をつけ、樹脂のような樹液が特徴的な木です。厳しい環境下でも生育し、冬でも青々とした生命力を感じさせるその姿は、不老長寿の象徴とされてきました。神様の宿る縁起の良い木として、「神を待つ」、「神をまつる」神聖な木とされてきました。これがマツの名前の由来との説が有力です。松は樹脂がたくさんあることから、戦時中には松根油が採集され、松明として灯りになり、その煤(すす)から墨が作られたりもしました。その火力の強さから、陶磁器窯の薪としても利用されました。
 飲食店のメニューやサービスのランクとして、「松竹梅」が使われています。すし店やソバ店など和食店でのランクでは、特上を松、上を竹、並を梅にするケースが多く、一番安い並やぜいたくな特上は注文がしにくいという客側への配慮から、間接的な表現が使われるようになったと言われています。本来縁起の良い植物の松竹梅には優劣はないのですが、「松➡竹➡梅」の順番になっています。これは縁起物となった歴史の古さの順番から、松の平安時代、竹の室町時代、梅の江戸時代からくるという説が一般的です。当博物館の松飾り(門松)にも松竹梅を使っており、松の不老長寿、竹の成長力、梅の気高さの象徴として飾っています。寒い時季でも松と竹は緑を保ち、梅は寒い時期に開花する画題として、中国の「歳寒三友」がその元になっています。
飲食店のメニューやサービスのランクとして、「松竹梅」が使われています。すし店やソバ店など和食店でのランクでは、特上を松、上を竹、並を梅にするケースが多く、一番安い並やぜいたくな特上は注文がしにくいという客側への配慮から、間接的な表現が使われるようになったと言われています。本来縁起の良い植物の松竹梅には優劣はないのですが、「松➡竹➡梅」の順番になっています。これは縁起物となった歴史の古さの順番から、松の平安時代、竹の室町時代、梅の江戸時代からくるという説が一般的です。当博物館の松飾り(門松)にも松竹梅を使っており、松の不老長寿、竹の成長力、梅の気高さの象徴として飾っています。寒い時季でも松と竹は緑を保ち、梅は寒い時期に開花する画題として、中国の「歳寒三友」がその元になっています。
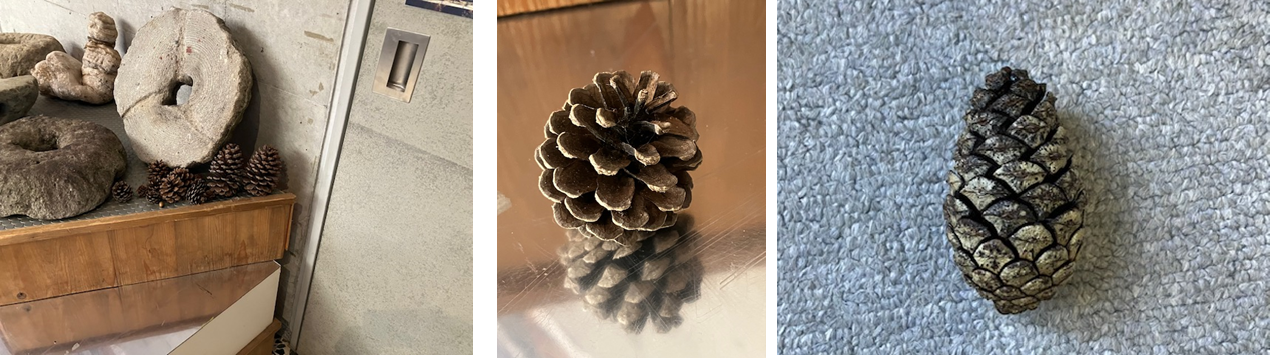 松ぼっくり(松かさ)は、マツ科マツ属が付ける球果と呼ばれる果実のことです。松ぼっくりの鱗片には、もともと羽の付いたタネが一つずつ入っているのです。春に受粉しためしべが成長し、春から夏に緑色の実となり秋ごろに茶色く変色し越冬して翌年の春に再び大きくなって、秋に鱗片が開いてタネを飛ばすのだそうです。2年かけてタネを成熟させ、タネを放出して役目を終えた松ぼっくりが落ちることになります。松ぼっくりには、湿っているとカサが閉じ乾燥すると開く性質があります。当館の前の石臼の展示しているところに松ぼっくりが、置いてあります。これを水につけてしばらく放置していたところ、マツカサが閉じていました。真ん中の松ぼっくりと右端のものは同一個体です。
松ぼっくり(松かさ)は、マツ科マツ属が付ける球果と呼ばれる果実のことです。松ぼっくりの鱗片には、もともと羽の付いたタネが一つずつ入っているのです。春に受粉しためしべが成長し、春から夏に緑色の実となり秋ごろに茶色く変色し越冬して翌年の春に再び大きくなって、秋に鱗片が開いてタネを飛ばすのだそうです。2年かけてタネを成熟させ、タネを放出して役目を終えた松ぼっくりが落ちることになります。松ぼっくりには、湿っているとカサが閉じ乾燥すると開く性質があります。当館の前の石臼の展示しているところに松ぼっくりが、置いてあります。これを水につけてしばらく放置していたところ、マツカサが閉じていました。真ん中の松ぼっくりと右端のものは同一個体です。
2月17日(月)
博物館の構内は山に接しているため、日陰で湿り気が強くコケ類には最適な環境が整っています。コンクリートの壁面や石の上、植栽の間、屋根の上にもたくさんの種類のコケが繁茂しています。10℃を越える春の到来を感じさせるこの季節になると、先日の雨もあって、乾燥して勢いがなく茶色に近かったコケに緑色や黄緑色の部分も観察できるようになってきました。
 コケは日本に約1700種類あるといわれ、地表や岩の上に這いつくばるように成長して広がっていきます。日本庭園やテラリウムや苔玉など、鑑賞用にも人気があります。苔寺で有名な京都の西芳寺は夢窓礎石の作庭とされ、上段に日本最古と言われる枯山水の石組が残り、下段が池泉回遊式の庭園です。苔で有名なのは下段の庭園で、黄金池と呼ぶ心字池を配し、金閣寺や銀閣寺のモデルになったと言われています。夢窓国師は甲斐の市川荘平塩寺で仏教を学び、禅宗や禅宗系庭園を全国に広めた仏教界の巨人です。
コケは日本に約1700種類あるといわれ、地表や岩の上に這いつくばるように成長して広がっていきます。日本庭園やテラリウムや苔玉など、鑑賞用にも人気があります。苔寺で有名な京都の西芳寺は夢窓礎石の作庭とされ、上段に日本最古と言われる枯山水の石組が残り、下段が池泉回遊式の庭園です。苔で有名なのは下段の庭園で、黄金池と呼ぶ心字池を配し、金閣寺や銀閣寺のモデルになったと言われています。夢窓国師は甲斐の市川荘平塩寺で仏教を学び、禅宗や禅宗系庭園を全国に広めた仏教界の巨人です。
 博物館で見られる苔は、シノブゴケ、ホソウリゴケ、エゾスナゴケ、ギンゴケなどです。サザンカの植栽の下にはおもにシノブゴケ、下部リバーサイドパークのメロディブリッヂ付近のホソウリゴケやギンゴケ、駐車場や通路のホソウリゴケやシノブゴケ、倉庫や公衆トイレの屋根のエゾスナゴケやギンゴケなどです。その他、名前の特定の難しいコケもたくさんあります。
博物館で見られる苔は、シノブゴケ、ホソウリゴケ、エゾスナゴケ、ギンゴケなどです。サザンカの植栽の下にはおもにシノブゴケ、下部リバーサイドパークのメロディブリッヂ付近のホソウリゴケやギンゴケ、駐車場や通路のホソウリゴケやシノブゴケ、倉庫や公衆トイレの屋根のエゾスナゴケやギンゴケなどです。その他、名前の特定の難しいコケもたくさんあります。
 我が家の庭は、造園業者に二十数年前に造成地に作ってもらったものです。竣工直後はコケが繁茂する立派な庭園だったのですが、いつしかコケも少なくなってしまいました。頻繁に散水するように言われていたのですが、なかなかコケは減少の一途をたどってとまりません。繁茂すると厄介なゼニゴケはいつの間にか広がっているのに、山や畑から移植したシノブゴケやエゾスナゴケはいつしか乾燥によって茶色くなってしまいます。環境が違うので一概に何とも言えませんが、博物館の周辺のように苔むす状態の庭に再現したいところです。
我が家の庭は、造園業者に二十数年前に造成地に作ってもらったものです。竣工直後はコケが繁茂する立派な庭園だったのですが、いつしかコケも少なくなってしまいました。頻繁に散水するように言われていたのですが、なかなかコケは減少の一途をたどってとまりません。繁茂すると厄介なゼニゴケはいつの間にか広がっているのに、山や畑から移植したシノブゴケやエゾスナゴケはいつしか乾燥によって茶色くなってしまいます。環境が違うので一概に何とも言えませんが、博物館の周辺のように苔むす状態の庭に再現したいところです。
2月13日(木)
この冬最強最長の寒波も一段落し、比較的暖かい朝を迎えました。昨日も慈雨となり、周辺の山々の雪も少なくなってきました。休みの前まで寒い日が続いて博物館日記にもあるように、東北や北陸など雪国の大雪のニュース映像は自然の驚異を感じていました。少し暖かくなってくると、今度は雪崩や屋根の落雪事故などまた違った災害の恐れも増えてきます。雪国の皆さんには、十分お気を付けていただきたいと思います。
 金山博物館のある場所は山の影になっていて、この時季日中でも窓から陽が差し込むことはないので寒さもひとしおです。とにかく鉄筋コンクリートの建物内部は、よく冷え切っています(もちろん暖房はしています)。身延町は役場のある切石が観測地点になるのですが、2月の初旬はマイナス5度前後の日が続き、9日にはマイナス6.8℃を記録しました。節分も過ぎて暦の上では春だというのに、まだまだ寒い日が続いていました。1月下旬に比較的暖かい日が続いたので、博物館の入口にパンジー、ビオラ、プリムラを近くのホームセンターで購入してきて20株ほど植えてみました。植えた直後はきれいに咲きそろっていたのですが、寒さで花も葉も萎れてしまい元気がありません。天気は良くても気温が上がらないので、せっかくの花が台無しになってしまいました。博物館の入り口部分の花壇は、これまで花などが育たないと聞いていましたので、植えてみたのですが少し早かったのかもしれません。それでも三寒四温で、暖かい春は着実に進んできています。春の芽吹きと桜の開花が待ち遠しいですね
金山博物館のある場所は山の影になっていて、この時季日中でも窓から陽が差し込むことはないので寒さもひとしおです。とにかく鉄筋コンクリートの建物内部は、よく冷え切っています(もちろん暖房はしています)。身延町は役場のある切石が観測地点になるのですが、2月の初旬はマイナス5度前後の日が続き、9日にはマイナス6.8℃を記録しました。節分も過ぎて暦の上では春だというのに、まだまだ寒い日が続いていました。1月下旬に比較的暖かい日が続いたので、博物館の入口にパンジー、ビオラ、プリムラを近くのホームセンターで購入してきて20株ほど植えてみました。植えた直後はきれいに咲きそろっていたのですが、寒さで花も葉も萎れてしまい元気がありません。天気は良くても気温が上がらないので、せっかくの花が台無しになってしまいました。博物館の入り口部分の花壇は、これまで花などが育たないと聞いていましたので、植えてみたのですが少し早かったのかもしれません。それでも三寒四温で、暖かい春は着実に進んできています。春の芽吹きと桜の開花が待ち遠しいですね
2月10日(月)
穴山氏は武田氏から分流した一族で、韮崎市の穴山が発祥の地です。塩川と釜無川とに挟まれた七里が岩の台地の上に位置します。穴山の地名は、韮崎穴の明神(現在の若宮八幡宮)に通じる洞穴が当地にあったことに由来すると『甲斐国志』にはあります。南北朝時代(14世紀中頃)、武田信武の四男義武が穴山に領地を与えられ、穴山氏を称したとされるのが通説です。義武は信武とともに足利尊氏に仕え、南北朝の動乱期に北朝方として戦って活躍したとされています。南北朝の統一によって足利幕府体制が確立した時、南朝方に味方し当時河内地方を支配していた南部氏一族は、甲州の旧領を捨てて奥州に移っていきました。その結果南部氏の跡が穴山氏に与えられたとされ、それは実子のいなかった義武が武田本家の信武の孫満春を養子に迎えた時か、満春の養子信介の時代に河内地方に進出してきたと言われています。
 穴山駅の穴山氏発祥の地の看板 穴山氏菩提寺大龍山満福寺 穴山氏一族の墓
穴山駅の穴山氏発祥の地の看板 穴山氏菩提寺大龍山満福寺 穴山氏一族の墓
中央本線の穴山駅には、穴山氏発祥の地の看板と穴山氏関連の史跡の案内板があります。付近には穴山氏の居館跡、氏神の若宮八幡神社跡地、菩提寺の満福寺には穴山氏代々の墓があります。穴山氏の墓所は韮崎市の史跡に指定されており、寺記には穴山信君の墓とされていますが、宝篋印塔や五輪塔の墓石の形式から義武や満春の墓の可能性が高いと考えられます。
2月9日(日)
南松院は、身延町下山にある臨済宗妙心寺派の寺院です。もとは当地の北西方向の南松院平に南北朝時代後半(14世紀)に創建され、穴山梅雪(信君のぶただ)が亡母の菩提寺として、母の隠棲地だった現在地に中興したとされています。寺名の由来は、当地の南に夫人の愛でていた老松があったことにちなむそうです(寺の説明板より)。穴山梅雪の母葵庵尼(きあんに)は、武田信虎の次女で信玄の姉にあたり、美人の誉れ高く信仰心が篤かった人物と言われています。永禄九年(1566)に夫人は亡くなり、梅雪はただちに母の面影の肖像画を描かせています。薄い青色の頭巾(ずきん)をかぶって法衣をつけ、緑色の絡子(らくす)を付けた比丘尼(びくに)姿で、右手には数珠を持っています。絵に付された添え書きの画賛には、容姿は観音様のように美しく眼は聡明そのものだと讃えています。

南松院の西側にある庭園は、創建当初の夢窓流借景式庭園(夢窓国師の作庭ではありません)で、池中には亀の形をした石が配されています。夫人が穴山信友に嫁ぐ時、父武田信虎に請い願って、武田家伝来の名石として名高いこの「亀石」をもらい受けてきたものです。武田氏館(つつじが崎館)庭園の名物として、代々受け継がれて来たと伝わる霊石です。「亀石」はその形がまるで生きているかのようで、夫人が大変気に入っていたと『甲斐国志』は記載しています。甲羅部分の長さは、縦約87センチ×横約60センチの大きさです。これに顔の部分と手足が別石で配されています。現在池に水がないので「亀石」の全体像が分かりますが、顔の部分は残念ながら一部割れてしまっています。甲羅の部分は色の微妙な違いや凹凸部分が、本物の亀の甲羅のように看て取ることができます。この「亀石」は、戦国大名武田氏と親族衆筆頭の穴山氏の歴史を伝える貴重な文化遺産です。

2月3日(月)
今日は立春です。暦の上では今日から春が始まります。ということは昨日が季節の変わり目、節目の日ということで「節分」でした。今日の新聞やネットニュースでも、昨日各地の寺社で行われた節分の行事が紹介されていました。多くは芸能人や力士を招いての豆まきですが、甲斐一之宮浅間神社では追儺板(ついないた)をバチでたたいて厄を祓う追儺神事が行われ、甲府横近習大神宮ではみこ姿の小学生による「浦安の舞い」が奉納されました。
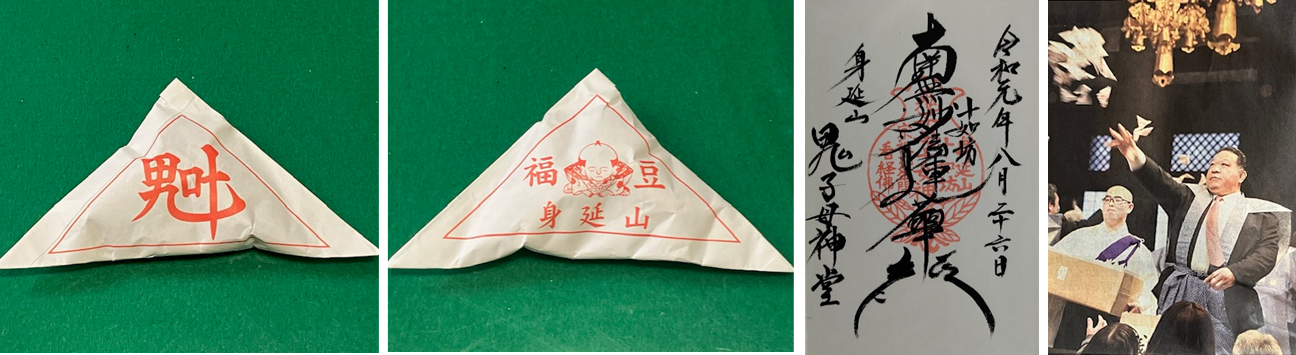 身延山久遠寺でも、節分の豆まきが雨天のため本堂で行われました。昨日は当博物館の有料入館者数が51万人目を迎えましたが、この記念すべき入館者の方が当館に来る前に身延山の節分会に行って来られ、その時拾った豆の一部をいただきました。この福豆が入った三角形の袋は、裏に奇妙な文字が書かれています。漢字のようですが、なんて読むのでしょうか?表には福豆、身延山の文字と「フクスケ」の絵があります。文字は「きかのう」と読み、昔から使われているものだそうです。鬼の字の最初の点にあたる角が無いものと、「叶(かのう)」という漢字との組み合わせ文字だそうです。当然辞書には載っていなくて、身延山独自の異体字の一種なのかもしれません。鬼子母神は仏教の守護神として、また、安産や子育ての神として身延山でも祀られています。悪鬼だった鬼子母神がお釈迦様に諭されて改心し角がとれたので、角の部分の点を付けないとも言われております。身延山鬼子母神堂の御首題(御朱印)の「鬼」の字も最初の点がついておりません。
身延山久遠寺でも、節分の豆まきが雨天のため本堂で行われました。昨日は当博物館の有料入館者数が51万人目を迎えましたが、この記念すべき入館者の方が当館に来る前に身延山の節分会に行って来られ、その時拾った豆の一部をいただきました。この福豆が入った三角形の袋は、裏に奇妙な文字が書かれています。漢字のようですが、なんて読むのでしょうか?表には福豆、身延山の文字と「フクスケ」の絵があります。文字は「きかのう」と読み、昔から使われているものだそうです。鬼の字の最初の点にあたる角が無いものと、「叶(かのう)」という漢字との組み合わせ文字だそうです。当然辞書には載っていなくて、身延山独自の異体字の一種なのかもしれません。鬼子母神は仏教の守護神として、また、安産や子育ての神として身延山でも祀られています。悪鬼だった鬼子母神がお釈迦様に諭されて改心し角がとれたので、角の部分の点を付けないとも言われております。身延山鬼子母神堂の御首題(御朱印)の「鬼」の字も最初の点がついておりません。
 皆さんの鬼の姿はどんなイメージでしょうか。鬼は恐ろしいもの、災いをもたらすもの、悪いものという漠然としたものがあります。妖怪なのか死霊なのかわからない得体のしれないものです。しかし、そこにはある一定の共通した姿があります。頭には角が生えていること、頭髪は直毛ではなく天然パーマでチリチリなこと、目は大きく光っていること、口には上下に鋭い牙があること、指には鋭い爪があること、ほとんど裸体に近く虎皮のふんどしや腰巻またはパンツをはいていること、突起のある金棒を持っていることなどです。このイメージはもともと姿形のないものに、鬼という仮想実態が作りあげられたものです。悪いことや疫病など災厄が来る方角は、鬼門の方角と言われております。すなわち北東の方角です。これを十二支で示すと丑寅(うしとら)になります。牛と虎の強く怖い部分を合わせてオニの共通するイメージが作られたのです。牛の角を持ち、虎の夜光るネコ科の目で虎の牙や爪で虎皮のパンツをはいているのは、この両者の動物を合わせて作り上げられたものなのです。ここでも十干十二支の陰陽五行説が援用されているのです。
皆さんの鬼の姿はどんなイメージでしょうか。鬼は恐ろしいもの、災いをもたらすもの、悪いものという漠然としたものがあります。妖怪なのか死霊なのかわからない得体のしれないものです。しかし、そこにはある一定の共通した姿があります。頭には角が生えていること、頭髪は直毛ではなく天然パーマでチリチリなこと、目は大きく光っていること、口には上下に鋭い牙があること、指には鋭い爪があること、ほとんど裸体に近く虎皮のふんどしや腰巻またはパンツをはいていること、突起のある金棒を持っていることなどです。このイメージはもともと姿形のないものに、鬼という仮想実態が作りあげられたものです。悪いことや疫病など災厄が来る方角は、鬼門の方角と言われております。すなわち北東の方角です。これを十二支で示すと丑寅(うしとら)になります。牛と虎の強く怖い部分を合わせてオニの共通するイメージが作られたのです。牛の角を持ち、虎の夜光るネコ科の目で虎の牙や爪で虎皮のパンツをはいているのは、この両者の動物を合わせて作り上げられたものなのです。ここでも十干十二支の陰陽五行説が援用されているのです。
2月1日(土)
本日、当博物館応援団AU会の主催によります第13回金山遺跡・砂金研究フォーラムが開催されました。応援団AU会の皆さんには、中高生の砂金掘り甲子園や一般の砂金掘り大会などの大きなイベントや当館の普段の活動や運営に大変なご協力をいただいております。改めて深く感謝申し上げます。
今回のフォーラムでは、都内で産出した砂金の報告(多摩川源流部は山梨の黒川・丹波山金山)、中世砂金産地と中世寺院、砂白金の年代測定、北米ゴールドラッシュと砂金掘り師の移動、金鉱脈を発見した後どうするかの発表がそれぞれありました。砂金採取のフィールドワークの魅力は絶大なものがあります。47都道府県すべて日本中から砂金が採取されており、都会の川でも大粒の砂金が採れたことによる鉱物の移動の実態が堀氏よりビデオで報告がありました。広瀬義朗氏は飛騨と越中の中世金産地と中世寺院の報告で、産金地の近くの山中にあった寺院が数キロ下った場所に移動したことを絵像本尊の裏書などから紐解いた研究報告です。金山の稼働によって新たな寺院が生まれ、人の移動とともに寺院も移動した実態が示されました。仁木創太氏は、砂白金の年代測定の挑戦と題して砂白金の形成年代を推定しています。若月敏郎氏はカナダやアラスカなど海外にまで砂金採取に出向いて、その歴史と現状を発表されました。アメリカに渡ったジョン万次郎も、砂金採取で莫大な利益をあげていたとは驚きです。野村敏郎氏は、新規発見の金鉱脈について今後どうしたら良いか、金含有量の分析結果から経費負担や想定される手間などを分析されています。
1月27日(月)
山梨と長野の縄文時代中期の土器や土偶の造形美は、世界中を見ても例のない素晴らしいものです。これらは考古学関係の一部の識者や岡本太郎などの芸術家からは注目されていましたが、地元からの情報発信は少なかったと言わざるを得ません。そこで改めて甲府盆地から諏訪に至る縄文人が残した世界的に貴重なこの歴史遺産を国内外に発信し、その価値を意識していただくために「縄文文化発信会議」が立ち上げられました。その設立記念のシンポジウム「え、縄文ってこんなにすごいのか!」が25日に山梨県立文学館で開催されて行ってきました。
 少し前まで日本の縄文土器が、世界最古の土器だと言われてきました。放射性炭素を利用した測定値では、今から1万6千年以上前になります。それから1万年以上も縄文時代は続きました。(現在は約2万年前の土器が中国江西省の洞窟遺跡から発見されたとの報道があります。)土器は物を煮炊きする道具として利用され続けてきました。煮ることによって栃の実やドングリなど堅果類などのアク抜きが可能となり、生では口にすることのできなかった動物の肉や魚介類、植物を食べることができ、食糧事情が飛躍的に安定したと考えられています。しかし、縄文の残された人骨を見ると飢餓線が確認され、縄文人の栄養状態が骨にその痕跡を何本も残すほど安定していなかったことがわかっています。縄文人の平均寿命は、男女とも31歳ちょっとくらいとかの研究報告がされています。かなり厳しい食料事情であったことがわかっています。
少し前まで日本の縄文土器が、世界最古の土器だと言われてきました。放射性炭素を利用した測定値では、今から1万6千年以上前になります。それから1万年以上も縄文時代は続きました。(現在は約2万年前の土器が中国江西省の洞窟遺跡から発見されたとの報道があります。)土器は物を煮炊きする道具として利用され続けてきました。煮ることによって栃の実やドングリなど堅果類などのアク抜きが可能となり、生では口にすることのできなかった動物の肉や魚介類、植物を食べることができ、食糧事情が飛躍的に安定したと考えられています。しかし、縄文の残された人骨を見ると飢餓線が確認され、縄文人の栄養状態が骨にその痕跡を何本も残すほど安定していなかったことがわかっています。縄文人の平均寿命は、男女とも31歳ちょっとくらいとかの研究報告がされています。かなり厳しい食料事情であったことがわかっています。
縄文土器は世界的に見ても極めて独自性の強いものであり、その立体的造形は目を見張るものがあります。山梨や諏訪地方の博物館や資料館に行って、この地域特有の縄文土器を見直し、その驚愕の芸術性と華やかさを再認識してみてはいかがでしょうか。
1月24日(金)
山梨県笛吹市の大蔵経寺山北側の山林火災は、18日の発生から6日たった時点でもまだ鎮火に至っておりません。今朝の情報では、焼失面積43ヘクタールと広大な面積が焼けてしまっています。現在煙や炎は確認されておらずヘリコプターからの放水も休止して、水を背負って人海戦術での消火活動が行われています。
 21日に山梨郷土研究会の現地で学ぶ文化財散策会の下見に、この火災現場の南側一帯に行ってきました。麓の春日居スポーツ広場の駐車場に消火活動の本部が置かれ、笛吹市消防本部、消防団、山梨県、自衛隊の方々が情報整理と消火指示に忙しくされていました。消火活動のため一般車両の通行規制がされる中、許可を得て菩提山長谷寺の入口まで行きました。山林火災は山の稜線よりも北側であったので、下見した範囲では山林火災の痕跡は確認されませんでした。散策会で訪れるこの付近の古墳と長谷寺の入口まで、見学場所の現状と歩行時間を確認しました。道路が広くなっている寺の入口には消防車両が入っており、ここから消防関係者が山の中に入って消火活動をしています。ご苦労様です。そのため長谷寺の境内まではいけませんでした。上空を見るとヘリコプターでの散水も繰り返し行われています。山林の地上部には落ち葉が厚く堆積しているため、火種が再燃する可能性もあるので火災現場での確実な鎮火の確認は慎重にならざるを得ません。
21日に山梨郷土研究会の現地で学ぶ文化財散策会の下見に、この火災現場の南側一帯に行ってきました。麓の春日居スポーツ広場の駐車場に消火活動の本部が置かれ、笛吹市消防本部、消防団、山梨県、自衛隊の方々が情報整理と消火指示に忙しくされていました。消火活動のため一般車両の通行規制がされる中、許可を得て菩提山長谷寺の入口まで行きました。山林火災は山の稜線よりも北側であったので、下見した範囲では山林火災の痕跡は確認されませんでした。散策会で訪れるこの付近の古墳と長谷寺の入口まで、見学場所の現状と歩行時間を確認しました。道路が広くなっている寺の入口には消防車両が入っており、ここから消防関係者が山の中に入って消火活動をしています。ご苦労様です。そのため長谷寺の境内まではいけませんでした。上空を見るとヘリコプターでの散水も繰り返し行われています。山林の地上部には落ち葉が厚く堆積しているため、火種が再燃する可能性もあるので火災現場での確実な鎮火の確認は慎重にならざるを得ません。
1月20日(月)
今日は二十四節気の大寒です。立春から始まり大寒まで1年を24に分けた二十四節気の最後の暦で、一年で寒さが最も厳しい頃になります。大寒から立春の前日である節分までの期間です。本来の節分は2月3日を想起する方が多いと思いますが、去年が閏年だったので今年2025年の節分は2月2日となります。1年の寒さも最深部となってピークを迎え、武道の寒稽古もこの頃行われます。私の小学生時代には、自宅近くの廃校となった体育館で柔道や剣道を友人の父兄に教わっていました。養蚕が主体の農業地域だったので、教える大人たちの都合により毎年冬の時期だけ冬季限定のスポーツ少年団でした。また、気温が低く水質が良いので、凍み豆腐や酒、みそ、醤油などを仕込む「寒仕込み」に最もよい時季とされています。
 大寒ではありますが今朝の気温は暖かくて霜も降りておらず、昨夜は雨が降ったこともあって湿気も加わり早春を思わせるような陽気です。博物館の周辺の苔もサザンカも花壇の雑草も、先週までの凍てつく寒風ではなく、少し温かみのある風に葉緑素の活動を再開する準備を進めているようです。
大寒ではありますが今朝の気温は暖かくて霜も降りておらず、昨夜は雨が降ったこともあって湿気も加わり早春を思わせるような陽気です。博物館の周辺の苔もサザンカも花壇の雑草も、先週までの凍てつく寒風ではなく、少し温かみのある風に葉緑素の活動を再開する準備を進めているようです。
1月19日(日)
道祖神まつりでは、身延町内でもどんど(ん)焼きを実施した地区もあったのではないでしょうか。道祖神祭りに付随する「お山飾り(お柳飾り)」は、博物館でもエントランスに飾りましたが本日をもって片付けました。これは「お山転ばし」と言って、「お山飾り(柳飾り)」を撤去し解体するものです。お山飾りは、「20日の風に当ててはならぬ」と言われ、遅くとも19日中にはお山を倒します。各集落ではそれぞれの柳は輪にして各戸に配られ、かつては火難除け、風難除けの呪い物として屋根の上に乗せられました。小さい輪にするのには、独特の感性と技術が必要です。ベテラン学芸員以外は要領を得ず悪戦苦闘の作業でした。今でも道祖神祭りは、小正月の行事としてかつての盛んだった様子をとどめていますが、明治期の「道祖神祭礼取締」を乗り越えて伝えられてきた特色ある伝統行事も、近年の過疎化の急激な進行によって祭礼そのものの取りやめや一部省略や簡略化などが進んでいるのは残念なことです。
 同じように15日の小正月には、小豆粥を食べる風習がありました。小豆粥を食べるとその年は病気にならないとされ、勝の木(ヌルデ)で作った箸で食べることを例としました。山梨市牧丘の実家では、この箸を1年間使用して毎年更新していたことを思い出しました。市販の使いやすい箸があるのに、なんで荒削りのヌルデの太箸を使うのか意味も分からずに受け入れていました。またこの箸と一緒にカツノキで直径10センチほどの「粥掻き棒」2本を作り、小豆粥の中でかき混ぜて米粒の付き方や十文字に入れた切れ込みに入った粥の数で、その年の稲作の豊凶を予察した粥占も行われていました。かつては、この身延町内でも普通に行われていた年中行事のようです。(下部町誌、中富町誌、身延町誌)14日の晩から15日の未明にかけて、諏訪大社をはじめ各地の神社で農作物などの豊凶を占う筒粥神事の各戸版といったところでしょうか。
同じように15日の小正月には、小豆粥を食べる風習がありました。小豆粥を食べるとその年は病気にならないとされ、勝の木(ヌルデ)で作った箸で食べることを例としました。山梨市牧丘の実家では、この箸を1年間使用して毎年更新していたことを思い出しました。市販の使いやすい箸があるのに、なんで荒削りのヌルデの太箸を使うのか意味も分からずに受け入れていました。またこの箸と一緒にカツノキで直径10センチほどの「粥掻き棒」2本を作り、小豆粥の中でかき混ぜて米粒の付き方や十文字に入れた切れ込みに入った粥の数で、その年の稲作の豊凶を予察した粥占も行われていました。かつては、この身延町内でも普通に行われていた年中行事のようです。(下部町誌、中富町誌、身延町誌)14日の晩から15日の未明にかけて、諏訪大社をはじめ各地の神社で農作物などの豊凶を占う筒粥神事の各戸版といったところでしょうか。
1月14日(火)
今日は小正月の道祖神祭りの日です。博物館でもエントランスに「お山飾り(柳飾り)」をこしらえました。昨年は空調工事で閉館中だったので、2年ぶりの復活です。出来上がったものを見るのは簡単なのですが、いざ作るとなると大変です。3メートルくらいの長さに切り出してきた竹を細く割り、薄く内側を削ってその周りに切れ込みを入れた色紙を巻き付けるのです。五色の色紙は、この世界を構成する全要素を表すとされ、古代中国の陰陽五行説がその大本となります。五行を色で表したのが五色で、「青・赤・黄・白・黒」なのですが、青を緑で代用、黒を紫で代用しています。五行は「木・火・土・金・水」に対応し、日本の文化に大きくかかわっています。
 上之平の集落の道祖神は、祭壇として盛り上げられた道祖神場四隅に竹を立てて、紙垂(しで)を垂らした縄を張って結界としています。かたわらには、各家々から持ち寄せられた正月飾りや門松などが集積されていました。道祖神本体は天明2年(1782)の石祠形ものです。今日14日の午後2時から「ドンド焼き」として燃やすそうです。お山飾りは今年から簡略化したとのことですが、本来は幟竿に五色の色紙で装飾した枝状の柳を、四方八方に均等に垂らしていたのです。今年は幟竿の代わりに藁で作った的状の俵に、お柳を刺しています。昔は13日に、米粉を練って繭玉や小判、巾着、カボチャなどの形を作り、これをドンド焼の火であぶって家に持ち帰り家族がこれを食べると、風邪をひかず虫歯にならなくて一年間無病息災でいられるとの風習があります。波高島や竹の島地区では12日に行っており、勤め人が多く消防団との関係もあることから14日直前の休日に実施する地区や、少子高齢化のため近年行われなくなってしまったところもあると聞いております。
上之平の集落の道祖神は、祭壇として盛り上げられた道祖神場四隅に竹を立てて、紙垂(しで)を垂らした縄を張って結界としています。かたわらには、各家々から持ち寄せられた正月飾りや門松などが集積されていました。道祖神本体は天明2年(1782)の石祠形ものです。今日14日の午後2時から「ドンド焼き」として燃やすそうです。お山飾りは今年から簡略化したとのことですが、本来は幟竿に五色の色紙で装飾した枝状の柳を、四方八方に均等に垂らしていたのです。今年は幟竿の代わりに藁で作った的状の俵に、お柳を刺しています。昔は13日に、米粉を練って繭玉や小判、巾着、カボチャなどの形を作り、これをドンド焼の火であぶって家に持ち帰り家族がこれを食べると、風邪をひかず虫歯にならなくて一年間無病息災でいられるとの風習があります。波高島や竹の島地区では12日に行っており、勤め人が多く消防団との関係もあることから14日直前の休日に実施する地区や、少子高齢化のため近年行われなくなってしまったところもあると聞いております。

1月10日(金)
1月7日は五節句の一つ「人実の節句」でした。七草がゆを食べて、一年間健康で過ごすことができるようにとの願いが込められた行事です。節句とは季節の節目に、五穀豊穣、無病息災を神仏に祈り、お供え物をしたり邪気を祓ったりするものです。この日に七草がゆを食べるのは、お正月のお節料理やお祝いの酒食で疲れた胃を休めようとするものです。この時期に採れる春の七草と呼ばれるセリ、ナズナ、スズナ、スズシロ、ホトケノザ、ゴギョウ、ハコベラと七種類の野草や野菜が入っています。
甲府市の甲斐善光寺でも、七草がゆの法要がテレビニュースで流されていました。法要では、年末年始に八幡様にお姿を変えたご本尊の阿弥陀様が御開帳され、阿弥陀様の印を額に受ける儀式が行われたのち、ご本尊に供えられた餅や小豆の入った寺独自の七草がゆが参加者にふるまわれました。

甲斐善光寺は、武田信玄が川中島合戦の戦禍に巻き込まれることを恐れ長野の善光寺を甲府に移したもので、武田氏滅亡後は徳川将軍家の位牌の安置所として保護されてきました。壮大な木造建築の善光寺本堂には、上方の破風板の合わせ目中央の所に武田菱紋、手前の唐破風の破風板に徳川家の葵の御紋が付されており、甲斐善光寺の歴史的由緒が偲ばれます。
1月6日(月)
お正月休みも昨日までで、今日からは通常の生活に戻りました。年末から新年にかけて、今年は曜日の並びによって九連休と長い休みの取得も可能といった方々も多かったのではないでしょうか。もっとも今年から来年にかけての年末年始も、九連休の取得可能な曜日配置になりますが、、、。
お正月は、暦の上で新しい年を迎える月です。入口に正月飾りの門松を飾り、お節料理を食べ、初詣など正月行事を行って新年を祝う年始めのことです。成長が早く冬でも枯れない常緑樹の松は、昔から縁起の良い植物と考えられてきました。「歳神様(としがみさま)」を家に迎えるための神様の依り代になるものです。お節料理は節(せち:季節の変わり目)に食べる料理で、特に正月料理を言うようになりました。博物館の門松は毎年職員の手作りです。斜めに切った竹を3本並べ、その前に松と梅の枝と竹の葉と赤い実のついている南天を盛り込み、下に菰を巻いて三、五、七の縄で〆て形を整えました。
 お正月は「歳取り」で、新しく年を取ることです。「数え年」の考え方で、お正月を境に一つ年齢を重ねることになります。年齢を「歳魂(としだま)」の数で数えるというものです。新年を迎えると歳神様がやってきて、人々に新しい年齢を授けます。授けられた年齢を「歳魂(としだま)」と呼びます。今の日本ではほぼ忘れ去られていますが、かつては老若男女を問わず、みんないっせいに神様から歳魂を授かって1歳ずつ年を取るのがお正月の大きな意味だったと、民俗学者の新谷尚紀氏は語っています。この歳魂が、子供が親や親戚からもらうお金の「お年玉」の起源になっているとのことです。
お正月は「歳取り」で、新しく年を取ることです。「数え年」の考え方で、お正月を境に一つ年齢を重ねることになります。年齢を「歳魂(としだま)」の数で数えるというものです。新年を迎えると歳神様がやってきて、人々に新しい年齢を授けます。授けられた年齢を「歳魂(としだま)」と呼びます。今の日本ではほぼ忘れ去られていますが、かつては老若男女を問わず、みんないっせいに神様から歳魂を授かって1歳ずつ年を取るのがお正月の大きな意味だったと、民俗学者の新谷尚紀氏は語っています。この歳魂が、子供が親や親戚からもらうお金の「お年玉」の起源になっているとのことです。
博物館のあるこの地域では、「歳神棚 12月31日に作る。新しい藁で注連縄を作り、座敷の中央に歳神棚を新しく吊り下げて歳神をまつる。歳神だなは恵方だなともいい明けの方に向けて作られたものである。お神名「年徳神」を注連縄の申央にはさみ神をまつる。その下に鏡もち(おそんねえ)、お酒、盛物(洗米、柿、栗、海老、慰斗飽、だいだい、田作等)をそなえる。家によってはお金をますに入れて供え、神聖な元日を迎える。これらはすべて歳神に感謝し家運の隆昌を願う縁起もので占められているが、現在では大分趣をかえている。」と昭和56年12月に刊行された『下部町誌』にはありました。下部地域出身の職員に聞いてみましたが、現在では全く行われていないそうです。
私の山梨市の実家でも平成のはじめころまでは、家の作り付けの神棚の前に藁ではなかったのですが歳神様を迎えるための臨時の神棚を設けておりました。いつの頃かその風習もしなくなってしまいました。民俗行事も、時代とともに変化(簡略化)もしくは失われてしまうのはしょうがないものなのでしょうか。
1月2日(木)
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日から通常どおりの開館となりました。お正月から多くの来館された皆様、どうもありがとうございます。数日間ですが年末年始のしばらくの休館がありましたので、常連さんや博物館応援団Au会の皆さんとそれに「推しもーん父さん」の方々にもたくさん来館していただきました。
入口の門松、干支の根付ほか来館者お正月プレゼント、小学生以下のおともだちへのぬいぐるみなどが当たるお年玉ガチャ、限定版福缶の販売などエントランス付近はお正月バージョンのBGM効果もあってか、年始そうそうお正月らしい賑わいを見せていました。この賑わいがずっと続きますようにと願っております。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
12月27日(金)
本日が2024年博物館の最終日です。時のたつのは早いもので、あっという間の一年間でした。今日は開館しながらの大掃除と、新年の準備の最終段階です。12月に少しずつ片付けや掃除は始めていたのですが、意外なところに盲点が見つかります。これでよいお正月が迎えられます。
博物館の入口で、来館者をお迎えしてくれていた菊を年末の大掃除で片付けました。5月に株分けして苗として植え替え、10月に開花した花の枯れた名残です。友人から博物館用にといただいたものは鉢上げして飾ることができましたが、私が去年の株から取り出して土手に植えた苗たちは、シカの食害にあってほとんど花が咲きませんでした。来年にむけての「冬至芽」は、既に準備がされています。今年の教訓を活かして、来年は「冬至芽」を上手く育て、鹿に食べられないようにして皆さんをお迎えできるようにしたいものです。

 4月21日に株分けして土手に150本以上の苗を植えましたが、シカに苗の頭を食べられてしまいました。9月30日菊の株がプレゼントされ、鉢上げして入口に並べました。かなり個体差がありましたが、10月中旬に花が咲き始めます。11月後半で花は枯れ始め、12月初旬にはすべて枯れてしまいました。
4月21日に株分けして土手に150本以上の苗を植えましたが、シカに苗の頭を食べられてしまいました。9月30日菊の株がプレゼントされ、鉢上げして入口に並べました。かなり個体差がありましたが、10月中旬に花が咲き始めます。11月後半で花は枯れ始め、12月初旬にはすべて枯れてしまいました。
 今日枯枝すべてを切り取り、風通しを良くし根元に出てきている「冬至芽」に陽が当たるようにしました。数鉢の「冬至芽」の横には、霜にもめげずにまだ黄色い花が咲いている鉢もありました。お正月まで持ってくれますかどうか微妙です。
今日枯枝すべてを切り取り、風通しを良くし根元に出てきている「冬至芽」に陽が当たるようにしました。数鉢の「冬至芽」の横には、霜にもめげずにまだ黄色い花が咲いている鉢もありました。お正月まで持ってくれますかどうか微妙です。
12月23日(月)
週明けの朝、テレビや通勤途中のラジオで今日の12星座占いを3局聞く機会がありました。その順位はなんと1位、12位、9位でした。星座占いをあまり真剣に信じる方ではないのですが、占ってくれる人によって最良日であったり、最下位の運勢であったりバラバラなのではあまり参考にはなりません。どちらかというと、普段は都合の良い部分だけは気にするようにしています。人間の運命は天体の運行に影響されるという考えが、西洋占星術、宿曜占い、四柱推命、陰陽道など洋の東西を問わずにあります。
武田信玄も軍配者として、易経を学びこれを駆使して戦にあたっていました。信玄自身のほか星や暦のことを司る呪術者を軍師として身近に置き、戦の作戦のほか諸事の行動など諸々のことについて、意見を参考にしていたことが知られています。武田家の軍師としては山本勘助が有名ですね。甲府駅前の信玄公の銅像の手には、軍配団扇が握られています。床几に腰掛け陣中の采配をしている姿で、軍配には北斗七星が陽刻され占星術を駆使していたことを示しています。
12月20日(金)
明日は二十四節気の一つ冬至です。一年で最も日照時間が短く、夜が長い日になります。今でこそインターネットやテレビ・ラジオ・新聞など、暦や季節の情報を簡単に手に入れることができますが、昔の人は太陽の運行で一年の周期をとらえていました。太陽の日の出、日の入りがそのわかりやすい目安になっていたと考えられます。周囲を山で囲まれた甲斐の各地の人々は、冬至にどの山のどのあたりで陽が登り陽が沈むかを、経験則として持っていました。この冬至の日を境に日照時間が再び増え始めて、新たな始まりを期待させ運気が上昇する節目の日なのです。
冬至の日にはカボチャを食べ、ゆず湯に入る風習があります。カボチャはカリウム、カロテン、ビタミンなどを多く含み、植物繊維が豊富で栄養価が高く冬のこの時期まで長期保存がきく野菜です。私の家にも夏に家庭菜園で作ったカボチャがまだ残っています。この時期には、甲州ではほうとうにカボチャを入れてよく食べられていました。今でこそカボチャ入りのほうとうはおいしいと感じるのですが、子供の頃は毎晩これが続くのであまり好きではありませんでした。ほうとうは山梨県を代表する郷土料理です。小麦粉を練って平たく切った麺を味噌で野菜と一緒に煮込んだ料理で、その由来は中国の「餺飥(はくたく)」が有力な説です。清少納言の『枕草子』にも「はうたう」として登場しておりその歴史の古さを感じます。甲府盆地側で「ほうとう」というのに対して、金山博物館のある身延町一帯では昔から「のしいれ」の呼び方が普通だったようです。
 ゆず湯は風呂にゆずの実を浮かべ、香りを楽しむとともに保温保湿効果があると言われております。柚子の木は庭先によく植えられており、甲州では比較的入手しやすい果物です。ゆずの香りは心身をリラックスさせ、風邪を予防するといわれています。
ゆず湯は風呂にゆずの実を浮かべ、香りを楽しむとともに保温保湿効果があると言われております。柚子の木は庭先によく植えられており、甲州では比較的入手しやすい果物です。ゆずの香りは心身をリラックスさせ、風邪を予防するといわれています。
この時期カボチャほうとうを食べ、ゆずを浮かべたお風呂に入り、季節の節目を肌で感じるとともに、陰から陽に転換する新たな門出をお祝いしてみるのはいかがでしょうか。
12月16日(月)
夕べは今年最後の満月でした。昨日の帰り道東側の山際には、いつになく明るく大きな月が出ていました。「満月」に近い言葉に「望月(もちづき・ぼうげつ)」があります。私「信藤」の本姓は「望月」で、南巨摩地域に多い名字です。長野県佐久市望月が名字発祥の地で、平安時代に勅旨牧の望月牧が置かれていました。
 昨夜はNHK大河ドラマの「光る君へ」が最終回を迎え、主人公の紫の君の相手役の藤原道長の死が描写されました。藤原道長は「この世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」の有名な和歌を詠んでいます。娘三人を天皇の后に立后し、自身の栄華を誇った歌と解釈されています。「満月」と「望月」はともに月が丸く見える状態を指していますが、「満月」は天文学的表現で「望月」は文学的な表現になります。
昨夜はNHK大河ドラマの「光る君へ」が最終回を迎え、主人公の紫の君の相手役の藤原道長の死が描写されました。藤原道長は「この世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」の有名な和歌を詠んでいます。娘三人を天皇の后に立后し、自身の栄華を誇った歌と解釈されています。「満月」と「望月」はともに月が丸く見える状態を指していますが、「満月」は天文学的表現で「望月」は文学的な表現になります。
12月15日(日)
12日に今年の世相を表す漢字が、日本漢字能力検定協会から京都の清水寺で発表されました。「金」です。清水寺の森清範貫主によって、例年どおり「金」と大きく筆で揮毫されました。「金」が選ばれるのは3年ぶり5回目のことで、パリ五輪の金メダルの獲得、政治の裏金問題、金価格の高騰、佐渡金山の世界遺産登録、新紙幣の発行など、金にまつわる話題が非常に多かった一年と言えるでしょう。「金」の字が選ばれた過去4回すべての年がオリンピックの開催年であるのは、金メダルの威力が絶大でいかにオリンピックが世相を反映する一大イベントであるのかがわかります。「金」の字は過去最多の選出で、これ以外の複数回選出された文字は「戦」、「災」、「税」の3文字です。これら字のイメージから、「金」の字ほど好印象は持てない感じですね。
 当湯之奥金山博物館も最多の入館者数を記録し、非常に賑わった1年でありました。来年もこの勢いのある流れを、持続させていきたいと考えております。
当湯之奥金山博物館も最多の入館者数を記録し、非常に賑わった1年でありました。来年もこの勢いのある流れを、持続させていきたいと考えております。
12月13日(金)
明日12月14日は、「忠臣蔵」でおなじみの赤穂浪士の討ち入りの日です。赤穂藩士47人が元禄15年(1702)12月14日の深夜、主君赤穂藩主浅野内匠頭長矩の敵を討つため吉良上野介義央邸を襲撃し、本懐を遂げて主君の眠る泉岳寺に報告した赤穂事件とも呼ばれる事件のあった日です。この事件の発端は、江戸城松の廊下で赤穂藩主浅野内匠頭が高家肝煎の吉良上野介に切りかかった傷害事件。浅野は当日中に切腹させられて赤穂藩はお取りつぶしになり、吉良にはお咎め無しと裁許されました。この結果を不服とした筆頭家老大石内蔵助ら47藩士が、主君の仇討ちを敢行した日なのです。この事件は主君への忠義心、武士道の美学などが日本人の多くの人に感銘を与え、事件直後から評判となり文芸作品などに美談として取り入れられてきました。
さて、『忠臣蔵』人気はこの頃ではだいぶ下火になってきています。テレビや映画での取り上げ数の減少は、浅野内匠頭のお殿様としての当時の評判や、自己犠牲の精神が現代の気風にそぐわないことなどに起因しているのではないでしょうか。磯田道史氏の『殿様の通信簿』は、『土芥寇讎記』という幕府の隠密が全国の諸大名の内情を幕府高官がまとめたものを現代語に解説した本です。(当ブログ11/3の柳沢氏の所でも引用)これによると、浅野内匠頭は智があって利発であるが女色を好む引きこもりで、政道はもっぱら家老に任せきりだというのです。その筆頭家老の大石は、主君の非をいさめない不忠の臣と記されているのです。大石の評判は、赤穂事件の前後で大きく変わっています。
 甲州と忠臣蔵との関連を調べると、赤穂の殿様である浅野氏は甲府城を完成させた浅野長政の分流であり、武田家の末裔は江戸時代に吉良家と同じ武家の儀式や典礼を司る高家旗本でした。また、当日討ち入りに参加しなかった赤穂藩家老の大野九郎兵衛は、甲府の能成寺にも墓があります。討ち損じたときの再起部隊の任を託されていたとの説があります。
甲州と忠臣蔵との関連を調べると、赤穂の殿様である浅野氏は甲府城を完成させた浅野長政の分流であり、武田家の末裔は江戸時代に吉良家と同じ武家の儀式や典礼を司る高家旗本でした。また、当日討ち入りに参加しなかった赤穂藩家老の大野九郎兵衛は、甲府の能成寺にも墓があります。討ち損じたときの再起部隊の任を託されていたとの説があります。
12月9日(月)
先日、急に思い立って窪八幡神社の本殿の扉に使われている金箔を確認してきました。窪八幡神社は山梨市北の笛吹川右岸に存在する大社で、古くは「大井俣神社」として『延喜式』神名帳に記載されている古社です。神社の記録(『大井俣神社本紀』)では、貞観元年(859)清和天皇の勅命により宇佐八幡宮を笛吹川の中島であった大井俣の地に勧請し、その後甲斐源氏の新羅三郎義光が現在地の窪に遷座して「窪八幡神社」になったと記されています。

モミジの赤や黄色の紅葉が冴えた静かな境内は、厳かな雰囲気に包まれていました。武田氏代々の崇敬が篤く、現存する社殿は室町時代に信虎・信玄の代にほとんどが再建されたものと伝えられています。境内には9棟11件の重要文化財指定の建物群が存在し、本殿は三間社流造の建物三棟を連結させた十一間社流造で、日本で唯一最大の規模を誇っています。この建物は武田信虎が再建し、正面の扉や柱には荘厳な金箔が押されており、今もきらびやかな痕跡をとどめています。これは信玄が第3回川中島合戦の出陣を前に、戦勝祈願のため甘利昌忠に命じて押させたものです。正面扉の両脇間の板壁には、剥落が激しいものの、見事な絵画が描かれています。近寄って詳しく観察することはできませんでしたが、竹・椿・立葵・タンポポなどの植物と鶴・雀・亀・猫・虎などの動物があるようです。現在は劣化を防止し保護するため、透明なアクリル板が絵の表面に設置されています。
 東側の参道にある大鳥居は木製の両部鳥居形式で、信虎が42歳の厄除けを祈願して建立したものです。「大井俣神社」と金箔で押された神額が掲げられています。木造鳥居としては、現存する日本最古の鳥居です。戦国大名武田氏の金は、ここでもふんだんに使われていることがわかります。
東側の参道にある大鳥居は木製の両部鳥居形式で、信虎が42歳の厄除けを祈願して建立したものです。「大井俣神社」と金箔で押された神額が掲げられています。木造鳥居としては、現存する日本最古の鳥居です。戦国大名武田氏の金は、ここでもふんだんに使われていることがわかります。
12月6日(金)
水曜日の休みを利用して、東京国立博物館の「はにわ展」を見に行ってきました。12月8日までの特別展なので、会期末に近いため平日とはいえ大変な混みようでした。入口の入場券売り場、平成館の建物内への入館もそれぞれ長蛇の列が続いていました。今回は「挂甲の武人」国宝指定50周年記念の特別展で、群馬県から出土した5体が初めて一堂に集められ、5体の武人はまるで戦隊ヒーローのようです。武人ハニワは埴輪の中で最初に国宝に指定された埴輪で、「埴輪武装男子立像」が正式名称になります。ある程度年配の方には、子供の頃に見た映画「大魔神」のモデルになった埴輪だと言ったらイメージがわくのではないでしょうか。
 最近の博物館は展示品の撮影が可能な場合が多く、武人はにわ以外の所ではまるでハニワをモデルにしたスマホでの撮影会のようで、展示ケースごとパシャパシャ写真を撮っていました。ハニワは古墳時代の3世紀から6世紀にかけて日本で独自に出現し、古墳に立て並べられた素焼きの造形物です。武人はにわ以外にも、鷹匠・農夫などの人物像やウマ・サル・イヌなどの動物、家・冑・舟などの器材形埴輪などなあります。簡略された人物の表現は、踊るハニワのようにゆるキャラを連想させてくれる愛くるしい表現となっているものもあります。
最近の博物館は展示品の撮影が可能な場合が多く、武人はにわ以外の所ではまるでハニワをモデルにしたスマホでの撮影会のようで、展示ケースごとパシャパシャ写真を撮っていました。ハニワは古墳時代の3世紀から6世紀にかけて日本で独自に出現し、古墳に立て並べられた素焼きの造形物です。武人はにわ以外にも、鷹匠・農夫などの人物像やウマ・サル・イヌなどの動物、家・冑・舟などの器材形埴輪などなあります。簡略された人物の表現は、踊るハニワのようにゆるキャラを連想させてくれる愛くるしい表現となっているものもあります。
さらに注目したいのは古墳からの副葬品の数々です。東大寺山古墳や江田船山古墳の金象眼の太刀、金製耳飾、金銅製沓等です。古墳時代後期になると、金色に輝く馬具や装飾付き大刀が大王から各地の王(豪族)へ配布されました。金はまだ日本国内から発見されておらず、朝鮮半島からもたらされた特別なものです。この授受にあたっては、ヤマト王権を統治していた大王と各地の王との支配と従属関係を示すと想定されています。
12月2日(月)
今日も朝の冷え込みが一段と厳しかったですね。甲府盆地の中央部に位置する昭和町の我が家では、お隣の中央市に畑を借りていて、旬の農作物を栽培しています。寒くなってきてあったかい鍋が恋しくなったので、夕飯用の鍋の材料となる大根や白菜を調達しようと、朝6時半ごろ日の出前に畑に向かいました。車外の気温は0℃を示しており、刈り取り終わった田んぼには一面に霜が降りています。当然、作物の上にもびっしり霜が降りていたため、朝の収穫はあきらめることにして帰ることにしました。陽が高くなり暖かくなってから収穫すれば、霜も解けて無くなるので、改めて収穫することにしました。
 晴天の夜間に盆地の底が寒くなるのは、周囲を山に囲まれた地形から盆地底部に冷気がたまるためで、これを「冷気湖」と言うそうです。昼に太陽熱で暖められた地面は、夜の間に熱が空中に逃げ出す天気予報でもおなじみの「放射冷却現象」です。満天の星が輝き熱を逃がさない蓋となる雲がない時、風がほとんどなく空気が乾燥した時に発生しやすい気象現象です。
晴天の夜間に盆地の底が寒くなるのは、周囲を山に囲まれた地形から盆地底部に冷気がたまるためで、これを「冷気湖」と言うそうです。昼に太陽熱で暖められた地面は、夜の間に熱が空中に逃げ出す天気予報でもおなじみの「放射冷却現象」です。満天の星が輝き熱を逃がさない蓋となる雲がない時、風がほとんどなく空気が乾燥した時に発生しやすい気象現象です。
 今朝の気温は平年並みなのですが、これまで暖かかったので一層冷え込みを感じてしまいます。川の水温が暖かく、大気の気温が低くなっているので、川面から水蒸気が発生しています。温泉の湯気のようにも見えます。今年の暖かさを象徴するように、川の斜面の草はまだ緑色をしていますが、草の上にも霜が降りています。八ヶ岳や南アルプスなど盆地周囲の山々も、空気が澄んで乾燥しているので、凛とした佇まい見せています。
今朝の気温は平年並みなのですが、これまで暖かかったので一層冷え込みを感じてしまいます。川の水温が暖かく、大気の気温が低くなっているので、川面から水蒸気が発生しています。温泉の湯気のようにも見えます。今年の暖かさを象徴するように、川の斜面の草はまだ緑色をしていますが、草の上にも霜が降りています。八ヶ岳や南アルプスなど盆地周囲の山々も、空気が澄んで乾燥しているので、凛とした佇まい見せています。
11月29日(金)
最近グッと気温が下がって霜も降りるようになり、秋らしい陽気になってきました。今日の空は気持ちの良い晴天なのですが、博物館の周辺は山の影となってしまって一日中陽が当たりません。それなので意外に底冷えがして暖房はついているのですが、建物内部は意外と冷えきっています。博物館から見える湯之奥金山の前山となる五老峰は、頂上部付近の木々の葉はすっかり落ち中腹において紅葉の葉が残っている境界となっています。博物館に隣接する山の木は、まだ緑の葉が残っていますが、リバーサイドパークのサクラやヤマボウシは葉がほとんど落ち切ってしまいました。カエデも早生の木には葉がなくなっていますが、奥手の木はやっと紅葉が始まったところの木もあり、現在いい色の変化が観察できるグラデーションを見せています。

そもそもなぜ夏にあれほど緑色に生い茂っていた葉が、秋の訪れが深まるたびに赤や黄色に変化するのでしょうか。それは植物が気温や日照時間の変化を読み取り、葉によって光合成をおこなって作り出すエネルギーと、葉を維持するためのエネルギーのバランスが崩れたときに葉を落とす経過措置なのです。蓄えたエネルギーを翌年の葉を茂らすために備蓄しておくためのシステムなのです。
11月25日(月)
「風林火山」は戦国大名武田氏本陣の旗印として有名です。「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」の14文字が書かれており、「疾(はや)きこと風の如く、徐(しずか)なること林の如く、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如し」と読みます。山梨県民には、武田節の詩吟の部分でよく聞くなじみの一節です。孫子の四如の旗というのが正式名称ですが、実はこれには続きがあるのです。「難知如陰(知り難きこと陰の如く)、動如雷霆(動くこと雷霆のごとし)」と続きます。味方の戦略は陰雲が日月を隠す暗闇の中のように敵に知られないようにし、いざ兵を動かすときは疾風迅雷のように迅速に激しくしなければならないという意味があります。(四如じゃなくて六如が本来の形になります。)
甲州市の雲峯寺などには、紺地に金字(金泥)で書かれた「風林火山」の旗が、何旒も残されています。金泥は、金箔を粉にした金粉を膠水(にかわすい・膠の入った水)に溶かした溶液で、絵画や文字を書くときに使われます。赤地の絹に「南無諏方南宮法性上下大明神」、「諏方南宮上下大明神」と金文字で書かれた旗も雲峰寺に残されています。諏訪神号旗ともいわれ、信玄直筆との伝承があります。
 金字は金色の字のことですが、「金字塔」となると「金」の字形をした塔のことで、ピラミッドの異称です。砂漠の中にあるあの巨大なピラミッドのことです。使用例としては「金字塔を打ち立てる」という風に使って、なかなか成し遂げることの難しい不滅の業績の比喩として用いられるのが一般的です。金は金メダルのように燦然と輝き決して錆びることのない金属であるので、成し遂げられた成果を永遠に讃える最高の表現と言っていいでしょう。
金字は金色の字のことですが、「金字塔」となると「金」の字形をした塔のことで、ピラミッドの異称です。砂漠の中にあるあの巨大なピラミッドのことです。使用例としては「金字塔を打ち立てる」という風に使って、なかなか成し遂げることの難しい不滅の業績の比喩として用いられるのが一般的です。金は金メダルのように燦然と輝き決して錆びることのない金属であるので、成し遂げられた成果を永遠に讃える最高の表現と言っていいでしょう。
11月24日(日)
昨日は醍醐山を愛する会主催の醍醐山一斉登山があって登ってきました。醍醐山は634.8mで、その標高から「山のスカイツリー」として地元有志・山岳関係者等により登山道が整備され、毎年春と秋に一斉登山の会を行っています。今回は24回目となり、県内はもとより隣県からも参加者があり総勢50余名の登山です。私はこの会には去年の春に続いて2度目の参加になります。
 主催者側で様々な面で配慮がなされており、展望の開けた場所では景色の説明、樹木の名前や寺跡・石造物などの歴史解説も駄洒落を交えて楽しい雰囲気でした。山頂ではミニカップラーメンと食後のコーヒーがふるまわれ、木陰の冷んやりした空気の中では、ありがたいホットなプレゼントでした。また、大子集落では甘いリンゴとお菓子の差し入れ、下ってきた上之平では愛する会の関係者によるカフェが準備されており、コーヒー、サトイモ、バナナ、菓子類など疲れた体と心に染み渡りました。
主催者側で様々な面で配慮がなされており、展望の開けた場所では景色の説明、樹木の名前や寺跡・石造物などの歴史解説も駄洒落を交えて楽しい雰囲気でした。山頂ではミニカップラーメンと食後のコーヒーがふるまわれ、木陰の冷んやりした空気の中では、ありがたいホットなプレゼントでした。また、大子集落では甘いリンゴとお菓子の差し入れ、下ってきた上之平では愛する会の関係者によるカフェが準備されており、コーヒー、サトイモ、バナナ、菓子類など疲れた体と心に染み渡りました。
 今回の登山でひときわ圧巻だったのは、山頂でのミニライブです。鉄塔を撤去した暖かい陽だまりの所に場所を移して、ソロボーカリストのヤマモトミカさん、ギタリスト兼作詞・作曲・編曲家・音楽プロヂューサー:YOU(藤岡洋)さんに、まずこの会のテーマソングの「希望の醍醐山」編曲versionⅡを披露していただきました。山頂でギターの生演奏の中、本格的な歌手の歌を聞いたのは初めてのこととみなさん感動していました。数曲のオリジナルソングを歌ってもらったあと、最後にみんなで「希望の醍醐山」編曲versionⅡを歌ったのはいい思い出になりました。
今回の登山でひときわ圧巻だったのは、山頂でのミニライブです。鉄塔を撤去した暖かい陽だまりの所に場所を移して、ソロボーカリストのヤマモトミカさん、ギタリスト兼作詞・作曲・編曲家・音楽プロヂューサー:YOU(藤岡洋)さんに、まずこの会のテーマソングの「希望の醍醐山」編曲versionⅡを披露していただきました。山頂でギターの生演奏の中、本格的な歌手の歌を聞いたのは初めてのこととみなさん感動していました。数曲のオリジナルソングを歌ってもらったあと、最後にみんなで「希望の醍醐山」編曲versionⅡを歌ったのはいい思い出になりました。
 湯之奥金山博物館に到着し、今回の登山の感想を含めた反省会を行いました。やはり山頂でのライブコンサートは皆に好評でした。いつもは紅葉のまっ盛りなのに今年は紅葉が遅れていて、山頂のモミジも色づき始めたばかりではありましたが、愛する会の暖かいおもてなしによって気持ちの良い山行となりました。博物館では、醍醐山の鳥観図を作成してくれたこまくさ山の会代表の温井一郎(温絵文)さんがお出迎えしてくれ、山梨県山岳連盟が作成した山の鳥観図と山の写真の来年のカレンダーも紹介してもらいました。
湯之奥金山博物館に到着し、今回の登山の感想を含めた反省会を行いました。やはり山頂でのライブコンサートは皆に好評でした。いつもは紅葉のまっ盛りなのに今年は紅葉が遅れていて、山頂のモミジも色づき始めたばかりではありましたが、愛する会の暖かいおもてなしによって気持ちの良い山行となりました。博物館では、醍醐山の鳥観図を作成してくれたこまくさ山の会代表の温井一郎(温絵文)さんがお出迎えしてくれ、山梨県山岳連盟が作成した山の鳥観図と山の写真の来年のカレンダーも紹介してもらいました。
山梨県山岳連盟のカレンダーには、9月の写真に昔私が中白根山で撮影したブロッケン現象の写真が採用されています。今春の博物館ロビーで「甲斐の山々」の写真展で飾った写真のうちの一枚です。
11月21日(木)
今朝甲府盆地は霧に覆われていました。通勤途中で周囲の山々を見ると、薄い霧の間から見える景色はある一定の高さで雲に隠されていました。博物館につく頃には晴れ間も見えて、身延山は中腹に雲がたなびいており、醍醐山も山頂付近が朝霧の残影と思しき雲がかかっていました。たぶん高い山々から霧で覆われた甲府盆地を見ると、盆地の中に溜まった霧がすばらしい雲海となる景色が広がっていたことでしょう。
 「あさっきりてっきり、ゆうきりふっきり」と小さい頃、近所の幼なじみのおじいさんの言葉を思い出しました。朝方の霧は昼前には晴れになり、夕方の霧は夜から翌日にかけて雨が降る兆候をあらわす言い習わしなんだそうです。実際にこの天気予報はかなりの確率であたっていて、経験則からくるお年寄りの話がためになるなあと子供心に感じていました。
「あさっきりてっきり、ゆうきりふっきり」と小さい頃、近所の幼なじみのおじいさんの言葉を思い出しました。朝方の霧は昼前には晴れになり、夕方の霧は夜から翌日にかけて雨が降る兆候をあらわす言い習わしなんだそうです。実際にこの天気予報はかなりの確率であたっていて、経験則からくるお年寄りの話がためになるなあと子供心に感じていました。
朝霧つながりで、朝霧高原は毛無山の稜線を越えて東の静岡県側一帯をいいます。富士山の西麓と毛無山塊の間に位置し、富士(麓)金山があります。湯之奥金山とは山の西面と東面の違いだけで、同じ金を含む鉱脈(岩盤)を採掘していました。両者は深いかかわりを持っており、中山金山の金山衆と掘間をめぐって争いが起こったこともあり、富士(麓)金山を采配した富士宮市の竹川家には両金山の密接な関係を示す古文書も残されています。
 朝霧は歳時記で秋の季語になります。お昼頃になると霧が晴れて晴天となり、気持ちの良い秋晴れが広がっています。「朝霧は晴れ」の天気のことわざ通りになりました。本来は、前日晴れていて風がなく高気圧に覆われて夜間に放射冷却が起こる時に空気が冷やされて、空気中にある水蒸気が霧となります。昨日は雨が降って寒かったのですが、雨のため湿度が高く空気中の水分量が多かったため、朝はそれほど冷えないにもかかわらず霧が発生したものと思われます。
朝霧は歳時記で秋の季語になります。お昼頃になると霧が晴れて晴天となり、気持ちの良い秋晴れが広がっています。「朝霧は晴れ」の天気のことわざ通りになりました。本来は、前日晴れていて風がなく高気圧に覆われて夜間に放射冷却が起こる時に空気が冷やされて、空気中にある水蒸気が霧となります。昨日は雨が降って寒かったのですが、雨のため湿度が高く空気中の水分量が多かったため、朝はそれほど冷えないにもかかわらず霧が発生したものと思われます。
11月17日(日)
博物館から見える周囲の山々も標高の高いところから、紅葉が進んできています。駐車場の中に植えてあるモミジは、大部分が赤く色づいているものと枝の先端から漸移的に赤く色づき始めている木が並んで立っており、好対照です。昨日の雨によってより色が鮮明に見えます。落ちているモミジ葉を見ると、黄緑、黄、橙、赤などが混じっていて同じ木から落ちたのに、葉の色の変化は情緒を感じさせてくれます。

「モミジ」は「カエデ」とも言います。どんな違いがあるのでしょうか。モミジはもともと「もみづ」という動詞が語源で、草木の葉の色が赤や黄色に変わることを指していたようです。草木から得られる染料を「揉み出づ(もみいづ)」から転訛して「モミヂ」の名詞となり、戦後に「モミジ」の表記になったということです。「カエデ」は葉の形がカエルの手に似ていることから、「蛙手(かえるて)」が「かえるで」になり「カエデ」に変化したものです。「モミジ」と「カエデ」は、植物分類学上はどちらも「カエデ」で区別がないとのことですが、「モミジ」は「カエデ」の仲間の中でも特に葉の切れ込みが深く、子供の手の平のような形状のものを指しているようです。
11月16日(土)
第3回シン・サンポを西嶋地区で開催しました。曇天模様の空の下、地区内の寺社を散策しました。おてんとうさまは顔をお出しになりませんでしたが、例年に比べて暖かく程よい散策日和でした。「西嶋」といえば「和紙」とすぐ連想される地区ではありますが、大きい集落なので和紙以外にも歴史的に豊富な史跡がいくつも存在していました。
最初の散策地は清源院です。本堂にお通しいただいてご住職から西嶋地区のこと、清原院の由緒、文化財指定の宝物などのお話を伺いました。身延町指定の「吻竜」「鴟吻頭竜(しふんずりゅう)」の彫刻は本堂の欄間にあり、下山大工石川七郎左衛門重甫の作品。「木造十王尊坐像」は集落内の「十王堂」にあったものを建物の撤去に伴って移されたもので、寄木造で水晶の玉眼がはめ込まれており、全体的に彩色が残っています。惣門は1間1戸の瓦葺の棟門で、瓦には菊十六弁の菊の紋章が入れられているそうです。隣の広禅寺と天神社については、穴山宗九郎との関係が指摘されました。宗九郎は穴山氏一族で、幽閉後に自殺をしたと伝わっています。天神様は菅原道真を祀る学問の神様であるのと同時に、藤原氏によって太宰府に左遷されて憤死した道真が怨霊となって京の都に天変地異を起こしたと伝わり、その祟りを収めるための神様でもあるのです。宗九郎の祟りを収めるための鎮守として、天神社が建立されたと考えられています。
 榮寶寺においてもご住職から、お寺の由緒、所有する文化財のお話をしていただきました。石造三十三番観世音像は西国三十三番の観音霊場を勧請したもので、石材は本町の夜子沢石で造られています。西嶋に和紙の製法を伝えた望月清兵衛の墓は、宝篋印塔の形式です。境内には紙の神様である蔡倫を祀った「蔡倫社」も存在し、和紙の製造をされている関係者の方々から篤く崇敬されているそうです。
榮寶寺においてもご住職から、お寺の由緒、所有する文化財のお話をしていただきました。石造三十三番観世音像は西国三十三番の観音霊場を勧請したもので、石材は本町の夜子沢石で造られています。西嶋に和紙の製法を伝えた望月清兵衛の墓は、宝篋印塔の形式です。境内には紙の神様である蔡倫を祀った「蔡倫社」も存在し、和紙の製造をされている関係者の方々から篤く崇敬されているそうです。
若宮八幡宮では、隋神門と本殿が町の文化財に指定されており、本町の下山大工の制作になるものです。境内にはイチョウの黄葉した落ち葉が見事であり、参加者は町天然記念物のケヤキの木からパワーをいただきました。
少人数ながら充実したシン・サンポに参加者も満足げのようすでした。
11月10日(日)
紅葉が進んできました。ここ最近の朝夕の冷え込みから、周囲の山々は、標高の高いところから麓にかけて、徐々に赤や黄色などに色づき始めています。夕日に映える周りの風景は、晴れ渡った空には気持ちがいいものです。リバーサイドパークのモミジやヤマボウシも紅葉が進んでいます。狂い咲きしていた桜の木を見てみると、花は散ってしまって枯枝のみの状況ですが、十月桜の花はまだまだしっかりと咲いています。
 16日(土)、第3回シン・サンポを西嶋地区で実施します。「西嶋」は、冨士川が半島状に湾曲する地域です。「しま」は周囲を水に囲まれた地を指すのですが、特定の仲間内の勢力範囲や縄張りを指すこともあります(やくざの世界など)。富士川右岸の河岸段丘上の平地で、集落のある上位段丘と水田地帯の下位段丘とは旧道を境に3~4メートルの段差があります。
16日(土)、第3回シン・サンポを西嶋地区で実施します。「西嶋」は、冨士川が半島状に湾曲する地域です。「しま」は周囲を水に囲まれた地を指すのですが、特定の仲間内の勢力範囲や縄張りを指すこともあります(やくざの世界など)。富士川右岸の河岸段丘上の平地で、集落のある上位段丘と水田地帯の下位段丘とは旧道を境に3~4メートルの段差があります。
 「西嶋神楽」は、武田氏滅亡の頃に戦禍と水害等で悩まされ続け悲観に暮れる人々の心を、神楽によって振興し霊鎮めをしようとして始められた伝承を持っている山梨県指定の無形民俗文化財です。「西嶋和紙」は、武田信玄に仕える武士であった望月清兵衛が伊豆方面に従事した際に、修善寺の製紙技術を学んで持ち帰って伝えたことに由来します。元亀2年(1571)西嶋で初めてその紙を信玄に献上したところ、信玄はその出来栄えを誉め大変よろこんで特に「運上紙」として認めたといいます。この時西嶋の「西」とこの年の干支の「未」を組み合わせた「西未」の印を与え、清兵衛に紙の役人を命じたといいます。以来現在に至るまで、伝統的な製紙業が盛んな地域となりました。清兵衛の墓は今回散策予定の榮寶寺に残されています。
「西嶋神楽」は、武田氏滅亡の頃に戦禍と水害等で悩まされ続け悲観に暮れる人々の心を、神楽によって振興し霊鎮めをしようとして始められた伝承を持っている山梨県指定の無形民俗文化財です。「西嶋和紙」は、武田信玄に仕える武士であった望月清兵衛が伊豆方面に従事した際に、修善寺の製紙技術を学んで持ち帰って伝えたことに由来します。元亀2年(1571)西嶋で初めてその紙を信玄に献上したところ、信玄はその出来栄えを誉め大変よろこんで特に「運上紙」として認めたといいます。この時西嶋の「西」とこの年の干支の「未」を組み合わせた「西未」の印を与え、清兵衛に紙の役人を命じたといいます。以来現在に至るまで、伝統的な製紙業が盛んな地域となりました。清兵衛の墓は今回散策予定の榮寶寺に残されています。
11月4日(月)
似て非なる植物があります。羽状複葉を持つもので、駐車場の廻りの山裾や下部川の河川敷などに、よく似ている木がたくさんあることがわかりました。樹種でいうとオニグルミ、ヌルデ、ウルシ、ハゼノキ、ニセアカシア、ニワウルシなどです。タラノキの葉も似ていますし、フジも葉だけを見ると形は同じように見えます。

先日、茅ヶ岳歴史文化研究所のSさんが、立ち寄ってくれました。縄文土器に残された植物の実の圧痕の研究で、カラスザンショウの原木を求めての来訪でした。カラスザンショウも葉の形はニワウルシに近いもののようです。標高300m以下で西日本には多いとのことで、山梨県内では南部町に自生しているという情報をもとに現地確認調査ということでした。帰った後、山裾に似たような木が何本かあるのを思い出しましたが、よく見ても何の木なのかわかりません。トゲが対生していること、実はサンショウによく似て果肉は赤く種子は黒いのですが、葉の形がサンショウとは異なります。実や葉をつぶしてみても、サンショウの独特の香りはあまりしません。トゲが互生するイヌザンショウではないことは明白ですが、カラスザンショウとも違うようで、いったい何の木なのでしょうか。

11月3日(日)
今日は文化の日。それとともに、武田信玄公の生まれた日でもあります。また、今年は甲府藩主であった柳沢吉里公が大和の郡山藩に移って300年の記念すべき節目の年にあたります。柳沢家は、甲斐源氏本家筋武田信玄の先祖からの分家にあたり、甲府藩は吉里の父である吉保が初代藩主でした。柳沢吉保は、徳川五代将軍綱吉の時に一介の藩士から異例の出世を遂げ、幕府側用人として大老格の地位にまで上り詰め、綱吉の忠実な家臣として幕政を仕切っていた能吏です。
しかし、その評判といえば、なぜか悪名高き佞臣のイメージがあります。そのイメージを作ったのは、①勧善懲悪のテレビ時代劇「水戸黄門」の黄門様の敵役とされたこと。②日本国民が大好きな「忠臣蔵」の処断に大きくかかわっていたこと。③身分の低い武士から甲府藩15万石の大名になる大出世を遂げたことによる妬み。④主君綱吉が「生類憐みの令」による「犬公方」と呼ばれるなど人気がなかったこと。⑤『護国女太平記』や『常山紀談』などの後世の作品などでの影響等があげられます。
さて、その実態はどうなのでしょうか。『土芥寇讎記』(どかいこうしゅうき)という元禄時代の大名の行状を密かに調べ上げた報告書があります。おそらく隠密が探索したものを、幕府官僚がまとめ上げたものであると考えられています。これらの一部は『殿様の通信簿』というタイトルの文庫本で、磯田道史氏が紹介解説しています。この報告がされた時点での吉保は、和泉国大鳥の2万2千石余の若い領主であり、まだ出世の途次にありました。この中では次のように記録されています。「保明(吉保)、生得才智発明也、、、行跡正シク、慈悲専ラトシテ、民ニ哀憐アリ。忠勤ヲ第一トシテ、仁心深キ故、殺生ヲ堅ク誡メラル。仍家人・百姓ニ至ル迄、物ノ命ヲ断タズ、慈悲専ラトス。心意順路ニシテ、邪佞ノ心ナク、誉之善将ト云ヘリ。」「評ニ云、本文之如クバ、更ニ難ナシ。誠ニ誉之善将ト云フベシ。信アレバ徳アル故ニ、上意ニモ叶ヒ、家繁昌スト見ヘタリ。」これらの記述から吉保は高い評価を得ており、慈悲による治世と上下ともに安定した統治をおこなった武将像が浮かび上がってきます。
ちなみに、水戸黄門様も『土芥寇讎記』に報告がされています。文武両道をよく学び、自分の身をただして道にのっとった政治をする。このように人物や政治向きは高評価されている反面、「女色に耽り、、、悪所に通(い)」と激しい女遊びのため遊郭に入り浸っているとの私生活の悪評も併記されています。
10月27日(日)
 博物館前の植え替えた鉢の菊の花が咲き始めました。金色に近い真っ黄色を主体とし、今年もまた長期にわたって楽しませてくれるものと思います。それらの株と同じ株から株分けした菊を、試しに土手に植えたものの現状です。これらはすべて丸い形の株にはなっておらずに、せいぜい数十輪ほどのつぼみがついているだけです。良い苗を準備することはもちろんながら、植え付けの適正な時期と十分な肥料分がなければ、立派な株には育たないことがわかりました。
博物館前の植え替えた鉢の菊の花が咲き始めました。金色に近い真っ黄色を主体とし、今年もまた長期にわたって楽しませてくれるものと思います。それらの株と同じ株から株分けした菊を、試しに土手に植えたものの現状です。これらはすべて丸い形の株にはなっておらずに、せいぜい数十輪ほどのつぼみがついているだけです。良い苗を準備することはもちろんながら、植え付けの適正な時期と十分な肥料分がなければ、立派な株には育たないことがわかりました。 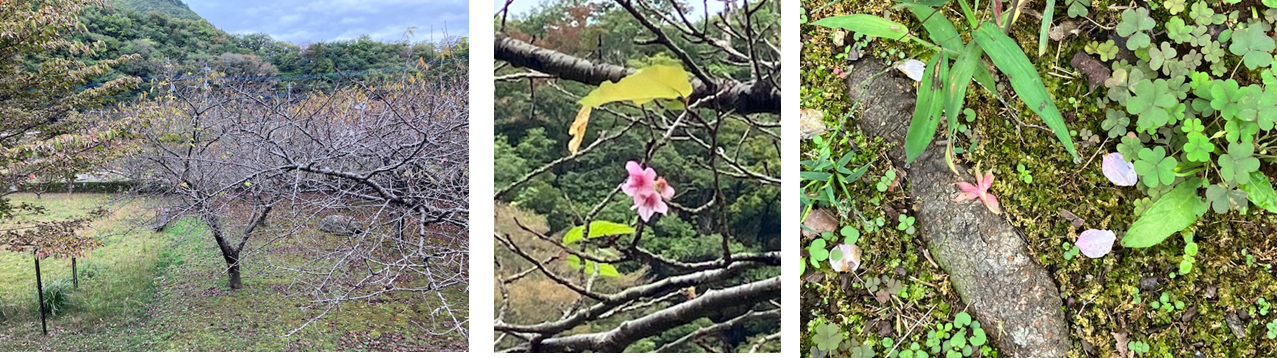 今朝博物館の駐車場に入る時、リバーサイド公園の桜の枝に花がついているのを見つけました。普通のソメイヨシノだと思いますが、2本の木にのみ花を咲かせています。この2本の木は葉が早く落ちてほとんど枝だけの状態で、他の木にはまだ半分ほど葉が残っているのとは対照的です。季節外れに花をつける「狂い咲き」です。今年の夏は本当に暑く猛暑が続いたため、他の地域でもこのような桜の狂い咲きが観察されて報告されています。ちなみにリバーサイド公園内の「十月桜」も、9月30日の掲載の時より花の数を増やしています。
今朝博物館の駐車場に入る時、リバーサイド公園の桜の枝に花がついているのを見つけました。普通のソメイヨシノだと思いますが、2本の木にのみ花を咲かせています。この2本の木は葉が早く落ちてほとんど枝だけの状態で、他の木にはまだ半分ほど葉が残っているのとは対照的です。季節外れに花をつける「狂い咲き」です。今年の夏は本当に暑く猛暑が続いたため、他の地域でもこのような桜の狂い咲きが観察されて報告されています。ちなみにリバーサイド公園内の「十月桜」も、9月30日の掲載の時より花の数を増やしています。
 リバーサイド公園内では、ヤマボウシの紅葉が始まっており、真っ赤になり始めた枝の木があります。ヤマボウシも実を付けており、ここ数日来の朝の冷え込みがやっと紅葉を促進してくれているようです。公園内のモミジも山々の木々も、メリハリのある赤や黄色の紅葉を愛でることのできる季節ももうすぐです。
リバーサイド公園内では、ヤマボウシの紅葉が始まっており、真っ赤になり始めた枝の木があります。ヤマボウシも実を付けており、ここ数日来の朝の冷え込みがやっと紅葉を促進してくれているようです。公園内のモミジも山々の木々も、メリハリのある赤や黄色の紅葉を愛でることのできる季節ももうすぐです。
10月24日(木)
 奈良県の大和郡山市は甲府市と姉妹都市です。江戸時代に甲府藩主だった柳沢吉里は、1724年に国替えによって大和郡山に家臣ともども移転したことにちなんだ締結です。大和郡山市は今年が市制70周年、金魚伝来300年を記念して金魚が旅した中山道を歩く「金魚旅」のオープニングイベントが昨日甲府駅でありました。柳沢氏は名字の元となった先祖の出身地が北杜市武川町柳沢で、甲斐源氏武田氏の分流になります。吉里の父吉保は五代将軍徳川綱吉の時に側用人(そばようにん)となり、大老格として幕政を主導した人物で、甲府藩主となって甲府の城下町が再整備されました。
奈良県の大和郡山市は甲府市と姉妹都市です。江戸時代に甲府藩主だった柳沢吉里は、1724年に国替えによって大和郡山に家臣ともども移転したことにちなんだ締結です。大和郡山市は今年が市制70周年、金魚伝来300年を記念して金魚が旅した中山道を歩く「金魚旅」のオープニングイベントが昨日甲府駅でありました。柳沢氏は名字の元となった先祖の出身地が北杜市武川町柳沢で、甲斐源氏武田氏の分流になります。吉里の父吉保は五代将軍徳川綱吉の時に側用人(そばようにん)となり、大老格として幕政を主導した人物で、甲府藩主となって甲府の城下町が再整備されました。

 この出発式に合わせて武田氏・柳沢氏にゆかりのある大泉寺を目指す「私の地域・歴史探訪」が開催され、講師を依頼されて散策会の案内をしてきました。甲府駅北口から甲府城2の堀跡➡妙遠寺➡華光院➡大泉寺➡八幡神社➡西昌院➡甲府城3の堀跡➡満蔵院から甲府駅北口に戻るコースです。大泉寺は武田信虎の菩提寺で、この日は重要文化財の「絹本著色武田信虎像」や「金銅金具装笈(おい)」、「絹本著色不動明王像」が特別公開されました。また、境内には柳沢氏の菩提寺であった旧永慶寺から移築された黄檗宗様式の総門があります。武田信虎の墓は、息子信玄と孫勝頼の三代の墓が立ち並び、その前に御霊殿(みたまや)が柳沢氏によって墓前に整備されています。それぞれの三人の尊像が配置され、下のふすまの扉を開けるとそれぞれの墓が臨める構造です。御霊屋と尊像も特別に公開していただきました。
この出発式に合わせて武田氏・柳沢氏にゆかりのある大泉寺を目指す「私の地域・歴史探訪」が開催され、講師を依頼されて散策会の案内をしてきました。甲府駅北口から甲府城2の堀跡➡妙遠寺➡華光院➡大泉寺➡八幡神社➡西昌院➡甲府城3の堀跡➡満蔵院から甲府駅北口に戻るコースです。大泉寺は武田信虎の菩提寺で、この日は重要文化財の「絹本著色武田信虎像」や「金銅金具装笈(おい)」、「絹本著色不動明王像」が特別公開されました。また、境内には柳沢氏の菩提寺であった旧永慶寺から移築された黄檗宗様式の総門があります。武田信虎の墓は、息子信玄と孫勝頼の三代の墓が立ち並び、その前に御霊殿(みたまや)が柳沢氏によって墓前に整備されています。それぞれの三人の尊像が配置され、下のふすまの扉を開けるとそれぞれの墓が臨める構造です。御霊屋と尊像も特別に公開していただきました。

 今回の特別の公開で気になったのは、これらの文化財に用いられている金の使用です。信虎像や不動明王像は、信玄の弟の信虎三男の信廉(のぶかど)の筆によるものです。信虎像の軍配団扇の装飾や袈裟の模様や環、不動明王像と矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制吒迦童子(せいたかどうじ)のネックレスのような瓔珞(ようらく)、ピアス式の耳飾りの耳璫(じとう)、ブレスレットのような腕釧(わんせん)やアンクレットのような足釧(そくせん)などは金泥で塗られ盛り上がっています。金銅金具装笈の金具類の金鍍金(めっき)はほとんど失われてわかりませんが、信虎笈の内側扉は金箔が押された後に、右の胎蔵界大日・左の金剛界大日の種子(しゅじ)が大きく描かれているのが鮮明にわかりました。また、御霊屋の三像の周囲の壁は、金箔で荘厳されていて美しく輝いていました。今回の散策会で、甲府の城下町の史跡とともに武田氏や柳沢氏が残してくれた貴重な文化財を間近で特別に拝観することができました。
今回の特別の公開で気になったのは、これらの文化財に用いられている金の使用です。信虎像や不動明王像は、信玄の弟の信虎三男の信廉(のぶかど)の筆によるものです。信虎像の軍配団扇の装飾や袈裟の模様や環、不動明王像と矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制吒迦童子(せいたかどうじ)のネックレスのような瓔珞(ようらく)、ピアス式の耳飾りの耳璫(じとう)、ブレスレットのような腕釧(わんせん)やアンクレットのような足釧(そくせん)などは金泥で塗られ盛り上がっています。金銅金具装笈の金具類の金鍍金(めっき)はほとんど失われてわかりませんが、信虎笈の内側扉は金箔が押された後に、右の胎蔵界大日・左の金剛界大日の種子(しゅじ)が大きく描かれているのが鮮明にわかりました。また、御霊屋の三像の周囲の壁は、金箔で荘厳されていて美しく輝いていました。今回の散策会で、甲府の城下町の史跡とともに武田氏や柳沢氏が残してくれた貴重な文化財を間近で特別に拝観することができました。
10月20日(日)
18日の金のグラム当たりの単価が1万4千円を超えました。史上最高値更新です。昨日の金木犀の花、黄金色の稲穂、マリーゴールドの花など、この時期は金色に彩られる季節です。マリーゴールドといえばあいみょんの歌で皆さんもご存じのことと思います。「♪~麦藁の帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる~♪」この歌は夏の歌なのですが、いまだに庭先の花壇にきれいな花を咲かせています。
 マリーゴールドの名前の由来は、聖母マリア様なんだそうです。聖母マリア様の祝日にいつも咲いていることから、「マリア様の黄金の花=マリーゴールド」と呼ぶようになったそうです。その聖母マリア様の祝日ですが、キリスト教の宗派によって、1月から12月まで年に何回もあるそうなんです。そんなにも長い期間ずっと咲いている、非常に強く丈夫な花であることを示すものだと言えるでしょう。日本名の「千寿菊」、「万寿菊」も、キク科のなかでも開花期間が長いことからの命名です。ちなみに新潟の日本酒に「千寿・萬寿」という銘柄の美味しいお酒もありますが、、、、。開花期間の長さはマリーゴールドの花言葉「健康・変わらぬ愛」の由来にもつながってきます。
マリーゴールドの名前の由来は、聖母マリア様なんだそうです。聖母マリア様の祝日にいつも咲いていることから、「マリア様の黄金の花=マリーゴールド」と呼ぶようになったそうです。その聖母マリア様の祝日ですが、キリスト教の宗派によって、1月から12月まで年に何回もあるそうなんです。そんなにも長い期間ずっと咲いている、非常に強く丈夫な花であることを示すものだと言えるでしょう。日本名の「千寿菊」、「万寿菊」も、キク科のなかでも開花期間が長いことからの命名です。ちなみに新潟の日本酒に「千寿・萬寿」という銘柄の美味しいお酒もありますが、、、、。開花期間の長さはマリーゴールドの花言葉「健康・変わらぬ愛」の由来にもつながってきます。
マリーゴールドは、農作物の虫よけとしても利用されます。同じキク科の除虫菊ほどではないと思うのですが、キク科独特の香りがありこれによって虫を寄せ付けないのかもしれません。金色に近いオレンジや黄色になる花は、公園の花壇やプランターにも植えられており、長期にわたって美しい花を見せてくれています。
10月19日(土)
昼間は日光が出ると暑いくらいの陽気ですが、朝夕の冷え込みは確実に秋の到来を感じさせてくれます。いつか知らない間に金木犀(キンモクセイ)の花が開花し、独特な香りを漂わせはじめています。自宅の周辺には、金木犀を庭木にしているお宅が多く、つい10日ほど前犬の散歩がてらにご近所を注意して見たときには花の気配すら感じられなかったのに、今はどの木も一斉に黄金色の花をつけています。金木犀はその樹皮が犀(サイ)の皮に似ていることから、「犀」の字が使われているといいます。
 金木犀はその香りが強いのが特長です。ジンチョウゲ、クチナシとともに日本の三大芳香木のひとつに数えられています。秋の運動会の季節になると、実家の庭にあった100年以上の大木となった金木犀が花を咲かせ、その甘い香りに秋を肌に感じたものでした。昭和の頃のトイレの芳香剤はこの金木犀の香りがするものが多く、友人の一人は金木犀の香りはトイレを連想するから嫌いだと言っていました。今朝の通勤途中に一般家庭の庭木にたくさん確認できたほか、注視してみると国母工業団地の植栽にも意外と多く使われていることがわかりました。
金木犀はその香りが強いのが特長です。ジンチョウゲ、クチナシとともに日本の三大芳香木のひとつに数えられています。秋の運動会の季節になると、実家の庭にあった100年以上の大木となった金木犀が花を咲かせ、その甘い香りに秋を肌に感じたものでした。昭和の頃のトイレの芳香剤はこの金木犀の香りがするものが多く、友人の一人は金木犀の香りはトイレを連想するから嫌いだと言っていました。今朝の通勤途中に一般家庭の庭木にたくさん確認できたほか、注視してみると国母工業団地の植栽にも意外と多く使われていることがわかりました。
10月14日(月)
多賀城跡といえば、身延町出身の平川南先生がおられます。平川先生は一時期宮城県の多賀城跡調査研究所に在籍され、ここから出土した漆紙文書の存在を新たに発見して、木簡も含めた出土文字資料から日本古代史の実像を描く研究を展開されています。国立歴史民俗博物館に移られて、助教授、教授、副館長、館長をされた後、山梨県立博物館の館長を歴任され、現在同館名誉館長をされています。
天平21年(749)、陸奥国守「百済王敬福」が小田郡(現遠田郡涌谷町)より金が産出したことを聖武天皇に報告し、900両(約13㎏)の金を献上しました。このことに対して天皇は「我が国始まって以来」と大いに喜び、元号を「天平」から「天平感宝」へと改め、陸奥国の租税の減免や関係者の叙位を行いました。
8世紀中頃に陸奥介だった「百済王敬福」の名が記された漆紙文書が発見されています。漆容器の蓋紙として用いられた文書の反故紙であったため、漆が浸潤して現在まで保存されたものです。百済王敬福は、陸奥守から上総守になった後、陸奥守に再任されています。百済王家はその姓が示すように、古代朝鮮半島にあった百済国の王族であり、金の採取のほか陸奥国の開発や整備に関わる技術を持った渡来系氏族と考えられています。
 涌谷町の黄金山神社一帯は、日本で最初の産金地です。湯之奥金山が山金採掘の最初の鉱山であるのに対して、北上山地を供給源として堆積した含金礫層が洗い出された砂金の産地です。当時東大寺大仏の建立という国家事業の鍍金用の金を賄うため、陸奥国多賀郡から北の諸郡の成年男子に黄金を納めさせることにして金の調達を命じています。そしてそれは中尊寺金色堂の建立という形に結びついてくるのです。やがて「黄金の国ジパング」として、ヨーロッパの大航海時代を生み出した原点がここにあったのです。
涌谷町の黄金山神社一帯は、日本で最初の産金地です。湯之奥金山が山金採掘の最初の鉱山であるのに対して、北上山地を供給源として堆積した含金礫層が洗い出された砂金の産地です。当時東大寺大仏の建立という国家事業の鍍金用の金を賄うため、陸奥国多賀郡から北の諸郡の成年男子に黄金を納めさせることにして金の調達を命じています。そしてそれは中尊寺金色堂の建立という形に結びついてくるのです。やがて「黄金の国ジパング」として、ヨーロッパの大航海時代を生み出した原点がここにあったのです。
日本遺産「みちのくGOLD浪漫-黄金の国ジパング、産金始まりの地をたどる―」の構成文化財として、「黄金山神社」等が認定されています。周辺には古代の布目瓦が分布しており、「天平」と刻まれた瓦も発見されています。
わくや万葉の里
日本で最初の金が発見された涌谷の地は、「天平産金」をテーマにした歴史館(天平ろまん館)があり、砂金採り体験場、世界の砂金コーナーなど「日本の産金地」の歴史ロマンが今に蘇る展示や砂金採り体験ができます。湯之奥博物館と同じように、昔ながらの「椀がけ法」による砂金採りで、砂の中から金の比重の違いを利用して砂金を見つけ出すものです。
黄金山神社には、産金を讃えた万葉歌人の大伴家持「天皇の御代栄えむと東なる陸奥(みちのく)山に金(くがね)花咲く」の日本北限の万葉歌碑があり、遺跡広場とともに万葉植物が四季を感じさせてくれます。
10月13日(日)
第59回全国史跡整備市町村協議会(全史協)大会が、宮城県多賀城市文化センターで開催されたので参加してきました。全史協は、加盟市町村が協調して史跡等の整備に関する調査研究及びその具体的方策の推進を図り、もって文化財の保護と活用に資することを目的に結成されました。毎年全国の加盟市町村が持ち回りで大会を引き受け、同県内の各市町村に所在する史跡や名勝及び天然記念物等を紹介し、史跡や指定文化財の整備の様々な維持管理や保護の事例とともに街づくりや観光活用の実際の様子を見せてくれるものです。加盟市町村は今年630市町村に及び、毎年漸増傾向にあります。
今年のホスト市となった多賀城市は、宮城県のほぼ中央の太平洋岸に位置しており、国特別史跡の「多賀城跡附寺跡」が存在し、「多賀城碑」が今年8月国宝に指定されました。奈良時代の神亀元年(724年)に陸奥の国府として創建され、今年は1300年目の節目の年を迎えました。現在多賀城南門の復元に続く築地塀の復元整備工事が進められ、周辺の発掘調査や整備が進行中です。多賀城の城下には多賀城を支える都市が広がっており、草創以来300年間古代東北の政治・文化の拠点となって、現在の街の礎となっています。今回の大会は、東北地方沿岸部の多くが、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けており、史跡整備が果たす震災からの再生・復興を成し遂げたシンボルとして位置付けられているとのことでした。「多賀城」の名は、「賀(よろこび)多き城」と読むことができるように、東北の安寧を願ってつくられた城と言われており、宮城県の県名の由来の一つとされています。
 大 会 多賀城南門復元状況 情報交換会
大 会 多賀城南門復元状況 情報交換会
10月6日(日)
 先日博物館出口のところの花壇で菊の鉢植え作業をしていた時に、黒い芋虫がいるのを見つけました。花壇だけでなく下部リバーサイドパークの土手にもおり、同じ種類の芋虫のみ7~8匹ほどがいました。体長は7~10センチほどで、鉛筆より太く多色ボールペンぐらいあります。気持ち悪いというよりも、その大きさと数に驚きました。これは調べてみると蛾のセスジスズメの幼虫になります。黒い体に目玉のような模様が目立ちます。この頭部の模様は蛇の目玉を連想させ、天敵から身を守るカモフラージュになります。
先日博物館出口のところの花壇で菊の鉢植え作業をしていた時に、黒い芋虫がいるのを見つけました。花壇だけでなく下部リバーサイドパークの土手にもおり、同じ種類の芋虫のみ7~8匹ほどがいました。体長は7~10センチほどで、鉛筆より太く多色ボールペンぐらいあります。気持ち悪いというよりも、その大きさと数に驚きました。これは調べてみると蛾のセスジスズメの幼虫になります。黒い体に目玉のような模様が目立ちます。この頭部の模様は蛇の目玉を連想させ、天敵から身を守るカモフラージュになります。
 ここ数日の雨もあって博物館周辺は、湿った状態になっております。砂金採り体験室裏の山側斜面を見ると、1.5メートル以上もある蛇のアオダイショウが横たわっていました。昨年もリバーサイドパークの土手から山に向かって、駐車場を横断する姿が何度か目撃されている個体と同じ個体かもしれません。土手の斜面の除草が丁寧にされているので隠れるところが限られてしまっているため、山側に移動したようです。アオダイショウは、からだの表面が青っぽいオリーブ色をしているためこの名がつけられたようです。アオダイショウに毒はなく、餌がネズミなどの小動物であるため、結果的に貯蔵する穀物を守ってくれるので家の守り神ともいわれます。職員間では「湯之奥金山博物館」の守護神なのだとささやかれています。
ここ数日の雨もあって博物館周辺は、湿った状態になっております。砂金採り体験室裏の山側斜面を見ると、1.5メートル以上もある蛇のアオダイショウが横たわっていました。昨年もリバーサイドパークの土手から山に向かって、駐車場を横断する姿が何度か目撃されている個体と同じ個体かもしれません。土手の斜面の除草が丁寧にされているので隠れるところが限られてしまっているため、山側に移動したようです。アオダイショウは、からだの表面が青っぽいオリーブ色をしているためこの名がつけられたようです。アオダイショウに毒はなく、餌がネズミなどの小動物であるため、結果的に貯蔵する穀物を守ってくれるので家の守り神ともいわれます。職員間では「湯之奥金山博物館」の守護神なのだとささやかれています。
10月4日(金)
今日は金曜日です。「月、火、水、木、金、土、日」の七曜日のひとつで、肉眼で顕著に見える七つの天体のうち太陽に近い方から2番目の惑星が金星です。今日は曇り空でこの後にまた雨が降る予報なので、西南西の低空の位置には残念ながら見えないと思われます。「水、金、地、火、木、土、天、海」と太陽系の惑星の位置を、理科で勉強しましたよね。あれっ、たしか冥王星があったはずですがどうしたのでしょう?こちらは2006年に惑星の定義から外れてしまい、「準惑星」の「太陽系外縁天体」となっています。金星は、真夜中には見ることはできずに、夕方の「宵の明星」や日の出前に「明けの明星」として明るく輝いています。
スポーツ界では「金星(きんぼし)」や「大金星」の言い方がありますよね。大相撲では勝敗を表す結果を、白黒の星で表す星取り表で表します。平幕力士が横綱を倒すと「金星」、大関を倒すと「銀星」と言いますが、相撲以外でも到底勝てないと思われる相手に勝利する時に使われています。
西洋と東洋問わずに生年月日や生まれた時刻により、その時の天体の状態から、その人の運勢や吉凶を占う占星術が発達してきました。現在は西洋占星術の12星座占いが流行っていますが、中国の四柱推命(しちゅうすいめい)、宿曜占星術(すくようせんせいじゅつ)など、生まれた時の太陽と月、惑星などの位置や動きから、その後の影響や運勢が導き出されています。
私は1958年生まれですので、「九星気学」で「六白金星(ろっぱくきんせい)」が本命星になります。金星の金はまだ磨かれていない「原石」を表し、磨き方によってはどのようにも変化する可能性を秘めているとされています。可能性は無限大でも、このまま原石で終わってしまうのでしょうか。
9月30日(月)
博物館に隣接する下部リバーサイドパークには、十月桜が1本あります。十月桜は、マメザクラとエドヒガンが交雑した種間雑種の栽培品種で 、春と秋から冬にかけての二度開花する二季咲きが最大の特徴の八重桜です。9月の末日で先週まで暑い日が続いていたのですが、季節は確実に進んでいます。葉はほとんど散って、秋空に白や薄いピンクの花が20輪ほど咲いています。
 先日山の仲間が菊の花を届けてくれました。去年と同じように博物館の入口に鉢を並べてみました。まだ小さなつぼみではありますが、株の樹形も大きくなっていて長く咲いて楽しませてくれることでしょう。
先日山の仲間が菊の花を届けてくれました。去年と同じように博物館の入口に鉢を並べてみました。まだ小さなつぼみではありますが、株の樹形も大きくなっていて長く咲いて楽しませてくれることでしょう。
 去年の鉢のままにしておいた菊の株は、春先に芽を出したので、話を聞く中で株分けしてリバーサイドパークの土手に植えてみました。植えたばかりの苗はシカに頭の部分を何度も食べられたり、乾燥で大きくならなかったりで、株にはなっておらず花芽もついていないものがほとんどです。適切な時期に、よい苗を選び出し、水や肥料を与えてきちんと管理しないと、しっかり育たないことがわかりました。
去年の鉢のままにしておいた菊の株は、春先に芽を出したので、話を聞く中で株分けしてリバーサイドパークの土手に植えてみました。植えたばかりの苗はシカに頭の部分を何度も食べられたり、乾燥で大きくならなかったりで、株にはなっておらず花芽もついていないものがほとんどです。適切な時期に、よい苗を選び出し、水や肥料を与えてきちんと管理しないと、しっかり育たないことがわかりました。
9月29日(日)
私の名前は、「信藤祐仁」です。山梨市牧丘町西保中の信藤家の次男として生を受け、祖父の「祐重」から「祐」1字をもらい、次男坊であるため「二」と同音で孔子の思想の「仁」の字をもとに名付けられたと聞いています。「ユウジ」の名前は当時はやっていた名前で、同級生に何人も同名の子がいたために、名字の頭の文字を冠して「(し)ゆうじ」と表記されて区別されました。小学校の頃、NHKの『南総里見八犬伝』が平日の夕方放送されていました。学校から帰り、ちょうど夕食を食べながらよく見ていたものです。八犬士が持つ「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の八つの字のある数珠の玉が鍵となっている長編人形劇でしたが、名前の中に「信・仁」2文字も入っていることが友人からはうらやましがられました。また、小学校高学年の頃「信藤」姓を調べている人から、電話帳で調べたところ全国でも数十軒しかない珍しい姓であって、その由来を教えてほしいと「信藤」姓の愛媛県の方から手紙が届きました。その時は大して気にも留めもせず親からも聞かずじまいでした。
 さて、姓が「信藤」と長くそうずっと思っていました。「信藤」姓は山梨県に江戸時代の終わりから2軒のみで増えることがなかったこと、歴史を勉強してきたので山梨に帰って来てから講演会や散策会の自己紹介の時に、信玄さんの「信」の字の「シンドウ」ですというと信玄さんに親しみを感じている山梨県人が多いこともあって、比較的早く覚えてもらえたという利点がありました。結婚して子供も授かり、名前に良い画数と良い意味の漢字をいろいろと組み合わせて苦労して名付けました。事情により子供が小学校に上がる時に妻の姓の「望月」を名乗ることになったのですが、戸籍の変更の手続きの時「信藤」の「藤」の字の「くさかんむり」が三画ではなく「++」の4画だと知らされました。長く「藤」が正しいものだと何の疑いもなく信じ込んでいました。
さて、姓が「信藤」と長くそうずっと思っていました。「信藤」姓は山梨県に江戸時代の終わりから2軒のみで増えることがなかったこと、歴史を勉強してきたので山梨に帰って来てから講演会や散策会の自己紹介の時に、信玄さんの「信」の字の「シンドウ」ですというと信玄さんに親しみを感じている山梨県人が多いこともあって、比較的早く覚えてもらえたという利点がありました。結婚して子供も授かり、名前に良い画数と良い意味の漢字をいろいろと組み合わせて苦労して名付けました。事情により子供が小学校に上がる時に妻の姓の「望月」を名乗ることになったのですが、戸籍の変更の手続きの時「信藤」の「藤」の字の「くさかんむり」が三画ではなく「++」の4画だと知らされました。長く「藤」が正しいものだと何の疑いもなく信じ込んでいました。
子供の名前を考えるときに、あれほど画数にこだわったのに無意味でした。もっとも、改姓することになったのですからどっちでもよいことなのかもしれません。そういえば、実家の土蔵に信藤姓の文字が表記されているのですが、よく見ると「信藤」の「藤」の草冠は離れていて「++」の4画になっています。子供の頃は草書体にしたので、離れているものだとばかり思っていました。「斉藤」さんや「渡辺」さんの文字にかなりのバリエーションがあるのと同じで、「++」のこの文字にしたのは特別な意味があったのかもしれません。
現在は昔から慣れ親しんできた「信藤」姓の方が、私を認識する場合わかりやすいので旧姓を使用しています。
9月24日(火)
「 暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、この数日朝晩は過ごしやすく感じられるようになってきました。 今年の秋の彼岸は、9月19日が彼岸の入り、秋分の日22日が彼岸の中日、25日が彼岸明けです。昼と夜の時間が同じ秋分の日の前後3日間は、彼岸(ヒガン=あの世)と此岸(シガン=この世)が最も近づくとされ、ご先祖の墓参りをしたり仏壇の掃除をしたりする風習は現在でも一般に行われています。
 先日ご先祖様の墓参りをしたとき、墓地の周囲の斜面に真っ赤な「彼岸花」が咲いていました。「彼岸花」は、独特の花の形が美しく、雑草の中でもよく目立つ存在です。まっすぐ伸びた茎の上に、放射状に反り返った花が5~7個付きます。秋のお彼岸の頃に花を咲かせるのでこの名があります。「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」、「死人花(しびとばな)」、「幽霊花」、「歯っ欠けばばあ」、「かみそり花」などの別名があります。「彼岸花を家に持ち帰ると火事になる」という迷信がありましたが、咲いている場所柄か子供の頃にはこの花をなんとなく不気味な花だと思っていました。原産地は中国大陸で、ヒガンバナ科の多年草です。日本においては、有史以前に稲や麦などの栽培植物とともに日本にもたらされた植物です。
先日ご先祖様の墓参りをしたとき、墓地の周囲の斜面に真っ赤な「彼岸花」が咲いていました。「彼岸花」は、独特の花の形が美しく、雑草の中でもよく目立つ存在です。まっすぐ伸びた茎の上に、放射状に反り返った花が5~7個付きます。秋のお彼岸の頃に花を咲かせるのでこの名があります。「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」、「死人花(しびとばな)」、「幽霊花」、「歯っ欠けばばあ」、「かみそり花」などの別名があります。「彼岸花を家に持ち帰ると火事になる」という迷信がありましたが、咲いている場所柄か子供の頃にはこの花をなんとなく不気味な花だと思っていました。原産地は中国大陸で、ヒガンバナ科の多年草です。日本においては、有史以前に稲や麦などの栽培植物とともに日本にもたらされた植物です。
「彼岸花」は毒性のあるアルカロイドを多く含んでいるため、「毒花」、「痺(しび)れ花」の別名もあるそうです。しかし、球根にはデンプン質を多く含んでいるため長時間水にさらせば食用になり、飢饉(ききん)のときには非常用食糧になったそうです。そのためにマイナスのイメージを植え付けて、非常時以外は手を付けないようにして保護していたのかもしれません。
9月23日(月)
今日は秋分の日の振替休日で、9月2回目の3連休の最終日です。
9月14日に中山金山に行ったとき、登山道に大きなオトシブミ(落とし文)が落ちていました。オトシブミは、オトシブミ科の甲虫のメスが、葉っぱのゆりかごを作ってその中に卵を産み、卵からかえった幼虫がそのゆりかごの葉を餌に食べて大きくなり、約3週間後に成虫になって穴をあけて外に出てくるのです。「落とし文」とは、昔手紙を渡したい人に巻物状の手紙を落として伝えてもらう風習があり、これに似ていることに由来するといいます。オトシブミは新緑の五月の連休の頃、広葉樹の若葉で作られるのが一般的なんですが、暦の上では秋のこんな時期に発見したのは初めてです。(昨年の5/8、5/28、5/29、6/25シン・ドウノヘヤ記事参照)
 今回採集のオトシブミは、広葉樹でも比較的堅い葉を利用したらしく、厚手の大きな葉を器用に巻いているのが観察できます。葉の状況からして、13日から14日の早朝にかけての創作物のようです。細長い方が長さ約7.0×1.1センチ、太くて短い方が約2.8×1.5センチと、去年の長さ約1.8センチ×太さ約0.8センチとは比べ物にならない巨大さです。写真では採集した直後のもの、去年の春に採集して成虫が出てきた穴のあるものと今回乾燥して変色したものを並べています。一般的なオトシブミは、写真でもわかるように葉の裏側が表面になるように巻いているのですが、長いものは葉の表面が外側に来ています。利用された葉がミズナラかと思って、近くに落ちていたミズナラの葉と実の写真も載せましたが、違う種類の葉を原材料にしているようです。去年のものと比べても大きさの差は歴然であり、今日から約2週間後どんな成虫が顔を出してくれるのかが楽しみです。
今回採集のオトシブミは、広葉樹でも比較的堅い葉を利用したらしく、厚手の大きな葉を器用に巻いているのが観察できます。葉の状況からして、13日から14日の早朝にかけての創作物のようです。細長い方が長さ約7.0×1.1センチ、太くて短い方が約2.8×1.5センチと、去年の長さ約1.8センチ×太さ約0.8センチとは比べ物にならない巨大さです。写真では採集した直後のもの、去年の春に採集して成虫が出てきた穴のあるものと今回乾燥して変色したものを並べています。一般的なオトシブミは、写真でもわかるように葉の裏側が表面になるように巻いているのですが、長いものは葉の表面が外側に来ています。利用された葉がミズナラかと思って、近くに落ちていたミズナラの葉と実の写真も載せましたが、違う種類の葉を原材料にしているようです。去年のものと比べても大きさの差は歴然であり、今日から約2週間後どんな成虫が顔を出してくれるのかが楽しみです。
9月22日(日)
夢は見るものですか?叶えるものですか?
夢の捉え方は人さまざまで十人十色です。
私の子供の頃の夢は、小学生低学年までは大きくなったら社長になりたいという単純なものでした。社長イコールお金持ち、社員の頂点で会社で最も偉い人、裕福で世間の人から尊敬される存在という漠然としたものでした。小学校卒業の頃の当時同級生の将来の夢は、プロ野球選手になりたいとか、歌手になりたいとか、博士や学者になりたいとか、当時の子供の頃の夢は、大人になってからどんな職業に付きたいかを意識していたように思います。
 我が家ではペットとして犬を飼っています。マルという13歳になるオスの黒柴です。今では老犬ですが小さい頃はヤンチャでやたらと吠えまくり、ご近所や親戚の人にも噛み付いたりもして結構苦労しました。そんなマルも年老いてきたのか、このごろは散歩と食事以外ほとんど横になって寝てばかりいます。先日寝ている時、空中を駆け巡るように足を動かしている姿を見ました。草原でも自由に駆け回っている夢を見ているのでしょうか。動物でも夢を見るんですね。
我が家ではペットとして犬を飼っています。マルという13歳になるオスの黒柴です。今では老犬ですが小さい頃はヤンチャでやたらと吠えまくり、ご近所や親戚の人にも噛み付いたりもして結構苦労しました。そんなマルも年老いてきたのか、このごろは散歩と食事以外ほとんど横になって寝てばかりいます。先日寝ている時、空中を駆け巡るように足を動かしている姿を見ました。草原でも自由に駆け回っている夢を見ているのでしょうか。動物でも夢を見るんですね。
中世まで睡眠中に見る夢は、神仏のお告げとして意識されていたようです。神社仏閣に宿泊参篭し、その結縁(けちえん)を結びたいと願って、人々はたびたび神仏詣でを行っています。そこで神仏からの夢のお告げを得て、諸願成就を果たすのです。夢は、今でこそレム睡眠中の脳の活動と解釈されるのでしょうが、戦争や災害など世知辛い世の中、すべての人々が幸せになる夢を実現してほしいものです。
9月20日(金)
先日中山金山に登った時、秋の気配を感じる木の実がありました。最初の休憩地点には、山栗の木があり栗のイガが落ちていました。まだ緑色をしており実は完全に熟していない感じです。イガに覆われているのは、動物や虫に食べられるのを防ぐためのもの。人間でも栗の実はおいしい季節の食べ物です。今が旬ですね。日本では縄文時代草創期の約1万3千年前の長野県お宮の森裏遺跡の竪穴住居跡から炭化したクリが出土しており、縄文時代を通じて全国各地で食されていました。山梨県内では、釈迦堂遺跡や梅ノ木遺跡などでもたくさん発見されています。栗のイガは葉が変形したものと考えられています。ブドウや桃の果実として食べられる部分が、栗だと堅い鬼皮部分にあたり、種子は渋皮の下の普通に食べている黄色の部分になります。

中山金山への登山道は、最初ヒノキの植林帯の中を進みます。ヒノキの種子が登山道のくぼみにまとまって落ちていました。この種子の形を見ると、セパタクローの玉に似ているなといつも思います。(もっともセパタクローの玉をじっくり見たことはないのですが。)種子の構造としてはマツボックリと同じで、内部にある種子がはじけて出てしまったものが、このセパタクロー状の玉になります。夏には緑色をしていたものが、成熟して乾燥すると内部に包蔵している種子を放出するのです。先日拾ってきた球体に近い種子を机の中に置いておいたところ、数日で乾燥して緑色から茶色になっており、ひび割れた間から種子が飛び出していました。
9月16日(月)
おとといの14日、東京大学のS先生、明治大学のS先生、出版社のH氏を案内して、K学芸員と共に中山金山に行ってきました。当日下界の最高気温は33.3℃と真夏日の暑い中、親子金山探険隊以来約1か月ぶりの金山訪問です。
登山口の駐車場には、毛無山登山者とみられる車が先に3台とまっていました。10時過ぎ登山開始。やはり金山への登山道は厳しく、最初のヒノキの植林地は風が通らないため、蒸し暑く汗が噴き出る状況でした。今年は特にクマの目撃情報が多いため、休憩のたびに爆竹をならしてクマに人間の存在をアピールしながら登りました。12時過ぎに中山金山入口の説明板到着、大名屋敷から七人塚を経由して第2地藏峠へ。残念ながらここからの富士山の眺望は、霧がかかっていて望めずに昼食。精錬場跡地へ向かい、おもなテラスごとの特徴や、金山臼、石造物、炭焼き窯、坑道などの概略を説明する。13時半過ぎに下山開始、15時少し前駐車場到着。
 東大のS先生は学生時代に黒川金山の発掘調査に参加されていたとのこと、30年以上も前のことなのでうろ覚えではありますが、この時に私も発掘調査現場を見学させていただいておりました。
東大のS先生は学生時代に黒川金山の発掘調査に参加されていたとのこと、30年以上も前のことなのでうろ覚えではありますが、この時に私も発掘調査現場を見学させていただいておりました。
暑いながらも季節が前回より進んでいるなと感じたのは、登山道沿いに秋のいろいろなキノコが顔を出していたからです。タマゴタケ、ヌメリイグチ、ホコリタケなど。下山後は黄金の足湯で疲れを癒しました。お疲れさまでした。
9月8日(日)
垣根涼介氏による『武田の金、毛利の銀』のタイトルの本が、7月末に刊行されました。織田信長の密命を受けた明智光秀が、武田と毛利の資金源となっている鉱山の金と銀の産出量を探ってくるという小説です。武田氏では湯之奥金山、毛利氏は石見銀山がその対象となっています。
光秀は盟友二人と連れだって、身延山詣での姿に変装し甲斐に潜入します。しかし、その金の搬出先となる田子の浦港の普請を命ぜられた土屋十兵衛長安(大久保長安)に見破られ、金山の情報を渡すのと引き換えに石見銀山密偵への同行を依頼されます。こうして4人組は表向きとして、毛利家へ信長の使者として赴きます。その岐路に毛利家の支配下となった石見銀山の代官所へ忍び込み、産出量を記した台帳を確認して無事役目を果たします。信長はこれまでの産出量、流通、換金率、埋蔵量など、武田の金山と毛利の銀山からその経済的基盤とともに、今後の両大名の動向を類推します。
 大久保長安は武田家滅亡後徳川家康に仕え、石見銀山奉行、佐渡金山奉行となり、家康の天下を支えた総代官として、各地にその足跡を残しています。甲斐では武田信玄のもと、組織の在り方や金の採掘法、治水技術などを学び、武田家の租税や食糧管理など民政を担当しました。武田氏滅亡後家康の配下となった長安は、角倉了以を京から呼び寄せ甲斐と駿河の間に富士川舟運を開きました。
大久保長安は武田家滅亡後徳川家康に仕え、石見銀山奉行、佐渡金山奉行となり、家康の天下を支えた総代官として、各地にその足跡を残しています。甲斐では武田信玄のもと、組織の在り方や金の採掘法、治水技術などを学び、武田家の租税や食糧管理など民政を担当しました。武田氏滅亡後家康の配下となった長安は、角倉了以を京から呼び寄せ甲斐と駿河の間に富士川舟運を開きました。
甲府市の天尊躰寺には、大久保長安の没した翌年(1614年)に建立された供養墓(無縫塔)が存在します。
9月2日(月)
先月8月の入館者は、なんと5,055人でした。1月間の入館者数で過去最高を記録しました。5の数字が3つあります。百の位が5であれば、ぞろ目になったのですが。ぞろ目(揃目)とは、2個のサイコロを振った時に同じ目(数字)が出ることです。そこから転じて、同じ数字が2桁以上続くことをいうようになりました。8月は、先日の有料入館者数も50万人目と、5には縁のある月となりました。
5は奇数で、五角形からくる安定と繁栄という意味も含まれています。五体、五感、五指、五臓など人間そのものを表す数字でもあり、自由、柔軟性、転換期、など自由な発想力と人間関係を表す数字と言われています。人間関係の豊かさを象徴しており、新しい人との出会いや交流が増えることをも意味しているそうで、当博物館にぴったりです。
オリンピックの五輪、ペンタゴン(五角形)、陰陽五行説、五芒星、五大陸、五大明王、五輪塔、五畿など、地理歴史上の事象にも「5」の数字が以外と多用されています。
8月30日(金)
昨日、3時過ぎに湯之奥金山博物館の有料入館者数が、50万人目を達成しました。東京から来た学習院中等科地学部の2年生小柴君です。台風の影響もあって数日前から記念すべき50万人目の入館者がいつになるのか、誰に当たるのか博物館スタッフの間では話題になって準備を進めていました。学習院中等科地学部の皆さんには、記念品として全員に常設展の展示図録が手渡され、記念撮影をしました。
 博物館の開館から27年経過し、受付の窓口で入場券を買っていただいた方が50万人になったということです。これは大変な数字です。今年の山梨県の人口が約80万人なので、県内の半数以上が有料で来館したということになります。最近ではコロナ禍で入館者数の停滞もあったのですが、49万人目が6月だったのでわずか3か月足らずで1万人増えて50万人目になりました。ここのところの入館者増は、スタッフは忙しくともうれしい悲鳴です。本当にありがとうございます。これからも引き続きよろしくお願いいたします。
博物館の開館から27年経過し、受付の窓口で入場券を買っていただいた方が50万人になったということです。これは大変な数字です。今年の山梨県の人口が約80万人なので、県内の半数以上が有料で来館したということになります。最近ではコロナ禍で入館者数の停滞もあったのですが、49万人目が6月だったのでわずか3か月足らずで1万人増えて50万人目になりました。ここのところの入館者増は、スタッフは忙しくともうれしい悲鳴です。本当にありがとうございます。これからも引き続きよろしくお願いいたします。
8月29日(木)
身延線金手駅の東の踏切を渡ると山八幡神社があります。この神社は、甲斐源氏で甲斐に最初に入植した武田義清が、甲斐源氏の守護神として甲斐市の篠原丘に西山八幡宮を建立したものを、鎌倉時代(一説には武田信虎時代)に甲府市の愛宕町に勧請し、甲府城造成にあたって現在地に移転したものです。この神社の鳥居の扁額には、「八幡宮」の文字がありますが「八」の字が「鳩」の姿を表しています。鳩の姿は拝殿の賽銭箱にもあります。

八幡神の神使は霊鳩です。源氏に関係する数々の戦に際して、鳩が軍陣の上を飛来して源氏軍を勝利に導いたとする奇瑞によるものです。神功皇后の三韓征伐、源頼義が奥陸奥の安倍氏と戦った前九年の役、壇ノ浦の戦いに代表される源平の合戦等枚挙にいとまがありません。故に八幡神は戦の神、軍神として武家の信仰を集めました。
宇佐八幡宮を、男山の石清水八幡宮に遷座するのに関わった奈良・大安寺の行教が宇佐での託宣ののち港を出るとき、「金色の鳩が来てとまり、その影が和尚の袖に映ると、阿弥陀三尊の像として現れた。」とされています。神仏習合で八幡大神の本地仏は、阿弥陀三尊なのです。八幡神は、阿弥陀様がお姿を変えたものとしてとらえられていました。八幡神は阿弥陀如来と同一のもので、神道側と仏教側でそれぞれの神仏が充てられていました。

長野の善光寺の御本尊は、絶対秘仏の阿弥陀様です。武田信玄公が善光寺を甲府に移設し、甲斐善光寺を開いたのも、甲斐源氏の正当である後継者としての思いがあったのでしょう。川中島の合戦によって善光寺が戦乱に巻き込まれるのを防ぐこと、善光寺信仰を領国経営に生かすことも重要な理由のひとつですが、源氏の守護神の八幡神と同一の日本最古の阿弥陀如来像を武田領国の中心である甲府に持ってきたことには、ひときわ特別な思いがあったと思われます。甲斐善光寺の御本尊は、信濃善光寺の前立本尊であった鎌倉期の阿弥陀三尊像です。これも現在は非公開の秘仏なのですが、七年に一度の信濃善光寺御本尊の御開帳に合わせて約3か月間公開されています。また、毎年お正月の七日間のみは八幡神に変身して一般に公開されており、そのお姿を拝見することができます。
信濃善光寺の山門の扁額には、5匹の鳩が隠れているといわれています。「善光寺」の文字をよく見て、鳩の姿を探してみてください。4匹はすぐに見つかると思うのですが、5匹目は難しいです。心あたりの部分を心眼で凝視して見つけ出してください。阿弥陀様が八幡様と同じととらえられていたことは、この「鳩字の額」からもうかがい知ることができます。
8月26日(月)
源氏の氏神は、八幡大神(はちまんのおおかみ・やはたのおおかみ)です。大分の宇佐八幡宮がその原点で、ご祭神は、応神天皇(誉田別命・ほんだわけのみこと)ですが、比売神(ひめがみ)と神功皇后(じんぐうこうごう)と合せて八幡三神として祀られることも多くあります。また、応神天皇の御子である仁徳天皇を祀る若宮八幡宮もあり、神社別では稲荷神社に次いで全国第2位の数です。早くから神仏習合の神として、八幡大菩薩と称されました。清和源氏や桓武平氏をはじめとする武家に厚く信仰され全国に広まり、甲斐源氏も氏神としたために県内各地に八幡神社が勧請されました。南部氏や下山氏の一族も、身延町・南部町の富士川谷各所に八幡神社を創設しています。
神様からの使者として神意を伝えたり、吉凶を示す特別な動物のことを神使(しんし)といいます。神様は目に見えて現れるものではありませんから、神様を感じたい神様の意思を知りたいという人間の欲求に対し、神様と人間の間をつなぐ使者の存在を模索するようになります。そこで、自然の中にあり神秘的な雰囲気を漂わせる鳥獣が、神使として考えるようになりました。
八幡神の神使は鳩になります。
8月23日(金)
平安時代から鎌倉時代にかけて、甲斐源氏の南部氏がこの地域一帯に勢力を伸ばしていました。南部(波木井)実長は、鎌倉から日蓮上人を招聘し身延山久遠寺を開いています。鎌倉時代に甲斐源氏の後裔、秋山光朝の長男光定は秋山氏を継ぎ、次男光重は下山に住して下山氏を名乗り、三男光季(みつすえ)は常葉の五条が丘に居を構えて常葉氏を名乗っています。常葉氏は十代約300年間豪族としてこの地に栄えたましが、やがて穴山氏が東河内領に勢力を強めるにしたがって次第に衰え、永禄8年(1565)に滅亡しました。常葉氏に関する史資料や史跡は、ほとんど残されていないのが現状です。
本栖道(国道300号線)が富士川にかかる富山橋を東に越えた、波高島トンネル手前の交差点東南には若宮八幡神社があります。常葉光季は、最初常葉川と栃代川合流点にこの若宮八幡宮を勧請しました。戦国時代に大風洪水(台風か)によって流出してしまい、富士川手前の波高島村前島において穴山氏の家臣佐野信義がこれを拾い上げて、祀ったと伝えられています。
 最初に祀られた所は川の合流点ということもあって、江戸時代前期に再建後にまた流失してしまったので、その社地に徳川家康公を祀って日光社(日光権現社)と称して今に至っています。境内の岩盤上には、目通り幹囲8.5m以上にもなる身延町指定の天然記念物「常葉日光社大ケヤキ」があり、目通り幹囲3.5m以上のケヤキと根が結びついていることから、誰言うこともなく「夫婦ケヤキ」と呼ばれ境内地の目印となっています。
最初に祀られた所は川の合流点ということもあって、江戸時代前期に再建後にまた流失してしまったので、その社地に徳川家康公を祀って日光社(日光権現社)と称して今に至っています。境内の岩盤上には、目通り幹囲8.5m以上にもなる身延町指定の天然記念物「常葉日光社大ケヤキ」があり、目通り幹囲3.5m以上のケヤキと根が結びついていることから、誰言うこともなく「夫婦ケヤキ」と呼ばれ境内地の目印となっています。
8月19日(月)
自宅から金山博物館の通勤途中には、数種の街路樹が植えられています。旧道の街中を通る道には歩道がなく街路樹を植えるスペースがありませんが、比較的最近に新設された広い通りの歩道部分には街路樹が整備されています。街路樹は桜(サクラ)、花水木(ハナミズキ)、白樫(シラカシ)、榎(エノキ)などが見られます。
 自宅の近くの街路樹のシラカシに、コブが異常にたくさんついている木があるのを発見しました。この木以外のほとんどにコブはなく、あっても数個のみでそれほど目立ちません。ネットの検索では樹幹こぶ病と記載しているものもありましたが、枯らすほどの性悪な病気ではないとのことです。ほとんどのこぶ病は細菌によって発生するそうです。病原の細菌は昆虫などによって運ばれて侵入し、細菌の増殖するときに分泌する成分によって組織の細胞が増えて肥大化してコブになるそうです。また、幹の傷口を自然治癒力で回復する肉巻きが原因でコブができるといった説もありますが、詳しいことはわかっていないみたいです。
自宅の近くの街路樹のシラカシに、コブが異常にたくさんついている木があるのを発見しました。この木以外のほとんどにコブはなく、あっても数個のみでそれほど目立ちません。ネットの検索では樹幹こぶ病と記載しているものもありましたが、枯らすほどの性悪な病気ではないとのことです。ほとんどのこぶ病は細菌によって発生するそうです。病原の細菌は昆虫などによって運ばれて侵入し、細菌の増殖するときに分泌する成分によって組織の細胞が増えて肥大化してコブになるそうです。また、幹の傷口を自然治癒力で回復する肉巻きが原因でコブができるといった説もありますが、詳しいことはわかっていないみたいです。
それにしてもこのコブの数の多さは、気持ちが悪いくらいですが、樹勢は他の木とほとんど変わらないようです。人間にも昔話に「こぶとりじいさん」の話がありましたが、その比ではありません。この木のこぶの大量発生のほんとの原因はいったい何なのでしょうか?
8月18日(日)
猛暑が続く中、乾燥しがちな陽気ですが博物館駐車場の周辺の植栽のまわりやリバーサイドパークの土手や河原には、雑草の中に紛れて帰化植物が意外とたくさん生えています。帰化植物とは、本来の自生地から人間の活動によって他の地域に運ばれ、意図せず野生化した外来植物の総称です。セイヨウタンポポ、シロツメクサ、セイタカアワダチソウ、オオマツヨイグサ、ビロードモウズイカ、キササゲ、ヨウシュヤマゴボウ、ヒメジョオン、ハルジオンなどが確認できました。
今の時期、この中ではヒメジョオンとヨウシュヤマゴボウが幅を利かせています。ヨウシュヤマゴボウは1~2メートルと大きくなっており、白い花と濃い紫色のブドウの房のような果実をつけています。一見おいしそうですが有毒植物です。

ヒメジョオンは漢字で「姫女菀」と表記し、「姫」は小さい、「女菀」は中国から来た野草を表しますが、原産地は北アメリカです。キク科の一年草または越年草で、白い小さな花を咲かせます。同類のハルジオンと似て混同されやすいのですが、茎の中身、つぼみの向き、葉の付き方で両者は見分けられます。日本に入ってきた当初は、「柳葉姫菊」や「鉄道草」と呼ばれていたそうです。江戸末期に観葉植物として移入されましたが、明治期には早くも雑草として野生化していたようです。
8月17日(土)
昨日は盆の送り火が焚かれ、お盆さんが終わりました。盆の帰省や盆行事によって、ご先祖様のことや家のことひいてはご自身の出自について再考された方々も多かったのではないでしょうか。祖先から脈々と受け継がれてきた血筋によって、今の自分自身が存在することは間違いありません。
現在個々の人間を特定するために、日本では「氏名」が用いられています。「氏名」は一般的には、「姓」と「名」から構成されます。「姓」は家や氏族の名称、「名」は個人の名称を表しています。
戦国時代の武士の名前は、氏(うじ)と名字、実名(じつみょう)と通称からなっていました。甲斐の戦国大名「武田信玄」に当てはめると、氏は源氏の「源」、名字は「武田」、実名は「晴信」、通称は「太郎」です。氏は先祖が天皇から与えられた本姓で、改まった場面で用いられました。出自が「甲斐源氏」の源義光にあたり、さらにさかのぼって「清和源氏」に通じるため「源」になります。しかし、これだけではわかりずらいので、多くの場合一族が定着した土地の名前を名字として用いていました。「武田」は武田信義が拠点とした韮崎の武田ではなく、信義の祖父義清が拠点とした常陸国武田郷(茨城県ひたちなか市)からきています。実名の「晴信」は、時の将軍足利義晴から一字をいただいて付けられました。通称は仮名(けみょう)の太郎、官途名(かんとめい・朝廷の官位のうち中央官)の大膳大夫(だいぜんのだいぶ)、受領名(ずりょうめい・朝廷の官位のうち地方官)の信濃守(しなののかみ)です。子供の頃の幼名(ようみょう)は勝千代、出家して法性院(徳栄軒)信玄、道号は機山、戒名は法性院機山玄公大居士などです。なんとたくさんのお名前があるのでしょう。実名は諱(忌名)とも言って直接呼ぶことが失礼にあたるので、普段は仮名などの通称で呼ばれるようになります。
なお、足利将軍家から特に「御屋形号」を名乗ることが認められており、領民や家臣から「御屋形様」と呼ばれていました。
8月12日(月)
金唐革紙(きんからかわかみ)という明治時代を中心に使われた高級な建築壁紙があります。これは和紙に金・銀・錫などの金属箔を張り、版木の凹凸文様を打ち出して彩色を施したものです。もともとは西欧で家具等に使われていた「金唐革」を、日本で革の代わりに和紙を用いて作られたそうです。甲府市の国重要文化財高室家住宅や同市の国登録文化財旧堀田家住宅にも一部にこれが使用されていることがわかっています。鹿鳴館にも使用されていたといわれ、旧岩崎家住宅(国重文)にも一部に当時の復元がされています。明治期にはウィーン万博やパリ万博にも出品されて好評を博し、輸出もされてバッキンガム宮殿にも使用されたということです。
 先日岡谷市の旧林家住宅に行ってきました。林家は製糸業で財を成した家柄で、金唐革紙や欄間彫刻に特長のある国重要文化財の建物です。金唐革紙を壁面や天井いっぱいに張り巡らされている離れ二階の和室は、「幻の金唐革紙」と言われるくらい希少価値が高く素晴らしいものでした。金唐革紙を当時の色に復元したサンプルもあり、当時いかに荘厳な空間であったかが偲ばれます。金の利用も時代によって、特殊な使われ方の一端を示す貴重な文化遺産です。
先日岡谷市の旧林家住宅に行ってきました。林家は製糸業で財を成した家柄で、金唐革紙や欄間彫刻に特長のある国重要文化財の建物です。金唐革紙を壁面や天井いっぱいに張り巡らされている離れ二階の和室は、「幻の金唐革紙」と言われるくらい希少価値が高く素晴らしいものでした。金唐革紙を当時の色に復元したサンプルもあり、当時いかに荘厳な空間であったかが偲ばれます。金の利用も時代によって、特殊な使われ方の一端を示す貴重な文化遺産です。
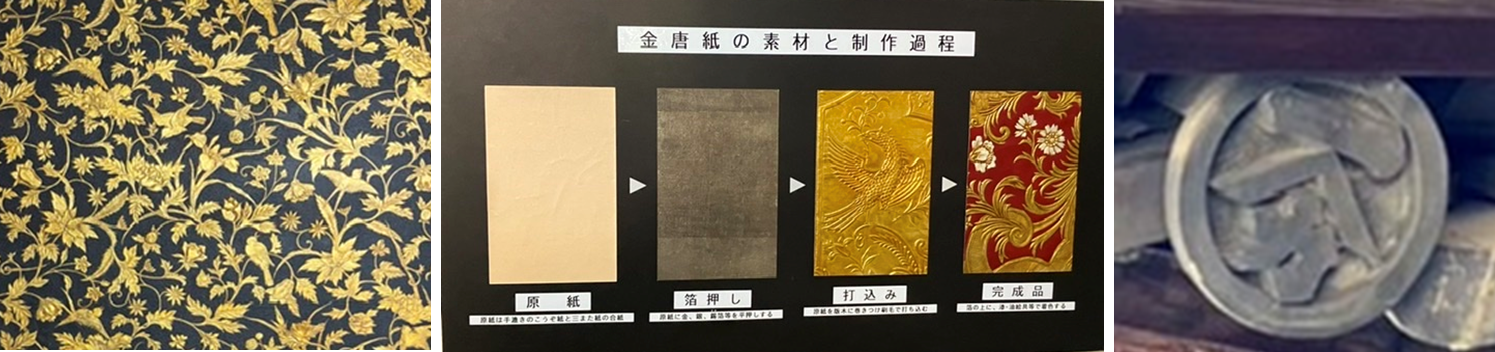
8月9日(金)
一旦思い込んでしまうととんでもない間違いをするものです。前回の「鬼百合」の記事がそうです。花のつぼみの形を見れば違うことは一目瞭然、これが「鬼百合」であるわけがない。判断を誤った理由は、かつて「鬼百合」が庭に植えられていたということのみです。よく見ればつぼみの形や色だけでなく、葉の付け根の所にあるはずのムカゴがありません。こんな初歩的な間違いをしたことには、いかに思い込みや先入観というものが、なかなか払しょくできないことの表れです。とんだ、早とちりでした。お詫び申し上げます。(早とちりとは、早合点をして間違えること。ホント、大人なんだからもう少し慎重で思慮深くありたいものです。)
そういえば直接関係ないのですが、小学校の時に漢字テストで、「庭」の字の「广(まだれ)」の中を「延」として覚えてしまっていたために先生にペケをもらった理由がすぐにわからなかったこと、しばらく正しい「庭」の字が書けなかったことを思い出しました。
8月5日(月)
私の自宅の庭はアスファルトの道路に面しています。道路と庭を分けるコンクリートの裂け目に、3本もの鬼百合(ホントは高砂ユリ)が花のつぼみを付けているのを今朝確認しました。「ど根性鬼百合(高砂ユリ)」です。もともと道路と庭の間に隙間はなく、よく見ると造成した盛土部分のコンクリートと道路の間にわずかな亀裂が生じているのがわかりました。その隙間に庭の土が上から落ちて少し溜まり、そこへ庭に植えてあった鬼百合(高砂ユリにはムカゴが無い)のムカゴが数年前に入り込んだ結果の産物だと思われます。この部分に鬼百合(高砂ユリ)が入り込んでいるのは、掃除や水撒きの際にその存在は確認しておりました。植物の生育には不適切な環境であるので30センチくらいと背丈は少し小さ目ではありますが、今年になって初めて花を咲かそうとしています。暖かく見守りたいと思います。金山博物館の入口付近の植栽の中にも鬼百合(高砂ユリ)があります。こちらは通常サイズの1メートル強の背丈です。
 百合の中でもは白い山百合が1か月ほど早く咲くのに対し、赤い鬼百合は真夏の花で夏休みの絵日記によく登場するイメージがあります。ユリの語源は諸説ありますが、ユリの花が風に吹かれて揺れる「揺り」から来ている説が有力だそうです。また、「百合」と漢字で表記されるのは、食用に供されていた「ユリネ」の球根の鱗片がたくさん合わさっているようすから、たくさんの数を表す「百」が使われているのだとか。同様に湯之奥三金山の一つの「中山千軒」という使われ方も実際の数字ではなく、たくさんを表す「千」の象徴的な使用です。
百合の中でもは白い山百合が1か月ほど早く咲くのに対し、赤い鬼百合は真夏の花で夏休みの絵日記によく登場するイメージがあります。ユリの語源は諸説ありますが、ユリの花が風に吹かれて揺れる「揺り」から来ている説が有力だそうです。また、「百合」と漢字で表記されるのは、食用に供されていた「ユリネ」の球根の鱗片がたくさん合わさっているようすから、たくさんの数を表す「百」が使われているのだとか。同様に湯之奥三金山の一つの「中山千軒」という使われ方も実際の数字ではなく、たくさんを表す「千」の象徴的な使用です。
8月2日(金)
今日も暑いですね。熱中症警戒アラートがまた発令されています。外は連日の猛暑日が続いており、まだあと何日かは続く予定です。今年の夏は過去最高気温が更新される予報だそうです。でも、当館は今夏、空調設備が改修され涼しく快適です。これまで扇風機の風だけという館内の冷房機器が、うそのようです。砂金採り体験室も相変わらず盛況です。水中の砂の中から砂金を探し出すので涼感が味わえ、夏休みを迎えた家族での挑戦が増えています。
 いつしかセミが盛んに鳴いているのに気づきました。セミは、夏の象徴ともいえる昆虫ですね。種類はアブラゼミとニイニイゼミがほとんどで、ミンミンゼミはまだ早いようです。実はセミの生態は、まだよくわからないことが多いのです。セミの成虫の寿命はこれまで約1週間くらいだと言われていたのですが、2019年の研究成果から2週間~1か月程度生きられることがわかりました。数年も地中で暮らし地上に出てからは短命だと言われていたのですが、昆虫の中では長生きな方です。これを発見したのが昆虫学者ではなく高校生だったというから驚きです。昆虫や生物に限らずまだまだ常識や定説とされていることも、新たな研究成果や地道な観察によって覆ることもありそうですね。日常のいろんなことに疑問を持つことが大事です。夏休みの自由研究のテーマの見つけ方も、身近なものや出来事になぜだろうと思う心が大切です。
いつしかセミが盛んに鳴いているのに気づきました。セミは、夏の象徴ともいえる昆虫ですね。種類はアブラゼミとニイニイゼミがほとんどで、ミンミンゼミはまだ早いようです。実はセミの生態は、まだよくわからないことが多いのです。セミの成虫の寿命はこれまで約1週間くらいだと言われていたのですが、2019年の研究成果から2週間~1か月程度生きられることがわかりました。数年も地中で暮らし地上に出てからは短命だと言われていたのですが、昆虫の中では長生きな方です。これを発見したのが昆虫学者ではなく高校生だったというから驚きです。昆虫や生物に限らずまだまだ常識や定説とされていることも、新たな研究成果や地道な観察によって覆ることもありそうですね。日常のいろんなことに疑問を持つことが大事です。夏休みの自由研究のテーマの見つけ方も、身近なものや出来事になぜだろうと思う心が大切です。
7月28日(日)
第21回砂金甲子園!東西中高交流砂金掘り大会がやってきました。灘中高、神戸女学院中高、逗子開成中高、桐朋学園中高、山梨学院中高、麻布学園中高、大妻中高、開成学園中高、市川学園中高、海城中学高等学校、早稲田大学高等学院の11校の精鋭たちが全国から集まってくれました。
「砂金掘りはスポーツだ」を合言葉に、小さな砂金粒をスピードとテクニック、そしてチームワークを駆使して集める白熱した大会となりました。優勝は灘中学・高等学校、準優勝は神戸女学院中学部高等学部、3位は桐朋学園桐朋中学高等学校です。優勝と準優勝は、昨年と同じ顔ぶれになりました。一年間かけて練習して磨いてきた技を、若い中高生たちが必死になって繰り出してくれました。本当に熱い熱い戦いで、選手はもとより応援にも熱が入っていました。速さと正確さが求められる厳しい戦いでした。
 真夏の暑い日差しが照り付ける中を全国から集まっていただいた選手の皆さん、そしてご協力をいただいた湯之奥金山博物館応援団AU会、砂金掘り友の会のみなさんありがとうございました。そしてお疲れさまでした。
真夏の暑い日差しが照り付ける中を全国から集まっていただいた選手の皆さん、そしてご協力をいただいた湯之奥金山博物館応援団AU会、砂金掘り友の会のみなさんありがとうございました。そしてお疲れさまでした。
7月22日(月)
今日から「二十四節気(にじゅうしせっき)」の「大暑(たいしょ)」に入ります。「二十四節気」は、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つの節気に分けたものです。それぞれの節気は、「立春」、「雨水」、「啓蟄」など天候や生き物の様子で表現され、季節の目安とされてきました。「大暑」はその字のごとく、1年で最も暑さが厳しい時期です。今年の「立秋」が8月7日なので6日までが「大暑」の期間になります。甲斐黄金村・湯之奥金山博物館では、この期間中に「砂金掘り大会」、「砂金甲子園!」を開催します。暑さを吹っ飛ばす熱戦が期待されます。
今日も非常に暑いですね。さすがに日本中が猛暑の熱気におおわれています。広範囲に熱中症警戒アラートが発令され、今日の最高気温が甲府では39.4℃、身延でも37.7度を記録しています。でも、博物館の中は、去年と違って冷房がよく効いていて快適です。(去年までは空調が壊れて扇風機のみでした。)また、砂金採り体験室は、水中の砂の中から砂金を探し出すので、水がひんやりして気持ちがいいですよ。小中学生、高校大学生のみなさんも、「大暑」の暑さを乗り切るためにも夏休みを利用して涼しい博物館に来てください。
7月21日(日)
今日は第16回化学実験教室、「教えてみやもん先生」を開催いたしました。開成中学校・高等学校の理化学部顧問の宮本一弘先生が、用意してくださった化学の実験です。3時限それぞれ15名前後の皆さんが参加してくれました。「水」と「氷」と「空気」など身近にあるものが、不思議な化学変化をして驚かせてくれました。水の上に浮かべた紙がひとりでに動いたり、ペットボトルを押したり離したりすることで中のものが浮いたり沈んだりする浮沈子実験などなぜなんだろう、どうしてだろうとみんな興味津々でした。
 今日から8月の28日まで、山梨県の小中学校は夏休みです。小中学校時代は、夏休みがなんと待ち遠しかったことでしょう。親子連れの来館者も増えて、また忙しくなりそうです。
今日から8月の28日まで、山梨県の小中学校は夏休みです。小中学校時代は、夏休みがなんと待ち遠しかったことでしょう。親子連れの来館者も増えて、また忙しくなりそうです。
7月15日(月)
昨日我家の庭にカミキリムシが来ていました。写真を撮ろうとしたら下に落ちたのと網戸にたかったのに分かれ、2匹のつがいだったようです。申し訳ないことに仲を裂いてしまった形になってしまいました。「つがい」は漢字で書くと「番」なのですね。「蝶番(ちょうつがい)」の「番」です。といっても、もう知らない人の方が多いんでしょうね。
カミキリムシは、「紙切り虫」だとずっと思っていましたが、「髪切り虫」が正しいのだそうです。結んだ髪さえも切り落とすほど、大きくて強い顎を持っていることがその名の由来だそうです。写真のカミキリムシは、「ゴマダラカミキリ」です。漢字では「胡麻斑」と書き、羽に胡麻を散らしたような細かい点があることから名付けられました。
 去年この時期にリバーサイドパークに「キボシカミキリムシ(黄星髪切虫)」がいました。(3枚目の写真)下部川の土手の桑園だった痕跡を残す桑の葉に乗っており、桑の木を食する害虫として嫌われものでした。子供の頃50~60年前に大発生し、駆除に補助金が出されていました。1匹捕まえれば10円であったような、、、。家の周りは桑園だらけ、子供の頃見つけたら殺すようにしつけられ、頭部を引きちぎっていました。今考えればなんと残酷な事をしていたか。でも頭の数で褒賞金をもらえると聞いたような、、、。
去年この時期にリバーサイドパークに「キボシカミキリムシ(黄星髪切虫)」がいました。(3枚目の写真)下部川の土手の桑園だった痕跡を残す桑の葉に乗っており、桑の木を食する害虫として嫌われものでした。子供の頃50~60年前に大発生し、駆除に補助金が出されていました。1匹捕まえれば10円であったような、、、。家の周りは桑園だらけ、子供の頃見つけたら殺すようにしつけられ、頭部を引きちぎっていました。今考えればなんと残酷な事をしていたか。でも頭の数で褒賞金をもらえると聞いたような、、、。
戦国時代いくさの手柄は、倒した大将や武将の首でした。下級武士では首実検もできず手柄にならないので、倒した数で褒美がもらえました。首を持ち運ぶには邪魔になるので、鼻をそいだり耳を切り落としたりしてその数を証拠として提出したようです。笛吹市に「花鳥山(はなとりやま)」という場所があります。一本杉が有名で縄文時代前期の大集落があり、今はリニア実験線の展望台として整備されています。一見きれいな地名なのですが、実は昔ここで戦があって首実検で戦功を証する「鼻取り山」が地名の語源なのです。本当は怖い話ですね。その時の遺体を埋葬したという塚が、今でも残されています。「首実検」と「リニア実験線」、、、、そういえば子供の頃に集めたカミキリムシも報奨金目当ての首実検だったんだなあ、、、。
7月12日(金)
「栃代川上流のハコネサンショウウオ及び生息地」が、山梨県の「自然記念物」に指定されています。「自然記念物」とは、山梨県自然環境保全条例に基づいて山梨県知事によって指定されるもので、文化財保護法や文化財保護条例で規定される「天然記念物」とは違った法体系のものです。自然環境の保護と活用を目的とし、生物の多様性を確保し学術的価値のあるもののうち将来にわたって保護する必要があるものがその生息地とともに指定されます。
先日、内山金山の現地調査で確認した「ハコネサンショウウオ」は、黒色に近い黒褐色で、子供と思われる小さい別個体は体に透明感のある灰褐色をしていました。内山金山に行くたびに、生息を確認することができます。
『山椒魚』といえば井伏鱒二の代表作としてよく知られています。その井伏鱒二はたびたび下部温泉を訪れており、井伏がこよなく愛した地として知られています。作品の中でも、下部の川や旅館がたびたび登場しています。かつて当博物館の特別展でも「つり人 井伏鱒二~下部を愛した文学者~」を開催し、下部の旅館や親交のあった「やまめ床」などに残っている当時の写真やゆかりの品々を集めて紹介させていただきました。
作品中の山椒魚は「オオサンショウウオ」のようですが、身延町の地域内でも標高の高い渓流部には、「ハコネサンショウウオ」がまだまだたくさん生息しています。
7月8日(月)
3日に金山の現地確認調査に行ってきました。甲斐黄金村・湯之奥金山博物館は、中山金山、茅小屋金山、内山金山と三つの金山のガイダンス施設です。中山金山は、発掘調査をはじめとする総合学術調査が実施されて、1997年に国史跡に指定されております。残りの茅小屋金山と内山金山については、未指定であるため再調査の計画を立てるにあたり、今回の現状確認調査になりました。
 朝5時に博物館に集合。参加者は、帝京大学山梨文化財研究所の職員2名、博物館からは学芸員2名と私、それに山に詳しい協力者1名の計6名で出発。支度を整え車で入ノ沢入口へ移動。歩き始めると参加者の1名が対岸に熊を発見する。すぐに山の中に逃げ込んでしまったが、この付近では過去の調査時にも熊の目撃情報があり、目的地のひとつ内山金山では平坦地のテラス群に熊のフンがいっぱい落ちていたので、調査時には熊対策も一つの課題である。今回も熊除けに爆竹を休憩するたびに鳴らし、笛を吹きながら、人間の存在を先に熊に知らしめながら登りました。茅小屋金山は6月21日に現地を確認しているため、小休止のみで内山金山に向かいました。
朝5時に博物館に集合。参加者は、帝京大学山梨文化財研究所の職員2名、博物館からは学芸員2名と私、それに山に詳しい協力者1名の計6名で出発。支度を整え車で入ノ沢入口へ移動。歩き始めると参加者の1名が対岸に熊を発見する。すぐに山の中に逃げ込んでしまったが、この付近では過去の調査時にも熊の目撃情報があり、目的地のひとつ内山金山では平坦地のテラス群に熊のフンがいっぱい落ちていたので、調査時には熊対策も一つの課題である。今回も熊除けに爆竹を休憩するたびに鳴らし、笛を吹きながら、人間の存在を先に熊に知らしめながら登りました。茅小屋金山は6月21日に現地を確認しているため、小休止のみで内山金山に向かいました。
茅小屋金山から先は道がなくなっており、ルートの目印となるテープを付けながら登りました。平地では猛暑日の予報で、熱中症警戒アラート発令中でした。標高が高くはなるのですが、暑さと疲労が体力を奪って、さすがにきつい。地図やスマホの位置情報を頼りに、急傾斜地を登って内山金山に到着。現地では昼食後平坦地や石垣を確認し、遺物の表面採集をしながら、前回行けなかったテラス群も調査しました。テラスにある石臼や墓石も再確認しました。早朝からの調査ではあるが内山金山の現場到着までに、道なき道を休憩も入れて4時間半はきついものがありました。
 帰りには澤の冷たい水でのどを潤し、石の下にいたサンショウウオ発見。しばし休憩して疲れを癒します。車に戻った時には、筋肉痛で体中が痛く、体がほてっていてとても暑かったです。体中の水分が汗で出てしまったようです。何度来ても、内山金山迄の経路はとても厳しいものです。たいへん疲れました。
帰りには澤の冷たい水でのどを潤し、石の下にいたサンショウウオ発見。しばし休憩して疲れを癒します。車に戻った時には、筋肉痛で体中が痛く、体がほてっていてとても暑かったです。体中の水分が汗で出てしまったようです。何度来ても、内山金山迄の経路はとても厳しいものです。たいへん疲れました。
7月7日(日)
今日は七夕です。五節句のひとつで、奇数月の月と日が重なった季節の節目の日に、邪気を払い無病息災を願う行事が行われました。五色の短冊へ願い事を書いて、葉の付いた竹の枝に吊るします。まだ梅雨明け前だというのに、この頃のこの暑さは尋常ではないですね。熱中症には十分お気を付けください。
さて、「金魚」はどうして赤や白が多いのに「金魚」というのでしょうか。当博物館の入口にも、水槽に大きな金魚達が皆さんのお出迎えをしてくれています。金山博物館とは言っても、金魚は金色ではありません。錦鯉には金色のものも見かけますが、金魚は赤、白、黒が基本のようです。もとをただすと、中国の揚子江流域にいた突然変異の赤いフナがそのおおもとで、室町時代に日本にわたってきたらしいのですが、詳しいことはわかっておりません。
 「金魚」といえば奈良県の大和郡山市が、産地として有名です。享保9年(1724)に、甲府から転封になった柳沢吉里公の家臣が、金魚を持ち込んだとも伝えられています。そして大和郡山藩の下級藩士たちがそれを広めて、現在のようになったというものです。
「金魚」といえば奈良県の大和郡山市が、産地として有名です。享保9年(1724)に、甲府から転封になった柳沢吉里公の家臣が、金魚を持ち込んだとも伝えられています。そして大和郡山藩の下級藩士たちがそれを広めて、現在のようになったというものです。
「金魚」は中国でも「金魚」と表記されています。金を生む魚かはたまた金のように貴重で珍しい魚からなのでしょうか。英語表記でも「Goldfish」というそうです。もとは赤より黄色に近かったとの説もあります。夏の風物詩、視覚からくる涼を金魚でお届けです。
7月1日(月)
今日から7月になりました。令和6年(2024)もすでに半分が過ぎてしまいました。6月30日の昨日は「夏越の祓(なごしのはらえ)」が各地の神社で執り行われていました。一年の折り返しにあたるこの日に、1月から6月までの穢れを祓い清め、7月から12月までの残り半年の無病息災を祈願する行事です。
夏越の祓では、「茅の輪(ちのわ)くぐり」と「人形(ひとがた)流し」が特徴的です。「茅の輪くぐり」は、左回り⇒右回り⇒左回りと8の字を描くように3回茅の輪を回ることで災厄を祓います。「人形流し」は、人形に切った紙の「人形代(ひとかたしろ)」に自分の罪や穢れを移して川などに流すのが本来の姿ですが、今ではごみ問題もあるのでお焚き上げをするところが多いようです。
 山梨県内でも武田神社などでおこなわれています。実際にはこの施設がある神社に行かないと行えませんが、皆さんもこれまでの半年を顧みるとともに今後の半年を健全に過ごせるよう、何かしらの方法で意識してリフレッシュしてみてはいかがでしょうか
山梨県内でも武田神社などでおこなわれています。実際にはこの施設がある神社に行かないと行えませんが、皆さんもこれまでの半年を顧みるとともに今後の半年を健全に過ごせるよう、何かしらの方法で意識してリフレッシュしてみてはいかがでしょうか
6月30日(日)
「大炊平」地区の区民総会に今月15日にお邪魔した時に、集落の入口に「禁酒」の文字の入った石柱が目についた。てっきり禅宗寺院の門前によく見られる「禁葷酒」もしくは「不許葷酒入山門」と書かれているかと思いきや、そこにある文字は「禁酒興國」でした。
 「不許葷酒入山門」は「葷酒(くんしゅ)山門に入るを許さず」と読み、「葷」はニラやニンニク、ネギなど臭いの強い野菜のこと。臭気のある強壮野菜類やお酒は、心を乱し修行の妨げになるので、清浄を旨とする境内(山門内)への持ち込みを禁止するという結界を示す言葉です。石碑のある上の位置に公民館があって、裏手に墓石もあったことからここが廃寺となった寺境内の入口だろうと、そう早とちりをしていたのでした。
「不許葷酒入山門」は「葷酒(くんしゅ)山門に入るを許さず」と読み、「葷」はニラやニンニク、ネギなど臭いの強い野菜のこと。臭気のある強壮野菜類やお酒は、心を乱し修行の妨げになるので、清浄を旨とする境内(山門内)への持ち込みを禁止するという結界を示す言葉です。石碑のある上の位置に公民館があって、裏手に墓石もあったことからここが廃寺となった寺境内の入口だろうと、そう早とちりをしていたのでした。
実際に記されている正面の文字は「禁酒興國 正三位勲二等長尾三平書」、左側面に「創立五周年記念/昭和六年七月建設/大炊平禁酒團」とあります。元号が12月に昭和に代わる大正15年(1926)に結成された「大炊平禁酒團」の創立五周年を記念して建設された石碑(石+コンクリート製かも)であることがわかります。まさにアメリカ合衆国でも禁酒法が施行されていた時期でもあり、アルコール中毒や犯罪などのトラブル防止運動と、飲酒に伴う散財を止めそれからねん出されたお金をお国のために使おうというものであります。当時の大炊平の若者たちが酒で身を亡ぼすことが無いよう、血判状までして禁酒団を結成したとも伝わっています。しかし、昭和恐慌から戦時体制下に移行する過渡期における農村部の疲弊が、その背景にあったのかもしれません。
写真左側の2枚が大炊平の「禁酒興國」の碑です。全国的にも珍しいもので他の類例を知りません。地域の歴史を物語る貴重な歴史遺産です。3枚目は甲府市朝日三丁目慶長院の「不許葷酒入山門」の石碑、右が甲府市元紺屋町宗信寺の「禁葷酒」の石碑です。
6月28日(金)
残念な名前の植物があります。「ヘクソカズラ」です。博物館周囲やリバーサイドパークに植栽されているツツジやアジサイ、フェンスなどにからみついている生命力の強いつる性の多年草です。「ヘクソカズラ」は「屁糞葛」「屁臭葛」とも表記され、万葉集にも「糞葛」として歌にも歌われた古くからこの名で登場する植物です。その名の由来は、葉や茎を揉んでみると糞尿や屁のような独特のにおいを発するからです。同じように英名もstinkvine(悪臭のするツル)や、chicken excrement plant(鶏糞の匂いがする植物)、中国名でも鶏尿藤(けいしとう)と悪臭に由来する不名誉な命名になっています。葉を揉んでにおいをかいでみたのですが、この梅雨時には臭みの成分が行き渡らないほど成長するためか、それほど嫌な臭さは私には感じられなかったのですが、、、。
 「ヘクソカズラ」の花は、真ん中が紅紫色で釣鐘形をした白い可憐な花です。別名は、「灸花(やいとばな)」、「早乙女花(さおとめばな)」です。灸花は、その中心の紅紫色がお灸をすえた跡に見えるためです。早乙女花は、花を水面に浮かべた様子が、早乙女のかぶる笠に見えることからだそうです。
「ヘクソカズラ」の花は、真ん中が紅紫色で釣鐘形をした白い可憐な花です。別名は、「灸花(やいとばな)」、「早乙女花(さおとめばな)」です。灸花は、その中心の紅紫色がお灸をすえた跡に見えるためです。早乙女花は、花を水面に浮かべた様子が、早乙女のかぶる笠に見えることからだそうです。
花の外見は可憐で美しく感じるのですが、ひとたび葉や茎を傷つけると、悪臭を放つのです。この悪臭は、花に誘われて寄ってきた害虫が葉などを食べたときに、いやなにおいを発して害虫を撃退するのです。植物が自らの身を守るために備わった防衛手段だそうです。
名前も別名の「早乙女花」であれば、美しく可憐なお田植えする早乙女をイメージ出来て好印象を持たれますが、正式名称が「ヘクソカズラ」とは、なんて残念でかわいそうな名称を付けられてしまったのでしょうか。
6月24日(月)
今日は昨日までと打って変わって、太陽が顔を出し気温が上昇しています。天気予報では、甲府で34℃の猛暑日の一歩手前にまで上がる予想です。博物館の外に出てリバーサイドパークを昼休みに散歩してみたのですが、日差しが強くものすごく蒸し暑い陽気です。
 トカゲが草むらから飛び出してきました。青い金属色をしたしっぽを持ち、頭から背中にかけて白い筋がありツヤのある体色をしています。ヒガシニホントカゲの幼体か若い個体のようです。このトカゲは大人になると、ツヤこそありますが茶色で地味な色に変わっていきます。カナヘビも茶色ですが、光沢はありません。どちらもこの付近ではよく目にする生き物です。なぜ幼体のトカゲのしっぽが青いのでしょう。それはトカゲの「しっぽ切り」に関係しているようです。若いトカゲは動きがまだ緩慢で、ヘビや鳥など敵に襲われやすいため、しっぽを自分から切断し天敵から身を守るのです。切り離されたしっぽはしばらく盛んに動き回って、敵の目を本体から目立つしっぽに向けさせるのです。その間に安全な草むらや石の影に逃げ込むのです。大人になると素早くなって、逃げ隠れも上手になるのでしっぽの色も地味目に変わるのです。
トカゲが草むらから飛び出してきました。青い金属色をしたしっぽを持ち、頭から背中にかけて白い筋がありツヤのある体色をしています。ヒガシニホントカゲの幼体か若い個体のようです。このトカゲは大人になると、ツヤこそありますが茶色で地味な色に変わっていきます。カナヘビも茶色ですが、光沢はありません。どちらもこの付近ではよく目にする生き物です。なぜ幼体のトカゲのしっぽが青いのでしょう。それはトカゲの「しっぽ切り」に関係しているようです。若いトカゲは動きがまだ緩慢で、ヘビや鳥など敵に襲われやすいため、しっぽを自分から切断し天敵から身を守るのです。切り離されたしっぽはしばらく盛んに動き回って、敵の目を本体から目立つしっぽに向けさせるのです。その間に安全な草むらや石の影に逃げ込むのです。大人になると素早くなって、逃げ隠れも上手になるのでしっぽの色も地味目に変わるのです。
6月23日(日)
甲府(こうふ)駅は、かつて「ふふか」と表記されていました。横書きでは、文字を右から左へ読むというのが一般的でした。明治時代以降、西洋の横文字文化の影響で、日本でもこの文章のように左から右への横書き表記が見られるようになります。前回記事の地図と同じ下の写真をよく見てください。「ふふか」、「園公鶴舞」、「町園花」の右から左への地名表記が見て取れます。
 「こうふ」は歴史的仮名遣い(旧仮名遣い)で「かふふ」と表記されます。当時の人には「かふふ」を「こうふ」なんて読むのは、知っている人じゃなければなかなか読めなかったんじゃあないかなと思います。
「こうふ」は歴史的仮名遣い(旧仮名遣い)で「かふふ」と表記されます。当時の人には「かふふ」を「こうふ」なんて読むのは、知っている人じゃなければなかなか読めなかったんじゃあないかなと思います。
現代仮名遣いで「こー」と発音する音韻の仮名で「こう」と表記されるものは、文化庁の歴史的仮名遣い対照表(ユー~ロー)で次のように示されています。歴史的仮名遣いで用いる仮名に、「こう」、「こふ」、「かう」、「かふ」、「くわう」の五種類の別があることがわかります。現代と同じ「こう」は「功績、公平など」、「こふ」は「永劫の濁点がない時」、「かう」は「咲かう、かうしてなど」、そして甲府の場合の「かふ」は「甲乙、太閤など」、「くわう」は「光線、広大など」で用いられます。これらを瞬時に峻別することは非常に難しいことで、調べてみたって頭が混乱するばかりです。
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに返還するとき、「ハ行」の「はひふへほ」は「ワ行」の「わいうえお」にまず変換します。「かふふ」は「かうう」となるように思われますが、二つ以上の語が合わさった時の「ハ行」は変わらないままなので「かうう」とはならずに「かうふ」になることになります。「かうふ」は「kaufu」と母音が重なるため「au」は「オー」と発音することから、「こーふ」となるようです。文化庁の歴史的仮名遣い対照表(ユー~ロー)の「甲(こう)」が「かふ」になります。「こうふ」が「かふふ」と表記される理由はのはこのようなことからでしょうか。
にわか仕込みなので、これでいいのかどうか?ハテナです。
6月21日(金)
明治36年(1903)に「新宿駅」から「甲府駅」までの中央線が開通しました。開通当時の「甲府駅」は「驛ふふか」と右から左への横書きで表記されていました。歴史的仮名遣いです。昔、中学や高校の古文で習いましたよね。昭和21年(1946)に現在のような「現代仮名遣い」に改められて、駅名についても「左書き、新かなづかい」の「甲府駅」となりました。同じように「驛うわうり」が「竜王駅」、「驛うやきうと」が「東京駅」など、全国の駅名が新しく書き換えられました。当時の甲府市の地図には、甲府駅が「ふふか」と表記されています。
昭和13年に静岡県の「富士駅」から「甲府駅」までの「富士身延鉄道」が開通しました。東海道本線と中央本線を結ぶ鉄道として、また、沿線の日蓮宗総本山身延山久遠寺への参詣客の輸送として建設されました。この現在の身延線の駅名も縦書きで「かふふ」と表記されています。昭和16年に国に買収されて国鉄となる以前なので、私鉄時代の地図表記となっています。

現在の甲府駅1番線ホームから身延線のホームに向かう途中に、「かふふ驛煉瓦ひろば」があります。開業当時の「甲府駅」の名残を伝えるモニュメントで、「旧煉瓦倉庫の一部」、「旧甲府駅の釣鐘」、「旧こ線橋柱」が移設されています。「旧煉瓦倉庫」は創業当時から平成の駅構内整備工事によって取り壊されるまで存在し、私も歴史的建造物として調査をおこなったことがあります。当時現状保存の声もあったのですが、その一部がこうして残されました。かつて明治から昭和初期までランプで灯りを取っていた当時、その燃料の保管やそれに従事した人の勤務場所だったとされています。煉瓦倉庫の妻側の一部が切り取られ、その前にベンチが置かれて休むことができます。「旧甲府駅の釣鐘」は、かつて甲府駅のホームに釣り下げられていたもので、駅構内の建物の火災の時連打されて大事には至らなかったといいます。台座上には明治36年に製造されたレールも展示されています。今は「かふふ来(幸福)の鐘」として、駅を利用される(甲府に来られた)方々に幸福が来るようにとの願いが込められているのではないでしょうか。「旧こ線橋柱」は、「旧煉瓦倉庫」のモニュメントの裏側にあってわかりずらいのですが、錆びた鉄柱が存在します。明治36年に製造された鋳鉄架構の一部で、甲府駅の旧こ線橋に使用されていたものです。
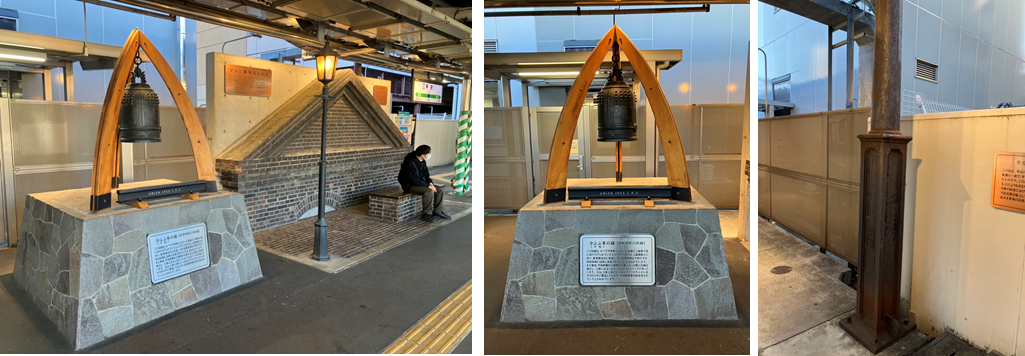
6月16日(日)
身延町の町章は、「身延町のイニシャル「M」をモチーフに、身延山、富士山に囲まれた緑豊かな大地で躍動する人。赤の円は輝く未来を。緑の円は夢・希望・安らぎを表し、ひらかれた、活力に満ち力強く躍進する町を表現。(平成17年12月1日告示第79号)。」ということです。
 今日は大炊平地区の住民総会に時間を取っていただき、同地区内にある柴金遺構の概要について久間先生からみなさまに説明をさせていただきました。一部調査をさせていただいた現状の説明と、地域住民からの情報収集をするためです。説明会の後に現地に行く途中広場にマンホールがあり、この蓋に身延町章があるのを発見しました。このカラーは黄色一色のものです。また、説明会を行った公民館の壁面には、大炊平地区が合併前の下部町体育祭で入賞した表彰状があり、旧下部町章もこれに印刷されていました。下部町の「下」の字を図案化したものです。
今日は大炊平地区の住民総会に時間を取っていただき、同地区内にある柴金遺構の概要について久間先生からみなさまに説明をさせていただきました。一部調査をさせていただいた現状の説明と、地域住民からの情報収集をするためです。説明会の後に現地に行く途中広場にマンホールがあり、この蓋に身延町章があるのを発見しました。このカラーは黄色一色のものです。また、説明会を行った公民館の壁面には、大炊平地区が合併前の下部町体育祭で入賞した表彰状があり、旧下部町章もこれに印刷されていました。下部町の「下」の字を図案化したものです。
 ちなみに、旧身延町の町章は身延町の「身」の字を象ったもので、旧中富町の町章は三つの「ト」の中に「中」の字を図案化したものとされています。旧下部町の町章の色は黒なのですが、町旗が緑色のため表彰状のように緑色も使われています。旧身延町章は赤色と旧中富町章は海老茶色だったのでしょうか。平成の大合併前の市町村章は、単色がほとんどだったのですが、合併後の市町村章は色彩豊かなものも多くなっています。
ちなみに、旧身延町の町章は身延町の「身」の字を象ったもので、旧中富町の町章は三つの「ト」の中に「中」の字を図案化したものとされています。旧下部町の町章の色は黒なのですが、町旗が緑色のため表彰状のように緑色も使われています。旧身延町章は赤色と旧中富町章は海老茶色だったのでしょうか。平成の大合併前の市町村章は、単色がほとんどだったのですが、合併後の市町村章は色彩豊かなものも多くなっています。
6月11日(火)
昨年あれほど咲き誇っていたアジサイ(紫陽花)が、今年は一部の株以外ほとんど花が咲いていません。今年伸びてきた新しい枝の葉の部分は勢いがいいものもあるのですが、株の中にほとんど花がついていないのです。

体験室東の今年の現状 去年の状況 葉も少ない株
アジサイが咲く花芽は、咲き終わった花から新しく伸びた枝に花芽がつくことになります。翌年に新しく伸びた枝 には花芽はつきません。初夏に花を咲かせたアジサイは夏以降に枝を伸ばしながら、翌年咲くツボミの元となる花芽を作ります。そのため8月以降に剪定すると、その花芽も一緒に切ってしまうことになるので花は咲きません。博物館の構内のアジサイは、昨年秋に大幅に株の枝を剪定して形を小さくしました。今年のアジサイはこのために花の数が少なくなってしまったのです。中には切りすぎて、新芽がほとんど出てきていない株もあります。柏葉アジサイやガクアジサイも同じで、剪定の仕方が適切でなかったため花は1輪ずつしか咲いていません。

花のない株 去年剪定しなかった株 柏葉アジサイとガクアジサイ
植物はそれぞれの種類によって特徴があり、その特徴をよく把握してないと今年のアジサイのような事態になってしまいます。昨日のケヤキもそうですが、切ってしまってからでは植物は元には戻りません。しかし、アジサイについては、来年またこれまで通りに見事な花を咲かせてくれるものと期待したいと思います。
6月9日(日)
植物の生命力には驚かされます。昨年、駐車場周辺の環境整備の一環で、山際の樹木などの枝払いや伐採をしました。指示する側と受け手の認識の違いによって、駐車場の中にあるケヤキの木が大胆に伐採されてしまいました。枝がほとんどなくなってしまい、太い枝の主幹のみとなってしまったのです。切りすぎたので木そのものが枯れてしまうのではないかと、心配していたところです。先日この木を見てみると、太い幹から細い枝が直接所々に見えるではありませんか。根は伐採後もそのままなので、根からの養分で新しい枝と葉を茂らせてくれたようです。砂金掘り大会の時など、夏の暑い時期には程よい木陰を提供してくれていたのですが、そのように復活するにはあと何年かかるのでしょう。

今年の梅雨入りは少し遅れているようです。農作物や自然界ではこの時期にまとまった雨は慈雨として必要なのでしょうけれども、人間界ではやっぱり気持ちの良い晴天がいいですよね。梅雨のこの時期の花といえばアジサイです。わが博物館の敷地内にもいろんな種類のたくさんのアジサイが植えられています。早いものではすでに大輪の花を咲かせています。その花の写真を撮影していると、カナブンのような虫がとまっていました。調べてみるとこれはカナブンではなく、ハナムグリのようです。両者の体の形はよく似ているのですが、決定的な違いは体に白い斑点模様があるのがハナムグリ、全くないのがカナブンだそうです。両者はおなじ仲間なので似ているのですが、ハナムグリには全身にカナブンにない細かい毛が密生しているのがわかります。この個体も白い斑点があり、よく見ると全身が細かい毛で覆われています。

6月8日(土)
夕べ身延町一色のホタルを見に行ってきました。午後7時半ごろ一色ホタルの里駐車場に到着すると、町の観光課の方が車の誘導をしてくださいました。去年も6月の後半に見に来ていますが、時期が遅かったのでわずかしか飛んでいなかったため、今年は最盛期に見たいと思って来た次第です。まだ暗くなったばかりなので駐車場の先客は20台ほど。ホタルの光は駐車場の目の前の川でも数多く飛んでいるのがわかります。駐車場近辺は車が来るたびにヘッドライトの光が邪魔をするので、川沿いの遊歩道を上流に向かって見ることにしました。川沿いの遊歩道だけでなく車道の反対側にも、たくさんのホタルの光の点滅が見られました。川に架かる橋からは二十匹ほどが乱舞しており、手の届くところにいるホタルの光の点滅に親子連れなどから歓声が上がっていました。

ホタルはお尻を発光させて、仲間に自分の居場所を知らせる情報伝達の手段、コミュニケーションの表れであるということです。光りながら飛んでいるホタルはほとんどがオスで、メスにプロポーズしてカップル成立までの一生懸命な自己主張の発光です。それぞれが繁殖相手を上手く見つけられるといいですね。
蛍雪の功には少し光量が足りないとは思いますが、自然の幻想的な光景を堪能することができました。
光る姿は数秒ずつなので、スローシャッターで撮影できればいいのですが、私の技術ではうまく写すこともできません。たくさんのホタルたちの光の競演が皆さんにうまく伝えられなくて残念です。
6月7日(金)
世界文化遺産登録を目指している「佐渡島(さど)の金山」について、ユネスコの諮問機関・国際記念物遺跡会議(イコモス)から、追加情報の提出を求める「情報照会」が勧告されました。同じ金山遺跡を抱える当博物館としては、早期に登録してもらいたいところです。世界遺産登録を考慮するに値する遺産のひとつとして、遺産範囲の修正など追加の情報が求められているという点において、今回登録までに至らなかったのは残念ですが、一歩前進したと好意的に受け止めたいところです。
 世界遺産登録といえば「富士山」の事があります。最初は自然遺産登録を目指したのですが、世界の山々に比べると富士山の形や火山活動がそれほど珍しくないこと、開発が進んでいたためごみやし尿など環境の悪化が進んでいたことなどで国内の検討委員会段階で落選したのです。ならば、目標を文化遺産に変更して2013年に「信仰の対象と芸術の源泉」としての価値が認められ、世界文化遺産に登録されました。富士山は噴火を繰り返す山として畏れられるとともに、高く美しいその荘厳な姿が神聖視され信仰の対象になっていきました。江戸時代には浮世絵などの題材となり、葛飾北斎の「富岳三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」などに描かれただけでなく、ゴッホやモネなどの印象派の画家にも影響を与えています。古代から連綿と続く人々のこうした思いと行いが「信仰の対象と芸術の源泉」と評価され、世界文化遺産に登録されました。着手から登録に至る迄20年の歳月がかかっています。
世界遺産登録といえば「富士山」の事があります。最初は自然遺産登録を目指したのですが、世界の山々に比べると富士山の形や火山活動がそれほど珍しくないこと、開発が進んでいたためごみやし尿など環境の悪化が進んでいたことなどで国内の検討委員会段階で落選したのです。ならば、目標を文化遺産に変更して2013年に「信仰の対象と芸術の源泉」としての価値が認められ、世界文化遺産に登録されました。富士山は噴火を繰り返す山として畏れられるとともに、高く美しいその荘厳な姿が神聖視され信仰の対象になっていきました。江戸時代には浮世絵などの題材となり、葛飾北斎の「富岳三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」などに描かれただけでなく、ゴッホやモネなどの印象派の画家にも影響を与えています。古代から連綿と続く人々のこうした思いと行いが「信仰の対象と芸術の源泉」と評価され、世界文化遺産に登録されました。着手から登録に至る迄20年の歳月がかかっています。
「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録についても着手から13年とすでに長い年月がかかっています。現在は登録まであと少しのところまで来ています。担当されている方々にイコモスが要求する追加情報を、しっかり整えて次回の登録に備えていただきたいと思います。
6月4日(火)
今日は虫歯予防デーです。6月4日の6(ム)4(シ)の語呂合わせで名付けられました。今日から10日までが「歯と口の健康週間」です。
数字にはラッキーナンバーとか聖数といったものがあります。日本では「8」、西洋では「7」がその代表例ですね。
数字の「8」は日本において、漢数字の「八」からイメージされる「末広がり」を連想させ、上(現在)から下(将来・未来)に向かって永久に発展・繁栄するといった意味していると認識されています。また「8」は、古代日本において、日本国を表す「大八州国」や「八百万の神」、「八岐大蛇」、「八雲」など数の多いことを表しています。「8」は我が国において聖数であり、大変呪力のある数字なのです。数字の「8」は横にすると「∞」になり、無限大を表しているというのも偶然でしょうか。
中国では日本以上に幸運な数字として「8」が好まれているそうです。これは8の発音が、富む、発展することを意味する「発」と似ていることによるとされています、2008年の北京オリンピックが8月8日午後8時8分8秒に開会したことは有名な話です。
西洋において「8」は、八本の足を持つタコを「悪魔の化身」と呼んで忌み嫌うなど、むしろ不吉な数字として認識されているようです。
6月1日(土)
今日から6月です。新たな月の初日ですが、うれしい記念日となりました。なんと有料入館者が49万人目を達成しました。静岡県から来られた団体さんのうち、親戚の叔母さんと一緒に来られたかわいらしい中学生でした。
さて、 戦国武田時代の金の利用について、今日は金泥を取り上げたいと思います。
金泥は、金箔を粉状にして膠(にかわ)で溶いたものです。にかわ(膠)は、広辞苑によると「獣類の骨・皮・腱などを水で煮た液を乾かし、固めた物質。ゼラチンを主成分とし、透明または半透明で弾性に富み、主として物を接着させるに用いる。」とあります。実際には、金粉を溶かした膠の原液を、刷毛や筆を使って塗ったり文字を書いたりしたものと思われます。
甲州市恵林寺の木造武田不動尊坐像並びに二童子像は三躯とも当初の截金、金泥を多用した極彩色が残っています。この像は信玄をモデルに造られたとの伝承を持ち、信玄が自ら髪の毛を焼いて像の髪の彩色に用いたとされています。不動明王がまとう条帛の文様には、武田氏の家紋である花菱文や竜の図案化されたものが金泥で描かれています。頭の内部に墨書が発見され元亀三年(1572)、信玄の没する前年に七条仏師の一人康住によって制作されたことがわかりました。金泥は仏像を荘厳化させるため、厨子の内側をすべて金泥で塗ったり、この像のように台座の表面装飾にも用いられています。

武田信玄の軍旗といえば「風林火山」の「孫子」の旗が有名です。同旗は武田神社ほか何旒か残されていますが、甲州市雲峰寺には紺地に金泥で「疾如風徐如林侵掠如火不動如山」と書かれた旗が六旒残されています。この旗は、信玄の師であり菩提寺恵林寺の快川和尚が大書したものと伝えられています。また同寺には赤地に金泥で「南無諏方南宮法性上下大明神」と書かれた諏方神号旗も伝えられており、戦において武神である諏方大明神の加護を受ける祈念が込められていると思われます。
5月26日(日)
湯之奥金山などで得られた武田時代金の消費は、なんといってもそのままを利用した甲州金があげられます。そのほか純金の装飾金具への加工、金箔への加工、銅製品への鍍金(めっき)、仏像等に見られる截金(切金・きりがね)、文字や絵画に見られる金泥(きんでい・こんでい)があげられます。
今日は截金の技法と、その作品のいくつかを見てみましょう。截金とはまず金箔をつくりそれを極細の線に切って、その金箔を貼り模様を施す装飾技法です。金箔は薄すぎると加工が大変なので、腰をもたせた程度の厚さが必要です。今では金箔数枚を焼き合わせて利用するそうです。それを筆端につけて貼りながら種々なる文様を描き出す技法で、仏像や仏画の加飾荘厳として用いられました。 2本の筆で一方に膠(にかわ)と布海苔(ふのり)を混ぜた接着剤 を含ませ、もう片方の取り筆で神経を研ぎ澄ませながら 金箔を置いていく技法です。
 甲府市円光院の山梨県指定文化財となっている「木造厨子入刀八毘沙門天及び勝軍地蔵坐像」は、京都の七條大仏師の康清作とされている像です。寺伝では武田信玄が陣中の守り本尊としていたものを、信玄没後に重臣の馬場信春が遺命により当寺に奉納したとされています。細かい截金によって仏像の鎧(よろい)や条帛(じょうはく)の文様を施しているのがわかります。
甲府市円光院の山梨県指定文化財となっている「木造厨子入刀八毘沙門天及び勝軍地蔵坐像」は、京都の七條大仏師の康清作とされている像です。寺伝では武田信玄が陣中の守り本尊としていたものを、信玄没後に重臣の馬場信春が遺命により当寺に奉納したとされています。細かい截金によって仏像の鎧(よろい)や条帛(じょうはく)の文様を施しているのがわかります。
5月24日(金)
今日は24日です。24という数字から皆さんは何を連想されますか。第1に1日の24時間を思い浮かべるでしょう。また24(にじゅうし)節気とか『二十四(にじゅうし)の瞳』とか想起される方も多いかと思います。山梨県民であれば甲州軍団の武田24将といったところでしょうか。(読みはタケダニジュウヨンショウではなくニジュウシショウというが正解です。おまちがいなく。)
1日を24時間と定めたのは、古代エジプトだと言われています。昼夜をそれぞれ12等分したことに由来するそうです。江戸時代までの日本でも1日をおよそ2時間ずつに分けた十二時辰(じゅうにじしん)が採用されていました。1日の時刻を十二支で表し、さらにそれを30分刻みで4等分したので、草木も眠る丑三つ時(うしみつどき)とは、午前1時から3時まで丑の刻の三つ目の午前2時から2時半までの間を表していました。丑三つは方角に当てはめると丑寅(うしとら)の東北の方位になり、災厄や疫病が来るという鬼門の方角にあたるので幽霊が出やすい時間帯だと信じられていました。
我が博物館で24といえば、純金の24カラットです。金はアルファベットのKを用いた「カラット(karat)」という単位で純度が表示され、24Kが100%の純金になります。18Kは24分の18の割合で金が含まれているということになるので、純度75%の金を含んでいるということになります。
ちなみにダイヤモンドの重さを表す単位の「カラット(carat)」とは、日本語の発音は同じですが異なる単位ですので、混同しないようにご注意ください。
5月19日(日)
博物館の駐車場の周囲やリバーサイドパークは、シルバー人材センターのみなさんによって雑草がきれいに刈り取られています。ほんとに地面すれすれの根元から刈り取られています。その腕前はさすがです。雑草という名の植物はないと牧野富太郎博士は言っておりますが、植栽したもの以外をひとくくりにする言葉として雑草は便利な言葉です。
 畑でも公園でも河原の土手でもこの時期の雑草のひとつに、カラスノエンドウがあります。リバーサイドパークのはずれの川沿いの除草されていないところに、このカラスノエンドウがありました。この辺りではシビビーと呼ぶのが一般的ですが、植物学的にはヤハズマメと言うそうです。シビビーやシービービーというのは、その鞘を使って小学生などが鳴らして出る音から来ています。私も子供の頃畑の土手にある実を見つけては、よく鳴らして遊んだものです。熟すと鞘が黒くなることからカラスノエンドウですが、「カラスの・エンドウ」ではなく「カラス・野豌豆」が正しい名称だということを植物の専門家からお聞きしていたのを思い出しました。ヤハズマメの名前の由来は、葉の形が矢の末端の弓の弦を受ける部分に似ていることからだそうです。いろんな呼び方があり、それぞれの名前の由来があるんですね。
畑でも公園でも河原の土手でもこの時期の雑草のひとつに、カラスノエンドウがあります。リバーサイドパークのはずれの川沿いの除草されていないところに、このカラスノエンドウがありました。この辺りではシビビーと呼ぶのが一般的ですが、植物学的にはヤハズマメと言うそうです。シビビーやシービービーというのは、その鞘を使って小学生などが鳴らして出る音から来ています。私も子供の頃畑の土手にある実を見つけては、よく鳴らして遊んだものです。熟すと鞘が黒くなることからカラスノエンドウですが、「カラスの・エンドウ」ではなく「カラス・野豌豆」が正しい名称だということを植物の専門家からお聞きしていたのを思い出しました。ヤハズマメの名前の由来は、葉の形が矢の末端の弓の弦を受ける部分に似ていることからだそうです。いろんな呼び方があり、それぞれの名前の由来があるんですね。
ちなみにノエンドウには三兄弟があり、実の大きいカラスノエンドウ、実の小さいスズメノエンドウ、その中間のカスマグサです。カスマグサはカラスノエンドウの「カ」とスズメノエンドウの「ス」の間の大きさの草であるということから付けられた名前だそうです。
5月17日(金)
博物館の隣のリバーサイドパークには、ヤヤマボウシの木に花がたくさん咲いています。ヤマボウシ(山法師)は、ミズキ科ミズキ属ヤマボウシ亜属です。名前の由来は真ん中の実になる部分が僧侶(法師)の頭、周りの4枚の花弁のような総苞(そうほう)の部分を白い頭巾に見立てて比叡山延暦寺の僧侶の姿の山法師に似ていることから名付けられたとされています。花びらに見える部分は、総苞と言って葉が変化したもので花ではありません。ヤマボウシでは坊主頭の薄黄緑色の部分が、密集した花にあたります。よく見ると花びらやおしべ、めしべとまだ開かないつぼみが確認できますね。秋にはこの花の部分が赤い実となり、直径2センチほどの甘い果実として結実します。鳥たちのおいしい食料になります。
 さて、街路樹でもよく見かけるハナミズキも同属の花になります。アメリカヤマボウシがハナミズキの別名であるとおりです。4月の後半と花の時期は先行していますが、花の構造は一緒です。一見して花と思っている部分は花ではなく、その中心部分が本当の花なのです。アジサイやどくだみの花もヤマボウシと同じ構造をしています。虫たちを集めるために、ひときわ目立つように変化(進化)したもののようです。
さて、街路樹でもよく見かけるハナミズキも同属の花になります。アメリカヤマボウシがハナミズキの別名であるとおりです。4月の後半と花の時期は先行していますが、花の構造は一緒です。一見して花と思っている部分は花ではなく、その中心部分が本当の花なのです。アジサイやどくだみの花もヤマボウシと同じ構造をしています。虫たちを集めるために、ひときわ目立つように変化(進化)したもののようです。
5月4日(日)
ゴールデンウィーク後半、4連休中日2日目のみどりの日です。大勢の方が来館してくれました。お子さんを連れた家族総出らしき入館者が多く、そのほとんどが砂金採り体験をしてくれています。うちの職員も、その対応にてんてこ舞いです。うれしい悲鳴です。
 菊の苗を植えたことは先日(4/21)書きました。博物館の駐車場の入り口の緑地帯の空閑地や、リバーサイドの柵際に菊苗を全部で150本以上、約1メートル間隔で植えました。しかし、何とこれまでに3回以上菊の苗の頭がシカにかじられていました。最初は虫かなとも思ったのですが、あまりにも被害の苗の数が多くそれに該当する虫は存在しません。地面をよく見ると苗の付近には、シカの足跡がいくつも残されていました。菊の苗の頭をかじられると、菊の株が良い形に仕上がらないというのでその都度植え替えています。苗の数はまだある程度確保してあるので、全部食べられてしまうか、苗が残るかシカとのイタチごっこです。(ん?鹿なのにイタチ)
菊の苗を植えたことは先日(4/21)書きました。博物館の駐車場の入り口の緑地帯の空閑地や、リバーサイドの柵際に菊苗を全部で150本以上、約1メートル間隔で植えました。しかし、何とこれまでに3回以上菊の苗の頭がシカにかじられていました。最初は虫かなとも思ったのですが、あまりにも被害の苗の数が多くそれに該当する虫は存在しません。地面をよく見ると苗の付近には、シカの足跡がいくつも残されていました。菊の苗の頭をかじられると、菊の株が良い形に仕上がらないというのでその都度植え替えています。苗の数はまだある程度確保してあるので、全部食べられてしまうか、苗が残るかシカとのイタチごっこです。(ん?鹿なのにイタチ)
4月28日(日)
江戸時代の刑罰のひとつに「島流し」というのがあります。罪を犯した犯罪者を孤島に送って、社会から隔絶する刑です。佐渡島や伊豆諸島など離島が一般的に知られていますが、古くは畿内地方から見て遠くに隔離するということから、必ずしも離島とは限りませんでした。源頼朝の伊豆や大奥の絵島事件の信州高遠が有名ですが、甲斐も流刑地のひとつでした。鎌倉時代に建長寺を開山した蘭渓道隆、江戸時代の後陽成天皇第八皇子の八宮良純親王も甲斐に流されてきています。島送りされた流罪人は、佐渡金山で強制労働させられていたイメージを持たれる方が多いのですが、実際にはやんごとなき人を中央政界などから遠ざけることが目的の刑罰であるため、流刑地では牢屋に入れられることはなく普通の生活ができたそうです。佐渡金山で働かされたのは、無宿人であって罪人ではありませんでした。
 蘭渓道隆が流された甲府の東光寺 八宮様の配流地のひとつ甲府興因寺
蘭渓道隆が流された甲府の東光寺 八宮様の配流地のひとつ甲府興因寺
江戸時代中期には、甲斐に甲府藩が置かれ柳沢吉保・吉里が藩主となり、吉里は江戸時代を通じて唯一甲府城に在城した大名でした。吉里が大和郡山に転封になると甲斐は幕府の直轄領となり、甲府勤番が置かれました。甲府には新たな役人が必要となり、旗本の次男坊、三男坊や、江戸城内のトラブルメーカーや問題のある役人が甲府勤番士に任命されて来たのです。甲府勤番に一度なると二度と江戸へは戻れなくなると思われており、甲府勤番は明らかに左遷人事でした。そのため江戸城の武士は、この勤番になることを非常に恐れたのです。選ばれた者は絶望のあまり「甲府へ山流しになる」と、自虐的に自分たちをこう言いました。こうして甲府勤番を「山流し」と呼ぶようになったのです。ところが後にはこれを、気を使う江戸城勤めよりよっぽど気楽でいいと、希望する者も出てきたといいます。こういった武士たちによって、甲府に江戸文化がドッと流れ込んできたのでした。
4月26日(金)
ハートマークのあるカメムシを発見。博物館駐車場に背中にハートマークが付いたカメムシを見つけました。これまで何回も目にはしていたのですが、やっと写真に撮ることができました。本当は樹上から糸で下に降りようとしていたきれいな色のイモ虫を観察していた時、アスファルト上にたまたま歩いていたのを撮影したものです。その名はエサキモンキツキノカメムシ、肩パットをしているようないかつい容貌ながら、その色合いは美しいではありませんか。カメムシの類は、そのいやなにおいを発すること、農作物を食い荒らすことで嫌われ者です。しかし、このエサキモンキツキノカメムシは、特徴的なハートマークといいその体の色合いといいカワイイ感じがしますね。

名前の由来は、「エサキ」が昆虫学者 江崎悌三氏の名前、「モンキ」は「紋黄」で成虫の背中の紋が黄色であることから名づけられたそうです。ハートマークといえば、石造物や寺社の建造物の妻飾りにある「猪の目」文様を思い出しますね。
4月21日(日)
去年の秋、博物館入口に菊の花の鉢を飾りました。1本20センチほどの苗から、径が1メートルになるほど枝が分岐した大きな株に成長したものです。畑の隣の河原の土手に植えたものを譲っていただいて、鉢上げにして飾ったものです。これらの黄金色の菊は、大きな株のため特大の植木鉢にしか入りませんでした。
 暖かくなって去年の鉢上げした株から新芽が成長し、1株からわんさかと30本以上の枝が出ています。これを1本ずつほぐして、苗としました。博物館の駐車場に隣接する下部リバーサイドパークの土手と、黄金の足湯の裏に1列に植えてみました。100本以上植えたので、全部が同じように成長したならばそれこそ見事な素晴らしい景観になることと思います。(博物館の環境美化運動の一環です。ほんとけ?)博物館に来られる皆さんにも、新しい見どころの一つになるように、しっかり水遣りや手入れをして、株が大きくなる秋を楽しみにして下さいね。
暖かくなって去年の鉢上げした株から新芽が成長し、1株からわんさかと30本以上の枝が出ています。これを1本ずつほぐして、苗としました。博物館の駐車場に隣接する下部リバーサイドパークの土手と、黄金の足湯の裏に1列に植えてみました。100本以上植えたので、全部が同じように成長したならばそれこそ見事な素晴らしい景観になることと思います。(博物館の環境美化運動の一環です。ほんとけ?)博物館に来られる皆さんにも、新しい見どころの一つになるように、しっかり水遣りや手入れをして、株が大きくなる秋を楽しみにして下さいね。
4月12日(金)
今日は「武田信玄」の命日です。歴史を勉強している私にとって、歴史上の人物には一般的に尊称はつけませんが、本当のところは「信玄」と呼び捨てにすることには少し抵抗があります。幼いころから「信玄さん」、「信玄公」と、周囲の身近な大人たちがそう呼んでいたので、「信玄さん」というのが当たり前で自然な呼び方でした。今での若い人にとっては少し違和感があるかもしれませんが、ある一定以上の年齢の山梨県人にとって「武田信玄」は、それほど特別な存在なのです。
さて、元亀4(1573)年4月12日、西上作戦の途次であった信玄は病気が悪化し、甲府に帰る途中信州駒場で53歳の生涯を閉じました。死因は胃癌や肺結核、その他の原因だったともいわれています。信玄は死に臨んで子の勝頼や信頼できる家臣を枕元に呼び寄せ、死後三年間は死を秘密にすること、後継者は孫の信勝を指名し彼が成長するまでは勝頼が陣代として統率すること、遺体は甲冑を着けて諏訪湖に沈めること、影武者に弟の逍遥軒を立てることなどを遺言しました。この結果、信玄の逝去地や墓など複数の候補地が知られるようになったといわれています。特に墓については、私が調べた限り22か所の該当箇所があり、逝去地、埋葬地、火葬地、分骨地、後世の仮託された伝承地や供養墓など信玄治世下のカリスマ性が見て取れます。信玄の死と墓については、さまざまな謎でいっぱいです。
 身延町内でも慈観寺、満福寺で新たに信玄の墓が発見されました。富士河口湖町本栖の七社大明神、南部町十島の葛谷城跡など、これまであまり注目されてこなかった山梨県峡南地域方面にも、信玄の供養塔が複数存在していることが再確認されました。死後100年以上がたっても、それぞれの村で墓碑を建立し追善供養しているところを見ると、死してもなお武田信玄のその影響力は相当なものだったことが伺えます。
身延町内でも慈観寺、満福寺で新たに信玄の墓が発見されました。富士河口湖町本栖の七社大明神、南部町十島の葛谷城跡など、これまであまり注目されてこなかった山梨県峡南地域方面にも、信玄の供養塔が複数存在していることが再確認されました。死後100年以上がたっても、それぞれの村で墓碑を建立し追善供養しているところを見ると、死してもなお武田信玄のその影響力は相当なものだったことが伺えます。
4月5日(日)
今年は桜の開花が遅かったのですが、博物館の駐車場周辺の桜も強風による花吹雪と雨によって、花は散ってしまってほとんど残っていません。山梨県は桜の名所が多いところです。身延山のシダレザクラのほか、日本三大桜のひとつ北杜市の山高神代桜は樹齢2000年といわれ、なんと弥生時代から咲いていることになります。韮崎市のわに塚の桜とともに数日前に満開を迎えたようです。  昨日、乙ヶ妻のシダレザクラと徳和の新羅桜を見に行ってきました。乙ヶ妻の桜はほぼ満開で丘の上に咲く一本桜はさすがに見事でした。県外からの見物客も多かったです。徳和吉祥寺の新羅桜は、昭和28年に倒木した先から天に向かって枝を伸ばし、現在の樹形を保っています。落雷により一部空洞となっており、内部の焼痕が痛々しいのですが、その生命力には驚かされます。
昨日、乙ヶ妻のシダレザクラと徳和の新羅桜を見に行ってきました。乙ヶ妻の桜はほぼ満開で丘の上に咲く一本桜はさすがに見事でした。県外からの見物客も多かったです。徳和吉祥寺の新羅桜は、昭和28年に倒木した先から天に向かって枝を伸ばし、現在の樹形を保っています。落雷により一部空洞となっており、内部の焼痕が痛々しいのですが、その生命力には驚かされます。
 桜を日本人が今のように愛でるようになったのは、平安時代からです。奈良時代の万葉集では花といえば梅の花のことで、やがて桜がとってかわってその主役に躍り出ます。桜の花は日本全国にいたる所に存在しています。天然の山桜のほか、園芸種もたくさんあります。桜前線によって春の訪れを日本中に告げます。木全体が一度にすべて花で覆いつくされるその華やかさと、わずかな期間しか咲きほこらず花吹雪として散って風に舞う姿は、そのはかなさについても魅力のひとつです。桜は日本人にとって特別な存在であり、日本の花の代表ですよね。この季節の桜花、花の景色と可能ならばそれを愛でての宴を十分に楽しんでみましょう。
桜を日本人が今のように愛でるようになったのは、平安時代からです。奈良時代の万葉集では花といえば梅の花のことで、やがて桜がとってかわってその主役に躍り出ます。桜の花は日本全国にいたる所に存在しています。天然の山桜のほか、園芸種もたくさんあります。桜前線によって春の訪れを日本中に告げます。木全体が一度にすべて花で覆いつくされるその華やかさと、わずかな期間しか咲きほこらず花吹雪として散って風に舞う姿は、そのはかなさについても魅力のひとつです。桜は日本人にとって特別な存在であり、日本の花の代表ですよね。この季節の桜花、花の景色と可能ならばそれを愛でての宴を十分に楽しんでみましょう。
3月31日(日)
今日をもって令和5年度の最終日となってしまいました。あっという間に一年間が過ぎ去ってしまいました。何度も同じことを繰り返すようですが、日々の時間の経過が最近早まっているようにつくづく感じます。日々の出来事に対して感動しなくなっていて、毎日のくらしに慣らされている証拠なのかもしれません。前にここに書いた「ジャネーの法則」(10/3.6)を痛感しています。
 昨日、今日と、とても暖かいです。車の中では暑いくらいになっています。昨日の最高気温は隣町の南部町で日本最高の27.8℃を記録しました。今日もぐんぐん気温が上昇しており、徐々に暑くなってきています。最高気温は身延町で27℃になる予報です。
昨日、今日と、とても暖かいです。車の中では暑いくらいになっています。昨日の最高気温は隣町の南部町で日本最高の27.8℃を記録しました。今日もぐんぐん気温が上昇しており、徐々に暑くなってきています。最高気温は身延町で27℃になる予報です。
 この暑さによって花も一斉に咲きはじめ、ヤマブキ、アオキ、オオイヌノフグリ、レンギョウ、タチツボスミレ、イヌナズナ、ニホンタンポポ、チューリップのほか沈丁花はもう終盤です。この沈丁花にはクジャクチョウが蜜を吸いにきて止まっており、アリや二ホントカゲも活発に活動をしています。
この暑さによって花も一斉に咲きはじめ、ヤマブキ、アオキ、オオイヌノフグリ、レンギョウ、タチツボスミレ、イヌナズナ、ニホンタンポポ、チューリップのほか沈丁花はもう終盤です。この沈丁花にはクジャクチョウが蜜を吸いにきて止まっており、アリや二ホントカゲも活発に活動をしています。
3月29日(金)
 昨日から今日の午前中までかなり強い雨でした。博物館駐車場の山側の沢からも、普段はちょろちょろとわずかにしか流れていない水が滝のようになっていました。下部川も水量が多く、濁流となって轟音をたてています。金山周辺から新たな砂金粒が、本流に供給されたのではないでしょうか。
昨日から今日の午前中までかなり強い雨でした。博物館駐車場の山側の沢からも、普段はちょろちょろとわずかにしか流れていない水が滝のようになっていました。下部川も水量が多く、濁流となって轟音をたてています。金山周辺から新たな砂金粒が、本流に供給されたのではないでしょうか。
 お昼前から天気は回復し、太陽が顔を出してきました。外はあったかい春の陽気です。館内は相変わらず冷え冷えとしていますが、忙しく動き回っている職員は汗をかいています。桜の開花は甲府気象台の標本木において、東京と同じく本日発表となる予定です。湯之奥金山博物館に隣接する下部リバーサイドパークでは、ほぼ咲き終わった河津桜が葉桜となって、ソメイヨシノは2~3分咲きといったところでしょうか。柳の木は緑色の葉が伸び始めています。さあいよいよ春です。いろいろなことが新しくなる年度初めももうすぐです。
お昼前から天気は回復し、太陽が顔を出してきました。外はあったかい春の陽気です。館内は相変わらず冷え冷えとしていますが、忙しく動き回っている職員は汗をかいています。桜の開花は甲府気象台の標本木において、東京と同じく本日発表となる予定です。湯之奥金山博物館に隣接する下部リバーサイドパークでは、ほぼ咲き終わった河津桜が葉桜となって、ソメイヨシノは2~3分咲きといったところでしょうか。柳の木は緑色の葉が伸び始めています。さあいよいよ春です。いろいろなことが新しくなる年度初めももうすぐです。
3月23日(土)
今日は朝開館前から雪がふってきました。山梨土研究会主催のシリーズ現地で学ぶ「下部温泉と湯之奥金山の歴史」の実施が危ぶまれましたが、雪はやがて冷たい雨にかわってなんとか開催することができました。身延町教育委員会とともに甲斐黄金村・湯之奥金山博物館にも協力依頼があり、下部温泉、周辺史跡、金山博物館を学芸員と一緒に案内しました。
 最初に下部温泉郷内をバスで通過しながら案内し、金山の入口まで行った後に門西家住宅へ行って建物を見学しました。門西家はもと佐野氏を名乗っており、湯之奥村の名主や関守を務めた名家です。江戸時代中期に建てられたこの建物は、富士川谷特有の民家形式である入母屋造りであり、国指定重要文化財となっています。規模が大きく梁組が整然とし木割の太いことが特徴の建物で、昭和44年の解体修理の際には屋根裏から金山で使用されたセリ板や木槽も発見されています。次に慈照院前の駐車場に移動し、ここから熊野権現神社に行って下部温泉の開湯の伝説を聞き、町指定の文化財となっている本殿を見学しました。神社では下部温泉のかつて賑わっていた当時の写真を見ながら、昭和の懐かしい時代の解説をしました。
最初に下部温泉郷内をバスで通過しながら案内し、金山の入口まで行った後に門西家住宅へ行って建物を見学しました。門西家はもと佐野氏を名乗っており、湯之奥村の名主や関守を務めた名家です。江戸時代中期に建てられたこの建物は、富士川谷特有の民家形式である入母屋造りであり、国指定重要文化財となっています。規模が大きく梁組が整然とし木割の太いことが特徴の建物で、昭和44年の解体修理の際には屋根裏から金山で使用されたセリ板や木槽も発見されています。次に慈照院前の駐車場に移動し、ここから熊野権現神社に行って下部温泉の開湯の伝説を聞き、町指定の文化財となっている本殿を見学しました。神社では下部温泉のかつて賑わっていた当時の写真を見ながら、昭和の懐かしい時代の解説をしました。
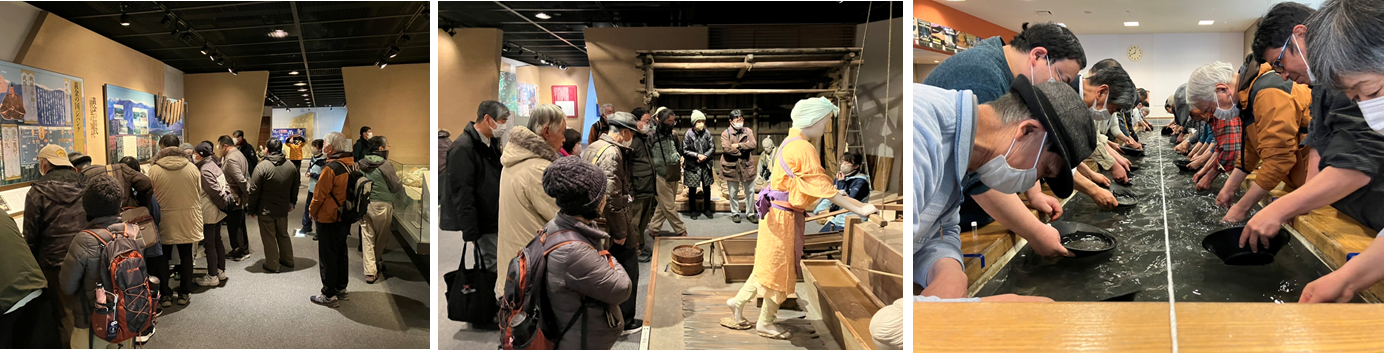 博物館では中山金山のジオラマの説明や展示品の解説をし、日本における初期の山金の採掘⇒粉成⇒汰り分け⇒吹き溶かしの工程を確認しました。最後に参加者に砂金採り体験をパンニング皿ではあるけれども、当時の採取の方法で砂金を探してもらいました。砂金粒ではあるけれども、黄金の魅力は絶大です。比較的若い方も年配者の方も、一生懸命水中の砂と格闘をしていたのが印象的でした。
博物館では中山金山のジオラマの説明や展示品の解説をし、日本における初期の山金の採掘⇒粉成⇒汰り分け⇒吹き溶かしの工程を確認しました。最後に参加者に砂金採り体験をパンニング皿ではあるけれども、当時の採取の方法で砂金を探してもらいました。砂金粒ではあるけれども、黄金の魅力は絶大です。比較的若い方も年配者の方も、一生懸命水中の砂と格闘をしていたのが印象的でした。
3月19日(火)
17日のシン・サンポの第2弾です。十五所神社は、15柱というたくさんの神様をお祀りしています。社名もこの祭神の数からきています。いつから鎮座しているのかは定かではありませんが、様々な神様を合同でお祀りすることによって、この地区の人々のどんな願いに対してもいずれかの神様がそれぞれかなえてくれそうなありがたいお宮でした。拝殿には絵馬や俳句の額がたくさん奉納されており、地域の人々にいかに親しまれているかが分かります。
 この境内には数種の道祖神があり、ご本殿の脇の玉(瑞)垣の中に5基が並んでいます。縄文時代から続く石棒型3基が中央にあり、右側に石祠形1基、左側に双体道祖神1基です。また、瑞垣の左側には石祠があり、きれいなハート形の穴があります。これは猪目(いのめ)といって日本古来からある文様です。当社ご本殿は一間社流造ですが、妻飾りに見られる懸魚(げぎょ)はハート形の透かしのある猪目懸魚になっています。
この境内には数種の道祖神があり、ご本殿の脇の玉(瑞)垣の中に5基が並んでいます。縄文時代から続く石棒型3基が中央にあり、右側に石祠形1基、左側に双体道祖神1基です。また、瑞垣の左側には石祠があり、きれいなハート形の穴があります。これは猪目(いのめ)といって日本古来からある文様です。当社ご本殿は一間社流造ですが、妻飾りに見られる懸魚(げぎょ)はハート形の透かしのある猪目懸魚になっています。

3月17日(日)
第2回シン・サンポを久那土地域で行いました。春のうららかな陽気の中、久那土駅に十六名が参加。久那土地区の史跡を訪ねました。久那土駅⇒随応寺⇒十五所神社⇒道祖神⇒馬頭観音⇒大草道祖神場⇒美枝きもの資料館⇒久那土駅のコースでめぐりました。
「久那土(くなど)」は「道祖神」の異称です。疫病・災害など災厄をもたらす悪神・悪霊が、集落に入るのを防ぐとされる神です。また、「久那土」はくなぐ、即ち交合・婚姻を意味するものという説もあります。「賽の神」「道陸神」「衢神」などの別称があり、多くの神々が習合されている複雑な神様です。村の入り口や集落内の辻に祀られることが多く、この地域では集落内の各組ごとにそれぞれ祀られています。
 地元からの参加者からは、甲斐源氏三沢氏の由来や三沢の地名由来となった三つの沢を説明していただきました。十五所神社では、宮司さんのご配慮で神社の由緒のお話だけでなく、拝殿内の天井絵や絵馬を特別に見せていただいたりしました。
地元からの参加者からは、甲斐源氏三沢氏の由来や三沢の地名由来となった三つの沢を説明していただきました。十五所神社では、宮司さんのご配慮で神社の由緒のお話だけでなく、拝殿内の天井絵や絵馬を特別に見せていただいたりしました。
最後に美枝きもの資料館に寄りました。冬季は休館であるので、まだ今年は開館したばかりとのことでした。上田美枝氏が収集した江戸時代から昭和までの特徴的な着物を中心に、皇室関係や島嶼部の着物のほか、芸術的な調度品も展示されてありました。同じ町内に住んでいながら初めて来館したという参加者も多く、貴重な収蔵品の数々に驚きの様子でした。また、全員におみやげもいただきました。
 やはり今回のシン・サンポで一番特徴的なのは各地区にあった道祖神です。文字碑のほかに丸彫りの双体道祖神や石棒形道祖神、丸石道祖神などいろんなバリエーションが見られました。当地域には道祖神像の優品が多く、他の地区にない道祖神信仰の深さをしみじみと感じました。
やはり今回のシン・サンポで一番特徴的なのは各地区にあった道祖神です。文字碑のほかに丸彫りの双体道祖神や石棒形道祖神、丸石道祖神などいろんなバリエーションが見られました。当地域には道祖神像の優品が多く、他の地区にない道祖神信仰の深さをしみじみと感じました。
本日の参加者されました皆さんお疲れさまでした。そして、本日立ち寄らせていただいた、十五所神社の関係者、美枝きもの資料館のスタッフの方に御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
3月14日(木)
湯之奥金山博物館は下部温泉郷内にあります。下部温泉は歴史が古く、『甲斐国志』に「熊野権現(下部村) 社記ニ承和三丙辰(836)年、熊野ノ神此ノ処ニ出現シ給ヒ温泉湧出ス故ニ温泉宮ト別号シ奉ル。修理大夫姓名欠ク造営ス。天正二(1574)年甲戌年穴山信君亦建立シテ神領一貫三百文寄附シ禁牓ヲ掲グ。天正壬午ノ乱後神祖此ノ温泉ニ御入浴アリテ制札等下シ賜ハルト云フ神主依田近江。」とあります。下部町誌には「・・・甲斐国主藤原貞雄二男修理太夫正信疥癬を病み川合の郷知温辺の湯をお訪ねになり入浴してたちまち全治す。その夜丑の上刻頃枕元に神霊が現れ「我は熊野権現なり。汝温泉より未申の方へ湯の保護神として我を祀るべし」と。霊夢覚めて驚き入りこれによって熊野三社大権現を祀り神殿並びに拝殿を建立す。・・・」とあり、平安時代には温泉が湧出して湯治が行われていたことが伝えられています。確実な史料としては建治4年(1278)日蓮書状に「しもへのゆのついてと申者を、あまたをひかへして候」とあります。
 日本全体を見渡しても、確実に江戸時代にまでさかのぼりうる温泉はきわめて数が限られており、現在の温泉のほとんどが近代以降の開削によるものだそうです。温泉の研究者の間では、①確実な史料が残されていること、②現在でも源泉が湧出していること、③湯権現が祀られていること、④温泉関連の遺構が残されていることなどがそろわないと開湯伝説の実証は難しく、実際そう古くは遡れないものが多いと言われています。そういった点からすると下部温泉は、確実に鎌倉時代までは遡ることができ、湯治場が早くから広く一般に知られていた温泉地ということができます。
日本全体を見渡しても、確実に江戸時代にまでさかのぼりうる温泉はきわめて数が限られており、現在の温泉のほとんどが近代以降の開削によるものだそうです。温泉の研究者の間では、①確実な史料が残されていること、②現在でも源泉が湧出していること、③湯権現が祀られていること、④温泉関連の遺構が残されていることなどがそろわないと開湯伝説の実証は難しく、実際そう古くは遡れないものが多いと言われています。そういった点からすると下部温泉は、確実に鎌倉時代までは遡ることができ、湯治場が早くから広く一般に知られていた温泉地ということができます。
この熊野権現神社本殿は、天正二年(1574)に造られたことが棟札からわかり、三間社流造、向拝を持つ桧皮葺の社殿です。拝殿を兼ねた覆屋に覆われてはいますが、傷みが激しく落書きも目立っています。
3月4日(月)
山梨市牧丘町倉科の大滝山上求寺は、奥の院を大滝不動尊、甲州子の不動と言われており、武田信玄公からも厚い信仰を受けていました。2月28日にこの大滝不動尊の祭礼護摩法要が営まれました。祭主は身延町八日市場の大聖寺ご住職。ご本尊の不動明王前に方形に組まれた護摩壇が用意され、灯明より火が点けられた後、5人の僧侶によってお経が唱和されました。火力が強まるとお堂内の信者が、それぞれの願い事の書かれた護摩木を順次火中に投じて合掌。今年は暖冬というけれど雪中のお堂内は寒く、護摩の火が暖かく感じられました。諸願成就、世界平和も祈願しました。
 「さそわずば くやしからまじ桜花 さねこん頃は 雪の降る寺」と詠んだ信玄の歌は、この大滝不動尊を参拝の折に恵林寺の千代桜を詠ったものだそうです。(「上求寺説明板」)
「さそわずば くやしからまじ桜花 さねこん頃は 雪の降る寺」と詠んだ信玄の歌は、この大滝不動尊を参拝の折に恵林寺の千代桜を詠ったものだそうです。(「上求寺説明板」)
2月29日(木)
26日に下山地区のEさんとHさんに案内していただき、下山の大沢石切り場跡に行ってきました。この石切り場の道路脇の巨石には、石を割るためにあけた矢(クサビ)穴の跡が今も直線状に残されています。矢穴を使って石を割る技術は安土桃山時代にはじまって、明治時代以降にも行われました。矢穴の大きさで時代の推定をすることが可能で、この場所でみられる矢穴は3寸(9センチ)ほどであり、江戸時代中期の採石稼業と考えられます。伝承では富士山宝永火山の噴火の際に、身延山菩提梯(山門先の石段)が崩れた時に利用されたと言われていますので、年代的には合致します。
 大沢川の石切り場より少し上流に法光山妙見寺があり、こちらも案内していただきました。戦国時代の草創で火災により小堂のみだったものを、地元有志の助力で現在の境内に整えられました。池や庭園も整備され、かつてはアジサイの名所だったとのことで、山畔にはその名残が残っています。本堂前の池には鯉が悠然と泳ぎ、下の池では驚くほどの数のヒキガエルが群集して繁殖行動における先陣争いの真っ最中でした。冬眠から覚めて活発に活動するヒキガエルに、春の到来を真近に感じることができました。
大沢川の石切り場より少し上流に法光山妙見寺があり、こちらも案内していただきました。戦国時代の草創で火災により小堂のみだったものを、地元有志の助力で現在の境内に整えられました。池や庭園も整備され、かつてはアジサイの名所だったとのことで、山畔にはその名残が残っています。本堂前の池には鯉が悠然と泳ぎ、下の池では驚くほどの数のヒキガエルが群集して繁殖行動における先陣争いの真っ最中でした。冬眠から覚めて活発に活動するヒキガエルに、春の到来を真近に感じることができました。

2月26日(月)
昨日からロビーで「甲斐の山々」の写真展が始まりました。第2回館長講座で峡南地域を中心とした「甲斐の信仰の山々」と題して、撮りためた写真をもとにそれぞれの山にまつわる山岳信仰のお話をさせて頂きました。その時使用した写真を中心に、それぞれの山頂やそこから見える周囲の山々のきれいな風景写真を展示しています。
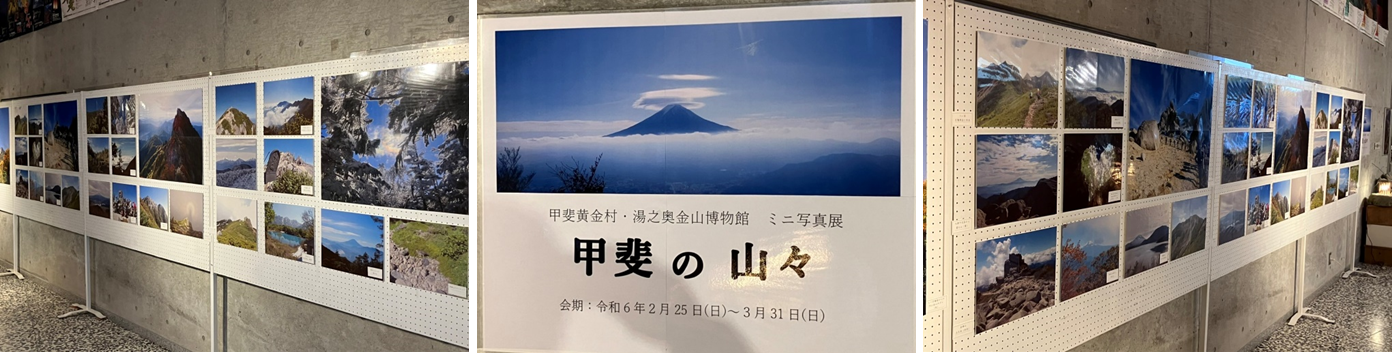 山行に何回も行っていると、「ブロッケン現象」にも何回か遭遇しました。これは山頂や稜線上において、日の出や日没前など太陽の位置が低い時に背後から太陽光が差し込み、霧や雲に自分の姿とその周りを囲んで虹の輪が投影される光学現象です。日本では、阿弥陀様が光背(光輪)を背負って出現したものとして有り難く信仰されていました。「御来迎」、「仏の後光」とも呼ばれています。展示しているのは白根三山縦走中に中白根山で早朝に観測したもので、この日は帰りの日没時にも同様に観察することができて、1日に2回も遭遇できて非常にラッキーでした。この名前の由来はドイツのブロッケン山で頻繁に観測されて報告されたことから、「ブロッケンの(妖)怪」、「ブロッケンの怪物」とも言われて、西洋では不吉なものとされていたようです。
山行に何回も行っていると、「ブロッケン現象」にも何回か遭遇しました。これは山頂や稜線上において、日の出や日没前など太陽の位置が低い時に背後から太陽光が差し込み、霧や雲に自分の姿とその周りを囲んで虹の輪が投影される光学現象です。日本では、阿弥陀様が光背(光輪)を背負って出現したものとして有り難く信仰されていました。「御来迎」、「仏の後光」とも呼ばれています。展示しているのは白根三山縦走中に中白根山で早朝に観測したもので、この日は帰りの日没時にも同様に観察することができて、1日に2回も遭遇できて非常にラッキーでした。この名前の由来はドイツのブロッケン山で頻繁に観測されて報告されたことから、「ブロッケンの(妖)怪」、「ブロッケンの怪物」とも言われて、西洋では不吉なものとされていたようです。
2月25日(日)
連休3日目、朝出勤時の家を出るときは雨だったのが霙に変わり、博物館到着時には雪になっていました。今日午後から第3回目の館長講座「山梨県の考古学-峡南地域を中心として-」の日なのですが、あいにくこの雪のため参加者はまばらでした。
 雪も講座が終わる頃には雨に変わって駐車場には積雪はなく、少し標高の高いところが雪で白くなっていました。リバーサイドパークに植えてある河津桜も可憐なピンク色の花が咲き始めており、対岸の醍醐山方面の雪景色と見事なコントラストを示してくれています。
雪も講座が終わる頃には雨に変わって駐車場には積雪はなく、少し標高の高いところが雪で白くなっていました。リバーサイドパークに植えてある河津桜も可憐なピンク色の花が咲き始めており、対岸の醍醐山方面の雪景色と見事なコントラストを示してくれています。
2月19日(月)
17日に久間先生のもの作り教室が開催されました。江戸時代に石見銀山などの坑道内で使われていたサザエの貝殻を使った「螺灯(らとう)」作りです。実際にはサザエの殻に油を入れて火を灯した道具ですが、LEDを使った灯りです。参加者はハンダゴテを使って器用につくりあげ、暗い映像室の中でいろいろな色に輝く出来栄えを確認しあいました。
 サザエは漢字で「栄螺」と表記し、螺旋状の貝殻がその由来となっています。「螺」とは巻貝の殻のことを言うそうです。サザエといえば国民的漫画の「サザエさん」が連想されます。昨日、早朝のテレビで再放送していたのを久しぶりに見ました。かなりの長寿番組なので、何人もの配役の声や時代設定などが変わっているのに気づきました。過去の番組内容との比較をすると、いつまでも長く変わってほしくないという思いと、時代とともに変わるのはしょうがないという思いが複雑に交錯します。
サザエは漢字で「栄螺」と表記し、螺旋状の貝殻がその由来となっています。「螺」とは巻貝の殻のことを言うそうです。サザエといえば国民的漫画の「サザエさん」が連想されます。昨日、早朝のテレビで再放送していたのを久しぶりに見ました。かなりの長寿番組なので、何人もの配役の声や時代設定などが変わっているのに気づきました。過去の番組内容との比較をすると、いつまでも長く変わってほしくないという思いと、時代とともに変わるのはしょうがないという思いが複雑に交錯します。
2月11日(日)
節分、立春、旧正月、春節と今月に入ってから暦のうえでも春の気配が感じられます。3日は節分でした。節分とは文字通り季節を分ける日のことで、もとは四季に合わせて4つあったのですが、今は春の立春の前日のみが一般に知れられています。邪気を払う行事等が行われ、身延山久遠寺でも節分の豆まき(節分会)が盛大に行われました。各家庭では「鬼は外、福は内」の掛け声ですが、久遠寺では鬼子母神を日蓮宗の守護神としているため「福は内」のみで、「鬼は外」の掛け声はありません。
 2月10日は中国で春節(旧暦の正月)が始まりました。2月17日まで8日間の連休となるようです。この長期休暇を利用して日本に旅行で来られる人も多いようですが、コロナでの規制が緩和されたにも関わらず、コロナ前の爆買いツアーや大挙して特定の観光地に押し寄せる姿は鳴りを潜めているようです。中国本土の景気低迷の影響でしょうか。日本でも明治6年(1873)まではこの旧暦で正月を祝っていました。現在の日本の暦は太陽の動きをもとにして作られた「太陽暦(新暦)」を採用しているのですが、以前の暦は月の満ち欠けをもとに太陽の動きを加えた「太陰太陽暦(旧暦)」を使用していました。
2月10日は中国で春節(旧暦の正月)が始まりました。2月17日まで8日間の連休となるようです。この長期休暇を利用して日本に旅行で来られる人も多いようですが、コロナでの規制が緩和されたにも関わらず、コロナ前の爆買いツアーや大挙して特定の観光地に押し寄せる姿は鳴りを潜めているようです。中国本土の景気低迷の影響でしょうか。日本でも明治6年(1873)まではこの旧暦で正月を祝っていました。現在の日本の暦は太陽の動きをもとにして作られた「太陽暦(新暦)」を採用しているのですが、以前の暦は月の満ち欠けをもとに太陽の動きを加えた「太陰太陽暦(旧暦)」を使用していました。

5日に雪が降った後は比較的暖かい日が続いたので、山際のアオキには新芽が膨らんでおり、その近くの低木(名前不詳)の葉も緑色になり始めました。その低木はよく見ると1輪の白い花が咲いています。季節は着実に進んでいます。春はすぐそこに・・・。
2月10日(土)
三連休の初日です。5日に降った雪も駐車場ではほとんどなくなりましたが、日陰の所はまだまだ真っ白です。日照時間がほとんど0だった1月とは異なり、日も高くなってきたため昼間のわずかな時間帯ではありますが、駐車場にもお日様の光が差し込んできてくれています。雪解けもこのところ急速に進んでいます。暦の上では立春を過ぎて春です。早く本格的なあったかい春にならないかなぁ。
 駐車場に至る通路の山際にある博物館の文字看板を、業者の方がクリーニングしてくれました。色褪せた古びた看板だなぁと思っていたのですが、洗浄しただけで当初の姿があらわれました。聞けば開館当初から、旧施設の看板の文字を書き換えたものだとのこと。古いものには経年変化の味がそれなりにあるけれど、ぼやけたものより鮮明なもののほうがシャキッとしていいなぁ。これから文字も塗り替えられる予定です。
駐車場に至る通路の山際にある博物館の文字看板を、業者の方がクリーニングしてくれました。色褪せた古びた看板だなぁと思っていたのですが、洗浄しただけで当初の姿があらわれました。聞けば開館当初から、旧施設の看板の文字を書き換えたものだとのこと。古いものには経年変化の味がそれなりにあるけれど、ぼやけたものより鮮明なもののほうがシャキッとしていいなぁ。これから文字も塗り替えられる予定です。
2月1日(木)
12月、1月と2か月間にわたって空調設備工事で休館中だった本館も、本日から再開いたしました。平日なので一般客は大人ばかりだったのですが、館内の観覧と砂金採り体験をしていただきました。久々の開館なので、運営委員さんやAU友の会の方も様子を見に来てくれました。ありがとうございました。
職員一同張り切っております。皆様のお越しをお待ちしております。
1月25(木)
峡南地区(南巨摩郡中心)の中世城館跡マップ作製を、山梨県埋蔵文化財センターで進めています。22日に埋文センターの早川町担当者と当館学芸員とともに、地元早川町硯匠館の天野館長の案内で奥沢金山の場所に行ってきました。雨畑湖の湖底では大型の重機が行き来しており、周囲の山々から流入して堆積した砂利を積みなおしていました。
雨畑の老平からゲートを開けてもらい、笊ヶ岳の登山道となっている林道を天野さんの先導に続いて慎重に車を走らせました。林道の奥沢谷は切り立った崖になっており、狭いうえに林道上に落石や枯枝が時々行く手を阻むので、これらを除去してもらいながらゆっくりと進みました。この道は私も10年ほど前に笊ヶ岳へ登山した時に歩いた道なのですが当時の記憶は曖昧でほとんど忘れており、最後に説明を受けた廃屋となっている民家のところの記憶がわずかにあるだけでした。
 かつて金山のあった坑道付近は、河川の氾濫によって流入した土石にすっかり覆われており、流量も多いことから近づくことができません。しかし、左岸にある坑道は現在でも残っている可能性があると、天野さんから説明がありました。日をあらためて天気の安定している時期にまた来てみたいと思いました。
かつて金山のあった坑道付近は、河川の氾濫によって流入した土石にすっかり覆われており、流量も多いことから近づくことができません。しかし、左岸にある坑道は現在でも残っている可能性があると、天野さんから説明がありました。日をあらためて天気の安定している時期にまた来てみたいと思いました。
過去の歴史の痕跡は、時代とともに徐々に失われていってしまうものです。早川諸金山だけでなく甲斐や全国の諸金山のそれぞれの現在の状況と、かつて操業していた当時からの変遷を正しくしっかり記録しておく必要性を再確認した今回の現地調査でありました。
1月16日(火)
14日は、小正月の道祖神祭りの伝統行事が各地区で行われました。道祖神場や集落の広場などには、お山(お柳)と呼ばれる竹を細く割って色紙を巻き付けた柳の枝のように装飾された柱が立てられ、お小屋(お庁屋)と呼ばれる一時的に神様の宿るための小屋が杉の葉などで作られました。
 現在でも大草集落において、丸石道祖神のある道祖神場四隅に竹を立てて紙垂(しで)を付けた縄を張り、広場にお小屋が設けられ片隅にお山が立てられていました。一般的にお小屋は、14日晩のドンド焼きにおいて正月飾りの松飾りや注連の類と一緒に焼かれます。米粉を練って繭玉や球の形をした団子をつくり、これをドンド焼きの火であぶって家に持ち帰り、家族がこれを食べると風邪をひかず虫歯にならないとされています。また、縄に貼られた書初めが空高く舞い上がれば書道が上達するという風習があります。他の地区でもこれらの施設の一部が設けられていたり、道祖神周囲の注連縄や紙垂、御幣などが新調されていました。
現在でも大草集落において、丸石道祖神のある道祖神場四隅に竹を立てて紙垂(しで)を付けた縄を張り、広場にお小屋が設けられ片隅にお山が立てられていました。一般的にお小屋は、14日晩のドンド焼きにおいて正月飾りの松飾りや注連の類と一緒に焼かれます。米粉を練って繭玉や球の形をした団子をつくり、これをドンド焼きの火であぶって家に持ち帰り、家族がこれを食べると風邪をひかず虫歯にならないとされています。また、縄に貼られた書初めが空高く舞い上がれば書道が上達するという風習があります。他の地区でもこれらの施設の一部が設けられていたり、道祖神周囲の注連縄や紙垂、御幣などが新調されていました。
 町内各地区の道祖神
町内各地区の道祖神
博物館日記にもあるように、お山飾りをエントランスに毎年飾っていましたが、今年は空調設備改修のため飾ることができませんでした。
1月6日(土)
今年は辰(竜・龍)年です。辰は十二支で唯一想像上の動物です。
干支(えと)と十二支を同じだと思っている方も多く見られますが、干支とは正しくは「十干十二支」の略です。「甲(こう・きのえ)、乙(おつ・きのと)、丙(へい・ひのえ)、丁(てい・ひのと)、戊(ぼ・つちのえ)、己(き・つちのと)、庚(こう・かのえ)、辛(しん・かのと)、壬(じん・みずのえ)、癸(き・みずのと)」の十干と、「子(ね・ねずみ)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う・うさぎ)、辰(たつ)、巳(み・へび)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い・いのしし)」の十二支の動物を組み合わせた60種類の数を表す言葉です。60で一回りして最初にかえってくるので、60歳を還暦というのもここからきています。
古代中国では、暦や時間、方位を示すのに「十干十二支」が使われていました。この影響を受けた日本でも同様に使われ、昔の成績表「甲、乙、丙」や契約書の書類中の「甲、乙」としても使われていますね。
今年の干支は甲辰(きのえたつ)です。「甲」は、学業成績では一番上のランクであり、等級では最上位を表しています。山梨県の古い国名「甲斐国」の「甲」です。「甲斐」の国名は、古くは「歌斐」、「柯彼」とも書かれていましたが、好字二字令により「甲斐」に統一されました。ちなみに「斐」の字は、麗しい、美しい、綾があって美しいという意味です。
「辰」は十二支の5番目で、「木の陽」に分類されます。草木の成長が一段落し、整った状態や、春の日差しが平等に降り注ぐ中春のイメージを表しています。「辰」の原字は、「蜃」で、二枚貝が開き弾力性のある肉を動かしているさまを描いたもので、「振」、「震」の意味を持っているそうです。年が明けた1月1日から能登半島地震で「震」の影響が出てしまったのは、循環する歴史の必然なのでしょうか。
「甲辰」と組み合わされた今年は、陽の気が動いて万物が振動し、急速な成長と変化の歳になりそうです。能登半島地震にみられるような振動やマイナス面での変革・変動は、遠慮したいものです。
 本栖湖からの竜ヶ岳と富士山 巌竜山慈観寺経蔵の竜の彫刻(切房木)
本栖湖からの竜ヶ岳と富士山 巌竜山慈観寺経蔵の竜の彫刻(切房木)
1月2日(火)
新年あけましておめでとうございます。
元日から能登半島では大地震が発生し、山梨でも揺れが確認されてビックリしました。
被害に遭われました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
さて現在12月から空調設備の改修工事中ですが、今日から8日まで期間限定で砂金採り体験のみ開館しております。ひさびさに来館されましたお客様の姿がみえて、職員一同張り切っております。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

12月4日(月)
2日に南アルプス市で「御勅使扇状地の古代牧を考える」をテーマに山梨郷土研究会の研究例会がありました。南アルプス山麓の八田の牧を中心に4本の発表とシンポジウムがありました。甲斐国は古代より「甲斐の黒駒」に代表される馬生産の伝統があり、三つの勅旨牧のほか私牧も多く存在していました。
身延町関連では、「飯野牧」、「南部牧」が「日蓮上人身延山御書」の文献上にも登場する私牧で、甲斐源氏のうち富士川流域の河内地方を拠点とした南部氏が富士川右岸に設けていた牧と推定されています。甲斐国内の牧の経営は甲斐源氏とのつながりが強く、武士道を弓馬の道と言うように流鏑馬に代表される弓馬の鍛錬に精通すると同時に、良馬の生産に関与していたことがうかがわれます。
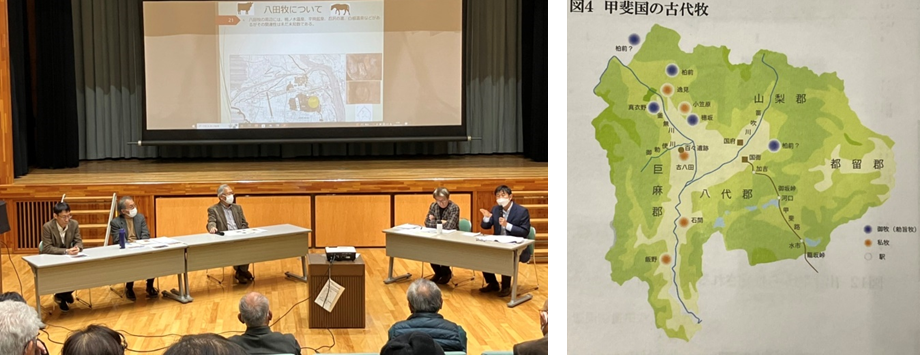 『身延町誌』では「飯富」を「おぶ」とも呼ぶことから「飯野」を「おおの」と訓じ、現身延町「大野」の地域に比定しています。また、南部氏が源頼朝に従って奥州藤原氏を攻め、その論功行賞により奥州糠部郡の各所を賜って移住し、甲斐で育んだ牧場経営にあたって、奥州南部氏として勢力を拡大して扶植するもとになっています。
『身延町誌』では「飯富」を「おぶ」とも呼ぶことから「飯野」を「おおの」と訓じ、現身延町「大野」の地域に比定しています。また、南部氏が源頼朝に従って奥州藤原氏を攻め、その論功行賞により奥州糠部郡の各所を賜って移住し、甲斐で育んだ牧場経営にあたって、奥州南部氏として勢力を拡大して扶植するもとになっています。
11月30日(木)
日本には美しい四季があります。一年の中を二十四節気七十二候に区分し、自然界の草花や生き物の様子など陽気の微妙な変化が細かく表現されています。二十四節気の「小雪」も過ぎ、北国や周辺の山々からも雪の便りも届くようになりました。今朝の通勤時には富士山、甲斐駒ケ岳、八ヶ岳、白根三山、鳳凰山などの雪を頂いた姿を車窓から見ながら金山博物館にきました。今は七十二候の第五十九候「朔風払葉」(きたかぜこのはをはらう)で、冷たい北風が木の葉を舞い落す頃に当たります。
 駐車場やリバーサイドパークの紅葉がかなり進んできました。紅葉も黄葉もまだまだ残っている木もあるのですが、山に接しているため山の木々から北風に飛ばされてきた枯葉が建物の入口や段差のある所に吹き溜まりとなっています。季節の移ろいは確実に進んでいます。
駐車場やリバーサイドパークの紅葉がかなり進んできました。紅葉も黄葉もまだまだ残っている木もあるのですが、山に接しているため山の木々から北風に飛ばされてきた枯葉が建物の入口や段差のある所に吹き溜まりとなっています。季節の移ろいは確実に進んでいます。
本日が臨時休館前の開館最終日となりました。ご来館いただいた皆様ありがとうございました。2か月間の空調設備改修工事のため、休館とさせていただきます。
11月28日(火)
長野県の守屋山に登ってきました。守屋山は諏訪市と伊那市の境界にある標高1,651mの山で、東峰と西峰があります。山頂からは北アルプス、御岳、乗鞍岳、中央アルプス、南アルプス、八ヶ岳、蓼科山、浅間山、美ヶ原など360℃の眺望があり、諏訪湖全体を一望できました。
 守屋山は、諏訪大社上社本宮のご神体とよく言われますが、そうではないようです。境内から守屋山を仰ぎ見ることができないだけでなく、古文献にもそのような記述は見いだせないようです。
守屋山は、諏訪大社上社本宮のご神体とよく言われますが、そうではないようです。境内から守屋山を仰ぎ見ることができないだけでなく、古文献にもそのような記述は見いだせないようです。  東峰には(物部)守屋神社の奥宮の石祠があり、神の依代である磐座(いわくら)と思われる岩の脇に鎮座していて、地元の方々の崇敬を集めていることがわかります。守屋山の周辺の村々では、日照りが続くと守屋山に登って雨乞いをしたそうです。石祠の前には模造弓2個とステンレス製の鎌1個がお供えされていました。前回の訪問時にはなく、どうも最近置かれたもののようです。これらは雨乞い神事のための奉賽物なのでしょうか。鎌は風切り鎌または諏訪神社特有のなぎ鎌祭祀に関係するものなのでしょうか。
東峰には(物部)守屋神社の奥宮の石祠があり、神の依代である磐座(いわくら)と思われる岩の脇に鎮座していて、地元の方々の崇敬を集めていることがわかります。守屋山の周辺の村々では、日照りが続くと守屋山に登って雨乞いをしたそうです。石祠の前には模造弓2個とステンレス製の鎌1個がお供えされていました。前回の訪問時にはなく、どうも最近置かれたもののようです。これらは雨乞い神事のための奉賽物なのでしょうか。鎌は風切り鎌または諏訪神社特有のなぎ鎌祭祀に関係するものなのでしょうか。
11月25日(土)
23日は「甲斐の信仰の山々―南巨摩地域を中心としてー」と題して第2回目となる館長講座を実施しました。ご来館していただいたみなさん、ありがとうございました。
甲斐国は周囲を高い山々に囲まれており、北には八ヶ岳、関東山地が北から東、西側に赤石山脈(南アルプス)、南に富士山、中央には山梨を東西に分ける御坂山地が囲繞しています。県土の八割を山岳地が占め、平地の極めて少ない山岳が連なる地勢であります。
 古代において甲斐国の枕詞は、「なまよみ」で「なまよみの甲斐」として訓じられてきました。「なまよみ」とは一体何なのでしょうか。「なま」は「生半可」のなまで中途半端・不完全なこと、「よみ」は「黄泉」であの世のことと解釈した場合、「なま黄泉の甲斐」すなわちあの世とこの世の境界の地を指すとの説があります。(諸説あり)古代の中心であった奈良や京都方面から甲斐国をみると、夏でも雪を頂き噴煙を上げていた霊峰富士のさらに向こう側にある地域であり、現生(うつしよ)と常世(とこよ)(死後の世界)との境目の地域として認識されていたのかもしれません。「甲斐」は「交ひ」で交わる・交差する意味です。
古代において甲斐国の枕詞は、「なまよみ」で「なまよみの甲斐」として訓じられてきました。「なまよみ」とは一体何なのでしょうか。「なま」は「生半可」のなまで中途半端・不完全なこと、「よみ」は「黄泉」であの世のことと解釈した場合、「なま黄泉の甲斐」すなわちあの世とこの世の境界の地を指すとの説があります。(諸説あり)古代の中心であった奈良や京都方面から甲斐国をみると、夏でも雪を頂き噴煙を上げていた霊峰富士のさらに向こう側にある地域であり、現生(うつしよ)と常世(とこよ)(死後の世界)との境目の地域として認識されていたのかもしれません。「甲斐」は「交ひ」で交わる・交差する意味です。
この「なまよみの甲斐」原典は、万葉集第三巻の高橋虫麻呂が富士山を詠った長歌ただ一つです。「奈麻余美乃 甲斐乃國 打縁駿河能國与 己知其智乃 國之三中従 出立有 不藎能高峰者 天雲毛 伊去波伐加利 飛鳥母 翔毛不上 燎火乎 雪以滅 落雪乎 火用消通都 言不得 名不知 霊母 座神香聞 石花海跡 名付而有毛 彼山之 堤有海曽 不盡河跡 人乃渡毛 其山之 水乃當焉 日本之 山跡國乃 鎮十方 座祇可間 寳十方 成有山可聞 駿河有 不盡能高峯者 雖見不飽香聞」と出てきます。
読みは「なまよみの 甲斐の国 うちよする駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ 出で立てる 富士の高嶺は 天雲も い行きはばかり 飛ぶ鳥も 飛ぶも上がらず 燃ゆる火を 雪をもち消ち 降る雪を 火をもち消ちつつ 言ひも得ず 名づけも知らず くすしくも います神かも せの海と 名付けてあるも その山の つつめる海ぞ 富士川と 人の渡るも その山の 水のたぎじぞ 日の本の 大和の国の 鎮めとも います神かも 宝とも なれる山かも 駿河なる富士の高嶺は 見れど飽かぬかも」となります。
意味は「甲斐の国、駿河の国とあちこちの国の中心に立っている富士山は、雲も行く手をはばまれ、鳥も上がってゆくことができず、燃える火を雪で消し、降る雪を火で消してしまいます。言葉では言い尽くせないほど神秘的な神の山です。せの海と名付けてある湖も、富士山が包んでいます。富士川もその源は富士の山です。日本を鎮めていらっしゃる神の山、宝の山なのです。駿河の国の富士の高嶺は、どんなに見ていても飽きることはありません。  現在では「なまよみの甲斐」は「なま黄泉の甲斐」ではなく、「行(並)吉みの甲斐」と解釈されて、美しい山並みの意味で使用されたとする説が有力視されています。
現在では「なまよみの甲斐」は「なま黄泉の甲斐」ではなく、「行(並)吉みの甲斐」と解釈されて、美しい山並みの意味で使用されたとする説が有力視されています。
11月20日(月)
実りの秋もそろそろ終盤です。湯之奥金山駐車場に隣接する山裾の木々やリバーサイドパークには、赤、紫、青、茶などのいろんな色の実がなっています。今日確認できたものに、ナンテン、コムラサキ、アオツヅラフジ、ノブドウ、ヘクソカズラ、ヤマボウシ、フユザンショウなどがあります。地中に根を張って自ら動くことのできない植物たちは、その果実を鳥や動物に食べてもらって消化しきれない種子がフンと一緒に排出されて移動します。植栽されたコムラサキとヤマボウシ以外は、このシステムによって当地にもたらされたものなのでしょう。
 植物の種子の移動は散布種子と言って、5類型に分類されます。前述の①動物散布型種子は糞とともに排出されるもののほか、ひっつきむし(ばか)の様に動物の毛や皮膚に付着して運ばれるもの、クルミやドングリなど食料として運ばれ貯蔵されたものの食べ残しが発芽するものなどがあります。風によって運ばれる②風散布型は冠毛や羽などの付属体を持つもので、タンポポやカエデなどがこれに当たります。③水流型は雨や川・海流などによって運ばれるもので、ヤシやヒシなど水辺の植物に多いタイプです。④自力散布は、植物自らの力を使ったもので、乾燥による収縮率の違いなどの力によって果実などが裂けて瞬間的に弾けることで種を飛ばします。フジやホウセンカがこれです。⑤重力散布は種子や果実にこれといった特徴はなく、親の周囲に重力によって自ら落下させる方法です。トチ、オニグルミ、クヌギ、カシなどですが、落下した種子は①動物貯蔵型や③水流型など二次的に動物や水によって運ばれることもあります。
植物の種子の移動は散布種子と言って、5類型に分類されます。前述の①動物散布型種子は糞とともに排出されるもののほか、ひっつきむし(ばか)の様に動物の毛や皮膚に付着して運ばれるもの、クルミやドングリなど食料として運ばれ貯蔵されたものの食べ残しが発芽するものなどがあります。風によって運ばれる②風散布型は冠毛や羽などの付属体を持つもので、タンポポやカエデなどがこれに当たります。③水流型は雨や川・海流などによって運ばれるもので、ヤシやヒシなど水辺の植物に多いタイプです。④自力散布は、植物自らの力を使ったもので、乾燥による収縮率の違いなどの力によって果実などが裂けて瞬間的に弾けることで種を飛ばします。フジやホウセンカがこれです。⑤重力散布は種子や果実にこれといった特徴はなく、親の周囲に重力によって自ら落下させる方法です。トチ、オニグルミ、クヌギ、カシなどですが、落下した種子は①動物貯蔵型や③水流型など二次的に動物や水によって運ばれることもあります。

11月19日(日)
 今朝も寒かったですね。身延町の最低気温は0℃。日中でもほとんど日陰の博物館一帯は、構内のベンチにあった朝の霜が真っ白にそのまま10時過ぎまで残っていました。
今朝も寒かったですね。身延町の最低気温は0℃。日中でもほとんど日陰の博物館一帯は、構内のベンチにあった朝の霜が真っ白にそのまま10時過ぎまで残っていました。
 この寒さで紅葉も一段と進んできたようです。博物館の駐車場の周りやリバーサイドパークにある葉の残っているモミジも、やっと色づき始めました。紅葉が進んでいる部分は赤色、朱色、橙色、黄色、緑と葉の色も同じ木なのに枝や場所によって様々です。色の濃淡とその複雑に入り交じった姿が、興味をそそります。特に黄色の葉なのに、葉脈の部分だけが赤く色付いている葉や中間色の色合いが変化している葉はふしぎです。モミジの歌の歌詞の2番に、「渓(たに)の流れに散り浮くモミジ 波にゆられて離れて寄って 赤や黄色の色さまざまに 水の上にも織る錦」とあるように、同じ木の葉なのにその環境によって色がさまざまに変化しています。
この寒さで紅葉も一段と進んできたようです。博物館の駐車場の周りやリバーサイドパークにある葉の残っているモミジも、やっと色づき始めました。紅葉が進んでいる部分は赤色、朱色、橙色、黄色、緑と葉の色も同じ木なのに枝や場所によって様々です。色の濃淡とその複雑に入り交じった姿が、興味をそそります。特に黄色の葉なのに、葉脈の部分だけが赤く色付いている葉や中間色の色合いが変化している葉はふしぎです。モミジの歌の歌詞の2番に、「渓(たに)の流れに散り浮くモミジ 波にゆられて離れて寄って 赤や黄色の色さまざまに 水の上にも織る錦」とあるように、同じ木の葉なのにその環境によって色がさまざまに変化しています。
 紅葉や落葉は葉っぱの老化現象によるものだそうです。日照時間が短くなったり気温が低くなったりすると光合成の効率が低下して、葉を維持するプラス部分がなくなってしまうため葉を落とす準備を始めます。光合成に必要な成分の葉緑体(クロロフィル)は緑色なのですが、この栄養分を来年の春に再利用するため枝や幹に回収します。この過程において、赤色の成分のアントシアニンや黄色の成分のカロテノイドなどが合成されるため、色素量のバランスが変化して葉の色が変わり紅葉や黄葉になるということです。
紅葉や落葉は葉っぱの老化現象によるものだそうです。日照時間が短くなったり気温が低くなったりすると光合成の効率が低下して、葉を維持するプラス部分がなくなってしまうため葉を落とす準備を始めます。光合成に必要な成分の葉緑体(クロロフィル)は緑色なのですが、この栄養分を来年の春に再利用するため枝や幹に回収します。この過程において、赤色の成分のアントシアニンや黄色の成分のカロテノイドなどが合成されるため、色素量のバランスが変化して葉の色が変わり紅葉や黄葉になるということです。
11月15日(木)
博物館の入口に並べてある菊の花がほぼ満開になりました。黄色の花がたくさん並んでいるのはそれなりに壮観で、金山博物館にふさわしい風情です。今日は菊をほめてくれる入館されたお客様もあって、提供した当事者としてはうれしい限りです。
 菊の株が思いのほか大きくなったので株がくっついてしまって、植えてくれた友人も驚いていました。鉢上げすると一つひとつの菊株の樹形が不安定になって、風で枝が折れたり地面にくっついたりしたので、紐でフェンスに括り付けてみました。来年チャレンジする時には、株の樹形がうまく球形に整うように間隔に注意して植えてみたいものです。このうまくいかなかった経験を、次年度の成功につなげたいと思いました。
菊の株が思いのほか大きくなったので株がくっついてしまって、植えてくれた友人も驚いていました。鉢上げすると一つひとつの菊株の樹形が不安定になって、風で枝が折れたり地面にくっついたりしたので、紐でフェンスに括り付けてみました。来年チャレンジする時には、株の樹形がうまく球形に整うように間隔に注意して植えてみたいものです。このうまくいかなかった経験を、次年度の成功につなげたいと思いました。
11月12日(日)
下部リバーサイドパークのヘリポートの北側にある桜の木1本に、花が咲いているのに気がつきました。駐車場やグラウンド・ゴルフ場の周囲にはたくさんのサクラの木がありますが、ほとんどがその葉を落として冬支度を終わらせています。わずかに紅葉した葉を残す木もある中で、唯一八重になった白や薄ピンク花がちらほら咲いています。わずかに緑の葉をつけている枝もあります。この桜は「ジュウガツザクラ」といって、春と秋から冬にかけての2時季に花を咲かせる種類のサクラでした。八重なので一重の「シキザクラ」とは別物になります。

秋の桜なので「秋桜」と表記すると「コスモス」のことになるので、「十月桜(ジュウガツザクラ)」の命名となったのでしょうか。サクラの花が咲いていたので正直驚きました。今月に入って2度の夏日があったこともあって、ここのところの高温による異常気象が原因の「狂い咲き」や「返り咲き」と思ったのですが、そういう種類の木なのだと知って納得しました。

同じように秋に咲く八重桜に「子福桜(コブクザクラ)」があります。ふつうは1つの花から1つの実ができるのですが、この桜は2つ以上の実をつけるらしいのです。それで「子宝の桜」ということで「子福桜(コブクザクラ)」と名前が付けられたそうです。これは「ヤツブサウメ」と同様に一つの花に複数のめしべがあって、たくさん実をつける種類のようです。
11月10日(金)
「エノコログサ」は、漢字で書くと「狗尾草」なんです。狗は犬のことで、その形が犬のしっぽの毛のふさふさしているところに似ていることからの命名だそうです。「イヌコログサ」とはならずに「エノコログサ」になったのは、誰かの発音がなまっていたものを正式名称に採用されたからだと考えられています。でも、一般の私たちには「ネコジャラシ」としての通称名の方になじみがありますね。その穂が風に揺れるのを見て、猫がじゃれ遊ぶ様子から名前が付けられました。この形に似せた猫用の遊具は、ペットショップやホームセンターで今でも売られています。
 現在は穂も茶色になってしまいましたが、夏まではきれいな緑色をしていました。野山にあるのはいいのですが、繁殖力が強くて畑や庭では手のかかる雑草です。犬のしっぽに似ているから「エノコログサ」、猫がじゃれるから「ネコジャラシ」、英語では「Green foxtail grass」(狐のしっぽ草)と同じ草なのに、犬だったり猫だったり狐だったり。いろいろな動物に関連付けられているのは面白いですね。
現在は穂も茶色になってしまいましたが、夏まではきれいな緑色をしていました。野山にあるのはいいのですが、繁殖力が強くて畑や庭では手のかかる雑草です。犬のしっぽに似ているから「エノコログサ」、猫がじゃれるから「ネコジャラシ」、英語では「Green foxtail grass」(狐のしっぽ草)と同じ草なのに、犬だったり猫だったり狐だったり。いろいろな動物に関連付けられているのは面白いですね。
11月6日(月)
篠井山(四ノ位山)は、その山名が凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)に由来し、山上の篠井神社の祭神とする説は昨日のブログのとおりです。彼は平安前期の歌人であり難読人名にもよく登場し、紀貫之とともに古今和歌集の選者としても著名な人物です。「心あてに 折らばや折らむ初霜の おきまどはせる 白菊の花」(小倉百人一首)は代表歌で、甲斐の国の地方官(国司)として直接赴任してきたことが知られており、富士川に関する歌もいくつか詠んでいるのが伝わっています。
 躬恒には地元で古くから伝わる、篠井山に関わる伝説がありました。『富沢町誌』(下巻)によると、ある時この地に居住していた凡河内躬恒は篠井山に登り、山頂に「山霊」鎮護のための宝物を埋めたというものです。明治24(1891)年5月、この話を信じた何者かによって篠井山頂が無断で掘り返され、宝物がどこかへ持ち去られるという盗掘事件がありました。盗掘した跡には三種類の陶器片と唐銅の蓋の擬宝珠が拾得され、これらの遺物が保存してあった木箱の蓋にこの経緯が記されていました。
躬恒には地元で古くから伝わる、篠井山に関わる伝説がありました。『富沢町誌』(下巻)によると、ある時この地に居住していた凡河内躬恒は篠井山に登り、山頂に「山霊」鎮護のための宝物を埋めたというものです。明治24(1891)年5月、この話を信じた何者かによって篠井山頂が無断で掘り返され、宝物がどこかへ持ち去られるという盗掘事件がありました。盗掘した跡には三種類の陶器片と唐銅の蓋の擬宝珠が拾得され、これらの遺物が保存してあった木箱の蓋にこの経緯が記されていました。
昭和59(1984)年、篠井山の山頂に宝物を埋めてあったという壺が南部町徳間で発見されました。「藤原顕長・惟宗遠清」など14行64文字が書かれた渥美焼の壺で、経塚の外容器であったことがその後判明しました。この経塚は経典を後世に残すためのタイムカプセルとして平安時代末の12世紀に造営されたものですが、凡河内躬恒ではなく「藤原顕長」が願主(スポンサー)だということが書かれた文字からわかりました。
 北峰一段下の満願寺跡の先には、江戸時代元禄年間に一字一石経の経塚が造営され、経碑が建てられています。篠井山が時代を超えて、信仰対象の霊山として地域の人々に崇められていたことを物語っています。
北峰一段下の満願寺跡の先には、江戸時代元禄年間に一字一石経の経塚が造営され、経碑が建てられています。篠井山が時代を超えて、信仰対象の霊山として地域の人々に崇められていたことを物語っています。
11月5日(日)
先日の休みを利用して、南部町の篠井山に行ってきました。篠井山は、標高1,394mの富士川右岸にそびえる険しい高山で、古くから山岳信仰の対象です。双耳峰の様に2か所に高い地点があり、北方に篠井明神社、南峰に最高所の三角点があります。南峰は山梨百名山の標柱や方位展望板があり、東に富士山、南東には駿河湾から伊豆半島まで望めました。北峰の山頂には篠井明神が祀られ、楮根・御堂地区の本殿とその覆屋があり、尾根を北に少し下ると満願寺跡の説明板の立つ平場があります。
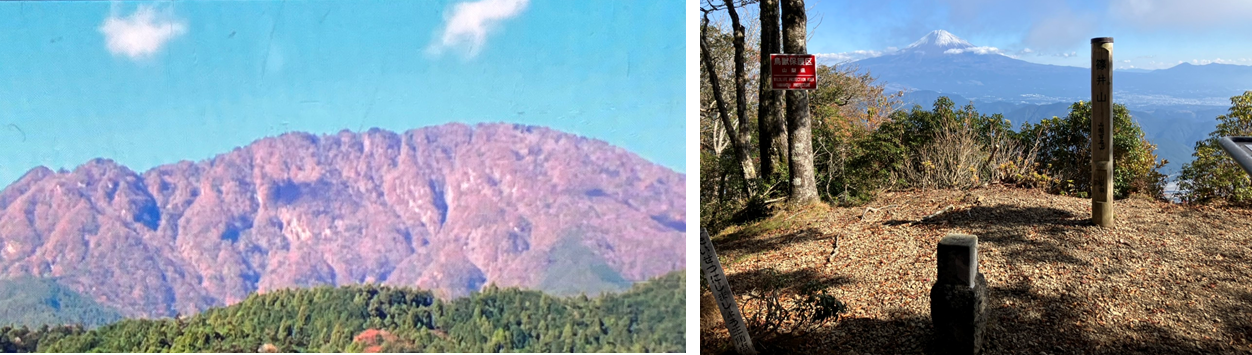 登山道は最初、福士川の上流部に沿って付けられており、不撓不屈の滝、明源の滝、絹糸の滝などの清流を見ながら川の右岸左岸を縫って登ります。川にはイワナと思しき魚が見られ、水量の多い淵には塩焼きにしたらおいしそうなサイズもいました。その後、ヒノキやスギの植林地帯をジグザグに登り頂上に到着しました。
登山道は最初、福士川の上流部に沿って付けられており、不撓不屈の滝、明源の滝、絹糸の滝などの清流を見ながら川の右岸左岸を縫って登ります。川にはイワナと思しき魚が見られ、水量の多い淵には塩焼きにしたらおいしそうなサイズもいました。その後、ヒノキやスギの植林地帯をジグザグに登り頂上に到着しました。
 篠井山は四ノ位山とも別称され、甲斐の役人として赴任してきた凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)がこの山に登ったことから彼の位階を山名にしたとの説があります。周辺集落を流れる幾多の河川の源流となっていて田畑を潤しているため、山すその集落の農耕神としても崇敬されてきました。篠井明神社は大山祇尊(おおやまづみのみこと)のほか凡河内躬恒を祭神とする説もあるそうです。
篠井山は四ノ位山とも別称され、甲斐の役人として赴任してきた凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)がこの山に登ったことから彼の位階を山名にしたとの説があります。周辺集落を流れる幾多の河川の源流となっていて田畑を潤しているため、山すその集落の農耕神としても崇敬されてきました。篠井明神社は大山祇尊(おおやまづみのみこと)のほか凡河内躬恒を祭神とする説もあるそうです。
10月30日(月)
28・29日に「考古学と中世史シンポジウム」が帝京大学文化財研究所で開催され、当館学芸員と行ってきました。
第一部「金銀山の世界」では「金銀山の鉱山技術」―中世後期の技術変革―と題して、当館開館時から長年ご指導いただいている井澤英二先生が発表されました。湯之奥金山を包括する甲斐地域が中熱水金鉱脈のエリアのひとつで、純度の高いやや粗粒の金が採取できたことが、初期の山金採掘を可能にさせた要因であると説明されました。ちなみに、佐渡や伊豆の金山は浅熱水金鉱脈で、主として金銀の合金として存在し金粒は細かく比重で分け採るには工夫が必要であり、金銀を分離しなければ金にならなかったと解説されました。
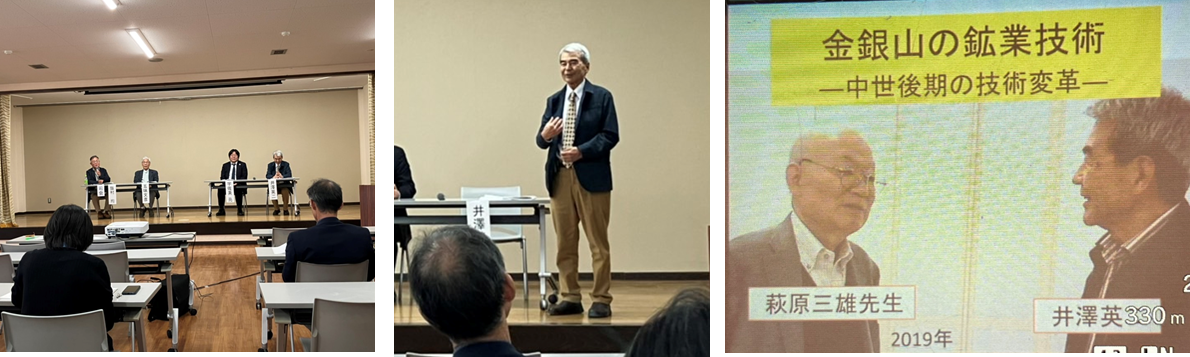 このシンポジウムは、世話人代表の一人故萩原三雄氏が中心となって立ち上げられたものです。萩原先生は当博物館の運営委員長として、中山金山の発掘調査から当博物館の設立に関して、学問的専門分野から主導的立場で関与されてきました。シンポジウムの各発表の中でも、萩原先生の広い視野で将来を見据えた学際的な取り組みが再認識され、余人をもって代えがたい先生の存在の大きさが再評価されました.
このシンポジウムは、世話人代表の一人故萩原三雄氏が中心となって立ち上げられたものです。萩原先生は当博物館の運営委員長として、中山金山の発掘調査から当博物館の設立に関して、学問的専門分野から主導的立場で関与されてきました。シンポジウムの各発表の中でも、萩原先生の広い視野で将来を見据えた学際的な取り組みが再認識され、余人をもって代えがたい先生の存在の大きさが再評価されました.
10月26日(木)
急に秋が深まってきました。朝夕の気温が10度を下回るようになり、肌寒さを感じるこの頃です。しかし、昼の気温は平年よりやや高めで推移しています。
 我が家の周辺の家の庭には、キンモクセイ(金木犀)を植えている家が何軒もあります。また、数軒先の家にはギンモクセイ(銀木犀)が咲いています。今年の秋はキンモクセイの開花が遅かったので香りが漂ってきたのは今月の中旬過ぎになってからでしたが、ここのところの朝の冷え込みで花も終盤となり、もう香りもあまり感じられなくなってきました。開花から散るまでの期間が意外と短いことは、実家に百年以上の大木があったことから知っていましたが、今さらながら再認識した次第です。近所の木の下には、花の散ったオレンジ色の花びらが溜まっていました。キンモクセイの花言葉は。「謙虚」「気高い人」「誘惑」「陶酔」などです。キンモクセイの香りは高貴な印象を与えるのに花自体が小さいこと、独特な強くて甘い芳香を漂わせることから来ているのでしょう。
我が家の周辺の家の庭には、キンモクセイ(金木犀)を植えている家が何軒もあります。また、数軒先の家にはギンモクセイ(銀木犀)が咲いています。今年の秋はキンモクセイの開花が遅かったので香りが漂ってきたのは今月の中旬過ぎになってからでしたが、ここのところの朝の冷え込みで花も終盤となり、もう香りもあまり感じられなくなってきました。開花から散るまでの期間が意外と短いことは、実家に百年以上の大木があったことから知っていましたが、今さらながら再認識した次第です。近所の木の下には、花の散ったオレンジ色の花びらが溜まっていました。キンモクセイの花言葉は。「謙虚」「気高い人」「誘惑」「陶酔」などです。キンモクセイの香りは高貴な印象を与えるのに花自体が小さいこと、独特な強くて甘い芳香を漂わせることから来ているのでしょう。

駐車場の山際にオニグルミの実が落ちています。緑色の落ちたてものから、熟して黒くなったもの、外側の仮果がとれて核果と呼ばれる硬い殻部分のみのものもあります。種子のかたい殻の中には仁という食用の部分があり、それを動物(野ネズミ)が食べた跡の穴があけられたものもあります。クルミの名前は、呉(中国)から来た実とか、その丸い形からくるくる回る実とかの説があります。クルミは湿地に多く分布する落葉高木で、古くは縄文時代の遺跡からも炭化した殻が出土しており食用に供されていたことがわかっています。甲斐国は古代からクルミの特産地であり、奈良時代の平城宮跡から出土した木簡(木札)にも税としてクルミを甲斐国から進上していたことを裏付ける文字が書かれていました。クルミには、体内で作ることのできない多価不飽和脂肪酸という体に良い脂質やタンパク質、ビタミン、ミネラルなど多くの栄養素を含んでいます。甲斐八珍果のひとつである旬のクルミを味わってみてください。
10月23日(月)
今日は旧暦の9月9日、「重陽の節句」です。中国では奇数のことを陽数と言って、縁起が良いとされてきました。特に最も大きな陽数である「9」が重なる9月9日を「重陽の節句」と定めて、菊酒を飲んだり栗ご飯を食べたりしてお祝いしました。
 節句とは、季節ごとに行われる無病息災や子孫繁栄を願う伝統行事です。日本では現在五節句が主に知られており、1月7日「人日の節句(七草の節句)」、3月3日「上巳の節句(桃の節句)」、5月5日「端午の節句(菖蒲の節句)」、7月7日「七夕の節句(青笹の節句)」、9月9日「重陽の節句(菊の節句)」の五つになります。元はもっとたくさんの節句がありましたが、江戸時代に公的な行事を行う式日としてこの五つを定めたことにより、五節句と呼ばれるようになったということです。その時期の旬の食材や、邪気を払うとされる行事食を食べたり、それぞれの節句ならではの飾りを楽しんだりして過ごすことが定着しました。(5/5ブログ参照)
節句とは、季節ごとに行われる無病息災や子孫繁栄を願う伝統行事です。日本では現在五節句が主に知られており、1月7日「人日の節句(七草の節句)」、3月3日「上巳の節句(桃の節句)」、5月5日「端午の節句(菖蒲の節句)」、7月7日「七夕の節句(青笹の節句)」、9月9日「重陽の節句(菊の節句)」の五つになります。元はもっとたくさんの節句がありましたが、江戸時代に公的な行事を行う式日としてこの五つを定めたことにより、五節句と呼ばれるようになったということです。その時期の旬の食材や、邪気を払うとされる行事食を食べたり、それぞれの節句ならではの飾りを楽しんだりして過ごすことが定着しました。(5/5ブログ参照)
 前述のように今日は別名「菊の節句」です。菊には邪気払いや不老長寿の効果があるとされています。キクの花言葉は「高貴」「高尚」「高潔」です。気品あふれる菊の花は、皇室や皇族関係の紋章にも定められていることはご承知のとおりです。博物館前に飾った菊の鉢は、小さな花がたくさん咲き始めていて賑やかにお客様をお迎えしています。また、リバーサイドパークの植栽と川との間や植栽中には、ノコンギク(野紺菊)が可憐な花をつけています。
前述のように今日は別名「菊の節句」です。菊には邪気払いや不老長寿の効果があるとされています。キクの花言葉は「高貴」「高尚」「高潔」です。気品あふれる菊の花は、皇室や皇族関係の紋章にも定められていることはご承知のとおりです。博物館前に飾った菊の鉢は、小さな花がたくさん咲き始めていて賑やかにお客様をお迎えしています。また、リバーサイドパークの植栽と川との間や植栽中には、ノコンギク(野紺菊)が可憐な花をつけています。
ちなみに、食卓にサラダなどでおなじみのレタスはキク科の野菜なんですョ。
10月22日(日)
10月19日のNHKニュースで「高濃度の金「藻」のシートで回収成功 東京青ヶ島沖の深海」と放送がありました。海洋研究開発機構などの研究グループが、深海の熱水噴出孔に藻を原料とした特殊なシートを約2年間設置し、熱水に含まれている金をこれに吸着させて、高濃度の金を回収することに成功したものです。金は1トンに対し20グラム相当の割合で藻に吸着していて、さらに銀は1トン当たり7000グラム相当の割合があったそうです。
採算の面から直ちに商業化につながるわけではないのですが、この技術は温泉や下水にも応用可能ということで、新たな金の採取方法となる可能性に夢が膨らみます。(5/29ブログ参照)
10月21日(土)
 今年の紅葉は少し変です。博物館駐車場の中ほどにあるモミジは、紅葉しないで葉が枯れ落ちて半分以上すでに枝のみになっています。しかし、山裾側にあるモミジは、まだ緑の葉のままです。夏の猛暑が続いたのと、ここのところの急な朝の冷え込みのせいでしょうか。
今年の紅葉は少し変です。博物館駐車場の中ほどにあるモミジは、紅葉しないで葉が枯れ落ちて半分以上すでに枝のみになっています。しかし、山裾側にあるモミジは、まだ緑の葉のままです。夏の猛暑が続いたのと、ここのところの急な朝の冷え込みのせいでしょうか。
空は澄んだ青空で空気はカラッとしているため、秋らしくとても気持ちの良い天気です。博物館のある場所は東から南に山が迫っており朝の数時間しか陽が当たらないため、外は快適な気候なのですが建物内は底冷えがしています。
 下部川にかかる「ふれあい橋」は県下一長い斜張橋で、歩くとメロディが流れます。秋の季節の曲は「もみじ」と「里の秋」です。スポーツの秋でもあり良い天気に恵まれているので、下部リバーサイドパークではゼッケンをつけた年配の方々によるグランドゴルフの試合が行われていました。
下部川にかかる「ふれあい橋」は県下一長い斜張橋で、歩くとメロディが流れます。秋の季節の曲は「もみじ」と「里の秋」です。スポーツの秋でもあり良い天気に恵まれているので、下部リバーサイドパークではゼッケンをつけた年配の方々によるグランドゴルフの試合が行われていました。
10月19日(木)
 15日の中山金山見学会の時、登山道沿いにモミの実が何かの動物に食べられた跡がありました。まだ緑色をした球果がバラバラになって、地面に散乱しています。調べてみるとこれはリスの仕業のようです。リスはモミの種子を好んで食べるとのことで、モミの球果の鱗片が食べ散らかされています。モミの果実は10センチにもなる円柱状の形をしており、日本の針葉樹の中でもひと際大きく、地面に落ちたその実はまるで地表を這うナマコのようです。この果実は、真ん中の軸の周りに鱗片がらせん状に並んでいます。若いうちは薄緑色で、表面に多数のトゲのようなものがつんつんと突き出ています。秋になると褐色に変わり、枝上で鱗片がばらばらに分解して落下し、この時に大きな翼のついた種子がばらまかれます。鱗片はそれぞれ角ばった扇形をしていることがわかります。元の球果ではなかなか観察することができませんが、リスのおかげで分解されてその構造が確認できました。
15日の中山金山見学会の時、登山道沿いにモミの実が何かの動物に食べられた跡がありました。まだ緑色をした球果がバラバラになって、地面に散乱しています。調べてみるとこれはリスの仕業のようです。リスはモミの種子を好んで食べるとのことで、モミの球果の鱗片が食べ散らかされています。モミの果実は10センチにもなる円柱状の形をしており、日本の針葉樹の中でもひと際大きく、地面に落ちたその実はまるで地表を這うナマコのようです。この果実は、真ん中の軸の周りに鱗片がらせん状に並んでいます。若いうちは薄緑色で、表面に多数のトゲのようなものがつんつんと突き出ています。秋になると褐色に変わり、枝上で鱗片がばらばらに分解して落下し、この時に大きな翼のついた種子がばらまかれます。鱗片はそれぞれ角ばった扇形をしていることがわかります。元の球果ではなかなか観察することができませんが、リスのおかげで分解されてその構造が確認できました。
10月17日(火)
 山の仲間から畑をお借りして、家庭菜園として野菜を作っています。別な山仲間が五月の中旬に、この畑の土手に菊を植えてくれました。植えた時はたった一本だった菊の苗は、枝が分結して大きくなり、それぞれがつながってまるで大きな芋虫のようになりました。かなり間隔をあけてあったのですが、1株が1メートルもの玉状になっていました。これらを自由に利用してよいとの承諾をいただいたので、鉢に植え替えて博物館の入口に並べて1週間ほどがたちました。鉢上げしても枯れるかもしれないとのことでしたが、温かい日差しの中でつぼみも大きくなりました。金山博物館にふさわしい黄金色の花が咲きそうです
山の仲間から畑をお借りして、家庭菜園として野菜を作っています。別な山仲間が五月の中旬に、この畑の土手に菊を植えてくれました。植えた時はたった一本だった菊の苗は、枝が分結して大きくなり、それぞれがつながってまるで大きな芋虫のようになりました。かなり間隔をあけてあったのですが、1株が1メートルもの玉状になっていました。これらを自由に利用してよいとの承諾をいただいたので、鉢に植え替えて博物館の入口に並べて1週間ほどがたちました。鉢上げしても枯れるかもしれないとのことでしたが、温かい日差しの中でつぼみも大きくなりました。金山博物館にふさわしい黄金色の花が咲きそうです
10月15日(日)
 今日は朝から雨が降っていますが、中山金山の現地見学会当日です。参加者も天候のためキャンセルもありましたが、少人数であり午後から回復するという天気予報を信じて時間を遅らせて実施しました。参加者は大人のみであったので、短時間で変更した計画通り挙行することができました。
今日は朝から雨が降っていますが、中山金山の現地見学会当日です。参加者も天候のためキャンセルもありましたが、少人数であり午後から回復するという天気予報を信じて時間を遅らせて実施しました。参加者は大人のみであったので、短時間で変更した計画通り挙行することができました。
 霧がかかっていて幻想的な雰囲気の中、樹木からの雨だれを受けながら登りました。登山道の脇の下草には、蜘蛛の巣がたくさん存在しています。昨夜からの雨と霧によって、クモの巣に不規則な水滴がついて、まるで自然の中の芸術作品です。この水滴はよく見るとキレイな球状をしています。クモの糸は、その強さと柔軟性がこれまで注目されてきましたが、その集水性も評価されるようになり、水不足解消の救世主として新技術開発が期待されています。
霧がかかっていて幻想的な雰囲気の中、樹木からの雨だれを受けながら登りました。登山道の脇の下草には、蜘蛛の巣がたくさん存在しています。昨夜からの雨と霧によって、クモの巣に不規則な水滴がついて、まるで自然の中の芸術作品です。この水滴はよく見るとキレイな球状をしています。クモの糸は、その強さと柔軟性がこれまで注目されてきましたが、その集水性も評価されるようになり、水不足解消の救世主として新技術開発が期待されています。
10月13日(金)
今年は天然キノコがほとんど採れない異常事態だそうです。暑さがつい最近まで続いていて、雨がほとんど降らなかった異常気象が原因で起きているようです。丹波のマツタケも初入荷が約2週間遅れで、その後の入荷もわずかとのこと。登山などアウトドアを趣味としている私としては、キノコの不作情報によってこの時期恒例の山行を躊躇せざるを得ません。山に行っても地面が乾燥していて、毒キノコや不食のキノコの姿もほとんど見かけませんでした。
 今年山で食用キノコを見たのは、湯之奥の中山金山下見と現地案内においてマスタケとタマゴタケと、微笑館に行く町道わきにタマゴタケくらいです。金峰山に登った9月初旬には、ホンシメジとショウゲンジを見つけて心が躍り、多少の遅れはあっても今年も期待できるのかなと思ったのですが、今年はホントに残念です。
今年山で食用キノコを見たのは、湯之奥の中山金山下見と現地案内においてマスタケとタマゴタケと、微笑館に行く町道わきにタマゴタケくらいです。金峰山に登った9月初旬には、ホンシメジとショウゲンジを見つけて心が躍り、多少の遅れはあっても今年も期待できるのかなと思ったのですが、今年はホントに残念です。
10月9日(月)
今日は「スポーツの日」、国民の祝日で三連休の最終日です。昭和39年(1964)10月10日に東京オリンピックの開会式が行われたのをきっかけに、昭和41年にこの日が「体育の日」に制定され「スポーツに親しみ健康な心身を培う」という目的で国民の祝日となりました。平成12年(2000)年からは「ハッピーマンデー制度」によって10月の第2月曜日となり、令和2(2020)年から「スポーツの日」に名称が変更になりました。
今日は朝から雨が降り続いています。「体育の日」は晴れになる確率が高く、晴れの特異日だと言われることもありましたが、統計上ではそうでもないようです。かつては、この日に小中学校の運動会を設定していたことが多かったようですが、現在の山梨県では9月後半の週末開催が主流のようです。スポーツの秋ともいわれるように、秋のすがすがしい時期は運動をするのに最適の時期ですネ。
「秋空高く澄み渡り 峰のこずえも色染めて 映えある心試さんと 二百に余るわが健児」これは私が小学校の時に、運動会で5年生の時まで歌った歌の一番の歌詞です。二番は「東と西にたち別れ 親しき友よ今日ここに 歓声高く勇ましく 正義(または精気or生気)の勝ちを争わん」。現在少子化で廃校となった山梨市の旧牧丘第三小学校は、私が6年生になると全校児童が200名を割ってしまい、前年まで歌っていたこの運動会の歌は歌いませんでした。かつて500名以上の児童数だった時には、「五百に余るわが健児」と歌っていたと聞いています。当時から人口減少が顕著でした。
さて、少子化の進行は、日本の未来を左右する大問題です。旧下部町域にあった小中学校も、統廃合によって全て無くなってしまいました。少子高齢化問題は喫緊の大テーマですネ。
10月6日(金)
3日のブログで「ジャネーの法則」を取り上げました。子供の時は時間が過ぎるのが遅いと感じていたのに、歳をある程度重ねた今現在は、一日一日がものすごく早く終わってしまうと感じています。
 NHKの『チコちゃんに叱られる』の中で「大人になるとあっという間に1年が過ぎるのはなぜ?」との質問があったことを思い出しました。チコちゃんの言葉を借りれば「人生にトキメキがなくなったから」(諸説あり。)だそうです。人生のトキメキそれは、期待や喜びで胸が躍ることです。そういえば、初恋のトキメキもあったよなぁ。好きなことへの好奇心は旺盛だったよなぁ。若いころは多感でいろんなことに感動したよなぁ。それに対してこの頃はなぜか感動することトキメキが少なくなったよなぁ。・・・
NHKの『チコちゃんに叱られる』の中で「大人になるとあっという間に1年が過ぎるのはなぜ?」との質問があったことを思い出しました。チコちゃんの言葉を借りれば「人生にトキメキがなくなったから」(諸説あり。)だそうです。人生のトキメキそれは、期待や喜びで胸が躍ることです。そういえば、初恋のトキメキもあったよなぁ。好きなことへの好奇心は旺盛だったよなぁ。若いころは多感でいろんなことに感動したよなぁ。それに対してこの頃はなぜか感動することトキメキが少なくなったよなぁ。・・・
時間の長さへの感覚は、人それぞれ違うのでしょうが、好きなこと楽しいことをしている時の時間は早く過ぎるのに、辛いこと苦しいと思っていることをしている時の時間は長く感じるのはなぜでしょう。
脳細胞の経年変化、老化現象の産物なのでしょうか。人生の体内時計はかくのごとく加速するものなのでしょうか?不思議ですネ。
10月5日(木)
金山博物館は、東に山を背負い、西に下部川から続いているリバーサイドパークがあるため、自然環境に恵まれています。そのため、いろいろな虫たちも博物館内に迷い込んできたりします。迷いこんだ敷地内で最期を迎えてしまった虫たちも季節によってさまざまです。ここ数日中に確認された生物は、タマムシ、ミンミンゼミ、ウマオイ、カマキリと虫ではないですがサワガニがあります。
 玉虫は金属のような光沢をもつきれいな緑色をしており、光の加減によって赤、青、黄色がみえます。その美しさは、飛鳥時代奈良法隆寺の「玉虫厨子」の外側にその羽が貼り付けられていたことからもうかがえます。玉虫厨子には現在ではそのほとんどが失われてしまっていますが、1万枚近くのタマムシの羽が使われていたといいます。
玉虫は金属のような光沢をもつきれいな緑色をしており、光の加減によって赤、青、黄色がみえます。その美しさは、飛鳥時代奈良法隆寺の「玉虫厨子」の外側にその羽が貼り付けられていたことからもうかがえます。玉虫厨子には現在ではそのほとんどが失われてしまっていますが、1万枚近くのタマムシの羽が使われていたといいます。
10月3日(火)
10月になりました。令和5年度も後半に突入です。あっという間に時間が過ぎてゆきます。若いころには時のたつのが遅く感じられて、学校から解放されて早く大人になりたいとあれほど思っていたのに、今では1年なんて瞬く間に終わってしまいます。気を引き締めていかないと、何もしないまま時だけがいたずらに過ぎ去ってゆきます。
この年齢とともに時が経過する速度が速くなる現象を、「ジャネーの法則」というそうです。生涯のある時期における時間の心理的長さは、年齢に反比例するというものです。時の長さは1秒、1日、1年とすべての人が同じであるはずなのに、主観的に記憶される時の長さは幼少期には長く年配者には短く感じられます。
 今月の木喰仏は、馬頭観音菩薩像です。馬頭観音は六観音の一つに数えられ、六道の中で畜生道に迷う人々を救済してくれます。また馬をはじめとする家畜の安全と健康を祈ったり、旅の道中を守る観音様としても信仰されました。昔は武家や農民にとって、馬は生活の一部となっており、馬を供養する仏としても信仰されました。木喰上人特有の放射状頭光をもち、総髪と一体化したような衣文が特徴的です。頭の上に馬の頭がありますが、これは衆生の煩悩を食い尽くすことを表現しています。
今月の木喰仏は、馬頭観音菩薩像です。馬頭観音は六観音の一つに数えられ、六道の中で畜生道に迷う人々を救済してくれます。また馬をはじめとする家畜の安全と健康を祈ったり、旅の道中を守る観音様としても信仰されました。昔は武家や農民にとって、馬は生活の一部となっており、馬を供養する仏としても信仰されました。木喰上人特有の放射状頭光をもち、総髪と一体化したような衣文が特徴的です。頭の上に馬の頭がありますが、これは衆生の煩悩を食い尽くすことを表現しています。
9月28日(木)
暑い暑いとは言いながらもう9月も末です。植物も子孫を残すため懸命の努力をしています。自分ではじけて種をまき散らしたり、風の力で遠くに飛んでいったり、鳥に食べられフンと一緒に種を落としてもらうものなどさまざまです。
 「ひっつきムシ」、「くっつきムシ」と俗称される植物の一群があります。子孫を広範囲に広げるために、表面にトゲや粘着力で種を人間の衣服や動物の毛につきやすくして運んでもらうタイプの植物です。博物館周辺ではセンダングサ類、イノコヅチ、ミズヒキ、チカラシバがみられます。枯れ始めるこれからの季節は草むらを歩くときには注意が特に必要です。
「ひっつきムシ」、「くっつきムシ」と俗称される植物の一群があります。子孫を広範囲に広げるために、表面にトゲや粘着力で種を人間の衣服や動物の毛につきやすくして運んでもらうタイプの植物です。博物館周辺ではセンダングサ類、イノコヅチ、ミズヒキ、チカラシバがみられます。枯れ始めるこれからの季節は草むらを歩くときには注意が特に必要です。
 私の生まれた地域(山梨市西保)では、子供のころは特にセンダングサ類を「コジキ」と呼んでいました。「ばか」や「どろぼう」と呼ぶ地域もあるようです。洋服やズボンにこれらがたかって(くっついて)いると、「コジキ」がたかっているとからかわれたりしました。男子はこの「コジキ」の投げっこをして校庭中を駆け回って遊んでいました。朝晩が冷え込むころ、「コジキ」の集合種は一つひとつの種がばらけて分離し、服から取り去るのに苦労をした経験があります。この「コジキ」というのは、大人になって一般的な呼称ではないとわかりました。衣服に引っ付くもの≒ヒトにたかるもの(ひと)➡乞食という発想から生まれた限られた地域的な俗称であると思われます。
私の生まれた地域(山梨市西保)では、子供のころは特にセンダングサ類を「コジキ」と呼んでいました。「ばか」や「どろぼう」と呼ぶ地域もあるようです。洋服やズボンにこれらがたかって(くっついて)いると、「コジキ」がたかっているとからかわれたりしました。男子はこの「コジキ」の投げっこをして校庭中を駆け回って遊んでいました。朝晩が冷え込むころ、「コジキ」の集合種は一つひとつの種がばらけて分離し、服から取り去るのに苦労をした経験があります。この「コジキ」というのは、大人になって一般的な呼称ではないとわかりました。衣服に引っ付くもの≒ヒトにたかるもの(ひと)➡乞食という発想から生まれた限られた地域的な俗称であると思われます。
9月25日(月)
朝、湯之奥金山博物館の駐車場に、セミが裏返しになって落ちているのに気が付きました。ミンミンゼミです。まだ生きています。夜露に当たって羽根が濡れて飛べなくなったのか、寿命が力尽きようとしていたのかわかりませんが、拾い上げてみると、手足を動かし羽根を勢いよくばたつかせています。駐車場内に生きた状態のミンミンゼミが今朝は計3匹いましたが、隅の枯葉の中にはミンミンゼミの死骸が10匹以上いることに気づきました。この中にアブラゼミやニイニイゼミはいません。いつのまにかこれらの種類はいなくなってしまっています。
 博物館で昨日と今日の両日で声を聞くことができた聞こえたセミは、ミンミンゼミ、ツクツクホーシのみでした。セミの声より草むらの中からは、コオロギやウマオイなど数種の虫の音が目立ってきました。ここ2、3日朝は涼しくなりましたね。気が付くとやっと秋の気配が感じられるようになりました。
博物館で昨日と今日の両日で声を聞くことができた聞こえたセミは、ミンミンゼミ、ツクツクホーシのみでした。セミの声より草むらの中からは、コオロギやウマオイなど数種の虫の音が目立ってきました。ここ2、3日朝は涼しくなりましたね。気が付くとやっと秋の気配が感じられるようになりました。
9月24日(日)
身延町内には15か所の郵便局があります。このうち3か所は簡易郵便局です。これらの郵便局のうち6郵便局に風景印があります。風景印は郵便局の消印の一種で、局名と押印年月日欄と共に、局周辺の名所旧跡等に由来する図柄が描かれています。その地域のことを知るには、うってつけの素材です。大学時代の友人に郵趣界では著名なコレクター兼研究者がおり、5月に博物館を訪問してくれた際にも風景印を複数ゲットしていました。これはいつかこのブログでも使えるかなと思い、今回集めてみましたので紹介します。
 下部郵便局の風景印は、温泉街の街並みと背後の山々、それに温泉マークに武田菱が配されています。鎌倉時代以前にさかのぼる歴史ある温泉は、武田信玄公の隠し湯としても知られています。身延山局と身延局は宗紋の枠内に身延山久遠寺の建物が配された同じ図柄で、古関局と久那土局も同じで木喰仏と本栖湖からの富士山、切石局は句碑の里がデザインされています。
下部郵便局の風景印は、温泉街の街並みと背後の山々、それに温泉マークに武田菱が配されています。鎌倉時代以前にさかのぼる歴史ある温泉は、武田信玄公の隠し湯としても知られています。身延山局と身延局は宗紋の枠内に身延山久遠寺の建物が配された同じ図柄で、古関局と久那土局も同じで木喰仏と本栖湖からの富士山、切石局は句碑の里がデザインされています。

9月19日(火)
一昨日、三連休の中日とあって朝からたくさんの親子連れの方々が、砂金掘り体験をしてくれました。ゴールデンウィークの一番忙しい時と同じくらいの混みようです。500人弱の人が砂金掘りを体験しました。
このなかに小中高の同級生だった女の人が訪ねて来てくれました。改姓をしているので名前を言われても最初は誰だかわかりませんでしたが、なんと私の初恋のマドンナだった人でした。県外から思いがけない再会にびっくりするとともに、約50年ぶりの再会に青春時代の思い出話に花が咲きました。
この館に来てからわずかの間に、何人かの幼馴染や同級生と再会でき旧交を温めることができたのは非常にありがたいことです。
9月17日(日)
昨日から「発掘された日本列島」2023の巡回展が、山梨県立考古博物館ではじまりました。中山金山と黒川金山の甲斐金山遺跡も、県内の国指定史跡のひとつとしてパネルで紹介しています。
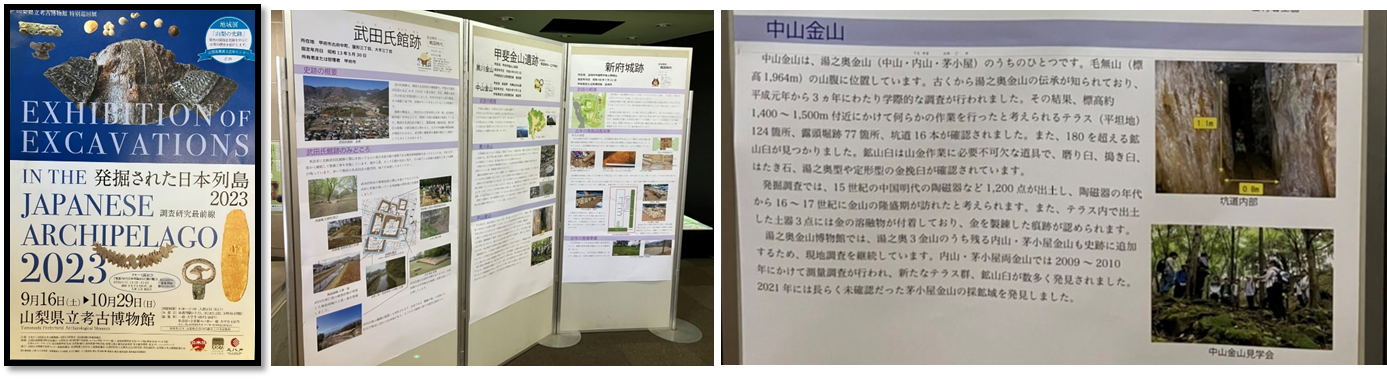 今回の展示品中、埼玉県加須市騎西城跡の発掘資料の中に「上」の字が刻まれた蛭藻金(ひるもきん)、切金、露金と金箔を施した馬鎧や兜の前立てがありました。騎西城は北条氏の最前線の城で、武田信玄が北条氏康と同盟し上杉方となった松山城を攻略した時、救援に間に合わなかった謙信がこの騎西城を攻略し焼き払っています。
今回の展示品中、埼玉県加須市騎西城跡の発掘資料の中に「上」の字が刻まれた蛭藻金(ひるもきん)、切金、露金と金箔を施した馬鎧や兜の前立てがありました。騎西城は北条氏の最前線の城で、武田信玄が北条氏康と同盟し上杉方となった松山城を攻略した時、救援に間に合わなかった謙信がこの騎西城を攻略し焼き払っています。
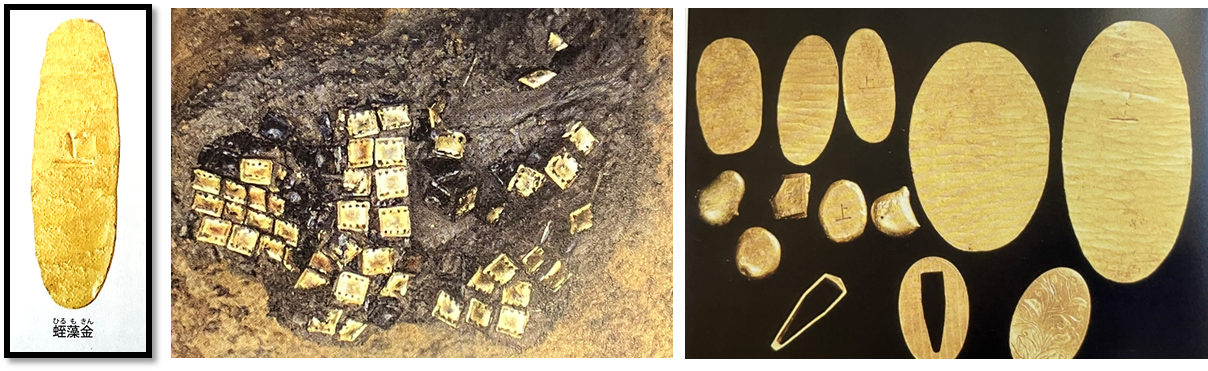 「上」の字の刻印のある金は、笛吹市の甲州金大判や諏訪大社秋宮の蛭藻金や碁石金にもみられます。金箔を施した馬鎧は武田氏館跡からも出土しており、皮に黒漆を塗り表に金箔を貼って四角い小札とし、それらを布に縫い付けたものです。
「上」の字の刻印のある金は、笛吹市の甲州金大判や諏訪大社秋宮の蛭藻金や碁石金にもみられます。金箔を施した馬鎧は武田氏館跡からも出土しており、皮に黒漆を塗り表に金箔を貼って四角い小札とし、それらを布に縫い付けたものです。
また、金関係では、岡山県佐良山古墳群の鍍金された単鳳環頭大刀の柄頭、奈良県郡山城跡の金箔軒丸瓦、軒平瓦があります。
東日本では唯一、山梨県としては2回目、27年ぶりの展示会です。全国的に話題と注目を集めた10遺跡を取り上げた速報展示ですので、全国の新発見の発掘調査成果を間近に観察してみてはいかがでしょうか。
9月15日(金)
昨日、甲府市立東小学校の児童45人が見学と砂金掘り体験にきてくれました。東小学校は甲府盆地の中央部に位置していますが、盆地底部の中では微高地状になっていて縄文時代から平安時代にかけての朝気遺跡(あさけいせき)があります。かつて下水管の埋設や校舎の改築に伴って、初代谷口館長や私も発掘調査を実施したことを思い出します。弥生時代の合わせ口壺棺墓や古墳時代の水路跡、平安時代の馬の埋葬跡、各時期の竪穴住居跡が、度重なる洪水砂の堆積とともに何層にもわたって検出されています。特に低湿地帯であったため木製品などの依存状況が良く、下駄、櫛、機織り機の一部、籠、ヒョウタンなどが発見されました。
 学校のある現在の地名は、朝気(あさけ)一丁目になります。酒折の宮にヤマトタケルノミコトが立ち寄ってしばらく滞在した時、南の方の村に朝餉(あさげ)の朝食準備の煙が見えたことが、朝気の地名の由来だと伝えられています。やや高台となっている酒折の宮からは、直線距離で2キロ弱です。
学校のある現在の地名は、朝気(あさけ)一丁目になります。酒折の宮にヤマトタケルノミコトが立ち寄ってしばらく滞在した時、南の方の村に朝餉(あさげ)の朝食準備の煙が見えたことが、朝気の地名の由来だと伝えられています。やや高台となっている酒折の宮からは、直線距離で2キロ弱です。
9月14日(木)
市川三郷町には山梨県天然記念物に指定されている「一瀬クワ」があります。明治時代に一瀬益吉が購入した桑苗の中から発見した原木で、葉が大きく収量が際立って多いものです。この原木から採取した苗は、自己桑園のほか村内や近隣の村にも配布し、西八代郡農会や蚕糸品評会山梨県支部にも出品されました。桑の収穫量の多さと、葉質ともに肉厚で抜群であることが認められ、優等賞が授与されて注目を集めました。後にこの苗木が全国に普及することになります。
この桑苗には性質の異なる二つの種類があり、落葉後の枝が青灰色のものと赤みを帯びているものとで、一瀬の青木(白木)、赤木と呼ばれています。これらの原木は、農林水産省では全国の共通名を「一ノ瀬」とすることに統一しましたが、山梨県では一瀬氏の功績をたたえ「一瀬クワ」と表記し、両原木を山梨県天然記念物に指定し保護しています。
 「甲斐絹」、「甲州財閥」、「製糸業」など、山梨県における養蚕と製糸業の興隆の歴史を生み出した原動力の遺産のひとつです。
「甲斐絹」、「甲州財閥」、「製糸業」など、山梨県における養蚕と製糸業の興隆の歴史を生み出した原動力の遺産のひとつです。
9月10日(日)
砂金採り体験室の北東の山裾部分にガラス窓越しに、黄色い花がチラホラと見えています。何だと思って近づいてみると、ヤマブキの花でした。4月の本来の開花時期の花とは違って、弱弱しく勢いがありませんが、8月末ごろから一部再開花しているようです。咲いているヤマブキは先端部分の花のみのものが多く、初秋のヤマブキもまた風情があっていいものですね。
 開花が終わった後の時季外れの季節に咲いた花を「狂い咲き」とか「返り咲き」といいます。「返り咲き」は、相撲などで一度失った地位(番付)に戻るときに、復活の意味で使うことが多いですね。博物館周辺にはたくさんヤマブキが自生しています。ヤマブキの群落の中には何本かに1本の割合で、二度目の狂い咲きの花をつけています。なお、春の花についた実は黒くなっているのもあります。
開花が終わった後の時季外れの季節に咲いた花を「狂い咲き」とか「返り咲き」といいます。「返り咲き」は、相撲などで一度失った地位(番付)に戻るときに、復活の意味で使うことが多いですね。博物館周辺にはたくさんヤマブキが自生しています。ヤマブキの群落の中には何本かに1本の割合で、二度目の狂い咲きの花をつけています。なお、春の花についた実は黒くなっているのもあります。
 山吹の花言葉は、「金運」「気品」「崇高」です。「金運」の花言葉は、深い谷底に落ちた小判が、ヤマブキの花になったという言い伝えから生まれたそうです。山吹の花は明るい黄色で、黄金をイメージすることから納得できますね。(4/11、6/8記事参照)
山吹の花言葉は、「金運」「気品」「崇高」です。「金運」の花言葉は、深い谷底に落ちた小判が、ヤマブキの花になったという言い伝えから生まれたそうです。山吹の花は明るい黄色で、黄金をイメージすることから納得できますね。(4/11、6/8記事参照)
9月7日(木)
明日9月8日は「桑の日」だそうです。9(く)と8(わ)のごろ合わせから、この日が制定されたものです。クワの語源は、蚕の「食う葉」が短縮したもの、「蚕葉(こは)」がなまったものなどの諸説があります。
 湯之奥金山博物館入口の下部川の橋を渡った山際やリバーサイドパーク内にも、クワの木が何本か残っています。かつて盛んだった養蚕業がしのばれます。下部町誌によれば、江戸時代中期ごろから栽培が開始され、コメなどの主要な作物とは別に大きなウェイトを占める作物に成長していったようです。桑園の面積は昭和40年代半ばから急速に減少し、今ではほとんど見られません。
湯之奥金山博物館入口の下部川の橋を渡った山際やリバーサイドパーク内にも、クワの木が何本か残っています。かつて盛んだった養蚕業がしのばれます。下部町誌によれば、江戸時代中期ごろから栽培が開始され、コメなどの主要な作物とは別に大きなウェイトを占める作物に成長していったようです。桑園の面積は昭和40年代半ばから急速に減少し、今ではほとんど見られません。
 クワは強い植物で、年二回の収穫が可能です。枝を切っても幹を伐採しても、再び枝を伸ばして葉を茂らせます。妻の実家の身延町常葉の畑にも、過去の遺産と思われる桑が生えています。葉の抉れている部分が深いものです。通勤途中の市川三郷町の道路の植栽帯や歩道にも、桑の木が大きく枝を伸ばしています。植栽は8月7日の神明の花火大会の前に剪定されて形を整えられているのですが、クワの木の成長が早いため植栽の中から枝が繁茂しています。生命力の強さに驚かされます。また、同町内に桑園があり養蚕用ではなく桑の葉茶用の栽培だそうです。
クワは強い植物で、年二回の収穫が可能です。枝を切っても幹を伐採しても、再び枝を伸ばして葉を茂らせます。妻の実家の身延町常葉の畑にも、過去の遺産と思われる桑が生えています。葉の抉れている部分が深いものです。通勤途中の市川三郷町の道路の植栽帯や歩道にも、桑の木が大きく枝を伸ばしています。植栽は8月7日の神明の花火大会の前に剪定されて形を整えられているのですが、クワの木の成長が早いため植栽の中から枝が繁茂しています。生命力の強さに驚かされます。また、同町内に桑園があり養蚕用ではなく桑の葉茶用の栽培だそうです。
 下部川沿いにあるクワの葉は丸くなっています。クワの葉は、同じ枝に丸い葉と抉れのあるものが一緒にあって、老木になった木が必ずしも丸くなるのではないようです。(7/2、8/27記事参照)
下部川沿いにあるクワの葉は丸くなっています。クワの葉は、同じ枝に丸い葉と抉れのあるものが一緒にあって、老木になった木が必ずしも丸くなるのではないようです。(7/2、8/27記事参照)
9月3日(日)
9月1日の防災の日と防災週間(8/30~9/5)に合わせて、午前中に博物館駐車場で消防訓練がありました。身延町消防団の方々によるポンプでの放水訓練です。火災や緊急災害時に、私たちの命と財産を守ってくれる頼もしい消防団のかたがたに敬礼です。
 博物館のエントランスは開放的な空間です。そのため意外な侵入者(訪問者)に驚かされます。27日に中山金山から帰った時、私の席の後ろの壁際にサワガニがいました。どの入口からにしてもかなりの距離になります。壁伝いに迷って入り込んでしまったのでしょうか。
博物館のエントランスは開放的な空間です。そのため意外な侵入者(訪問者)に驚かされます。27日に中山金山から帰った時、私の席の後ろの壁際にサワガニがいました。どの入口からにしてもかなりの距離になります。壁伝いに迷って入り込んでしまったのでしょうか。
 また、先日は売店エリアにトカゲがいるではないですか。職員とともに捕まえて外に追い出そうとしましたが、商品棚の下に逃げ込んでしまいました。人がいなくなった後、無事脱出できたのでしょうか。
また、先日は売店エリアにトカゲがいるではないですか。職員とともに捕まえて外に追い出そうとしましたが、商品棚の下に逃げ込んでしまいました。人がいなくなった後、無事脱出できたのでしょうか。
8月31日(木)
南巨摩地域に「ナラ枯れ」の被害が深刻です。「ナラ枯れ」は、ナラ、シイ、カシなどのドングリの木が病原菌のまん延によって枯れる被害です。病原菌はカビの仲間で、カシノナガキクイムシが媒介し、被害木の根元に木屑が落ちているのが特徴です。五月の醍醐山一斉登山の時にはかなり顕著に見られ、先日の中山金山に行く途中の登山道沿いにも夏なのに枯葉になっている木が何本もありました。今年若葉が出た後に、急激に枯れたことがうかがえます。マツクイムシ同様に山々の木にとっては深刻な被害になっています。

8月28日(月)
8月26・27日の2日間、日本地球科学教育普及協会主催、甲斐黄金村・湯之奥金山博物館共催で甲斐黄金村湯之奥金山地学実習が行われました。最近世界的に中等教育での地学履修者の減少が叫ばれ、草の根的に地球科学の普及を図るために始まったイベントだそうです。若い世代に地学の興味と、産業とのつながりの歴史を学ぶ機会を提供し、地球科学の普及を図ることをめざしているとのことです。
初日は午後から博物館脇にある下部川の河川敷実習で岩石や砂を観察し、昨日は中山金山遺跡の現地見学でした。山梨県身延地域は南部フォッサマグナの断層が通る重要な地域なので、湯之奥金山の形成過程から日本列島の成り立ちを考える雄大な視点での考察ができるそうです。
最近山梨県内でも熊の目撃情報や居住地への出没など何かと話題になっているので、出発時に爆竹を鳴らし途中では笛を随時鳴らして、熊に対し人間の存在をアピールし危険を回避しながら登りました。今回は健脚の若い中高生が対象であり、時間配分的にはスムーズに現地に到着できました。金山の史跡エリア内ではドローンを使って現地を見学しているようすを撮影し、新しい視点での記録映像が撮れたようです。また、第2地蔵峠では真正面に富士山の姿が雲間から顔を出し、小俣さんの地球規模の話に聞き入っていました。中山金山跡では小松学芸員が金山遺跡全体の概要を説明し、それぞれの地点ではそのエリアの使われ方や石臼、石造物、石垣、炭窯などの個別に解説しました。
 湯之奥金山から日本列島の成り立ちを見るという広い視野を再認識するとともに、若者の知識欲、頭の柔軟性などに触れることができました。
湯之奥金山から日本列島の成り立ちを見るという広い視野を再認識するとともに、若者の知識欲、頭の柔軟性などに触れることができました。
8月27日(日)
人間は歳を取ると丸くなるとよくいわれます。樹木も年を重ねると葉が丸くなるものがあります。ヒイラギの木はその葉に棘(トゲ)があり、節分にはこの枝にイワシの頭を刺して家の入口に飾り、災厄が家に入ってこないようにする風習があります。触れると痛いヒイラギの棘と焼いたイワシの独特の臭気によって、邪鬼を払うとのことです。このヒイラギの葉は、老木になると棘が無くなり全縁の葉になっていきます。この左端の写真の木は、同じ1本の木なのに両方の葉の特徴がみられます。
 また、クリスマスツリーに使われるモミの木も、先端にある棘状の部分が若木と老木では異なります。若木の葉は手で触れるとチクチクして痛みを感じますが、樹高がある程度伸びているものでは葉先が丸くなっていて痛くありません。常緑樹のこれらの木は、葉を食料とする草食動物から身の守るための護身術・防衛手段として、葉先の棘を獲得したものと考えられます。
また、クリスマスツリーに使われるモミの木も、先端にある棘状の部分が若木と老木では異なります。若木の葉は手で触れるとチクチクして痛みを感じますが、樹高がある程度伸びているものでは葉先が丸くなっていて痛くありません。常緑樹のこれらの木は、葉を食料とする草食動物から身の守るための護身術・防衛手段として、葉先の棘を獲得したものと考えられます。

8月24日(木)
湯之奥金山博物館入口では、木喰上人作の仏像のレプリカ像が皆様をお迎えしてくれています。木喰上人は、江戸時代中期に甲斐国丸畑村(現身延町古関丸畑)に生まれ、出家して木食戒を受け、全国各地を修行しながら千体を超える仏像を制作しています。その仏さまの表情は独特の微笑をたたえていることから、微笑仏として庶民に親しまれてきました。
 今月の木喰さんは、如意輪観音菩薩像です。「如意」とは意のままに智慧や財宝、福徳をもたらす如意宝珠という宝の珠のことで、「輪」は法輪を指し釈迦の説いた教えを車輪にたとえたものです。 本来その2つを手に持った観音菩薩ということで如意輪観音といいます。
今月の木喰さんは、如意輪観音菩薩像です。「如意」とは意のままに智慧や財宝、福徳をもたらす如意宝珠という宝の珠のことで、「輪」は法輪を指し釈迦の説いた教えを車輪にたとえたものです。 本来その2つを手に持った観音菩薩ということで如意輪観音といいます。
8月20日(日)
通勤途中の久那土地区や常葉地区に、昭和時代のレトロ感を漂わせているホーロー看板やブリキ看板があります。ホーロー看板は、金属に光沢のある塗装で仕上げられた屋外用看板です。身延町内の旧商店街もかなりの割合で店をたたみ、色あせた看板のみがかつての賑わいの痕跡をわずかにとどめています。マツダランプの看板は久那土の電柱と、ハイキングコースの毛無山登山道の中山金山の七人塚跡にあります。毛無山のタイプのものは各地に同様のものが設置されており、現在でも道標や目印として活躍しており、高い耐久性が証明されています。マツダランプはわが国初の電球を製作した会社で、現在は「東芝ランプ」として東芝ライテック(株)に引き継がれています。ちなみにこの「マツダ」という名前は、松田さんという創業者や発明者の名前ではなくてゾロアスター教の主神で善と光明の神、アウラ・マツダに由来するんだとか。
 大村崑のオロナミンCやスプライトの看板は、退色や錆が進んでいて原型さえ推測が難しくなっています。タバコや塩の看板はさすがに専売公社から支給されたものと推測されるので、今でもしっかりした作りとなっています。
大村崑のオロナミンCやスプライトの看板は、退色や錆が進んでいて原型さえ推測が難しくなっています。タバコや塩の看板はさすがに専売公社から支給されたものと推測されるので、今でもしっかりした作りとなっています。
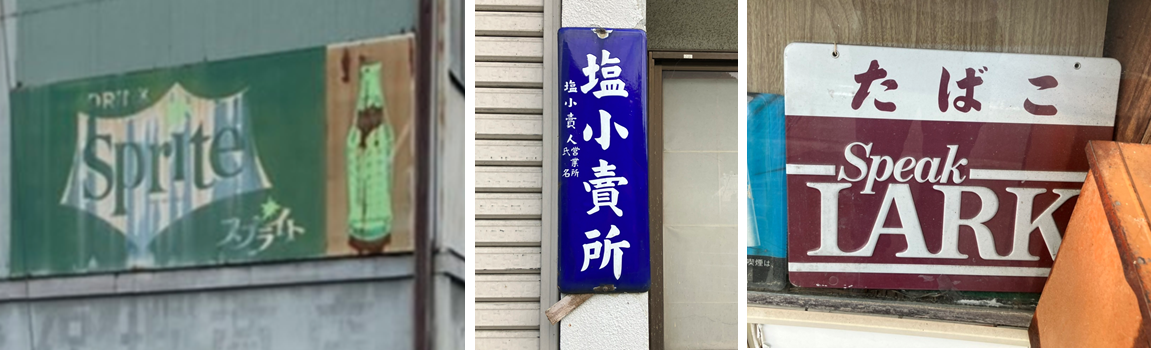
8月14日(月)
11日に実施した「おやこ金山探検隊」で、登山道途中の山の神の休憩地点に小さいマムシがいました。長さ30センチほどで、頭は三角形に近く、体には特徴的な銭形文様があります。大勢の人に発見されて素早く逃げて動き回っていたため、なかなかいいアングルの写真が撮れませんでした。
 約30年前の中山金山の発掘調査をしていた時、夏場に精錬場での泊まり込みでのテント生活だったのですが、地元の方々が食糧などを荷揚げしてくれていました。この時にお手伝いいただいた方の話では、登山道中にマムシがよく出没するのでこれを捕獲して売るといいこづかい稼ぎになったとの話を思い出しました。生きたマムシは滋養強壮の薬として焼酎漬けにされて需要があり、かなり高額で取引されていたと聞いています。
約30年前の中山金山の発掘調査をしていた時、夏場に精錬場での泊まり込みでのテント生活だったのですが、地元の方々が食糧などを荷揚げしてくれていました。この時にお手伝いいただいた方の話では、登山道中にマムシがよく出没するのでこれを捕獲して売るといいこづかい稼ぎになったとの話を思い出しました。生きたマムシは滋養強壮の薬として焼酎漬けにされて需要があり、かなり高額で取引されていたと聞いています。
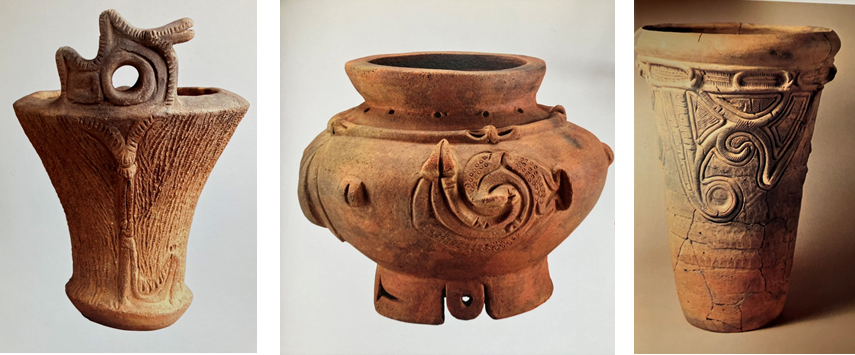 二ホンマムシは猛毒を持ち、かまれると命を落とすこともある恐ろしい毒蛇です。蛇は古来から山の神の使いで、縄文時代にはその強さと生命力、脱皮と冬眠からの再生能力などから不思議な力を持つ畏敬の対象として考えられていました。そのため縄文時代中期の縄文土器には蛇体モチーフが多用されています。特に山梨県と長野県諏訪地方を中心とする地域に独特の文化圏を形成し、ヘビ、カエル、イノシシなどの生き物がいろいろな土器の文様に融合して見え隠れしています。
二ホンマムシは猛毒を持ち、かまれると命を落とすこともある恐ろしい毒蛇です。蛇は古来から山の神の使いで、縄文時代にはその強さと生命力、脱皮と冬眠からの再生能力などから不思議な力を持つ畏敬の対象として考えられていました。そのため縄文時代中期の縄文土器には蛇体モチーフが多用されています。特に山梨県と長野県諏訪地方を中心とする地域に独特の文化圏を形成し、ヘビ、カエル、イノシシなどの生き物がいろいろな土器の文様に融合して見え隠れしています。
 身延町お宮横遺跡出土の土器の文様にも蛇体を表しているモチーフがみられ、口縁部にはヘビの胴体から尾を示す渦巻き文、胴部に蛇体をくねらしている姿が確認できます。
身延町お宮横遺跡出土の土器の文様にも蛇体を表しているモチーフがみられ、口縁部にはヘビの胴体から尾を示す渦巻き文、胴部に蛇体をくねらしている姿が確認できます。
8月13日(日)
11日の山の日の休日、博物館では第23回激烈☆親子金山探検隊を開催しました。晴れの天気に恵まれ、親子12名、協力スタッフ5名、事務局5名の総勢22名の部隊です。出発式の後、ジオラマ展示室で金山の現地でのかつてのようすの事前学習をして、町のバスで登山口まで移動。準備体操、日程説明、注意事項の確認の後、登山開始。猛暑が続いている下界とは異なり、登山道の空気は清涼で気持ちがいいくらいでした。しかし斜度がきつくなる金山跡前後になると、汗もだらだら吹き出してきました。やっぱり夏です。精錬場入口、大名屋敷を通って、新地蔵峠で昼食休憩。残念ながら富士山は雲がかかっており眺望はお預けで、わずかにすそ野部分のみ確認できたにすぎませんでした。この後、登山道から道なき斜面を30分歩ほど登り、標高1600メートル付近の坑道域に到着しました。坑道群はかなりの部分に土砂等が流入していましたが、保存状況の良いいくつかの坑道には参加した親子も直接入ってみて、坑道のようすを観察することができました。坑道からは涼しい風を感じることができました。その後来た道を少し引き返し、精錬場跡で炭焼き窯跡、鉱石をすりつぶす石臼やテラスを安定させる石垣を確認し、学芸員から説明を聞いて当時のようすに思いをはせながら下山しました。
 この親子金山探検隊に合わせて、七人塚、精錬場跡、Bテラスの三か所の倒れてしまっている説明板を協力スタッフの応援をお借りして立て直しました。
この親子金山探検隊に合わせて、七人塚、精錬場跡、Bテラスの三か所の倒れてしまっている説明板を協力スタッフの応援をお借りして立て直しました。
 博物館に戻ってからは少しの休憩の後、純銀の地金を使った「甲州金」を、自分の気に入ったデザインで作ってみました。朝早くから丸一日がかりで、中山金山の金鉱石を採掘した坑道の中に入って探検し、作業場のようすを景観や地形とともに確認し、記念品を自分の手で作成しました。ホントに疲れたけれども、一生の思い出に残る経験ができたと思います。
博物館に戻ってからは少しの休憩の後、純銀の地金を使った「甲州金」を、自分の気に入ったデザインで作ってみました。朝早くから丸一日がかりで、中山金山の金鉱石を採掘した坑道の中に入って探検し、作業場のようすを景観や地形とともに確認し、記念品を自分の手で作成しました。ホントに疲れたけれども、一生の思い出に残る経験ができたと思います。
10日(月)
博物館と下部リバーサイドパークの看板や公衆トイレの内外ともに、落書きやいたずら書きは皆無です。ひと昔前には、至る所に落書きがありましたが、下部温泉駅のトイレやホームでもまったく見ることができませんでした。温泉観光地なのできれいにしているだけではなく、訪れる方々のマナーも向上している結果だとおもいます。いくら探してもないのには、正直驚きました。
 しかし、温泉街の一部の道路壁面や熊野神社の板壁には、少し時間の経過した平成や昭和時代の落書きがありました。相合傘、ドラえもん、ピカチュウのほか、訪れた記念日や名前などを記したものです。
しかし、温泉街の一部の道路壁面や熊野神社の板壁には、少し時間の経過した平成や昭和時代の落書きがありました。相合傘、ドラえもん、ピカチュウのほか、訪れた記念日や名前などを記したものです。
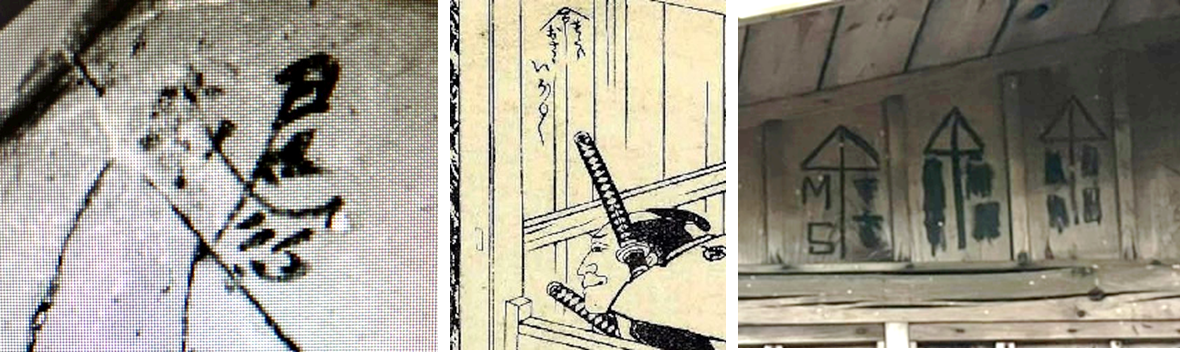 相合傘は、昔から落書きの定番でした。この相合傘の落書きは、江戸時代の「北斎漫画」にも便所の壁に描かれていることから、200年以上の歴史があります。かつて平城宮から出土した土器に「我、君、念」の三字を合わせた墨書がみられ、「君我を念い、我君を念う」と推測されて、相合傘に通じるまじないと解釈されていました。しかし、これは逆に夫婦の離別に関わる呪符として用いられたものだと後にわかりました。
相合傘は、昔から落書きの定番でした。この相合傘の落書きは、江戸時代の「北斎漫画」にも便所の壁に描かれていることから、200年以上の歴史があります。かつて平城宮から出土した土器に「我、君、念」の三字を合わせた墨書がみられ、「君我を念い、我君を念う」と推測されて、相合傘に通じるまじないと解釈されていました。しかし、これは逆に夫婦の離別に関わる呪符として用いられたものだと後にわかりました。
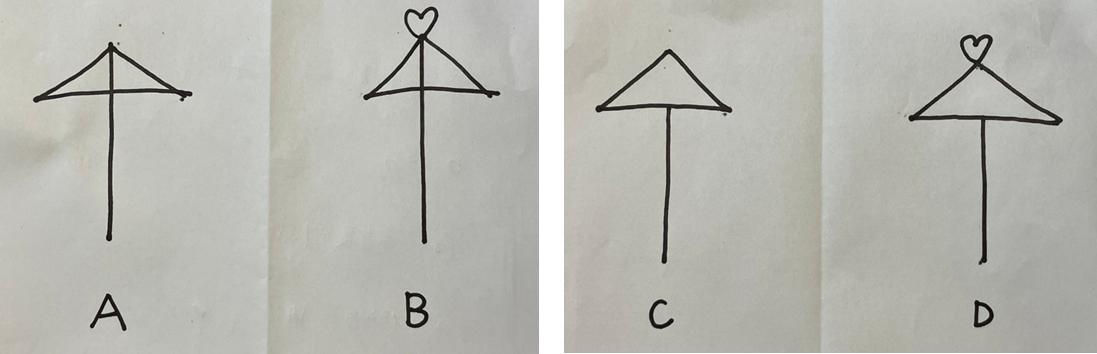 今みなさん相合傘を描いてみてください。相合傘は年代によって、描き方が異なるだけでなく、意味も真逆になっているのです。これは地域性や時代によって微妙な若干のズレがあるので、おおかたの傾向としてとらえてください。私や50才代以上の人が描くのはAです。三角形の頂点から傘を突き抜けて真ん中の線が来て、その両側に自分の名前と思う人の名前を書いて相思相愛になることを祈るまじないです。これにハートがつくBや傘が突き抜けないでハートがつかないCは40才代,傘が突き抜けないでハートの付くDは20代以下です。当館の職員の年代別描き方にこのような差が出ました。Aは30代以下の人には別れ傘として、付き合っている人の離別を願う意味のまじないであるそうです。さらに、思う人の気持ちがこちらに向かうように傘を自分の名前のほうに軸を傾けたり、握り手部分の「J」の部分を追加して自分側に向けたという例もあったそうです。
今みなさん相合傘を描いてみてください。相合傘は年代によって、描き方が異なるだけでなく、意味も真逆になっているのです。これは地域性や時代によって微妙な若干のズレがあるので、おおかたの傾向としてとらえてください。私や50才代以上の人が描くのはAです。三角形の頂点から傘を突き抜けて真ん中の線が来て、その両側に自分の名前と思う人の名前を書いて相思相愛になることを祈るまじないです。これにハートがつくBや傘が突き抜けないでハートがつかないCは40才代,傘が突き抜けないでハートの付くDは20代以下です。当館の職員の年代別描き方にこのような差が出ました。Aは30代以下の人には別れ傘として、付き合っている人の離別を願う意味のまじないであるそうです。さらに、思う人の気持ちがこちらに向かうように傘を自分の名前のほうに軸を傾けたり、握り手部分の「J」の部分を追加して自分側に向けたという例もあったそうです。
このように落書き一つをとっても、時代による形の変化と意味の付加や逆転があり、歩んできた歴史があるのです。
8月7日(月)
今日は館長による夏休み自由研究の相談室の日です。入口のホールの一角に特設の相談コーナーをスタッフが用意してくれていました。岩石鉱物標本、身延町内出土の縄文土器や石器、昆虫や花の写真パネルなど、夏休みの宿題の自由研究のヒントになる資料が飾られて雰囲気を作っています。
 遠方から来館された小学生の家族連れが縄文土器に引き寄せられて相談に来られ、縄文土器に直接触れて感激してくれたのをはじめ、信玄堤の工事や合戦の城攻めで金山衆の土木技術が使われていたことへの関心、麓金山の状況など、歴史に関する相談や質問が多かったようです。子供だけでなく同伴された大人も興味を示してくれていました。
遠方から来館された小学生の家族連れが縄文土器に引き寄せられて相談に来られ、縄文土器に直接触れて感激してくれたのをはじめ、信玄堤の工事や合戦の城攻めで金山衆の土木技術が使われていたことへの関心、麓金山の状況など、歴史に関する相談や質問が多かったようです。子供だけでなく同伴された大人も興味を示してくれていました。
8月6日(日)
当博物館の周りにある各種のアジサイの花が、一段落しました。6月の梅雨の時期にきれいに咲き誇っていたホンアジサイの青やピンク、柏葉アジサイの白、ガクアジサイの薄紫の花もほぼ枯れて、褐色に変色しています。

 我家の庭にもホンアジサイと柏葉アジサイがありますが、一昨年は剪定方法を間違えて一個も花をつけませんでした。剪定のし過ぎだったようです。どちらも旧枝咲の種類なので、花が終了後、夏のうちに翌々年の花芽になる花から2~3節目で上部を数センチ残して剪定するのが良いそうです。アジサイは成長が早く剪定をしないとやたらと伸びてしまうので、2年後に花の咲く位置や樹形を考えて切りましょう。
我家の庭にもホンアジサイと柏葉アジサイがありますが、一昨年は剪定方法を間違えて一個も花をつけませんでした。剪定のし過ぎだったようです。どちらも旧枝咲の種類なので、花が終了後、夏のうちに翌々年の花芽になる花から2~3節目で上部を数センチ残して剪定するのが良いそうです。アジサイは成長が早く剪定をしないとやたらと伸びてしまうので、2年後に花の咲く位置や樹形を考えて切りましょう。

8月3日(木)
 7月30日午前、博物館では有料入館者47万人を達成しました。東京都西東京市からお越しいただいた荒さんご一家です。博物館の駐車場では、砂金掘り大会(一般の部)の真っ最中で、にぎやかに競技が行われ右往左往している時に、このうれしいお知らせが届きました。
7月30日午前、博物館では有料入館者47万人を達成しました。東京都西東京市からお越しいただいた荒さんご一家です。博物館の駐車場では、砂金掘り大会(一般の部)の真っ最中で、にぎやかに競技が行われ右往左往している時に、このうれしいお知らせが届きました。
これまでコロナウィルス感染症の影響で外出やイベントの自粛など何かと影響のあった時期でしたが、5月からその対応が緩和され、荒さんご一家も夏休みの家族旅行で博物館に来られ、47万人目のお客様となりました。金山博物館では記念品を贈呈し、記念撮影をしました。
偶然ですが、昨年の砂金掘り大会中にも45万人目の有料入館者を迎え入れており、2年連続の同イベント中の慶事となりました。 1年間でぴったし2万人の有料入館者ということになりました。
7月31日(月)
2日間の砂金掘り大会で、参加者の皆さんが取り残した砂金はどうなったのでしょうか。それは、順次博物館友の会の皆さんが、回収をしてくれていました。スルースボックスという大掛かりな道具によって、水槽の中に残った大量の土砂の中から、流水を使って砂金を選り分けてくれていました。比重選鉱なので競技用パンニング皿と同じ理論です。山側のテントの隣の場所で実演していたのを、みなさん確認されていますか。見た目以上に、重労働で大変な作業なんですよ。金は高価なので微細な1点まで、もれなく回収していただきました。
 今回の砂金掘り大会、砂金甲子園大会が無事終了することができたのは、博物館応援団AU会、友の会の皆様のご協力があってこそ実現できたものです。大会の準備から運営及び最後の片つけまで、献身的なご協力をいただき本当にありがとうございました。
今回の砂金掘り大会、砂金甲子園大会が無事終了することができたのは、博物館応援団AU会、友の会の皆様のご協力があってこそ実現できたものです。大会の準備から運営及び最後の片つけまで、献身的なご協力をいただき本当にありがとうございました。
7月30日(日)
昨日、第23回砂金掘り大会を開催しました。中学生以下のジュニアの部と高校生以上の一般の部に分かれて、総勢195名の参加がありました。あらかじめバケツに入った砂の中に砂金を一定量仕込んで置き、制限時間内にいかに早く正確に砂金採取するかの競技です。今年はジュニアの部も一般の部も、砂金甲子園大会の出場校の生徒たちが上位を独占し、ベテランの砂金掘り師たちが誰もかなわなかったことが特徴としてあげられます。いかに学校で猛練習をしているかがわかります。砂金掘り師のベテラン陣も、若い人たちの熱気に圧倒されることなく奮起を期待します。総合優勝は桐朋学園の佐藤さん、準優勝は神戸女学院の堤さんです。佐藤さんは昨年に引き続き2連覇を達成しました。
 本日、第20回砂金甲子園!東西中高交流砂金掘り大会を行いました。参加校は桐朋学園中学・高等学校(東京都)、山梨学院中学・高等学校(山梨県)、灘中学・高等学校(兵庫県)、麻布学園中学・高等学校(東京都)、逗子開成中学・高等学校(神奈川県)、明治大学付属中野中学・高等学校(東京都)、市川学園中学・高等学校(千葉県)、西大和学園高等学校(奈良県)、大妻中学・高等学校(東京都)、神戸女学院中学部・高等学部(兵庫県)、開成学園中学・高等学校(東京都)の計11校です。
本日、第20回砂金甲子園!東西中高交流砂金掘り大会を行いました。参加校は桐朋学園中学・高等学校(東京都)、山梨学院中学・高等学校(山梨県)、灘中学・高等学校(兵庫県)、麻布学園中学・高等学校(東京都)、逗子開成中学・高等学校(神奈川県)、明治大学付属中野中学・高等学校(東京都)、市川学園中学・高等学校(千葉県)、西大和学園高等学校(奈良県)、大妻中学・高等学校(東京都)、神戸女学院中学部・高等学部(兵庫県)、開成学園中学・高等学校(東京都)の計11校です。
 学校対抗の優勝校は灘中学・高等学校、準優勝は初参加の神戸女学院中学部・高等学部、3位は逗子開成中学・高等学校でした。非常にレベルが高く1位と2位は同点で、わずかなタイム差で順位が決まりました。最優秀選手賞は山梨学院の今泉さん、新人賞は明大中野の山田さんでした。熱中症警戒アラートが発令されている暑い中、熱の入った熱い戦いが繰り広げられました。
学校対抗の優勝校は灘中学・高等学校、準優勝は初参加の神戸女学院中学部・高等学部、3位は逗子開成中学・高等学校でした。非常にレベルが高く1位と2位は同点で、わずかなタイム差で順位が決まりました。最優秀選手賞は山梨学院の今泉さん、新人賞は明大中野の山田さんでした。熱中症警戒アラートが発令されている暑い中、熱の入った熱い戦いが繰り広げられました。

7月24日(月)
NHK朝ドラの「らんまん」で、主人公の万太郎が「雑草という名前の草はない。」「すべての草に名があり役割があると」と語られていました。どんな植物にもそれぞれ固有の名前があります。牧野富太郎博士の名言として知られていますが、この言葉は、山本周五郎が牧野博士に雑誌のインタビューをした時「雑草」という言葉を口にしたところ、「きみ、世の中に雑草という草はない。どんな草だってちゃんと名前がついている。私は雑木林(ぞうきばやし)という言葉が嫌いだ。松、杉、ナラ、カエデ、クヌギ、…みんなそれぞれ固有名詞がついている。それを多くの人々が“雑草”だの“雑木林”だのと無神経な呼び方をする。もし君が“雑兵”と呼ばれたら、いい気がするか。人間にはそれぞれ固有の姓名がちゃんとあるはず。人を呼ぶ場合には、正しくフルネームできちんと呼んであげるのが礼儀じゃないかね。」とたしなめたそのくだりの由来が示されています。(木村久邇典『周五郎に生き方を学ぶ』)
ちなみに、山本周五郎は山梨県大月市出身の作家です。大河ドラマにもなった「樅ノ木は残った」や映画「赤ひげ」の作者で、売れる前に雑誌の記者をしていました。
「雑草」とは、人間社会に農耕や景観の点で迷惑をかける草本系植物と定義されています。人間の役に立つか立たないかで判断されるので、「雑草」とされた植物もいい迷惑だと思っているでしょうね。
この博物館の周りの植栽やリバーサイドパークの中も「雑草」がはびこっていて、環境整備には手を焼いています。
7月23日(日)
県内の小中学校では夏休みに入り、最初の日曜日になりました。本博物館の夏休み最初のイベントである化学実験教室「教えて☆みやもん先生」が第15回目を数え開催されました。開成中学・高等学校の宮本一弘先生をお迎えし、第1時限目「身のまわりの光るものを探そう!」、2時限目「おもしろ科学実験」、3時限目「不思議なカラーマジック」の実験でした。小学生を対象に身近にあるものを使って、化学の特定の条件下で変化したり、物質同士が反応するメカニズムを利用して、温度の変化による冷却パックを作る、シャボン玉を浮かせる気体の発生、色彩を変化させる酸とアルカリなど、大人でも知らなかった興味深い実験が目の前で繰り広げられました。化学反応は宮本先生のわかりやすいやさしい語り口で、身近なところにもたくさん利用されていることがわかりました。引率のお父さんやお母さんがたも目からうろこのようすで、我が子の実験を感心しながら見ていました。

7月20日(木)
茅小屋金山の現状は、上部の宮屋敷テラスとその下のテラスが大雨の被害により流失してしまっていました。宮屋敷にあった山の神の石祠は確認できませんでした。承応5年(1654)の板碑型石塔は、入り口部分のテラスの中央にそのまま立っています。高さ180センチと大きなもので、台座とともに設立時の原位置を保っているのかもしれません。各テラスには石臼がまとめてあるのを点検し、地面が見えるところでは茶碗や猪口などの陶磁器も見られましたが1点の染付皿以外明治期以降の新しいものばかりでした。
 入ノ沢川を遡上しているとき、河原の分流のよどみの石の下に3匹のサンショウウオがいました。体長7~8センチのハコネサンショウウオです。身延町の栃代川上流部に生息するものは県の自然記念物になっています。私もひさびさにサンショウウオを確認し、同行者も初めて見るものとのことです。
入ノ沢川を遡上しているとき、河原の分流のよどみの石の下に3匹のサンショウウオがいました。体長7~8センチのハコネサンショウウオです。身延町の栃代川上流部に生息するものは県の自然記念物になっています。私もひさびさにサンショウウオを確認し、同行者も初めて見るものとのことです。
 内山金山では、主要部分のテラスと測量杭の確認、石臼、墓石、整形した石、陶磁器の遺物とともに多量の熊のフンがありました。糞の周りには餌となるどんぐりが散らばっています。また、帰りの斜面には夏椿(シャラの木)の花が初夏の名残を感じさせてくれていますが、熊の存在の恐怖はもっと大きく背後にひしひしと感じられましたので、疲れた足でもおのずと早足になりました。
内山金山では、主要部分のテラスと測量杭の確認、石臼、墓石、整形した石、陶磁器の遺物とともに多量の熊のフンがありました。糞の周りには餌となるどんぐりが散らばっています。また、帰りの斜面には夏椿(シャラの木)の花が初夏の名残を感じさせてくれていますが、熊の存在の恐怖はもっと大きく背後にひしひしと感じられましたので、疲れた足でもおのずと早足になりました。

7月16日(日)
14日に茅小屋金山、内山金山の現地確認調査に行ってきました。調査隊は私と2名の学芸員と現地経験のある有志1名の総勢4名です。
博物館に6時集合、車で林道湯之奥猪之頭線を入ノ沢の入口まで行き、歩行開始、これまでの梅雨によって水量が増した川を右岸に渡渉し、荒れて寸断されている山道を登ること約40分で茅小屋金山に到着。過去の調査ではクマに遭遇したこともあるので、途中笛を鳴らしながら、休憩ごとに爆竹によって人間の存在を熊に知らしめながら進みました。前日の雨で湿度が多く樹林帯の下で薄暗く蒸し暑かった中、墓石や石臼の残存状況や炭焼き小屋跡と石積みをチェックし、2019の大雨で流失した上部の宮屋敷のテラスを確認しました。
 ここからは道らしきものは完全に消えており、川沿いに右岸、中洲、左岸と進みます。中継地点を過ぎると、ここからはさらに急な痩せ尾根をジグザグに上りました。やがて前回確認されていた尾根の露頭掘り跡にきました。岩を城郭の尾根切り状に切断して、鉱脈側は竪堀状に掘削されています。この上部にはかつての道の痕跡が残ってはいましたが、沢越え地点が危険なため安全なルート確保には経験者の記憶がたよりでした。
ここからは道らしきものは完全に消えており、川沿いに右岸、中洲、左岸と進みます。中継地点を過ぎると、ここからはさらに急な痩せ尾根をジグザグに上りました。やがて前回確認されていた尾根の露頭掘り跡にきました。岩を城郭の尾根切り状に切断して、鉱脈側は竪堀状に掘削されています。この上部にはかつての道の痕跡が残ってはいましたが、沢越え地点が危険なため安全なルート確保には経験者の記憶がたよりでした。
 さらに急斜面を登ること約80分で内山金山の中核部の広いテラスに到着しました。ここでいったん休憩とともに昼食。よく見ると熊のフンがそこかしこに何十か所とあるではありませんか。人がほとんど来ることのない広い平坦地なので、熊のねぐらには丁度うってつけの場所なのでしょう。
さらに急斜面を登ること約80分で内山金山の中核部の広いテラスに到着しました。ここでいったん休憩とともに昼食。よく見ると熊のフンがそこかしこに何十か所とあるではありませんか。人がほとんど来ることのない広い平坦地なので、熊のねぐらには丁度うってつけの場所なのでしょう。
ここでも墓石や石臼の集積場所の再点検と、テラスの現状を確認しました。いくつかのテラスの東側で、志野焼皿、明染付皿?、肥前系磁器の破片が表採でき、金山稼働時期を示す追加資料が得られました。帰りは同じ道をたどって17時過ぎに入ノ沢に到着。
 非常にハードな現地確認調査でした。30年以上前の記憶は不確かで曖昧なものとなっていて役に立ちませんでしたが、金山の現地のようすをしっかりと頭に刻むことができました。
非常にハードな現地確認調査でした。30年以上前の記憶は不確かで曖昧なものとなっていて役に立ちませんでしたが、金山の現地のようすをしっかりと頭に刻むことができました。
7月10日(月)
 博物館の入口東側の斜面にヤマユリが大輪の花をいくつも咲かせて見事です。昔から4本が自生しているとのことです。ヤマユリの学名auratumは黄金色を意味しています。金山博物館にぴったりですね。これは白い花びらの中にある黄色い筋に由来します。昔から「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」と、美人を形容する言葉として知られています。シャクヤク、ボタン、ヤマユリとこれらはすべて婦人病の薬草で、これらを用いると美人になるとかならないとか。ヤマユリの花ことばは、「荘厳」「威厳」「純潔」「飾らぬ美」「高貴な品性」などです。
博物館の入口東側の斜面にヤマユリが大輪の花をいくつも咲かせて見事です。昔から4本が自生しているとのことです。ヤマユリの学名auratumは黄金色を意味しています。金山博物館にぴったりですね。これは白い花びらの中にある黄色い筋に由来します。昔から「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」と、美人を形容する言葉として知られています。シャクヤク、ボタン、ヤマユリとこれらはすべて婦人病の薬草で、これらを用いると美人になるとかならないとか。ヤマユリの花ことばは、「荘厳」「威厳」「純潔」「飾らぬ美」「高貴な品性」などです。
 受付のところの花瓶には、オニユリが飾られています。鬼百合は赤い花びらに黒い斑点が目立ち、赤鬼を連想させることから名付けられたそうです。茎には黒色のむかごがあり、これを植えて3、4年すると花をつけるそうです。花言葉は「賢者」です。
受付のところの花瓶には、オニユリが飾られています。鬼百合は赤い花びらに黒い斑点が目立ち、赤鬼を連想させることから名付けられたそうです。茎には黒色のむかごがあり、これを植えて3、4年すると花をつけるそうです。花言葉は「賢者」です。
7月9日(日)
身延山久遠寺の広大な境内を散策した後、ロープウェイの下の駐車場に下る坂道の途中に琥珀明珠大菩薩のお堂がありました。このお堂の前を通った時、建物の前にある注連縄(しめなわ)につけられた紙垂(しで)を見た友人は、日蓮宗系独特の紙垂だと教えてくれました。普通の紙垂に耳のようなものが付いているのが特徴で、装飾的な効果があるようです。まして紅白2色の紙を組み合わせているのは注目されます。建物の扁額は「琥珀閣」とあり、入母屋造の建物の前には赤く塗られた神明鳥居があります。この鳥居に注連縄が張られ、特徴のある紙垂が下げられていました。
 一般的な神社などによく見られる紙垂は、四角く特殊な裁ち方をして折った白いひらひらした紙です。雷(稲妻)を象ったZ形をしており、神(仏)の領域と人の領域を分ける聖域を表すと同時に不浄なものが入らない結界を示しています。
一般的な神社などによく見られる紙垂は、四角く特殊な裁ち方をして折った白いひらひらした紙です。雷(稲妻)を象ったZ形をしており、神(仏)の領域と人の領域を分ける聖域を表すと同時に不浄なものが入らない結界を示しています。
 常葉諏方神社の拝殿の注連縄には一般的な紙垂があり、拝殿内本殿の前には紙垂を2つ合わせたような御幣が安置されています。常葉の道祖神にも石祠本体に一般的な紙垂がつけられており、竹で囲った注連縄の紙垂は風雨により一部が残るのみでした。
常葉諏方神社の拝殿の注連縄には一般的な紙垂があり、拝殿内本殿の前には紙垂を2つ合わせたような御幣が安置されています。常葉の道祖神にも石祠本体に一般的な紙垂がつけられており、竹で囲った注連縄の紙垂は風雨により一部が残るのみでした。
7月6日(木)
同窓会のメンバーで博物館の砂金採り体験を堪能した後、身延山久遠寺に行きました。日曜日の夕方4時過ぎだったので、東南アジア系の観光客が数集団と日本人の参拝者がちらほらいたくらいで、本堂から仏殿までじっくり見学、西谷へ移動し苔むした静寂な御草庵跡を案内すると、皆がこの一帯にくるのは初めてとたいそう感激してくれました。
 翌日は晴天に恵まれて、ロープウェイで奥之院思親閣へ行き、南アルプス連山の眺望、富士川谷や久遠寺境内の遠望を満喫。門前町で昼食後、身延を後にしました。
翌日は晴天に恵まれて、ロープウェイで奥之院思親閣へ行き、南アルプス連山の眺望、富士川谷や久遠寺境内の遠望を満喫。門前町で昼食後、身延を後にしました。
 さて、私が下部温泉に宿泊するのは30数年ぶりです。同窓会のみなさんには温泉で旅の疲れをいやしてもらった後、女将のおいしい料理を堪能しての宴会。旧交を温めて近況を語り合いました。
さて、私が下部温泉に宿泊するのは30数年ぶりです。同窓会のみなさんには温泉で旅の疲れをいやしてもらった後、女将のおいしい料理を堪能しての宴会。旧交を温めて近況を語り合いました。
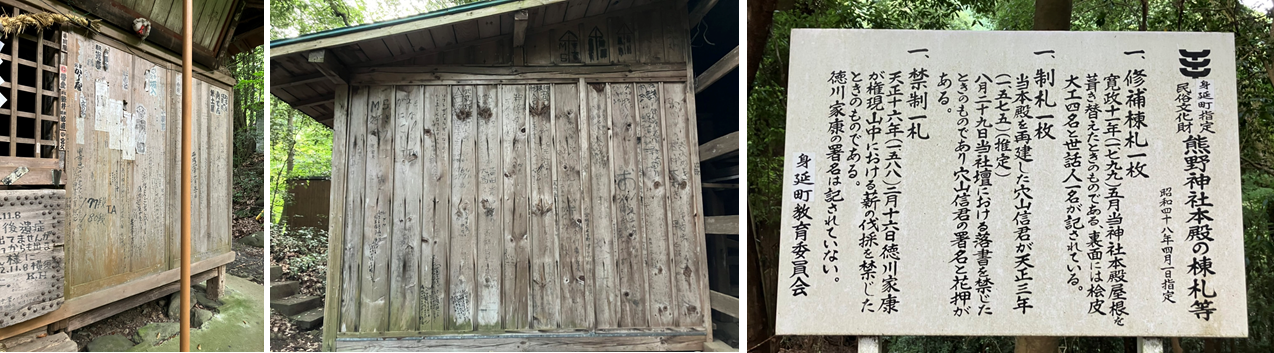 翌朝はいつもの習慣で明るくなる前に目覚めたため、温泉街や熊野神社を散策しました。落書きがそこかしこにいっぱいつけられています。下部温泉らしく湯湯治での病気快癒、足などのけがの回復祈願が目立ったけれども、戸板を埋め尽くすほどの落書きはいかがなものか。熊野神社は本殿、太々神楽、本殿の棟札等が町指定の文化財になっています。指定文化財の本殿の柱にまで書かれています。本殿の棟札等の中に穴山信君の境内での落書禁止の制札があると説明板にあります。「落書」とは「らくしょ・おとしがき」で「らくがき」ではありません。時の権力者への批判や社会風刺を匿名で掲示したものです。同じ漢字ながら別物であるのに不思議な一致です。発給した穴山さんも現代の落書きもしかりと、あの世で腹を立てているかもしれません。下部の落書きは願いを書いた文字のものが多く外国語のものも見られます。文字以外では来訪の年月日のほか、一般的に見られる相合傘やピカチューやドラえもんの姿もあります。
翌朝はいつもの習慣で明るくなる前に目覚めたため、温泉街や熊野神社を散策しました。落書きがそこかしこにいっぱいつけられています。下部温泉らしく湯湯治での病気快癒、足などのけがの回復祈願が目立ったけれども、戸板を埋め尽くすほどの落書きはいかがなものか。熊野神社は本殿、太々神楽、本殿の棟札等が町指定の文化財になっています。指定文化財の本殿の柱にまで書かれています。本殿の棟札等の中に穴山信君の境内での落書禁止の制札があると説明板にあります。「落書」とは「らくしょ・おとしがき」で「らくがき」ではありません。時の権力者への批判や社会風刺を匿名で掲示したものです。同じ漢字ながら別物であるのに不思議な一致です。発給した穴山さんも現代の落書きもしかりと、あの世で腹を立てているかもしれません。下部の落書きは願いを書いた文字のものが多く外国語のものも見られます。文字以外では来訪の年月日のほか、一般的に見られる相合傘やピカチューやドラえもんの姿もあります。
7月4日(火)
大学時代の考古学専攻生有志の同窓会を、下部温泉にて開催しました。コロナ前には恒例によって東京で毎年実施していたものを、幹事の一存で急きょこの場所でやることに決定になったのです。一昨日4名が金山博物館に集合、お互いの無事を確認しつつ5年ぶりの再会。この年になると多少の体型の増減を除いては、もうあまり変化がなく変わっていないのは良いことなのか悪いことなのか?
展示をゆっくり解説して見学後、砂金採り体験。博物館スタッフの説明を受け、いざ開始。全員砂金採り体験は初心者、金は比重が重いこと、独特の黄金色をしていることをたよりに、パンニング皿をやたら振り回す。力に任せて振り回すも、砂金は見つからない。見かねたスタッフがお手本を再度丁寧に指導してくれる。なぜかスタッフのお手本の砂の中には、砂金が存在しているのが不思議だ。夢中で作業をしているうちに、あっという間に制限時間が来てしまった。それでも一人3粒~5粒の成果があった。みんな大喜びで大満足、それこそ大の大人が欲をむき出しに、楽しいひと時をすごしました。1回やったらやめられない、中毒性のあることを身をもって感じました。

7月2日(日)
博物館入口の下部川の橋のたもとに桑の木が数本残っています。山梨県は江戸時代から養蚕の盛んな地域で、明治時代になると政府によってさらに奨励されました。山梨県では富士吉田や都留などの郡内地域で絹織物が織られ、甲斐絹(カイキ)の名で外国にもたくさん輸出されました。生産量は昭和40年代後半をピークとして、桑畑はどんどん果樹園や蔬菜畑に替えられて行き、現在ほとんど見ることができません。この桑の木はその当時の名残を留めているものです。桑畑が当時かなりの面積広がっていたことは、山間部の耕作放棄地が桑の巨木なっていたり、道路の植え込みの植栽の中に桑の木が顔を出していたりするのを目にすることでその痕跡を今でも確認できます。
 桑の葉の間をよく見ると、カミキリムシがいました。キボシカミキリです。この虫は桑の葉を食べるので、養蚕農家にとっては厄介ものの害虫です。私の実家は養蚕地帯の農家だったので、小学生のころこのキボシカミキリが大発生し困っていました。山梨県内の市町村では、この成虫を駆除すると1匹10円の報奨金を出していたことがあり、かつて桑畑の中を探し回ったことが懐かしく思い出されます。
桑の葉の間をよく見ると、カミキリムシがいました。キボシカミキリです。この虫は桑の葉を食べるので、養蚕農家にとっては厄介ものの害虫です。私の実家は養蚕地帯の農家だったので、小学生のころこのキボシカミキリが大発生し困っていました。山梨県内の市町村では、この成虫を駆除すると1匹10円の報奨金を出していたことがあり、かつて桑畑の中を探し回ったことが懐かしく思い出されます。
6月29日(木)
博物館の入口にある定礎や小原島の貝化石の周辺に「蟻地獄(アリジゴク)」がたくさんあります。ウスバカゲロウの幼虫が、乾いた土にすり鉢状の穴を掘って作った罠のことをこう呼びます。通りかかった蟻などの昆虫が滑り落ちてきたら、土の斜面が次々に崩れてなかなか逃げ出すことができません。そうしているうちに土を跳ね上げて穴の底の中心部に寄せ、土の中に隠れていたウスバカゲロウの幼虫がその虫を捕食します。
 その体には大きなあごをもち、体中に毛が生えているのがわかります。このたくさんの毛がセンサーとなって蟻などの虫の落下したことを素早く感知し、大きなあごで土の中に引きずり込んで体液を吸うのです。体液を吸われて抜け殻のようになった虫は、大きなあごを使ってアリジゴクの巣穴の外に放り投げます。
その体には大きなあごをもち、体中に毛が生えているのがわかります。このたくさんの毛がセンサーとなって蟻などの虫の落下したことを素早く感知し、大きなあごで土の中に引きずり込んで体液を吸うのです。体液を吸われて抜け殻のようになった虫は、大きなあごを使ってアリジゴクの巣穴の外に放り投げます。

裏返しにして写真を撮ったのですが、あごを器用に使って一瞬で元の姿に戻っていました。
6月26日(月)
博物館の建物の周りの植え込みの中や東側の山裾には、つる性の植物が勢力拡大を狙ってこの時期相当な勢いで伸張してきています。
 ヘクソカズラ(屁糞葛)はその名のとおり、葉や茎を傷つけると独特の嫌なにおいを出すつる草です。花は可憐でそれなりに美しいのですが、こんな名前を付けられたことに対して本人にとってまことに不本意ではないでしょうか。私のところの畑に隣接する土手にはこの草がはびこっており、地上部を刈り取っても地下に伸ばしている根から何度も再生してくるため、なかなかせん滅できません。博物館西側の植え込み中や東側のフェンス、下部リバーサイドパークなどいたるところで見ることができます。
ヘクソカズラ(屁糞葛)はその名のとおり、葉や茎を傷つけると独特の嫌なにおいを出すつる草です。花は可憐でそれなりに美しいのですが、こんな名前を付けられたことに対して本人にとってまことに不本意ではないでしょうか。私のところの畑に隣接する土手にはこの草がはびこっており、地上部を刈り取っても地下に伸ばしている根から何度も再生してくるため、なかなかせん滅できません。博物館西側の植え込み中や東側のフェンス、下部リバーサイドパークなどいたるところで見ることができます。
 ヤブガラシ(藪枯)は、生育が早いため巻き付いた植物に覆いかぶさって伸張し、光を遮断することでその植物を枯らしてしまうためこの名がつけられています。博物館の東側のフェンスには何本も絡んでいて、5メートル以上もあるフェンスの上部にまで達しています。
ヤブガラシ(藪枯)は、生育が早いため巻き付いた植物に覆いかぶさって伸張し、光を遮断することでその植物を枯らしてしまうためこの名がつけられています。博物館の東側のフェンスには何本も絡んでいて、5メートル以上もあるフェンスの上部にまで達しています。
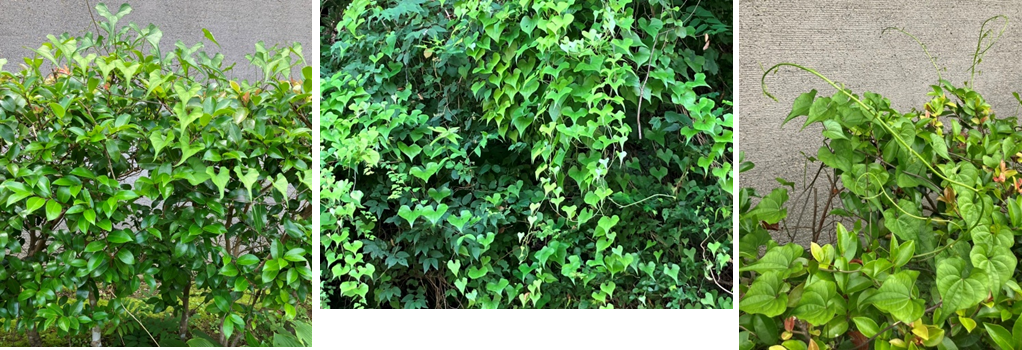 オニドコロは、一見ヤマイモのような葉をしていますが、葉の付き方が互生のため対生のヤマイモとは異なります。ヤマイモはおいしい食材ですが、オニドコロは毒性があって食べられません。葉を見るとほとんど見分けがつきませんが、似て非なるものです。ご注意あれ。
オニドコロは、一見ヤマイモのような葉をしていますが、葉の付き方が互生のため対生のヤマイモとは異なります。ヤマイモはおいしい食材ですが、オニドコロは毒性があって食べられません。葉を見るとほとんど見分けがつきませんが、似て非なるものです。ご注意あれ。
そのほか、ヒルガオ、フジ、クズなどつる性植物のオンパレードです
6月25日(日)
5月6日の醍醐山一斉登山のときにオトシブミを5個採集し、5月28日と29日にそれぞれ1匹ずつ羽化したことはすでに報告しました。残りの3個は、その後1か月近く経過しても全く外観からは生きている気配が感じられません。みずみずしかった葉の揺籃も机の上で枯葉のようになってしまっていたので、中のようすがどうなっているか確認してみました。巻かれている葉を慎重に崩しながら開いていくと、驚いたことに中から幼虫がそれぞれでてきました。大きさは3~5ミリほどで小さいのですが、まだ生きており動いています。
 写真を撮ってから乾燥してしまった揺籃の代わりにヤマブキの葉を入れ、暗さを確保できる引き出しの中に安置してしばらく様子を見ることにしました。揺籃の揺り籠はなくとも新鮮な葉の布団の中で、これを食することができれば大きくなって成虫になれるかもしれません。わずかでも望みを持って観察したいと思います。
写真を撮ってから乾燥してしまった揺籃の代わりにヤマブキの葉を入れ、暗さを確保できる引き出しの中に安置してしばらく様子を見ることにしました。揺籃の揺り籠はなくとも新鮮な葉の布団の中で、これを食することができれば大きくなって成虫になれるかもしれません。わずかでも望みを持って観察したいと思います。
夕べ身延町一色地区のホタルを見てきました。土曜日だけに駐車場には30台くらい先客がいました。川沿いの遊歩道には、蛍の光がちらほら。視界の中には3~4匹ほどが、入れ代わり立ち代わり光を放っています。場所を移動してもどこも同じような感じで、数匹ずつが見える程度です。ピークはとっくに過ぎていて光の乱舞とまではいかないですが、見え隠れする蛍のともしびはホントに幻想的です。
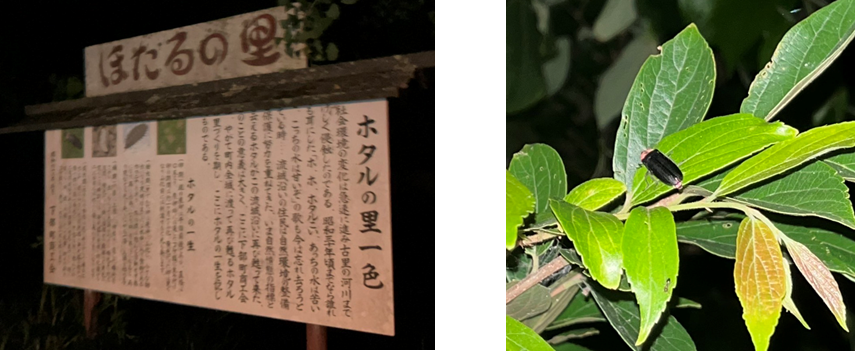
ホタルが光るのはオスのみで、メスとカップル誕生のために一生懸命の自己主張です。短い繁殖期に理想の相手を求めて、夜の水辺に光による最後のアピールをしています。この中でいったい何匹が恋愛成就できたのでしょうか? (一色でのホタルのフラッシュ撮影は禁止されています。右側の葉の上のゲンジボタルは1週間前に甲府市相川で撮影した資料画像です。)
6月23日(金)
生物学において新種の発見や天文学で新星の発見をしたとき、その命名に際して自分の名前などを冠して功績を未来永劫に残すことは、その道の研究者にとっては大変名誉なことです。
NHK朝ドラの「らんまん」の主人公のモデルとなっている牧野富太郎は1500以上の植物の新種を発見し、その命名に自分だけでなく近親者の名前も使っています。笹の新種に愛妻の名前を付してスエコザサとしています。それなのに、牧野はアジサイの学名に日本人妻の名を冠した植物学の先人シーボルトを、痛切に批判しています。シーボルトはアジサイの学名の一部に「オタクサ」と名付け、長崎で愛した「お滝さん」の名前にあやかって付けたことについて、「神聖な学名に自分の情婦の名をつけるとはけしからんことだ」と憤慨しておられたとのことです。(中村浩『植物名の由来』)
ちなみにこのブログの命名についても、それなりのこだわりと理由があります。(4月20日ブログ参照)
6月19日(月)
梅雨の時期の花と言えば、アジサイですよね。博物館の周囲にもたくさん植えられています。普通のアジサイのほかにガクアジサイや柏葉アジサイもあります。ここ数日梅雨の中休みですが、ほぼ梅雨の期間中を通じてかなり長期にわたってきれいな花をそれぞれ見せてくれています。
 アジサイは日本原産の植物です。一般的なアジサイはホンアジサイともいわれ、日本原種のガクアジサイを改良した園芸品種です。青やピンクのきれいな花と思われている部分は、実は花ではなくガクが大きく発達した「装飾花」と呼ばれるものです。個々の花のようなガクの中央には、一見めしべのような玉状の部分がありますが、これもガクの変異したものです。花ではない花なのです。
アジサイは日本原産の植物です。一般的なアジサイはホンアジサイともいわれ、日本原種のガクアジサイを改良した園芸品種です。青やピンクのきれいな花と思われている部分は、実は花ではなくガクが大きく発達した「装飾花」と呼ばれるものです。個々の花のようなガクの中央には、一見めしべのような玉状の部分がありますが、これもガクの変異したものです。花ではない花なのです。
 前述したようにガクアジサイでは、周囲の白い花弁のような部分はガクであって見せかけの花です。ガクの中央にある青くて小さな花の部分が本当の花で、「真花」と呼ばれています。咲いている花の周りには、まだつぼみがたくさん控えています。早く開いた花の下にある葉には、小さい花びらやオシベや花粉がまとまって落ちており、こちらが本当の花であることがわかります。
前述したようにガクアジサイでは、周囲の白い花弁のような部分はガクであって見せかけの花です。ガクの中央にある青くて小さな花の部分が本当の花で、「真花」と呼ばれています。咲いている花の周りには、まだつぼみがたくさん控えています。早く開いた花の下にある葉には、小さい花びらやオシベや花粉がまとまって落ちており、こちらが本当の花であることがわかります。

6月17日(土)
昨日令和5年度第1回目の博物館運営委員会を開催しました。これまでの6名の先生方と新しく鉱山学分野の学識経験者2名、地元身延町の知識経験者2名の先生方をお迎えしました。昨年度の事業報告、今年度の事業計画と今後の博物館運営等に係る諸課題について、審議していただき貴重なご意見を賜りました。26年周年を迎えた本年、これまでの積み重ねてこられた歴史の上に、さらに新しい何かを積み重ねていけるよう気の引き締まる思いです。
本日は九州大学総合研究博物館と湯之奥金山博物館のコラボによる『歴史を動かした革新的マイニングヒストリー』と題した特別講演会を開催しました。中西哲也先生の「湯之奥茅小屋金山採掘跡に見られる鉱石の特徴について」、久間英樹先生の「みんなで楽しく鉱山遺跡調査~iPhone&iPad編~」のご講演をいただき、本館小松美鈴学芸員と伊藤佳世学芸員の茅小屋金山遺跡の概要と調査方法についての報告がありました。
これまで未確認であった茅小屋金山遺跡の採鉱域について、発見の経緯と調査状況やiPhoneやiPadを使った新しい3次元レーザ測定の結果と有用性を披露していただきました。本館の全国に誇る専門的・学問的部分を九州大学総合研究博物館の両先生に発表していただき、茅小屋金山のたいへん険しい現地の状況が、来場された皆さんにわかっていただけたのではないでしょうか。
梅雨休みで蒸し暑い中、遠方からも多くの研究者にお集まりいただきました。ありがとうございました。
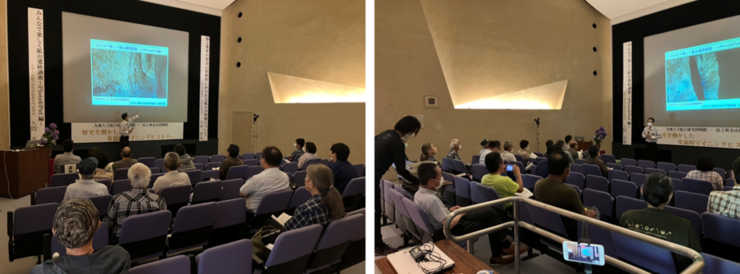
6月12日(月)
身延町一色地区はホタルの里として有名です。先日の地元紙山梨日日新聞でも一面紙上にゲンジボタルが乱舞する姿の写真が掲載されていました。梅雨の真っただ中、雨の日も多いのですが現在飛来の最盛期を迎えていることと思います。
さて、当館南の崖の途中にホタルブクロが群生しており、薄赤紫や白い色の花もそろそろ終わりに近づいています。ホタルブクロの花は、釣り鐘状の花を下向きに咲かせており、筒状の花に子供が昔ホタルを入れて遊んだことから「ホタルブクロ」の名がつけられたといわれています。幼いころ蜜を吸いに来ていたミツバチをこの花の中に閉じ込めて、刺された痛い経験がありました。ホタルなら花弁を透して、幻想的な光がみられることでしょうね。
英名ではSpotted bellflowerです。まだら模様になっている花の形が教会の鐘を連想させることからの命名だそうです。

6月11日(日)
第1回シン・サンポを開催しました。館長講座のアウトドア編です。あいにくの雨の中、27名もの参加者がありました。かなりの割合で常葉地区在住の方々でした。
途中シロツメグサの株があり、小学生と大人の何人かが4つ葉のクローバーを見つけることができました。植物学者の牧野富太郎を主人公にしたNHKの朝ドラ「らんまん」でも、シロツメグサのシーンがあり、オランダから輸入したガラス製品の破損防止のクッション材として詰められていたため詰め草がその名前の由来であったことや4つ葉がなぜ幸せを呼ぶラッキーアイテムになったのかも紹介しました。
 常幸院と東前院の両お寺では、ご住職に直接お寺の由緒や常葉地域の歴史についてもお話をしていただきました。ありがとうございました。
常幸院と東前院の両お寺では、ご住職に直接お寺の由緒や常葉地域の歴史についてもお話をしていただきました。ありがとうございました。
史跡や文化財は身近にあっても普段はあまり気にも留めない存在かもしれません。しかし、それぞれに地域に溶け込んだ長い歴史の積み重ねがあって、今日を迎えています。ふるさと再発見のいい機会になったのではないでしょうか。
6月8日(木)
ヤマブキに実がいっぱいなっています。これを見ると「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだになきぞ悲しき」の和歌と江戸城を造った太田道灌の有名な話が想起されます。
ある日鷹狩りに出かけた道灌はにわか雨に降られ、とある家に雨よけの「蓑(みの)」を借りに立ち寄った。すると、その家の女が出てきて、山吹の花一枝を黙って差し出してきたので、怒って雨の中を帰宅した。のちにその山吹の花の行為には、その家は貧しくて「蓑」がないので貸すことができないという古歌が託されていることを家臣から教えられ、おのれの無学を恥じたという有名な話です。(出典「常山紀談」)
「実の」と「蓑」が掛詞(かけことば)になっていますね。日本では昔から栽培されていたヤマブキの多くが、実をつけない八重咲種であったため、ヤマブキは実をつけないといわれるようになったとのことです。突然変異で八重になったヤマブキには実がないので種ができず、株分けでしか増やすことができません。そういえば、私の実家の裏庭にも八重咲のヤマブキが咲いていました。当博物館に植えられているヤマブキは、周辺の山裾にある一重のヤマブキと同じ野生種なので、今たくさんの実をつけています。
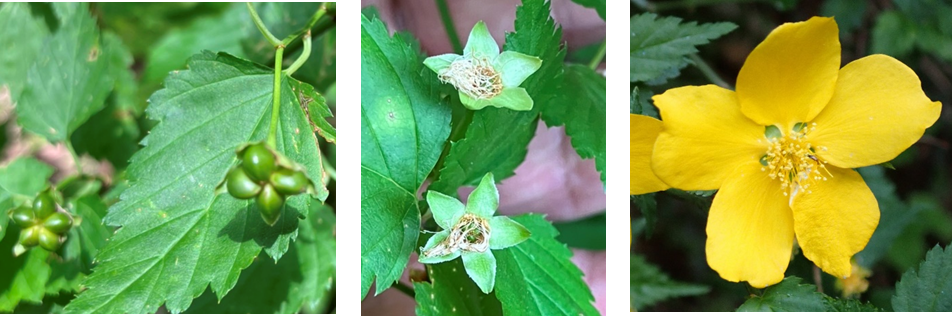
6月4日(日)
6月11日に実施する第1回「シン・サンポ」の下見に、「常葉(ときわ)」に先日行ってきました。甲斐常葉駅に集合し、日向の道祖神➡常光院➡本栖高校➡東前院➡諏訪神社➡甲斐常葉駅とまわって来るコースの予定です。
 日向地区の道祖神場にはいくつかの石造物が集められており、記念碑のほか三種3体の道祖神があります。流造屋根の付く双体道祖神、舟型の双体道祖神、自然石の丸石道祖神です。屋根付きのものには寛延四年(1751)の年号がありますが、石がもろいためヒビが入って紀年銘が無くなってしまうのも時間の問題かもしれません。顔はもう表情がわからなくなっていますが、左の女性像は右手に扇子を持ち、左手を合掌している男性像の肩に置いています。舟形双神像は掌に掌を重ね仲睦まじい姿をしておられます。丸石のものは甲府盆地東部に多く分布しているものと同じく、縄文時代にはじまった丸石信仰がそのルーツと思われます。
日向地区の道祖神場にはいくつかの石造物が集められており、記念碑のほか三種3体の道祖神があります。流造屋根の付く双体道祖神、舟型の双体道祖神、自然石の丸石道祖神です。屋根付きのものには寛延四年(1751)の年号がありますが、石がもろいためヒビが入って紀年銘が無くなってしまうのも時間の問題かもしれません。顔はもう表情がわからなくなっていますが、左の女性像は右手に扇子を持ち、左手を合掌している男性像の肩に置いています。舟形双神像は掌に掌を重ね仲睦まじい姿をしておられます。丸石のものは甲府盆地東部に多く分布しているものと同じく、縄文時代にはじまった丸石信仰がそのルーツと思われます。
道祖神というのは、本来中国の道の神と日本古来の邪悪を遮る神とが合わさったもので、集落の入口や辻に立って災いの侵入を防ぎ、村を守る神でありました。また、旅人の安全を守り、良縁・和合の神、さらに生産神、農耕神など複雑に重層的に発展してきました。いろいろな側面を持つことから、それぞれの地域では賽の神(さいのかみ)、道陸神(どうろくじん)、衢神(ちまたのかみ)、岐の神(くなどのかみ)、サルタヒコなど様々な別名があります。
常葉地区には文字道祖神や石祠形道祖神も各小地域にあって、種類も豊富であります。いずれにしても当地域一帯には魅力的な道祖神が多く、石造物愛好家にはたまらない地域です。

5月29日(月)
地球上の未採掘の金の埋蔵量は、おおよそ50,000トン余りと考えられています。これまで世界各地で採掘された金は約180,000トンであり、毎年約3,000トン余りが採掘され続けています。このペースでいくと約15年後には地球上の金は採りつくされてしまう計算になるようです。しかし、金の埋蔵量はあくまで採掘可能な固体としての金であり、海水や地下のマグマ中に含まれている金はカウントされていません。
先月日本経済新聞に海洋研究開発機構とIHIの研究グループが、秋田県玉川温泉から金の回収に成功したとの報道がありました。藻の一種である「ラン藻」が金を吸着する性質を利用し、これをシート状にして温泉水に浸すだけで金が回収できたということです。現在日本で商業的経営が行われている金鉱山は、鹿児島県の菱刈鉱山が唯一でありますが、温泉大国の日本にはまだまだ可能性が残されているといえるでしょう。
下部温泉を有するこの身延町でも、温泉水の中に金が溶け込んでいて、それを回収することができればその可能性は無限大です。
本日も昨日に続きオトシブミが1匹羽化しました。やはり朝の来館時には変化がなかったのですが、10時過ぎに成虫になって動いていました。揺籃に開けられた穴は3ミリと昨日より小さいです。今日の個体のほうが首が長いのでオスで、昨日の個体はそれほど長くないのでメスなのでしょうか。揺籃の中からは黒くて小さい棒状のフンが、一緒に出てきました。観察している間に、入口から外へ飛んで出て行ってしまいました。
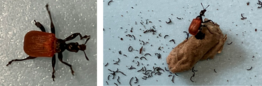
5月28日(日)
5月6日の醍醐山一斉登山の時に山頂付近で採取したオトシブミが、成虫になって出てきました。オトシブミの葉っぱの巻物の個体は山中でよく見かけるのですが、その正体については詳しく調べたことがありませんでした。(5月8日のブログ参照)その独特な形状とロマンチックな名前から、関心は前々から持っていたのですが、、、。
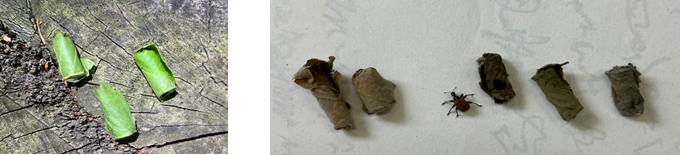
5個を山から持ち帰り、透明なビニール袋の中に入れて、出勤時は常時観察できるようにしていました。オトシブミの巻物は、長さ1.5~2.2センチ、葉の直径は7~8ミリの円筒形です。採取当日にはみずみずしい鮮明な緑色だったのが、次第に乾燥して迷彩服にあるような枯葉色になっていました。今朝の朝一には特に変化はなかったのですが、11時ごろふと気が付くともそもそと袋の中で何かが動いているではないですか。よく見ると、袋の中には赤い羽根をした虫が1匹います。全長8ミリほどで、前翅部の堅い羽根が赤いほかは、真っ黒な色をしています。また、葉っぱの揺籃の一つには5ミリほどの穴があけられているのが観察できました。採取から22日後に成虫になったのですから、約3週間で卵から孵化して揺籃の葉を食べ大きくなって羽化したもののようです。

写真を撮影し、大きさを計測して記録したのちには、外の自然界に戻してあげました。
5月25日(木)
今年度第2回目の古文書講座が実施されました。本館運営委員会委員の西脇先生の指導で、佐渡金山の金精錬工程を記した絵図を解説した古文書の、読み合わせおよび逐字の解説です。本日出席の聴講生と学芸員は、すでに数年来先生のご指導をいただいているとのことです。私はというと、大学での古文書演習以来、各地の文化財調査で地方文書は目にする機会はあったのですが、本格的に近世文書に対峙するのは何十年ぶりでしょうか。教材本は読みにくい変体仮名などの文字だけならいざ知らず、精錬における当時の専門用語の羅列までもが私の理解を苦しめます。しかし、先生の懇切ていねいな文字の崩し方や表現方法を解説していただき、なんとなくわかった気がします。
本当のところは、、、
当時の作業工程の内容と金精錬に関する用語を知るには、たいへん勉強になっていると思います。
5月22日(月)
先日のこどもの村小学校の中山金山への登山の同行は、私自身約5年ぶりの現地への訪問でした。湯之奥三金山の学術調査時以来、毛無山登山にこのルートを利用して数回来ただけだったので、ひさびさの中山金山の現地です。
 調査時と地形はほとんど変わっていなませんが、周囲の樹木の成長や植生の変化は、だいぶ様相を異にしているように思われました。車を置いた下部川沿いの林道から入る登山道は、植林されたヒノキが大きく育って登山道を覆っており、女郎屋敷のテラスもカラマツが成長して若木であった当時の面影はありません。テントに泊りがけで調査していた夏の当時、ふもとから食糧や燃料をほとんど毎日地元の方に運んでいただいていました。日当たりが良かった植林の間の藪を縫うようにして整備された登山道にはマムシがたくさん出没し、毎回運搬途中で数匹捕獲できたとの話の記憶がよみがえります。(当時は薬用、強精剤としてのマムシの焼酎付けに供されていた。)いまでは直径30センチほどに育ったヒノキの樹間は、保安林改良事業で間伐されて下草もほとんどなく、30余年の歳月の長さをあらためて痛感した次第です。
調査時と地形はほとんど変わっていなませんが、周囲の樹木の成長や植生の変化は、だいぶ様相を異にしているように思われました。車を置いた下部川沿いの林道から入る登山道は、植林されたヒノキが大きく育って登山道を覆っており、女郎屋敷のテラスもカラマツが成長して若木であった当時の面影はありません。テントに泊りがけで調査していた夏の当時、ふもとから食糧や燃料をほとんど毎日地元の方に運んでいただいていました。日当たりが良かった植林の間の藪を縫うようにして整備された登山道にはマムシがたくさん出没し、毎回運搬途中で数匹捕獲できたとの話の記憶がよみがえります。(当時は薬用、強精剤としてのマムシの焼酎付けに供されていた。)いまでは直径30センチほどに育ったヒノキの樹間は、保安林改良事業で間伐されて下草もほとんどなく、30余年の歳月の長さをあらためて痛感した次第です。
 学芸員から精錬場にはトリカブトが多かったというイメージがあったということでしたが、現在トリカブトはごくわずかしか見られず、その代わりにコバイケイソウが群落をなしています。林道近くの登山道沿いには、フタリシズカがかなり見られました。名前のフタリシズカ(二人静)は、2本の花序が源義経を愛した静御前の亡霊が舞う能楽「二人静」における静御前とその亡霊の舞姿にたとえたものに由来するそうです。2本の花序になるものが多いはずなのに、1~4本までのさまざまなものが存在しています。花の盛期はまだこれからのようです。
学芸員から精錬場にはトリカブトが多かったというイメージがあったということでしたが、現在トリカブトはごくわずかしか見られず、その代わりにコバイケイソウが群落をなしています。林道近くの登山道沿いには、フタリシズカがかなり見られました。名前のフタリシズカ(二人静)は、2本の花序が源義経を愛した静御前の亡霊が舞う能楽「二人静」における静御前とその亡霊の舞姿にたとえたものに由来するそうです。2本の花序になるものが多いはずなのに、1~4本までのさまざまなものが存在しています。花の盛期はまだこれからのようです。

登山道脇には、ワイヤーロープと鉄製の滑車が使われなくなったままの状態で放置されており、これらは昔の調査時にも確認しています。かつてこの山の木材搬出用に設置されたもののようで、尾根付近には直径1メートル以上の大木の切り株がいまだに腐りきらずに存在しています。滑車にはツキヂ索道と書かれたプレートもあり、昭和40年代に伐採された可能性があります。廃棄されたままの鉄製のロープや滑車はかなり重量があって腐食もさほど進んではいないので、資源として再利用してほしいところです。山中ではしばしばこういった放置物を見かけますが、どうにかならないものでしょうか。今では廃棄物処理法違反なのでしょうが、、、。

5月21日(日)
18日に南アルプスこどもの村小学校の児童30人、引率者3名と、湯之奥中山金山遺跡の現地に行ってきました。こどもの村小学校は私立の小学校で、こどもの自由を教育理念とした非常に特色ある学校です。プロジェクトと呼ばれる縦割りクラスの授業の一環で、1~6年生までの男女が参加してくれました。
当館は、国指定史跡甲斐金山遺跡(湯之奥中山金山遺跡)のガイダンス施設でもありますので、まずは博物館で中山金山の事前学習。そのあと、車で登山口へ移動しました。
ここからは比高差600mの山道をひたすら登ります。約2時間かけて、中山金山の作業をした遺跡の現場に到着しました。現地でお昼のお弁当のあとに、学芸員から採掘の跡や現地に残る作業テラスの概要の説明を受けました。約500年前の戦国時代当時に思いをはせながら、熱心に聞き入っていました。
年齢差があり体格差や体力差は当然まちまちで、体力的に厳しくて弱音を吐きそうな子もいましたが、お友だちのサポートもあって全員無事に往復することができました。
登山の過酷さや厳しさと、歴史のロマンを感じた1日だったと思います。
5月15日(月)
「シン・サンポ」を実施します。前出月館長の「いでさんぽ」を引き継いだかたちで、身延町内各地域の身近な歴史や文化と自然に触れる機会を踏襲します。館長講座の現地版です。それぞれの地域を直接歩くことによって地域を再発見するもので、地域を知ることが地域に親しみを持ち、地域(身延町)を好きになってもらうきっかけづくり動機づけの一つになればと思っています。
第1回目は「甲斐常葉周辺」を散策します。「シン・サンポ」としたのは、ひらがなの「いでさんぽ」に対抗してというよりは、このブログ(4月20日記事)の時のように、地域探訪に参加された方々がさまざまなことをそれぞれが感じ取ってほしいという思いから計画しました。

これから作成する募集案内を確認してみてください。
5月13日(土)
5月6日の醍醐山一斉登山の時、今回の登山道沿いにある石造物や寺社について、樹木や草花の名前とともに醍醐山を愛する会の関係者からいろいろと説明をしていただきました。その中で、今から約40年前の湯之奥金山遺跡学術調査を思い出す資料の解説がありました。大子(だいご)集落の入口手前にある石祠の時です。この本体部分の正面の穴を指して「猪の目です。」と解説してくれました。この石祠は、石を二段積んだ基壇上に、四角い台座石、その上に正面に逆ハート形の穴が穿たれた軸部、流造りの形式の屋根が組み合わさった山梨県ではごく一般的な形式のものです。その穿たれている穴の形に、遠い脳の片隅の記憶がよみがえってきました。
金山学術調査の検討会の時、中山金山の七人塚下方の谷から発見された石殿の軸部に、このハート形の穿った穴と長方形の穴が上下に並んだ資料がありました。「原位置ではハート形の穴になっているがこれは上下が逆になっており、この形は宝珠を表しているものであって本来尖がっている部分が上にくる点を注意してください。」といった内容の発言が石造物専門の先生からあったことです。
このことを考えると大子集落手前の石祠は、猪の目を表したものではなく、宝珠を表している可能性もあるのではないかと思った次第です。
5月11日(木)
北杜市小淵沢町の中学2年生が、社会科見学で金山博物館に来てくれました。
日本における人と金とのかかわりやその技術を学びました。映像による日本の金の歴史と湯之奥金山の解説をみて、山金採掘に関する道具や甲州金をはじめとする金貨の展示品を見学したあとは、お楽しみの砂金採り体験です。みんな楽しくわいわいと、小さな砂金を一生懸命探していました。
苦労して探し当てた砂金は、思い出に残る大切な宝物となることでしょう。
5月8日(月)
湯之奥金山の現地調査でいつもお世話になっているIさんに誘われて、醍醐山を愛する会に入会しました。
恒例の醍醐山一斉登山が6日の土曜日にあったので、早速参加してきました。少し前の天気予報では雨予報であったのが、すばらしい五月晴れの天気になりました。私が晴れ男のせいか、イエイエ関係者みなさまの日ごろの行いの成果であります。甲斐常葉駅前広場に60名近い人数が集合して開会式。役員さんから班分けの後に趣旨説明、コース説明、注意事項の確認のあと、準備体操をして班ごとに出発しました。
役員さんから眼下に見える集落や遠望できる山名の解説があり、随所で樹木や山野草の説明もありました。スギ、ヒノキ、クロモジ、キンラン、ギンラン、フタリシズカなど。貴重な植物に出会えたのも役員さんの事前の下見のおかげです。

会の有志が北側を切り開いてくれた山頂直下からは、茅ガ岳から奥秩父山塊が見渡せます。山頂に到着し荷物を置いて、稜線を少し下った展望台に行きました。下山集落から南側の富士川流域は見えましたが、周囲の植林した木々が大きく育っていて山などの眺望は以前に比べて望めなくなったとのベテランの会員さんの声です。。
登山道は転石などがあり注意して下を見て歩くのは当然ですが、私の普段からの習性で何か落ちてはいないか、周囲の地形は自然か人工的なものか、石や土は何なのかなど地表面を観察して歩きました。山頂手前の登山道にオトシブミが落ちていました。昆虫のオトシブミの母親がこれに卵を産み付け、巻物のようにていねいに巻いて落としたものです。卵は幾重にも重ねられた葉の中にまもられていて、葉っぱのふとんかゆりかごのようです。卵からかえった幼虫は、この巻物の葉を食べて成長し、約3週間後には成虫になったオトシブミが出てくるのでしょう。葉はまだ青々として緑が鮮明で、今朝の創作物と思われます。
山頂では出発の時に配られたカップ麺をいただきながら、おにぎりをほおばりました。食事後に、峡南消防本部特別救助隊の山岳救助における講習と実演のあと、交流会で参加者の方からいろいろな話が聞けました。会の発足から登山道の整備など、会員の方の長年にわたるご苦労があってこそ安全な登山ができ、楽しい山行を堪能できることを改めて認識しました。
下山の途中では山頂にあった村の痕跡や、ナラ枯れの被害状況、鉄塔で切り開かれた地点からの眺望の説明と、大子の集落でリンゴとオレンジの接待を受けました。
下山後、車の運転手は甲斐常葉駅に、それ以外の人は湯之奥金山博物館へ直行しました。博物館では、金粉入りの梅茶でおもてなしです。汗をかいた疲れた体には、適度な塩分と水分の梅茶は体中にしみわたります。一息ついたところで反省会を行い、再度参加者からそれぞれの感想と意見を聞いて散会となりました。

主催者の役員の皆様お疲れ様でした。そしてありがとうございました。楽しく有意義な登山ができました。
5月5日(金)
今日は端午の節句、こどもの日です。親子連れでたくさんの人が来てくれました。節句とは季節の節目となる日のことです。中国から伝わった陰陽五行説がそのルーツで、古代中国では月と日が奇数で重なる日を忌み嫌って、邪気を払う行事が行われたということです。端午の節句は五月の最初の午の日のということで、午と五の音が同じことから五月五日と定められました。昔はこの日を悪日として、災難をよける魔除けのために、菖蒲やヨモギを屋根に刺したと『下部町誌』では記載しています。
少し前まで男の子のいる家では、鯉のぼりや武者のぼりの旗が家の入口にはためいていました。個人のお宅に建てられることは少なくなってしまいましたが、今では使わなくなってしまった鯉のぼりをたくさん集めた地域おこしの名物として、北杜市南清里のほか全国各地で新たな活躍の役目を担って、風香る五月の空に何百匹も遊泳している姿を見せてくれています。
端午の節句は菖蒲の節句ともいわれ、菖蒲から尚武に転じて男の子の誕生を祝うとともに、その健やかな成長を祈念しました。武者人形や鎧兜を飾るのも、これに由来したとされています。
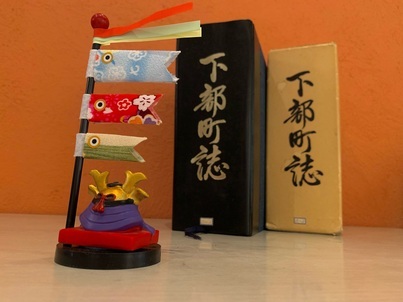
5月4日(木)
大型連休後半2日目突入。朝から入館待ちの大行列ができています。きゃぁーっと、うれしい悲鳴。砂金採り体験は大多数のみなさんが希望されているため、開館直後を除けば30分待ちの大渋滞が発生で、これが夕方まで続きました。体験の順番待ちのお客さんが、入り口のホールで大混雑になっています。
 親子連れ、ご家族連れ、友人グループなどいろんなパターンがあるけど、やっぱり家族連れが多いかな。天気もよく風は少し強いけど、行楽日和な一日でした。
親子連れ、ご家族連れ、友人グループなどいろんなパターンがあるけど、やっぱり家族連れが多いかな。天気もよく風は少し強いけど、行楽日和な一日でした。
当館のスタッフは、一日中てんてこ舞いです。昼食も取れない状況でした。ご苦労様です。戦力にならない館長なので、せめて応援のエールをおくります。ほんとうにお疲れ様でした。ファイト。明日もまだ5連休の中日です。もう少しの辛抱です。頑張りましょう。
5月1日(月)
夕べのNHK大河ドラマ「どうする家康」番組の最後の「紀行潤礼」で、甲斐黄金村・湯之奥金山博物館が登場しました。武田信玄にまつわる関係地として、甲府市の「武田神社(躑躅ヶ崎館跡)」とともに身延町の当博物館が紹介されたものです。甲州金(甲州露壱両判)や鉱山作業を再現した展示と砂金採り体験室のようすが放映されました。
見逃した方は、当館のホームページから「もん父Twitter」でご覧ください。
これを見た学生時代の同級生から、久しぶりに連絡がありました。
私がここに来たことから、金山ツアーとして下部温泉で同窓会をやってくれることになっています。みんな砂金採り体験を楽しみにしてくれています。
4月30日(日)
今朝は館に緊急事態発生です。全館の停電です。電気が来ないと暗いばかりか、水も出ないしトイレも使えません。それに今日午後からは第1回目の館長講座の予定。「どうする家康」じゃなかった。さあどうするどうする。
職員のみんなで対応検討。発電機の手配や、最悪復旧しなかった場合も想定して、講演会開催の別施設の確保など、職員のみんなてんてこ舞い。目が血走って対応してくれています。
ゴールデンウィーク中なので、開館時間前から入館者が並んでいます。臨時休館にするかとも検討しましたが、砂金採り体験だけでもしたいとのことで、電気のないうす暗がり中での一部開館です。関東電気保安協会の職員の方の点検調査によって、雨と湿気による漏電が原因と分かり、焼損した部品を交換して2時間ぐらいで何とか復旧しました。ほっと一安心。
館長就任記念講演会に、たくさんの方々が来てくれました。ラジオでの宣伝効果もあって、幼馴染や元職場の大先輩や親戚までも駆けつけ盛会でした。講演内容はともかく、みなさんの反応は良好でした。
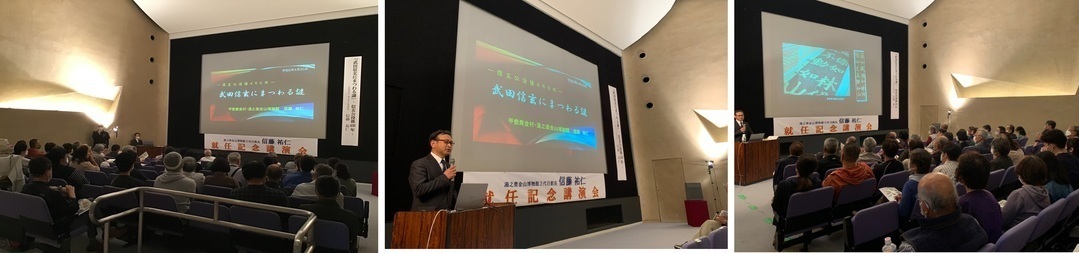
今回の講演会の開催に当たり、いつもご協力いただいている博物館応援団のみなさんに下準備や会場整理のお手伝いしてもらいました。ありがたいことです。感謝、感謝です。
4月29日(土)
新館長就任記念のお花が届きました。SPCさんありがとうございます。お花はロビーに飾らせていただきました。いくつになっても花をいただくのはうれしいものですね。お花をいただくのは久々で、何年ぶりのことでしょう。前の職場の退職の時以来かな。どの花も一つひとつがそれぞれ美しく、心がなごみます。

昨日、身延町の日帰り温泉施設「しもべの湯」が下部温泉駅に隣接してオープンしました。地元放送局の夜のテレビ番組で紹介していました。建物の1階には大浴場や露天風呂など男女それぞれ6種類の温泉やサウナにレストランと休憩室、2階はスポーツジムが完備されています。町民の健康づくりとともに観光の拠点として、下部温泉郷活性化の起爆剤となればいいですね。

これにあやかって、金山博物館の入館者も大幅に増えることを期待しちゃいます。
4月24日(月)
今日は金山博物館の26回目の誕生日です。
皆様のお引き立てとご協力があってこそ、本日を迎えることができました。どうもありがとうございます。
館の職員が入り口に「26」を意識した特別な飾りをつけてくれました。
初代谷口館長が立ち上げて基礎を固め、二代出月館長が充実させてきた当館の存在意義を、さらに発展させるべく皆様に親しまれるよう努力したいと思っております。
さて、あれほど当館周辺の山裾や花壇に群生して目立っていたゴールデンカラーのヤマブキの花も、いつしか花びらが落ちてほとんどが額と葉の緑だけになってしまっています。

時の過ぎゆくことが、なんと早いことか。このところ、年齢とともに特に加速度がついてきていると感じるのは、私だけでしょうか。
26年間はとても長いと感じますか。それともあっという間なのでしょうか。みなさんはどう感じられますか?
4月23日(日)
四つ葉のクローバーを見つけると幸せになれるといいます。
わたしは小さいころから、地面に落ちているものを拾い集めるクセがあります。土器片であったり水晶であったり。土器片は実家の畑とその周囲、水晶は近くの石切り場とそこから運ばれた土砂が敷かれた道路など。このことについては、他の人よりもたくさん珍しい物を集められる自信があります。これまでの代表的成果品としては、甲斐駒山頂の縄文土器片やブドウ畑でのヒスイの勾玉などがあります。この地表面観察の特殊な目利きは、山での山菜採りにも活かされています。(タラの芽、コシアブラなど今まさに春の山菜のピークですね。)
同様に、シロツメグサを見かけると、その葉の一枚一枚を凝視して四葉のクローバーを探してしまいます。下部リバーサイドパークには、シロツメグサの小さい株が一斉に生えはじめました。まだほとんどが手のひらサイズの株です。でも眼が地表を追ってしまう小さいころからの性で、歩くたびにいくつもの株をなんとなく見やっていました。
なんとそのうちの一株に四葉のクローバーがあるではないですか。小さな株の中に2個も。その確率はなんと1万分の1~10万分の1。さらに同じ株には、五つ葉クローバーもありました。こちらの発見率は100万分の1だとか。なんとラッキーなことでしょう。
めったに見つけることのできないことから、幸運の象徴としてみなさんも知ってのとおりです。また、四つ葉にはその葉一枚一枚に「愛、健康、幸福、富」とそれぞれ意味があって、四葉のクローバーがそれらを運んで来てくれるとも言われています。
これらのラッキーアイテムは、取ることなく現地にそのままにそっとしておいてあります。金山博物館の隣の下部リバーサイドパークのどこかには、これらの株があります。みなさん金山博物館の砂金採りとともに、四葉のクローバーも探しに来てみてはいかがですか。
4月20日(木)
さて、このブログのタイトルは「シン・ドウノヘヤ」です。シン・ドウは名字(姓)の信藤(しんどう)からきています。でも「シン」のあとの「・」中点は何なのかといいますと、「シン・ゴジラ」にはじまり先月公開された「シン・仮面ライダー」などのシリーズに由来します。(最近発売された缶チューハイの名前にも「シン・レモンサワー」があったりして、、、)
「シン・」シリーズの映画を制作された庵野監督は、〝「新、真、神」など見る人によってさまざまなことを感じてもらいたいということで正解はありません〟とおっしゃっています。それにあやかって、つれづれなるままに日々のことを綴ったこのコーナーのタイトルに引用させていただきました。
4月17日(月)
博物館で管理する隣接している下部リバーサイドパークには、複数の鹿のフンがありました。どうも昨夜の落とし物のようです。黒豆のように表面は黒光りさえしています。
そういえば吉永小百合さんの「奈良の春日野」の歌詞に「青芝に腰をおろせば 鹿のフンフンフンフーン 黒豆や」とあって、50年くらい前のテレビのお笑い番組でよく明石家さんまさんが歌っていたとおりの姿でした。
そのフン溜まりには50個以上がまとまってありました。一昨日の雨よりも前のものもあり、こちらは黒豆が煮崩れていて形をほとんどとどめていません。自然が身近に感じられます。

4月12日(水)
今日は武田信玄公の命日。元亀4年(1573)4月12日、信玄公は西上途中に信州駒場で亡くなりました。今からちょうど450年前のことです。今日は武田神社で例大祭と武田24将騎馬行列が行われ、甲州市の恵林寺では法要と信玄公まつりが4年ぶりに実施されました。
信玄公は亡くなる直前に、自身の死を3年間秘密にすることなどを遺言しました。そのため死因や亡くなった場所に諸説があり、影武者説や徳川家康に与えた影響などその生前の実態は謎に満ちあふれています。
近年の研究の進展や発掘調査、新資料の発見などによって、新たな信玄像が描かれつつあります。甲府駅前の信玄公の銅像は別人を見本としていること、信玄公が生きていた時代の武田氏の家紋は武田菱ではなかったこと、信玄公は甲斐国内に城を築いていたことなど,私たちが持っている信玄公の常識は実際違ってきているのです。
これらの概要の一端を4月30日の講演会で紹介したいと思っています。
どうぞ、ご期待ください。
4月11日(火)
4月から出月館長に代わり、金山博物館三代目の館長に着任しました信藤祐仁です。
出月前館長と引継ぎをしていたころ館の周囲の桜の花もまだまだきれいだなと思っていたら、いつの間にか葉桜になってしまっています。葉の緑色も濃くなってきて、今年は例年になく春の訪れが早かったですね。桜の開花も観測史上もっとも早いタイ記録だとか。
博物館の周りに目をやると、山吹がたくさん自生しています。山吹の花の黄色が緑の葉に映えて目立ってきれいです。山吹色は黄金色、大判小判の異称としても知られています。博物館にふさわしい花が、今周囲を取り囲んでいます。
その名のとおり黄金色に輝くように、皆様のご支援とご協力をいただきながら館長の重責を全うしてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
← 前のページに戻る