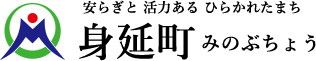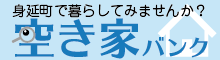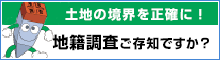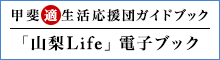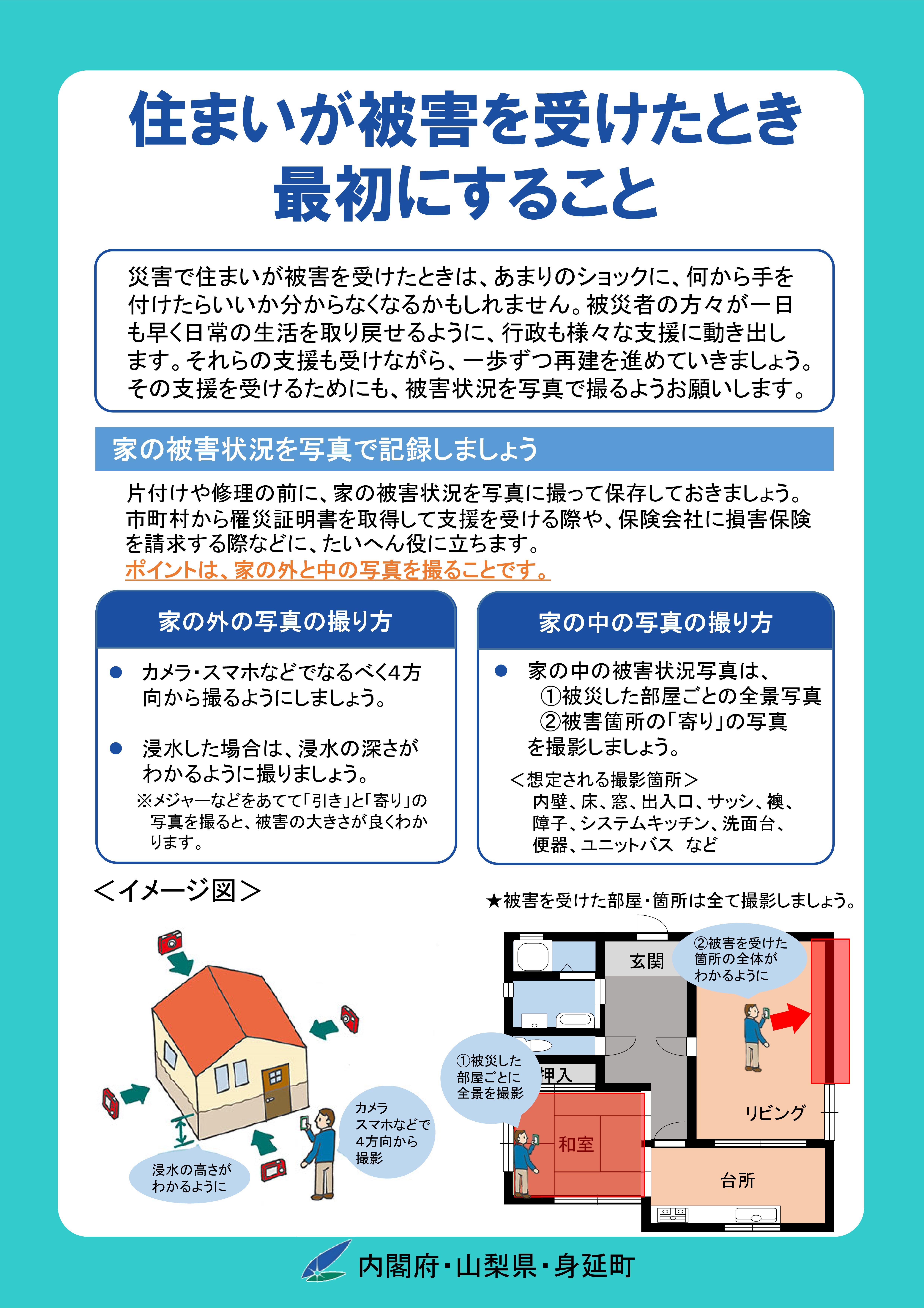印刷#そなえる防災~命を守る防災のポイント~
#そなえる防災
#そなえる防災は、災害に対する事前の備えや発災時の対処法など、今すぐ活用でき、いざというときにも役立つ情報を発信しようと、令和5年の広報みのぶ8月号から掲載しています。
◎その1~誰にでもできる日常備蓄~![]() (450KB)
(450KB)
日ごろからできる日常備蓄と備蓄のポイントについて解説しています。
◎その2~「家庭内避難」と「家庭外避難」~![]() (379KB)
(379KB)
避難と避難時非常用持出袋のチェックリストを掲載しています。
◎その3~避難先を確認しよう!~ ![]() (529KB)
(529KB)
身延町内の指定避難所とハザードマップについて紹介しています。
◎その4~日常からの備え~ ![]() (503KB)
(503KB)
家具等の転倒防止対策と、家族等との連絡方法として災害伝言ダイヤル等を紹介しています。
◎その5~弾道ミサイルが飛んで来たら~![]() (507KB)
(507KB)
弾道ミサイル落下時の行動について、とるべき行動をまとめています。
◎その6~地震から身を守ろう~![]() (611KB)
(611KB)
地震が発生した時の行動について、とるべき行動をまとめています。シェイクアウト訓練を日ごろから実践してみましょう。
地震前に
■防災訓練への参加
消火器の使い方や避難のしかたなどは、経験してみなければなかなか理解するのは難しいものです。友人を誘ったり、家族で参加するなど、自信を深めるため、防災訓練に参加しましょう。
■非常持出品の準備
食料品や電池など期限のあるものは、「防災の日」などに点検し、交換しておきましょう。また、非常持出袋は、目立ちやすく持ち出しやすい場所に置きましょう。
■家族会議で話し合い
「責任分担」「避難場所」「緊急時の連絡方法と連絡先」「非常持出袋の置き場所」などについて、ふだんから家族で話し合っておきましょう。
地震直後は
■身の安全の確保
・丈夫な机やテーブルなどの下に身を伏せる
・座布団などで頭を保護
・あわてて外に飛び出さない
・玄関などの扉を開けて、避難口を確保
■落ち着いて火の始末
・小さい揺れでもすぐ消火
・揺れが大きい時は、揺れがおさまってから消火
・出火したら、消火器や三角消火バケツなどで、小さいうちに消し止める
■避難は徒歩で、持ち物は最低限に
・緊急車や避難する人のじゃまになるので、車は使わず徒歩で避難する
・服装は動きやすいもので、靴は底の厚いものを
・荷物は少なく、リュックサックなどで両手が使えるように
・ガスの元栓を締め、電気のブレーカーを切る
■壁ぎわ、がけや川べりに近寄らない
・狭い路地や塀ぎわは、かわらの落下やブロック塀、コンクリート塀が倒れてくる危険があります
・がけや川べりでは、地盤が緩んで崩れやすくなっている場合があります
■正しい情報の入手
・デマに惑わされない(ラジオ・テレビ・消防署・町などから情報を入手)
・不要・不急な電話はかけない(消防署などへの災害状況の問い合わせは消防活動に支障をきたす)
■協力し合って応急救護
・けがをした人がいたら、協力し合って応急手当を
・けがの程度が重いときには、早急に病院へ
※消防署では、随時、救命講習(心肺蘇生法など)を行っています。
正しい知識と技術を身に付けるためにも、是非参加しましょう。
■地震直後の火災、家屋倒壊や救出活動に備えて用意しておきたいもの
消火器、三角消火バケツ、防火用水、ジャッキ、ロープ、バール、のこぎり、ペンチ、おの、ハンマー、ビニールシート、スコップなど
お問い合わせ
担当:交通防災課
TEL:0556-42-4809(直通)