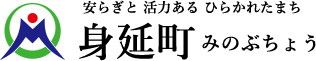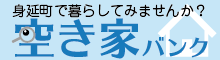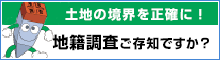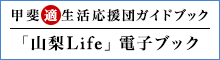印刷軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有している事実に担税力を見出し、その所有者に課する町税です。
道路等との間に極めて直接的な受益関係を持つ特殊な財産税としての性格を持つほか、道路損傷負担金的な性格を持っています。
★納める人(納税義務者)
毎年4月1日時点で、町内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者として登録されている方
※ただし、車検証上、所有権が留保されている車両(自動車販売会社等の売主が車検証の所有者欄に記載されている割賦販売の車両)の場合は使用者として登録されている方が納税義務者となります。
※軽自動車税(種別割)には、普通車に対する自動車税(種別割)のような月割制度がないため、廃車や名義変更を4月2日以降にされた場合も、4月1日現在の所有者の方がその年度の納税義務者となります。
★納める金額
軽自動車等の種類、用途、排気量、初度検査年月等により異なります。課税の対象となる車両の種類および税額をご覧ください。
★納税の方法
5月上旬に送付される納税通知書により、5月31日までに納めていただきます。
(令和7年度の納期限は6月2日・月曜日です。)
課税の対象となる車両の種類および税額
原動機付自転車および二輪車など
| 区 分 | 税率(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下のバイク、 新基準原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0㎾以下のバイク) 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) |
2,000円 | |
| 51cc~90ccまでのバイク | 2,000円 | ||
| 91cc~125ccのバイク | 2,400円 | ||
| ミニカー・電気自動車 | 3,700円 | ||
| 軽自動車 | 二輪 | 126cc~250ccまでのバイク | 3,600円 |
| ボートトレーラー等 | 3,600円 | ||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 最高速度35km/h未満のもの | 2,400円 |
| その他 | 最高速度15km/h未満のもの | 5,900円 | |
| 二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | |
※原動機付自転車、小型特殊車両(トラクタ、フォークリフト等の小型の作業用自動車で運転席があるもの)をお持ちの場合は、公道を走行するかどうかにかかわらず、課税の対象になりますので、未登録の車両をお持ちの場合は役場に申告して課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
※トレーラタイプの農耕作業機が農耕作業用トレーラとして、農耕作業用自動車に指定され、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車として新たに位置づけられました。(例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ等)
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラが小型特殊自動車となる場合、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告により課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
また、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。
小型特殊自動車に分類される農耕作業用トレーラは以下の要件を満たすものになります。
・農耕用トラクタのみにけん引されるもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
なお、最高速度や車両の大きさなどが、小型特殊自動車の上限を超えている車両(大型特殊自動車)については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。
※お持ちの車両が、小型特殊自動車かどうか不明な場合は、販売店、メーカー等にお問い合わせいただくか、車両の型式等がわかる書類(説明書等)を用意したうえで、税務課までお問い合わせください。
軽三輪および軽四輪以上
初度検査年月により①旧税率、②現行税率、③重課税率のいずれかの税率が適用されます。初度検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※初度検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。
①旧税率
平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両に、初度検査から13年を経過するまで適用されます。
②現行税率
平成27年4月1日以降に初度検査を受ける車両に、初度検査から13年を経過するまで適用されます。
③重課税率
平成28年度以降、初度検査から13年を経過した車両に適用されます。
※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車には、重課税率は適用されません。
※令和7年度に新たに重課税率が適用となるのは、 初度検査年月が「平成23年4月から平成24年3月」の車両です。
初度検査年月が「平成23年3月」以前の車両は、令和6年度以前から重課税率が適用されています。
| 区 分 | 税率(年額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①旧税率 | ②現行税率 | ③重課税率 |
||||
| 軽 自 動 車 |
三輪 | 660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 四輪 | 乗用 | 自家用(660cc以下) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
| 営業用(660cc以下) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
| 貨物用 | 自家用(660cc以下) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
| 営業用(660cc以下) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
軽自動車税(種別割)のグリーン化(軽課)特例について
環境性能に優れた軽自動車として、一定の要素に該当する前年度に新規取得した車両について、今年度の課税のみ適用する軽減税率となります。
※令和3年度税制改正により令和4年度課税からは電気軽自動車や営業用車両などで一定の条件を満たす、ごく一部の車両のみが対象となります。
令和5年4月1日~令和6年3月31日の新規登録車両の軽減率と要件
④概ね75%軽減
・電気自動車
・天然ガス自動車 (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
⑤概ね50%軽減
・営業用の乗用車のうち、ガソリン車・ハイブリッド車(令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成)
⑥概ね25%軽減
・営業用の乗用車のうち、ガソリン車・ハイブリッド車(令和2年度基準達成かつ令和12年度基準75%達成)
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)を満たす場合に限ります。
| 区 分 | 税率(年額) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | ④概ね 75%軽減 |
⑤概ね 50%軽減 |
⑥概ね 25%軽減 |
||||
| 軽 自 動 車 |
三輪 | 660cc以下のもの | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
| 四輪 | 乗用 | 自家用(660cc以下) | 10,800円 | 2,700円 | ― | ― | |
| 営業用(660cc以下) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
| 貨物用 | 自家用(660cc以下) | 5,000円 | 1,300円 | ― | ― | ||
| 営業用(660cc以下) | 3,800円 | 1,000円 | ― | ― | |||
軽自動車の異動手続き
手続き期限について
車両を取得(購入、譲受、相続)した場合、転居等で登録済みの内容(車両の定置場等)に変更があった場合:15日以内
車両を廃車(売却、譲渡、処分)した場合:30日以内
原動機付自転車、小型特殊自動車の異動手続きについて
手続きの際、申告書届出者の本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(免許証等)をお持ちください。(販売店の方が届出をする場合も、本人確認をさせていただきます。)
また、車両の所有者ご本人または同じ世帯の方以外の方が届出を行う場合は、不正登録を防ぐため、申告書の委任欄への記載をお願いしています。(販売店の方が届け出をする場合も、所有者となる方に、あらかじめ委任欄を記載していただくようお願いします。)
※委任欄の記載がない場合は、改めて申告していただくことになりますので、事前に下記リンク先から、申請書をダウンロードの上、委任欄への記載をお願いします。
郵送による申告を御希望の場合は、税務課での受付後に標識や証明書をお送りします。申告の種類によらず、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いいたします。
(標識交付の場合は、折りたたんでの発送ができません。レターパック用の封筒など縦横12センチ×25センチ以上の封筒を同封してください。)
| 手続き | 内 容 | 持参するもの |
|---|---|---|
| 取得 (標識交付) |
○新車・中古車を販売業者から購入した | ・販売証明書 |
| ○身延町で廃車済の車両を再び登録する | ・廃車済書(廃車申告受付書) ※身延町での廃車後に他市町村ナンバーで登録していた場合は、一番新しい廃車済書を持参してください。 |
|
| ○廃車済の車両を譲り受けた(所有者を変更した) | ・廃車済書(廃車申告受付書) ・譲渡証明書 |
|
| ○廃車済の車両を相続した ○他市町村で廃車済の車両とともに身延町へ転入した ○他市町村で廃車済の車両の主たる定置場を身延町内に変更した |
・廃車済書(廃車申告受付書) | |
| ○車両の主たる定置場を身延町内の別の場所へ変更した ○車両の使用者を変更した |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
|
| 廃車 および 取得 |
○ワンだふるナンバープレートへの交換 ○車体を買い替えた ○排気量を変更したため、税額が変わる |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
| ○未廃車の車両を譲り受けた(所有者を変更した) | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・譲渡証明書または委任状 |
|
| ○未廃車の車両を相続した ○他市町村ナンバーの車両とともに転入した ○他市町村ナンバーの車両の主たる定置場を身延町内に変更した |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
|
| 廃車 (標識返納) |
○廃棄処分にした ○売却・譲渡した ○転居等に伴い車両を身延町外に移した ○車両の主たる定置場を身延町外に移した ○紛失した ○盗まれた ○災害・事故・老朽化等で車両として二度と機能しない状態(滅失または修理不能な状態)となった |
・ナンバープレート ・標識交付証明書 ※盗難の場合は、警察への届出後に手続きをしてください。 (廃車手続きの際、盗難届受理番号が必要となります。) ※ナンバープレートがない場合は、税務課までご連絡ください。 |
(注)
1.学生等で身延町に住民票を有しない方が登録を行う場合は、住民票上の住所および車両の主たる定置場を確認させていただきますので、確認できる書類(免許証、住民票等。コピーも可)を提示してください。
2.軽自動車税(種別割)は、賦課期日時点で身延町内に主たる定置場のある車両の所有者に対して課税されます。廃車後に継続して所有していたことが判明した場合や、未登録の車両を譲渡したことが新規登録時に提出していただく譲渡証明書にて判明した場合には、過去に遡って課税することがあります。
3.同一の車台番号の車両が過去に登録されていた場合は、廃車から再登録の間の所有状況について、登録時に確認させていただくことがあります。
・例:3月31日に廃棄もしくは譲渡を理由にした廃車申告したものと同一の車両を、同じ方が4月2日以降に再登録する等、同じ方(もしくは関係者)が賦課期日を挟んで同じ車両の廃車・再登録を行う場合
4.所有者の身延町への転入日または販売証明日もしくは譲渡証明日が賦課期日以前の場合には、登録時に賦課期日時点の状況を確認させていただくことがあります。
・例:4月2日に登録を行う車両の「他市町村での廃車受付日と所有者の身延町への転入日の両方」または「販売(譲渡)証明の日付」が3月30日である等、登録前に賦課期日を経過している場合
5.車両の所有者を変更した場合、旧所有者の廃車手続きを行い、新所有者の名義で登録を行います。新所有者が手続きを行う場合は、旧所有者が記入した委任状と譲渡証明書をお持ちください。
6.他市町村ナンバーの廃車手続きは、身延町ナンバーの登録と同時に行う場合のみ受付けます。他市町村ナンバーの廃車のみご希望の場合は、登録されている市町村へお問い合わせください。
7.ナンバープレートを破損・紛失された場合は、税務課にご連絡ください。また、故意または過失によりナンバープレートを破損・紛失された場合は、弁償金(200円)を負担していただきます。
軽自動車等の異動手続き窓口
手続きについては、下記の窓口で受付を行っています。
※納税義務者が死亡した場合は、各窓口で廃車もしくは所有者変更の手続きを行っていただきますが、遺産分割協議が完了しない等の理由で、翌年度の賦課期日(死亡後最初の4月1日)までに手続きを行えない場合は、税務課までお問い合わせください。
※車両やナンバープレート、車検証等がお手元にないため廃車手続きができない場合は、軽自動車税種別割課税保留処分等事務取扱要綱![]() による課税保留等の申請が可能な場合があります。手続きについては、税務課までお問い合わせください。
による課税保留等の申請が可能な場合があります。手続きについては、税務課までお問い合わせください。
| 車 種 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ・原動機付自転車 (125cc以下) ・小型特殊自動車 |
身延町役場 税務課 (身延支所、下部支所でも お手続きいただけます) |
0556-42-4803 |
| ・軽三輪 ・軽四輪 |
軽自動車検査協会 山梨事務所 (笛吹市石和町唐柏792-1) |
050-3816-3121 |
| ・軽二輪 (125ccを超え250cc以下) ・二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
山梨運輸支局 (笛吹市石和町唐柏1000-9) |
050-5540-2039 |
山梨ナンバーの二輪車の税止めの手続きについて
身延町で課税されている山梨ナンバーの二輪車(125CCを超えるバイク)の廃車、名義変更、住所変更を県外で行ったときは、「税止め」の手続きが必要となります。
税止め手続きをされない場合、変更内容を身延町で把握できず課税が続いてしまいますので、手続きをお忘れないようご注意ください。
特に、名義変更の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。(代理人に手続きを依頼している場合は、税止め手続きが完了しているか、必ず確認していただくようお願いします。)
なお、登録内容の変更の手続きをした際に運輸支局等に近接する関係団体に有料で申告の代行を依頼した場合は、税止めの手続きは不要です。
自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを税務課にお持ちいただくか、郵送または0556-42-2127までファックスでお送りください。
税止め手続きの受付完了の連絡を希望される場合は、その旨を提出する書類へ書き添えていただくようお願いします。なお、郵送での連絡が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
・軽自動車税申告書
・軽自動車税(転出)申告書
・車検証返納証明書
・変更前と変更後の自動車検査証のコピー
車検用納税証明書について
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の開始により、軽自動車と排気量250cc以上の2輪車(軽自動車税の課税対象のうち車検制度のあるすべての車両)について、車検時の納税証明書が原則不要になりました。
※軽JNKSへの反映には納付から一定の日数を要するため、納付書での納付から概ね2週間以内に車検を受ける場合には、引き続き納税証明書が必要な場合があります。お持ちの車両の車検の際に納税証明書が必要かどうか確認されたい場合は、税務課までお気軽にお問い合わせください。
※納税証明書は税務課、各支所の窓口で発行可能なほか、郵送でも請求可能です。郵送を希望される場合は、郵送による税証明書の交付申請についてをご覧ください。なお、車検以外の理由のために納税証明書が必要な場合は車両1台につき300円の手数料がかかります。
※口座振替納付済の場合、納期限当日から車検用納税証明書の提示は不要です。このことに伴い、口座振替後の納税証明書の発送は行っておりません。
軽自動車税(種別割)の減免について
■身体障害者等の減免
身体障害者等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方)が所有する軽自動車等について、申請により、軽自動車税(種別割)が減免されます。
新たに減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の納期限までの手続きが必要となります。
※納付書で軽自動車税(種別割)を納付した場合は、その年度の減免の申請をすることが出来ません。翌年度からの減免適用となりますのでご注意ください。
※身体障害者等お一人につき減免される車両は1台のため、自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免の対象外となります。
※車両の取得の際に課税される環境性能割の減免については、山梨県自動車税センター(総合県税事務所自動車税部 ℡055-262-4662)へお問い合わせください。
対象となる車両
●身体障害者等が運転する軽自動車等
●身体障害者等の通学、通院、通所もしくは生業のためにその身体障害者等と生計を一にする者や身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等
詳しい申請方法、申請期間、減免要件(障害の程度)について税務課までお問い合わせください。
■「公益のため直接専用する軽自動車等」および「構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等」への種別割の減免については、税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)